教育と保育のための発達診断セミナー 2025年11月30日(日)
500人ほどの参加申込を受付けました。
当日はよろしくお願いします。
「見逃配信」は1月12日まで行っています。ご案内は参加申込者にメールしています。
教育と保育のための発達診断セミナーの詳しいご案内は以下をクリックしてください

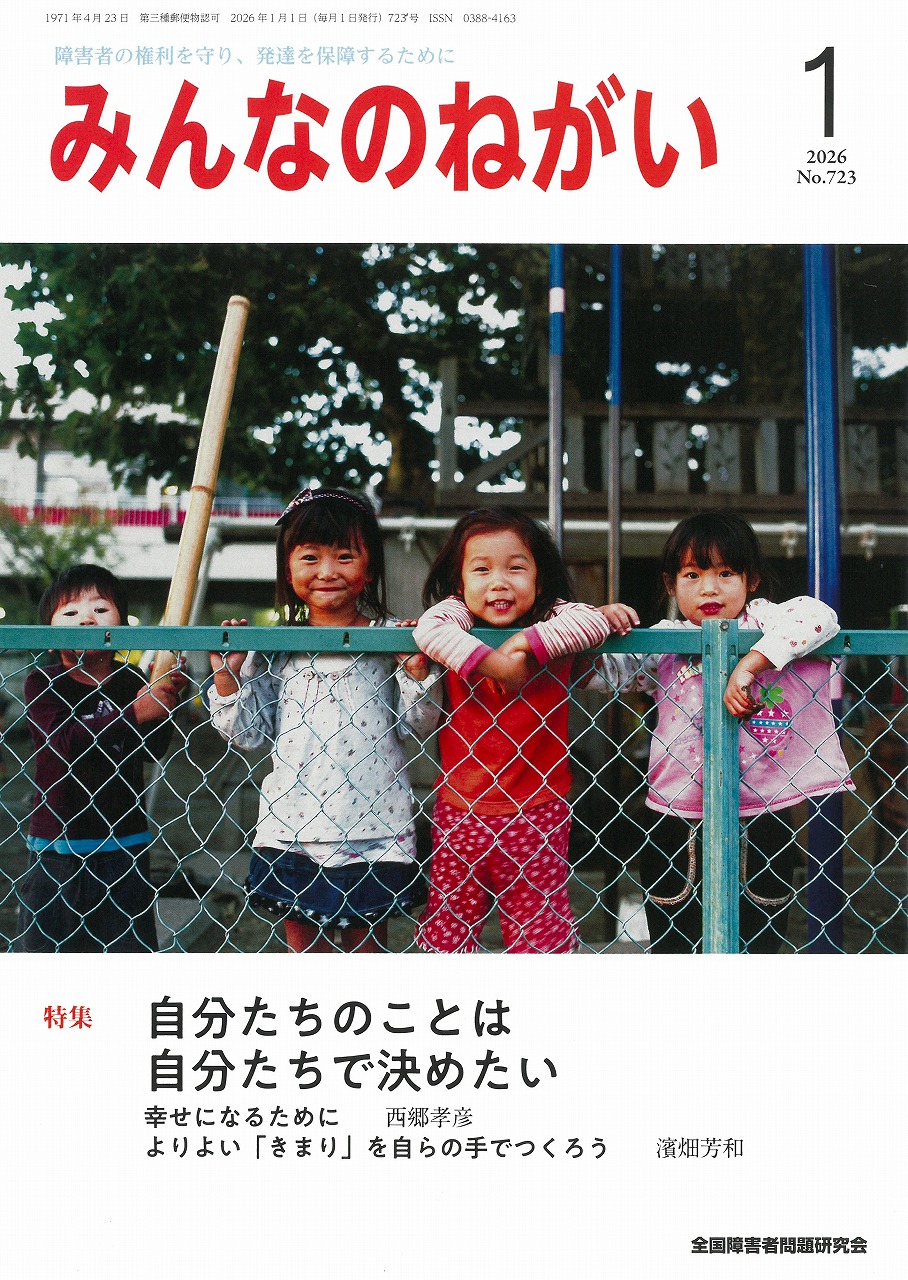
<表紙のことば>
夕暮れ時、地方の海沿いの町を歩いていると、河口近くの小さな川のほとりに保育園があった。お迎えの時間が近いのか、子供達は帰るのが惜しそうにめいっぱい園庭を走り回っている。夕陽に照らされ楽しそうに遊ぶ姿に見入っていると、園児たちが駆け寄ってきた。こんにちは~と元気よく僕の前ではしゃぐ。写真を撮る様子を向こうで見ながら先生も笑って会釈した。まるで映画のワンシーンのような時間だった。
今年も素敵な瞬間に出会うため旅に出よう。僕の写真を通して、人と人との繋がりを少しでも感じてもらえたらと思います。そして、この清らかな子供たちが悲しい涙を流さずに過ごせる日々でありますように。
土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある
<目次>
◆特設 1月号「試し読み」のページへ
1 人として 大下利栄子
2 教員のはじめの一歩 桜井佳子
4 心に種をまく 安田菜津紀
5 あなたに届けたいこの一冊 菊地澄子
6 この子と歩む 宮澤幸江
9 進め! 推し活道 佐野初音
10 息子と歩く 千葉桜 洋
特集 自分たちのことは自分たちで決めたい
12 【座談会】幸せになるために―西郷孝彦さんを囲んで
16 なんでも「集団生活だから仕方がない」で終わらせないで 奥田智江
18 文化部がつくりたい! 50年ぶりの
生徒会規約改正に挑んだ盲学校の高校生たち 深津冬惟
20 みんなのねがいを自治体に届けよう! 脇田美樹
22 よりよい「きまり」を自らの手でつくろう 濵畑芳和
24 私ときょうだい 由良拓也
26 子どものミカタ 檀上貴史
28 ソーシャルワークってなんだろう? 木全和巳
32 シリーズ 18歳 辻 正
34 暮らしの場は今 鷲見俊雄
36 実践にいかす障害と医療 全 有耳
38 ニュースナビ 川口市「きじばと」廃止問題 久遠貞志
40 実践の魅力 井上三奈
43 全障研の支部ニュース、紹介します 澤田淳太郎
44 みんなのひろば
46 BOOK/編集後記
裏表紙 おいしいひととき 大髙美和
デザイン・イラスト
うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、日本印刷、橋野桃子、山内若菜
▶ご購読希望は出版部オンラインへ
「障害者問題研究」53巻第3号 特集=障害のある子どもの意見表明を権を考える
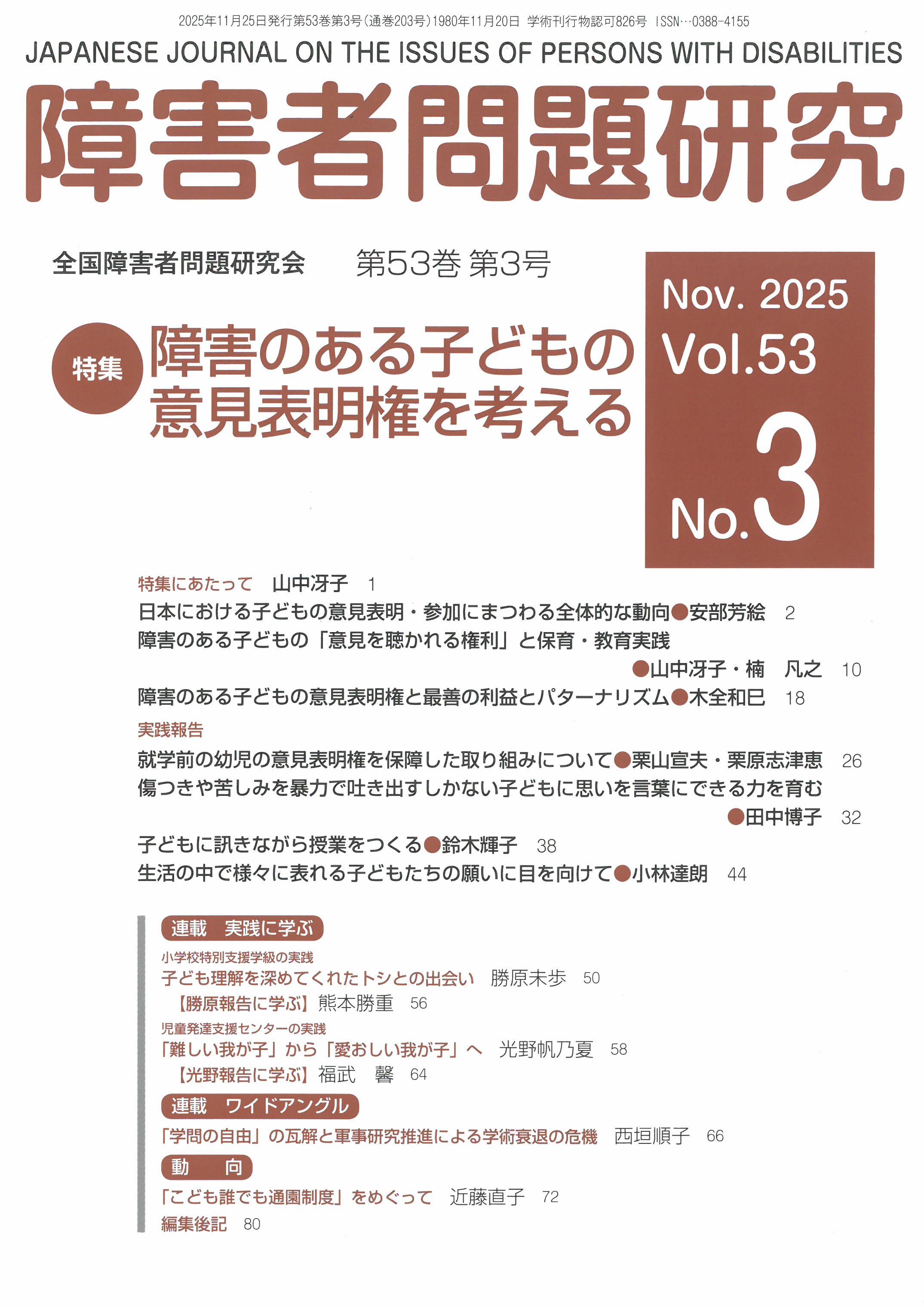
JAPANESE JOURNAL ON THE ISSUES OF PERSONS WITH DISABILTIES
2025年11月25日発行 第53巻第3号(通巻203号)
ISBN978-4-88134-266-4 C3036 定価2750円(本体2500円+税)
特集 障害のある子どもの意見表明権を考える
特集にあたって
山中冴子(埼玉大学)
日本における子どもの意見表明・参加にまつわる全体的な動向
障害のある子どもを包摂する子ども参加に向けた課題
安部芳絵(工学院大学)
本稿の目的は,こども基本法・こども家庭庁設置法施行後の日本国内における子どもの意見表明・参加の動向を整理し,障害のある子どもの包摂的参加に向けた課題を提示することである.ここでいう子どもの意見とはviewsであり,理路整然とした子どもの発言だけでなくうまく言葉にならない気持ちや想い・願いも含まれる.こども基本法は,すべての子どもを包摂し,非言語の「意見」も含む子ども参加のプロセスを支えるための社会全体の共通理念となり得る.このような動向を踏まえ,子どもの意見反映に関する各種「ガイドライン」や「手引き」が作成され,国や自治体における子どもの意見反映のしくみづくりが進んでいる.他方,これらの周知啓発や子どもの権利に関する研修の不足から障害のある子どもの参加機会は限定的である.とりわけ,ランディ・モデルの視点からは,政策決定者が子どもの声に耳を傾け,子どもの願いや想いを実現することが期待される.
障害のある子どもの「意見を聴かれる権利」と保育・教育実践
山中冴子(埼玉大学)・楠 凡之(北九州市立大学)
障害のある子どもの意見を聴かれる権利は,障害や年齢に相応しい支援を受けながら,自身を取り巻く環境づくりに主体的に参加する権利である.この権利は子ども個人としても集団としても保障されねばならず,保育・教育を良質なものとするための絶対条件である.本論文では,子どもの意見を聴かれる権利の内実について,子どもの権利条約と障害者権利条約を手がかりに考察した.さらに,こども家庭庁から2024年に出された「障害児支援におけるこどもの意思の尊重・最善の利益の優先考慮の手引き」での「意思形成支援─意思表明支援─意見形成支援─意見表明支援─意見実現支援」のプロセスを紹介した後,障害のある子どもの意見を聴かれる権利を実現する保育・教育実践の留意点を提起した.
障害のある子どもの意見表明権と最善の利益とパターナリズム
木全和巳(日本福祉大学)
障害のある子どもの意見表明権と最善の利益とパターナリズムとの関連について,ソーシャルワーク実践理論研究の立場から,療育実践や教育実践も念頭に置きつつ,「ケアの倫理」の視点も加え,こうした論点について考察をしながら議論を整理した.パターナリズム概念には,「正当性」による介入や実践の担保,「ケアの倫理」との関連では「弱いパターナリズム」の許容などの議論があり,そもそもこの概念を使用することにより,子どもの意見表明権や最善の利益という権利を侵害する介入などの行為であると批判することは,適切ではないという結論に至った.
就学前の幼児の意見表明権を保障した取り組みについて
保育園での取り組みを中心に
栗山宣夫(育英短期大学)・栗原志津恵(群馬県・社会福祉法人育美会 生品保育園)
傷つきや苦しみを暴力で吐き出すしかない子どもに思いを言葉にできる力を育む
田中博子(筆名 福岡県・中学校教諭
子どもに訊きながら授業をつくる
訪問教育生Aくんとの授業づくり
鈴木輝子(全障研茨城支部)
生活の中で様々に表れる子どもたちの願いに目を向けて
小林達朗(東京都・一般社団法人江東ウィズ さくらんぼ子ども教室)
連載 実践に学ぶ
小学校特別支援学級の実践
子ども理解を深めてくれたトシとの出会い
勝原未歩(大阪府・小学校教員)
【勝原実践に学ぶ】
子どもと先生の成長物語に寄せて
子どもたちに自分理解,自己決定の力を
追手門学院大学非常勤講師 熊本勝重
児童発達支援センターの実践
「難しい我が子」から「愛おしい我が子」へ
親子を支える療育・仲間
光野帆乃夏(広島県・社会福祉法人「ゼノ」少年牧場 「ゼノ」こばと園)
【光野実践に学ぶ】
人のつながりの中で育ち合う
愛知県・(社福)名古屋キリスト教社会館 東部地域療育センターぽけっと 福武 馨
連載/ワイドアングル
「学問の自由」の瓦解と軍事研究推進による学術衰退の危機
日本学術会議法変更問題によせて
西垣順子(大阪公立大学)
動向
「こども誰でも通園制度」をめぐって
子ども施策の保険化への危惧
近藤直子(NPOあいち障害者センター)
▶ご注文は 全障研出版部オンラインショップへ
●案内チラシ(PDF)
▶ 「読む会」情報
日時 2026年1月30日(金)19:00~21:00
Zoomミーティングによる開催
詳細は案内参照
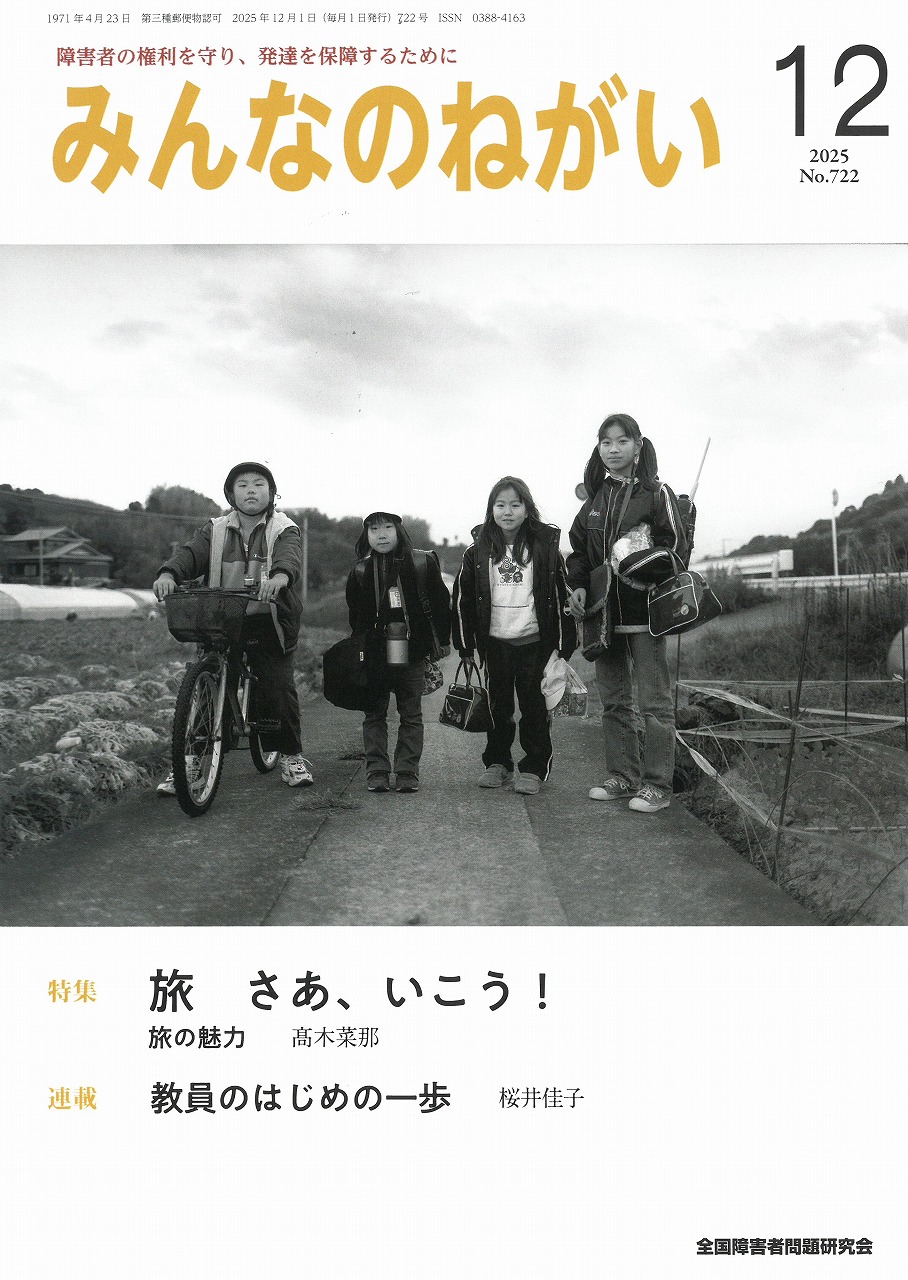
<表紙のことば>
和歌山の山あいの小さな農道で、学校帰りの児童たちに出会った。生徒数が少ないのだろうか皆学年が違うようだが、いつもの帰り道を楽しそうに仲良く歩いてゆく。穏やかな冬の夕暮れと、いつの時代も変わらず無垢で汚れない子どもたち。
2025年もいろんなことがあった。
世界中で分断が生まれ、いまだ戦争で罪のない人々が犠牲になっている。何よりも重たくて尊いものは、ひとりの命であり、子どもの笑顔である。それを失ってまで進めることなんて絶対にありえない。
世界を救うのは、強大な権力者でも最先端のテクノロジーでもなく、たったひとつの小さな命を必死で守ろうとする無償の愛である。
土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある
<目次>
◆特設 「試し読み」のページへ
1 人として 小林功治
2 【インタビュー】いま語りたい 心の窓を広げて 有原誠治(アニメーション監督)
4 教員のはじめの一歩 桜井佳子
6 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)
7 あなたに届けたいこの一冊 大河原妙子
8 この子と歩む 向井恵子
11 進め! 推し活道 蛭川浩一郎
特集 旅 さあ、いこう!
12 旅行の楽しみ あんなこと、こんなこと
14 旅の魅力 髙木菜那
16 「広島に行けてよかった!」“チームおかもと”旅日記 岡本美知子
18 ただいま〜誇らしげな子どもたちの声 丸目香耶
20 友だちと寝食を共にする宿泊行事の価値 松本将孝
22 二人で計画・実行した修学旅行 シャンティつくば
24 私ときょうだい 下田有輝
26 子どものミカタ 檀上貴史
28 ソーシャルワークってなんだろう? 木全和巳
32 シリーズ 18歳 藤井佳樹
34 暮らしの場は今 田岡泰子
36 実践にいかす障害と医療 土岐篤史
38 ニュースナビ 心臓病の子どもを守る会生活実態アンケート 下堂前 亨
40 実践の魅力 飯田清久
43 全障研の支部ニュース、紹介します 樋口京子
44 みんなのひろば
46 息子と歩く 千葉桜 洋
47 BOOK/編集後記
裏表紙 おいしいひととき 福井真央
デザイン・イラスト
うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、日本印刷、橋野桃子、山内若菜
▶ご購読希望は出版部オンラインへ
「障害者問題研究」53巻第2号 特集=知的障害・ボーダーライン知的機能の教育を拓く
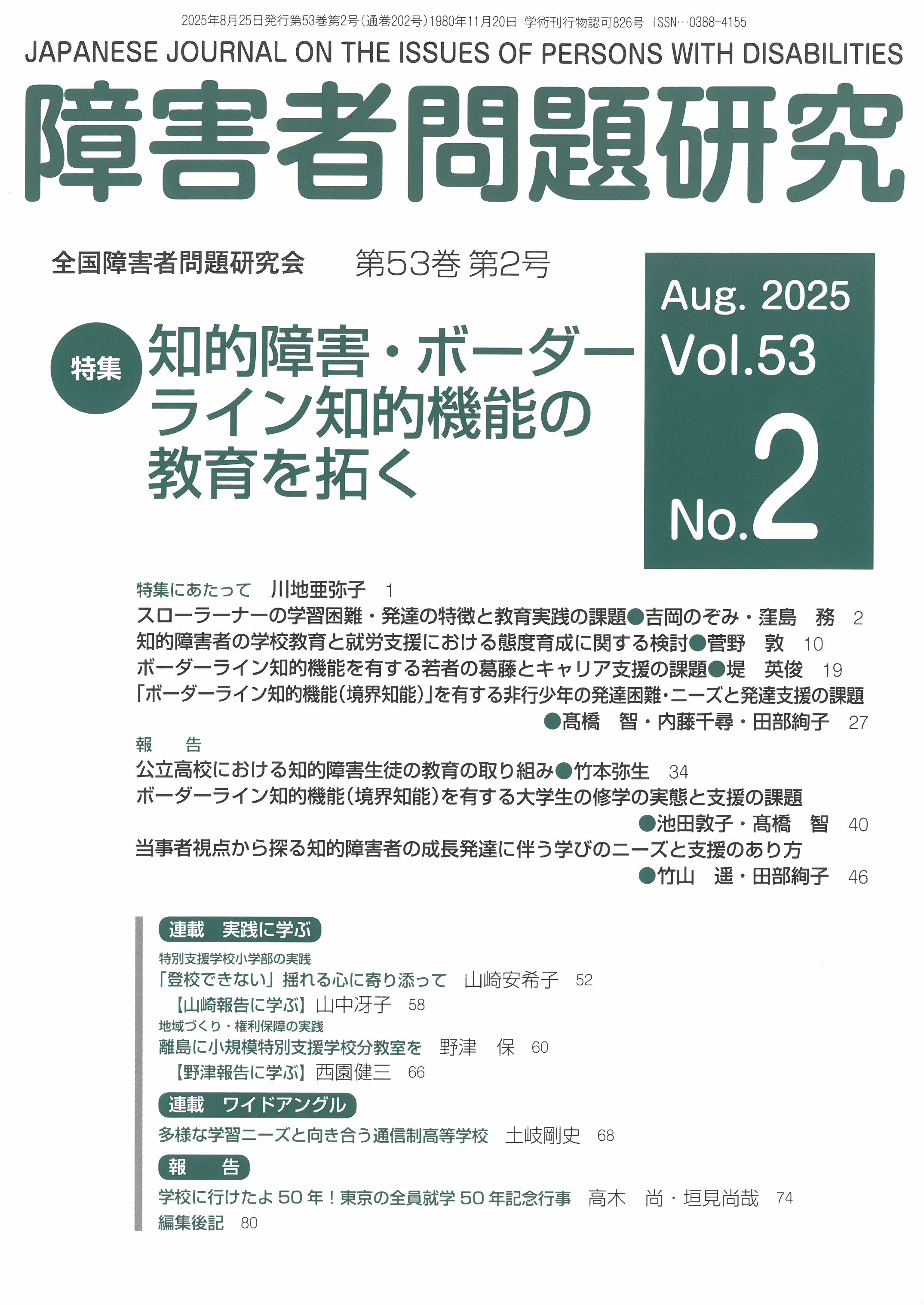
JAPANESE JOURNAL ON THE ISSUES OF PERSONS WITH DISABILTIES
2025年8月25日発行 第53巻第2号(通巻202号)
ISBN978-4-88134-256-5 C3036 定価2750円(本体2500円+税)
特集 知的障害・ボーダーライン知的機能の教育を拓く
特集にあたって
川地亜弥子(神戸大学人間発達環境学研究科)
スローラーナーの学習困難・発達の特徴と教育実践の課題
スローラーナーのA児の10年間の発達経過と教育指導
吉岡 のぞみ(小学校教諭・SKCキッズカレッジ)・窪島 務(滋賀大学名誉教授・SKCキッズカレッジ)
スローラーナーは,学習上の困難を有するボーダーライン知的機能の子どもを指す.その特徴は,1つに,学力不振があること,とりわけ抽象的思考の段階に入るところでの大きなつまずきを示す.2つに,知的障害には該当しないが,知的機能に大きな制約があり,IQ70~85の範囲にある.3つに,年齢にふさわしい集団参加と社会的適応能力が乏しいという特徴がある.また,心理的不安が大きく,獲得したスキルを新しい課題や新しい状況に適用することが困難である.今日の最大の問題は,教育学が理論的にも実践的にもその存在を認知していないことである.教育・心理的側面から見たときの指導の基本は,レジリエンス(回復力)と困難に立ち向かう能力を高めることであり,そのためにはa)子どもの安心と自尊心を第一におくこと,b)社会的認知と教育的支援方策を生み出すこと,c)社会的対処能力を高めることが重要である.本稿では第1に,スローラーナーの特徴と研究動向を確認しつつ,第
2 にスローラーナーである1人の子ども(A児)の小学校1年から高等学校入学までの10年間の学習困難の実態と発達の可能性を,質的記述的方法を用いて明らかにした.
知的障害者の学校教育と就労支援における態度育成に関する検討
態度とは,そしてその育成の考え方
菅野 敦(東京学芸大学名誉教授)
本稿では,近年,学校教育において特に育成が求められるようになった「主体的に学習に取り組む態度」と,就労支援において重要な「働く態度」について,両者の関係とその育成に関して検討,考察した.はじめに,態度を3つの要素から整理し,定義した.さらに,学習活動や作業活動への取り組みで現れ,変化する姿・行動を態度として捉え,諸活動への取り組みの過程を辿ることで
6 種類の態度を見出した.それら6種類の態度は,生涯発達支援の視点に立ちライフステージ各期の発達課題への取り組みから,水準の異なる態度で,しかも階層の構造で捉えられることを明らかにした.
ボーダーライン知的機能を有する若者の葛藤とキャリア支援の課題
当事者のライフストーリーを手がかりとして
堤 英俊(都留文科大学教養学部学校教育学科)
本稿では,当事者のライフストーリーを手がかりとして,ボーダーライン知的機能を有する若者の葛藤とキャリア支援の課題について明らかにすることを試みた.その取り組みの過程で浮かび上がってきた,当事者の葛藤に関わるキーワードが,「内なる能力主義」であった.それを踏まえて,キャリア支援の課題として,①「本人なりの合理性」を把握した上で実践を行うこと,②就労支援のみに注力するのではなく,生活の質(QOL)の向上を目的とした実践を展開すること,そして③「複数の居場所をもつ」ことを支援するという視点のもとに,就労支援の取り組みを位置づけること,という3点を提起した.
「ボーダーライン知的機能(境界知能)」を有する非行少年の発達困難・ニーズと発達支援の課題
少年院在院少年の面接法調査から
髙橋 智(東海学院大学人間関係学部子ども発達学科)
内藤 千尋(山梨大学大学院総合研究部教育学域障害児教育講座)
田部 絢子(日本大学文理学部教育学科)
本稿では,筆者らがこれまで少年院において実施してきた継続的な面接法調査結果をもとに,「境界知能」を有する非行少年の発達困難の実態と支援ニーズおよび発達支援の課題について検討してきた.「境界知能」等の発達困難を有する少年の多くは,学校忌避・逃避や不登校等に伴う長期間の学習空白を有しており,就労・社会的自立に必要な基礎的学力を習得できておらず,少年院ではその点の発達支援が大きな課題になっている.法務省の再犯防止推進計画でも重点課題として学校等と連携した修学支援の実施が掲げられている.法務省は2024年度より全国すべての少年院で通信制高校に入学できる制度を開始したが,さらに少年院内における高校・特別支援学校の分校・分教室設置や大学等の高等教育への進学保障にも着手することが求められている.
公立高校における知的障害生徒の教育の取り組み
神奈川県の「インクルーシブ教育実践推進校」を事例に
竹本 弥生(横浜薬科大学)
ボーダーライン知的機能(境界知能)を有する大学生の修学の実態と支援の課題
当事者の聞き取り調査から
池田 敦子・髙橋 智(東海学院大学人間関係学部子ども発達学科)
当事者視点から探る知的障害者の成長・発達に伴う学びのニーズと支援のあり方
竹山 遥(知的障害当事者・大学卒業・企業正社員)
田部 絢子(日本大学文理学部教育学科)
連載 実践に学ぶ
特別支援学校小学部の実践
「登校できない」揺れる心に寄り添って
山崎 安希子(奈良県・公立校)
【山崎実践に学ぶ】
子どもの混乱を受け止め子どもにとっての登校の価値を考える
埼玉大学 山中冴子
地域づくり・権利保障の実践
離島に小規模特別支援学校分教室を
地域と結びついた教育実践を創造し,地域を支える人を育てるために
野津 保(元 島根県立隠岐養護学校)
【野津実践に学ぶ】
地域と共に歩み,離島の声を拾い上げ,そして願いを実現していく
麦の芽福祉会・ユーススコラ鹿児島 西園健三
連載/ワイドアングル
多様な学習ニーズと向き合う通信制高等学校
土岐 剛史(北海道有朋高等学校通信制課程 教諭)
報告
学校に行けたよ50年!東京の全員就学50年記念行事
東京の全員就学50年記念行事実行委員会 高木 尚・垣見 尚哉
▶ご注文は 全障研出版部オンラインショップへ
●案内チラシ(PDF)
▶ 「読む会」情報
日時 2025年10月31日(金)19:30~21:00
Zoomミーティングによる開催(終了しました)
進行 川地亜弥子さん(今号特集担当編集委員)
【話題提供】
窪島務さん(滋賀大学名誉教授)スローラーナーの学習困難・発達の特徴と教育実践の課題
田部 絢子さん(日本大学)当事者視点から探る知的障害者の成長発達に伴う学びのニーズと支援のあり方
【参加者の意見交流】
コメント 楠凡之さん(本誌編集委員)
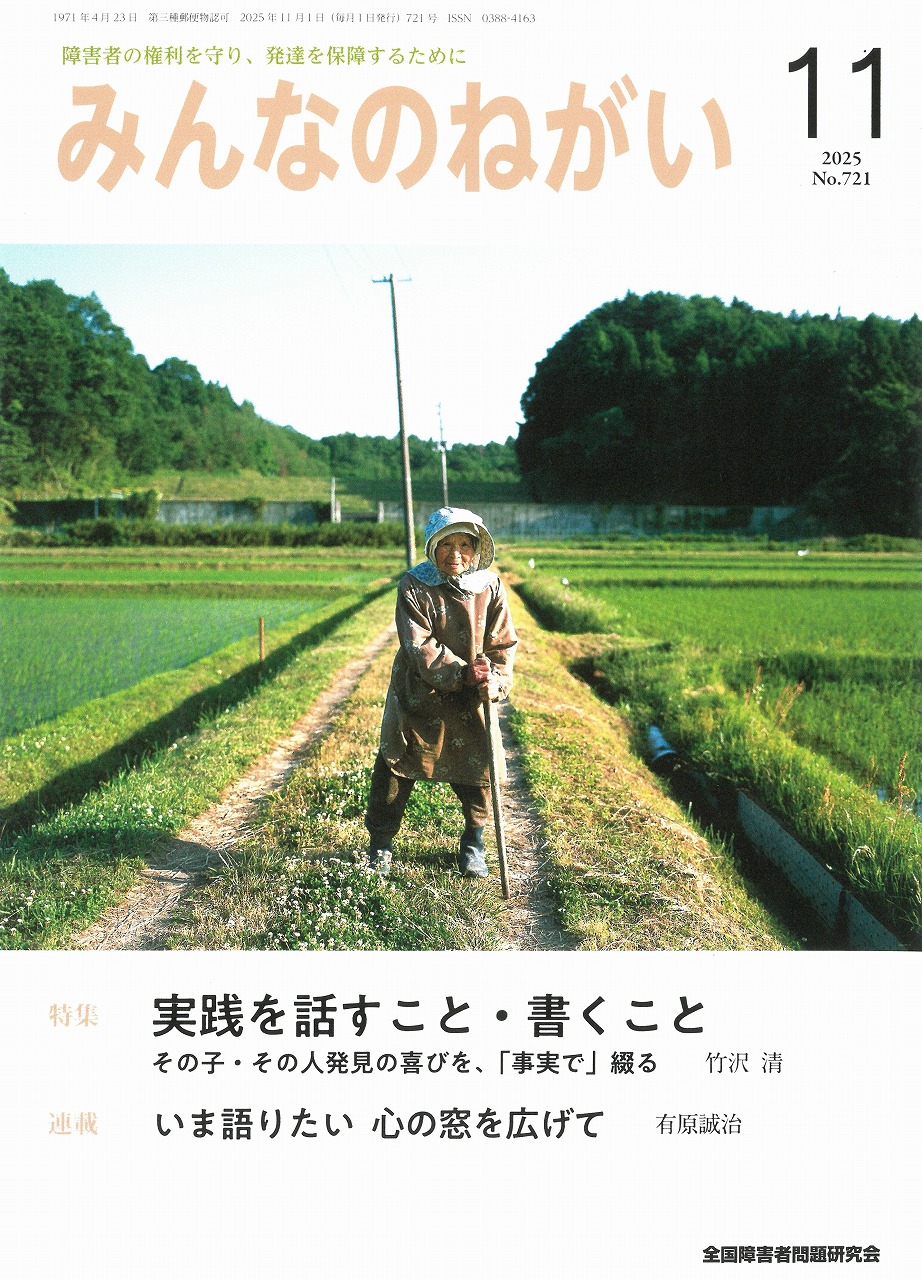
<表紙のことば>
東北の山あいの道をゆく。午後の日差しに照らされた里山の風景は長閑で美しい。開けた視界の先に杖をついた女性が見えてきた。長い畦道をゆっくり進んでいるのだろう、まるで時が止まっているようだ。一枚の写真が見えた。
僕はとっさに車を止め、カメラを手に走っていった。突然目の前に現れ挨拶をする僕に、おばあちゃんは優しく微笑えむ。家の前にある広い畑の様子を見にいくのが日課らしい。ゆっくりと時間をかけて毎日のルーティンをこなす、彼女の人生なのだろう。写真を数枚撮ったあと、帰りの一本道をいっしょに歩いた。なんだか懐かしくて愛おしくて、抱きしめたくなった。
おばあちゃんありがとう。どうかいつまでもお元気で。
土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある
<目次>
◆特設 「試し読み」のページ
1 人として ちばかおり(イラストレーター)
2 【インタビュー】いま語りたい 心の窓を広げて 有原誠治(アニメーション監督)
4 教員のはじめの一歩 木澤愛子(全障研滋賀支部)
6 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)
7 あなたに届けたいこの一冊 石井啓子(元教員)
8 この子と歩む 須藤淑子(川口市)
11 進め! 推し活道 山口悠生(奈良)
12 息子と歩く 千葉桜 洋(写真家)
特集 実践を話すこと 書くこと
14 おもいを伝える「心の声」を大切にしたい 大川彩子(愛知・みなと福祉会児童デイさざなみ)
16 本当の「おもい」に向き合うまで 木村千秋(同さざなみ)
18 綴ることを続けていくために 森脇拓恵(みなと福祉会研修委員長)
20 「自分らしく」働く職場に 小林健一郎(東京・のびのび共同作業所青空)
22 その子・その人発見の喜びを、「事実で」綴る 竹沢 清(愛知障害者センター)
25 ニュースナビ 「いのちのとりで裁判」「天海訴訟」
坂下 共(きょうされん)・纐纈建史(天海訴訟を支援する会)
28 私ときょうだい 萩原千晶(東京)
30 子どものミカタ 竹脇真悟(日本福祉大学)
32 ソーシャルワークってなんだろう? 木全和巳(日本福祉大学)
36 シリーズ 18歳 西園健三(鹿児島・ユーススコラ鹿児島)
38 暮らしの場は今 和田大輝(福岡ひかり福祉会かしはらホーム)
40 実践にいかす障害と医療 土岐篤史(発達臨床研究・研修サポート/医師)
42 実践の魅力 仁村菜月子(滋賀・養護学校教員)
45 全障研の支部ニュース、紹介します 米倉拓也(長野支部)
46 みんなのひろば
47 BOOK/編集後記
裏表紙 おいしいひととき 小畑友希(さっぽろひかり福祉会)
デザイン・イラスト
うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、日本印刷、橋野桃子、山内若菜
▶ご購読希望は出版部オンラインへ
定価1980円 ISBN978-4-88134-246-6 2025年8月9日
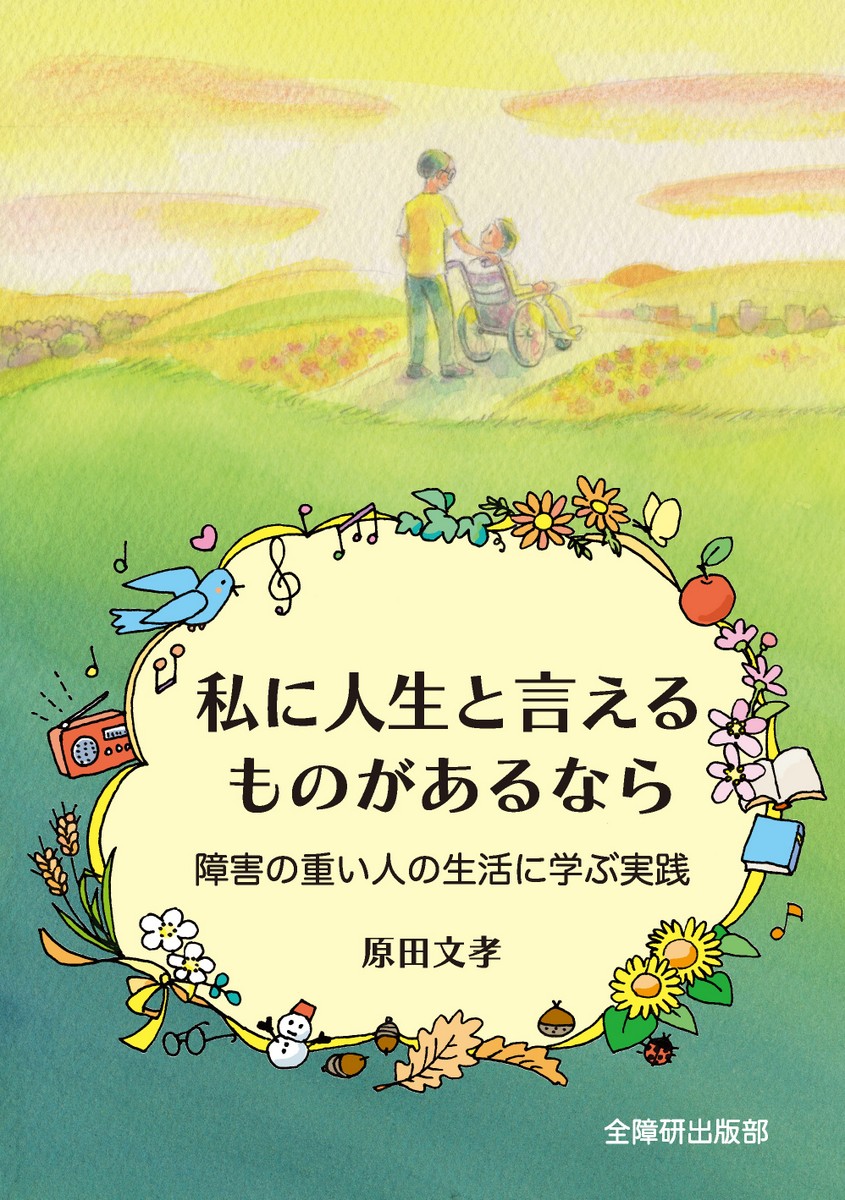
もくじ
はじめに(試し読みできます)
Ⅰ 私に人生と言えるものがあるなら
1 人生どうにかなるさ
2 一日は人生を刻むもっとも大切な時の単位
3 悲しみは人生を豊かにする
4 人生、苦労は買ってでもしよう
5 わがケアは魂におよび
6 人生を再発見する
7 運がいいとか悪いとか
8 人生、一人じゃ生きていけない
9 人生、わかっちゃいるけどやめられない
10 明日がある
11 人生、どう生きるべきか
12 楽器は自ら鳴り響かない
Ⅱ 語り合い、深め合う
1 鼎談 障害の重い人たちと、ともに学び、ともに生きる
鼎談を終えて 〜語り残したこと
2 解説 考え抜き、考え続ける教師 越野和之(全障研委員長・奈良教育大学教授)
おわりに
参考文献
◯40年以上にわたる生活文化を学ぶ実践を軸に、障害の重い人たちと家族に向き合い続け、ともに生きる軌跡とその思い
◯『みんなのねがい』好評連載に、コラムを書き下ろし
◯原田さんと特別支援学校・学級の教員によるてい談を収録
○越野委員長による「解説=考え抜き、考え続ける教師」
定価2200円 ISBN978-4-88134-186-5 2024年8月15日
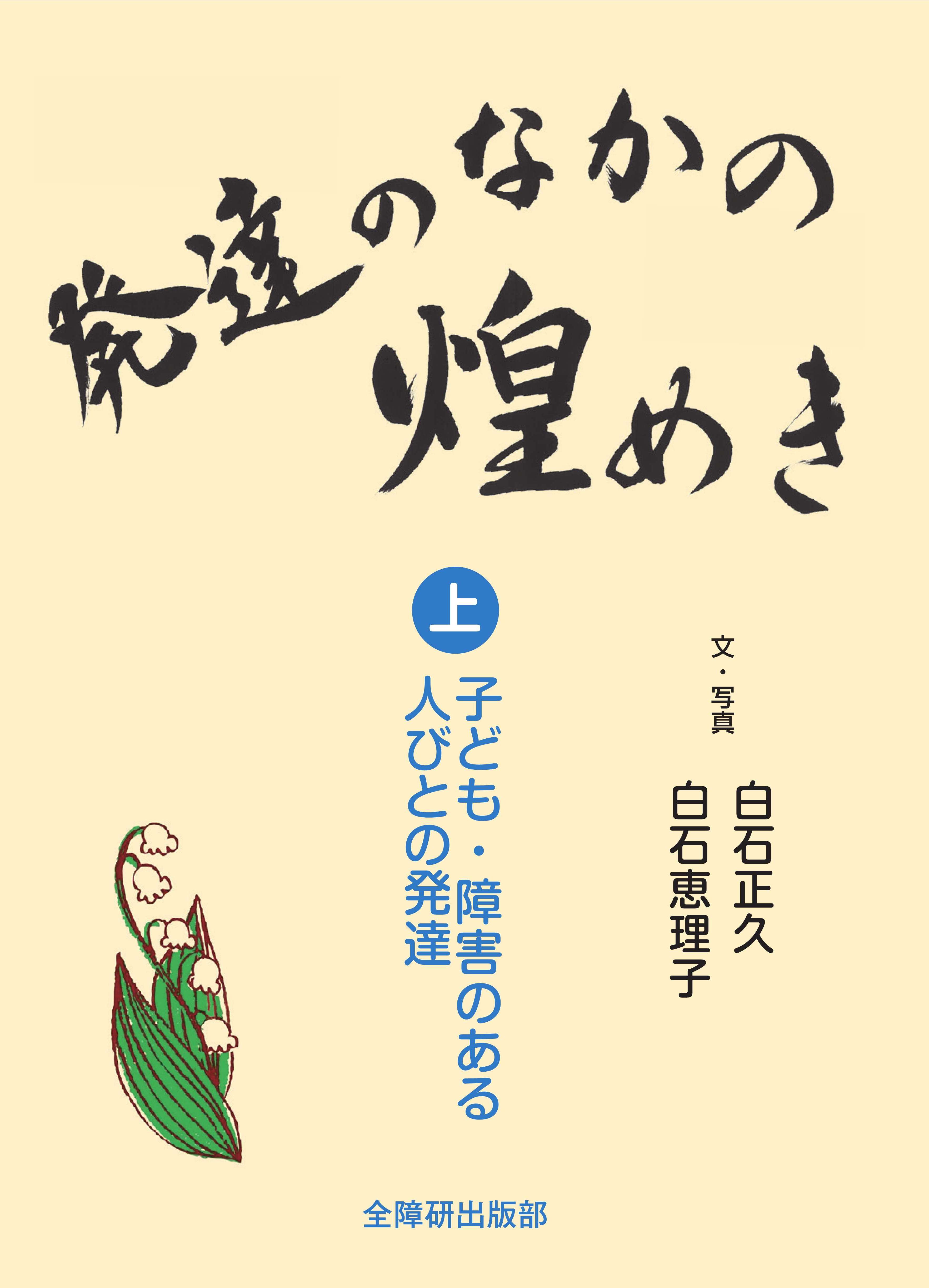
目次
はじめに
第Ⅰ部 生きる・つながる・発達する
第1章 生きる・つながる・発達する
先生方、2年ぶりにお便りします/「発達の節」を乗り越えるとは/お母さんに謝りたい/縦糸に発達の道すじを、横糸に人間を大切にするしごとのことを
第2章 あなたといっしょに、もっと生きたい
─重症児教育と「生後第1の新しい発達の力」
『瞳輝いて』/乳児期前半の発達と「人を求めてやまない心」/人しり初めしほほえみ/年輪のふくらみ、あたたかさ
第3章 子育てを応援する地域づくり
─「新しい発達の力」が親、地域、社会を変える
大津市における乳幼児健診の歴史から/「生後第2の新しい発達の力」の誕生と10か月児健診/大きな社会的連帯で子育てを応援する/先輩たちの思いを受け継いで
第4章 言葉の世界を拓く
─障害のある子どもといっしょに創る文化を通して
本当に言葉を理解していないのだろうか/子どもをつなぐ文化のねうち/発達の主人公として「1歳半の節」を迎える/言葉の世界へ誘う責任をもって/おとな集団の響きあい
第5章 「本当の要求」とはなにか
─自閉症児と「1歳半の節」
コウジくんが「本当の要求」に出会うまで/「1歳半の節」と発達の連関/自分の意図と他者の意図の調整が難しい自閉症児/「本当の要求」とは
第6章 「みかけの重度」問題を考える
─「2次元の世界」を切り開く重症児
アヤちゃんと「給食の海苔」/「2次元の世界」の不確かさへの不安/「みかけの重度」問題と向きあって
第7章 成人期の「労働」から考える
─その人らしさが「2次元の世界」を豊かにする
作業所づくり運動のなかで/一人ひとりの労働観を探る/対の世界で揺れる/反抗と密着を繰り返しながら
第8章 「…だけれども…する」と心をまとめあげていく
─「2次元可逆操作期」の自分づくり
一枚の絵から/「2次元可逆操作期」とは/「問題行動」は発達要求のあらわれ/友だちに必要とされる自分を感じる
第9章 仲間とともに「だんだん大きくなる」
─「3次元の世界」を切り開く
「ぼく、へたやから」/友だち大好きになる/新しい次元の自分へと「だんだん大きくなる」/友だちとともによりよくありたいねがい
第10章 導き、導かれる関係のなかで自分を育てる
『夜明け前の子どもたち』から/導き、導かれる/学部を越えたつながりのなかで/「違い」をくぐって「同じ」に気づく
第11章 自分を客観的にみる「9歳の節」
ケイタさんのこと/リレーの取り組みで/先生についてきてほしい/学級集団を育むということ/集団もまた、揺れながら発達していく
第12章 「社会」のなかで自分をつくる.
─「9歳の節」と集団のなかでの自己
「自分のことを書いてください」/「社会」のなかにある一人の自分/「お互いに苦しいこともあるよね」/私たちも発達の道を歩いている
第Ⅱ部 解説のページ 学びあい、語りあうために
第1章 発達とはなにか
発達の学習に王道はない/発達とはなにか/「発達段階」と「発達の節」/「可逆操作の高次化における階層-段階理論」
第2章 乳児期前半の発達の階層-段階
発達の階層と3つの段階/「回転可逆操作の階層-段階」の特徴/発達段階から発達段階への移行/ハルちゃんの発達と教育から学ぶ
第3章 乳児期後半の発達の階層-段階
「連結可逆操作の階層」とは/「連結可逆操作の階層」への飛躍的移行/「連結可逆操作の階層-段階」の特徴/発達段階から発達段階への移行/子育てを「自己責任」にしない
第4章 幼児期の発達の階層と「1次元可逆操作」の世界
目的(つもり)をつくって行動する/相手の目的(つもり)にも気づく/「…ではない…だ」/指さしやことばなどによるコミュニケーション/変化する素材と道具の発達的意味/幸福感においてつながる
第5章 「2次元の世界」を開く
「次元可逆操作の階層」の3つの段階/「2次元の世界」を開く/「…してから…する」2次元の構成と自他の領域の分化
第6章 機能障害の重い子どもの発達理解
「みかけの重度」問題について/機能の障害の重い自閉スペクトラム症と「みかけの重度」
第7章 「2次元可逆操作」の世界
「2次元可逆操作期」の特徴/知的障害のある成人期の方たちのこと/誇りある自分を育んでいく発達の土台
第8章 「3次元可逆操作」の世界
「3次元の世界」を開く/「導き、導かれる関係」のなかで自分を育てる
第9章 「9歳の節」への飛躍
「3次元可逆操作」への発展/「9歳の節」─「1次変換可逆操作」へ
おわりに
▼本書の紹介 しんぶん赤旗 2024年11月4日
下記をクリックすると大きな画像のPDFファイルでご覧いただけます

●ご活用ください 案内チラシです
クリックするとPDF版(A4)がダウンロードできます

あなたの街の投票環境は改善されましたか?
投票環境のバリアフリーでJD(日本障害者協議会)が実態調査
以下は、JDからの調査協力のお願いです
投票環境バリアフリーのアンケート2025 調査のお願い
特定非営利活動法人 日本障害者協議会(JD)代表 藤井克徳
障害のある人の投票に関して、合理的配慮を欠くことは、すべての人に保障された参政権を侵し、障害者権利条約第29条(政治的及び公的活動への参加)実現の妨げとなる重大問題として、その改善を国などに求めてきました(資料:JD要請書2025)。各地での当事者の声や実態などはマスコミも大きく報道しました。
こうしたなかで総務省はホームページで「対応例」や「好事例」を紹介し、また総務省留意事項(別添1)、厚労省事務連絡(別添2)を発しました。
その結果、この度の参議院選挙2025では、各地の投票所でどんな改善の動きがあったでしょうか。改善されたことや今後の課題など、率直な声や事例をお聞かせください。来たるべき総選挙にむけて、さらにとりくみをすすめてまいります。
つぎの回答フォームURLより、10月末日までにご意見をお願いいたします。
https://forms.gle/cqKG5TWYeFBDVboJA
上記フォームからの書き込みがご不便な場合は、次の項目をJD事務局にメールください。
①お名前
②所属団体または「個人」
③障害の 有・無
④参議院選挙2025であなたの投票環境は改善されましたか? 改善された・改善されていない
<自由記述>
1) 選挙情報に関する実態や課題でのご意見
2) 投票所の環境などに関連するご意見
3) 投票方法、投票用紙などに関連するご意見
4) 郵便投票や期日前投票などに関連するご意見
5) その他の課題などへのご意見
担当事務局=薗部英夫(JD副代表)、白沢仁(JD理事)、山本忠(立命館大学)
連絡先=日本障害者協議会(JD)
メール:office@jdnet.gr.jp
TEL:03-5287-2346
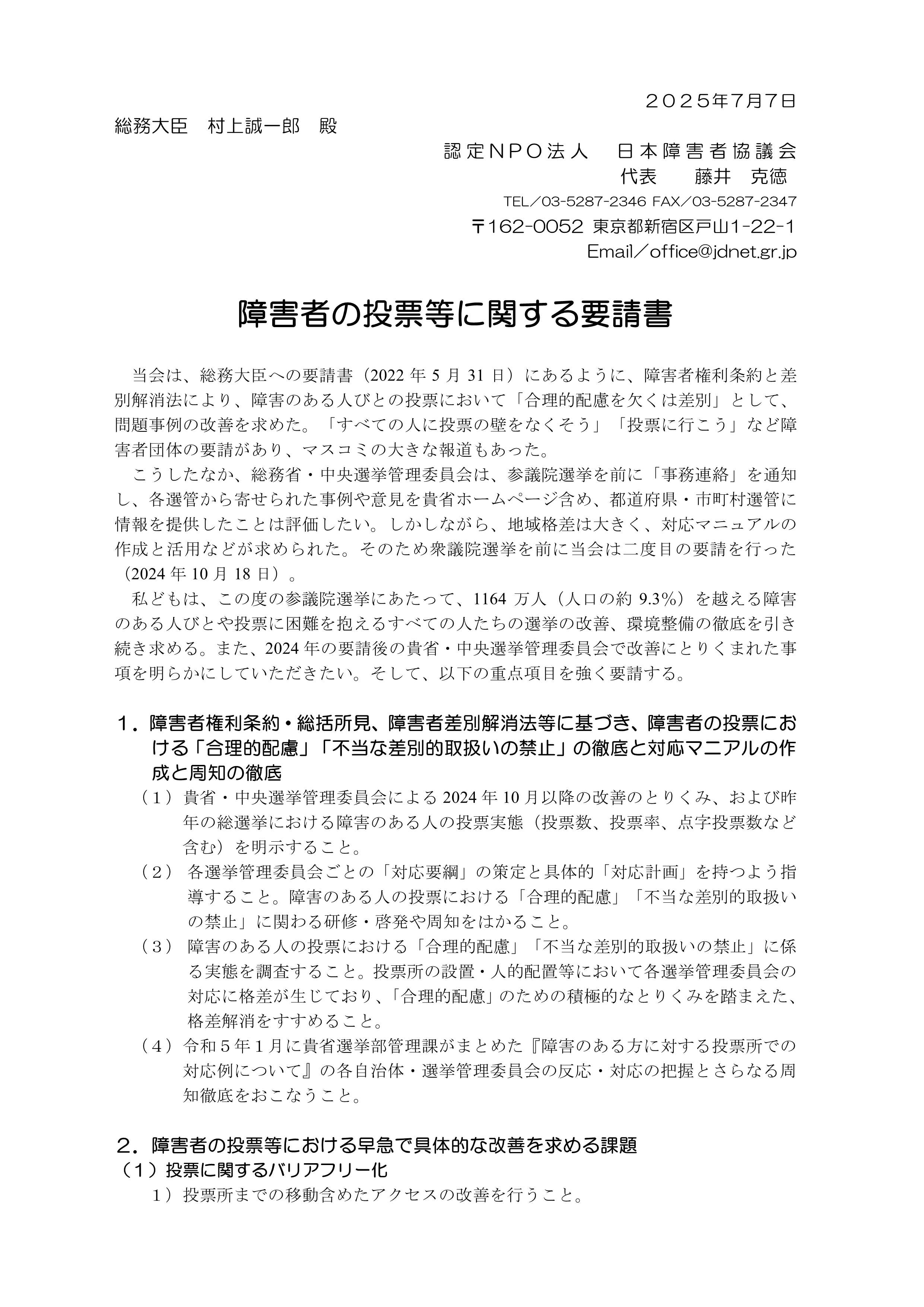
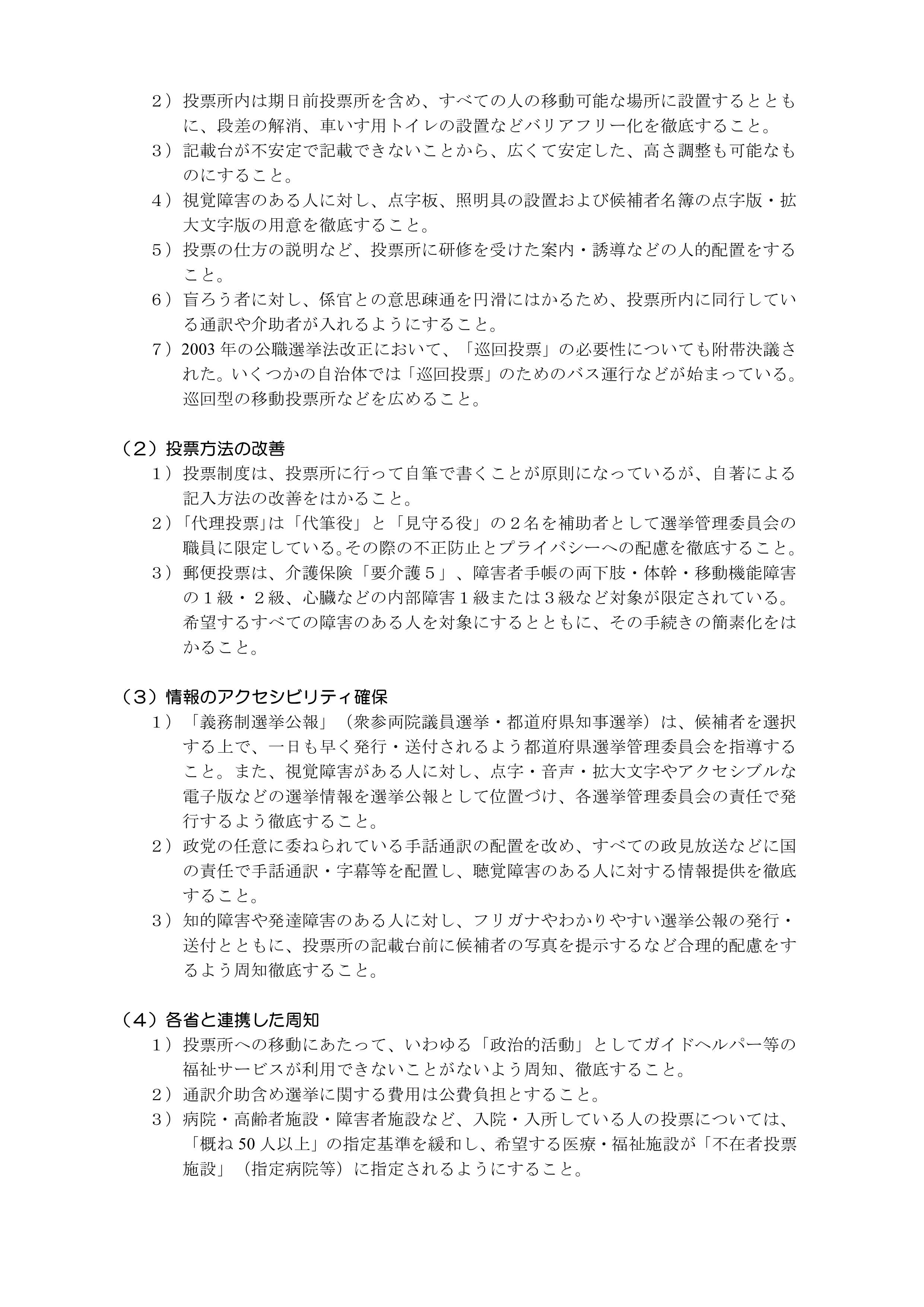
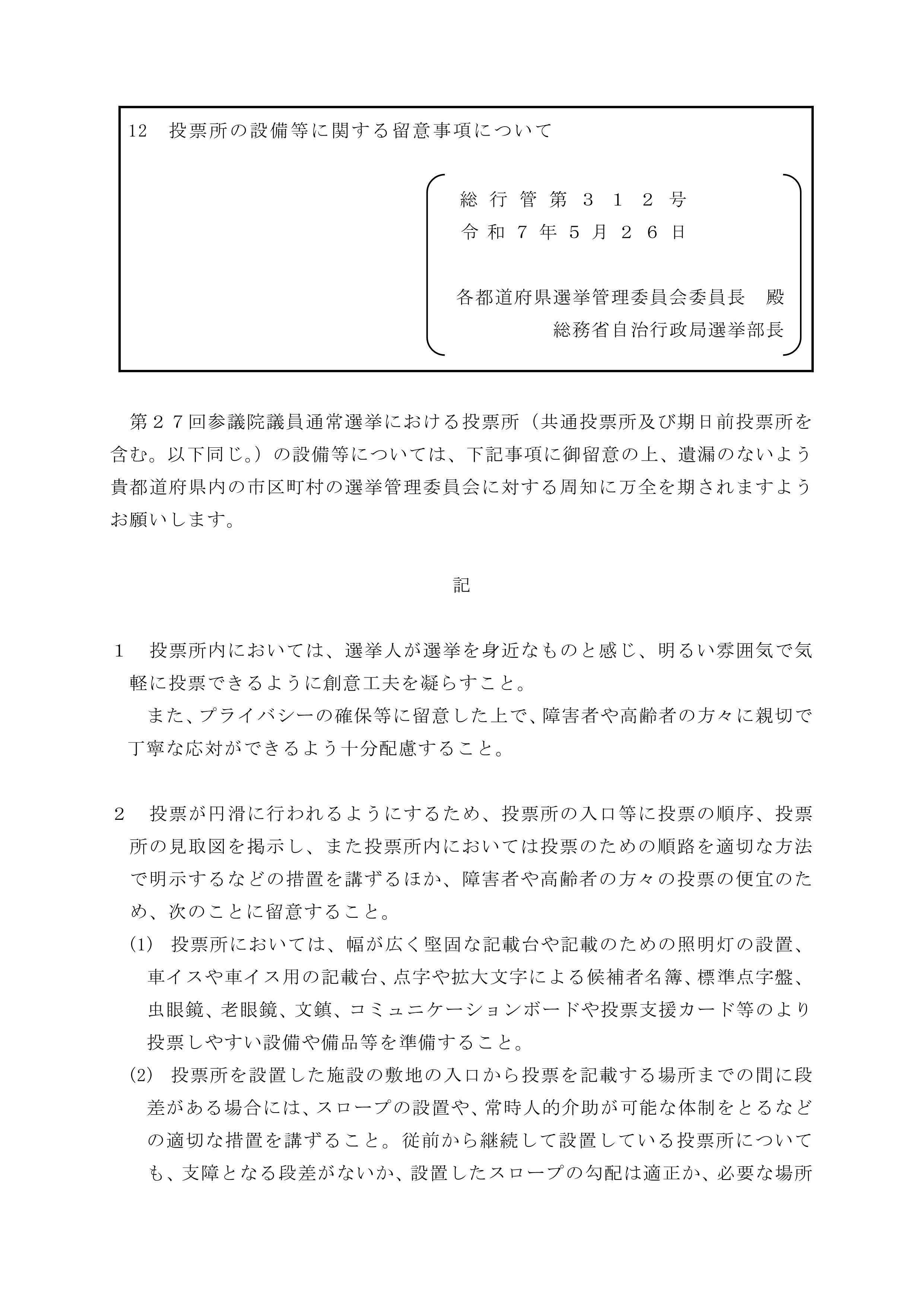
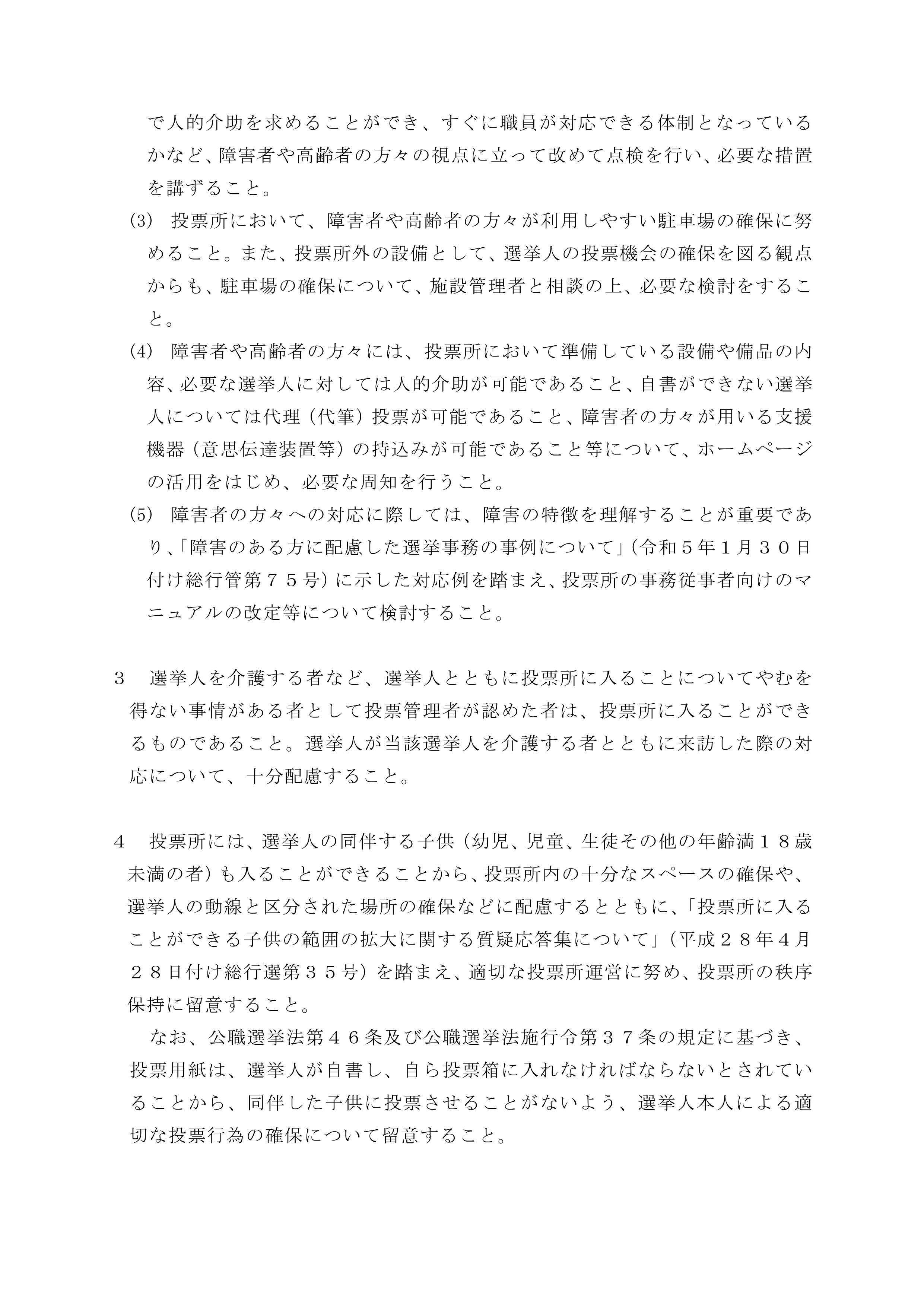
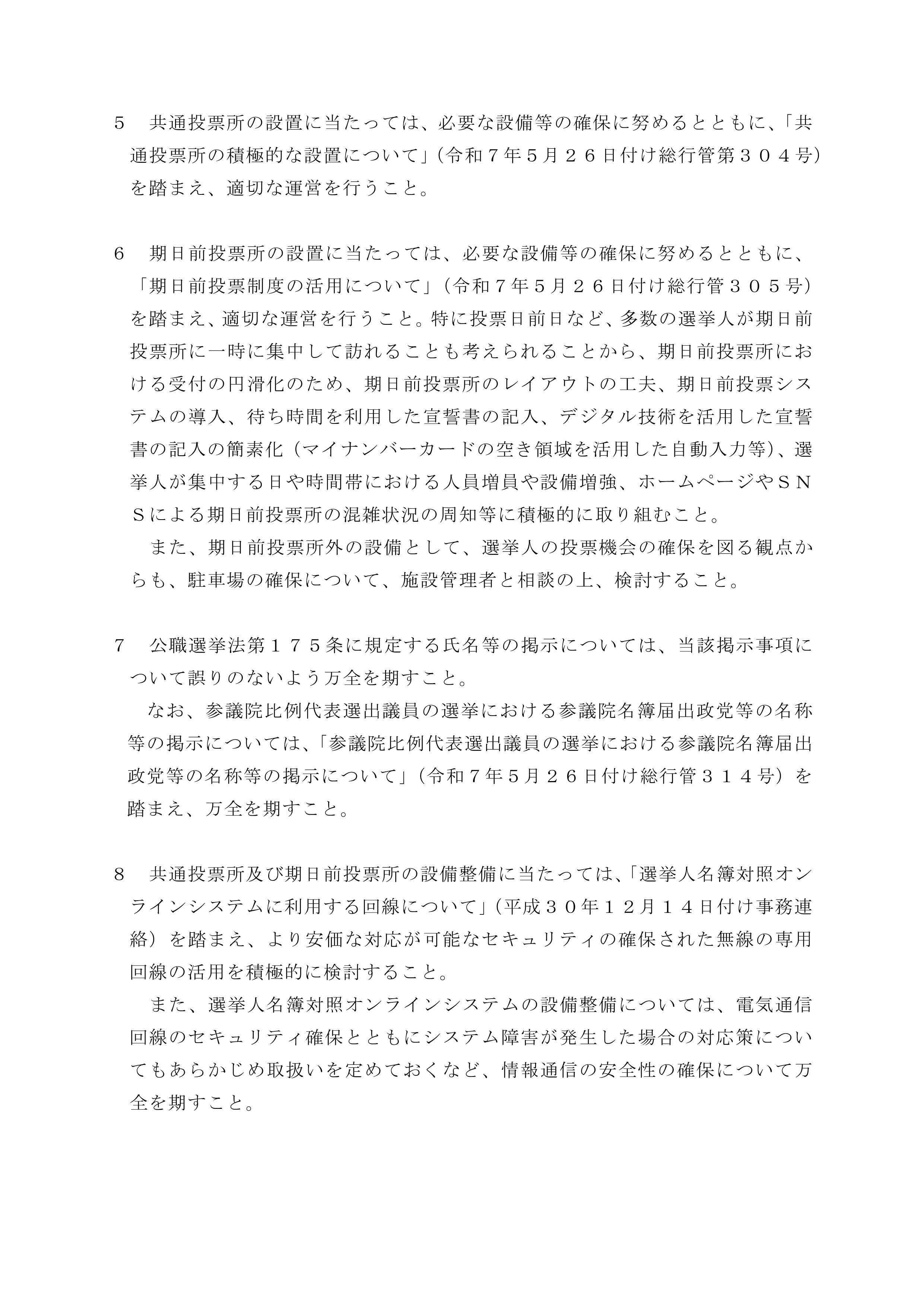
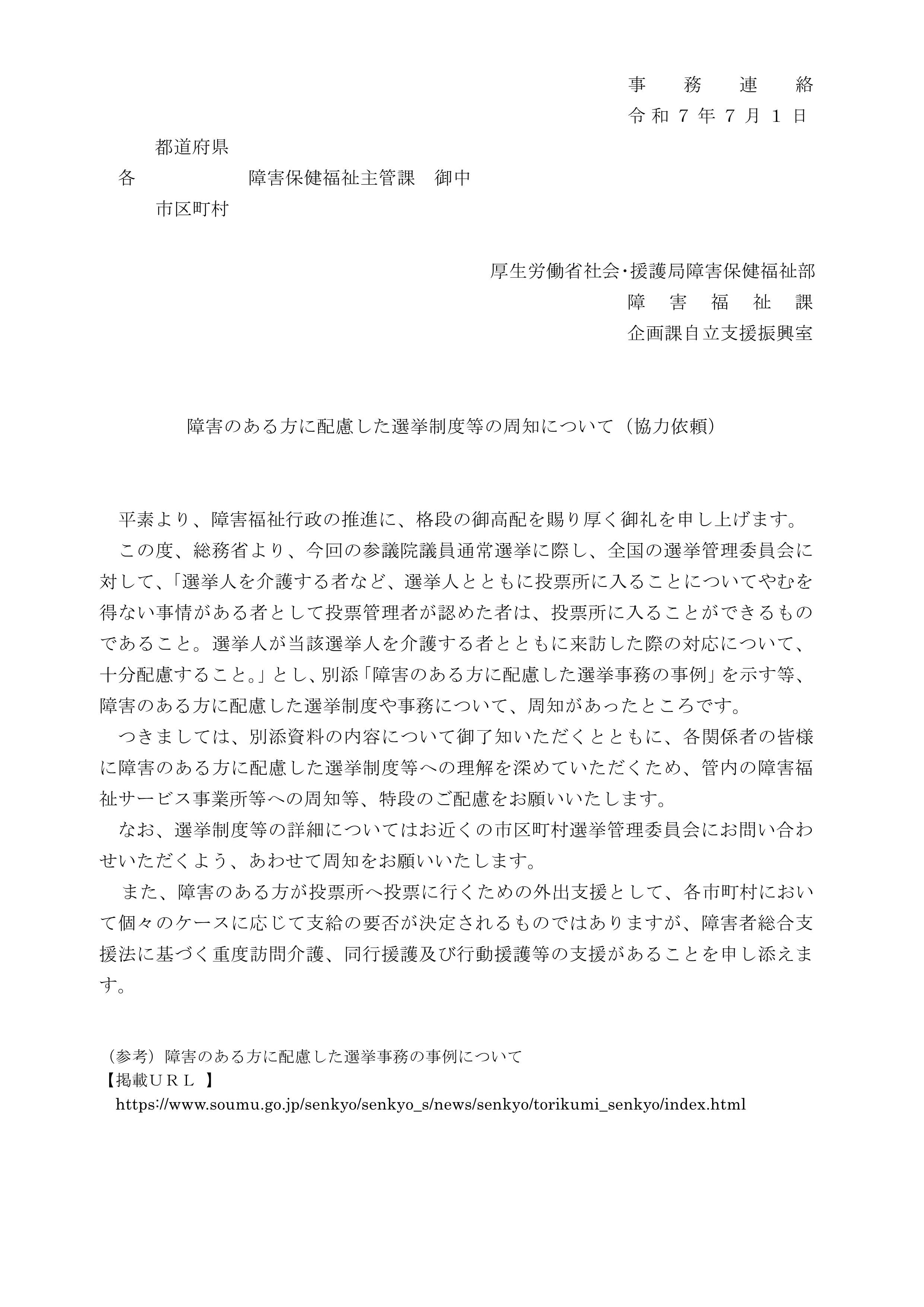
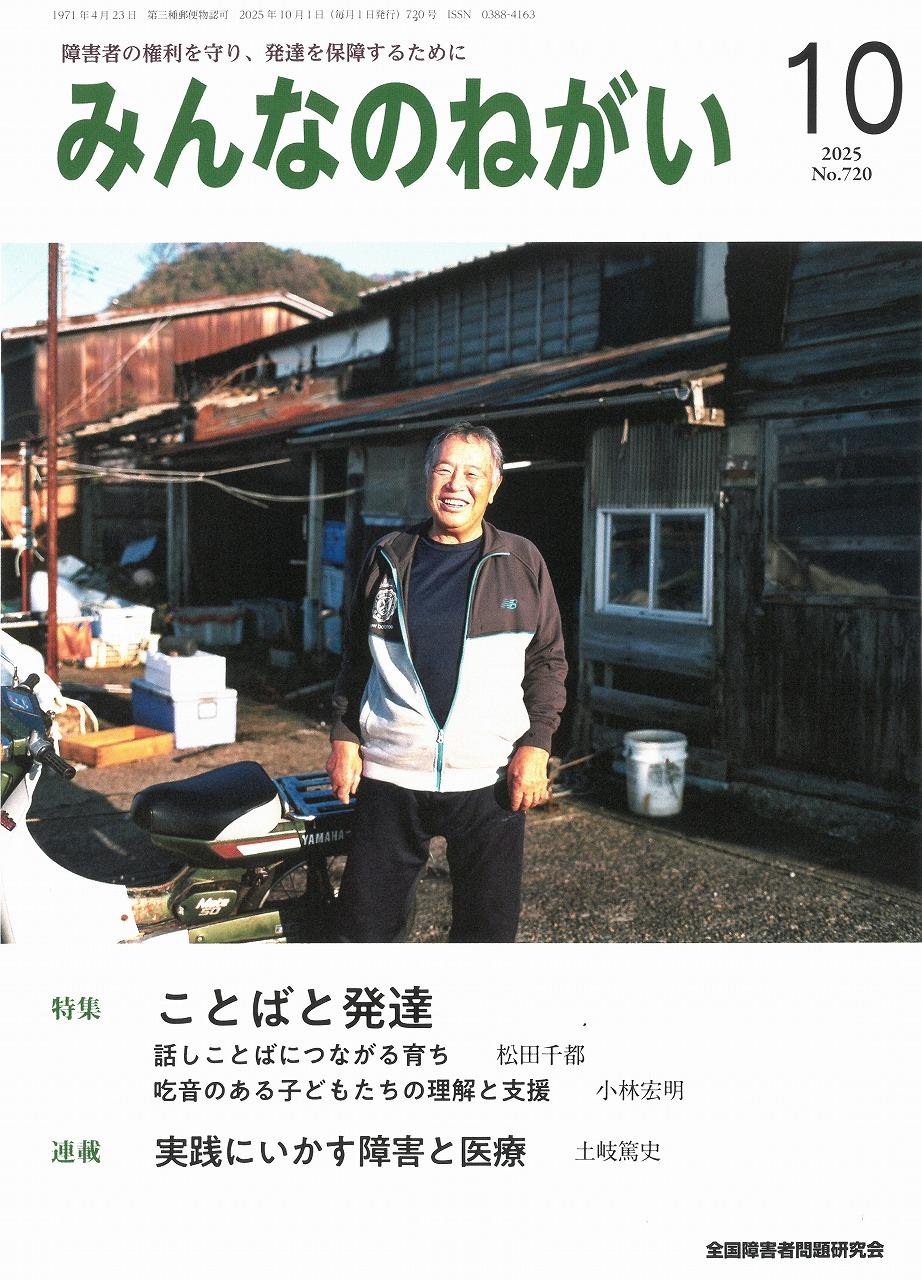
<表紙のことば>
日本海沿いの鄙びた漁村。夕暮れ時は人影も無く静まり返っている。ぶらぶらと散策してると、ひとりの漁師が声をかけてきた。こんなところでカメラを下げて歩いているのが珍しいのだろうか。
俺なんか撮っても絵にならんよ、と照れながらも撮影に付き合ってくれる。漁師はずっと穏やかに笑っていた。
この小さな漁村で彼は今までどんな人生を送ってきたのだろう。
ひとは顔じゃなく、顔つきが大事だと思っている。そして歩んできた人生がそのひとの顔つきをつくる。
僕も彼と同じくらいの歳になったとき、こんな笑顔でいれるよう生きていこう。
土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある
<目次>
◆特設 「試し読み」のページ
1 人として 池田倫子(コーダ)
2 【インタビュー】いま語りたい 心の窓を広げて 有原誠治(アニメーション映画監督)
4 教員のはじめの一歩 木澤愛子(全障研滋賀支部)
6 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)
7 あなたに届けたいこの一冊 横内弥生(臨床心理士)
8 この子と歩む 江見敏恵(吹田市)
11 進め! 推し活道 千葉真実(福島)
12 息子と歩く 千葉桜 洋(写真家)
特集 ことばと発達
14 ことばや見通しの力が自分への自信につながっていく 藤村純子(京都・与謝の海支援学校)
16 自閉症の子どもの「ひとりごと」 末長詩織(奈良教育大学付属小学校)
18 「ことばの心配」を入口として、子どもの発達をまるごととらえる 吉田文子(東京・東久留米市児童発達支援センターわかくさ学園発達相談室)
20 話し言葉につながる育ち 松田千都(京都文教短期大学)
24 吃音のある子どもたちの理解と支援 小林宏明(金沢大学)
26 私ときょうだい 安田美咲(東京)
28 子どものミカタ 竹脇真悟(日本福祉大学)
30 ソーシャルワークってなんだろう? 木全和巳(日本福祉大学)
34 シリーズ 18歳 福本直美(東京)
36 暮らしの場は今 富永安理沙(愛知・ゆたか希望の家)
38 実践にいかす障害と医療 土岐篤史(発達臨床研究・研修サポート、精神科医)
40 ニュースナビ 基本合意15年 薗部英夫(障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会世話人)
42 実践の魅力 河口泰孝(京都 小学校)
45 全障研の支部ニュース、紹介します 辻 恭子(愛媛支部)
46 全障研第59回全国大会報告
48 BOOK/編集後記
裏表紙 おいしいひととき 松村理香(埼玉 おにっこハウス)
デザイン・イラスト
うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、日本印刷、橋野桃子、山内若菜
▶ご購読希望は出版部オンラインへ
◆第59回全国総会で新役員が選出されました 2025年8月9日
2025年度 第59期 役員
全国委員長 越野和之 奈良教育大学教授
副委員長 河合隆平 東京都立大学人文社会学部准教授/研究推進委員長
同 川地亜弥子 神戸大学発達科学部准教授
同 児嶋芳郎 立正大学社会福祉学部教授/NPO法人発達保障研究センター理事長
同 薗部英夫 非常勤職員/日本障害者協議会副代表
同 丸山啓史 京都教育大学准教授
常任全国委員 荒川 智 茨城大学名誉教授/前全国委員長
同 安藤史郎 あかつき・ひばり園
同 石田 誠 特別支援学校
同 木全和巳 日本福祉大学社会福祉学部教授
同 田中智子 佛教大学社会福祉学部教授
同 塚田直也 特別支援学校/「みんなのねがい」編集長
同 深谷弘和 天理大学人文学部准教授
同 古澤直子 特別支援学級
同 別府 哲 岐阜大学教育学部教授
同・事務局長 櫻井宏明 非常勤職員/元特別支援学校
出版部経営委員長 越野和之 (全国委員長兼任)
発達保障研究センター長 児嶋芳郎 NPO法人発達保障研究センター理事長
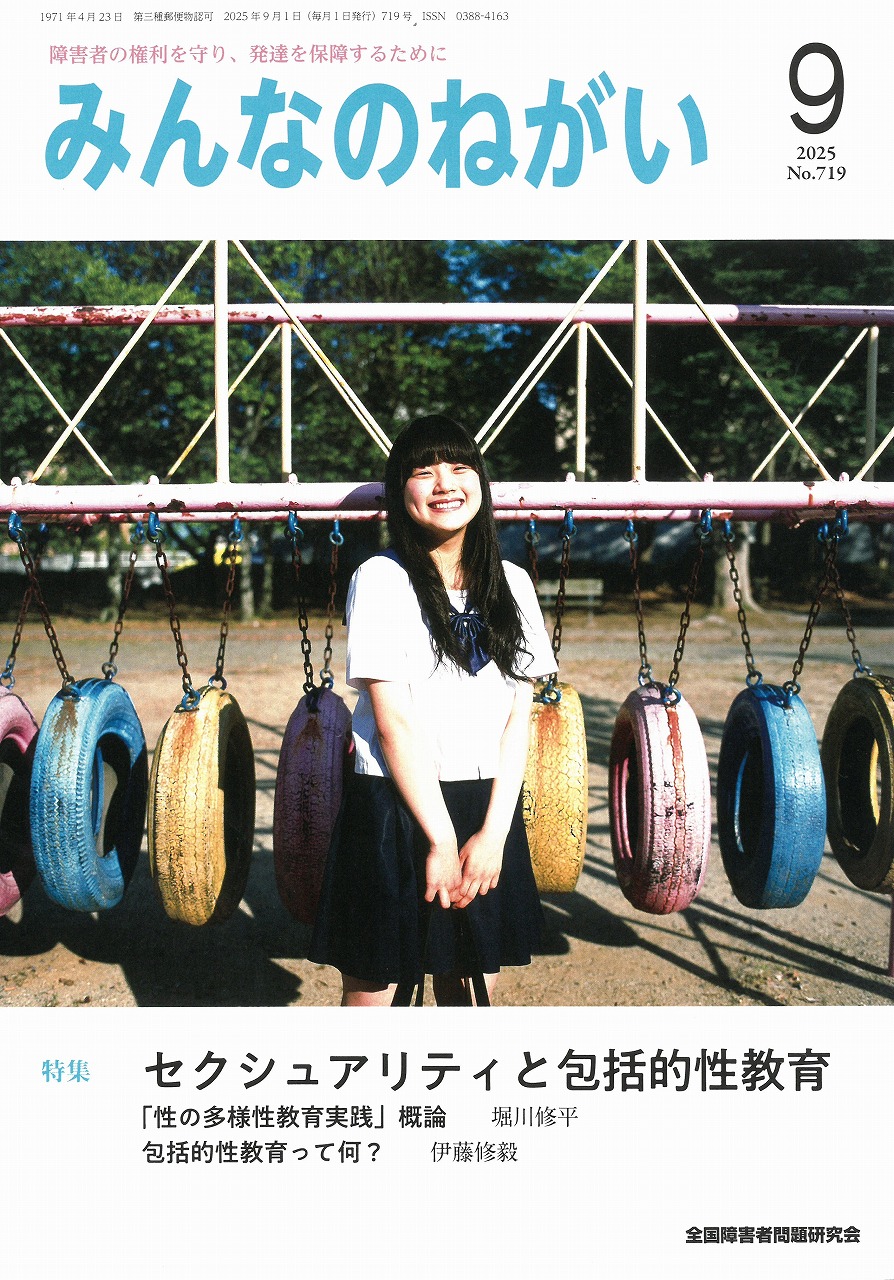
<表紙のことば>
初秋の午後の日差しはまだまだ強い。とある田舎町のちいさな古びた公園で下校中の女子学生に出会う。写真撮ってもいいですか?と聞くと、少し戸惑いながらもはにかんで頷く。純朴で清々しい佇まいに胸がグッとなる。
いきなり道端でカメラを持った知らないひとに声を掛けられるなんて、驚きや不安もきっとあるだろう。それでも撮らせてくれる人は、一瞬でもレンズを介して僕と向き合ってくれる。そしてその一期一会の空気感が僕の写真をつくる。
あの時、彼女がどんな気持ちで僕に撮られていたかは知るよしもない。でもきっと、ここに写る屈託のないその笑顔が答えだと信じている。
土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある
<目次>
◆特設「試し読み」のページ9月号(PDF)へ
1 人として 田門 浩(障害者権利委員会委員・弁護士)
2 【インタビュー】いま語りたい 心の窓を広げて 松林紗希(映画上映会「みんbio」主催者)
4 教員のはじめの一歩 木澤愛子(全障研滋賀支部)
6 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)
7 あなたに届けたいこの一冊 武田佳子(公共図書館司書)
8 この子と歩む 仲 直美(名古屋市)
11 進め! 推し活道 長澤笑子(東京)
特集 セクシュアリティと包括的性教育
13 発達障害とトランスジェンダー男性として生きる僕 高橋れん(東京)
14 包括的性教育って何? 伊藤修毅(日本福祉大学)
16 一人ひとりがこころとからだの主人公に 磯部浩美(埼玉 特別支援学校)
18 対話を重ね、言葉をつむぎ、学びをつくる 寺部佳代子(愛知)
20 素敵な大人になるためのスキルアップ講座 金室修平(千葉 よつかいどう福祉会)
22 「性の多様性教育実践」概論 堀川修平(埼玉大学)
25 息子と歩く 千葉桜 洋(写真家)
26 子どものミカタ 塩田奈津(京都 特別支援学校)
28 ソーシャルワークってなんだろう? 木全和巳(日本福祉大学)
32 シリーズ 18歳 相澤純一(訪問大学おおきなき)
34 暮らしの場は今 大平 光(埼玉 みぬま福祉会太陽の里)
36 実践にいかす障害と医療 安藤佳珠子(日本福祉大学)
38 ニュースナビ 教員の改定給特法 村田信子(全教中央執行委員)
40 実践の魅力 杉谷 伸(滋賀 あゆみ福祉会ホームぽれぽれ)
43 全障研の支部ニュース、紹介します 高橋誠衛(新潟)
44 みんなのひろば
46 BOOK/編集後記
裏表紙 おいしいひととき 黒田絵美(三重)
デザイン・イラスト
うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、日本印刷、橋野桃子、山内若菜
▶ご購読希望は出版部オンラインへ

<表紙のことば>
青森県各地で8月に開催されるねぶた祭り。20年ほど前に友人に連れられてから、その魅力の虜になり毎年津軽の地へ出向いている。青森の冬は長く厳しい。春が訪れ、梅雨が明け、祭りの夏がやってくる。青森の人はこの季節を心待ちにしている。祭りの期間は皆、心も身体も跳ねて躍動する。
運行が始まる夕暮れ時には、青森市のシンボルであるアスパム前の公園にハネトの衣装を来た若者たちが集まってくる。僕はここで祭りの始まりを待つ彼女たちを撮るのが好きだ。
待ち詫びた夏。夢のような時間。夕陽に照らされたその表情は一年でいちばんキラキラと輝いているに違いない。
そう、僕はこの笑顔を見るために青森へと向かうのだ。
土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある
<目次>
特設!「試し読み」のページ8月号(PDF)へ
1 人として 吉田輝男(書家・画家)
2 【インタビュー】いま語りたい 心の窓を広げて 松林紗希(映画上映会「みんbio」主催者)
4 教員のはじめの一歩 木澤愛子(全障研滋賀支部)
6 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)
7 あなたに届けたいこの一冊 越川裕美(学校司書)
特集 戦後80年 ~知る、学ぶ、つなぐ 戦争と平和を自分の言葉で語るために
13 平和の街 三枝信也(山梨・カラフルデイス)
14 悲しみを忘れないで 松田春廣(東京)/土佐和史(写真)
16 戦争と平和を自分の言葉で語るために ー東京大空襲・戦災資料センター訪問記 本誌編集部
20 戦争の記憶を語り継ぐ 沢村智恵子(団体職員)
22 自分らしく生きる 辻 和美(三重・特別支援学校聖母の家学園)
24 私ときょうだい 井上健太郎(福井)
26 子どものミカタ 塩田奈津(京都・特別支援学校)
28 ソーシャルワークってなんだろう? 木全和巳(日本福祉大学)
32 シリーズ 18歳 小林瑞(栃木 自治医科大学小児科医)
34 暮らしの場は今 加藤佳帆(東京 共同ホームさらさ)
36 実践にいかす障害と医療 安藤佳珠子(日本福祉大学)
38 ニュースナビ 改正育児・介護休業法の要点 工藤さほ(障がい児及び医療的ケア児を育てる親の会)
40 実践の魅力 西尾 栞(愛知 障害児デイケアさざなみ)
43 全障研の支部ニュース、紹介します 松島恵美子(青森支部)
44 みんなのひろば
46 息子と歩く 千葉桜 洋(写真家)
47 BOOK/編集後記
裏表紙 おいしいひととき 西岡美紀(大阪)
デザイン・イラスト
うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、日本印刷、橋野桃子、山内若菜
▶ご購読希望は出版部オンラインへ
全国障害者問題研究会
第59回全国大会(広島2025)基調報告(案)
常任全国委員会
2025年7月2日
はじめに
今年は、沖縄での地上戦と、広島、長崎への原子爆弾投下を経て、第二次世界大戦が終結してから80年目です。この年に広島で全国大会が開催されることに特別の想いを抱く人も多いでしょう。2024年にノーベル平和賞が授与された日本原水爆被害者団体協議会の代表委員の田中熙巳さんは、授賞式の講演で次のように話されました。「…原爆被害はいのち、からだ、こころ、くらしにわたるすべての被害を加えるというものでありました。命を奪われ、身体にも心にも傷を負い、病気があることや偏見から働くこともままならない実態が明らかになりました。…(中略)…自分たちが体験した悲惨な苦しみを二度と、世界中の誰にも味わわせてはならないとの思いを強くいたしました」。戦争中、壮絶な体験をされた方々が、次の世代に平和と偏見や差別に苦しむことのないすべての人々の平等な暮らしを手渡したいという願いを持ち続けて活動を続けてこられたことに深い感謝と敬意を表したいと思います。
この年にあっても、ウクライナやパレスチナでの戦火は止まず、イスラエルとアメリカ合衆国はイランへの軍事攻撃を強行しました。全障研常任委員会は緊急声明「戦争するな!攻撃するな!殺すな!命を守れ!」を発表しました。
今年は、介護保険制度の創設25年、障害者自立支援法違憲訴訟基本合意15年という節目の年でもあります。いずれも障害のある人の自立と社会参加、そしてケアの社会化を謳ったものでしたが、現状はどのようになっているでしょうか。
近年、全国各地で社会福祉分野における職員不足、あるいは事業所の閉鎖の話題を耳にするようになりました。2024年度は介護事業者(老人福祉・介護事業)の倒産件数は過去最多となっており、慣れ親しんだ地域で暮らし続けることが困難になっている人が多くいます。また就労継続支援A型事業所の閉鎖が相次ぎ、多くの障害者が解雇され、路頭に迷うこととなりました。いずれも報酬改定をきっかけとしたものですが、そもそも福祉事業の基本報酬は低く、職員を安定して継続的に雇用できるものではありません。日々、福祉労働者が障害のある人や家族と真摯に向き合い支援しても、本来、それを下支えすべき国家によって、その梯子を外され続けている状況です。
福祉事業に営利を目的とした企業の参入も目立つようになりました。全国でグループホームを運営していた企業の劣悪な支援に対して、自治体の指定取り消しの処分に続き、国も同一企業が運営する他の事業所にも福祉事業の指定更新を認めないとするいわゆる「連座制」を適用したことによって、多くの障害者と家族が混乱させられました。福祉事業に多様な経営主体の参入を認めるのであれば、適切な運営がされているかどうかを監督する責任は行政が果たさなければなりません。
障害基礎年金の支給決定が、日本年金機構の人事により左右されていた可能性が報じられました。年金などの所得保障は今日の社会で生活する上で不可欠な制度です。それが、属人的な判断に影響されていたとすれば言語道断です。
このような事象は、社会福祉から“社会”が除かれ、個人的な幸福だけを追求する、しかもそれが手に入るかどうかは個人の経済力に左右されるという市場化された福祉が広がってきたことによるものです。効率や利益を追求し、個々人が競争社会の中で勝ち残りを目指す資本主義社会と、一人ひとりの多様性が尊重され、誰もが安心して暮らせる社会のあり方は、本質的に相容れないものです。今こそ、すべての人に人間らしい権利を保障する社会全体の福祉を追求すべきときです。私たち一人ひとりは社会福祉の実現に向けて決して傍観者ではいられません。
こうした動きの一方で社会を切り拓く連帯の輪も広がってきています。
2025年6月27日、最高裁第三小法廷は、2013~15年の国による生活保護費の引き下げを違法とする画期的な判決を下しました。この判決を引き出した「いのちのとりで」裁判や、2024年に同じく最高裁において歴史的な勝訴判決を勝ち取った優生保護法をめぐる裁判、職親からの長年の虐待をめぐる裁判などにおいては、現状を変えなければならないと勇気を持って立ち上がった原告たち、さらにはそれを支援する人々の輪が大きく広がりました。学問の自由を脅かす日本学術会議法の改正に関しても多くの人々が反対の声を挙げました。実践面においても、被災地域における障害のある人を取り残さない復興や、高齢化、子育て、触法など、多様なニーズに応える実践力も集団的に高めてきました。
いくつもの節目を迎える今年、改めて、私たちの日常の暮らしの中にある願いや困りごとを共有しながら、誰もが安心して暮らしていける共同的な関係を私たちの手に取り戻し、それを支える公共の復権を目指すための「社会」福祉のあり方について皆で考えていきましょう。
Ⅰ 乳幼児期をめぐる情勢と課題
(1)療育の質は「子どもの最善の利益」を軸に
「やってみたいなぁ」「今日は何をするのかな」。子どもたちは、生活や遊びのなかで世界への期待をふくらませます。大人や友達と活動を積み重ね、「あんなふうになりたいな」とあこがれ、自らをゆたかにしていきます。からだを思いっきり動かし、楽しさやもどかしさなどの感情に満たされた遊びが、安心できる生活と切り離されずにあることが大切です。
そう考えた時、現在こども家庭庁を中心にすすめられている保育や障害児支援について、子どもの最善の利益をないがしろにしていないか、注意深く検討する必要があります。
例えば、「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」です。4月から、市町村を実施主体にしてはじまったこの制度では、日によって預けられる場所が異なることも想定されますが、それでは子どもが大人と安心した関係を築くことはできません。「昨日の続きで遊びたい」とねがっても、生活と遊びの連続性がありません。医療的ケア児を含め障害のある子どもも利用できることになっていますが、そのために必要な条件整備は保障されていません。
2024年には児童発達支援ガイドラインが改訂されました。このガイドラインの普及により、大人が求める能力が身につくように子どもの行動を変えることが発達支援の目標とされ、発達の基盤となる生活から切り離されたところで支援が行われることや、一人ひとりに即して吟味されるべき支援が画一化されることが危惧されます。
止まらない物価の高騰と広がる困窮は、子どもたちがゆたかに育つ生活基盤を脅かしています。くらしを維持するための就労によって親子通園療育に通いたくても通えず、保育所に通いながら短時間でも児童発達支援を利用したり、療育時間の延長を希望する保護者の実態があります。療育に通うことと安定した生活を築くことを両立させるための就労条件などが社会的に保障されなくてはいけません。また、地域の保育園・幼稚園に通う場合でも、保護者が子どものねがいをつかみ、安心して子育てができるための支援のあり方も問われています。発達を保障するべき療育が、営利主義のもとで、子どものねがいに目を向けず、発達を侵害するものになっていないでしょうか。多様な療育のあり方や延長療育など、地域の実情に合わせて考えていくべき課題はたくさんあります。2025年2月に開催された発達保障をめざす保育実践・療育実践交流集会(NPO法人発達保障研究センター)では、子どもたちの発達を保障し、保護者が安心して子育てに向かえるような保育・療育実践について学び合いました。参加者からも、時間をかけて保護者と共同して子どものねがいを知っていくことが大事、という感想が寄せられました。子どもの最善の利益を軸にして保護者とともにつくりあげる療育のあり方について語り合い、自分たちの言葉で「子どもの発達を保障する療育」を訴えていきたいと思います。
(2)ねがいに応える制度を
療育の制度上の基盤である児童発達支援は、日額報酬制、利用契約制度、応益負担の枠組みのもとで、保護者の利用料負担や不安定な財務状況の中で運営されています。こども家庭庁は、制度の持続性と他の制度との平等性を論拠として、この制度の妥当性を譲りません。教育分野では、一部負担は残しているものの、多子世帯の大学や専門学校などの授業料が無償となりました。2019年からの幼児教育無償化を受け、療育も3~5歳児の利用料は無料になっています。しかし、子どもの育てづらさや障害で保護者の気持ちが揺れやすい0歳から2歳児期の療育では利用料負担があります。療育は子どもの命と発達を保障するものであり、早期からの公的な保障が必要です。住民のねがいに応え、自助努力で療育の利用料を無償化している自治体もありますが、費用がかかるので療育を利用しないというケースも実際にあります。また、事業所と契約していても、保護者の精神面や生活の状況によって子どもが継続して療育に通うことが難しいケースもあります。家庭への支援が必要なのですが、電話をするとお金がかかる、家庭訪問をするとお金がかかる、といったように、今の制度の枠組みは、ほんとうに支援を求めている人への支援を阻害する仕組みです。
子どもたちのねがいに応える療育と、子育てのなやみを一緒に分かち合って歩んでいく支援が必要です。保護者の収入や生活状況、子どもの年齢や障害の程度によって必要な支援が受けられないことがあってはいけません。平等性の観点からも療育は無償であるべきなのです。自己責任論や市場原理に気づかぬうちに支配され、見えづらくなっている課題を、他の児童との平等(障害者権利条約第7条1項)の視点で浮き彫りにしてく必要があります。
(3)みんなで展望を語り合おう
2023年度から実施自治体への国庫補助がはじまった5歳児健診は、今年度には実施率を引き上げるために補助金が大幅に引き上げられました。目的は、発達障害の発見や不登校への早期からの対応と言われており、各自治体でも実施の方向で検討されています。しかし、私たちが大切にしてきた乳幼児健診は、問題を発見して終わりなのではなく、母子保健システムの一環として、地域の身近な存在として、早期から一緒に子育てを支える保健師の活動などと結びついて発展してきました。それぞれの地域の出生数や地域資源にあわせて子育てを応援するシステムを構築してきたのです。ライフステージの最初の時期に、発達を保障する公的な仕組みは、その後の教育、福祉の分野でのゆたかな自立につながっていきます。5歳児健診や療育など、国の仕組みを画一的に地域に適用するのではなく、研究運動や要求運動を通して地域の状況を捉え、現代的なニーズ、既存のシステムの課題を見出し、住民の要求にかなうシステムとして再構築していく必要があります。各地域で、分野や職種を越えてつながり、地域の現状、課題を語り合う集まりがもたれています。地域ごとに条件は異なっていても、共通する根本的な問題と展望を見出すことも必要です。そのために、地域をこえて状況や課題、思いを出し合うことで、問題の根っこを捉えていくことが求められています。
Ⅱ 学齢期をめぐる情勢と課題
(1)子どもの発達を長い目で確かめ合う
特別支援学校の教師、下田有輝さんは、子どもたちに「自分たちで考えたり、悩んだり、選んだりしながら、一人ではできなくても、仲間と力を合わせればねがいは実現するという手応えや感動を、人間らしい営みの中で保障していくことが私たちの専門性だ」と語っています(『障害者問題研究』第53巻1号、2025年)。教師の専門性は日々子どもたちと過ごしながらその思いやねがいをつかみ、教材を吟味し、授業を通してそのねがいを子どもたちと共に実現していくところにあります。専門性を磨いていくためには、子どものねがいや育ちについて、教師の仕事の価値について、自分の言葉で語り、綴りながら、試行錯誤することが必要です。
しかし、学習指導要領による教育課程の押し付けや「スタンダード」は、目の前の子どもから出発する教育を大きく制約します。教育のICT化、「個別最適化」の名の下に教育のマニュアル化と画一化が広がっています。私たちは、学校現場の苦境や理不尽さを訴える教師たち、子どもへの信頼や教育の希望を見失したくないというねがいを受けとめ、すべての子どもが安心して楽しく学ぶことのできる学校づくりのための研究運動を進めていきたいと思います。
特別支援教育にも観点別評価が導入され、子どもの発達を細かく切り刻むような評価が浸透しています。目の前の子どもの行動をなんとかしたいという思いから、行動変容を謳う指導技法が頼りに見えることもあるかもしれません。しかし、教師が子どもたちの行動の背後にある苦しみや悲しみを聴きとり、内面に潜むねがいをつかむためには、じっくりと時間をかけて、子どもたちが安心できる関係を結ぶことが欠かせません。
教育の内容を縛るような官製研究に追われて、子どもの姿や授業の様子を振り返る余裕も奪われ、授業準備にすら時間をかけられないという苦悩も深まっています。『みんなのねがい』の2025年5月号の特集では、こうした厳しい現状にあっても、同僚とともに悩みながら、子どもたちの心を揺さぶるような授業づくりに取り組んでいる実践が紹介されています。
全国大会に持ち寄られるレポートには、子どもたちのねがい、教師のねがい、保護者のねがいがより合わさりながら、子どもが育ちゆく姿が豊かに綴られています。教師が自分のねがいを語り、思いを分かち合うことが難しくなっているからこそ、実践や子どもの発達の事実を語る言葉を吟味しながら、教育の喜びや希望を見出せるような議論をしていきましょう。「ライフステージを貫く実践と課題」の分科会も全国大会の醍醐味です。子どもも教師も短期間のうちに目に見える成果が求められがちな今、ライフステージを貫く長い目で子どもの発達を確かめ合う視点を大切にして、学校教育の役割や課題を深めましょう。
(2)一人ひとりに合った場の整備と教育の質
文科省の「インクルーシブな学校運営モデル事業」のもとで、いくつかの自治体ではインクルーシブ教育に関する事業が取り組まれ、身近な地域や同じ学校で共に学ぶことが強調されています。本来、共に学ぶことの追求と、障害のある子ども一人ひとりに合った教育の場の充実は矛盾するものではありません。子どもたち一人ひとりの固有のニーズが大切され、安心して学ぶことのできる集団や環境のなかで発達が最大限に保障されることが、社会に参加していく土台となります。インクルーシブな教育や社会を実現していくうえでも、特別支援学校や特別支援学級の条件整備は欠かせません。しかし、特別支援学校の設置基準は既設校には適用されないため、特別支援学校の過大・過密化は解消されていません。新設予定の学校ですら、すでに設置基準を満たしていなかったり、校舎の高層化が計画されている地域もあります。引き続き、設置基準の内容と運用の改善に向けた運動が求められます。また、2022年に出された「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について」(文部科学省通知2022年4月27日)が、特別支援学級の在籍や開設の状況、教育機能に及ぼす影響も長期的に検証していく必要があります。
今通常国会で成立した「給特法改定」では「教職調整額」の増額が示される一方、特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室担当の教員に支給されてきた「給料の調整額」を半減させる決定が強行されました。文科省は、通常学級にも障害のある子どもや支援が必要な子どもが多数在籍し、学校全体で特別支援教育を進める体制となっていることから、特定の教職員のみに調整額を支給するのは不均衡と説明しています。一方、特別支援学校では担任以外の複数の教職員が子どもの指導や支援に関わっていることを理由に、特別支援学校と特別支援学級の担任に「学級担任手当」加算を支給しないとし、さらに「主務教諭」を新設、そこに特別支援教育コーディネーターを位置づけました。今回の「給特法改定」はそもそも教師の仕事にゆとりをもたらすものではなく、それに加えて、障害児教育の専門性を否定し、どの子も安心して学べるインクルーシブな学校づくりへの共同の努力を阻むものです。
私たちは、通常の学校教育全体の改革として、インクルーシブな学校づくりを進めるなかでこそ、すべての子どもの教育権保障が展望できることを確認してきました。日々子どもに関わる教職員には教育の内容を決定する裁量が保障されるべきであり、そのためには、同僚性のもとで専門性を発揮することができる労働環境が欠かせません。権利としての障害児教育の歴史は、差別的な特殊教育を乗り越えて、障害のある子どもたちに憲法や教育基本法が謳う権利としての教育をひとしく保障するために、障害があるがゆえの困難や固有なニーズに応えることと、どの子にも必要とされる教育を手渡すことの統一をめざしてきました。通常学校・学級を含めて教師としての誇りある仕事とそれを保障する労働条件を追求していくなかで、障害のある子どもの教育に固有な専門性を深めていきましょう。
インクルーシブ教育の実現には、教員配置などの条件整備と子どもの実態に即した柔軟な教育課程の運用が不可欠です。日々子どもと向き合っている教師たちには、自律的で自由な議論、研究・研修の機会が保障されなければなりません。「こんな教師になりたい」「こんな授業をしたい」と憧れや希望を持ちながら、教師として成長することのできる教職員集団づくりや学校づくりを進めていきましょう。
(3)安心して過ごせる放課後や地域の生活をつくる
インクルーシブ教育の実現には、学校だけではなく、学校外の地域の隅々にまで、子どもが安心して過ごせる環境をつくることが必要です。放課後の生活を支える放課後等デイサービスでは、不安定な財政・運営体制のもと、厚生労働省の放課後等デイサービスガイドラインに対応した「支援」を行わざるを得ない場合も多く、学校、家庭とは異なる「第三の場」としての時間や空間は狭められがちです。この間、放課後等デイサービスでの虐待が多く報じられていますが、その背景には、子どもたちの楽しく安心できる生活を支えるには不十分な職員配置基準があります。指導員は、子どもの様子や実践を振り返りながら活動を展開する余裕を奪われています。
厚生労働省は放課後等デイサービスガイドラインによって現場に支援の質を高めると言いますが、実践の困難の背景には利用契約制度と日額報酬制があり、乏しい条件を改善せずに、ガイドラインの具体化だけが一方的に求められれば、実践現場はますます疲弊します。利用契約を結んで個人のニーズを満たすという「商品化」の発想ではなく、すべての子どもに豊かな放課後生活を保障する公的責任を認め、それに見合う制度と条件整備を行うことこそが求められます。
子どもがどのような学校生活を送っているのか、放課後・休日はどのように過ごしているのか、学校でも事業所でも互いの様子が見えにくくなっています。日々の生活や仕事に追われて保護者もお互いの悩みを聴き合う機会が減り、孤立する保護者も少なくありません。コロナ禍以降、学級懇談会を開催しなくなった学校もあります。子どもの生活が見えにくくなるということは、保護者の不安や悩みが見えにくくなるということでもあります。こうして子どもの姿や保護者の苦悩を共有しにくいことが、保護者の自己責任意識をいっそう助長し、保護者が学校や事業所に安心や信頼を寄せにくくさせているのではないでしょうか。
学校や事業所が地域のさまざまな資源や機関とも手をつなぎ、障害のある子どもの育ちを関係する人たちみんなで支える仕組みを整えながら、障害のある子どもを育てる保護者や家族が排除されず、安心して暮らせる地域をつるために何が求められているのか、これを明らかにする研究運動を進めましょう。
Ⅲ 青年期・成人期の情勢と課題
(1)家族依存の限界と暮らしの場の整備
2024年7月、千葉県長生村で、父親が重度の障害のある息子を殺害するという痛ましい事件が発生しました。両親は自宅での介護に限界を感じ、長期入所を希望していたものの施設が見つからず、ショートステイを利用しながら自宅での介護を続けていたと報じられています。いわゆる「老障介護」の状況でした。命が絶たれるという決して許されない事件ではありますが、その背景には、重度障害のある人が安心して暮らせる場の整備が進まず、家族のケアに過度に依存している現実があります。加えて、入所施設のあり方など、当事者や家族、現場の職員の声を十分に踏まえない政策決定がなされてきたという構造的な問題もあります。
佛教大学の田中智子研究室とNHKが共同して2024年に全国の自治体を対象に行った調査によれば、入所施設の利用を希望しながらも空きがなく、待機状態にある人が少なくとも約2万人にのぼることが明らかになりました。待機者の7割以上は知的障害者であり、特に重度の障害者が暮らせる住まいが全国的に不足している実態が浮き彫りになりました。また、調査では自治体ごとに待機者の実態把握の方法が異なり、回答のあった自治体のうち3割は、待機者数そのものを把握していないことも分かりました。全国障害児者の暮らしの場を考える会の事務局長である九内康夫さんは「暮らし方に対する概念や希望する暮らしの形は、人それぞれで違うからこそ、多様で選択できる暮らしの場の整備が必要です」と指摘しています(『みんなのねがい』4月号。連載「暮らしの場は今」)。
公的責任が縮小されるなかで、まずは待機者の実態を正確に把握する仕組みづくりが求められます。その上で、実態に即した暮らしの場の整備が不可欠です。
(2)報酬改定の影響と制度の20年を問う
2024年4月の報酬改定の影響に関する、きょうされんの調査結果が報告されました。この調査では、生活介護では7割以上の事業所が、共同生活援助(グループホーム)では9割近くの事業所が、基本報酬の減算対象となったことが明らかになっています。生活介護に導入された「時間刻み報酬」や、取得可能な加算の少なさが背景にあると指摘されています。
障害福祉の現場では、働き手の不足が深刻化しています。処遇改善加算による賃金改善も言われますが、事業所の加算取得状況により賃金格差が生じています。求められるのは加算による調整ではなく、基本報酬そのものの底上げです。深刻な働き手不足は、実践や運動の継承にとっても大きな課題です。実践や運営を長年担ってきた人たちから新たな人たちへバトンを渡していくための方法をの職場や、運動のつながりの中で共有するとともに、そのつながりを生かして、国に対して働き手の確保に向けた抜本的な対策を求めていく必要があります。
2025年は、障害者自立支援法違憲訴訟の基本合意から15周年の節目の年にあたります。同法は、利用契約制度への移行、三障害のサービス一元化、利用者負担の導入など、障害福祉制度を大きく転換した法律でした。その後、応益負担を焦点として違憲訴訟が提起され、国との和解にあたり、基本合意文書が結ばれました。しかし、新たに制定された障害者総合支援法でも、公的責任の縮小や市場原理の導入は依然として続いています。その結果、グループホーム「恵」での過大徴収や虐待の問題に象徴されるように制度の矛盾が各地で顕在化しています。障害者自立支援法違憲訴訟では、「トイレに行くのにも金がかかるのか」という当事者の声が、運動の大きな指針となりました。同法の成立から20年を迎える今、改めて当事者の「ねがい」を軸に、障害のある人の権利保障は国の責任であることを、社会として再確認していく必要があります。
(3)障害のない人と平等に社会参加できる社会を
2014年に日本が批准した障害者権利条約は、障害のある人が他の人と平等に社会に参加し、尊厳をもって生きる権利を保障しています。障害者差別解消法が2024年に改正され、企業などの民間事業者による障害のある人への合理的配慮が義務化されてから1年が経過しました。しかし、現状では、障害のある人の声を十分に反映しない、一方的な対応となっているケースも見られます。
毎日新聞が2025年に連載している「これってわがままですか?障害者差別を考える」では、駅や飲食店などでICT化による無人化が進み、障害のある人たちにとって利用しづらい場面が増えている実態が報告されています。障害のある人のために環境を整えるのではなく、すべての人が暮らしやすい社会を実現するために、生じる課題の解消に取り組んでいくことが重要です。
2024年7月には優生保護法について、立法時点で違憲だったとする画期的な判決が出されました。障害のある人が子どもを産み育てる権利を奪われてきた事実が改めて問われる中で、「障害のある人のケアする権利」に注目が集まっています。『みんなのねがい』2024年11月号では「恋愛・結婚・子育て」が特集され、2025年2月に発刊された『障害者問題研究』では「障害のある人のケアする権利」がテーマとなりました。障害のある人が子どもを育てたり、親の介護を担ったりする際に、ヘルパー制度やグループホームなどを活用できるよう、制度的な裏付けを明確にし、全国どこでもその権利が保障される仕組みづくりが必要です。
障害のある人たちが、18歳以降にも学ぶことのできる場や機会の提供も、「障害のない人と平等」との点では不充分です。引き続き、18歳以降の学びの場(専攻科、大学、福祉型専攻科、生涯学習)を保障する取り組みを進めましょう。
Ⅳ 研究運動の課題
(1)多彩な活動を発展させよう
私たちの研究運動は、身近なところでの語り合いを大切にしてきました。地域に、職場にサークル活動をつくり、『みんなのねがい』の読者会をつくってきました。こうした活動の意義は、今も変わりません。
各支部の学習会や、各地方でのブロック集会なども、みんなで顔を合わせて学ぶことのできる場です。それぞれの支部・ブロックが、工夫して企画しています。
春には、発達保障研究集会をもち、私たちの目の前にある課題を考えています。また、今年の7月には、関西で「みんなのねがいセミナー」を開催しました。
オンラインによる学習活動も、コロナ禍の下にあった2020年以降、活発に展開しています。年2回の「教育と保育のための発達診断セミナー」は、全国の人々の学習要求に応える内容であり、仲間が広がる機会にもなっています。「発達保障をめざす保育実践・療育実践交流集会」も、多くの人の参加を得ています。また、研究推進委員会による「オンラインゼミ」も、さまざまな実践について考え合えるものです。
そして、夏の全国大会は、私たちの研究運動にとって特に重要なものです。今回の広島大会を充実したものにして、来年の滋賀大会につなげていきましょう。
オンラインの利点を活かすとともに、実際に会って話し合うことを大切にしながら、発達保障のための研究運動を進めていきましょう。
(2)一人ひとりのねがいから出発しよう
私たちの研究運動が大切にしてきたのは、一人ひとりの「ねがい」です。「このことに困っている」「こういうものが地域にほしい」「職場で納得のいかないことがある」「あんな実践をしてみたい」。こうした一つひとつのねがいが、研究運動の出発点です。
私たちの研究運動は、完成された理論を学ぶことではありません。十分に整理された情報を吸収することでもありません。それぞれの人が自分の仕事や生活、自分の思いを語ることに、小さくない意義があります。一人ひとりが研究運動の主体であり、誰もが研究運動の担い手です。
身のまわりの実態を出し合いましょう。考えていることを話し合いましょう。取り組んできたことを伝え合いましょう。
全国大会の分科会は、参加者が持ち寄るレポートが研究の土台です。実態を記し、ねがいを書きとめ、実践をつづることが、私たちの研究運動の力になります。仲間と協力してレポートをまとめることも、大切にしたい取り組みです。レポートをもとに語り合い、考え合うことが、障害者の権利保障・発達保障に結びつきます。
(3)教育や社会福祉のあり方を考えよう
権利保障・発達保障に向けて、教育や社会福祉のあるべき姿を問い続けていきましょう。
長年にわたり、国や地方自治体の責任を曖昧にする制度改変が重ねられてきました。学校教育の領域をみても、社会教育・生涯学習の領域をみても、条件整備は不十分です。福祉領域では、事業の多くが民間任せにされており、民間事業者と「利用者」が契約を結ぶかたちが広がっています。「サービス」という言葉が行き交い、営利企業の参入が目立つ分野もあります。
同時に、現場の実践が制度的なものに縛られてもいます。学校教育に関しては、学習指導要領に従うべきことが強調され、特定の指導方法・支援技法が教室にもちこまれるような状況もみられます。福祉領域では、事業所への「報酬」をめぐる仕組みが現場に葛藤をもたらしています。
長い時間をかけて政策によって押し付けられてきた現状は、批判的に問い直されるべきものです。現在とは異なる教育や社会福祉のかたちがあった歴史も振り返りながら、教育や社会福祉の今後のあり方を描いていきましょう。
教育や社会福祉の仕事の核心を確認することも重要です。制度の変遷に振り回されることなく、仕事のなかでめざすべきものを確かめながら、求められる専門性の内実を考えていきましょう。
(4)平和を追求しよう
社会の問題に向き合っていくことも大切です。
障害者・患者9条の会の「リレートーク」において、脳性まひのある池田光さん(全障研廿日市サークル)は、「障害者は平和な世でしか生きられない」「戦争はイヤです」「戦車もミサイルも要りません」と語っています。
現在の世界において、戦争・武力行使に抗い、平和を追求することは、極めて重要な課題です。障害者の権利保障・発達保障は、平和な社会のなかでこそ十全に実現していくことができます。
戦争は、障害者の生命と生活を脅かし、たくさんの人に新たな障害をもたらします。障害者の権利保障・発達保障と戦争とが相反するものであることを、歴史の事実をふまえて繰り返し語り、次の世代に伝えていかなければなりません。
50年前に終結したベトナム戦争では、米軍が使用した「枯葉剤」によって、甚大な被害がもたらされました。PFAS(有機フッ素化合物)による汚染の問題にもみられるように、軍事活動は環境の汚染につながり、私たちの生命と健康を脅かします。軍隊が排出する大量の温室効果ガスは、気候危機をいっそう深刻なものにし、私たちの安全を奪っていきます。
戦争も軍隊もない平和な社会をめざすこと、障害者の権利保障・発達保障を追求することは、深く結びついています。「戦争と障害者」の歴史を学び、今の世界の動向をつかみながら、戦争を許さない世論、軍拡を認めない世論、核兵器の廃絶を求める世論をつくっていきましょう。
日本には、戦争放棄と戦力不保持を明記した憲法があります。憲法9条を守り、憲法9条の価値を確かめていきましょう。
(5)仲間を広げ、学び合おう
研究運動を進めることで、仲間が広がります。仲間が広がれば、研究運動はさらに豊かなものになります。
私たちの研究運動の軸になるのは、月刊誌『みんなのねがい』です。誌面には、障害者や家族、さまざまな領域の実践者が登場します。小さな子どもの話題から、高齢期の人をめぐる話題まで、幅広い内容になっています。『みんなのねがい』を読み、誰かと話をすることで、『みんなのねがい』の輪が広がります。
季刊誌『障害者問題研究』も、私たちの研究運動に欠かせないものです。理論的な探究を進めるとともに、実態や動向をまとめ、実践を報告しています。各号の特集を読むと、そのテーマをめぐる全体状況に迫ることができます。オンラインで開催されている「『障害者問題研究』を読む会」に参加すれば、さらに理解が深まり、人どうしのつながりも生まれます。
身近なところで読者会を開き、人と出会い、みんなで語り合うことは、魅力的な取り組みです。日常のなかで、「気になる内容が載ってたね」「ここに書かれていること、どう思う?」と話題にすることも、私たちの研究運動です。
全障研の仲間を広げ、『みんなのねがい』や『障害者問題研究』の輪を大きくしながら、私たちの研究運動を豊かなものにしていきましょう。
*基調報告案へのご意見は、7月30日までに、電子メールなど文書で全国事務局にお寄せください。
電子メール info@nginet.or.jp FAX 03-6265-0194
みんなのねがいセミナー 100人こえるご参加ありがとうございました
前半は、みんなのねがいの人気コーナー「この子と歩む」に執筆された、小川真奈美さん(滋賀)、江畑早苗さん(京都)、山口歩さん(奈良) から、我が子の子育て、そこで出会った様々な出来事や人たち、そして現在とこれからを語っていただきました。
まさに涙あり笑いありのあっという間の1時間でした。
後半は、休憩時間にフロアから出た質問を中心に、白石恵理子さんのコーディネートで、トークセッションが展開されました。就学前のこと、親同士のつながりのこと、成人期に入ってからのことなど、「そこもう少し聴きたかった!」という柱に沿って、ご自身の経験やお考えをたっぷりと話していただきました。
まだまだ聴いていたい! と 思える素晴らしい時間でし た。
(京都支部長 石田誠)
日時=2025年7月6日(日)13:00~15:30
会場=京都教育大学 C棟2階 大講義室1
●テーマ=今こそ、ねがいを語り合おう 〜親の声、聞いてますか?〜(仮)
療育施設や保育園、学校の先生♪
作業所やグループホーム、入所施設などの職員さん♪
日々奮闘されているご家族のみなさん♪
立ち止まって、親御さんの本音にふれて、感じ合いませんか?
●参加費=1000円(「みんなのねがい」のまとめ購読担当者の方はご本人とお連れの1名まで無料)
*学割=500円(25歳までの学生のみなさんを対象に) 登場しました!
●参加申込み6月30日で締め切らせていただきました

▼チラシ第二弾です(裏表に印刷して折ってくださいね)
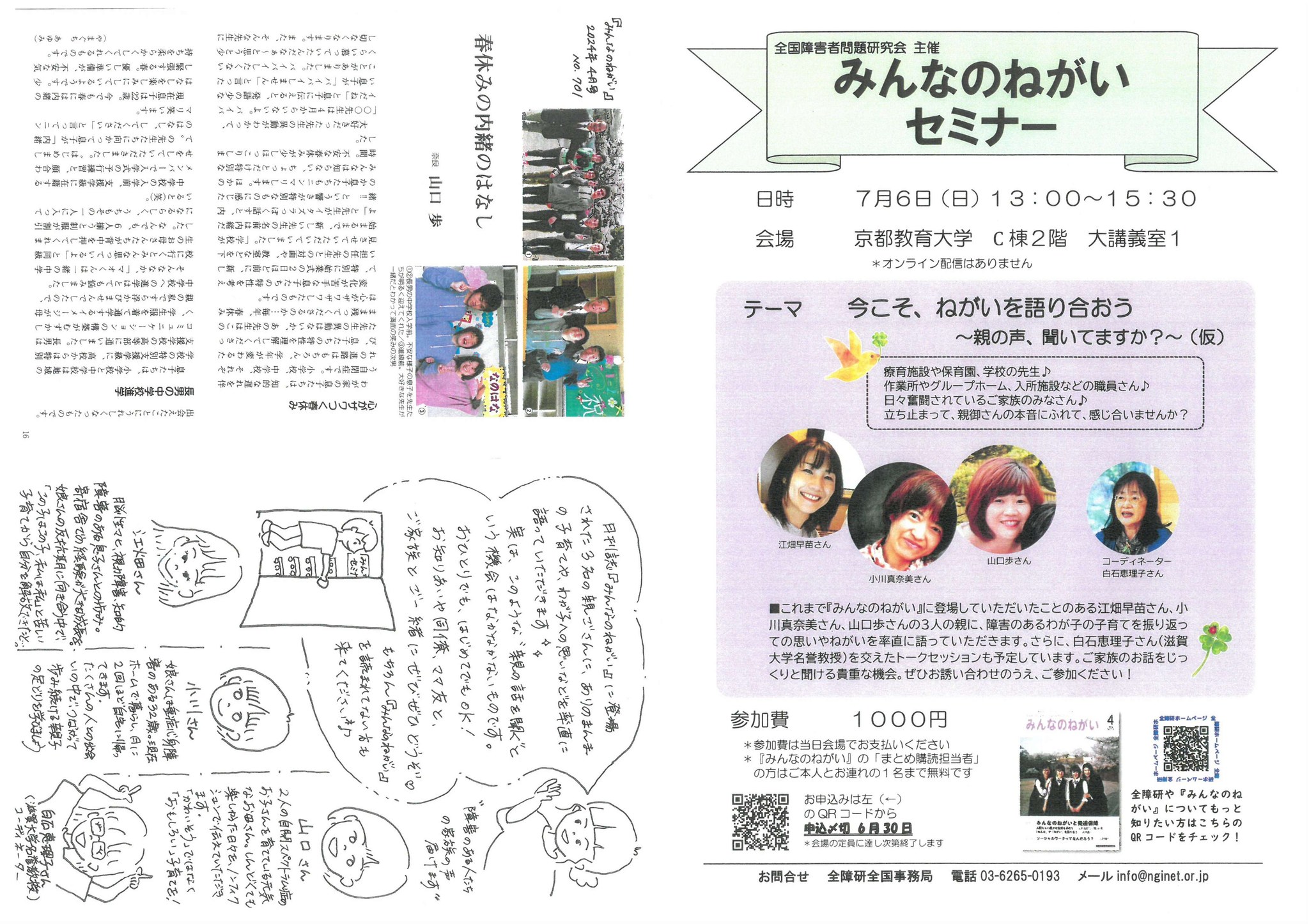
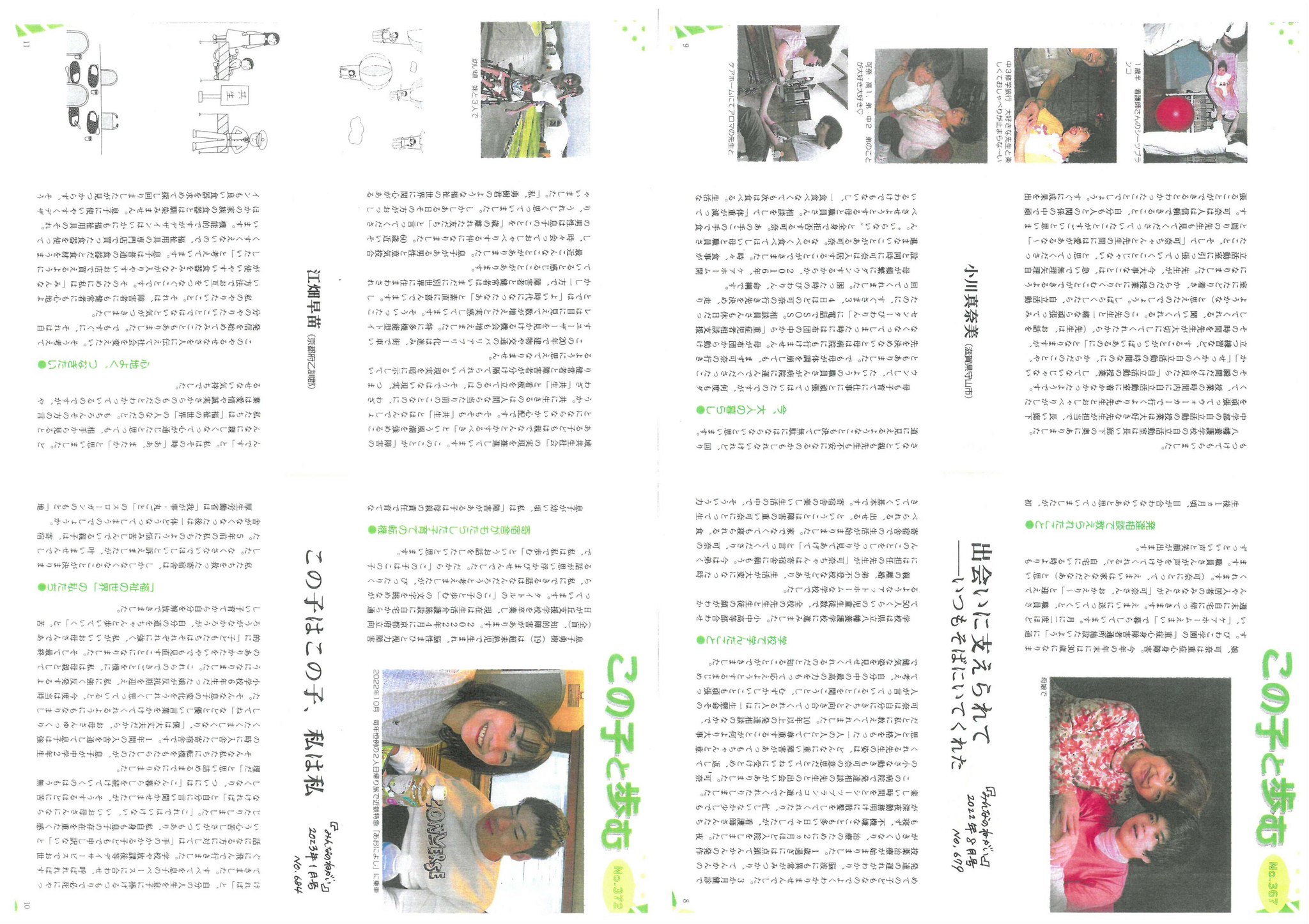
緊急声明
戦争するな! 攻撃するな! 殺すな! 命を守れ!
2025年6月25日
全国障害者問題研究会常任全国委員会
イスラエル軍がイランに軍事攻撃を行いました。
米軍がイランの核施設に軍事攻撃を行いました。
国際法にも違反する軍事攻撃は断じて許されません。
パレスチナのガザ地区では、イスラエル軍によるジェノサイドが続いています。
世界中で続いている戦争はいますぐ終わらせなければなりません。
障害児者の権利保障・発達保障は、生命・生活を脅かす暴力の対極にあります。
平和な社会を築くことは、障害児者の権利保障・発達保障と切り離せません。
そのことを、私たちは何度も確認してきました。
私たちは、繰り返し、繰り返し、訴えます。
忘れてはならないことだから。
諦めてはならないことだから。
戦争するな!
攻撃するな!
殺すな!
命を守れ!
全国障害者問題研究会は、戦後80年、被爆80年の今年、8月に広島で全国大会を開催します。
平和な社会を追求しながら、障害児者の権利保障・発達保障をめざして取り組んでいく決意です。
▶PDFデータです
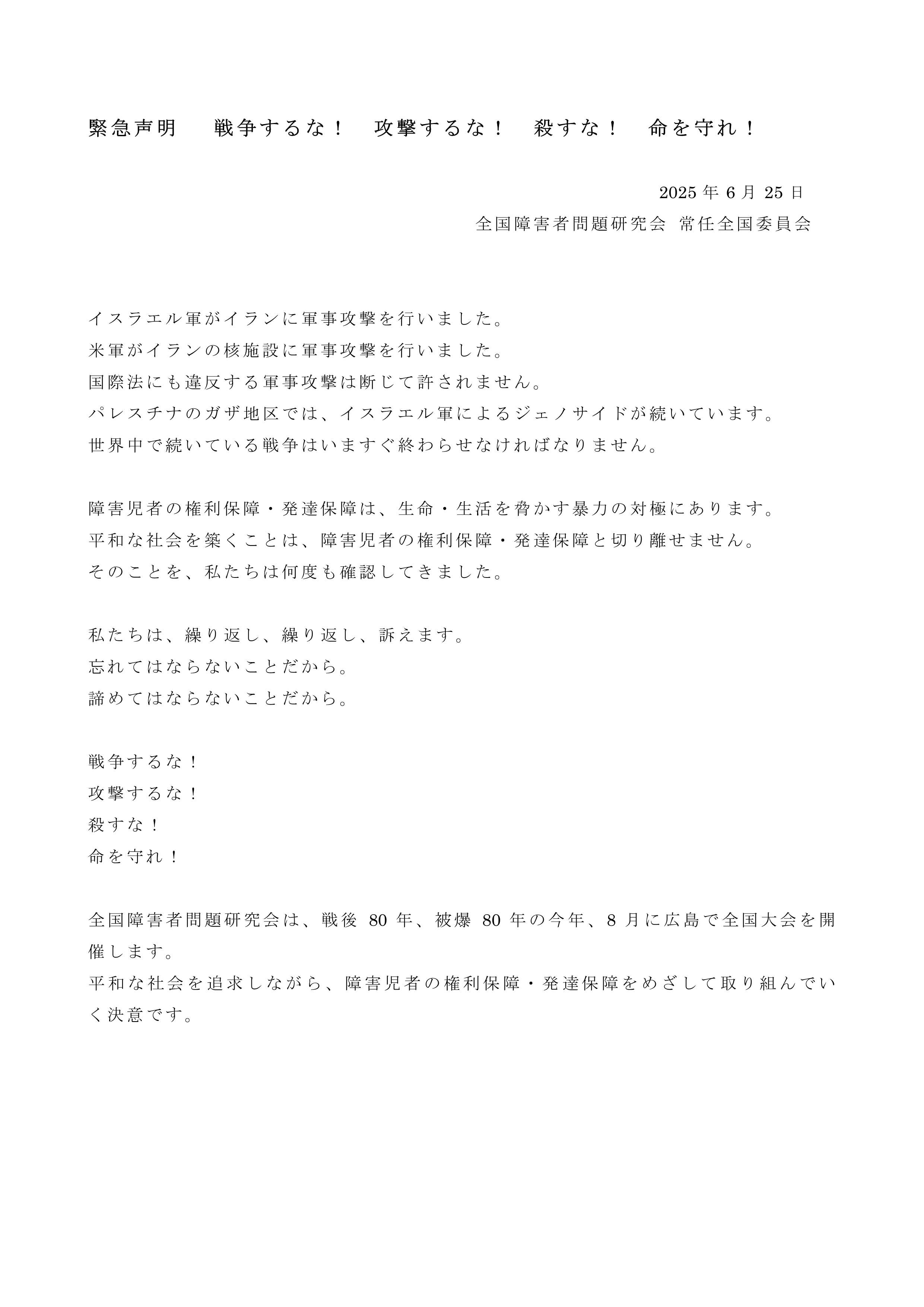
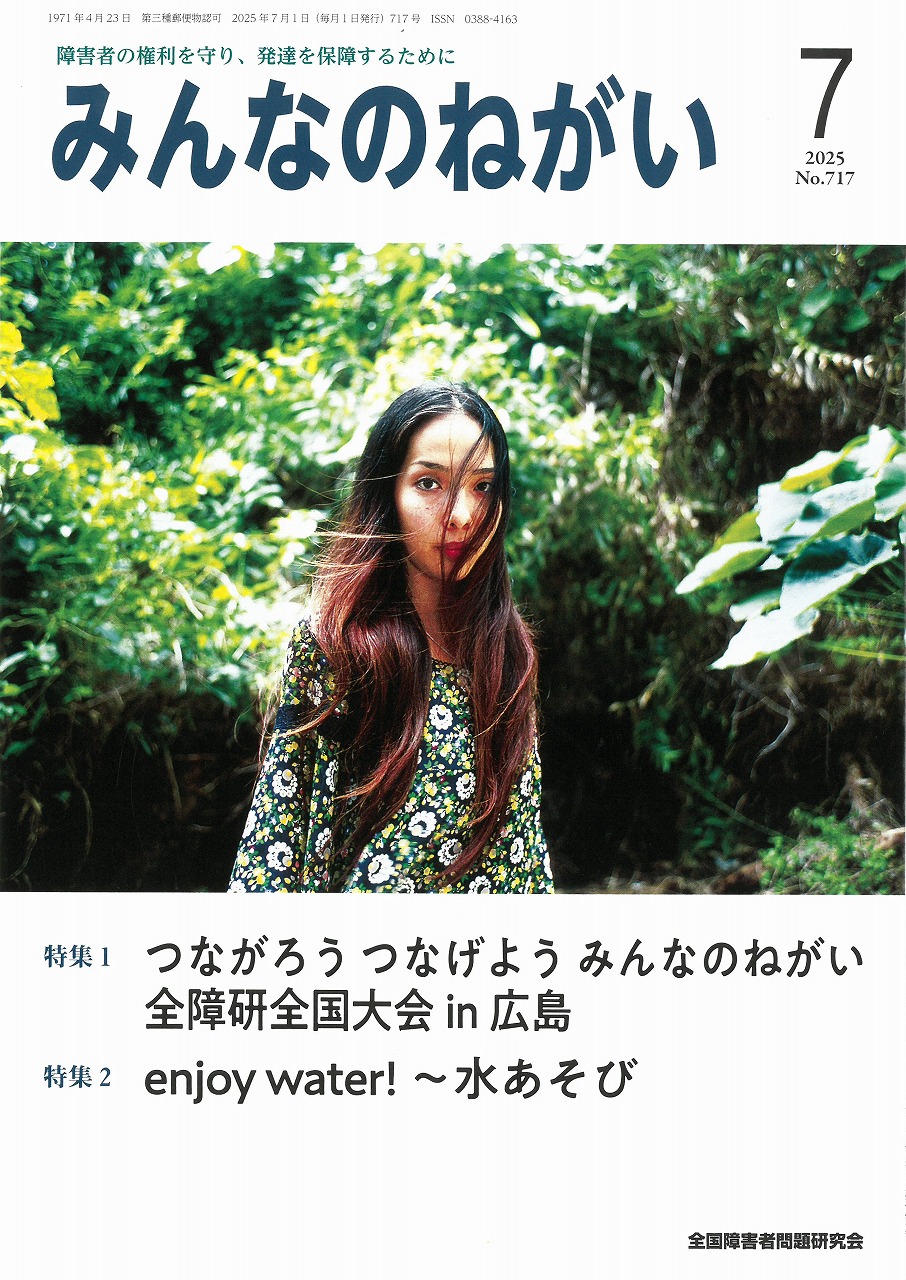
<表紙のことば>
沖縄を撮ろうと本格的に訪れだしたのが2010年。学生時代に旅先で出会った女性たちの目の強さがずっと心に引っかかっていた。
美しい珊瑚の海が広がる絶景の浜で佇む女性に出会った。この先に御嶽(ウタキ)があるらしく、お詣りに来たという。彼女は僕をその御嶽に案内してくれたが、ここから先は気が強いので待っていてとひとり祠の奥へ入っていった。いま思えば、彼女はユタだったのかもしれない。祠から出てきた彼女の車の後部座席に、宿で借りた自転車を無理矢理のっけて、帰り道を一緒にドライブしたことを思い出す。あの時の沖縄の風と彼女の深く澄んだ瞳を忘れない。
あれから15年。今年の夏もまた、愛しき島へ向かう。
土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある
<目次>
特設!「試し読み」のページ7月号(PDF)へ
1 人として 石井奈美(元公立保育園園長)
2 【インタビュー】いま語りたい 心の窓を広げて 松林紗希(映画上映会「みんbio」主催者)
4 教員のはじめの一歩 小畑耕作(全障研和歌山支部)
6 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)
7 あなたに届けたいこの一冊 鷹野祐子(医学系司書)
特集① つながろう つなげよう みんなのねがい 全障研全国大会in広島
10 魅力いっぱい 広島大会
12 学習講座講師からのメッセージ
13 広島大会記念グッズ絶賛発売中!/ぜひ行きんさい! お勧めの場所
14 この子と歩む 盛次千秋(広島・世羅郡)
17 進め! 推し活道 久我明寛(広島)
18 私ときょうだい 川尻亜門
特集② enjoy water! ~水あそび
21 びしょぬれ大作戦 万野友紀
22 ボランティアから友人♡相棒に! 澤佐景子(東京)
23 ステキな夏休みはステキな水場にあり 阿部智子(放課後デイ かたつむり)
24 水泳は、魔法のような力を持っている 宮浦めぐみ(神奈川)
25 プールの魔力とみんなの満面の笑み 番場智恵子(埼玉)
26 子どもにとっての水遊び、プール 大宮ともこ(日本福祉大学)
28 ソーシャルワークってなんだろう? 木全和巳(日本福祉大学)
32 子どものミカタ 岡田徹也(滋賀 特別支援学校)
34 シリーズ 18歳 永田三枝子(東京 清瀬わかば会スマイル青年)
36 暮らしの場は今 宮原茂雄(兵庫 あぜくら福祉会)
38 実践にいかす障害と医療 安藤佳珠子(日本福祉大学)
40 ニュースナビ 2024年度報酬改定の見直しを求める 小野 浩(きょうされん)
42 実践の魅力 山﨑知子(東京)
45 全障研の支部ニュース、紹介します 伊津佳恵(広島乳幼児サークル)
46 みんなのひろば
47 息子と歩く 千葉桜 洋(写真家)
48 BOOK/編集後記
裏表紙 おいしいひととき 九内康夫(広島)
デザイン・イラスト
うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、日本印刷、橋野桃子、山内若菜
▶ご購読希望は出版部オンラインへ
「障害者問題研究」53巻1号 特集=発達相談のしごとと相談援助
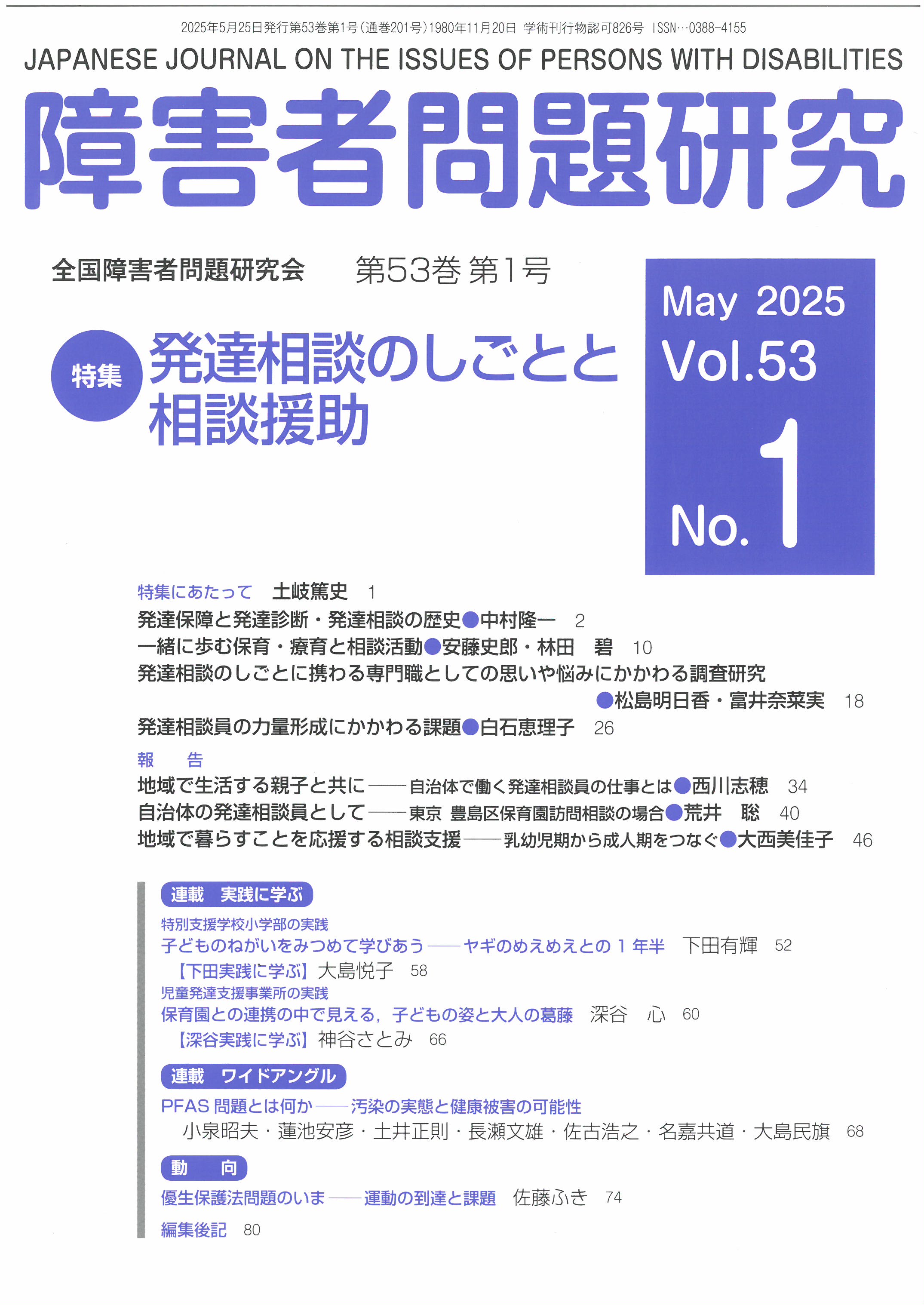
JAPANESE JOURNAL ON THE ISSUES OF PERSONS WITH DISABILTIES
2025年5月25日発行第53巻第1号(通巻201号)
ISBN978-4-88134-236-7 C3036 定価2750円(本体2500円+税)
特集 発達相談のしごとと相談援助
特集にあたって
土岐篤史(発達臨床研究・研修サポートOffice Reborn)
発達保障と発達診断・発達相談の歴史
大津市の場合を例に(覚え書き)
中村隆一(人間発達研究所)
大津市を例に地域の中で発達相談が登場した経過を紹介した.発達相談は,心理相談であるが社会的性格もある.発達を語ることが発達を侵害しかねない矛盾の極点においてそれは登場した.一方,発達相談における発達理解の基礎となる発達診断は近江学園での発達研究の中で生まれた.発達診断の技術や方法は,発達主体の側に立とうとする限り常に対象統一的に吟味される必要があり,継続的な研究は今も欠かせない.
一緒に歩む保育・療育と相談活動
保護者と協力・共同で進める発達保障
発達相談員 安藤史郎・福祉相談員 林田碧(療育・自立センター 寝屋川市立あかつき・ひばり園)
あかつき・ひばり園では,1973年の開園より保護者との協力・共同を理念とし,保護者と職員が互いに意見を交換し同じ思いに立ち,ともに療育目標を練り上げ,子どもの発達を保障することをめざしてきた.本稿では,その児童発達支援センターにおける発達相談と福祉相談の活動と役割の形成を述べた.保護者のもつ価値観や置かれた生活背景に目を向け,ことばにならない悩みやねがいをつかみ,子どもにとっての生活や発達をともに考えていくことが相談活動に欠かせない.事例検討により,保護者と時間をかけて関係をつくり保護者・職員集団でともに子ども理解を深めていくことが,子どもと保護者の支援にも相談活動の力量形成にもつながることを示した.
発達相談のしごとに携わる専門職としての思いや悩みにかかわる調査研究
発達相談員を対象としたアンケート調査から
松島明日香(滋賀大学)・富井奈菜実(奈良教育大学)
本研究は発達相談のしごとに携わる79人を対象に,発達相談員が発達診断や発達相談を進めるうえで何を大切にし,どのような思いや悩みを抱えているのかに関する意識調査を実施した.調査の結果,仕事上の困難さややりがい,発達相談で大切にしていることなどについてのリアルな実態が明らかになったとともに,“大切にしたいことがあるからこそ悩む”という発達相談員の願いと,その願いが実現されにくい現状や課題があるということがみえてきた.
発達相談員の力量形成にかかわる課題
白石恵理子(滋賀大学名誉教授)
発達相談とは,子どもや障害のある人の発達理解をもとに,保護者や支援者が育児,保育,教育等の実践を主体的に行っていくために話しあうプロセスであるが,それを担う発達相談員に求められる力量とはいかなるものであろうか.心理テストの結果が過大視されるような発達観,子どもや家族が置かれている生活現実を捨象して発達や心理をとらえようとする心理主義も強まるなか,発達相談員の力量形成について,子ども理解に求められる
3 つの視角(全体性,歴史性,社会性)をふまえ,他の専門職との対等な連携・協働,実地経験との往還等について述べた.
地域で生活する親子と共に
自治体で働く発達相談員の仕事とは
西川志穂(滋賀県・大津市役所)
自治体の発達相談員として
東京 豊島区保育園訪問相談の場合
荒井 聡(東京都豊島区立東部子ども家庭支援センター)
地域で暮らすことを応援する相談支援
乳幼児期から成人期をつなぐ
大西美佳子(大阪府・さつき福祉会 くらしの支援センターみんなのき)
連載 実践に学ぶ
特別支援学校小学部の実践
子どものねがいをみつめて学びあう
ヤギのめえめえとの1年半
下田有輝(長野県・公立特別支援学校)
【下田実践に学ぶ】
子どもをつつむ共感の世界
元 障害児学級教員・大島悦子
児童発達支援事業所の実践
保育園との連携の中で見える,子どもの姿と大人の葛藤
深谷 心(奈良県・SORATO(UMIE)てんり)
【深谷実践に学ぶ】
共に悩み共に歩む療育と保育の連携
子どもの内面に寄り添う実践
「ゼノ」こばと園・神谷さとみ
連載/ワイドアングル
PFAS問題とは何か
汚染の実態と健康被害の可能性
全日本民医連PFAS問題委員会
小泉昭夫・蓮池安彦・土井正則・長瀬文雄・佐古浩之・名嘉共道・大島民旗
動向
優生保護法問題のいま
運動の到達と課題
佐藤ふき(きょうされん全国事務局、優生保護法問題の全面解決をめざす全国連絡会事務局)
▶ご注文は 全障研出版部オンラインショップへ
●ご案内チラシ(PDF)
▶ 「読む会」情報
日時 7月18日(金)19:00~21:00/オンライン開催
話題提供 地域で生活する親子とともに ~自治体で働く発達相談員の仕事とは/西川志穂さん(大津市)
参加者による意見交換
○参加申込はここから
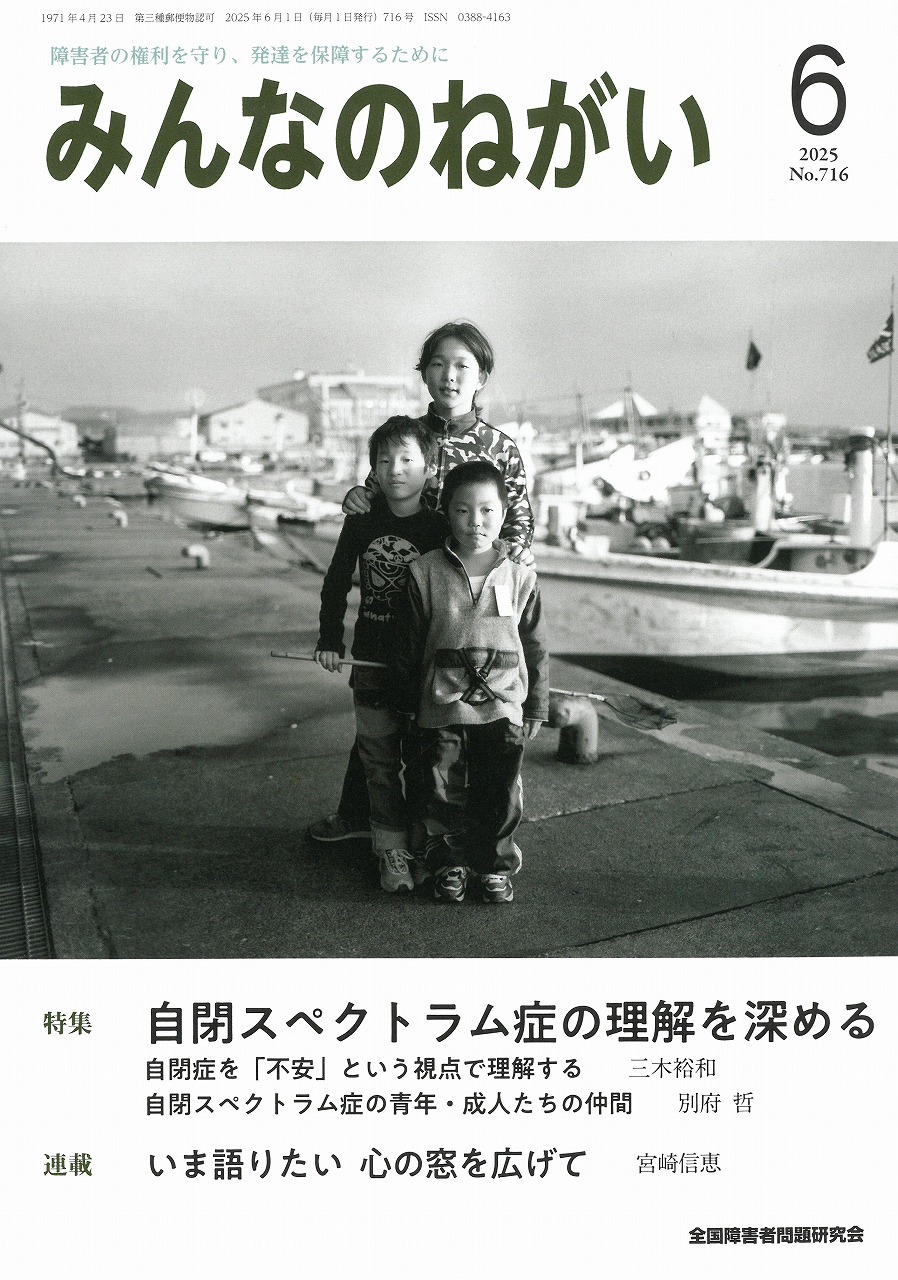
<表紙のことば>
田辺漁港で遊んでいた地元の子供達。カメラを向けると、はにかみながら仲良く並んだ。港の美しい午後の光と、三人の関係性や性格が伺える表情。シャッターを切った瞬間にグッと手応えを感じた。この写真を撮ったのが二十数年前。和歌山を撮り続けた、僕にとっての処女作である「和らぎの道で」のキービジュアルとなった。
代表作と自分が思えたものは、誰から見ても強く印象に残ると信じている。そういう写真が撮れたときの喜びは半端ないし、それがあるから写真家を続けていける。ミラクルは起こるものだと思うけど、ただそれには数も必要で、それって努力である。そしてその瞬間を「きた」と感じ取れるのが地力なんだと思う。
土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある
<目次>
特設!「試し読み」のページ6月号(PDF)へ
1 人として 尾崎 望(小児科医)
2 【インタビュー】いま語りたい 心の窓を広げて 宮崎信恵(映画監督)
4 教員のはじめの一歩 小畑耕作(全障研和歌山支部)
6 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)
7 あなたに届けたいこの一冊 吉田真知子 (元教員)
8 この子と歩む 冨田博子 (広島県福山市)
11 進め! 推し活道 藍 涼之介 (東京)
特集 自閉スペクトラム症の理解を深める
13 親としての私のねがい 戸田紀子 (埼玉 みぬま福祉会)
14 社会の主体者として人生を豊かに切り拓く人に 黒川陽司 (神戸大学附属特別支援学校)
16 自閉スペクトラム症の職員と職場の関係 元障害者施設管理者
18 自閉スペクトラム症の青年・成人たちの仲間 別府 哲(岐阜大学)
20 さらに学びを深めるために 全障研出版部書籍紹介
21 自閉症を「不安」という視点で理解する 三木裕和(立命館大学)
24 私ときょうだい 小室 径 (東京)
26 子どものミカタ 岡田徹也 (滋賀 特別支援学校)
28 ソーシャルワークってなんだろう? 木全和巳(日本福祉大学)
32 シリーズ 18歳 下川和洋 (NPOケアさぽーと研究所)
34 暮らしの場は今 村瀬智弘 (千葉 八千代翼友福祉会)
36 実践にいかす障害と医療 安藤佳珠子(日本福祉大学)
38 ニュースナビ 聴覚障害女児逸失利益裁判 久保陽奈 (弁護士)
40 実践の魅力 保木あかね (滋賀県立聾話学校)
43 全障研の支部ニュース、紹介します 柴田ますみ (岐阜支部)
44 みんなのひろば
45 【トピック】親子みらいワーク 報告集の紹介 清時忠吉 (大阪 いずみ野福祉会)
46 息子と歩く 千葉桜 洋(写真家)
47 BOOK/編集後記
裏表紙 おいしいひととき 吉田史枝 (大阪 さつき福祉会)
デザイン・イラスト
うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、日本印刷、橋野桃子、へむかか、山内若菜
▶ご購読希望は出版部オンラインへ
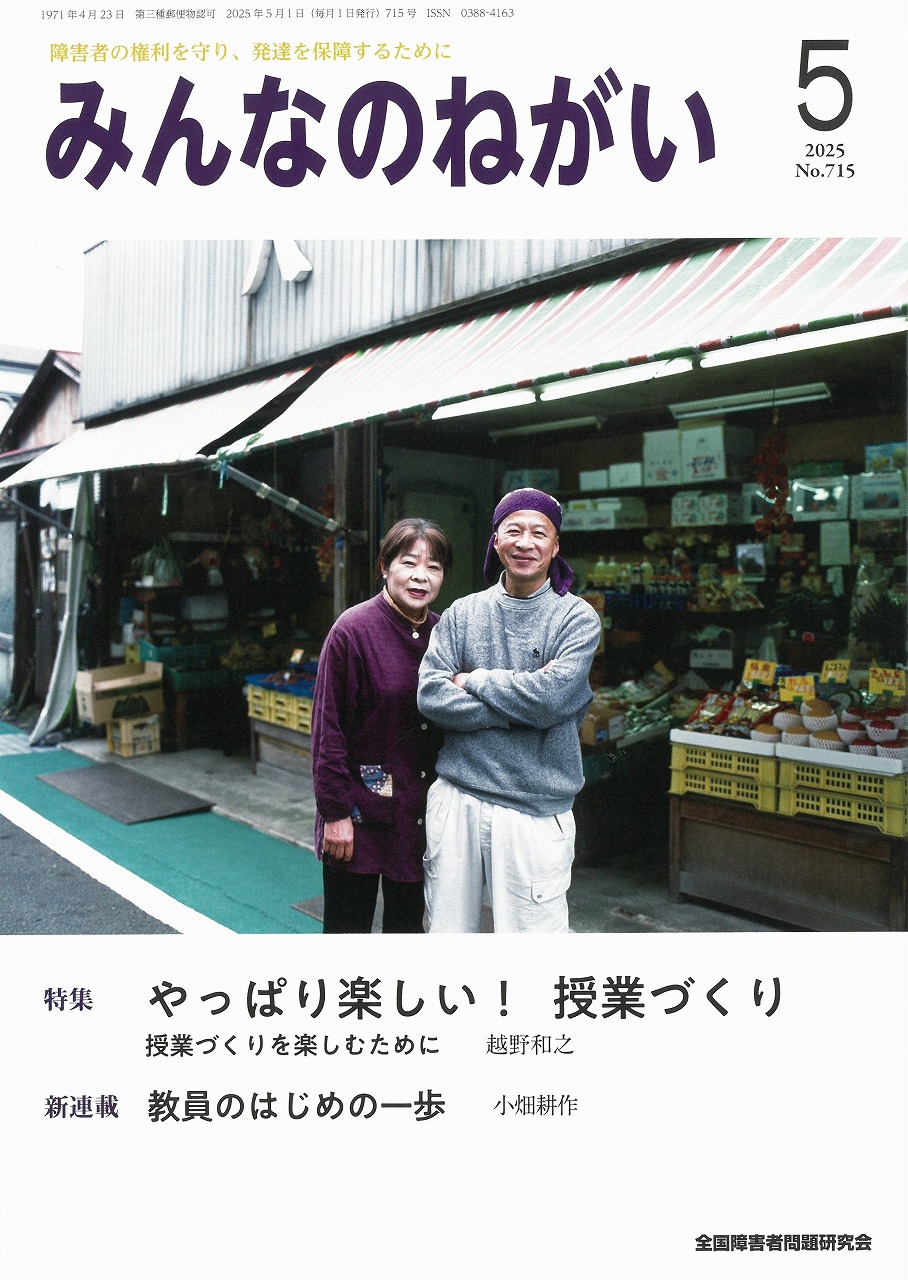
<表紙のことば>
北関東のとある町の裏路地に佇む、昔ながらの青果店を営むご夫婦。さりげない紫色のペアルックから仲の良さが伝わってくる。もう何十年も二人三脚で支え合いながらこの店を切り盛りしてきたのだろう。そっと寄り添う姿に関係性やこれまでの歴史が垣間見える。
僕は小さい頃から八百屋さんが好きだった。絵本の中で見た、色とりどりの野菜や果物がとても綺麗で美味しそうで。それを手にするお客さんも嬉しそうだった。もし違う人生があるなら、八百屋か漁師だな。自然の恩恵を生業に出来るって、なんか凄い。そしてそれを生涯のパートナーと共にできるなんて最高に幸せだなあ。この歳になって勝手にそんなことをふと想い耽ってしまう。
土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある
<目次>
特設!「試し読み」のページ5月号(PDF)へ
1 人として 稲塚秀孝(映像プロデューサー・映画監督)
2 【インタビュー】いま語りたい 心の窓を広げて 宮崎信恵(映画監督)
4 教員のはじめの一歩 小畑耕作(全障研和歌山支部)
6 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)
7 あなたに届けたいこの一冊 安達敬子(大学非常勤講師)
8 この子と歩む 三原瑞穂(東京都江東区)
11 進め! 推し活道 佐々木裕都(京都)
特集 やっぱり楽しい!授業づくり
14 訪問学級担任としての授業づくりの根っこ 松元 巌(東京・特別支援学校)
16 古典をみんなで学ぶ 久野碧衣(東京・中学校特別支援学級)
18 授業を通して、子どもたちが手を伸ばしたくなる
文化との出会いをつくる 長友志航(滋賀・養護学校)
20 教育実践の醍醐味を考える 山中冴子(埼玉大学)
22 授業づくりを楽しむために 越野和之(奈良教育大学)
25 息子と歩く 千葉桜 洋(写真家)
26 私ときょうだい 春田幸翼(東京)
28 子どものミカタ 安藤史郎(あかつき・ひばり園)
30 ソーシャルワークってなんだろう? 木全和巳(日本福祉大学)
34 シリーズ 18歳 佐久間 徹(宮城・福祉型専攻科きおっちょら)
36 暮らしの場は今 伊藤成康(大阪・さつき福祉会)
38 実践にいかす障害と医療 安藤佳珠子(日本福祉大学)
40 ニュースナビ 障害者の暮らしの場実態調査 周 英煥(NHK報道局社会部)
42 実践の魅力 池田 翼(奈良教育大学付属小学校特別支援学級)
45 全障研の支部ニュース、紹介します 伊藤光子・村瀬智弘(千葉支部)
46 みんなのひろば
48 BOOK/編集後記
裏表紙 おいしいひととき 飯島裕美(埼玉 HIBIKICAFF)
デザイン・イラスト
うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、日本印刷、橋野桃子、へむかか、山内若菜
▶ご購読希望は出版部オンラインへ
全国委員のみなさま、各⽀部事務局のみなさまへ
職場に地域に「みんなのねがい」と発達保障の風を
―2025年度を迎えるにあたり特別のお願い―
全障研出版部経営委員⻑ 越野和之
全障研出版部経営委員会(以下経営委員会)では2021年の夏に全国委員会ならびに全国総会で の審議を経て中期経営計画を策定し、その実現に向けて努⼒を重ねてきました。その甲斐もあって、⻑いコロナ禍の下でも、なんとか出版部の経営を維持し、⽉刊誌『みんなのねがい』、研究誌
『障害者問題研究』や各種の書籍の刊⾏を続けてくることができました。両誌や書籍の普及を通 して発達保障の理念と実践を広めるとともに、出版部の経営を⽀えていただいている各⽀部の全国委員や⽀部事務局のみなさんのお⼒に改めて感謝申し上げます。
経営委員会は現在、本年夏の全国委員会ならびに全国総会に提案すべく、新たな中期経営計画の策定に向けて討議を重ねています。それに先⽴ち、新年度を迎えるにあたって、当⾯各⽀部でさらに取り組みを進めていただきたい点について特別のお願いを差し上げます。ぜひ⼀層のお⼒
をお貸しいただきたく、ご協⼒を⼼よりお願いいたします。
1.特別支援学校に『みんなのねがい』の風を吹かせよう
まとめ読者の実態を調べたところ、各地の特別⽀援学校に『みんなのねがい』が⼀冊も届いていない学校が、思った以上に多数ある可能性が明らかになりました。学校では荷物を受け取れな
い、校内では配れないなどの困難もありますが、『みんなのねがい』の読者が⼀⼈もいない学校ばかりになっては困ります。ぜひ各⽀部で、『みんなのねがい』の⾵を特別⽀援学校に吹かせるとりくみを進めましょう。各校の読者の状況を把握し(全国事務局にお尋ね下さい)、それぞれの学校の先⽣⽅の名前をあげて、働きかけの計画を⽴てましょう。
特別⽀援学校ばかりではなく、⽀部事務局メンバーのつながりを⽣かして、作業所にもグループホームにも、あるいは放課後デイサービスや児童発達⽀援事業所にも、『みんなのねがい』の⾵
を吹かせましょう。
2.『障害者問題研究』の定期購読を広げよう
『障害者問題研究』は他に類を⾒ない発達保障と障害者問題の総合的な研究誌です。難しそうで⼿が出ないと思われるかもしれませんが、毎号必ずオンラインでの読む会を開催しています。
特集を⾒て興味があったら購読するという読者も⼤切ですが、⽀部の役員、事務局員のみなさんには、ぜひ定期購読をお願いしたいと思います。そしてその輪をもう⼀回り広げてください。読む会にも誘い合ってぜひご参加ください。
3.各地の学習会に全障研出版部の本の販売コーナーを
全障研出版部の単⾏本は障害のある⼈たちの権利保障の課題と、その羅針盤となる発達保障を学ぶための宝庫です。でも残念ながら⼀般の書店ではなかなか⽬に触れることがありません。各⽀部主催の学習会や、つながりのある⼈たちの研究会などにぜひ書籍販売コーナーを設けて、参加者に「全障研の本」を⼿にとる機会を作ってください。⽀部事務局のみなさんのお勧め本を仲
間の⼿にも!
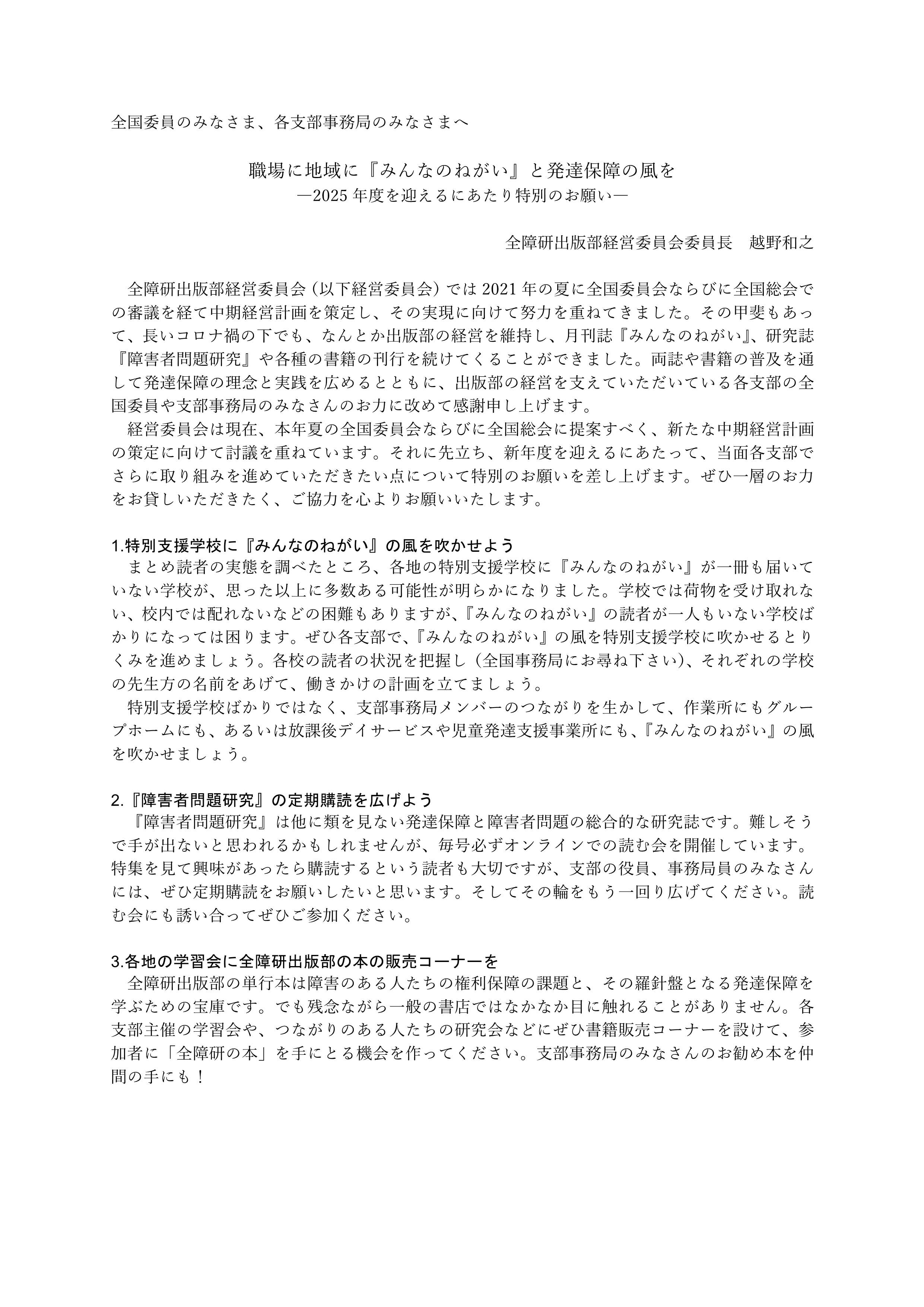
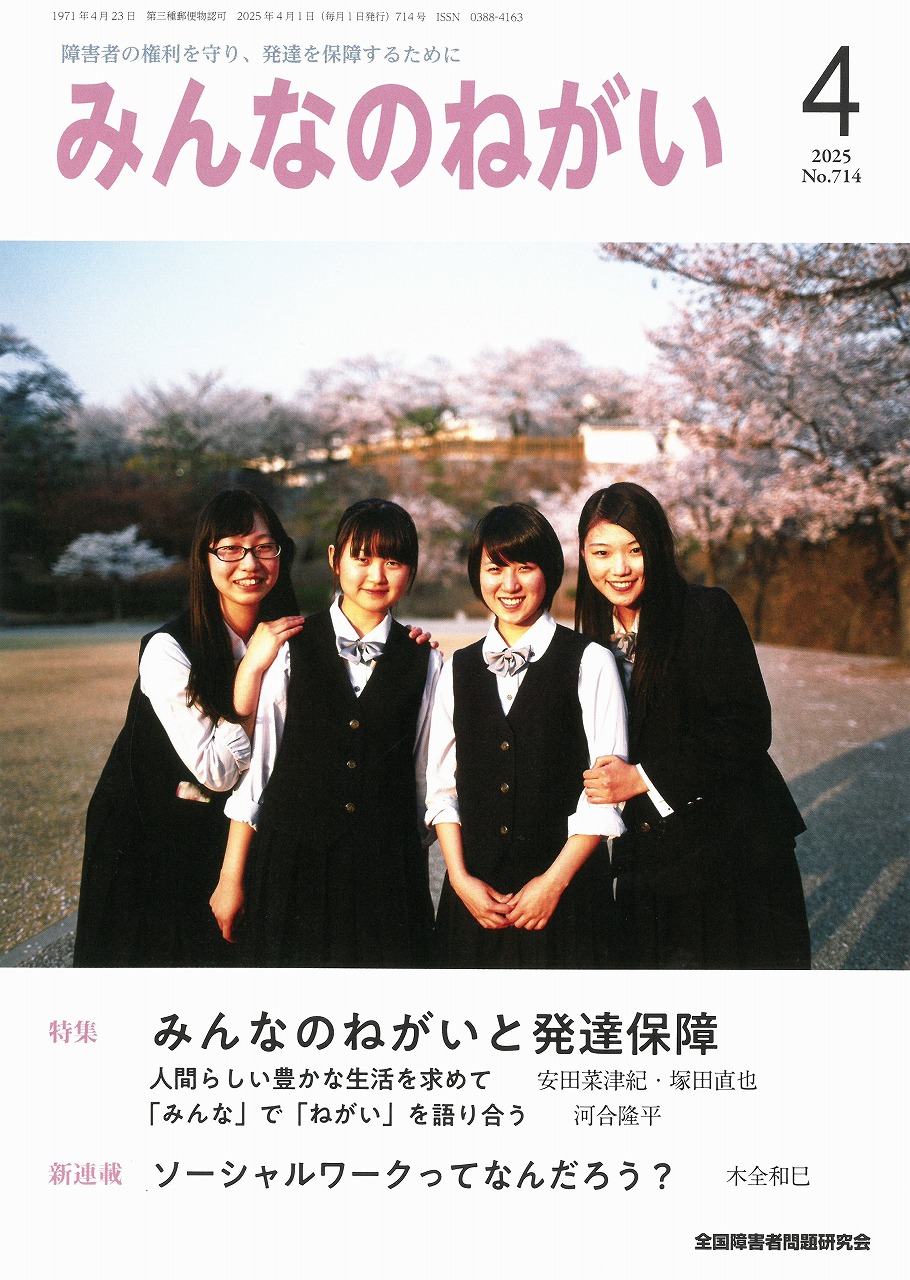
<表紙のことば>
城跡に咲く桜の木々を夕陽が照らす。
花びらの淡いピンクにオレンジの光が混じって、なんとも柔らかな雰囲気に包まれている。
仲良し4人組は、高校卒業の思い出作りでお花見に来たそうだ。しかもメンバーの誕生日祝いも兼ねて。なんだか出てくるもの見えるもの全てが眩しい。青春の瞬間に立ち会えて、写真に残せてよかった。
彼女達はこれからそれぞれの道を進んでゆくけど、きっとこの時間を忘れないだろう。
鮮やかに咲き誇る満開の桜も素晴らしいが、はらはらと花びらが散ってゆくころが好きだ。
春の別れは切なくて、美しい。
土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある
<目次>
特設!「試し読み」のページ4月号(PDF)へ
1 人として 福場将太(激辛カレー好きの精神科医)
2 【インタビュー】いま語りたい 心の窓を広げて 宮崎信恵(映画監督)
4 教員のはじめの一歩 小畑耕作(全障研和歌山支部)
6 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)
7 あなたに届けたいこの一冊 菊地澄子(児童文学作家)
8 この子と歩む 南田惠子(千葉市)
11 進め! 推し活道 稲垣大空(大阪)
特集 みんなのねがいと発達保障
12 人間らしい豊かな生活を求めて 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)・塚田直也(編集長)
16 発達保障は北極星、全障研は北斗七星 池田 光(広島)
17 職場における発達保障的課題 瀧澤颯大(札幌こころの診療所)
18 人の優しさにふれ続け 上西範洋(奈良)
19 ちいさな朝市の実践 近藤未希子(京都)
20 自己実現をめざして 小渕隆司(北海道)
21 「みんな」で「ねがい」を語り合う 河合隆平(東京都立大学)
24 私ときょうだい 関根果那(茨城)
26 子どものミカタ 安藤史郎(あかつき・ひばり園)
28 シリーズ 18歳 清時忠吉(いずみ野福祉会)
30 ソーシャルワークってなんだろう? 木全和巳(日本福祉大学)
34 暮らしの場は今 九内康夫(全国障害児者の暮らしの場を考える会)
36 実践にいかす障害と医療 安藤佳珠子(日本福祉大学)
38 ニュースナビ マイナ保険証問題 家平 悟(障全協)
40 実践の魅力 井原あどか(ゆうやけ子どもクラブ)
43 全障研の支部ニュース、紹介します 豊田悦子(兵庫支部)
44 みんなのひろば
46 息子と歩く 千葉桜 洋(写真家)
48 BOOK/編集後記
裏表紙 おいしいひととき 植山有希(京都)
デザイン・イラスト
うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、日本印刷、橋野桃子、山内若菜
▶ご購読希望は出版部オンラインへ
「障害者問題研究」52巻4号 特集=障害のある人のケアする権利
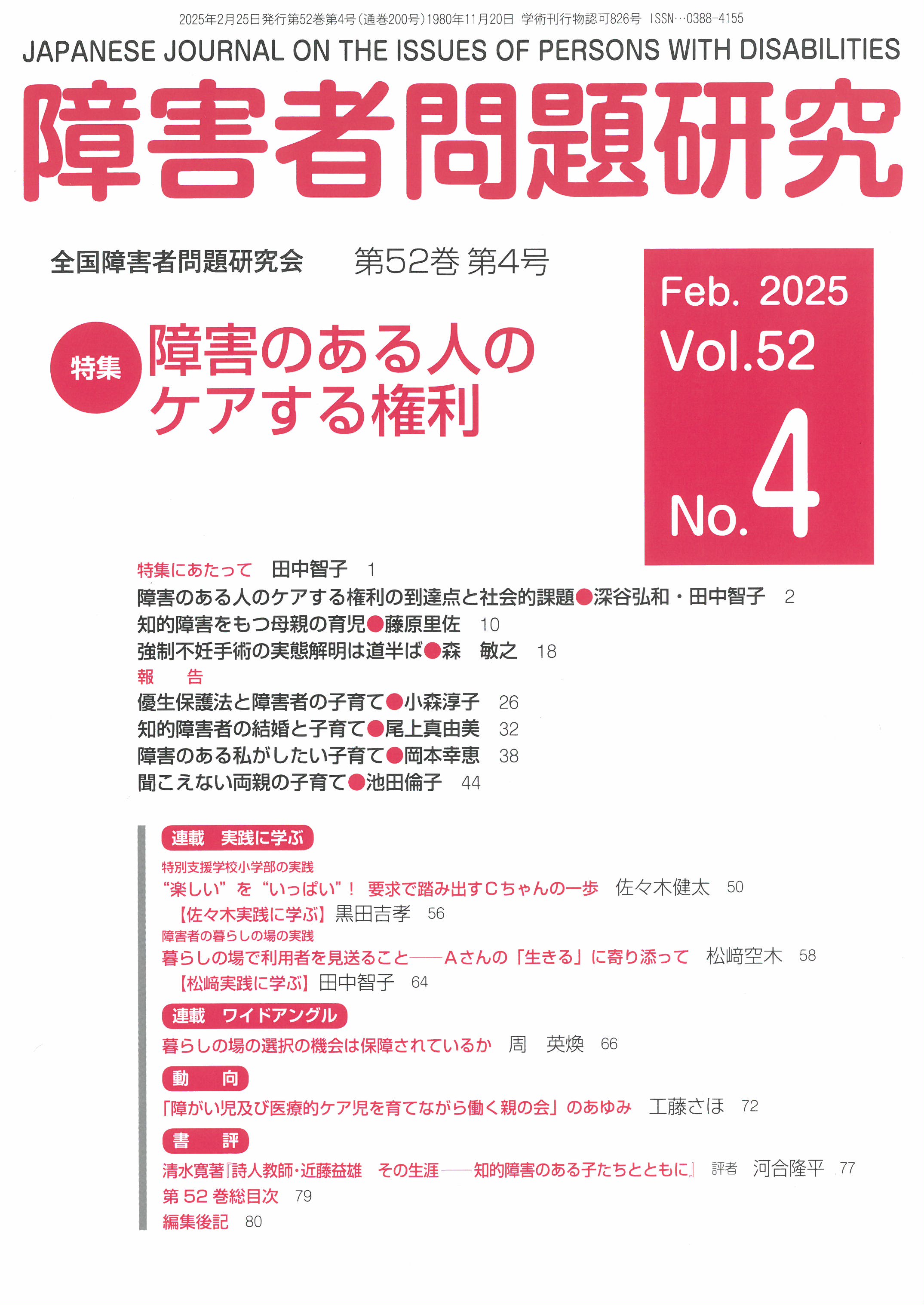
JAPANESE JOURNAL ON THE ISSUES OF PERSONS WITH DISABILTIES
ISBN-984-4-88134-226-8 C3036 定価2750円(本体2500円+税)
特集 障害のある人のケアする権利
特集にあたって
/田中智子(佛教大学)
障害のある人のケアする権利の到達点と社会的課題
/深谷弘和(天理大学人文学部社会福祉学科)・田中智子(佛教大学社会福祉学部)
障害のある人のケアする権利については,いまだに差別や権利侵害が存在しており,そこには障害のある人とケアをめぐる交差的な問いがある.エヴァ・キテイは,これまでの政治哲学における平等概念では,私たちが誰かに依存しなければ生きていない存在であることが無視されてきたと批判し,「つながりに基づく平等」を主張する.障害のある人がケアされながら,「ケアする存在」として位置づいた制度の整備が求められる.
知的障害をもつ母親の育児
母子生活支援施設における養育支援を視野に
/藤原里佐(北星学園大学短期大学部)
子どもの養育者である親に知的障害があり,生活,子育て全般に支援が必要な場合,誰がどのように,その家庭に関わることができるのだろうか.障害者のグループホームに入所しての共同生活や,親族の援助に拠る暮らしを選択する例が散見される.知的障害者のライフステージに,結婚や妊娠,出産,育児というライフイベントがあることをあたりまえのこととし,必要な支援を拡充していく段階にあると思われる.本稿では,母子生活支援施設の調査を通して,障害のある母親がケアを受けながら育児を担い,母子が分離されずに生活する可能性を検討する.児童福祉施設である母子生活支援施設は,様々なニーズをもつ養育者をケアし,子育てを支援してきた実績がある.施設に入所し,生活が安定する中で,母親の障害が顕在化することも想定される.障害をもつ母親が育児支援を得ることは,子どもの福祉の向上にもつながると考える.
強制不妊手術の実態解明は道半ば
/森 敏之(京都新聞記者)
優生保護法下で少なくとも約 2 万 5 千人に行われた強制不妊手術の実態解明は道半ばである.理由は三つある.第一に,被害者や家族,手術に関与した医療者や福祉施設職員ら当事者の多くが沈黙していること.第二に,病状や生活状況,手術理由が記載された当時の一次資料の大半を都道府県が既に廃棄したこと.第三に,現存するわずかな一次資料について,報道機関や研究者が情報公開請求しても,都道府県が「プライバシー保護」を名目に伏せる必要のない情報まで「黒塗り」で伏せていることが挙げられる.本稿では,最高裁判所が
2024 年 7 月,国に対し,被害者への賠償を命じた強制不妊手術問題の概要を振り返った後,被害者の証言を通して人権侵害の実態の一端を明らかにする.その上で,京都新聞社が滋賀県に情報公開を求めた裁判で「
8 割開示」を命じた一審と二審の判決を踏まえ,都道府県の恣意的な不開示判断が第三者による検証を阻んでいる現状を指摘する.
優生保護法と障害者の子育て
当事者の語り合う会の取り組み
/小森淳子(岐阜協立大学非常勤講師)
知的障害者の結婚と子育て
子どもは未来につなげてくれる
/尾上真由美(京都府・社会福祉法人よさのうみ福祉会)
障害のある私がしたい子育て
/岡本幸恵(京都府在住)
聞こえない両親の子育て
/池田倫子(佛教大学 研究員)
連載 実践に学ぶ
特別支援学校小学部の実践
“楽しい”を“いっぱい”!要求で踏み出すCちゃんの一歩
/佐々木 健太(滋賀県・野洲養護学校)
【佐々木実践に学ぶ】
子どもの心に寄りそい,子どもと共につくる実践
/黒田吉孝(滋賀大学教育学部 元教員)
障害者の暮らしの場の実践
暮らしの場で利用者を見送ること──Aさんの「生きる」に寄り添って
/松﨑空木(埼玉県・みぬま福祉会 太陽の里)
【松﨑実践に学ぶ】
当たり前に生きる・死ぬ権利,それを支える社会的支援
/田中智子(佛教大学)
連載/ワイドアングル
暮らしの場の選択の機会は保障されているか 実態調査から考える
/周 英煥(NHK報道局社会部)
動向
「障がい児及び医療的ケア児を育てながら働く親の会」のあゆみ
/工藤さほ(同会会長)
書評 清水寛著『詩人教師・近藤益雄 その生涯──知的障害のある子たちとともに』
評者 河合隆平(東京都立大学)
第52巻総目次
▶ご注文は 全障研出版部オンラインショップへ
▶ 「読む会」情報 詳細案内はこちら(PDF)
日時=4月28日(月)19時~21時/zoom
【話題提供】
障害のある人のケアする権利の到達点と社会的課題 深谷弘和さん
障害のある私がしたい子育て 岡本幸恵さん
聞こえない両親の子育て 池田倫子さん
【参加者の意見交流】
▼参加申込は
https://form.run/@shoumonken52-4
「障害者問題研究」52巻3号 特集=障害のある人の人権と社会保障裁判
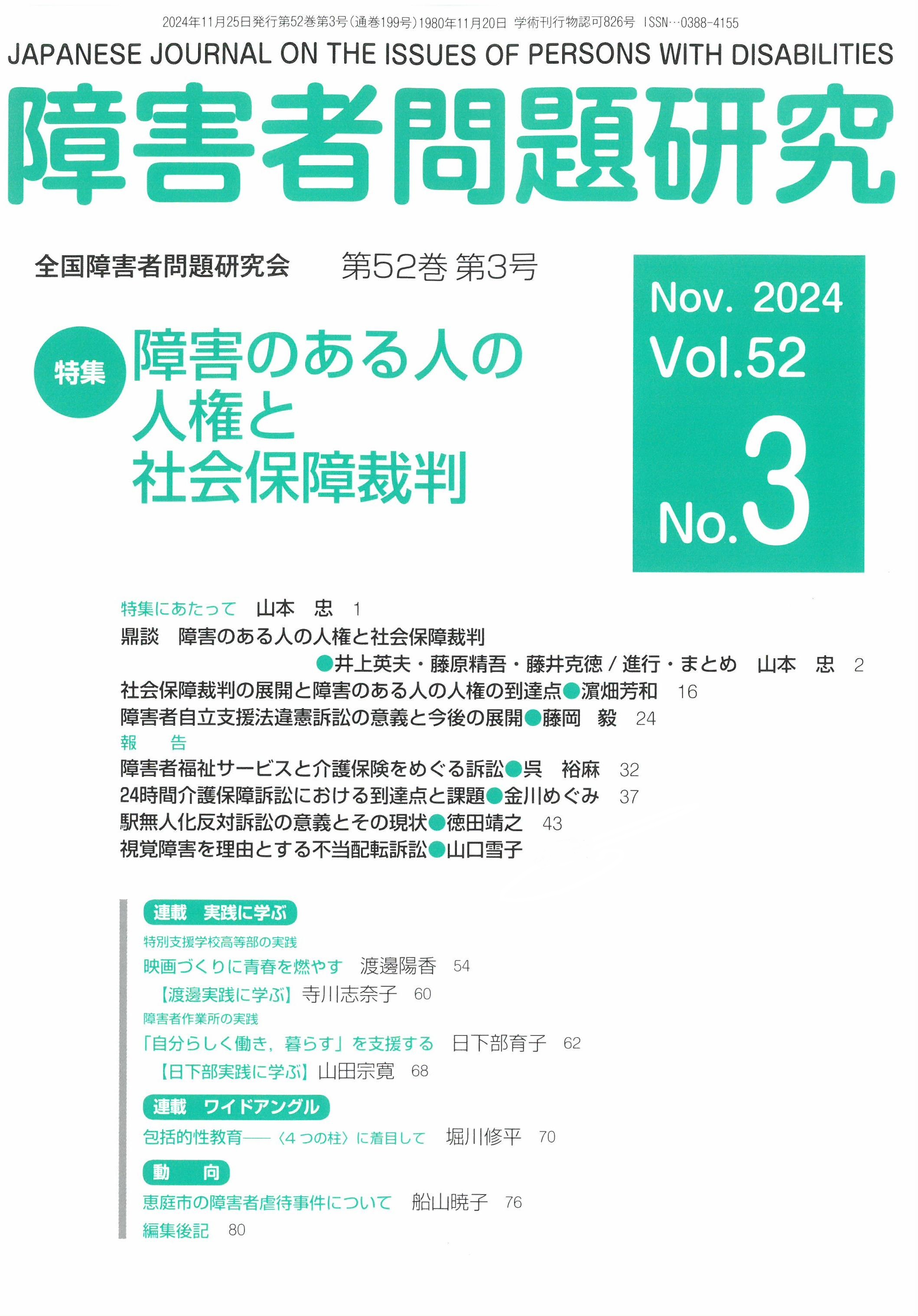
JAPANESE JOURNAL ON THE ISSUES OF PERSONS WITH DISABILTIES
ISBN-984-4-88134-207-7 C3036 定価2750円(本体2500円+税)
特集 障害のある人の人権と社会保障裁判
特集にあたって
山本 忠 立命館大学法学部教授
鼎談 障害のある人の人権と社会保障裁判
井上英夫、藤原精吾、藤井克徳
進行・まとめ 本誌編集委員 山本 忠
井上英夫 1947 年生.金沢大学名誉教授.日本高齢期運動サポートセンター理事長.日本社会保障法学会代表理事,厚労省ハンセン病問題検討会委員長,最高裁特別法廷問題有識者委員会座長などを歴任.
藤原精吾 1941 年生.1967 年弁護士登録.堀木訴訟,原爆症認定集団訴訟,優生保護法訴訟,障害年金裁判などを担当.日本弁護士連合会副会長,同人権擁護委員長などを歴任
藤井克徳 1949 年生.1982 年都立小平養護学校教諭退職.あさやけ作業所や共同作業所全国連絡会(現・きょうされん)結成に参加.日本障害者協議会代表,きょうされん専務理事などを歴任.
社会保障裁判の展開と障害のある人の人権の到達点
濵畑芳和 立正大学社会福祉学部
障害のある人が提起した社会保障裁判とその展開について,1960 年代から現代にかけて権利確立期,権利転換(反動)期,権利発展期に区分して,代表的な訴訟をとりあげ紹介し検討した.障害のある人が自身の権利侵害に対して,訴訟を提起することにより自身の権利救済を求めるとともに,社会に対して障害のある人の人権問題を問うてきた.社会保障裁判は,障害のある人のみならず,支援者,運動団体や弁護士,研究者も加わって社会運動を形成し,これらの人々の不断の努力によって,差別的な人権侵害への救済を図りつつ,国際的な人権保障の水準に近づける社会改革を促しながら,障害のある人の人権の獲得と進歩に寄与してきた.
障害者自立支援法違憲訴訟の意義と今後の展開
藤岡 毅 弁護士,障害者自立支援法違憲訴訟全国弁護団事務局長
障害者自立支援法違憲訴訟は,「応益負担」を導入した障害者自立支援法は障害者の尊厳を傷付け,平等権,生存権等を定めた憲法に反し,違憲・違法であるとして,国及び自治体を被告として全国
14 地裁で行われた訴訟である.基本合意文書が締結され,その後の制度改革に影響を及ぼした.また,基本合意を履行しているかを検証する定期協議が
14 年間で14回実施されている.
報告
障害福祉サービスと介護保険をめぐる訴訟
65歳問題と浅田訴訟,天海訴訟
弁護士 呉 裕麻 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所
報告
24時間介護保障訴訟における到達点と課題
金川めぐみ 和歌山大学経済学部教授
報告
駅無人化反対訴訟の意義とその現状
弁護士 徳田靖之 大分市・徳田法律事務所
報告
視覚障害を理由とする不当配転訴訟
何故,大学での教壇復帰は果たされないのか
山口雪子 岡山短期大学
連載/実践に学ぶ
【報告】特別支援学校高等部の実践
映画づくりに青春を燃やす
〝優しくユーモアに溢れるZくん〟が友達に受けとめられるまで
渡邊陽香 京都府・特別支援学校教員
【渡邊実践に学ぶ】
青年期の内面的成長を支える集団活動を通した授業づくり
寺川志奈子 鳥取大学地域学部
連載/実践に学ぶ
【報告】障害者作業所の実践
「自分らしく働き,暮らす」を支援する
日下部育子 社会福祉法人亀岡福祉会 第三かめおか作業所 管理者
日下部実践に学ぶ
「生活まるごと」を見つめ,温かい声かけを大切に
山田宗寛 立命館大学産業社会学部
連載/ワイドアングル 第27回
包括的性教育
〈4 つの柱〉に着目して
堀川修平 埼玉大学ダイバーシティ推進センター
動向
恵庭市の障害者虐待事件について
弁護士 船山暁子 札幌市・ルピナス法律事務所
▶ご注文は 全障研出版部オンラインショップへ
▶ 「読む会」情報
日時=2025年1月9日(木)18時30分~21時/zoomで開催し、60人の参加で学びあいました
編集委員=濵畑芳和(立正大学)、山本忠(立命館大学)司会
〇話題提供=鼎談 障害のある人の人権と社会保障裁判 より
井上英夫さん(金沢大学名誉教授)藤原精吾さん(弁護士) 藤井克徳さん(日本障害者協議会)
〇参加者の意見交流

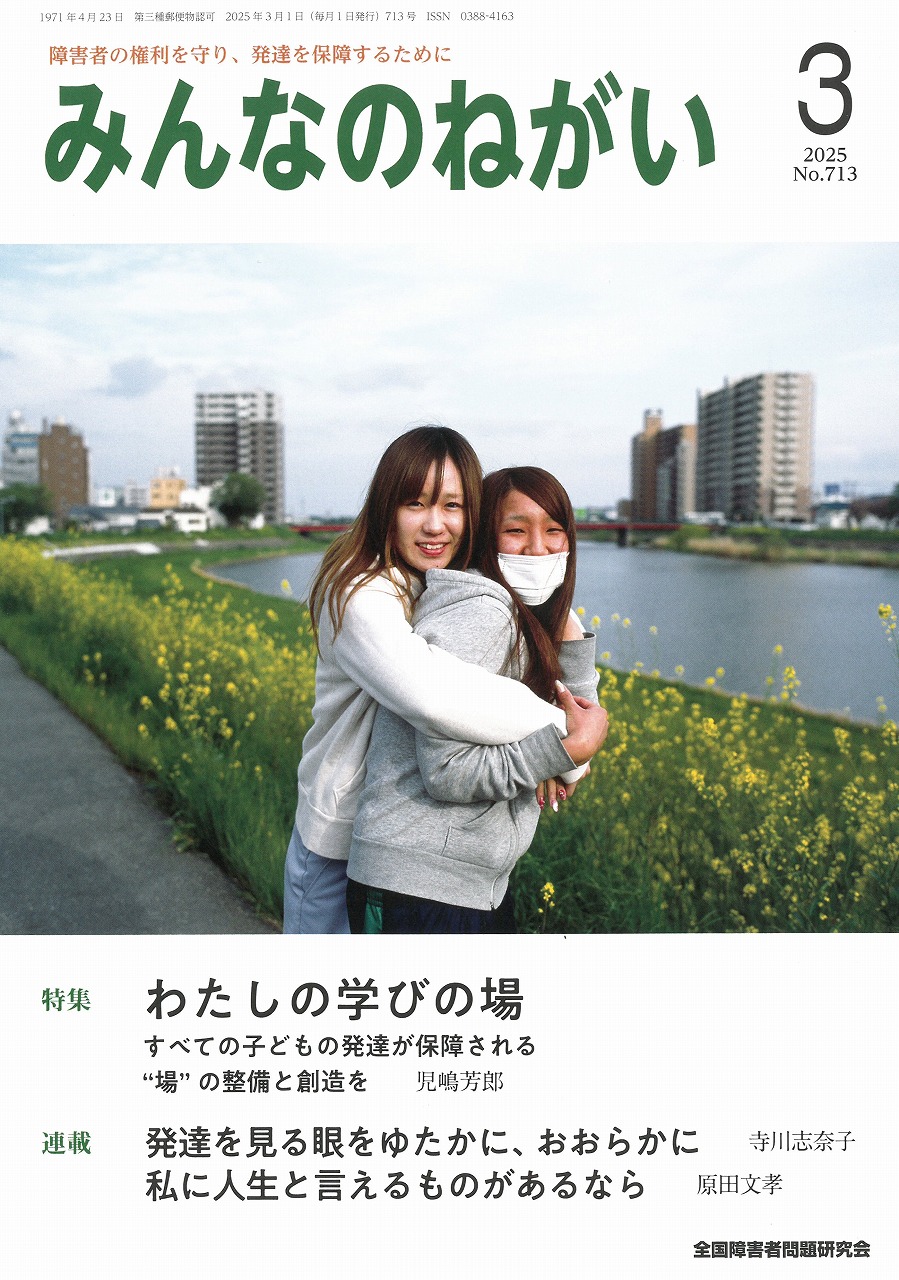
<表紙のことば>
地元の川べりに座り、彼女たちは恋話でもしていたのだろうか。
声をかけカメラを向けると「ええーめっちゃ寝巻きだしー」と照れながらも嬉しそうにくっつく姿が愛おしい。
飾らない表情と普段どおりの風景。何気ない日々のなかの1コマがきらきらとした青春の1ページをつくっていく。こんな一期一会の出会いだからこそ、垣間見えるものが胸に沁みる。
寒くて長い冬からようやく春へと近づくこの季節。
菜の花の花言葉は「小さな幸せ」。
僕は、これからも市井の人々を撮り続けていこうと思う
土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある
<目次>
特設!「試し読み」のページ(PDF)へ
1 人として 今井彰人(俳優)
2 【インタビュー】いまを語りあう 永井玲衣(哲学研究者)
4 はじめの一歩~障害のある人を理解する 吉留英雄(全障研大阪支部)
6 人生苦あり笑いあり 秋保喜美子(広島)
7 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)
8 この子と歩む 島田和子(兵庫)
11 進め! 推し活道 伊藤伸矢(東京)
特集 わたしの学びの場
13 わが子が学ぶ学びの場への思い 榮 幸世(東京)
14 病弱支援学校で学ぶ子どもたち 金澤園子(神奈川)
16 離島に、小規模特別支援学校分教室設置を 野津 保(島根)
18 仲間とともによくわかる楽しい授業を 金坂美穂(東京)
20 フリースクールの学びの多様性 平野和弘(moonlight project)
22 すべての子どもの発達が保障される“場”の整備と創造を 児嶋芳郎(立正大学)
25 【マンガ】のんびり ぼちぼち 池添鉄平・ナガノテツコ
26 私ときょうだい 竹田裕靖(京都)
28 発達を見る眼をゆたかに、おおらかに 寺川志奈子(鳥取大学)
32 私に人生と言えるものがあるなら 原田文孝(ささゆり会)
36 シリーズ 保育の現場から 山本いつみ(京都)
38 実践にいかす障害と発達 安藤佳珠子(日本福祉大学)
40 ニュースナビ 障害児通所支援利用者負担有料化反対運動
鮫島梨紗(障害児通所支援利用者負担無料の継続を求める会)
42 実践の魅力 川野美幸(奈良)
45 あそぼう、つくろう 長谷川聡一朗(兵庫)
46 みんなのひろば
48 BOOK/編集後記
デザイン・イラスト うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、橋野桃子、山内若菜
▶ご購読希望は出版部オンラインへ
第33回発達保障研究集会
日時 2025年3月22日(土)、23日(日)
会場 埼玉大学教育学部
締切日 3月17日(月)
申込先 https://form.run/@happoken33
発達保障研究集会のお誘い
市場や競争の原理を至上のものとする新自由主義が教育や福祉の現場にも深く入り込み、障害のある人の発達や権利が著しく脅かされる状況が続いています。本人の「個性」や「自由」が強調されるほど、かえって障害のある本人の生活はある方向へと枠づけられ、教育・福祉実践もまた画一化され管理・統制がいっそう厳しくなっていきます。
今回の集会では、そうした新自由主義が浸透する生活や実践現場の困難さを正面から見つめることで、発達保障の課題を吟味したいと思います。
全体会では、2024年8月に『新自由主義教育の40年—「生き方コントロール」の未来形』を出版された児美川孝一郎さんをお呼びします。この40年間に新自由主義教育改革がいかに進められてきたのか、なぜ私たちは新自由主義を受け入れてしまうのか、学校現場の感覚や同時代の経験に即してその「抗いがたさ」を見つめながら、新自由主義教育への対抗軸や研究運動の足場がどこに見出せるかを考えたいと思います。
全体会の問題提起や議論を課題研究におけるライフステージや分野ごとの実践・研究課題につなげて深め、新自由主義が猛威をふるう社会のなかで、私たちの生活感覚や社会意識も厳しく問い直しながら、実践・研究運動の課題を話し合いましょう。多くのご参加をお待ちしています。
全障研研究推進委員長 河合隆平
■全体会 3月22日(土)13:00~14:30
講演 児美川孝一郎さん(法政大学)
「教育・福祉の現場のしんどさはどこから来るのか? ―新自由主義の「抗いがたさ」に向きあう―」
■課題研究 22日(土)15:00~18:00
3つの分科会を設けます
課題研究1=乳幼児期
親の発達保障について考える〜親と子どものねがいを支えるために〜(仮)
保護者の立場から…埼玉より
児童発達支援センターの実践と現状報告
課題研究2=学齢期
「行動を変える指導」と学校教育~私たちが大切にしたい教育とは?~
応用行動分析に基づく「教育」の実情を学ぶ 長野支部より
私たちが大切にしたい教育を考えよう 埼玉より
課題研究3=青年・成人期 強度行動障害と暮らしの場
報告 大阪・いずみ野福祉会山直ホームより
埼玉・みぬま福祉会より
▼詳しい案内や申込方法は以下をクリックください。
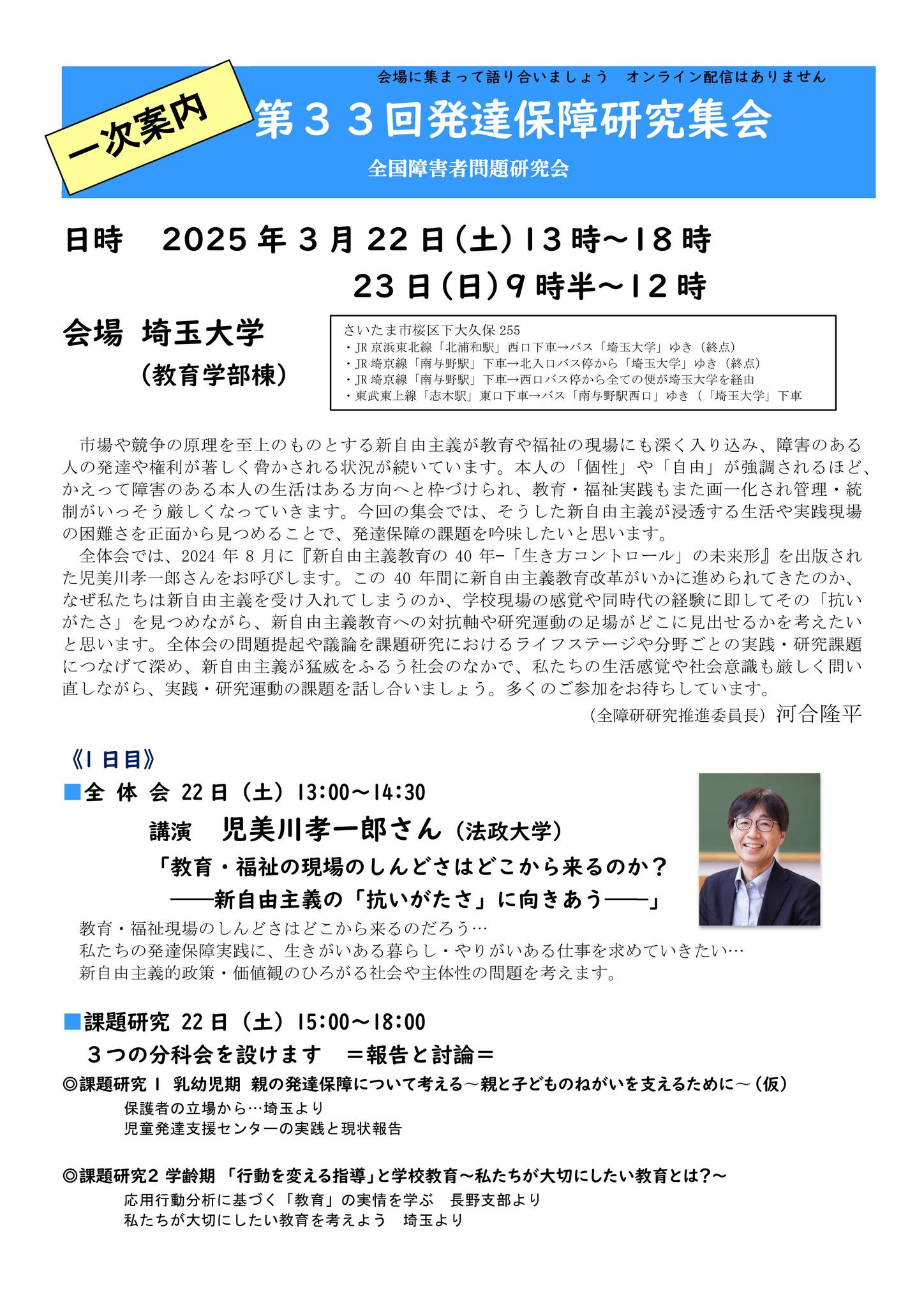
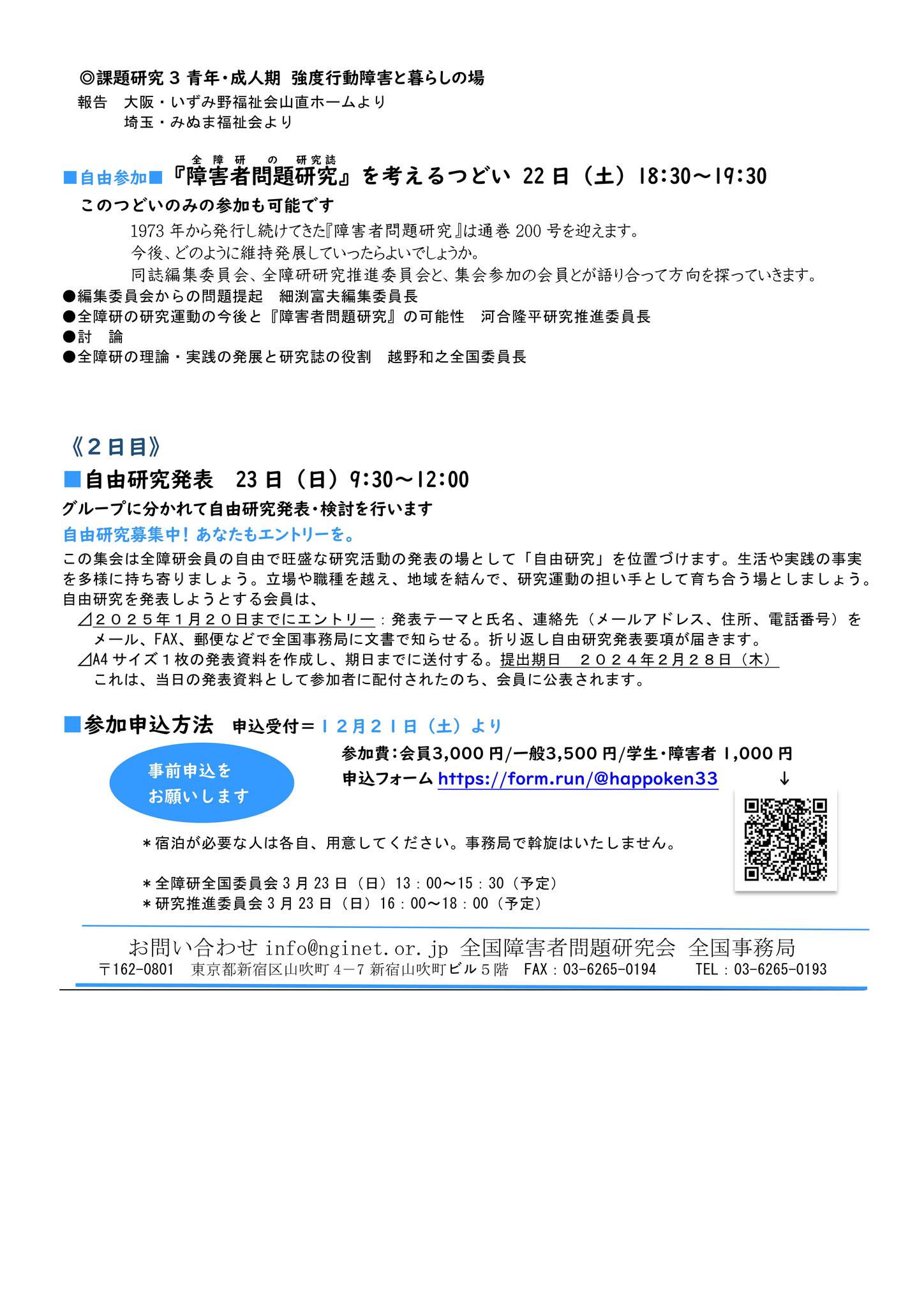
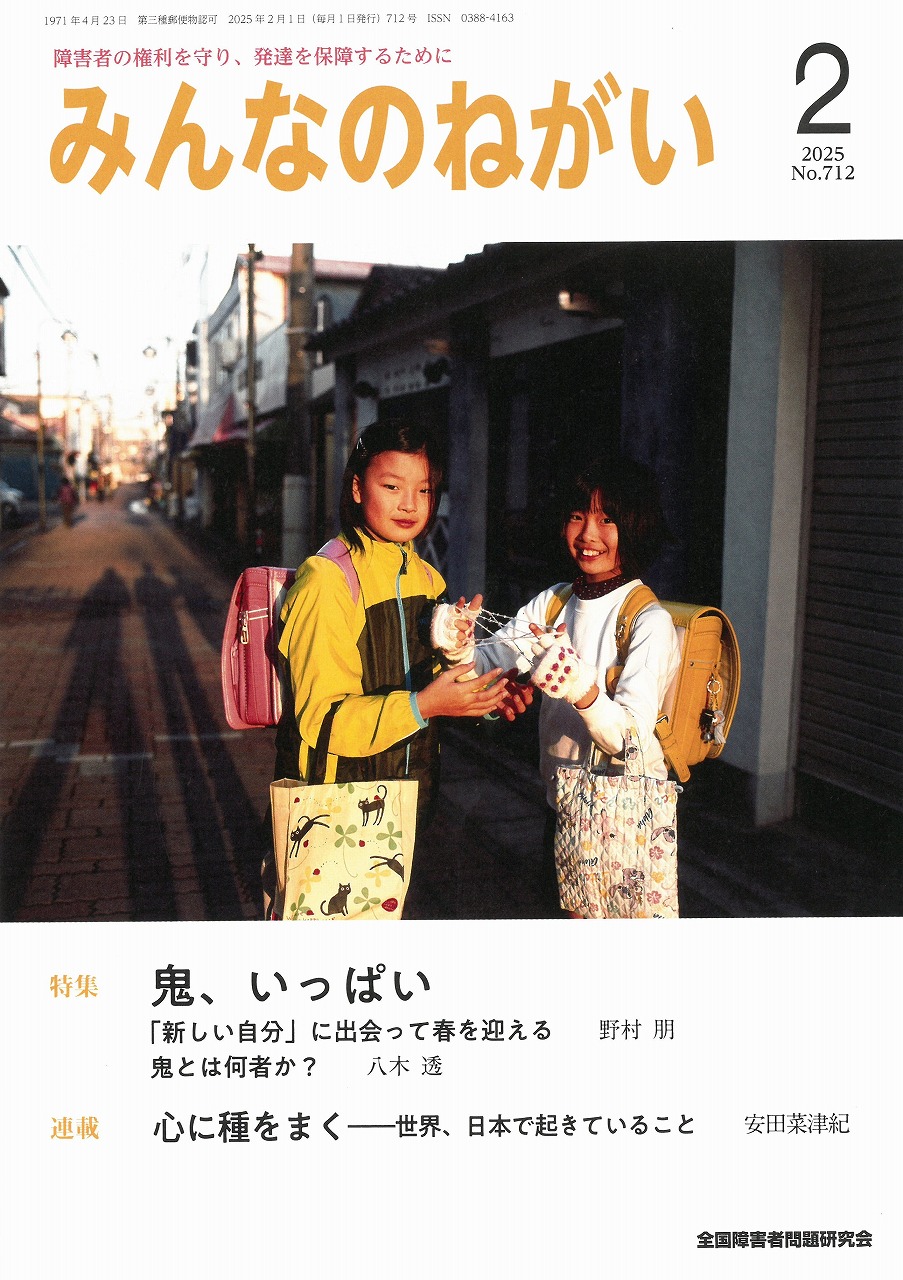
<表紙のことば>
暮れゆく港町の商店街をあやとり遊びしながら歩く放課後の帰り道。学校での出来事を楽しそうに話すその顔を夕陽がやさしく照らす。
僕も小学生の頃、下校の道は楽しい時間だった。友達と石蹴りやクイズや探検ごっこしながら帰ったことをとてもよく覚えている。草の匂い、土の感触、オレンジのあたたかい光の色。からだ全部で受け取った感覚は今でもちゃんと残っている。
歳を重ねるごとに幼い頃の記憶を辿ることが増えてきた気がする。センチメンタルな記憶。このさき撮っていく写真にもじんわりと映したい。。
土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある
<目次>
特設!「試し読み」ver2(PDF)ページ へ
1 人として 五十嵐 大(作家)
2 【インタビュー】いまを語りあう 永井玲衣(哲学研究者)
4 はじめの一歩~障害のある人を理解する 吉留英雄(全障研大阪支部)
6 人生苦あり笑いあり 秋保喜美子(広島)
7 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)
8 この子と歩む 中根登紀子(さいたま市)
11 進め! 推し活道 浜本宇太郎(京都)
特集 鬼、いっぱい
12 おに 鬼 オニ
16 鬼とは何者か? 八木 透(佛教大学・世界鬼学会会長)
18 怖い鬼に向かい、人との信頼関係を紡ぐ 伊津佳恵(広島乳幼児サークル)
20 鬼の絵本、いっぱい 古澤直子(特別支援学級)
21 「新しい自分」に出会って春を迎える 野村 朋(大阪健康福祉短期大学)
24 私ときょうだい 仁村菜月子(滋賀)
26 発達を見る眼をゆたかに、おおらかに 寺川志奈子(鳥取大学)
30 私に人生と言えるものがあるなら 原田文孝(ささゆり会)
34 シリーズ 保育の現場から 益田有紀(高知)
36 実践にいかす障害と発達 安藤佳珠子(日本福祉大学)
38 ニュースナビ 日本手話による教育を求める裁判 藤野友紀(札幌学院大学)
40 実践の魅力 阿部直子(埼玉)
43 あそぼう、つくろう 小山紗知(兵庫)
44 みんなのひろば
46 【マンガ】のんびり ぼちぼち 池添鉄平・ナガノテツコ
47 BOOK/編集後記
裏表紙 おいしいひととき 林 裕也(大阪)
デザイン・イラスト うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、橋野桃子、山内若菜
▶ご購読希望は出版部オンラインへ
当会のさまざまな活動への日頃よりのご協力にこころから感謝いたします。
世界各地での戦闘はやまず、国内では膨大な軍事費増・福祉切り捨ての動きです。地球環境の悪化も深刻です。
障害者権利条約・総括所見をいかしながら、障害者の権利を守り、発達を保障するための研究運動をみなさんと共にすすめます。
2025年1月1日
全国障害者問題研究会 全国委員長 越野和之
全国障害者問題研究会 出版部長 越野和之
NPO発達保障研究センター 理事長 児嶋芳郎
役員・全国事務局・編集部 一同
東京都新宿区山吹町4−7 新宿山吹町ビル5F
電話番号:03-6265-0193
FAX番号: 03-6265-0194
メール:info@nginet.or.jp
地図など詳細はここをクリックしてください

<表紙のことば>
熱海の雰囲気のある裏路地に惹かれてカメラを覗いていると、向こうからひとりの女性が歩いてきた。はっとして声をかけ聞くと、近くの熱海見番に通う芸妓さんとのこと。麗らかな光と香ばしい路地に美しい芸妓。こんな奇跡のタイミングが訪れるとき、自分には写真の神様がついていると思ってしまう。夢を追い求めやってきたこの地できらきらと輝く彼女は、優しく凛としていた。被写体が写真を作ってくれる。そして、見る私たちに気付かせてくれる。2025年も写真を通してたくさんの素敵な出会いがあることを、写真の神様に願う。
土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある
<目次>
1 人として 山本美里(写真家)
2 【インタビュー】いまを語りあう 永井玲衣(哲学研究者)
4 はじめの一歩~障害のある人を理解する 吉留英雄 (全障研大阪支部)
6 響け石突き 秋保喜美子(広島)
7 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)
8 この子と歩む この子と歩む 吉田美奈(天理市)
11 進め! 推し活道 町金(大阪)
特集 私のねがい2025 ~今年は何をしようかな
12 自分らしくがんばりたい 小山怜音(山梨)
13 前向きでやさしい気持ちに 俊文書道会(青森)
14 この島で人と人をつなぎたい 前原真奈美(鹿児島)
15 春希の2024年の成長 厚東泰子(山口)
16 ドンドンつながれ太鼓サークル2025(埼玉)
17 私のねがい 南家孝之(広島)
18 つないでいきたい被爆世代の思い 高垣慶太(国際赤十字ユース代表)
22 宮沢賢治の作品をたっぷりと 松本春野(絵本作家)
24 私ときょうだい 町野愛花(岐阜)
26 発達を見る眼をゆたかに、おおらかに 寺川志奈子(鳥取大学)
30 私に人生と言えるものがあるなら 原田文孝(ささゆり会)
34 シリーズ 保育の現場から 三輪由香里(奈良)
36 実践にいかす障害と発達 精神障害のある子ども・若者の理解と支援 安藤佳珠子(日本福祉大学)
38 ニュースナビ 株式会社恵問題 今治信一郎(きょうされん愛知支部)
40 実践の魅力 十田朋也(兵庫)
43 あそぼう、つくろう 岡田由希(京都)
44 みんなのひろば
46 【マンガ】のんびり ぼちぼち 池添鉄平・ナガノテツコ
47 BOOK/編集後記
裏表紙 おいしいひととき 六十谷尚美(奈良)
デザイン・イラスト うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、橋野桃子、山内若菜
▶ご購読希望は出版部オンラインへ
◆全障研事務所の移転と連絡先のお知らせ 2024年10月24日
全障研事務所の移転と連絡先をお知らせします。
〒162-0801
東京都新宿区山吹町4−7 新宿山吹町ビル5F
電話番号:03-6265-0193
FAX番号: 03-6265-0194
メールアドレスやWEBの変更はありません。
メール:info@nginet.or.jp
地図など詳細はここをクリックしてください
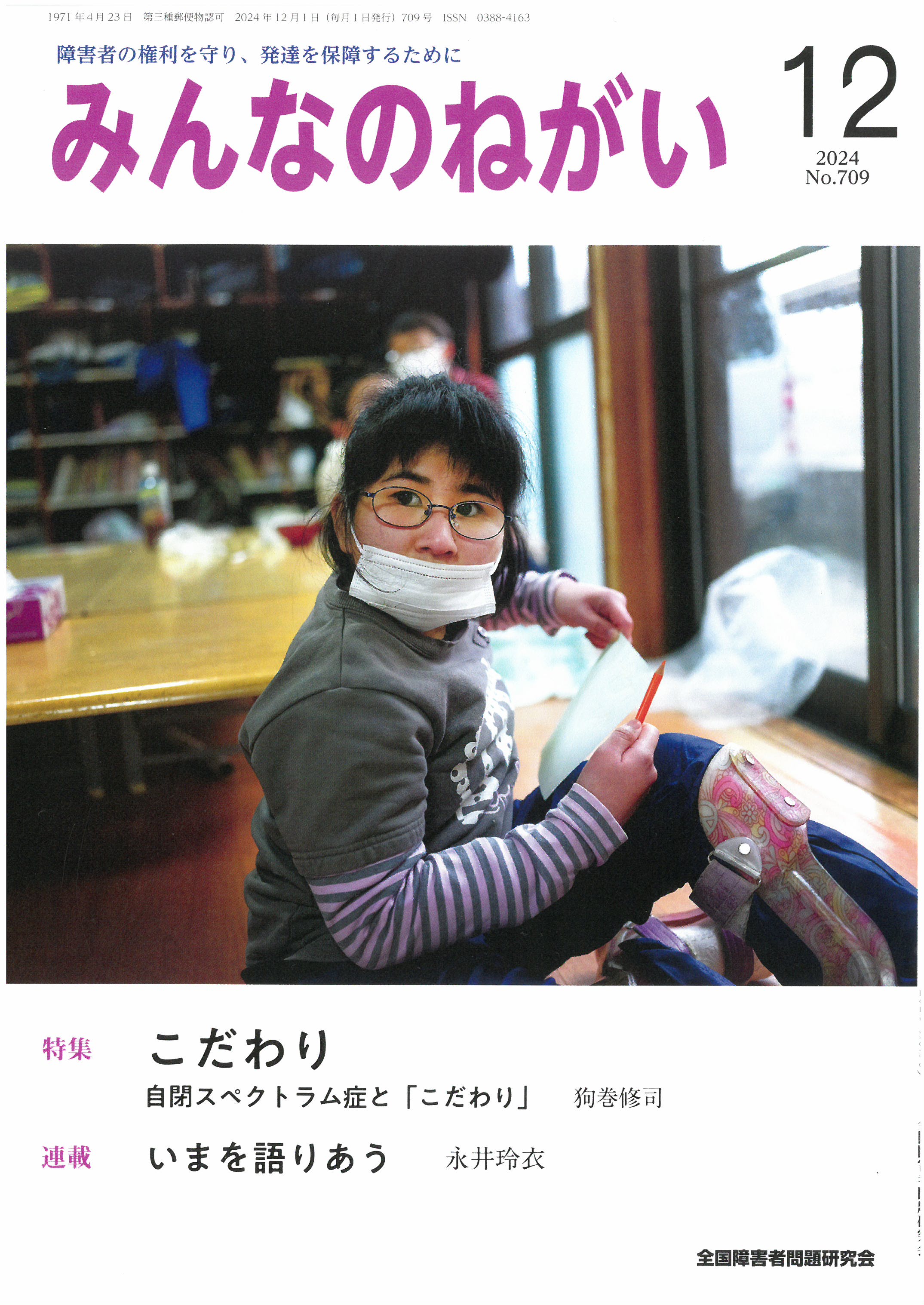
<表紙のことば>
障害児学童保育「モンキーポッド」を訪れたのは2022年冬。思えば、ここが写真家として障害を持つ方たちと向き合った始まりの場所だった。慣れない雰囲気に戸惑う僕をじっと見つめる彼女。その澄んだ瞳は、今までの僕の「普通」という小さな薄っぺらい価値観を全て見透かしているようだった。でも同時に、この場所で出来ることは一生懸命写真を撮ることだけだと気付かせてくれた。目を凝らして必死にシャッターを切って、精一杯向き合わなければ。あれから三年が経った。僕はまだまだ人として至らないけど、それでも写真家としてやれることをやり続けようと思う。それを導いてくれた彼女の瞳を忘れない。
土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある
<目次>
1 人として 倍賞千恵子(女優)
2 【インタビュー】いまを語りあう 永井玲衣(哲学研究者)
4 はじめの一歩~障害のある人を理解する 吉留英雄 (全障研大阪支部)
6 響け石突き 秋保喜美子(広島)
7 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)
8 この子と歩む 佐野美樹 (山梨市)
11 進め! 推し活道 堀井大輝(京都)
特集 こだわり
12 こだわりは『味』 星 雄一朗 (奈良 NPO法人ふぁーちぇ)
13 自閉スペクトラム症と「こだわり」 狗巻修司(奈良女子大学)
16 安心できる保育者を支えに変わっていったやまとくん
今井悠月 (愛知 東部地域療育センターぽけっと)
18 この子はこんなにおもしろい 安井恵理 (奈良)
20 空想の世界から現実の社会への移行 井上麻衣子(愛知 るっくコーポレーション)
22 こだわりの世界に入ってみる 赤木和重(神戸大学)
24 私ときょうだい 加藤綾乃(奈良)
26 発達を見る眼をゆたかに、おおらかに 寺川志奈子(鳥取大学)
30 私に人生と言えるものがあるなら 原田文孝(ささゆり会)
34 シリーズ 保育の現場から 田中亮多(滋賀 大津市立保育園)
36 実践にいかす障害と発達 精神障害のある子ども・若者の理解と支援 安藤佳珠子(日本福祉大学)
38 ニュースナビ 性虐待損害賠償請求裁判 武田 仁 (Aさんの性虐待損害賠償請求裁判を支援する会)
40 実践の魅力 平松洋子・前田僚子 (山梨)
43 あそぼう、つくろう 周防美優 (京都 児童発達支援事業所ひろば)
44 みんなのひろば
46 【マンガ】のんびり ぼちぼち 池添鉄平・ナガノテツコ
47 BOOK/編集後記
裏表紙 おいしいひととき 小林幸路 (埼玉)
デザイン・イラスト うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、橋野桃子、山内若菜
▶ご購読希望は出版部オンラインへ
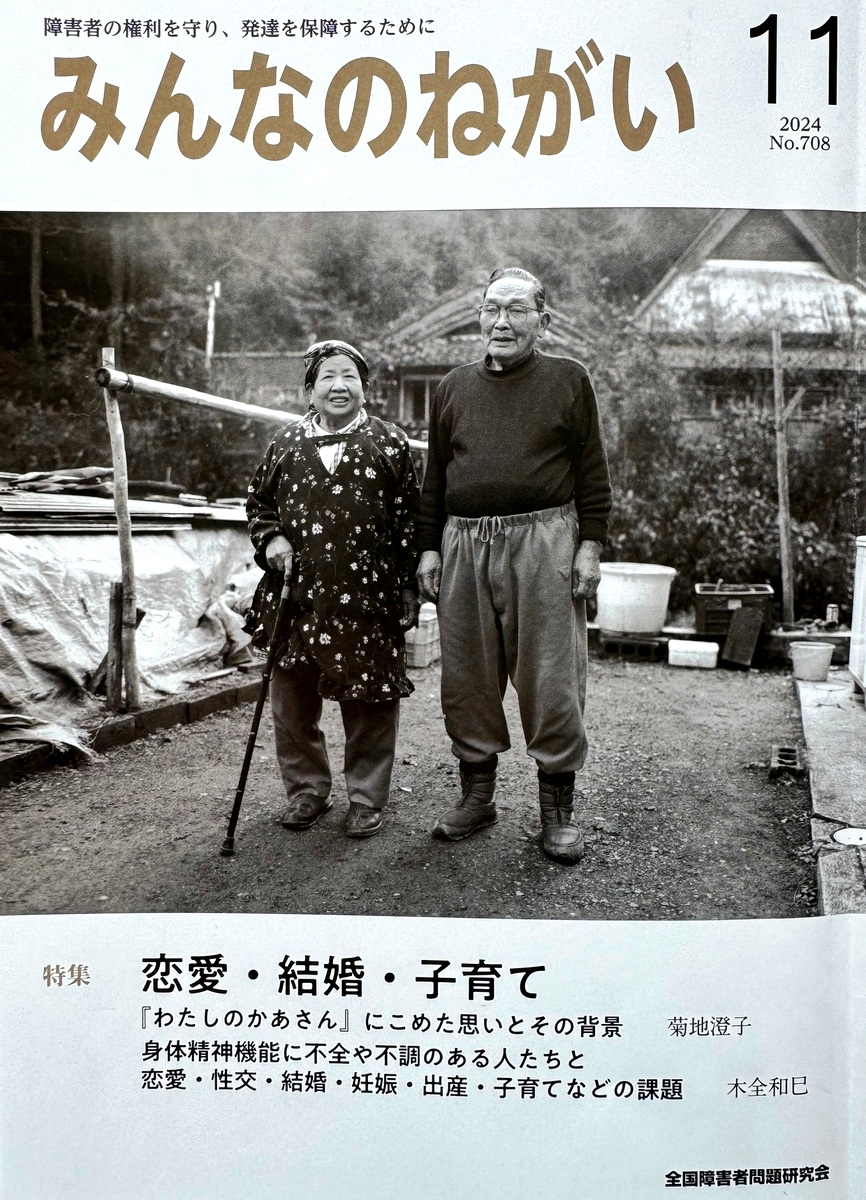
<表紙のことば>
紀伊半島の内陸部、深い深い山あいの道を行く。朝霞が立ちこめるまるで隠れ里かのような小さな集落。古い一軒家の庭先に老夫婦が立っていた。人と出会うこと自体が珍しい状況にお互い少し驚いた感じだったが、声をかけると優しく微笑んでくれた。穏やかなその顔つきとふたりの距離感に、これまでの人生が滲んでくる。便利さとはかけ離れたこの場所で、そっと支え合いながら和らかな日々を送ってきたに違いない。
豊かさっていったい何だろう。十数年前に撮った写真を眺めながら、改めて思いにふける。
土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある
<目次>
1 人として 松田貴義(ゆらぐ「じぶん」の生き方を共に模索する同行者)
2 【インタビュー】いまを語りあう 永井玲衣(哲学研究者)
4 はじめの一歩~障害のある人を理解する 船橋秀彦(全障研茨城支部)
6 響け石突き 藤野喜子(日本視覚障害者協議会理事)
7 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)
8 この子と歩む 桐山久美(和歌山市)
11 進め! 推し活道 大橋伸和(北海道)
特集 恋愛・結婚・子育て
12 『わたしの母さん』に込めた思いとその背景 菊地澄子(児童文学作家)
14 「障害者は子どもを産むな」という優生保護法の影響に抗いながら 小森淳子(岐阜)
16 障がいのある仲間とともに社交ダンスを楽しみながら包括的性教育を学ぶ 鈴木良子(宮城)
18 しんごさん一家とともに支え支えられて、発達し合う私たち 本田瑞絵(鹿児島)
20 じいちゃんとぼく 市橋 怜・市橋 博(東京)
21 身体精神機能に不全や不調のある人たちと恋愛・性交・結婚・妊娠・出産・子育てなどの課題 木全和巳
日本福祉大学)
24 私ときょうだい 今野優希(神奈川)
26 発達を見る眼をゆたかに、おおらかに 寺川志奈子(鳥取大学)
30 私に人生と言えるものがあるなら 原田文孝(ささゆり会)
34 シリーズ 保育の現場から 保育士の配置基準を考える みんなのねがい編集部
36 実践にいかす障害と発達 精神障害のある子ども・若者の理解と支援 安藤佳珠子(日本福祉大学)
38 ニュースナビ 栃木県特別支援学校寄宿舎問題について 矢口直(全教障教部寄宿舎担当)
40 実践の魅力 大前学(福井)
43 あそぼう、つくろう 塚田直也(筑波大学附属視覚特別支援学校)
44 みんなのひろば
46 【マンガ】のんびり ぼちぼち 池添鉄平・ナガノテツコ
47 BOOK/編集後記
裏表紙 おいしいひととき 松田美由紀(神奈川)
デザイン・イラスト うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、橋野桃子、山内若菜
▶ご購読希望は出版部オンラインへ
『発達のなかの煌めき 上』 出版記念です!
秋の オンライン・トークイベント
発達と発達保障をご一緒に学びませんか
白石正久さん
白石恵理子さん
★スペシャルトーク&質問にこたえて
●日時 2024年10月20日(日) 13:00~15:00
八ヶ岳の麓 野の花こども館より オンライン・ライブ配信
●参加費:無料(定員100人)
●参加申込みは、ここをクリックしてお申し込みください。
発達は、他者と手をつなぎあうことを知り、そのつながりや集団を通じて、みんなが幸福になれる社会を創っていく過程でもあります。
成長でも発育でもない発達という概念は、人間を外側から捉え、計測するだけでは見えてこない内的な営みの存在を抜きにして語ることはできません。
私たちは悩み、ときに諦めたり逃げ出したくなりつつも、本を読んだり、悩みを言語化したり、子どもの姿を書き言葉で綴ったり、何よりも仲間や同僚と語りあうことで、その矛盾を越えようとしていきます。そして、少しでも、子どもの姿がみえてきたときに喜びや実践への手ごたえを感じ、また前に進んでいこうとします。ごいっしょに職場や地域で、語りあい、学びあってまいりましょう。
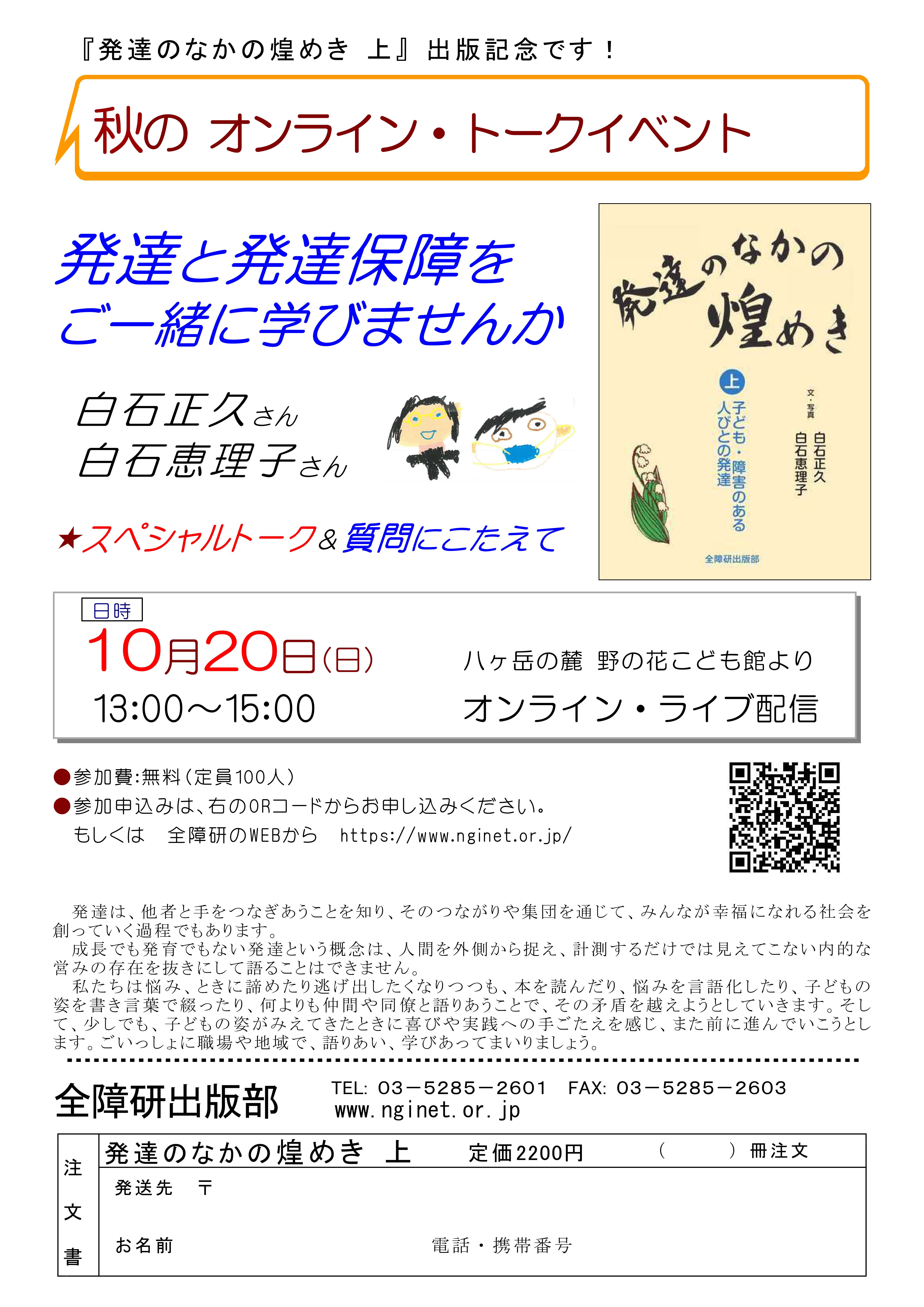
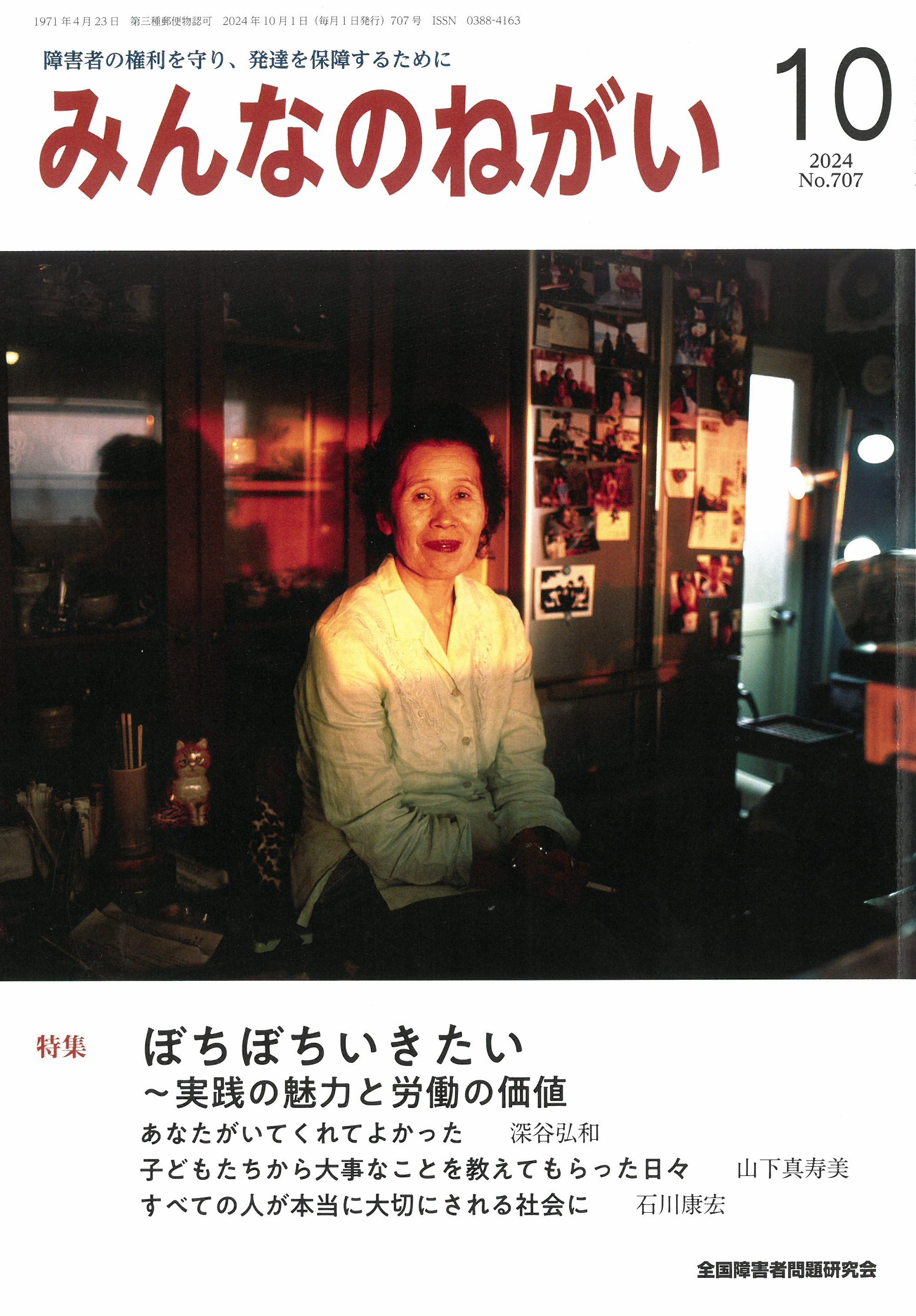
<表紙のことば>
千葉県内房の海岸の先端に佇む喫茶店「岬」。女店主はオープンから半世紀近くもの間ずっとひとりでこの店を切り盛りしてきた。かつて火事で店が焼失したこともあり、様々な苦難を乗り越え、房総の絶景を望むこのカフェは今も営業を続けている。その素晴らしいロケーションと店主のドラマチックな人生は小説や映画のモデルにもなった。
太平洋に沈む夕陽とスピーカーから流れるビートルズ。閉店後のいつもの一服に付き合わせてもらい昔話を聞く。この場所でこの景色をずっとずっとひとりで眺めてきた彼女の、夕焼けに照らされた横顔をじっと眺めていた。
土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある
<目次>
1 人として 佐伯 淳(元愛媛県数学教育協議会委員長)
2 【インタビュー】いまを語りあう 永井玲衣(哲学研究者)
4 はじめの一歩~障害のある人を理解する 船橋秀彦(全障研茨城支部)
6 響け石突き 藤野喜子(日本視覚障害者協議会理事)
7 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)
8 この子と歩む 撫 理恵子(神戸市)
11 進め! 推し活道 石吉(三重)
特集 ぼちぼちいきたい 実践の魅力と労働の価値
13 進路指導のやりがいとむずかしさとワークバランスと 六車加代(岡山 特別支援学校)
14 私が実践を続ける理由 谷延幸祐(鹿児島 学童支援ゆめの樹)
15 この仕事、捨てたもんじゃないな 荒瀬耕輔(京都 特別支援学校)
16 同僚たちとの議論から得られた気づき 荒瀬修三(岐阜 ポップコーン福祉会)
17 あなたがいてくれてよかった 深谷弘和(天理大学)
20 子どもたちから大事なことを教えてもらった日々 山下真寿美(島根)
22 すべての人が本当に大切にされる社会に 石川康宏(神戸女学院大学名誉教授)
24 私ときょうだい 白井綾乃(埼玉)
26 発達を見る眼をゆたかに、おおらかに 寺川志奈子(鳥取大学)
30 私に人生と言えるものがあるなら 原田文孝(ささゆり会)
34 シリーズ 保育の現場から 金子美音子(大阪 コスモス いづみ保育園)
36 実践にいかす障害と発達 精神障害のある子ども・若者の理解と支援 安藤佳珠子(日本福祉大学)
38 ニュースナビ 生活のしづらさなどに関する調査 佐藤久夫(日本社会事業大学名誉教授)
40 実践の魅力 中藤美紀(高知)
43 あそぼう、つくろう 塚田直也(筑波大学附属視覚特別支援学校)
44 みんなのひろば
46 【マンガ】のんびり ぼちぼち 池添鉄平・ナガノテツコ
47 BOOK/編集後記
裏表紙 おいしいひととき 篠原憲一(熊本)
デザイン・イラスト うじたなおき、勝倉大和、ちばかおり、永野徹子、橋野桃子、山内若菜
▶ご購読希望は出版部オンラインへ
「障害者問題研究」52巻2号 特集=障害児保育の半世紀 -制度と実践の課題
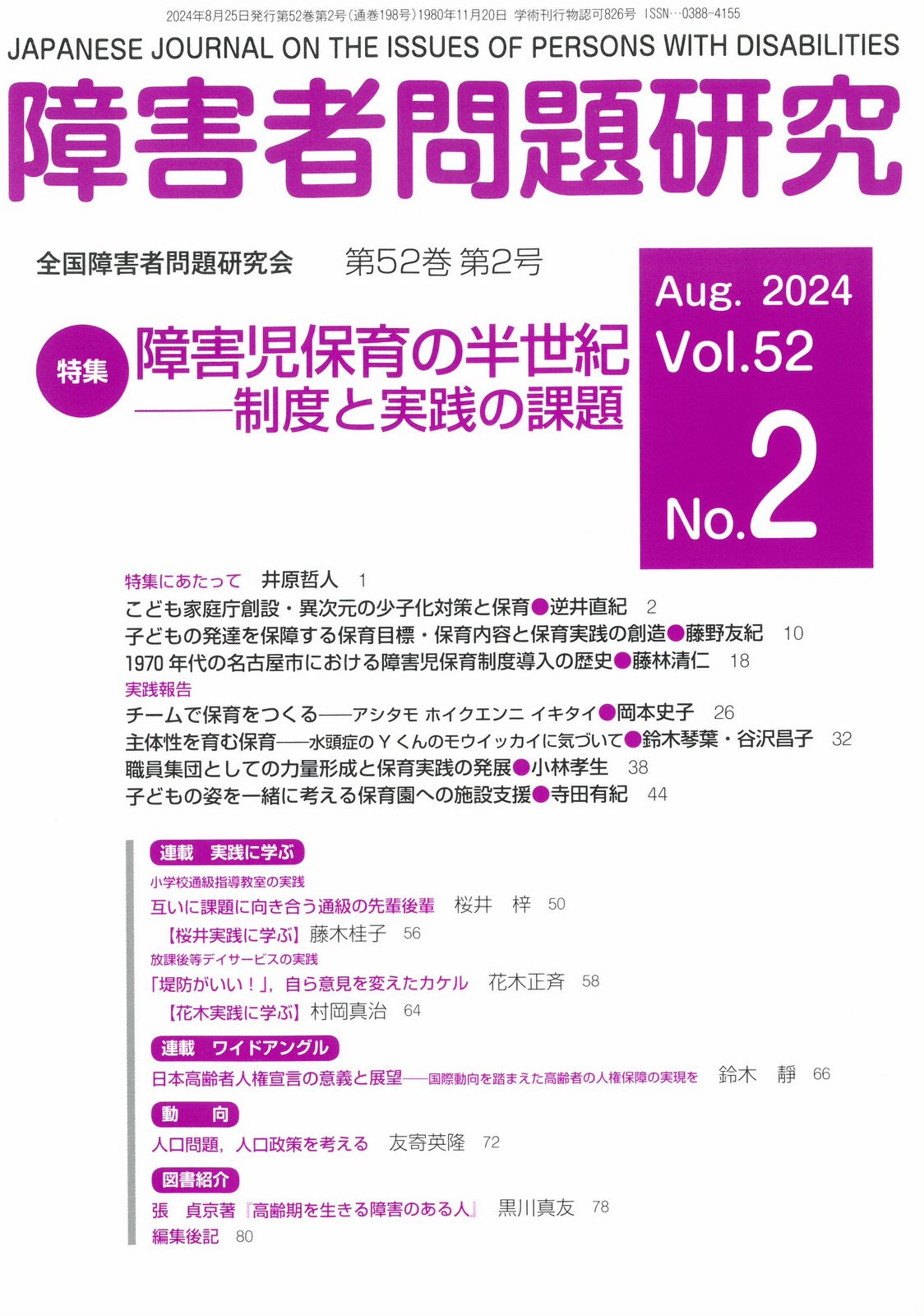
JAPANESE JOURNAL ON THE ISSUES OF PERSONS WITH DISABILTIES
ISBN-984-4-88134-196-4 C3037 定価2750円(本体2500円+税)
特集 障害児保育の半世紀 -制度と実践の課題
特集にあたって
/井原 哲人 白梅学園大学
こども家庭庁創設・異次元の少子化対策と保育
子ども人口の減少局面における保育政策の動向
/逆井 直紀 保育研究所・全国保育団体連絡会
1990年代,保育政策は,女性労働力活用のために保育所積極活用策へと転換が図られた.社会福祉基礎構造改革により福祉は利用者と事業者との直接契約方式に切り替えられたが,2015年度からの子ども・子育て支援新制度でも,保育所は児童福祉法24条1項にもとづく公的責任が維持された.その一方で,条件の異なる多様な保育の受け皿が併存した.2023
年度にこども基本法等が施行,こども家庭庁が創設され,2024年からこども未来戦略が始動したもとでの保育政策では,保育士の配置基準の若干の改善があり,子どもの権利保障を拡充する兆しはあるものの,政策の基調は依然,規制緩和中心の新自由主義的な路線である.特に,保護者の就労の有無を問わず柔軟に一定時間だけ6ヵ月~2歳までの子どもを預かる「こども誰でも通園制度」は,一時託児の市場化の恐れがあり,多方面から警鐘が鳴らされている.
子どもの発達を保障する保育目標・保育内容と保育実践の創造
/藤野 友紀 札幌学院大学人文学部人間科学科
現行の「保育所保育指針」は幼児教育のグローバル・ガバナンスの影響を受けて,小学校教育との接続の視点を明確に打ち出している.その具体化が「幼児期までに育ってほしい姿」である.個人の認知能力や非認知能力の育成を保育目標とし,その達成に向けて保育の「質」を上げていく発想は,子どもを「人材」とみなし,保育から創造性を奪う危険
性を孕んでいる.子どもの発達を保障することは,子どもの「能力」の開発と同義ではない.保育は目の前の子どもの願いを探ることから出発する.子どもの願いを踏まえて保育目標と保育内容をつくりだし,新しい価値を共有する.この保育の創造性が守られてこそ,子どもの発達は保障される.
1970年代の名古屋市における障害児保育制度導入の歴史
/藤林 清仁 同朋大学社会福祉学部社会福祉学科
1974年に「障害児保育実施要綱」が策定されると,愛知県名古屋市においても障害児保育が制度化されていった.名古屋市では,民間保育所において障害のある子どもの受け入れが行われていた.その実践があったため,民間保育所を対象にした人件費補助制度が先に始まった.公立保育所への障害児保育補助制度においては,労働組合も議論に参加して制度をつくりあげていった.
実践報告
チームで保育をつくる
アシタモ ホイクエンニ イキタイ
/岡本 史子 滋賀県・大津市立 保育園
実践報告
主体性を育む保育
水頭症Yくんのモウイッカイに気づいて
/鈴木琴葉、谷沢昌子 京都府・社会福祉法人 保健福祉の会 洛西保育所
実践報告
職員集団としての力量形成と保育実践の発展
/小林 孝生 神奈川県・社会福祉法人あおぞら理事,あおぞら菅田保育園園長
実践報告
子どもの姿を一緒に考える保育園への施設支援
/寺田 有紀 北海道・社会福祉法人 楡の会
連載/実践に学ぶ
【報告】小学校通級指導教室の実践
互いに課題に向き合う通級の先輩後輩
/桜井 梓 大阪府・小学校通級指導教室
【桜井実践に学ぶ】
働きかけつつ内面に近づく
──子どもたちをつなぐ通級指導教室
/大阪府・小学校通級指導教室 藤木 桂子
連載/実践に学ぶ
【報告】放課後等デイサービスの実践
「堤防がいい!」,自ら意見を変えたカケル
実践しつつ,子どもの内面に近づける放課後実践の魅力
/放課後等デイサービス指導員 花木 正斉 鹿児島県・社会福祉法人麦の芽福祉会 学童支援ゆめの森
花木実践に学ぶ
地元生活に根ざした,人間としての豊かさの追求
/ゆうやけ子どもクラブ 村岡 真治
連載/ワイドアングル 第26回
日本高齢者人権宣言の意義と展望
国際動向を踏まえた高齢者の人権保障の実現を
/鈴木 靜 愛媛大学法文学部
動向
人口問題,人口政策を考える
/友寄 英隆 労働者教育協会
図書紹介
張 貞京著
『高齢期を生きる障害のある人──人とつむぎ,織りなす日々のなかで』
(全障研出版部2023年)
/黒川 真友 滋賀県・社会福祉法人おおつ福祉会
▶ご注文は 全障研出版部オンラインショップへ
▶ 「読む会」情報
日時 2024年9月27日(金)19時~21時 /zoomミーティングによる開催
■ 障害のある子も含めた地域の保育は今どうなっているのだろうか。
■「こども未来戦略」「10の姿」「誰でも通園」などの政策は子どもの権利を
保障するの?
■子どもの発達を保障する保育実践を創造するには?
【話題提供】こども家庭庁創設・異次元の少子化対策と保育
逆井直紀さん(保育研究所、全国保育団体連絡会)
【参加者の意見交流】
○参加費無料。お手元に当該号をご用意ください。
○つぎのフォームより参加申し込みをお願いします。
https://form.run/@shoumonken52-2
定価1650円 ISBN978-4-88134-176-6 2024年8月6日

公設公営の療育センターの民間委託、児童発達支援センターや児童発達支援事業の市場化、世帯の経済状況や親の働き方の変化…子どもをめぐる状況が目まぐるしく変化していくなか、障害のある子どもたちの生活は「午前中は保育園、午後からは児童発達支援事業」というように、一日の中でも切り売りされるようになってきています。そんななか、私たちは療育をどのように考えていけばいいのでしょうか。
全障研広島乳幼児サークルは、2012年の全障研広島大会をきっかけに、発達保障に根ざした療育を広めていくために結成されました。本書は、「療育って楽しい!」と思えるような療育づくりを、保護者とともに数々の実践と運動を紡いできた広島からのメッセージです。療育で大切にしたいこと、明日の療育が見えてくる、そんな一冊になりました。
ぜひ、この本を手に自分たちの職場では、地域では…と考え合うきっかけに。
もくじ●
療育って楽しい!
仲間がいっぱい ひろしまの療育
序 療育の灯火 2/白石正久・白石恵理子
はじめに ~子どもの笑顔と仲間がいっぱいの療育を
part1 療育の中で育つ子どもたち・・・・・・・・・・・・・・・
1 「~だけれども」と自分の心と向き合うⅯちゃん
2 保護者とともにAちゃんについて悩んだ日々
広島市の療育センター一覧
part2 療育を紡ぐ楽しさと喜び・・・・・・・・・・・・・・・・
1 実践と運動の歴史をつなぐ
2 『仲間がいっぱい ひろしまの療育』
3 子ども・家族・職員がつながる「行事」
4 子育ての基盤になる親子通園
part3 親・保護者と療育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 障害児の親になること①
2 障害児の親になること②
3 保護者として、ひとりの生活者としての私
part4 縦糸に歴史、横糸に実践と人々の思いを・・・・・・・・・
~広島の療育の歴史と運動
1 広島市の療育を充実・発展させる運動
2 自治体労働者として
3 保護者とともに
part5 広島乳幼児サークルの役割・・・・・・・・・・・・・・・
part6 療育が教えてくれること・・・・・・・・・・・・・・・・
◉障害の重い子どもの療育にたずさわる保育士として出会いの中で学び大切にしてきたこと
◉マンガ「だいじょうぶ 大丈夫」
おわりに ~平和であればこそ
執筆者一覧
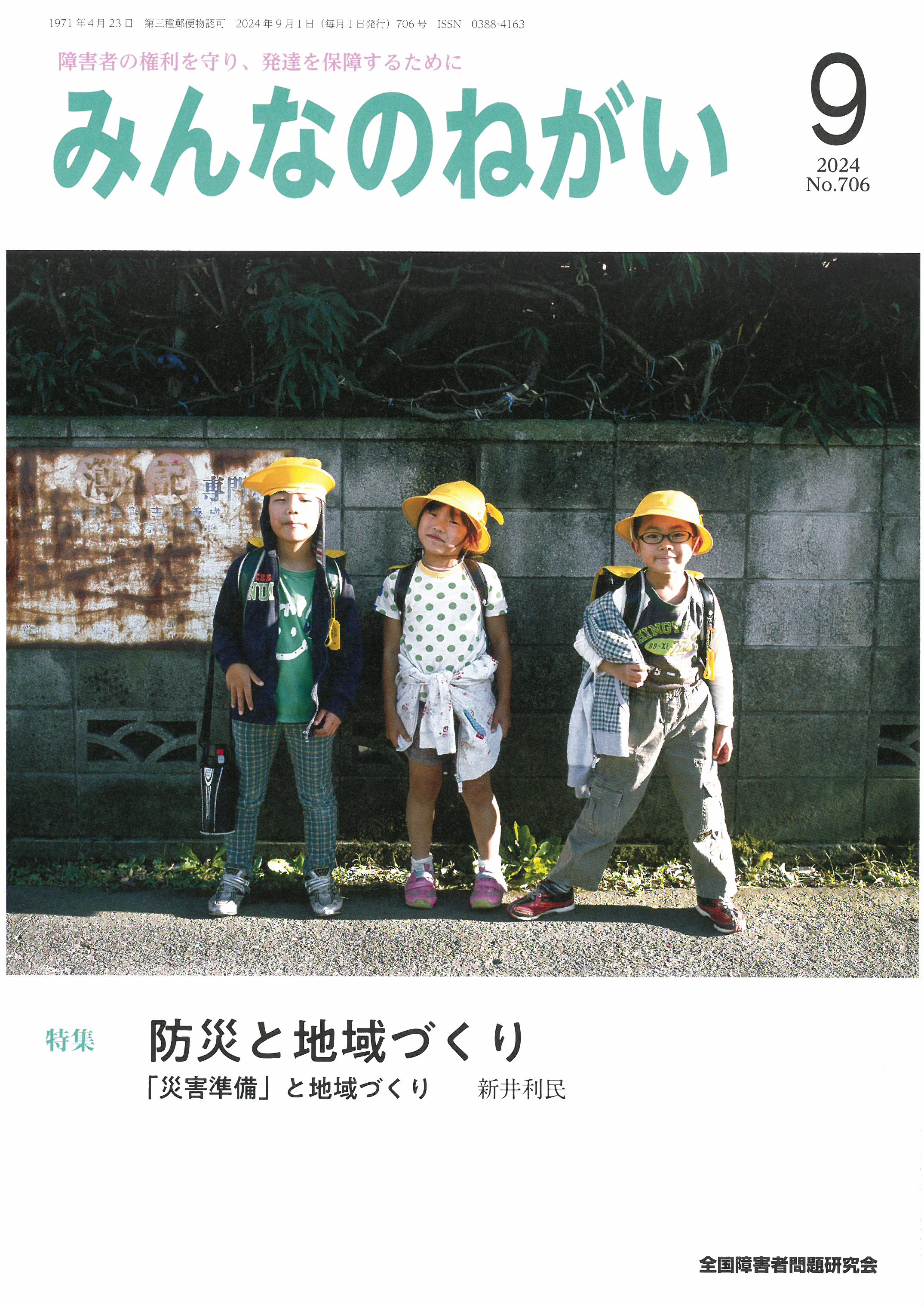
<表紙のことば>
子どもたちにレンズを向けると、みんなそれぞれの雰囲気を醸しだしてくれる。生まれてきて10年足らずだけど、もう個性やキャラは出来上がっているのだ。僕は小学生の頃の記憶をやたらと鮮明に覚えている。友達との人間関係、学校の行事、家族とのこと。すごく周りを見ていたし、今よりもっと繊細な悩みをいっぱい抱えていたような気がする。子どもは、大人の想像よりもはるかにひとりの人間として自立している。でも、表面に出てくるものは無垢で自由奔放で可愛いらしい。そのギャップが魅力なんだろうなあと、いつも街や道で出会う子どもたちを眺めている。あの頃の自分を隣に並べながら。
土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある
<目次>
1 人として 佐藤初美(NPO 10代、20代の妊娠SOS新宿キッズ&ファミリー理事長)
2 【インタビュー】いまを語りあう 浜田桂子(絵本作家)
4 はじめの一歩~障害のある人を理解する 船橋秀彦(全障研茨城支部)
6 響け石突き 藤野喜子(日本視覚障害者協議会理事)
7 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)
8 この子と歩む 川波多三紀(大津市)
11 進め! 推し活道 志村大樹(宮城)
特集 防災と地域づくり
13 能登半島地震から半年が過ぎて 宮本典潔(石川・相談支援センターつばさ)
14 福島の震災・原発事故のいま 加賀重哉(全障研福島支部)
16 防災に関する障都連(東京)のとりくみ 垣見尚哉(障都連)
18 大阪の「障害者・家族にとっての防災課題検討会」のとりくみ 雨田信幸(きょうされん大阪支部)
20 熊本地震、その時わが家は 山内美代子(熊本)
21 「災害準備」と地域づくり 新井利民(立正大学)
24 私ときょうだい 村瀬智弘(千葉)
26 発達を見る眼をゆたかに、おおらかに 寺川志奈子(鳥取大学)
30 私に人生と言えるものがあるなら 原田文孝(ささゆり会)
34 シリーズ 保育の現場から みんなのねがい編集部
36 実践にいかす障害と発達 楠 凡之(北九州市立大学)
38 ニュースナビ 旧優生保護法訴訟最高裁判決 佐藤ふき(きょうされん)
40 実践の魅力 間山響子(青森)
43 あそぼう、つくろう 羽地知香(沖縄女子短期大学)
44 みんなのひろば
46 【マンガ】のんびり ぼちぼち 松島明日香・ナガノテツコ
47 BOOK/編集後記
裏表紙 おいしいひととき 阿利澄江(埼玉)
デザイン・イラスト うじたなおき、勝倉大和、永野徹子、橋野桃子、山内若菜
▶ご購読希望は出版部オンラインへ
いざ奈良!
第58回全国大会 奈良2024 情報です 8月9日
〇2024年8月3日、4日と奈良で開催された第58回全国大会は、1500人の参加のもと成功しました。
さまざまなご協力にこころから感謝いたします。
〇全体会、学習講座の「録画配信」は、8月9日~9月30日までおこないます。
参加者には、登録いただいたメールに録画配信のURLなどをお知らせしています。
○奈良大会テーマソング ここからの一步 大好評です
▶特設ページ「奈良大会2024」へ
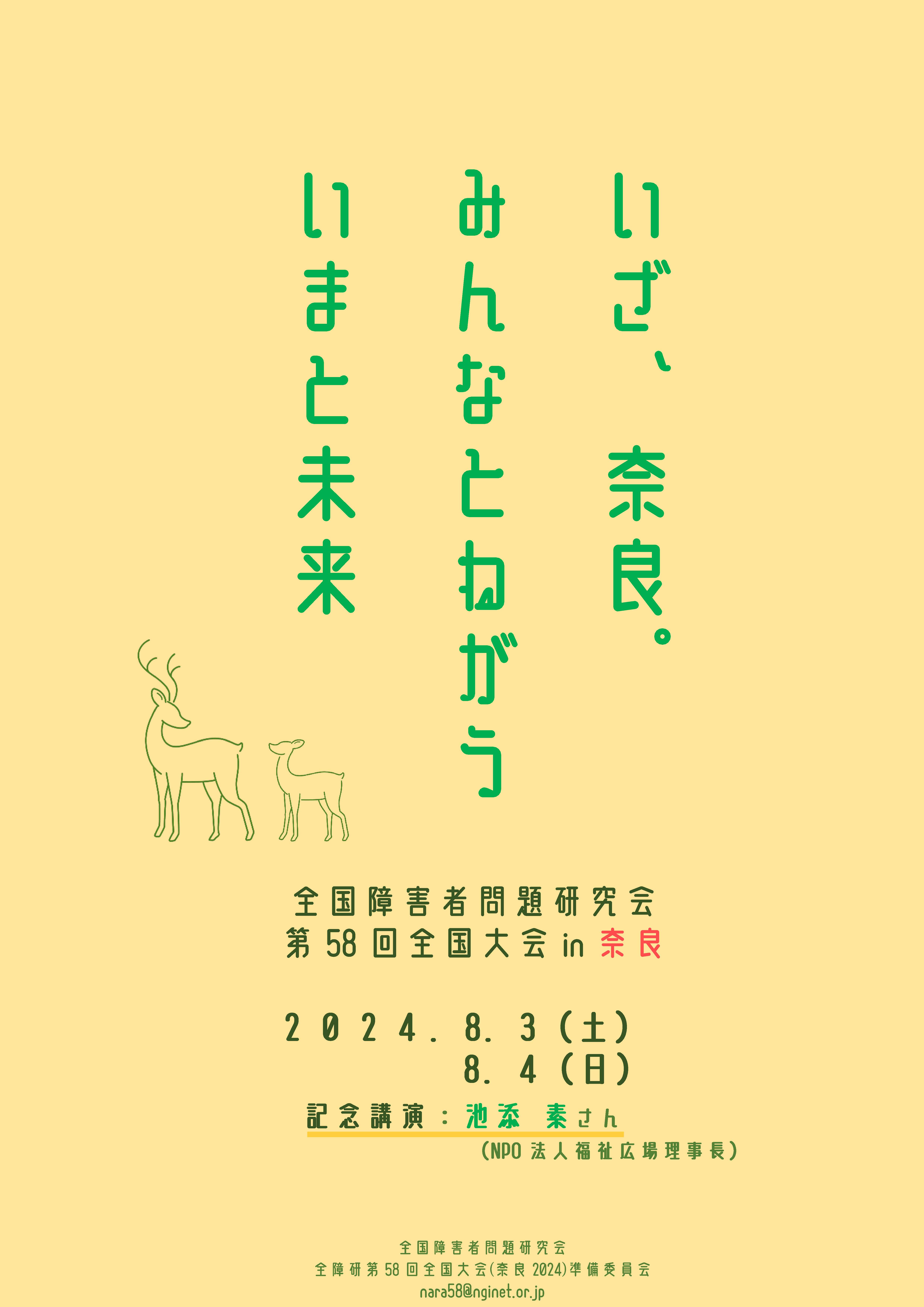
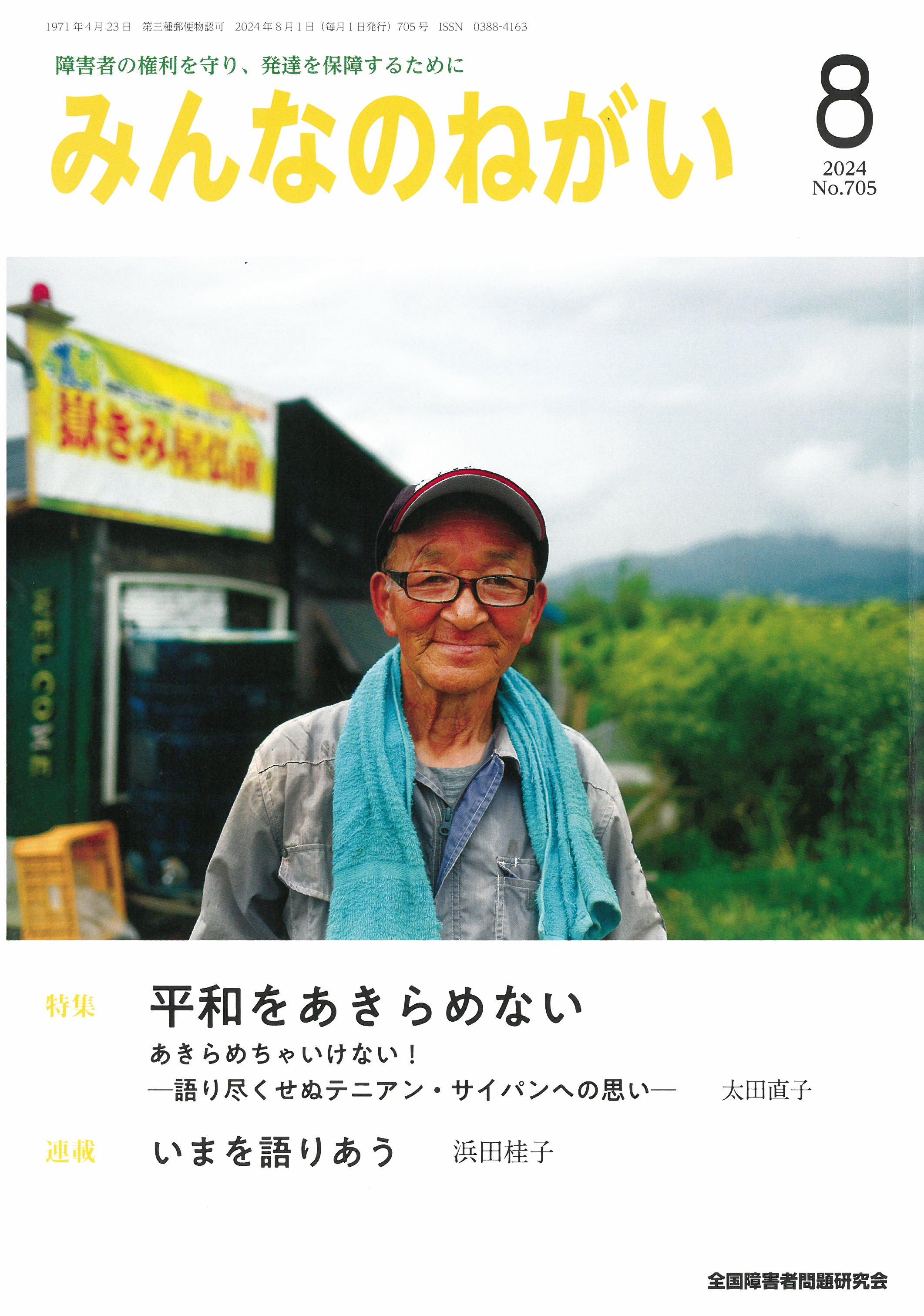
<表紙のことば>
毎年撮影に訪れる、夏の青森。県道沿いの小さな看板に惹かれ、岩木山のふもとにあるお店にたどり着いた。ここは“嶽きみ”というこの地域特産のとうもろこしの直売所。首にタオルをかけた元気なおっちゃんにとりあえずこれ食べてみな、と生の嶽きみを渡され、かじった瞬間驚いた。こんなに甘くてみずみずしいとうもろこしは食べたことがない!しかも生で。その反応におっちゃんは満面の笑みを浮かべた。この時期この場所でしか作れない嶽きみ。この味に仕上げるにはとても手間がかかるそうだ。愛しい津軽弁で語るおっちゃんと日本一甘い嶽きみ。ものづくりへの誇りと生き甲斐がひしひしと伝わってきた。
土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある
<目次>
1 人として 奥田和男(奈良県精神障害者家族連合会)
2 【インタビュー】いまを語りあう 浜田桂子(絵本作家)
4 はじめの一歩~障害のある人を理解する 船橋秀彦(全障研茨城支部)
6 響け石突き 藤野喜子(全日本視覚障害者協議会理事)
7 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)
8 この子と歩む 山﨑理恵(高知市)
11 進め! 推し活道 西田真緒(埼玉)
特集 平和をあきらめない
13 あきらめちゃいけない!―語り尽くせぬテニアン・サイパンへの思い― 太田直子(記録映画制作)
16 [座談会]平和ってどんなこと?(浜田桂子・山中信吾・古澤直子・中村美知子)
20 青年たちと平和公園で学ぶ 長迫 稔(広島 まなびキャンパスひろしま)
22 私と平和
24 私ときょうだい 上西範洋(奈良)
26 発達を見る眼をゆたかに、おおらかに 寺川志奈子(鳥取大学)
30 私に人生と言えるものがあるなら 原田文孝(ささゆり会)
34 シリーズ 保育の現場から 山田真理子(京都 青い空保育園)
36 実践にいかす障害と発達 楠 凡之(北九州市立大学)
38 ニュースナビ 公立特別支援学校教室不足調査 村田信子(全日本教職員組合)
40 実践の魅力 川合 桃(奈良 小学校)
43 あそぼう、つくろう 羽地知香(沖縄女子短期大学)
44 みんなのひろば
46 【マンガ】のんびり ぼちぼち 松島明日香・ナガノテツコ
47 BOOK/編集後記
裏表紙 おいしいひととき 村瀬弘明
デザイン・イラスト
うじたなおき、えむあーる、勝倉大和、永野徹子、橋野桃子、山内若菜
▶ご購読希望は出版部オンラインへ
「障害者問題研究」52巻1号 特集=在宅医療を受ける子どものトータルケア
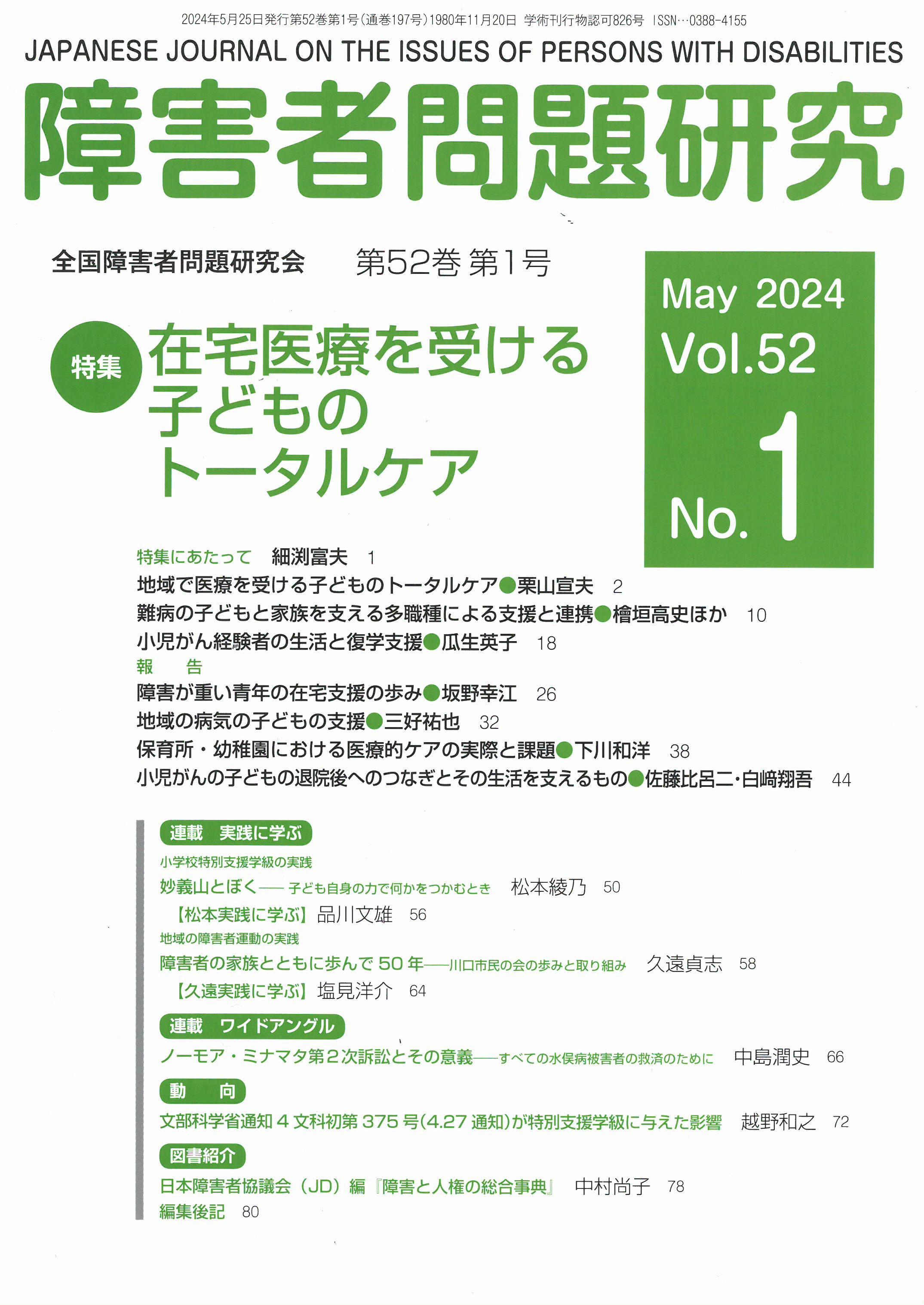
JAPANESE JOURNAL ON THE ISSUES OF PERSONS WITH DISABILTIES
ISBN-984-4-88134-166-7 C3037 定価2750円(本体2500円+税)
特集 在宅医療を受ける子どものトータルケア
特集にあたって/細渕富夫(長野短期大学)
地域で医療を受ける子どものトータルケア
/栗山宣夫(育英短期大学)
本論は,自宅等で医療や医療的ケアを受けている,あるいは通院して医療を受けているなど,地域で医療を受けている子どもの多様性に応じたトータルケアとは何か,どのように検討されるべきであるのかについて示した.トータルケアとは多職種による支援ということに留まらない.「トータル」には子どもを丸ごと受けとめるという意味と,支援者同士が互いに補完し合っていくという意味がある.この「2つのトータル」の見地から事例をあげ,その中で「ニーズの高さ」という言葉が異なった解釈をされている状況も示し,この異なる解釈から生じる問題を克服していくためには他職種とのコーディネートの有無が影響すること等,支援の実現に向けた重要なポイントについて述べた.
難病の子どもと家族を支える多職種による支援と連携 ラ・ファミリエの活動より
/檜垣高史(愛媛大学大学院医学系研究科、NPO法人ラ・ファミリエ)・太田雅明(愛媛大学大学院医学系研究科)・赤澤祐介(愛媛大学大学院医学系研究科)・樫木暢子(愛媛大学大学院教育学研究科)・西朋子(NPO法人ラ・ファミリエ)
「子どもたちが,病気を乗り越えて,成長して発達して,自立していくことは,小児医療をはじめ,小児保健・福祉・教育分野・就労分野の関係者など,子どもに携わるみんなの共通の願いです」.慢性疾病や難病の子どもとその家族を支援するためには,多職種による連携(医療,ソーシャルワーカー,地域資源,心理,教育,経済的支援も含めた就労支援などの連携)が必要である.病気を乗り越えながら,成長・発達して自立していくためには,多くのハードルがあるため,ライフステージに合わせた切れ間のない支援体制を構築して,多領域・多職種・専門職が実質的に連携して,支援の必要性を予測し,専門家として積極的に関わっていくことが重要である.その具現化に向けて,認定NPO法人ラ・ファミリエにおける,小児慢性特定疾病児童等自立支援事業の取り組みの一部を紹介する.ラ・ファミリエに相談すれば何とかなるかも…といわれるような「地域子どものくらし保健室」を目指している.
小児がん経験者の生活と復学支援
/瓜生英子(国立国際医療研究センター病院 小児科)
小児がんでは,疾患自体の特性や治療,長期入院が,治療中のみならず治療後の長期にわたり,小児がん経験者の学習に影響を及ぼすリスクがある.小児がん経験者がスムーズに復学を行えるよう,診断・入院の早期から教育に関する課題に取り組む必要がある.復学できる状況となった場合には,退院前に,がんそのものや治療に伴う身体的合併症や心理状態により,学習・学校生活に影響しうるリスクにはどのようなものが予測されるか,復学支援会議の場で情報を共有し,多職種による支援につなげる.復学には,当事者である小児がん経験者が主体的に課題に向き合うとともに,家族と医療者,院内教育を担当する特別支援学校等と復学後の学校が,治療中から治療後,将来の自立までを見通して長期にわたり連携・協働し支える必要がある.
報告
障害が重い青年の在宅支援の歩み
/理学療法士 坂野幸江(大阪府・訪問看護ステーション非常勤職)
報告
地域の病気の子どもの支援 ネフローゼ患者当事者として支援に携わって
/三好祐也(認定NPO法人ポケットサポート 代表理事)
報告
保育所・幼稚園における医療的ケアの実際と課題
/下川 和洋(特定非営利活動法人 地域ケアさぽーと研究所・理事)
報告
小児がんの子どもの退院後へのつなぎとその生活を支えるもの
/佐藤比呂二(元都立特別支援学校教員、都留文科大学特任教授)・白﨑翔吾(東京都立墨東特別支援学校 いるか分教室OB)
連載/実践に学ぶ
【報告】小学校特別支援学級の実践 妙義山とぼく
子ども自身の力で何かをつかむとき
/松本綾乃(群馬県・安中市立安中小学校 教諭)
【松本実践に学ぶ】子どもの事実から実践をつくる
/品川文雄(元 障害児学級教員)
連載/実践に学ぶ
【報告】地域の障害者運動の実践 障害者の家族とともに歩んで50年
川口市民の会の歩みと取り組み
/久遠貞志(埼玉県・障害者の生活を高める川口市民の会 事務局長)
【久遠実践に学ぶ】地域の障害者運動が育ててきたもの
/塩見洋介(NPO法人 大阪障害者センター)
連載/ワイドアングル 第25回
ノーモア・ミナマタ第2次訴訟とその意義 すべての水俣病被害者の救済のために
/ノーモア・ミナマタ第2次熊本訴訟弁護団 中島潤史(はみんぐ法律事務所 弁護士)
動向
文部科学省通知4文科初第375号(4.27通知)が特別支援学級に与えた影響
第1年次としての2023年統計の検討
/越野和之(奈良教育大学)
図書紹介
日本障害者協議会(JD)編『障害と人権の総合事典』
/中村尚子(NPO法人 発達保障研究センター)
▶ご注文は 全障研出版部オンラインショップへ
▶ 「読む会」情報です
日時 2024年7月11日(木)19:00~21:00/zoomzoomミーティングによる開催
話題提供 小児がんの子どもの退院後へのつなぎとその生活を支えるもの
白﨑翔吾さん(東京都立墨東特別支援学校いるか分教室OB)
佐藤比呂二さん(元 都立特別支援学校教員、都留文科大学特任教授)
参加者の意見交流
参加申込は https://form.run/@shoumonken52-1
参加費無料です。お手元に本号をご用意ください。
全国障害者問題研究会
第58回全国大会(奈良2024)基調報告(案)
常任全国委員会
はじめに
「子どもを産む・産まないは人から勝手に決められることではありません。判決が自分のことを自分で決められる社会につながることを、心から願っています」。
旧優生保護法のもとで障害を理由に不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求めた裁判(以下、優生保護法裁判)を審理した最高裁判所大法廷で原告の一人、北三郎さん(81歳、活動名)はこう訴えました。原告のみなさんは異口同音に、家族や自分が悪いのではない、法律をつくった国に責任があったことがわかって裁判を起こしたのだと来し方を振り返って訴えました。
7月3日最高裁は、旧法と手術は憲法に違反する、不法行為から20年で損害賠償請求権が消える除斥期間を適用するのは「著しく正義・公平の理念に反する」と断じました。まさに歴史的な全面勝訴判決です。問題の本質を社会に広げ、日本社会の人権水準を高め、力にしていきましょう。
障害者の権利を保障する視点で社会を見たとき、改善すべきさまざまな矛盾や課題が明らかになってきます。
その例が災害です。2024年1月1日に発生した能登半島地震は甚大な被害を生み、被災者は現在も多くの困難を抱えた生活を余儀なくされています。いち早く現地支援を開始したきょうされん「能登半島地震」災害対策本部は、高齢化率が5割を超える状況の中、支援が必要なのに、そのニーズが認識されずに孤立状況にある障害者々の実態を報告しています(『みんなのねがい』6月号)。支援者不足のために福祉避難所が開設されなかったという報道もされました。能登半島地震では、現在の日本が抱える高齢化、地域格差などさまざまな矛盾が浮き彫りになりました。
しかし、これまでに各地で発生したさまざまな災害をみると、そこで得られた教訓が国の施策に十分に反映されているとは言えません。東日本大震災から13年が経過しましたが、福島第一原発周辺の「帰宅困難地域」は解消されておらず、故郷に帰れない人々がいます。被災地で生活している人々の声をしっかりと聞き続け、今何ができるのか、被害を最小限に留めるためにどのような備えが必要なのかを考え続けなければなりません。そのためには、国や自治体の行財政のあり方を、生活するすべてのものの安全・安心を保障するものに転換する必要があります。
4月、2024年度の障害福祉サービス等報酬改定が行われました。今次改定の特徴は、成人、児童分野ともに「加算による評価」を前提にした基本報酬引き下げ、成果主義の強化、支援時間による報酬の細分化にあります。これらが重なり合い、すでに年間数百万円もの減額が見込まれるという事業所からの声もあがっています。こうした報酬の特徴は、障害福祉を介護保険制度にさらに近づけようとすることにあります。生きること、生活すること、働くことに対する支援が細切れにされたり、加算が付くかどうかといった観点での支援になったりしてよいわけがありません。状況の改善に向けて、高齢者分野との共同がますます求められており、それはまた、福祉の公的責任を問う運動にもつながっていきます。
2022年9月に国連・障害者権利委員会から日本政府に対して出された障害者権利条約の履行状況に関する「総括所見」は、あらゆる面での「父権主義」と人権保障の遅れを指摘しています。しかし政府は、締約国としての自らの責任を投げ打ち、「総括所見」に対応する法的義務はないと開き直っています。環境省と水俣病患者・当事者団体との懇談会での発言制止問題にみられるように、この国の政府は、そもそも当事者などの声を真摯に受け止める姿勢を欠いています。“私たち抜きに、私たちのことを決めないで”は、障害者権利条約の基本理念であり、政策決定過程に当事者が参加し、その声を行政がしっかりと受け止めていくことの大切さを示しています。「総括所見」の内容をしっかりと読み解き、発達保障の視点から施策の改善を提起していくことが必要です。
そのためにも私たちは、それぞれが抱えている問題を持ち寄り、話し合い、聴き取りあって、それぞれの思いをより合わせ、手を取り合って根本的な課題の解決に向けてともに力を出し合いましょう。
ロシアによるウクライナへの軍事侵攻は3年目を迎えました。イスラエルは世界中の世論の厳しい批判にもかかわらず、ガザ地区での大量虐殺行為を止めていません。戦禍は一般市民に多大なる被害を生むとともに、障害者の生活に甚大な影響を及ぼし、人権を踏みにじります。武力に武力で対抗しようとする考え方では、暴力が暴力を生み出し続ける負の連鎖を断ち切ることはできません。しかし、日本政府は軍事費に2024年度に約8兆円もの支出を計上し、また防衛装備品の輸出ルールを緩和するなど、軍拡の方向に舵を切り、憲法9条の改悪も目論んでいます。障害者を生み出す最大の原因は戦争であることを正面に据えて、今こそ、憲法9条をもつ国から、武力ではなく対話と連帯による安全保障の道を、全世界に発信していく必要があります。
Ⅰ 乳幼児期をめぐる情勢と課題
1)「子どもの権利」を軸に考えよう
保育所では、76年ぶりに保育士一人あたりの子どもの人数が見直され、4・5歳児が30人から25人に、3歳児が20人から15人になりました。「子どもたちにもう1人の保育士を」と声を上げてきた運動の成果です。しかし制度上の改善が、“ゆっくりと待ってあげたいけど余裕がない”という保育現場の悩みの解消にはつながっていません。そもそも発達上の課題をもつ子どもとともにクラスづくりをするにはあまりにも不十分な保育条件です。
そのようななか、保育所・幼稚園において、保育時間中にスポット的に児童発達支援事業所に通うケースも増えてきたという指摘があります。「○○の力をつけてあげたいから」というねがいによるのですが、子どもの生活や集団はどうあるべきか、保育所等と療育機関が考え合うことが必要です。
6月、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が成立しました。「異次元の少子化対策」を具体化する「こども未来戦略」(2023年12月閣議決定)に対応する法改正です。なかでも注目される新事業の一つが「こども誰でも通園制度」。これを推進する人たちは、「同世代の子どもと関わる機会を得て発達を促す」「親の育児負担の軽減や孤独感の解消につなげる」と主張しますが、3歳未満児をスポット的に保育所等に預けることを可能にするこの制度は、安心・安定した関係や環境のもとで生活したいという子どもの要求とはかけ離れています。子どもに関するすべての措置は「子どもの最善の利益」を第一に考慮して行わなければならないという子どもの権利条約にも反するでしょう。社会福祉政策の視点から見ると、公的責任のもとで実施されている保育の分野に自由契約制度を導入することになる点も見過ごせません。
こども基本法施行やこども家庭庁の発足(ともに2023年)以来、そこに子どもの権利条約の記述が盛り込まれたことをもって、子ども施策が前進するとみる世論もあります。しかし「こども未来戦略」は経済・社会システムの維持、持続的な経済成長の達成を前面に押し出しています。子どもがゆたかに発達する権利を保障し、また、保護者が悩みながらも安心して子育てに向かえるようにするという本来的な目的を見失い、労働力対策としての少子化対策に偏重していないでしょうか。
2)言葉にならない思いに応える保育・療育を譲らない
2024年4月、改正児童福祉法が施行されました。今回の改正で、児童発達支援センターの中核機能が法に定められ、努力目標であった地域支援が報酬上で評価されることとなりました。しかし、児童発達支援センターの運営基盤は依然として日額報酬制、応益負担であり、利用契約という保護者に責任を押しつける制度には全く手が付けられていません。子どもが遊ぶこと、保護者の相談にのることにお金がかかる仕組みはそのままです。
今報酬改定に際して、「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」という「5領域との関連性」や、「インクルージョンの観点を踏まえた取組」、「支援提供におけるインクルージョンの視点」を個別支援計画に明記することが求められました。現在示されている「児童発達支援ガイドライン(素案)」では、「発達支援」のなかに5領域の支援の具体的な内容まで例示されています。
子どもたちは、“ほんとうはやりたいんだよなぁ”といった、そっと触れないとはじけてしまいそうな揺らぐ心をもって日々を生きています。その心にゆっくりと時間をかけて寄り添い、向き合ってもらうことで、自分と他者への安心と信頼を育て、外の世界に向かっていくのです。私たちは、言葉にならなくとも、まなざしや身体の微細な動きに表される子どもたちのねがいを要求の表現として大事にしてきました。5領域の具体例として示されるものは、そのような子どもの繊細な能動性を大切にして、子ども自身が発達的な自由を広げていくものではなく、望ましい能力や行動をてっとりばやく形成しようとする狭い発達観をもたらすのではないでしょうか。子どもたちの“やりたい!”がつまった遊び、生活をまるごと捉えた療育が、個別支援計画の「5領域」や「インクルージョンの取組」によって、子どものねがいからかけ離れた実践にならないようにしなくてはいけません。
3)地域で手をつないで共同の輪を
乳幼児期には、出生時から乳幼児健診を経て保育・療育へと連なる、母子保健のネットワークを基盤に、身近な地域の保健師や保育・療育を支える専門職と一緒に、保護者自身の精神的なしんどさ、貧困などの生活苦も見つめつつ、家族を支え、応援していける体制が必要です。近年、多様な療育事業所や在宅サービスが広がり、保護者の就労へのねがいも高まるなかで、親子通園療育をはじめとする必要な支援につながりづらいといった状況も聞かれます。医療機関委託ではない集団健診、気になる時期からの親子教室のねうちをあらためて確認し合いましょう。保護者が一人で悩まずに安心して子育てができるような子育てネットワークも必要です。公的責任のもと、地域の状況に応じて、医療や福祉など多様な分野が連携して今日的な共同のあり方を考えていかなくてはいけません。
各地で就学前の関係者を中心に粘り強く集い、地域、ライフステージをこえた課題を共有する努力が続けられています。深まる矛盾をひとりで、あるいは職場や地域だけで抱えるのではなく、職場・地域をこえて語り合う場があることは貴重です。子どもの要求を大切にした療育と、保護者・家族を支えるネットワークとは何かを考え合い、仲間がいることに勇気をもって日々の仕事に向き合うことができます。“子どもと関わる仕事がしたい”という思いを通して生まれてくる悩みも喜びも、みんなのものにできるような集団的な取り組みが求められています。
今年2月、「発達保障をめざす保育実践・療育実践交流集会」(主催・発達保障研究センター)が開かれ、保育・療育の実践、保育と療育の連携について学び合いました。子どもの発達を保障する地域をつくり、保育・療育をゆたかなものにしていくために、分野をこえて手をつないでいきましょう。
Ⅱ 学齢期をめぐる情勢と課題
1)インクルーシブ教育と発達保障
国連・障害者権利委員会の総括所見は、障害児学校・学級など分離された特別な教育をやめるように要請したと報じられました。全障研は、総括所見が障害児者・家族の権利保障に生かされることをねがって、『障害者権利委員会総括所見とインクルーシブ教育』(2023年8月)を出版、『障害者問題研究』で「障害者権利条約総括所見の焦点と課題」(51巻2号)を特集し、総括所見の理解を深めました。
これらを通して、総括所見は、障害のある子どもへの排除圧力を強め続けている日本の通常学校・学級の現状や、特別支援学級に在籍する子どもの実状をないがしろにして一方的に学ぶ場を規定した文科省通知(2022年4月27日)、18歳以降の障害のある青年・成人の教育を受ける権利の著しい制限など、旧来の差別的な特殊教育の性格が残存した「特別支援教育」が永続化することへの警鐘と批判であることを学びました。インクルーシブ教育の実現を阻む教育条件の貧困さや課題は、通常学校・学級をはじめとして、教育全体に及んでいることを押さえておく必要があります
「障害のある子どもの教育改革提言―インクルーシブな学校づくり・地域づくり―」(2010年3月3日全障研常任委員会)は、「障害のある子どもの教育の改革は、単に特別支援教育の問題でなく、通常の学校教育全体の改革、とりわけ差別と排除がなく学習参加の権利が保障されるインクルーシブな学校づくりと連動」すること、それは「すべての人が安心して暮らし活動できるインクルーシブな地域づくりの一環として展開される」ものであることを指摘しています。この観点を改めて学びなおし、真のインクルーシブ教育について議論を深めていきましょう。
2)子ども、保護者、教師の悲しみ、苦しみ――笑顔あふれる学校を取り戻したい
競争的、管理的、暴力的な教育により、子どもたちのねがいが抑圧され、その結果、いじめや不登校、自殺など、生存権、発達権、教育権が侵害される事態が生じています。保護者は、学校に背を向け、教職員と共同することができない状況に追いつめられています。また、自分の指導力不足を責め、心を病み、休職や退職する教職員が増加の一途をたどっています。
こうした異常な状況の背景には、全国や自治体独自の学力テストをはじめとして、学力至上主義の競争的な教育を推し進めてきたこと、現場の実情に応える教職員定数の改善や、教師に無定量な労働を強いる給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)の是正に背を向け、臨時・非常勤教職員ばかりを増やしてきたこと、学習指導要領改訂を盾に教育内容をこと細かく規定し、教育課程づくりへの管理を強めてきたことなど、行き届いた教育のために必要な条件を整えないまま、管理と統制ばかりを強めてきた政治があります。
特別支援学校では、教室不足が深刻化しています。2023年度の文科省調査では、教室不足数は2年前の調査から381教室減り、3,359教室と報じられましたが、間仕切り教室や倉庫等の転用など、いわゆる「転用教室」にる「一時的な対応」の総数は352ヵ所も増加し、7,476ヵ所に上っています。子どもたちの教育を受ける権利を阻害する「一時的な対応」を教育上「支障がない」と捉える自治体が増え、障害のある子どもたちは劣悪な環境で学ぶことが当たり前、とする価値観が浸透していることが危惧されます。
私たちは、悲しみや苦しみ、しんどさに侵された学校ではなく、子ども、保護者、教職員の笑顔があふれ、希望や夢を語りあうことのできる学校、権利としての障害児教育を取り戻し、真のインクルーシブ教育を実現していきたいと思います。
月刊誌『みんなのねがい』には、今を懸命に生きる人たちが綴ったねがい、一人ひとりが自分や相手の大切さを実感できるようなことばがつまっています。『障害者問題研究』には、障害児者をめぐる情勢の背後に潜む本質的な問題や課題に切り込むための多彩な英知がつまっています。本大会には、子どもたちの人間的な発達へのねがいを見つめ、それにこたえる実践を創造したいと願って綴られたレポートがたくさん寄せられました。障害のある子どもたちの豊かに学ぶ権利を保障するために、私たちに何ができるのか、子どもの姿と実践の事実に学び、考え合っていきましょう。
3)子どもたちの豊かな発達を保障するために――安心と信頼で満ちた放課後を
学齢期の子どもたちは、自分と共通の価値をもつ多彩な仲間とのつながりや、自分にとって真に意味・価値のある世界を発見していくような生活を求めています。
放課後の生活も大切なその一部です。しかし、放課後生活を支える放課後等デイサービスの場は、財政面で不安定な下に置かれ、その結果、子どもの発達・命が脅かされるような事態が生じています。運営の財源となるのは一日単価制の基本報酬です。今回、子どもの支援時間を3つに区分した基本報酬が導入されました。これに障害の状態や時間延長などのさまざまな支援によって「加算」が付くしくみですが、そもそも実践者の仕事や活動にふさわしい単価(報酬)ではありません。また、乳幼児期同様、「健康・生活」、「運動・感覚」など5領域に対応した個別支援計画の様式が示され、子どものねがいから発想する遊びを中心とした活動ではなく、領域に対応した目標を立て、それに応じた指導をする放課後等デイサービスが増加しかねない状況になっています。
子どもたちは、安心感と信頼感で包まれ、多彩な仲間との交流が保障された場だからこそ、豊かな発達の道筋を歩んでいくことができます。低い基本報酬を前提として、見かけだけの専門性を掲げて加算を求めざるを得ない矛盾だらけの制度では、そうした豊かな場は実現できません。
全障研の研究運動から生まれた「障害のある子どもの放課後保障全国連絡会」の実践、運動に学び、子どもも大人も安心できる放課後の場を実現していきましょう。
Ⅲ 成人期をめぐる情勢と課題
1)障害のない人と平等に社会参加ができる社会を
4月、改正障害者差別解消法が施行され、国と自治体だけに課せられていた合理的配慮の提供義務が民間企業などにも適用されました。けれども実施に必要な財政的な裏付けはなく事業者任せです。そもそも、同法が施行された時から、差別の定義や訴える手段などが不明確でしたが、今回も法を生かすための施策は不十分なままです。
社会参加の端緒である移動やアクセスの点では、たとえばJR九州で駅員が配置されず鉄道を使えない事態が生じるなど、社会的障壁が残され、あるいは新たに生み出されています。公共的な施設でもアクセスできないだけでなく、トイレ等が使えない、タッチパネルによる注文や支払いができないなど、障害に対応すべき改善課題はあらゆるところにあります。それを訴えたくても、訴えるしくみそのものも整備されていません。インターネット上の匿名掲示板では、当事者の声に対する「わがまま」「めいわく」などの声もあります。格差と貧困が社会に広がる中で、障害者の声を拒み、受けとめない分断も強まっていきます。
2)支援者の不足は働くこと・暮らすことの破壊
労働人口が減少し、福祉の仕事を選ぶ人たちが減っています。地域において生活を支えられない事態が起こっています。保育・療育、介護などの仕事に携わる人たちの不足は深刻で、高齢分野では2025年には介護人材の需要が約253万人見込まれるのに対して、供給は約215.2万人にとどまるといわれています。障害分野、保育分野も同様で、求人に対して応募がありません。そのうえ離職率も高く定着率が低いままです。公的なハローワークを介した求人では職員を得られず、欠員を埋める必要から派遣会社を使うと、本来、障害者のために使われる税金の一部が派遣会社に流れることになります。
職員不足の原因は、まず賃金や労働時間などの条件が悪いことにあります。賃金の面では他職種に比して8万円以上も低賃金です。夜勤などもある過酷な労働条件もあります。加えて、障害分野の仕事に就いた人に、どんな支援をすればいいのか、仕事の中核となることがらを伝えようにも、マニュアルに頼ることができない仕事です。強度行動障害や愛着依存行動への対応などには、高い専門性が必要ですが、ゆとりのない職場では、学び合いができない状況もあります。常勤換算方式による職員配置のしくみの下で、限られた時間内で働くパート職員も多く、話し合いもできません。
言葉がなく障害の重い人の激しい行動を止めようとして「虐待が生じる」という事態も多発しています。虐待防止研修の実施や身体拘束減算による「締め付け」だけでは適切な支援にならないことは明らかです。
職員が退職し未充足となった結果、入所施設との契約が打ち切られた事例も出ています。ヘルパー不足は余暇支援を制限することにもつながっています。家族のレスパイトのためのショートステイも同様です。「健康で文化的な最低限度の生活」そのものが成り立たなくなっています。
3)障害者支援事業そのものを揺るがす報酬制度
2024年度からの新報酬は、支援提供時間、利用者の障害支援区分、支援者の資格条件を組み合わせた、より複雑で細分化されものとなりました。就労継続支援B型などは、さらに利用者の工賃で報酬単価が決められます。加えて、「食事提供」、「医療連携」、「強度行動障害」、「地域連携」などを実施した場合には、様々な要件をクリアした上で加算請求ができることになります。職員の賃金保障と事業の維持のために少しでも収入を増やそうと、施設の管理者は必死に検討しています。
今回の報酬改定の複雑さは、行政職員も困らせています。事業者から加算要件などの問い合わせがあっても応えられないほどで、たとえば「強度行動障害支援加算」もそのための「研修を受けた支援員がマニュアルどおりに支援」していれば加算の対象となるといった程度の答えしか返ってこない自治体もありました。
営利企業運営の不正もあとを絶ちません。株式会社が全国展開で運営するグループホームで食材費の不正が露見して事業停止措置となった事件もありました。停止となると入居者たちの生活はまったく保障されません。就労継続支援B型などで利用者の出勤不正の報告などもあり、貧困ビジネスがからむ不正が続いています。報酬さえ入れば企業は成り立ちます。行政の監査も人手不足と専門職不足で是正が追いついていない背景もあります。市場化、競争化を徹底的に推し進めようとするこの間の制度改革がこうした現実を生んだことは明らかです。
4)過度な家族負担の解消と暮らしの場づくり
自己責任、家族責任という圧力が強まる中で、重い知的障害、自閉スペクトラム症、医療的ケア、重い身体機能の不全などの課題がある人たちへの家族によるケア、特に女性である母親への加重な負担が問題になっています。「80-50問題」とも言われ、親が高齢化した時の双方のケアの課題は深刻です。戦後の入所施設一辺倒の政策の結果、大規模で生活の場とは言えない施設が多く存在しますが、こうした入所施設でもたくさんの待機者がいます。しかし行政は、その実態すら把握していません。
解決のためには、入所施設、グループホームなど形態は異なっても、暮らしの場そのものを増やしていくことと、そこでの暮らしの質を高めること、そのための財政保障を伴った条件整備が連動し、一貫性をもって進められる必要があります。
家族との暮らしが継続する場合であっても、慣れた通所施設にそのまま通えること、相談も含め活用できる緊急のショートステイ事業など、多面的なサービスを早急に充実することが不可欠です。青年期以降の親ばなれ子ばなれという自立の課題も見据えた支援実践と実践を支える制度が必要です。
Ⅳ 研究運動の課題
1)すべての人の命と暮らしが守られる社会を求めて
気候変動の深刻さは、水や食料の確保の困難に直結しており、暮らしの前提が脅かされています。円安・物価高騰が進行する中で、実質賃金が低下し、私たちの生活を直撃しています。障害者やその家族には特に影響が大きく、各地の事業所運営にも深刻な困難をもたらしています。日々の生活を成り立たせていくことそのものが大変、という状況です。しかし、こうした状況だからこそ、きびしい情勢に圧倒され、流されてしまわず、私たちが大事にしてきた、障害者の権利保障を軸においた研究運動が求められています。
これまで述べたライフステージごとの課題を、障害者権利条約の基本である「他の者との平等」、すなわち障害のない人とあらゆる面で自分らしく生きるために必要な課題としてとらえると、検討すべきテーマがさまざまに浮かび上がってきます。身近なところから語り合い、学習と研究をすすめていきましょう。
2)ひとりのねがい、みんなのねがいを基盤に、一生を通じた権利保障を求めよう
こども基本法が施行され、こども家庭庁が発足しました。子どもの権利尊重がうたわれていても、それが自己責任や家庭依存を前提にしたものでないか、注意深く分析する必要があります。子どもを、さまざまな能力や特性などの観点でバラバラにとらえ、個別の能力を伸ばそうとするような保育や教育ではなく、子ども時代にふさわしい学び、遊び、集団への参加を保障し、子どもらしいゆたかな生活の中で発達へのエネルギーを蓄え、膨らませていけるように訴えていく必要があります。
一人ひとりのねがいや思いを深く読み解くことよりも、決まりを守らせることを重視する教育が進行しています。そうした傾向はパンデミックによる学校一斉休校を経ていっそう強化されていないでしょうか。大人も、自分で考えずに決められた通りやる方が効率がよい、と流されていないでしょうか。私たちは、一人ひとりの疑問、ねがいを大切に、そこからみんなで議論し学習を深め、声にしていくことを大事にしてきました。一見マイナスに見える言動でも、その深い意味を考えるなかで、発達的共感が広がっていきます。『みんなのねがい』の本年6月号では、うその発達的な意味、文化を共に学ぶことの意味などが深められています。「〇〇の力がつきました」と簡単にまとめることのできない、けれど人間の発達にとって大事な日々の取り組みを、私たちは語り合っていく必要があります。
青年・成人・高齢期と、人生を積み重ねていく中で、差別と排除の何層もの困難に直面していく社会ではなく、憲法前文に示されている「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利」がいっそう保障されるような社会への転換を求めていきましょう。張貞京さんは、もみじ・あざみ寮の実践を描く中で、高齢期を生きる障害者の発達に光をあてています(『高齢期を生きる障害のある人 ―人とつむぎ、織りなす日々のなかで―』全障研出版部)。単純に何かができるようになるという発達観ではなく、発達を、自分自身の変化、環境の変化の中で、関わり方やつき合い方を新たにし、意味づけ直していく過程としてとらえること。そして、一人ひとりの発達保障に取り組む中で、周りの人が発達していく契機になることを訴えています。安心して暮らし、文化を味わい、みんなで集まり、仕事をし、選挙に行き、家族だけで抱え込まずにケアし、ケアされる権利が保障されるような社会への展望を語り合いましょう。
3)学び、運動する輪を広げよう――職場で、地域で、全国で
困難な中でも、障害がある人によりそう職員、仲間がいます。社会の大きな希望です。教育・福祉の現場では、教員・職員の確保が難しい状況が続いており、最低限の仕事を「こなし、まわす」ことに意識が向きがちです。しかし、そんな時こそ、何に価値をおいて仕事をするのかを考え、学び、語り合うことが必要です。ピンチはチャンス! 働く仲間の集団をつくり、「こんなのおかしい」と疑問を出しあい、発達保障についての学習を積み重ねていきましょう。実践記録を読むこと、書くことは、そのための大きな力になります。
地域の暮らしと問題にねざした研究運動を支える軸となるのは、支部活動です。パンデミックの期間にも私たちは、ハイブリッドでの学習会、ゆるやかに話す「ゆるカフェ」、会員限定でじっくり話し合う相談会など、さまざまな取り組みを展開してきました。郵送費高騰、支部事務局の多忙化の中でも行われている工夫について、ぜひ交流していきましょう。
『みんなのねがい』の「読む会」も広がっています。みんなで読むと新しい発見があり、記事をきっかけに自分の話ができて、盛り上がることがたくさんあります。『障害者問題研究』の「読む会」は、内容が難しい…と思っている人も深く学べるよう、執筆者が分かりやすく話してくれます。どちらも、読み終わる前でも参加でき、深めることができます。教育と保育のための発達診断セミナー、発達保障のための相談活動を広げる学習講演会は、発達の権利を保障するための診断・相談・実践について、具体例をふまえながら学べます。これらはすべてオンラインで参加できます。
そして、夏の全国大会、春の発達保障研究集会。顔をあわせてじっくり語りあえる貴重なチャンスです。職場や支部で語られた実践を、ぜひレポートにまとめて、全国の仲間にも広げて下さい。障害者権利条約や総括所見を生かした権利保障について、しっかりと研究し、運動を進めていきましょう。
*全国大会基調報告案へのご意見は、7月25日までに、電子メールかFAXで必ず文書で全国事務局にお寄せください。
電子メール info@nginet.or.jp FAX 03-5285-2603
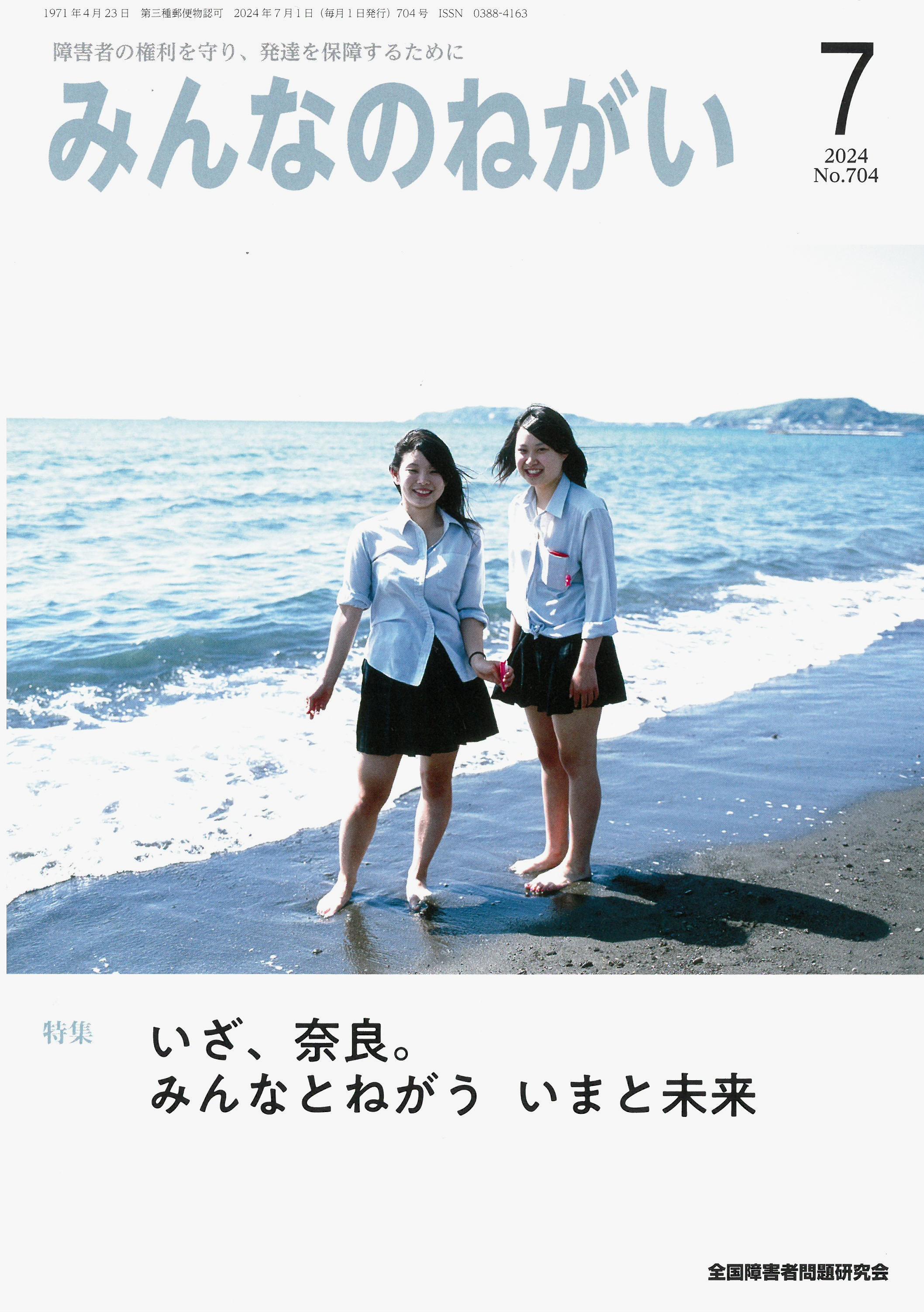
<表紙のことば>
カメラを持って地方を歩いていると、たまらなくキュンと胸打つシーンに出くわすことがある。
誰もいない初夏の海岸で遊ぶ女学生。置きっぱなしの鞄と靴。
裸足で走ったり、写真を撮ったり、砂浜に絵を描いたり。
人生のなかで一番キラキラと輝く時間ではないだろうか。
駆け寄って写真を撮らせてもらうと、少し照れながらもこの状況がエモい、と楽しそうだ。
僕もまるでクラスメイトになった気分でレンズを向ける。
きっと、昔からずっとずっと変わらないこの光景、
青春だった。
土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある
<目次>
1 人として 島田尚志(奈良県視覚障害者の生活を守る会)
2 【インタビュー】いまを語りあう 浜田桂子(絵本作家)
4 はじめの一歩~障害のある人を理解する 細野浩一(全障研埼玉支部)
6 みのりある話 加藤みのり
7 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)
8 この子と歩む 玉腰梨絵(奈良県大和郡山市)
11 進め! 推し活道 澤田 純(奈良)
特集 いざ奈良。みんなとねがう いまと未来
12 全障研大会ってこんな感じです!
14 いざ、奈良。 みんなとねがう いまと未来 池田 翼・中筋達也・秋光平天下
16 大会グッズ いざならへ! 杉本 圭
17 全障研出版部5年ぶりの書籍販売です
18 微力かもしれないが、無力ではない 池添 素
19 学びがいっぱい 学習講座 富井奈菜実・山口 歩
20 分科会で会いましょう
22 わたし流の全国大会の楽しみ方
24 私ときょうだい 幸田みのり(広島)
26 発達を見る眼をゆたかに、おおらかに 寺川志奈子(鳥取大学)
30 私に人生と言えるものがあるなら 原田文孝(ささゆり会)
34 シリーズ 保育の現場から 福野千穂(神奈川 梶原の森たんぽぽ保育園)
36 実践にいかす障害と発達 楠 凡之(北九州市立大学)
38 ニュースナビ 「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟 加藤丈晴(弁護士)
40 実践の魅力 萩原君江(茨城 シャンティつくば)
43 あそぼう、つくろう 五島丸太(まるたせんせ)
44 みんなのひろば
46 【マンガ】のんびり ぼちぼち 松島明日香・ナガノテツコ
47 BOOK/編集後記
裏表紙 おいしいひととき 中野雅哉(奈良)
デザイン・イラスト
うじたなおき、えむあーる、勝倉大和、永野徹子、橋野桃子、山内若菜
▶ご購読希望は出版部オンラインへ
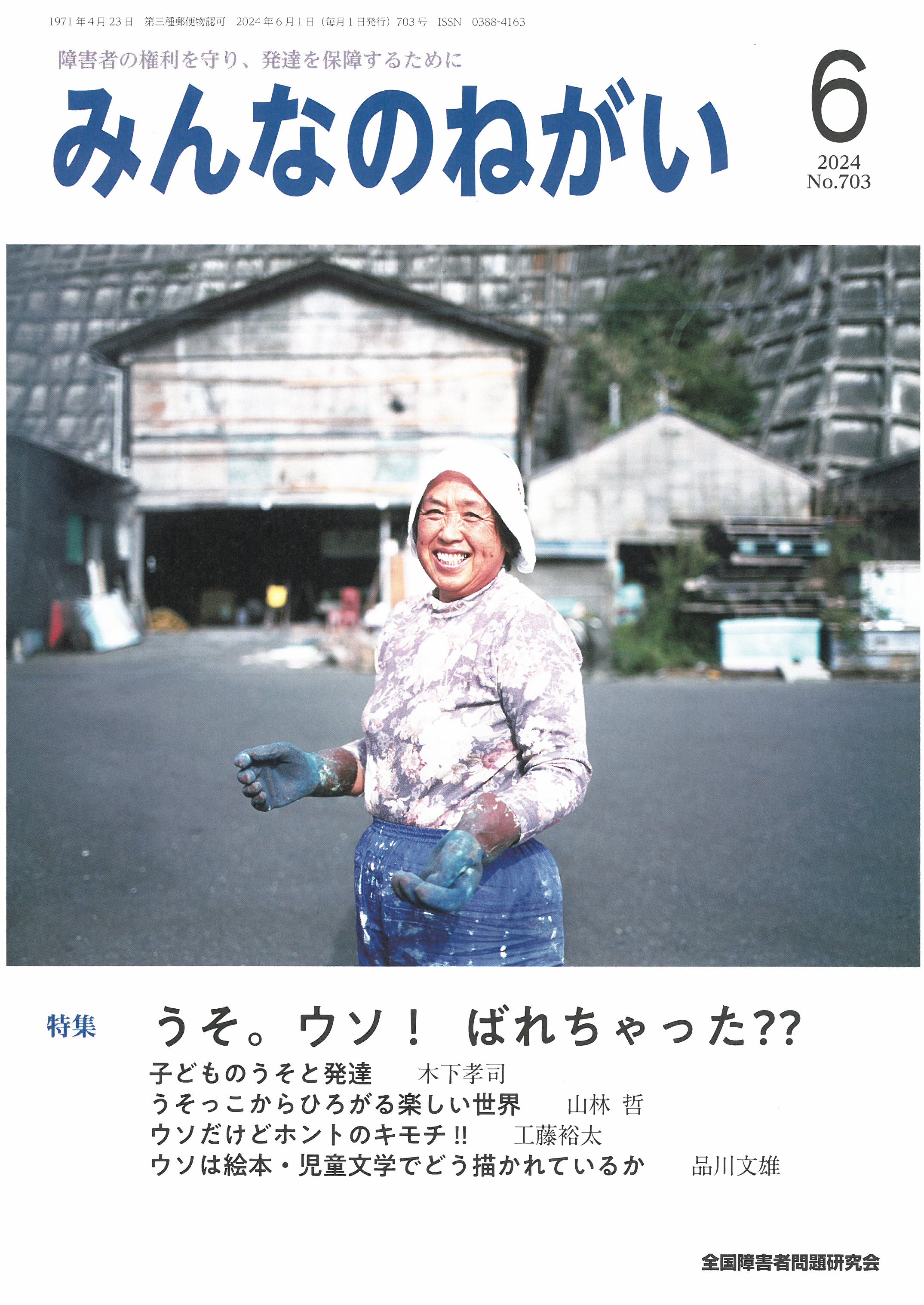
<表紙のことば>
木造りの船小屋の前でペンキまみれの女性は満面の笑みを浮かべた。東日本大震災から数年経った頃、ふらっと立ち寄った千葉県外房の小さな漁港で船作りをする夫婦に出会った。聞くと、二人で一年かけてコツコツと作り上げてきた漁船が先ほど完成したそうだ。このあと出港、被災地であるいわき市の漁師の元へ向かうと。こんな記念すべき瞬間に立ち会えた感動と、被災地が復興へ動き出している嬉しさをしみじみ感じたことを思い出す。ちなみにシャイな主人はツーショットを撮らせてくれなかった。行先での一期一会の出会いに、いつも僕は人生の糧をもらっている。そして写真は出会うための最高の方法だ。
土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある
<目次>
1 人として/ダニー・ネフセタイ(木製家具作家、反戦・人権活動家)
2 【インタビュー】いまを語りあう/浜田桂子(絵本作家)
4 はじめの一歩~障害のある人を理解する/細野浩一(全障研埼玉支部)
6 みのりある話/加藤みのり(岐阜)
7 心に種をまく/安田菜津紀(DfP副代表・フォトジャーナリスト)
8 この子と歩む/高木智子(広島市)
11 進め! 推し活道/中村水生(神奈川)
特集 うそ。ウソ!ばれちゃった??
12 うそ、いろいろ(編集部)
14 うそっこからひろがる楽しい世界/山林 哲(大阪市小学校)
16 ウソだけどホントのキモチ!!/工藤裕太(愛知児童デイ)
18 ウソは絵本・児童文学でどう描かれているか/品川文雄(発達保障センター元理事長)
20 子どものうそと発達/木下孝司(神戸大学)
24 私ときょうだい/高原千夏(大阪)
26 発達を見る眼をゆたかに、おおらかに/寺川志奈子(鳥取大学)
30 私に人生と言えるものがあるなら/原田文孝(NPO法人ささゆり)
34 シリーズ 保育の現場から/増元花菜(大阪 みどり保育園)
36 実践にいかす障害と発達/楠 凡之(北九州市立大学)
38 ニュースナビ 能登半島地震/大野健志(きょうされん「能登半島地震」災害対策本部事務局長)
40 実践の魅力/市原真理(京都 児童発達支援)
43 あそぼう、つくろう/五島丸太(常磐会学園大学)
44 みんなのひろば
46 【マンガ】のんびり ぼちぼち 松島明日香(滋賀大学)・ナガノテツコ(
47 BOOK/編集後記
裏表紙 おいしいひととき 南家孝之
デザイン・イラスト うじたなおき、勝倉大和、永野徹子、橋野桃子、山内若菜
▶ご購読希望は出版部オンラインへ

<表紙のことば>
房総の海沿いの街で昔ながらの小さな時計店に出会う。店内には年季の入った時計や眼鏡や雑貨などが沢山置かれ、店主のおばあちゃんは微笑みながら嬉しそうに商品を見せてくれた。そこに僕の欲しい物は無かったけど、なんだかとてもあったかくて優しい時間を過ごせた。元々お店って、商品を売買するだけじゃなく大切なコミュニケーションの場所だった気がする。近況報告や世間話をしたりして、生活の中での楽しみや人との繋がりをそこで感じていたんだと思う。いまや入店して会計まで誰とも出会わずに買い物や食事ができる。でも、便利さやタイパの追求では決して得られない満足感や幸せがきっとある。
土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある
<目次>
1 人として 志水克典(岡山県 視覚障害者友の会事務局長)
2 【インタビュー】いまを語りあう 浜田桂子(絵本作家)
4 はじめの一歩~障害のある人を理解する 細野浩一(全障研埼玉支部)
6 みのりある話 加藤みのり(岐阜)
7 心に種をまく 安田菜津紀(フォトジャーナリスト)
8 この子と歩む 小林洋子(長野県上伊那郡)
11 進め! 推し活道 寸田純子(岐阜)
特集 「強度行動障害」を考える
12 強度行動障害のある人の理解と支援 別府 哲(岐阜大学)
16 大切なひとり 和田泰代(滋賀)
18 強度行動障害といわれる子と出会い、教えてもらったこと 和田美果(京都)
20 アカネさんの気持ちのよりどころになった「作業」 藤田紀子(愛知・さくらんぼの会)
22 Kさんはどう生きたかったのか 小寺直人(埼玉・みぬま福祉会)
24 私ときょうだい 原 哲治(岐阜)
26 発達を見る眼をゆたかに、おおらかに 寺川志奈子(鳥取大学)
30 私に人生と言えるものがあるなら 原田文孝(NPOささゆり会)
34 シリーズ 保育の現場から 木原千栄(愛媛・朝日保育園)
36 実践にいかす障害と発達 楠 凡之(北九州市立大学)
38 ニュースナビ 2024年度障害児通所支援報酬の特徴 中村尚子(発達保障研究センター)
40 実践の魅力 松本一色(東京・特別支援学校)
43 あそぼう、つくろう 北村直子(奈良教育大学付属小学校)
44 みんなのひろば
46 【マンガ】のんびり ぼちぼち 松島明日香(滋賀大学)・ナガノテツコ(作画)
47 BOOK/編集後記
裏表紙 おいしいひととき 浦野明美(兵庫)
デザイン・イラスト うじたなおき、勝倉大和、永野徹子、橋野桃子、山内若菜
▶ご購読希望は出版部オンラインへ
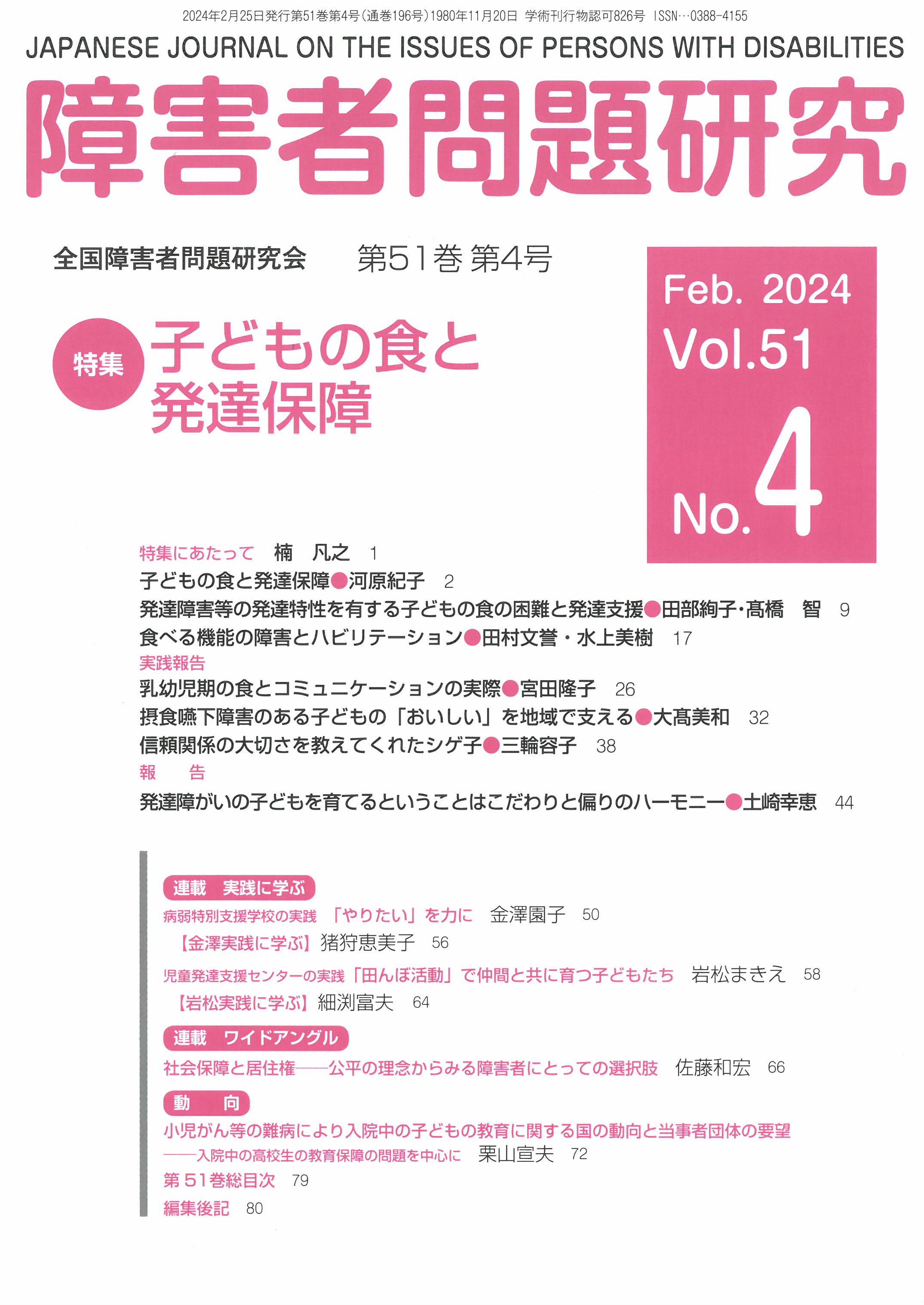
JAPANESE JOURNAL ON THE ISSUES OF PERSONS WITH DISABILTIES
2024年2月25日発行 ISBN-984-4-88134-156-8 C3037 定価2750円(本体2500円+税)
特集 子どもの食と発達保障
特集にあたって/楠 凡之(北九州市立大学)
子どもの食と発達保障/河原 紀子(共立女子大学家政学部)
本稿では,はじめに子どもの食の発達に関する国内外の動向を概観し,乳幼児期の食行動の中でも,好き嫌いの特徴とその発達的変化に焦点を当てて検討した.次に,好き嫌いとの関連で新奇性恐怖と味覚について考察し,さらに食事場面でのやりとりに見られる自我の特徴について発達的に検討した.最後に,子どもの食の発達を保障する課題について
の提案を試みた.
発達障害等の発達特性を有する子どもの食の困難と発達支援/田部 絢子(金沢大学人間社会研究域学校教育系)・髙橋 智(日本大学文理学部教育学科)
本稿では発達障害等の発達特性を有する子どもの食の困難の動向と発達支援のあり方を検討してきた.第一に,食物選択性(偏食)の背景にある発達障害当事者が抱える「不安・緊張・恐怖・ストレス」等を丁寧に検討し,食における「安心・安全・信頼」を構築していくことが不可欠である.第二に,食の困難を有する発達障害当事者がどのような支援を求めているのかについて,丁寧に傾聴することが最適なアプローチになる.第三に,食の困難を抱える当事者・保護者・家庭を孤立させずにエンパワメントしながら支えていくシステムの構築である.具体的には,子どもの食の困難と発達支援に関わる管理栄養士,栄養教諭,保健師,小児科医師,歯科医師,歯科衛生士,言語聴覚士,教師,保育士等の専門家が協働していく発達支援システムの構築が不可欠である.
食べる機能の障害とハビリテーション/田村 文誉・水上 美樹(日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック)
ヒトは生まれるとすぐに哺乳機能によって栄養を摂取する.その後大脳の発達とともに摂食機能を獲得していく.障害児では食べる機能に遅れや障害があることも多く,摂食指導が必要となる.小児の摂食嚥下障害は,成人とは異なりハビリテーションの考え方が重要となる.障害児では感覚過敏があることも多く,感覚の異常は食べる機能に影響を及ぼす.摂食嚥下機能の評価では,外部観察評価が重要である.評価に基づき行われる摂食指導では,食環境指導,食内容指導,摂食機能訓練を行う.食べることは個別性が大きく,個人個人に応じた支援が重要である.
実践報告
乳幼児期の食とコミュニケーションの実際/宮田 隆子(京都府・社会福祉法人樹々福祉会 朱い実保育園 管理栄養士)
実践報告
摂食嚥下障害のある子どもの「おいしい」を地域で支える 通所支援事業所での取り組み/大髙 美和(東京都日野市・NPO法人ゆめのめ理事長・管理栄養士)
実践報告
信頼関係の大切さを教えてくれたシゲ子/三輪 容子(福岡県・特別支援学校)
報告
発達障がいの子どもを育てるということはこだわりと偏りのハーモニー/土崎 幸恵(東京都東村山市・NPO法人すくすくはあと理事、保護者)
連載/実践に学ぶ
【報告】病弱特別支援学校の実践 「やりたい」を力に/金澤 園子(神奈川県・病弱特別支援学校)
【金澤実践に学ぶ】
入院中の子どもの自分づくりを支える 学びと人と関わる力をゆたかに/猪狩恵美子
連載/実践に学ぶ
【報告】児童発達支援センターの実践 「田んぼ活動」で仲間と共に育つ子どもたち/岩松 まきえ(鹿児島県・社会福祉法人麦の芽福祉会 むぎのめ子ども発達支援センターりんく)
【岩松実践に学ぶ】
なかまと共に,期待を育む生活の創造/細渕 富夫(まつもと幼稚園)
連載/ワイドアングル 第24回
社会保障と居住権 公平の理念からみる障害者にとっての選択肢/佐藤 和宏(高崎経済大学地域政策学部)
動向
小児がん等の難病により入院中の子どもの教育に関する国の動向と当事者団体の要望 入院中の高校生の教育保障の問題を中心に/栗山 宣夫(育成短期大学)
第51巻総目次
▶ご注文は 全障研出版部オンラインショップへ
▶ 「読む会」情報 2024年4月12日(金)19時~21時 /ZOOM
話題提供
子どもの食と発達保障 河原紀子さん(共立女子大学)
嚥下障害のある子どもの「おいしい」を地域で支える 大髙美和さん(NPO法人ゆめのめ)
参加者の意見交流
▶詳細案内はこちらをクリックしてください
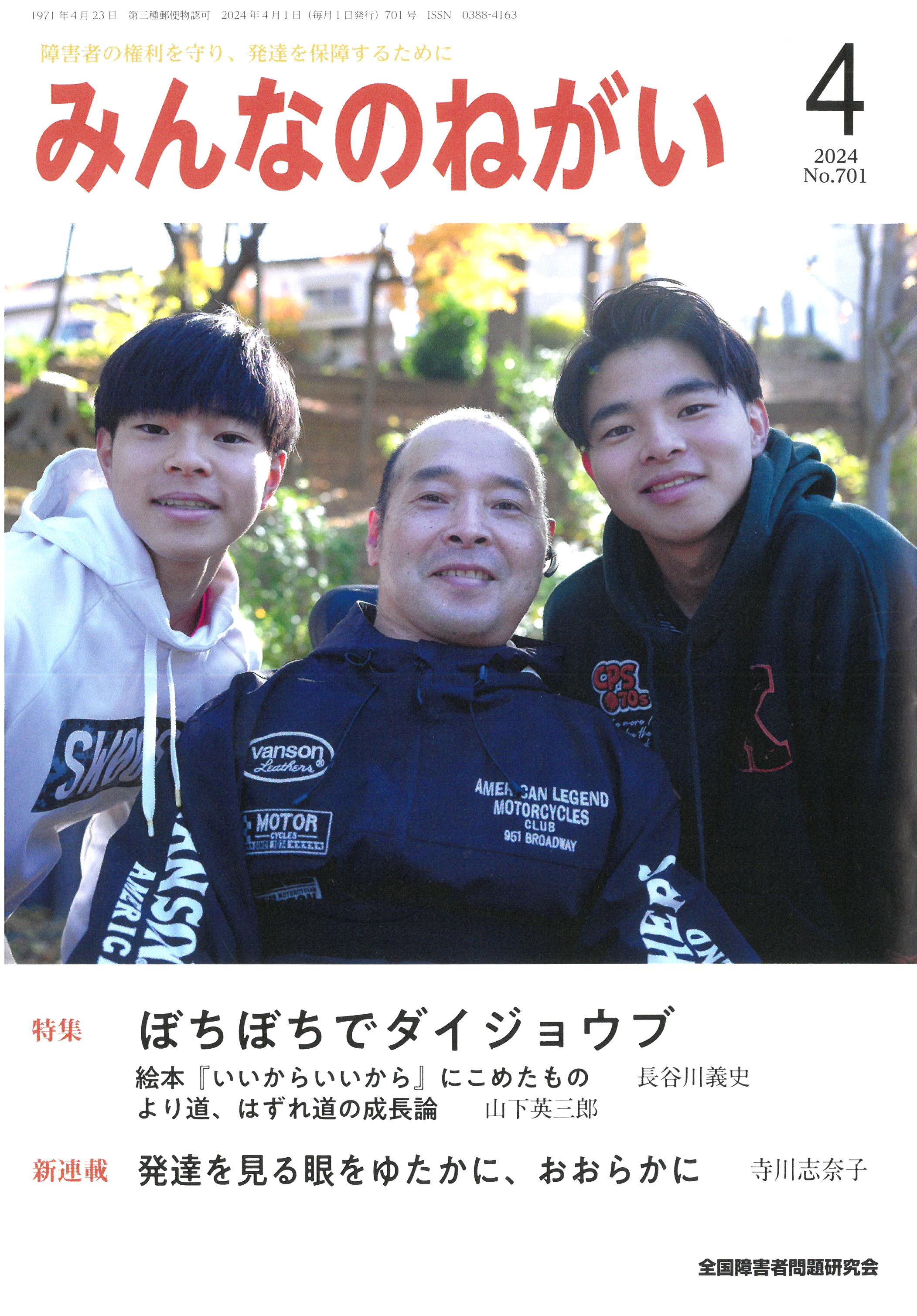
<表紙のことば>
15歳の時に頸髄損傷で障害を持ち、その中で結婚、子育てをしてきた家平悟さんの自宅を訪れた。滞在中、終始笑顔が絶えない温かい雰囲気。しかしサポート時はとてもシビアだった。家族が慎重に丁寧に車椅子を支える姿には怠惰さや雑さは微塵も無かった。そして思った。父親は身体的なサポートは必要だけど、人としての強さを身をもって家族に示しているんじゃないか。それを汲み取って日々の経験の中で子どもは強く優しく成長している。きっとそれぞれに葛藤や衝突もある。でもそれを温かく中和してきた母親がいて。それが、支え合うということ。そんなことを想像しながら、僕も自分の家族を想った。
土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある
<目次>
1 人として 四谷姉妹
2 【インタビュー】いまを語りあう 浜田桂子
4 はじめの一歩~障害のある人を理解する 細野浩一
6 みのりある話 加藤みのり
7 心に種をまく 安田菜津紀
8 この子と歩む 不破世界
11 進め! 推し活道 澤佐景子
特集 ぼちぼちでダイジョウブ
12 絵本『いいからいいから』にこめたもの 長谷川義史
14 苦しくて涙が出ても、きっと笑顔になれるよ 近藤直子
16 春休みの内緒のはなし 山口 歩
17 わが家の〝太陽(お日様)〟 本田 東
18 受けとめられる安心感のなかで私たちは自分らしさを発揮できる 岡田徹也
19 宿題とテキトーに付き合う 丸山啓史
20 ぼちぼち子育て 赤木和重
21 より道、はずれ道の成長論 山下英三郎
24 私ときょうだい 岩谷 亮
26 発達を見る眼をゆたかに、おおらかに 寺川志奈子
30 私に人生と言えるものがあるなら 原田文孝
34 シリーズ 保育の現場から 飯田のぞみ
36 実践にいかす障害と発達 楠 凡之
38 ニュースナビ 子どもの権利を保障する放課後活動 郡 奈美
40 実践の魅力 金田一仁志
43 あそぼう、つくろう 猪澤由起子
44 みんなのひろば
46 【マンガ】のんびり ぼちぼち 松島明日香・永野徹子
47 BOOK/編集後記
裏表紙 おいしいひととき 坂元悠人
デザイン・イラスト うじたなおき、勝倉大和、永野徹子、橋野桃子、山内若菜
▶ご購読希望は出版部オンラインへ
2024年3月 白石正久・白石恵理子
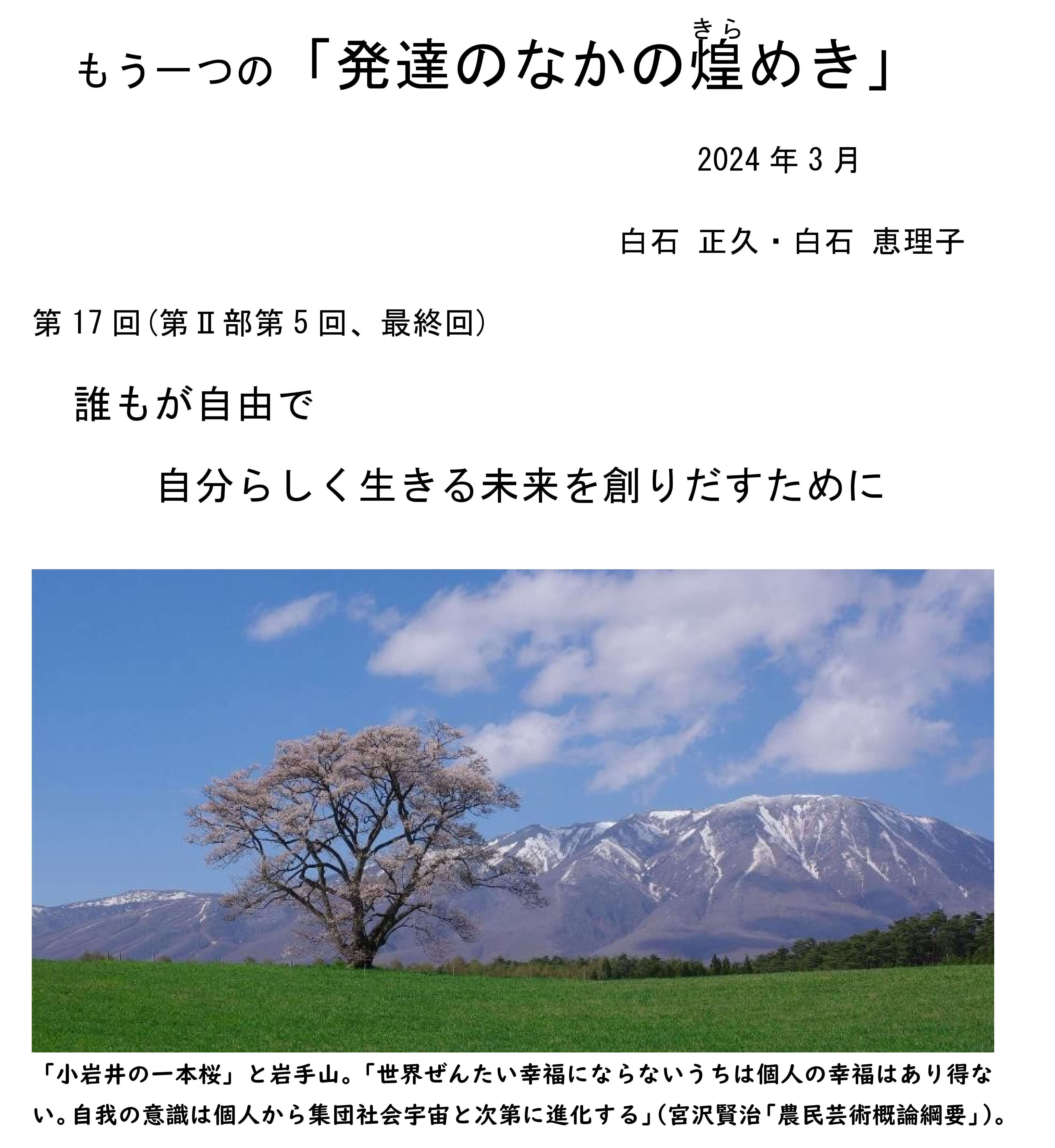
2年間つづけてきた連載「発達のなかの煌めき」は、3月号で無事、最終回となりました。この2年間、お読みくださった皆さん、ご感想・ご意見をお寄せくださった皆さん、「執筆者交流会」にご参加くださった皆さん、そして、地域や職場で「読む会」をつづけてくださった皆さんに心より感謝いたします。この「もう一つの『発達のなかの煌めき』」(以下では「もう一つ」)も今回で最後となります。
最終回ということで、さてさて何を書きましょうか、という話になったわけですが、タイトルである「発達のなかの煌めき」に込めた思いをもう一歩、掘りさげてみたいと考えました。今思えば、この連載を通して、私たちが自分自身に課した課題でもあったのだと思います。それは、一言でいえば、人間の発達をとらえることが、これからの未来社会を創りだす力にどうつながっていくのかということです。
唯物弁証法について
連載の1年目(第Ⅰ部 障害のある子ども・なかまの発達)では、それぞれの発達の時期で努力しつづけている子どもたち・なかまたち一人ひとりのことを想起しながら(ときには、出会ったときには十分に見取ることのできなかった自分の目の貧しさに、情けなさと申し訳なさを感じながら)、発達とは何かを考えてきました。
私たちは学生時代に、田中昌人さんから発達について、「可逆操作の高次化における階層-段階理論」を通して学んできました。それは、ゲゼルやピアジェらによる発達心理学の先行知見をふまえつつ、弁証法的発展のプロセスとしてとらえなおしたものでした。若い私たちにとって、「発達」も「弁証法」も難解きわまりないものでしたが(もちろん、今もそうですが)、でも何か未来につながるような、自分自身や社会への不安を切り拓いてくれそうな魅力をもつ響きでもあったように思います。
では、弁証法的発展のプロセスとはどのようなものでしょうか。弁証法とは、世界のあらゆる事物・事象は、互いに関連しあいながら、たえず運動し、変化・発展し、生成・消滅をつづけているとみる見方です。連載タイトルの「煌めき」は、宇宙に広がる一つひとつの星のイメージにもつながるのですが、宇宙や自然の営みと人間の発達は、深いところで連動しているのです。その連動を以下で考えます。
この、「あらゆるものは、たえず運動し、変化・発展と、生成・消滅を繰り返している」という弁証法的見方の萌芽は、古代ギリシャにまでさかのぼります。古代ギリシャの哲学者たちは、「対話」を重視していました。真剣な対話においては、意見の対立や矛盾が必ず生じ、それを解決するために議論が発展していきます。これは、私たちも日々、実感するところです。弁証法について包括的な論述をおこなったのはヘーゲル(ドイツの哲学者、1770-1831)です。ヘーゲルは、万物は、孤立し静止しているという見方、すなわち自然や社会の事物・事象をバラバラな部分の集まりとみるような機械的な見方に対し、①事物・事象の相互連関や全体をとらえ、②外からの力だけでなく、事物の内部の力による運動をとらえ、③同じ運動のくり返しではなく、進化や発展をとらえました。そして、万物の運動が起きるのは、その事物・事象のなかで生じる矛盾が原動力となり(「対立物の統一と闘争」)、それが「量から質への転換(およびその逆)」をひきおこすこと、そこには「否定の否定」の原則が働いているということを指摘したのです。
*対立物の統一と闘争:あらゆる事物や現象の内部には、たがいに対立し、排除しあう傾向や力が存在している。そのような対立物(矛盾)は互いに他を必要としつつ(統一)闘争しており、それが事物や現象の変化・発展の根本原因であるということ。
*量から質への転換(およびその逆):事物や現象には量的側面と質的側面があり、量の一定の蓄積が質的転換をもたらし、質が変わることによって、新たな量的蓄積をもたらすということ。
*否定の否定:質的転換は、それまでの質との断絶ではなく、その積極的なものは受け継ぐこと(これを弁証法的否定という)。そして低い段階の質的特徴が、高い段階において反復してあらわれる、すなわち「らせん的」といえる発展をみせるということ(否定の否定)。
(この3つを弁証法的発展法則といいます。しかし、これを事物や現象の解釈のための既成のメガネとすることは正しくありません。解釈の手がかりでありつつ、事物や現象の具体的な変化に潜む法則性を明らかにしていくなかで、この発展法則の認識がさらに豊かになっていくという研究の経路を大切にしたいと思います。)
これらは、きわめて重要な歴史的意味をもつ解明でした。しかし、ヘーゲルの弁証法は、精神(人間の似姿としての神)を世界の根源とみる観念論と結びついていました。ヘーゲルは、人間の労働や社会的実践の主体的意義を十分にはとらえていなかったのです。
このヘーゲルの弁証法を受け継ぎ、唯物論的な弁証法につくり変えたのがマルクス(1818-1883、ドイツの経済学者・哲学者・革命家)です。
ヘーゲルの時代に主流であった観念論においては、精神(神)が世界をつくっているという逆立ちが起っていたわけですが、それに対し、自然や社会をありのままにとらえるのが唯物論です。唯物論は、精神のはたらきを認めないのではなく、精神もまた神経系などの物質的基礎をもっていることから出発するものです。
ただ、マルクス以前の古い唯物論では、対象や現実を「客体」として観察するにとどまり、実践として、主体的にとらえてはいませんでした。マルクスは、人間が実際におこなっている労働や社会的実践によって、対象や現実をつくりかえていることに着目したのです。つまり、人間という「主体」が、実践によって、現実の「客体」のなかに入り込むこと、そのことによって、人間自身にも変革が起きるのだということを見抜いたのです。こうした新しい唯物論と弁証法がむすびつくことによって、弁証法的唯物論がうまれました。
人間発達と唯物弁証法
このことを人間の発達にひきよせて考えてみましょう。
実は、ヘーゲル以前に主流であった、万物は孤立し静止しているという見方、自然や社会の事物・事象をバラバラな部分の集まりとみるような機械的な見方は、現在でも発達や教育の考え方のなかに、たびたび顔を出すことがあります。
子どもの姿を、運動面ではどうか、言語面ではどうか、認識面ではどうか、社会性の面ではどうかとバラバラにとらえるだけで終わっていないでしょうか。ある能力だけに焦点をあててくり返し「訓練」し、それで「できるようになった」とみるような保育・教育になっていないでしょうか。こうした発達の見方、保育・教育のとらえ方は、子どもの内なる自然、子ども自身のなかで発達という運動が起こっていることを軽視し、外側から子どもを操作してつくりかえようとする考え方といってもよいでしょう。
また、ヘーゲルが明らかにした、矛盾を原動力にして変化が起きるということ、量から質への転換(あるいはその逆)、否定の否定という3つの原則も、人間の発達をとらえるうえで極めて重要です。矛盾が原動力になるという点は後述しますが、発達には量的側面と質的側面があり、それらは互いの前提となっているという見方は、イメージしやすいと思います。人間の発達の道すじにおいては、量的蓄積(ヨコへの発達)の時期と質的転換(タテヘの発達)の時期がくりかえし訪れます。また、発達の新たな段階では、以前の発達の段階で特徴的であったことが、より高次なものになって、くりかえし「らせん的」にあらわれます。
さらにマルクスが明らかにした、人間は外界を「観察」するだけでなく、外界にはたらきかけ、そのことによって人間自身に変革が起きるというのは、まさに、人間発達そのものを言い表しています。幼い子どもたちも、障害の有無にかかわらず、外界に自分の力ではたらきかけ、その結果を何らかの形で受け取ることによって、手ごたえを得、それが発達につながっていくのです。
そして、人間が発達するのは、その人のなかで「矛盾」を原動力とした「自己運動」が起きるからだと言えるでしょう。保育や教育など外部からのはたらきかけは、この「自己運動」をうながしたり、さまたげたりと、その方向に影響を与えることはできますが、発達の原動力そのものになることはできません。ヴィゴツキー(1896-1934、旧ソ連の心理学者、唯物弁証法を土台に新しい心理学を構築した)が提起した「発達の最近接領域」という考え方は優れた知見ですが、日本では誤った解釈が流布し、子どもにとって、難しすぎず、簡単すぎず、ちょうどよいくらいの抵抗が教育的に与えられることが重要だという浅薄で誤った理解で広まった経緯があります。
子どもにとって、ちょっとだけ難しいことをのりこえることで達成感や満足感につながり、それが次への意欲につながるというわけですが、このとらえ方では、子どもの前に次のハードルを準備しつづけていくという発想に陥りがちです。そうした見方を批判し、田中昌人さんたちは、人間の内部に、発達の原動力がどのように誕生・生成していくのかの解明に力を尽くしました。ひらたく言えば、子どもの前に教育内容がハードルのように用意されるだけで発達という「自己運動」が起こるのではなく、子ども自身がその教育内容を自分の内側に取り込み、「不安だけどやってみたいな」「難しそうだけど面白そうだな」と心が動くことが必要であり、それが発達に必要な「矛盾」になるのです。そして、そのためには、子どもの今に必要な教育内容だけではなく、「不安だけどやってみたいな」「難しそうだけど面白そうだな」と心を前に動かすための支えも必要です。
「可逆操作の高次化における階層-段階理論」では、階層間の移行(質的転換)をなしとげる力として、「新しい発達の力」が誕生することを明らかにしました。通常の場合、4か月頃に「生後第1の新しい発達の力」、10か月頃に「生後第2の新しい発達の力」、5・6歳頃に「生後第3の新しい発達の力」が誕生することは、連載や「もう一つ」で述べてきまた。「新しい発達の力」は、次の大きな発達の質的転換期(「6か月の節」、「1歳半の節」、「9歳の節」)をのりこえていくための大切な力になります。詳細はここでは述べませんが、4か月においては、目の前の相手にむかって「心の窓」が開かれ、微笑みをもって相手との関係を結ぼうとすること、10か月においては、相手の心のなかの意図も感じ取りながら、自分の意図をつくって生活や遊びの主体になろうとすること、5・6歳においては、集団や社会のもつ価値にも気づいたうえで、友だちとつながり、未来の自分もつくろうとすること…こうした力の誕生が「新しい発達の力」です。それらは、いずれも、子どもが相手や社会との関係において、「客体」から「主体」になりかわろうとする心のはたらきとも言えるでしょう。
誰もが自由で自分らしく生きる未来を創りだすために
マルクスが提起したのは、唯物弁証法だけではありません。彼は、エンゲルス(1820-1895、ドイツの社会思想家)とともに、人間の社会と歴史を唯物論的にとらえる「史的唯物論」の研究も進めました(史的唯物論に対して、唯物弁証法を弁証法的唯物論ということもある)。それは、経済学批判の方法ともなり、マルクスの主要な労作である『資本論』にもつながっていきます。
「史的唯物論」の核心となる命題は、①これまでのすべての歴史は、原始共産制を例外として、生産手段をもって支配するものと支配されるものの階級闘争の歴史であり、歴史を階級闘争の見地でとらえなければならない、②たがいに闘争する社会の諸階級は、いつでもその時代の支配者と被支配者などの生産関係や交易関係、つまり経済的諸関係によって生みだされる、③支配、被支配という階級の相互関係を直接規定する経済的諸関係が、人間の社会生活の「現実の土台」をかたちづくっており、それぞれの歴史的時期の法的かつ政治的諸制度ならびに宗教的、哲学的、その他のイデオロギーからなる上部構造の特徴は、結局、この土台の性格を反映し、そこから説明される、という3つにまとめられます。
それまでの歴史観では、歴史は英雄などの個々の人間の動機や意志による偶然の出来事の積み重ねと思われていたことに対し、人間の歴史と社会にも弁証法的な発展法則があることを明らかにしたのです。この「史的唯物論」の確立によって、人間はみずから歴史を推進する道すじをつかむことにもなったと言えるでしょう。連載第Ⅱ部第12回(3月号)でお話しした二つの力の「せめぎあい」とは、階級闘争のことを言いかえたものです。
連載や「もう一つ」では、障害のある子どもたち・なかまたちをめぐる現状について、決して楽観できるものではないことを述べてきました。とりわけ、この間、日本社会を席巻している新自由主義は、福祉も教育も、ひいては人間の命や尊厳すらも「お金次第」にし、人々に格差と分断をもちこもうとしています。もちろん、そうした流れに抗って、人間の「優しさ」「つながり」を大切にしようとする人たちがたくさんいるのも事実です。しかし、そうした善意すらふみにじるような「改革」も、次々に画策されています。いったい誰のための政治なのか、誰のための経済なのか、耳をすまし、目をそばだてて感じ取り、考え、そして心をつないでいくことが今こそ求められているのではないでしょうか。
一人ひとりのねがいを徹底的に大切にしていく発達のとらえかた、そこから見えてくる人間への信頼と未来への希望が、社会全体のものになっていくためには、個人の発達をとらえるまなざしだけではなく、社会そのものの変化を創りだすまなざしと結びつく必要があるのだと、連載を終えた今、強く思います。
連載のむすびに
たとえば「1歳半の節」を越えて、幼児期の発達の階層への質的転換を成し遂げた子どもたちは、「1次元可逆操作」という力を手にして発達の歩みを進めます。しかし、その力がいっそうたしかになっていくためには、その力を大切に守り、生かそうとする社会的関係や環境、つまり教育的関係が必要です。もし、それがなかったならば、せっかくの力も委縮したり形骸化したりしてしまうかもしれません。
歴史も、同じです。日本は、絶対主義的天皇制がひきおこした戦争や国民への専制支配を、悲劇的な結末を踏み台にしてのりこえて、「国民主権、基本的人権の尊重、平和主義」の日本国憲法を手にしました。そのときから、共有の財産としての憲法を守るために、国民には「不断の努力」(憲法第12条)が求められているのです。しかし、その憲法の諸原則を押しつぶそうとする力が、亡霊のように存在しつづけています。それは、まさに二つの力の「せめぎあい」の歴史でした。
連載第Ⅱ部第12回でお話ししたように、障害のある人びとの基本的人権の保障を前進させようとする国民の力は、ゆっくりゆっくりではありますが、大切な前進を遂げてきました。1970年代、私たちが大学生であったころ、学生は学問と共に、社会から問いかけられるようにして自らの価値意識を形成し、階級関係のなかでの自分の立ち位置を模索していました。そして、いつしか全障研の会員や『みんなのねがい』の読者にもなり、それからの人生を歩いてきました。
しかし、時代は変わりました。二つの力の「せめぎあい」を意識させまいとする政治、それとむすびついた教育、そしてそういった「せめぎあい」が社会の本質ではないとするイデオロギーは、その後の若い世代の価値意識を変容させ、自らの立場を問うことからも遠ざけていることでしょう。
だからといって二つの力の「せめぎあい」が、この社会からなくなったのではありません。いやむしろ、くりかえし述べてきたように、新自由主義の台頭の下で、苦しい生活や人生へと追いこまれ、精神的にも孤立する人びとが増えました。さらに、国家間の分断と憎悪、戦争の時代がつづき、憲法の平和原則を崩しつつ、軍事費の増大を不可避とする意識が、意図的に拡げられようとしています。
人間発達が、質的転換を達成したあと、その新しい力を生かし、拡げていく条件や関係を必要とするように、歴史にも質的な発展の後で新しい時代の市民の力を生かし、拡げていく条件が必要なのです。その条件とは何かを問い、それを産みだしていかなければならないのではないでしょうか。
先に述べたように、私たちが若かったころは、二つの力の「せめぎあい」をリアルに認識し、国民の立場、弱くさせられている人の立場に立つのか、それとも支配者の側に立って栄達を望むのかを問いかけてくる社会がありました。全障研も『みんなのねがい』も、その条件のもとで大きくなったのです。社会が、同じねがいをもつ人びとをつないでくれたとも言えるでしょう。
私たちは今、自前で、一つひとつの「つながり」を創るべき時代を生きているのです。そのことへの覚悟が必要です。しかし、それは本当にステキなことではないでしょうか。全障研も『みんなのねがい』も、自分たちの言葉で訴えかけ、一つひとつ拡げていかなければならない。言いかえれば、人とつながりあうために、自分のあり方を問い、自分の言葉で語りつつ発達していくことができるという、自由な意志が生きる段階にあるのだと思います。
そして、そもそも人は、つながって生きたいのではありませんか。それを強要されたり、大きな力で抑えられるのはイヤだけれど、苦しい思いの仲間、この社会のなかで弱くさせられている仲間がいるならば、その人とともに生きてみようとする。
発達においては、自我を誕生させ、たしかな要求の主人公になっていくけれど、それとともに他者にも思いや要求があり、うれしいことも悲しいことも抱えて生きていることを、子どもは知っていきます。そして、視座を他者に転じて、他者のことを想いつつ、自分自身を省みていく力を発達させていきます。
かつてそのことを、「思いを一つにするという意味でのcompassion(共感)、つまり他者への思いやりをもった寛容で度量のある人格」(『発達をはぐくむ目と心』全障研出版部)と表現してみました。人間の大切な本質であり、互いにはたらきかけあい、力をあわせる実践のなかで、あらわれ出るのだと思います。
それを信頼して、職場の同僚や地域の仲間に、子どもたち・なかまたちの発達へのねがいをわかりあうために、『みんなのねがい』をいっしょに読みませんかとはたらきかけてみよう。連載の最後に、私たちはそう呼びかけました。そして、生活や労働の苦しさの背景にあるものを語りあい、学びあって、一人ひとりがより良い社会を創るための「社会の主人公」になっていこう。そうも呼びかけました。
それに応えて手をつないでくれた仲間、そして、はたらきかけた仲間は、タカラモノです。一人の同僚が全障研の会員になってくれた、『みんなのねがい』を購読してくれたという、その「一人」のことを、全国の仲間と喜びあえるような全障研であってほしいと思います。
では、3月2日の最後の「執筆者交流会」で読み上げた糸賀一雄さんの言葉を紹介して、むすびといたします。
世の中にきらめいている目もくらむような文明の光輝のまえに、この人びとの放つ光は、あれどもなきがごとく、押しつぶされている。その光は異質の光なのである。文明の輝きになれた目には、その異質の光は、光としてうつらないかもしれない。
しかし私たちは、この人たちの放つ光を光としてうけとめる人びとの数を、この世にふやしてきた。異質の光をしっかりとみとめる人びとが、次第に多くなりつつある。人間のほんとうの平等と自由は、この光を光としてお互いに認めあうところにはじめて成り立つということにも、少しずつ気づきはじめてきた。この異質の光をみとめるというはたらきは、なにか特別な能力であるかのようであるが、じつは決してそうではない。いつの世にも、そしてだれにもそなわっているのである。しかしその能力は、あやまった教育と生活のために、長いあいだ隠されており、はたらきがにぶってしまったのである。
精神薄弱な人びとと、そうでない人びとが、この異質の光の照らす世界では、時として優劣は逆転するかもしれない。いや、これまで自分が優れていると思っていた人びとが、この光の照らす世界にきて、その優越感をかなぐり捨てて謙虚になるというだけのことである。優劣といった競いあう心ではない。排他的でないところに、この光の照らす世界の特質がある。釈尊の説くような、真実の「あきらめ」がある。
みせかけの科学的というかけ声に酔って、現実の悩みをひとごとにしてしまってはいけない。この悩みや呻き声に耳を傾けること、それへの共感の心情をたっぷりもって、そして改めてこの人びとと共に生きてみることである。そこにかすかではあるが、この世ならぬ、一条の光が放たれていることに気づかされるのである。この光は、新しい「世の光」である。それはこの人びとから放たれているばかりではなく、この人びとと共に生きようとしている人びとからも放たれているのである。
(生前未発表原稿、糸賀一雄『福祉の道行-生命の輝く子どもたち-』中川書店、2013年)
(白石註) 釈尊の説く真実の「あきらめ」とは、仏教の教え。人間の苦悩は自己中心的な欲望と無知に発する。そのことをありのまま見つめる(諦める、諦観する)ことができれば、解決の方法や真理に近づくことができるとする。キリスト者であった糸賀にあっては、「喜ぶ人とともに喜び、泣く人とともに泣きなさい。思いあがることなく、互いに思いを一つにし、小さくされた仲間とあゆみをともにするのです。自己中心になってはいけません」(「ローマの教会の人びとへの手紙」、本田哲郎氏訳)というパウロの言葉でもあったろう。
学習参考文献
牧野広義『世界は変えられる-マルクスの哲学への案内』学習の友社、2016年
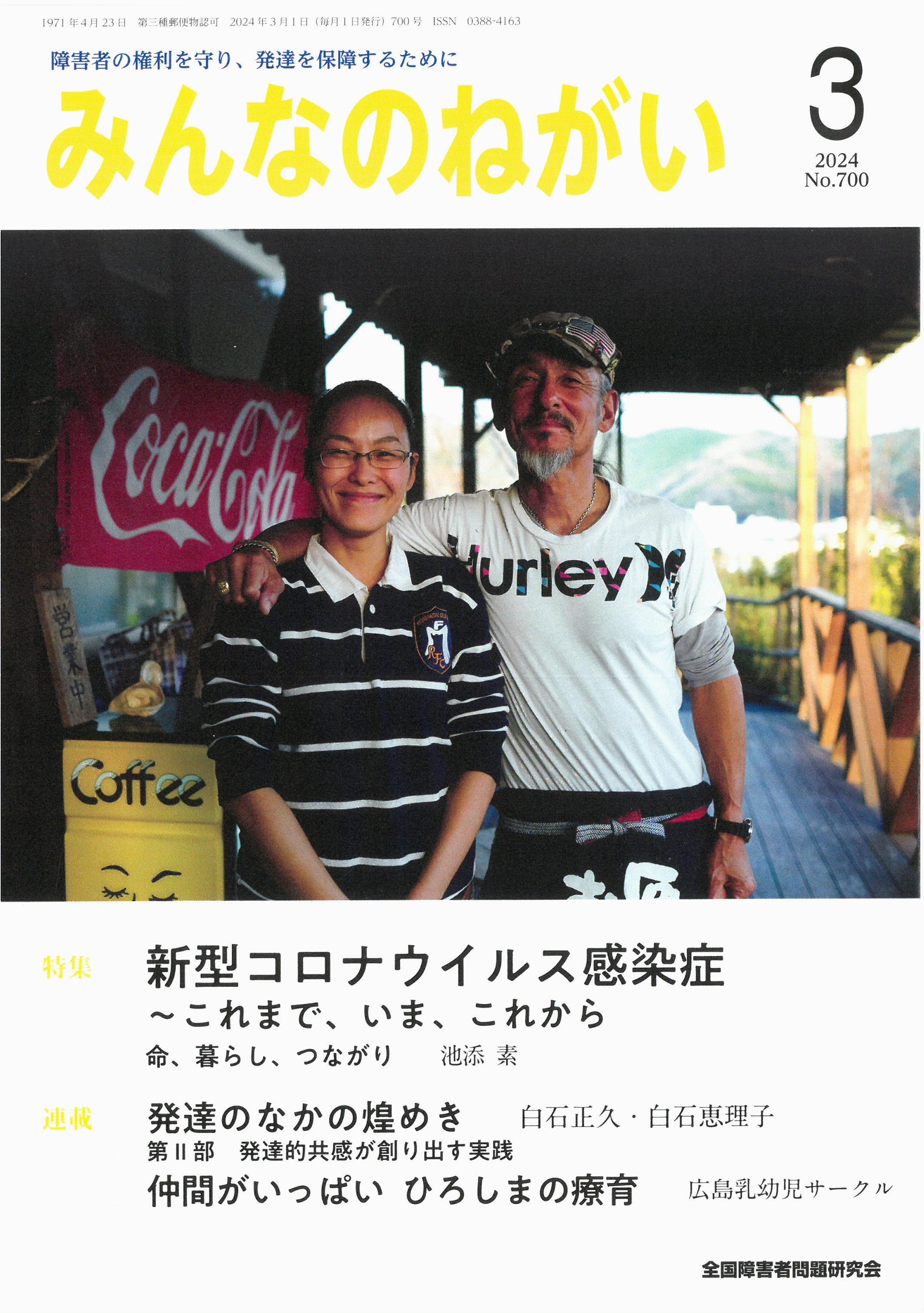
<表紙のことば>
女川町にある喫茶店「おちゃっこクラブ」のオーナー夫妻を撮影したのは震災の復興がようやく進み始めた頃だった。それまで経営していたライブハウスは津波に流され、仲間たちも命を失った。自身の悲しみを抱えながらも、女川の人々の気持ちを少しでも癒そうと、仮設店舗として高台の土地にこの憩いの場を開いた。それから二人の笑顔がどれほどの沈んだ心に灯をともしてきたことだろう。2020年、またこの場所でという思いが9年越しに同じ地域にライブハウス&カフェを復活させた。震災で失ったものは計り知れない。でも、故郷への愛とそこに集まる人々の絆はもっともっと、深いものになったに違いない。
土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある。
<目次>
1 人として 山内若菜(日本画家)
2 【インタビュー】今、あなたと生きて 三上智恵(映画監督・ジャーナリスト)
4 この子と歩む 楠本詩季
7 私のタカラモノ 関野啓治
8 仲間がいっぱい ひろしまの療育 伊津佳恵(広島市こども療育センター)
11 世界の風 瀬見さち子(オーストラリア)
特集 新型コロナウイルス感染症~これまで、いま、これから
13 運営よりも子どものことを一番に考えたい 神谷さとみ(福山市)
14 行事の継承、連帯性の低下 全障研鳥取支部事務局
15 楽しいことを我慢してきた子どもたち 益本裕美(久喜市)
16 5類移行に伴う現場の負担増と公的責任の縮小 黒川真友(大津市)
18 障害児・者と家族の暮らし 二見清一(足立区役所)
20 私の暮らしと新型コロナ感染症 中野まこ(愛知)
22 命、暮らし、つながり 池添 素(福祉広場)
24 発達のなかの煌(きら)めき 白石正久(龍谷大学名誉教授)・白石恵理子(滋賀大学)
28 社会をみる 杉田真衣(東京都立大学)
30 福祉現場の今を読み解く 田中智子(佛教大学)
32 基礎から学ぶ 障害と医療 平田正吾(東京学芸大学)
34 私ときょうだい 須甲詩織
36 実践の魅力 武市真奈
39 支部だより 稲吉綾美
40 発達保障インタビュー バトンゾ→ン 大島悦子(全障研大阪支部長)
42 みんなのひろば
44 ニュースナビ 危険水域に達した「職員不足」と2024年度報酬改定のゆくえ 小野浩(きょうされん)
46 誠司くんの見たこと、聞いたこと、歩いてきた道 松本誠司(高知)
47 BOOK/編集後記
デザイン・イラスト うじたなおき、永野徹子、橋野桃子、細川茉莉
▶ご購読は出版部オンラインへ
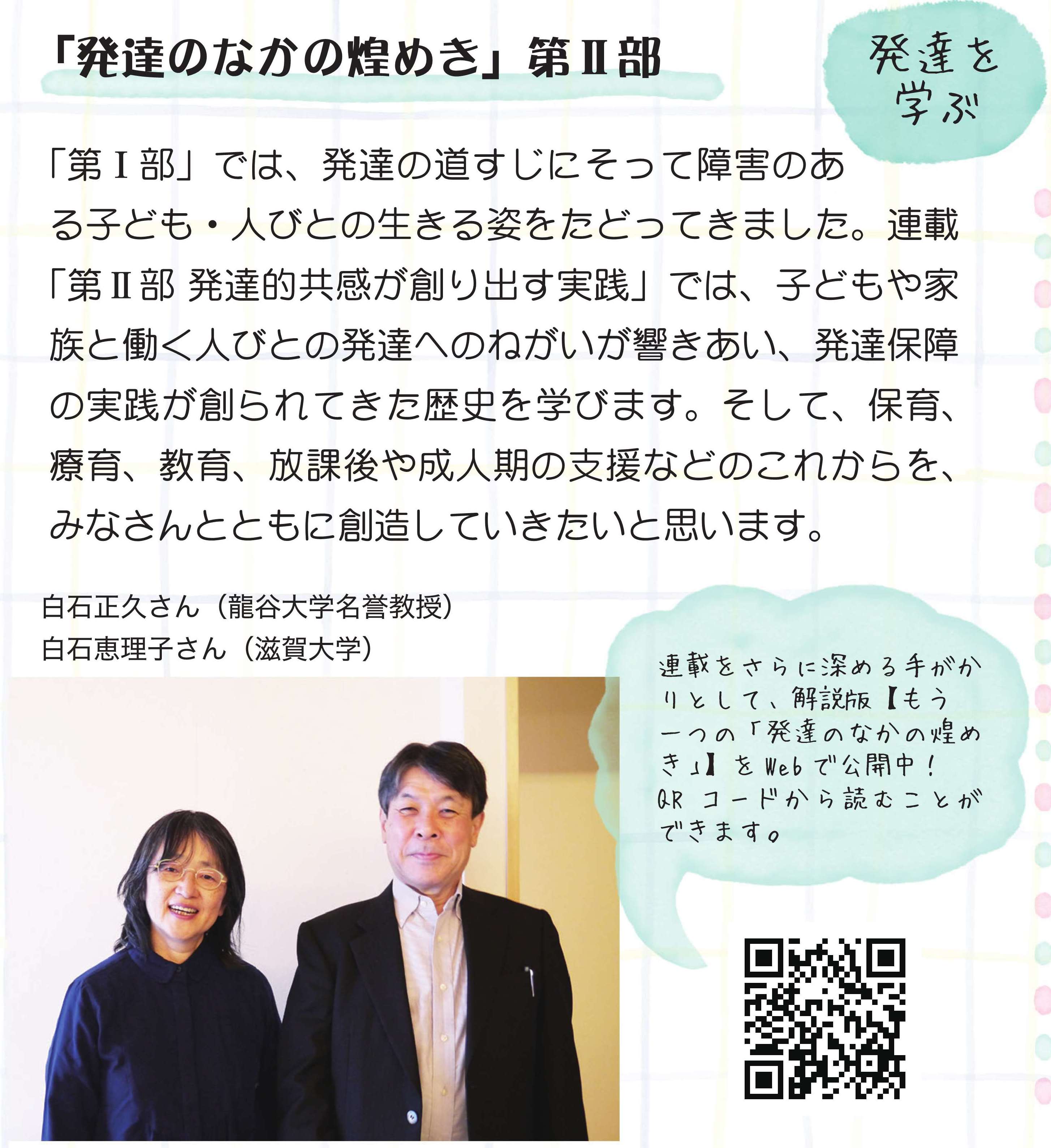
能登半島地震(震度7、M7.6)障害者、関係者の情報
2024年1月1日16時10分ごろ、能登半島で震度7、M7.6の大地震がありました。
大津波警報も心配されましたが、その後も大きな余震がつづいています。
ときがたつにつれ大きな被害状況が報道されています。
冬の寒い被災地を思うと、障害者、関係者のみなさんの状況がたいへん気がかりです。
みなさんのところで、支えるべき障害者・関係者の情報が寄せられましたら、
全国事務局(info@nginet.or.jp)にお知らせください。
JDなど障害者関係団体と連携して対応を検討させていただきます。
なお、JDF(日本障害フォーラム)は、4日に「JDF災害対策本部会議」を招集し、19日に現地情報を寄せ合って会議します。
JDの加盟団体の難民を助ける会(AAR JAPAN)は、発災直後から、きょうされん等と連絡を取り合い現地への緊急支援チームを派遣し、炊き出しや障害者施設への支援を開始しています。
きょうされんは14日~16日、先遣隊を現地に派遣しています。
2024年1月18日現在
〇きょうされん
https://www.kyosaren.or.jp/
災害支援基金にとりくんでいます
●郵便振替●
<口座名義>きょうされん自然災害支援基金口
<口座番号>00100-7-86225
〇難民を助ける会 (JD加盟団体です)
https://aarjapan.gr.jp/news/12732/
〇NHKハートネットTV 能登半島地震 障害のある人たちの状況は
https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/888/
〇石川県保険医協会「令和6年能登半島地震」特設ページ
https://ishikawahokeni.jp/2401notojisin/
〇厚生労働省 石川県能登地方を震源とする地震について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00442.html
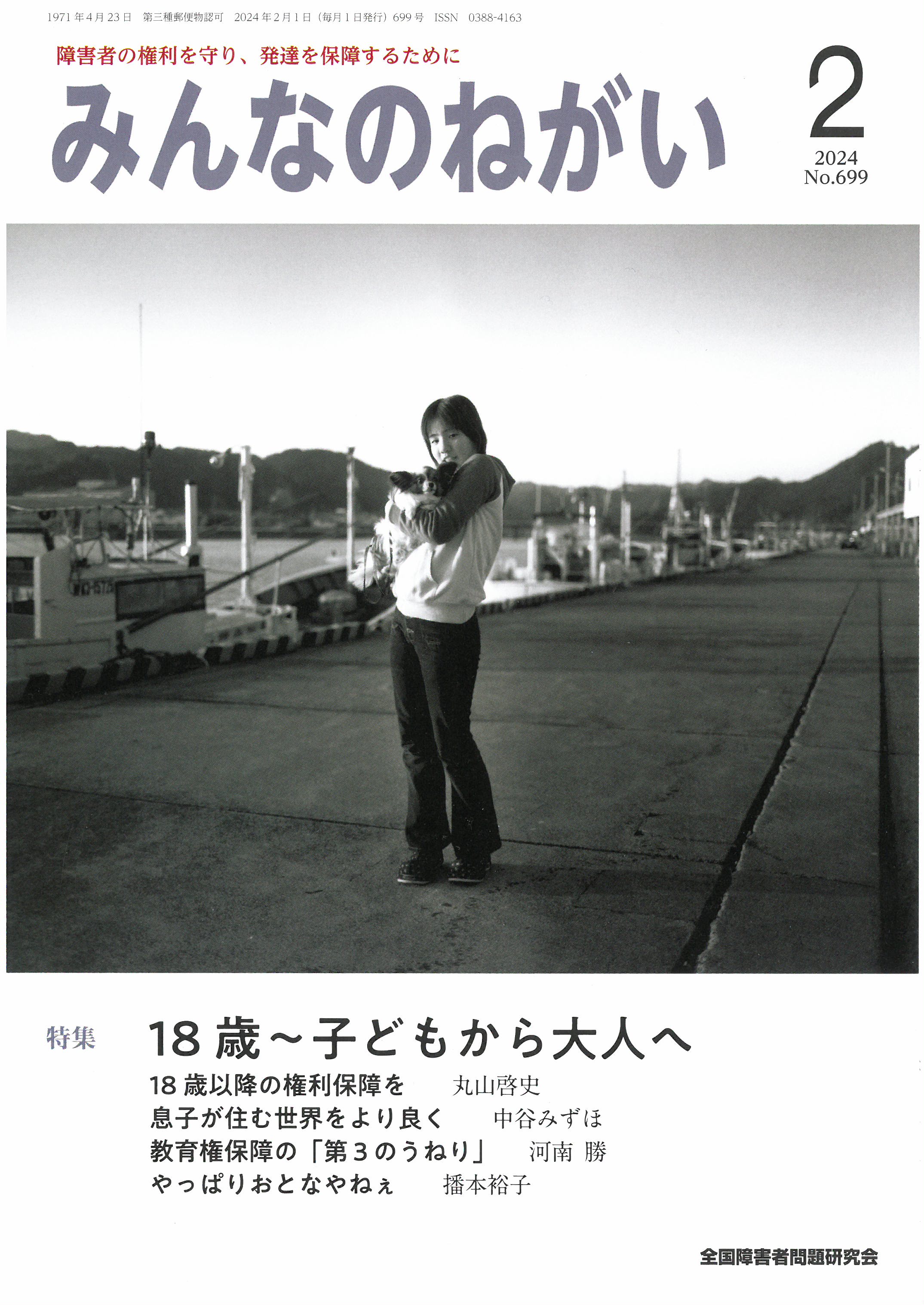
<表紙のことば>
今から20数年ほど前に和歌山県各地で撮り続けていた、僕の写真家としての初めての作品「和らぎの道で」より。
夕方の漁港で犬の散歩をする女の子に出会う。写真撮られるん恥ずかしいなあと照れながら、愛犬を抱き上げてはにかむ。黄昏時のきらきらした瞬間だった。彼女はいまではもう30代くらいの素敵な大人の女性になっているだろう。ひょっとしたら故郷の港町を離れて家庭を持ち、あの時と同じ歳くらいの娘の母親になっているのかもしれない。もし、いま、この写真を彼女が見たらいったいどんな思いを馳せるのだろうか。
一期一会の出会いって、やっぱりセンチメンタルだ。
土佐 和史 とさ かずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある。
<目次>
1 人として 別所尭俊(AOiスクール・小田急電鉄運転士)
2 【インタビュー】今、あなたと生きて 三上智恵(映画監督・ジャーナリスト)
4 この子と歩む 田中亜矢(寝屋川市)
7 私のタカラモノ 大野仁美(岐阜)
8 仲間がいっぱい ひろしまの療育 佐々木里美(広島市北部こども療育センター)
11 世界の風 瀬見さち子(オーストラリア)
特集 18歳~子どもから大人へ
12 青年の主張
14 18歳以降の権利保障を 丸山啓史(京都教育大学)
17 自分で考え、自分で決める 吉松ふみ(大阪 ぽぽろスクエア)
18 息子が住む世界をより良く 中谷みずほ(茨城)
20 教育権保障の「第3のうねり」 河南 勝(兵庫障害者センター)
22 やっぱりおとなやねぇ 播本裕子(大阪障害児・者を守る会)
24 発達のなかの煌(きら)めき 白石正久(龍谷大学名誉教授)・白石恵理子(滋賀大学)
28 社会をみる 杉田真衣(東京都立大学)
30 福祉現場の今を読み解く 田中智子(佛教大学)
32 基礎から学ぶ 障害と医療 平田正吾(東京学芸大学)
34 私ときょうだい 中川彩夢(広島)
36 実践の魅力 日下部育子(京都 第三かめおか作業所)
39 支部だより 玉城啓(沖縄支部)
40 発達保障インタビュー バトンゾ→ン 大島悦子(全障研大阪支部長)
42 みんなのひろば
44 ニュースナビ 埼玉県虐待禁止条例改正案撤回 馬場久志(埼玉大学名誉教授)
46 誠司くんの見たこと、聞いたこと、歩いてきた道 松本誠司(高知)
47 BOOK/編集後記
裏表紙 心のことば 小林宏夢
デザイン・イラスト うじたなおき、永野徹子、橋野桃子、細川茉莉
▶ご購読は出版部オンラインへ
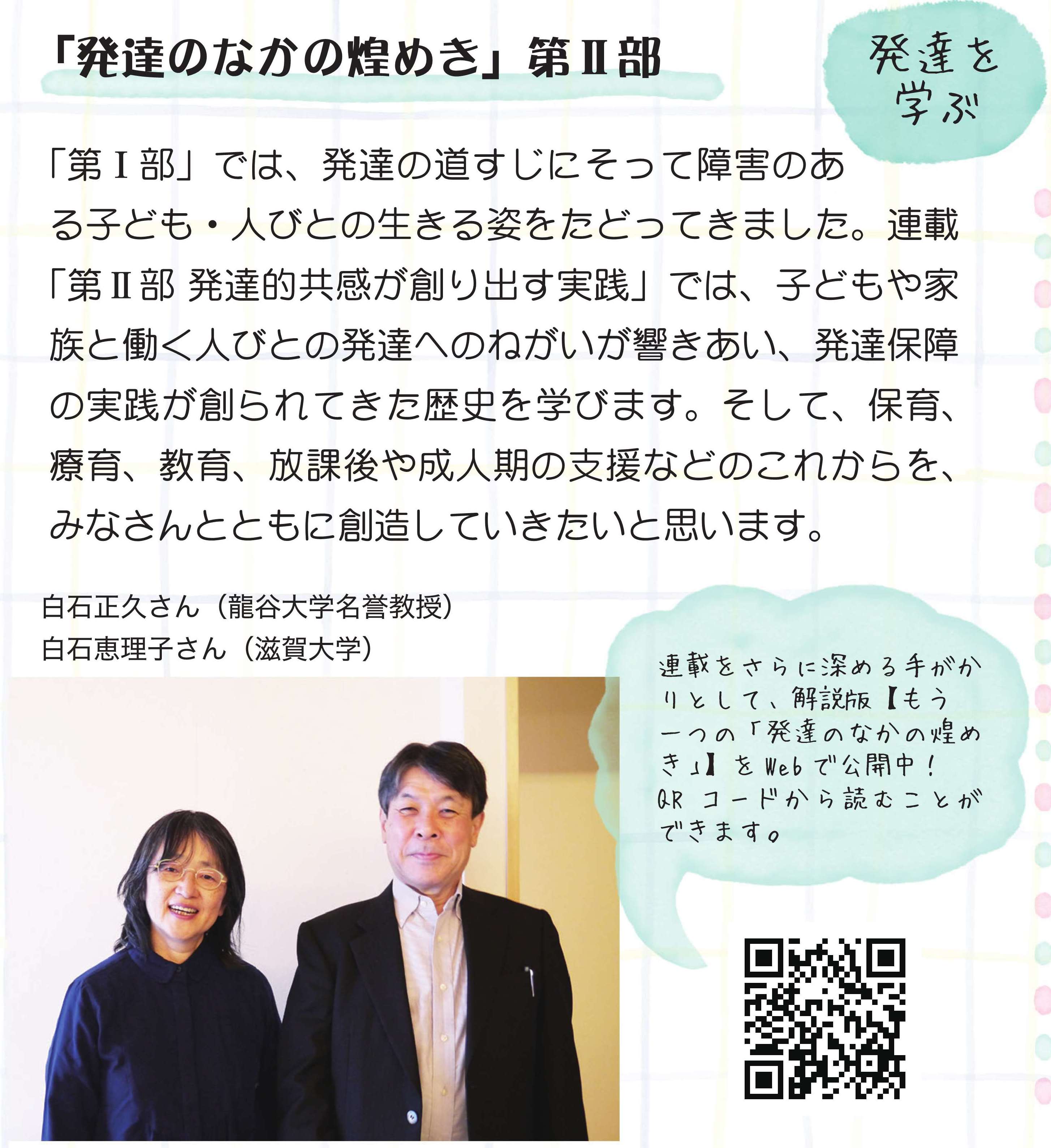
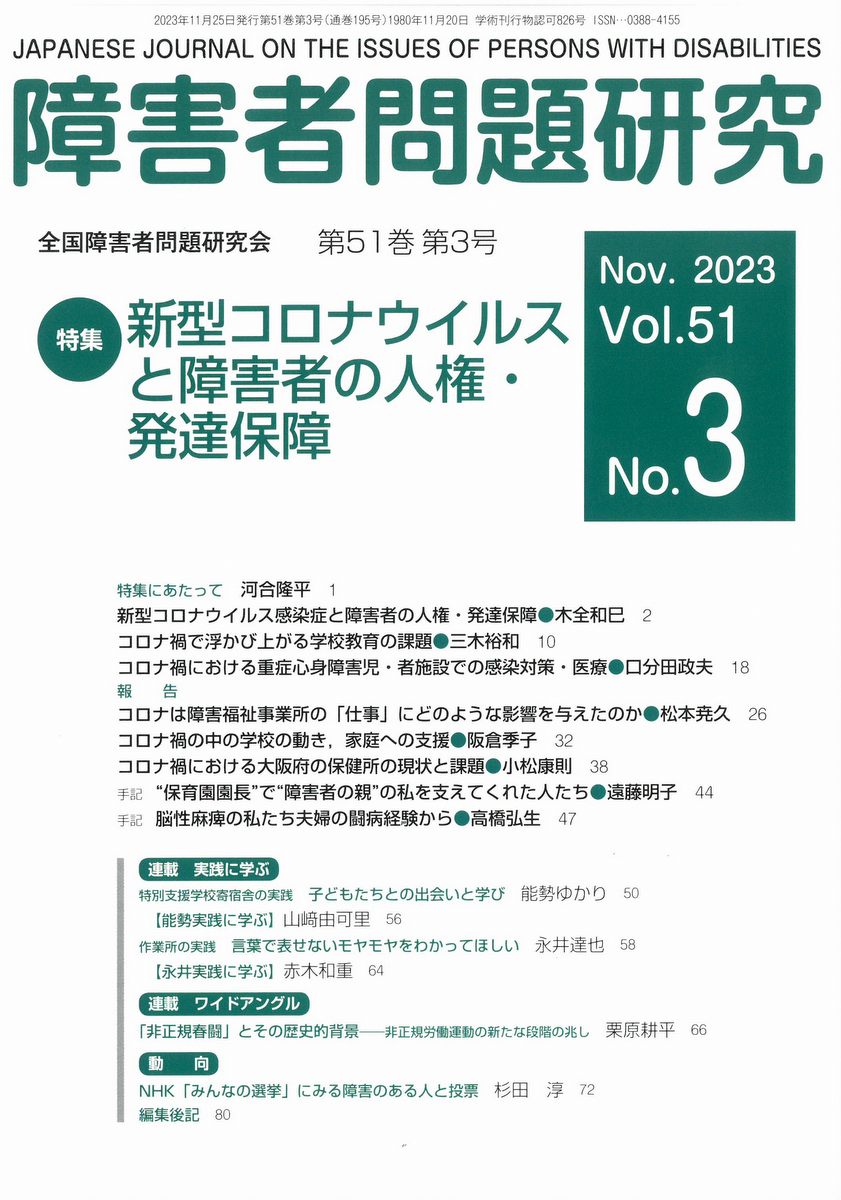
JAPANESE JOURNAL ON THE ISSUES OF PERSONS WITH DISABILTIES2023年
11月25日発行 ISBN-984-4-88134-136-0 C3037 定価2750円(本体2500円+税)
特集 新型コロナウイルスと障害者の人権・発達保障
特集にあたって/河合隆平 東京都立大学
新型コロナウイルス感染症と障害者の人権・発達保障
ソーシャルワーク実践研究の立ち位置から改めて「民主主義」を問い直す
/木全和巳 日本福祉大学社会福祉学部
世界規模の新型コロナウイルス感染拡大から4年が経過しようとしている.「しょうがい(disability)」を中心にソーシャルワークを研究している立ち位置から,関係している社会福祉法人の出来事とその対応,スーパーバイザーとして関わっている地域の相談支援,当事者の青年たちとの学び合いなどを通して,コロナ・パンデミックと対峙してきた.本稿では,文献からコロナ・パンデミックで明るみになったことを整理して,次にある社会福祉法人の専務理事と事務長の聴き取りを中心に他の障害者福祉現場の実態とも重ね合わせての取り組みと課題について書き,特にケアとケア労働の重要性の再確認をした後に,最後にコロナ・パンデミックの教訓と課題についてまとめた.障害者の人権と発達を保障していくためには,改めて「コモン」と「自治」を重視した「民主主義」の在り方を問い直すことが求められる.
コロナ禍で浮かび上がる学校教育の課題
障害のある子どもと家庭を念頭に/三木裕和 立命館大学産業社会学部
新型コロナ感染症による社会的混乱,長期の休校措置は,障害のある子どもにどのような影響を与えたのか.また,学校はそれにどう応えたかを検討した.学校教育では人間的共感関係,医療・福祉との連携が重要であった.学校再開後,学校の情報化が進み,人間的共感関係の形成に不安が生じている.
コロナ禍における重症心身障害児・者施設での感染対策・医療
/口分田政夫 (社福)びわこ学園 びわこ学園医療福祉センター草津
新型コロナが拡大し始めた 2020年より,重症心身障害児・者施設では,新型コロナ感染への対応に向かわざるを得なかった.オンライン面会の導入,短期入所の制限を行った.びわこ学園医療福祉センター草津でも
2022 年度,それぞれ2 度の病棟クラスターを経験した.また,法人が運営するグループホームでも,クラスターが発生していた.病棟では,特別の感染対応や,職員の休業者の増加に伴う勤務シフトが必要となった.また,グループホームでは,地域医療連携が有用だった.重症心身障害病棟での面会に関して,家族の問いかけがあり日本重症心身障害学会で議論があり,学会として提言が出されてた.
報告 コロナは障害福祉事業所の「仕事」にどのような影響を与えたのか
きょうされん「コロナの影響に関する生産活動・利用者工賃実態調査」をふまえて
/松本尭久 きょうされん全国事務局
報告 コロナ禍の中の学校の動き,家庭への支援
地域との連携に学ぶこと
/阪倉季子 滋賀県障害児学校教職員組合
報告 コロナ禍における大阪府の保健所の現状と課題
現場の声とともに振り返る
/小松康則 大阪府関係職員労働組合執行委員長
手記 “保育園園長”で“障害者の親”の私を支えてくれた人たち
パンデミックの日々の中で
/遠藤明子 神奈川県横浜市
手記 脳性麻痺の私たち夫婦の闘病経験から
/高橋弘生 障害者(児)を守る全大阪連絡協議会
連載/実践に学ぶ
【報告】特別支援学校寄宿舎の実践子どもたちとの出会いと学び
──寄宿舎指導員生活を振り返る
/能勢ゆかり 奈良教育大学非常勤講師
【能勢実践に学ぶ】教育実践に生活の視点を求めて
/山﨑由可里 和歌山大学教育学部
【報告】作業所の実践言葉で表せないモヤモヤをわかってほしい
仲間の本当のねがいを追い続けて
/永井達也 (社福)あぜくら福祉会 尼崎あぜくら作業所
【永井実践に学ぶ】割る/折る/祈る
/赤木和重 神戸大学大学院人間発達環境学研究科
連載/ワイドアングル 第23回
「非正規春闘」とその歴史的背景
非正規労働運動の新たな段階の兆し
/栗原耕平 首都圏青年ユニオン副委員長
動向 NHK「みんなの選挙」にみる障害のある人と投票
/杉田 淳 NHK 報道局選挙プロジェクト
▶ご注文は 全障研出版部オンラインショップへ ▶本誌紹介チラシはこちらPDF
▶ 「読む会」情報 2024年1月17日(水)19時~21時 /ZOOM
司会・進行 河合隆平(本誌編集委員) コメント 越野和之
【話題提供】木全和巳(日本福祉大学) 三木裕和(立命館大学)
▶詳細案内はこちらをクリックしてください
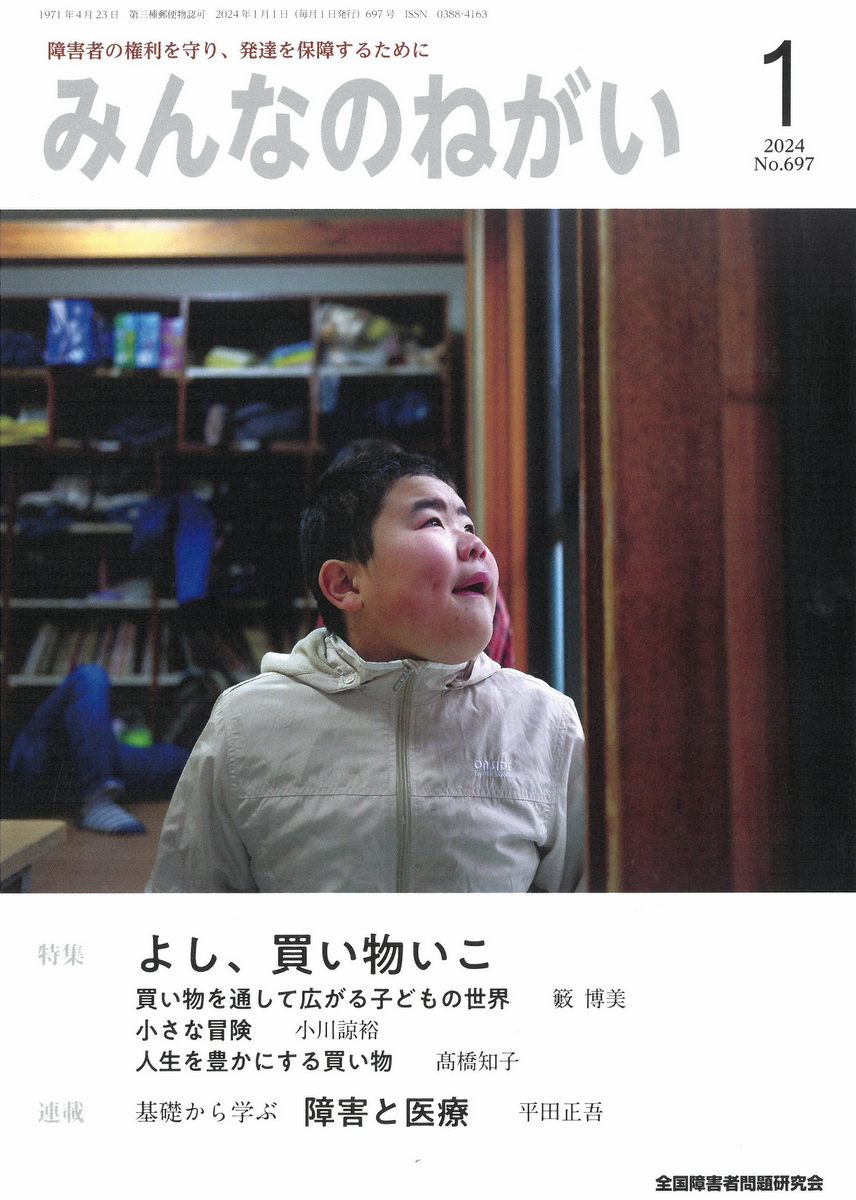
<表紙のことば>
埼玉県久喜市にある「モンキーポッド」を訪ねたのが二年前の冬、湿った雪が降り続くとても寒い日だった。僕にとって初めての障害児施設の取材で、ただただ目の前で起こる事に圧倒され状況を見つめるしかなかった。ひとりの少年が不安定になり、ひたすらに泣き叫んでいた。周りはそのシビアな現実を心の中で共有しながらただただ見守っているように見えた。
しばらくして、細雪が大きな牡丹雪に変わった。少年はふと空を見上げ、落ちてくる雪をじっと見つめる。涙が止まった。僕はそっとカメラを向けシャッターを切った。何かが始まったような気がした。あの瞬間を、きっと忘れないだろう。
土佐和史 とさかずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある。
<目次>
1 人として 西郷孝彦
2 【インタビュー】今、あなたと生きて 三上智恵(映画監督・ジャーナリスト)
4 この子と歩む 吉野由里子
7 私のタカラモノ 成清恵規
8 仲間がいっぱい ひろしまの療育 中村有里
11 世界の風 瀬見さち子(オーストラリア)
特集 よし、買い物いこ
13 買い物はコミュニケーション 内田智也
14 僕のお買い物ストーリー&ヒストリー 鷲見俊雄
15 娘と冷蔵庫と買い物と 倉科美和
16 タイミングと気遣い 市橋 博
17 買い物を通して広がる子どもの世界 籔 博美
20 小さな冒険 小川諒裕
22 人生を豊かにする買い物 髙橋知子
24 発達のなかの煌(きら)めき 白石正久(龍谷大学名誉教授)・白石恵理子(滋賀大学)
28 社会をみる 杉田真衣(東京都立大学)
30 福祉現場の今を読み解く 田中智子(佛教大学)
32 基礎から学ぶ 障害と医療 平田正吾(東京学芸大学)
34 私ときょうだい 道村理乃
36 実践の魅力 林 陽子
39 支部だより 樋口京子(高知支部)
40 発達保障インタビュー バトンゾ→ン 小畑耕作(前全障研和歌山支部長)
42 みんなのひろば
44 ニュースナビ 「基本合意」と第14回定期協議 薗部英夫(めざす会・JD)
46 誠司くんの見たこと、聞いたこと、歩いてきた道 松本誠司
47 BOOK/編集後記
裏表紙 心のことば 小林宏夢
デザイン・イラスト うじたなおき、永野徹子、橋野桃子、細川茉莉
▶ご購読は出版部オンラインへ
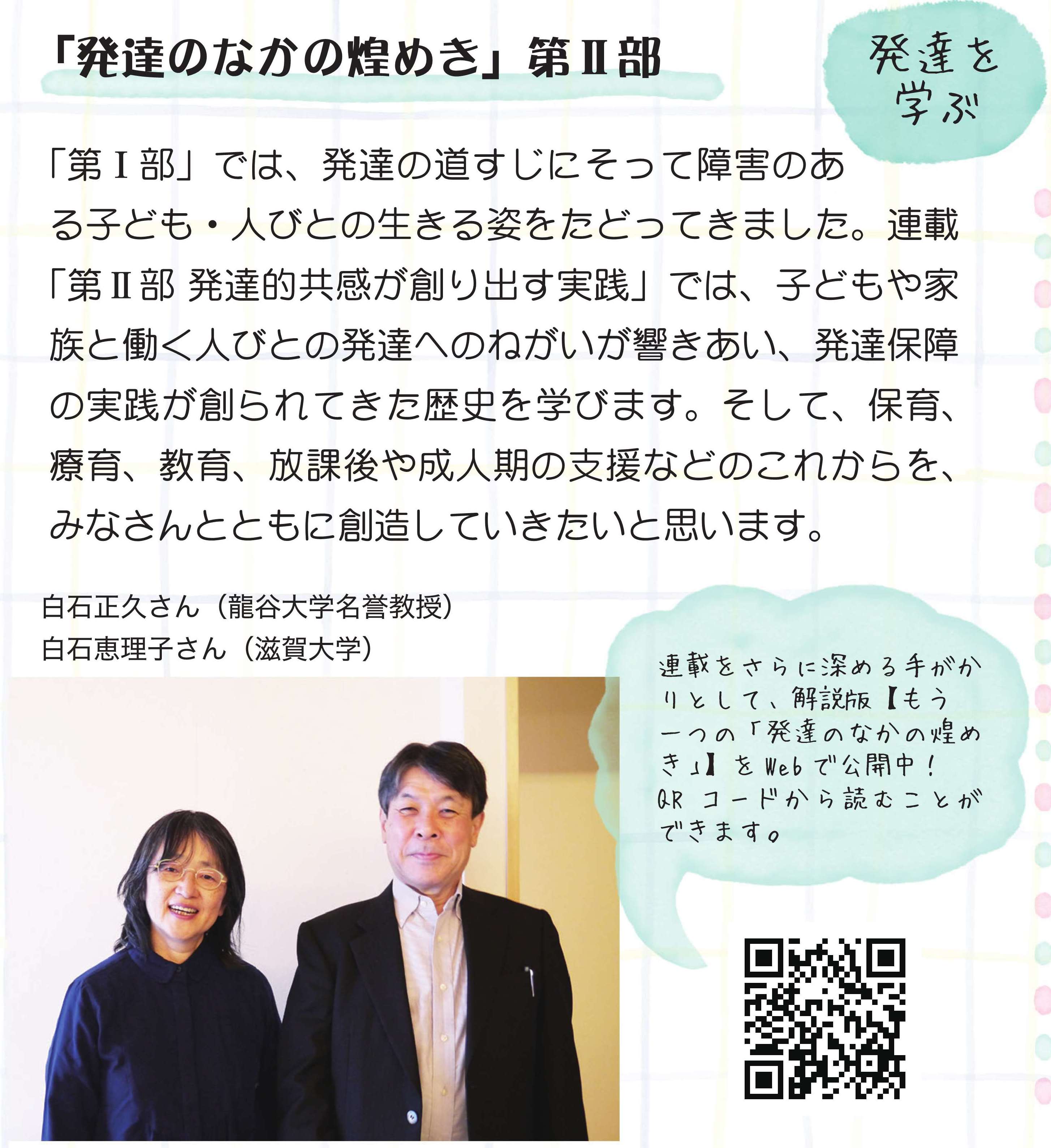
声明
ガザ地区への攻撃の停止を求めます
2023年11月15日
全国障害者問題研究会 常任全国委員会
殺された人がいます。傷つけられた人がいます。大切な人を奪われた人がいます。住むところを失った人がいます。おびえる子どもたちがいます。
殺されようとしている人がいます。
イスラエル軍によるガザ地区への攻撃が続くなか、およそ1か月の間に、ガザ地区では1万人を超える人びとが命を奪われました。
ガザ地区では、水も不足しています。食べるものも手に入らなくなっています。物資や電力が断たれ、医療活動ができなくなり、子どもたちが亡くなっています。
障害のある子どもたち、障害のある人たちは、どういう状況にあり、何を思っているでしょうか。家族は、どういう日々のなか、何を感じているでしょうか。
ガザ地区の惨状が目の前にありながら、イスラエルはガザ地区への攻撃をやめようとしません。また、米国・英国・日本などG7の国々は、イスラエルの「自衛権」を語り、攻撃をやめさせようとしません。
日本政府は、「人道的休戦」を求める国連決議にも賛成しませんでした。イスラエルによる国際法違反を批判することもしません。
私たちは、攻撃をやめようとしない勢力に対して、「攻撃をやめろ」と言わなければなりません。「攻撃をやめさせろ」という声を、日本政府に向けなければなりません。
全国障害者問題研究会は、障害者の権利を守り、発達を保障することをめざして歩んできました。障害者の権利保障・発達保障は、生命や生活を脅かす攻撃の対極にあります。
私たちは、断固として訴えます。「戦争、殺戮をやめろ」
▶PDFデータです
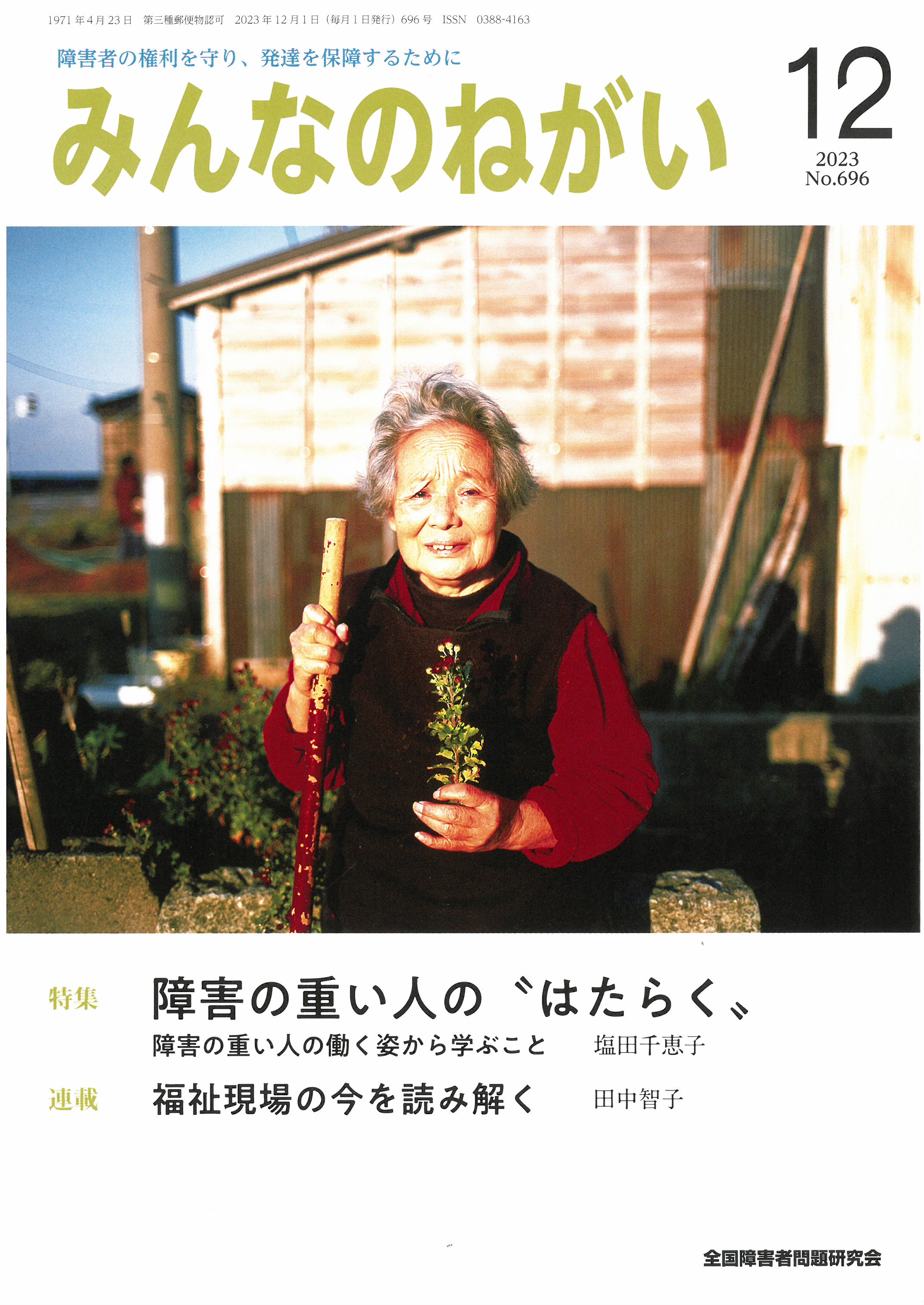
<表紙のことば>
新潟県出雲崎海岸沿いの車道をひとりの老婆が横切る。杖をつきながら足元はおぼつかなさそうだ。おばあちゃん大丈夫?と駆け寄ると、彼女が全盲であることを伝えられた。安全な場所まで導いて別れ、近くの漁村を撮り歩く。
しばらくするとさっきのおばあちゃんが庭先に座っていた。再び声をかけようとすると向こうから「さっきはありがとうね」と。面食らって尋ねると、見えなくても僕とわかったらしい。光は感じなくともそれ以上に見えるものがあるのだろうか。
家の前に咲いていた赤い花をそっと手に、彼女はカメラを真っ直ぐに見つめ微笑んだ。
土佐和史 とさかずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある。
<目次>
1 人として 栗山龍太(シンガーソングライター)
2 【インタビュー】今、あなたと生きて 三上智恵(映画監督・ジャーナリスト)
4 この子と歩む 江見和則(大阪・吹田市)
7 私のタカラモノ 五十嵐 匠(東京)
8 仲間がいっぱい ひろしまの療育 幸田千代子(広島市北部こども療育センター元職員)
11 世界の風 瀬見さち子(オーストラリア)
特集 障害の重い人の”はたらく”
12 はたらく仲間たち
14 障がいの重い人の労働を考えるとき 金室修平(千葉・生活介護はちみつ)
17 仲間の思いを伝える仕事づくり 湯口郁子(京都・あみの福祉会)
20 働く姿を見つめて 桜井みゆき(岐阜)
21 障害の重い人の働く姿から学ぶこと 塩田千恵子(大阪 ひびき福祉会)
24 発達のなかの煌(きら)めき 白石正久(龍谷大学名誉教授)・白石恵理子(滋賀大学)
28 社会をみる 杉田真衣(東京都立大学)
30 福祉現場の今を読み解く 田中智子(佛教大学)
32 基礎から学ぶ 障害と医療 柴田実千代(小児科医)
34 私ときょうだい 戸田竜也(北海道)
36 実践の魅力 渡辺隆子(福岡)
39 支部だより 福永ひろみ(和歌山)
40 発達保障インタビュー バトンゾ→ン 小畑耕作(前全障研和歌山支部長)
42 みんなのひろば
44 ニュースナビ 名古屋城バリアフリー市民討論会における差別発言 上田 孝(愛障協)
46 誠司くんの見たこと、聞いたこと、歩いてきた道 松本誠司
47 BOOK/編集後記
裏表紙 心のことば 小林宏夢
デザイン・イラスト うじたなおき、永野徹子、橋野桃子、細川茉莉
▶ご購読は出版部オンラインへ
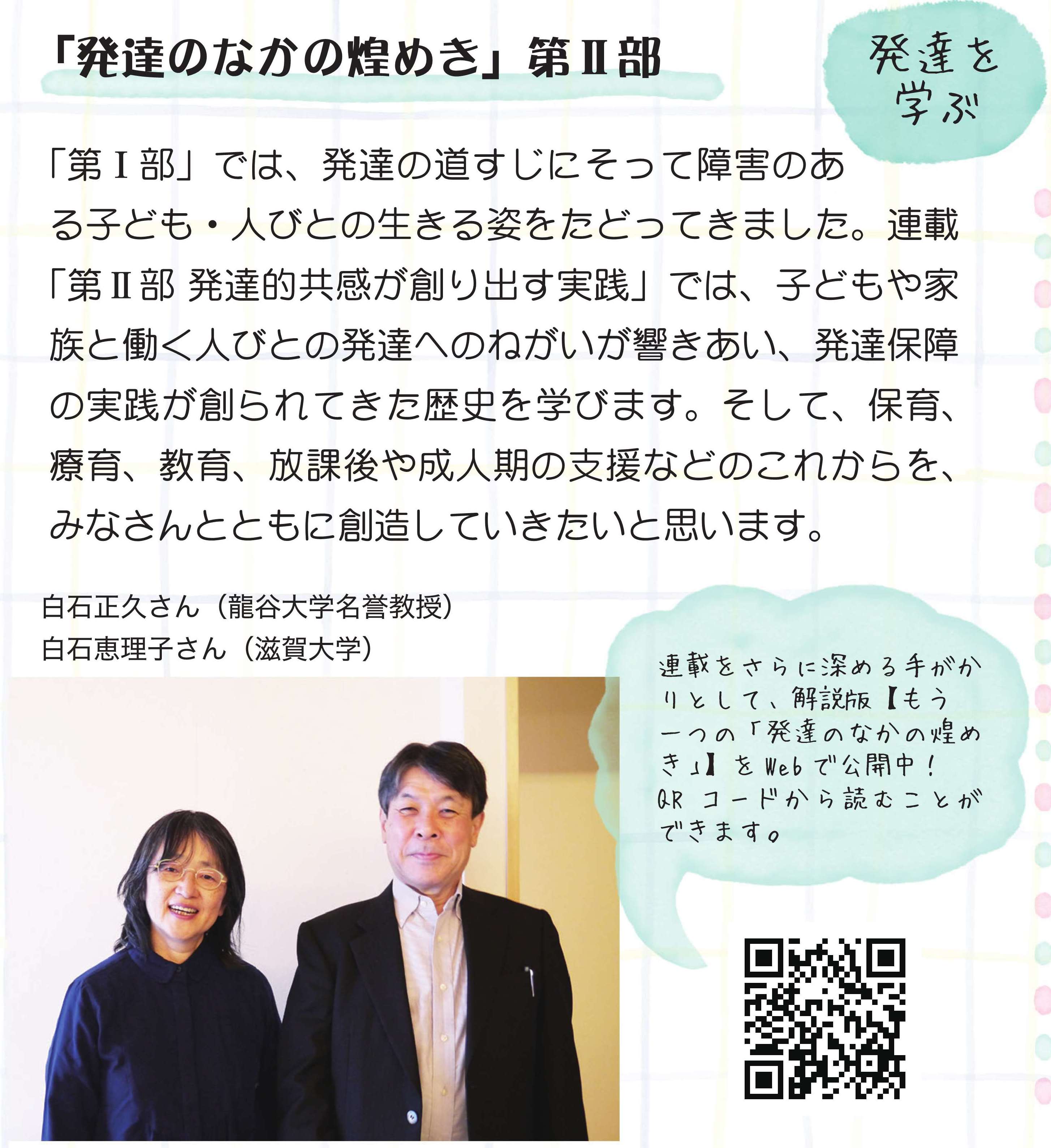
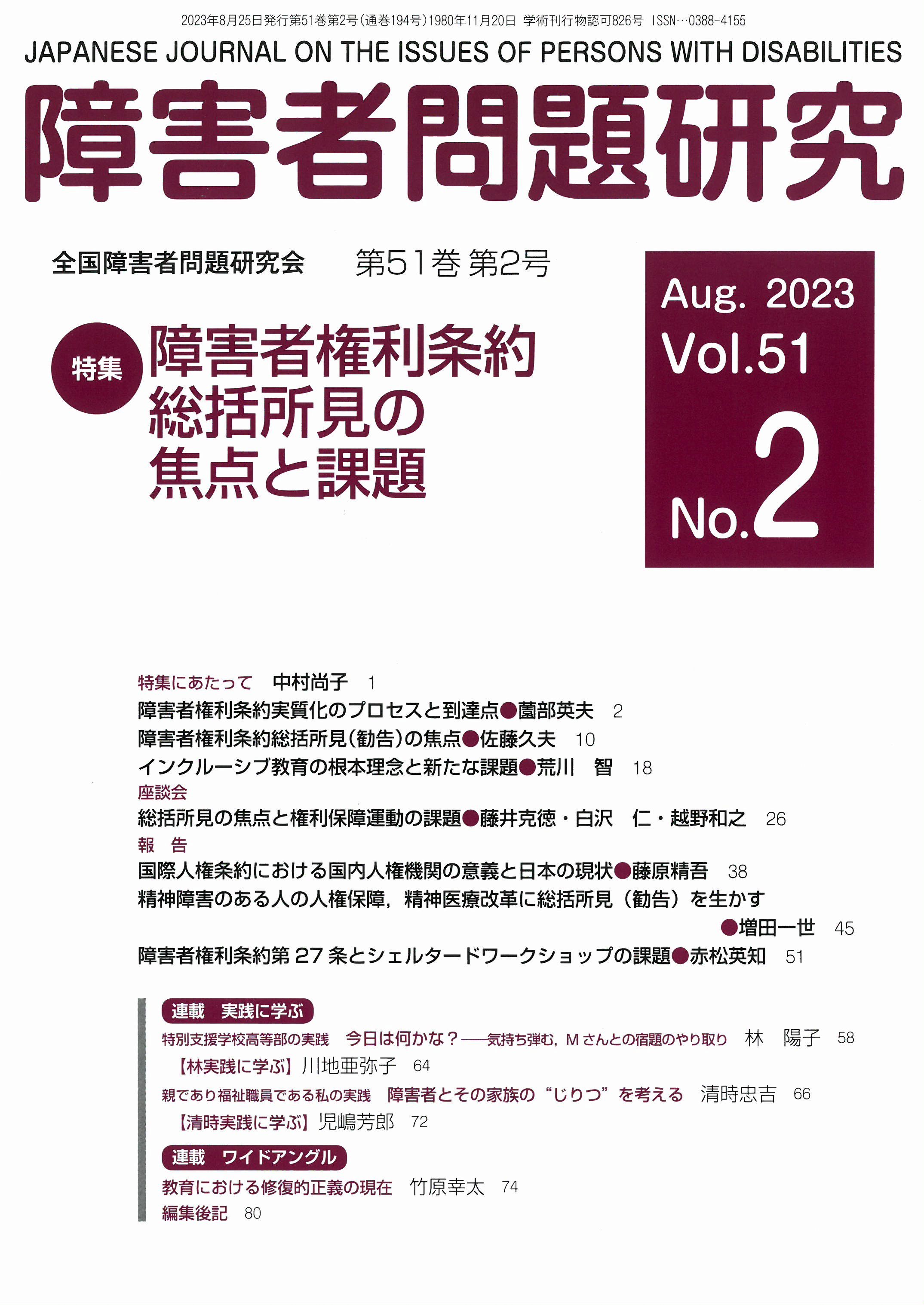
JAPANESE JOURNAL ON THE ISSUES OF PERSONS WITH DISABILTIES
2023年8月25日発行 ISBN-984-4-88134-106-3 C3037 定価2750円(本体2500円+税)
特集 障害者権利条約総括所見の焦点と課題
特集にあたって/中村尚子
本誌編集委員・発達保障研究センター理事長
障害者権利条約実質化のプロセスと到達点/薗部英夫
全国障害者問題研究会副委員長・日本障害者協議会副代表
障害者権利条約(国連,2006)は,第二次世界大戦後の平和と人権保障をめざす国際社会の取り組みの到達点であることを確認した上で,最初に条約の内容と構成について述べた.障害者権利条約には合理的配慮やインクルージョン,アクセシビリティなど,「他の者との平等を基礎として」保障すべき権利が表現されており,人権の発展としてとらえることの重要性を指摘した.つぎに,障害者権利委員会審査による日本政府に対する総括所見(勧告)に向けた日本障害フォーラム(JDF)のとりくみについて,パラレルレポート作成とロビー活動を中心に述べ,主な条文の論点を整理した.権利条約のめざすところを日本社会に実現するには,条約,総括所見(勧告)を深め,障害者の要求にもとづく運動をすすめることが重要である.
障害者権利条約総括所見(勧告)の焦点/佐藤久夫
日本社会事業大学大学名誉教授
まずこの総括所見の勧告の全体像を把握するために,条約の第 1 条から 33 条までの勧告の要点を抽出した.その際できるだけ修飾句を取り除いて具体的な勧告ポイントは何かをみた.ついで,総括所見の直前の「建設的対話」での日本政府の回答を整理した.なお,総括所見を受けた後で,政府のスタンスは変わっている可能性もある.これらの権利委員会や日本政府の見解は,今後の法・政策の改正や自治体の障害者計画の見直しなどに活用できると思われる.さらに,生活,教育,労働の分野について「特別な場」の廃止を目指すよう促す勧告をどう見るか,そして権利委員会の役割などその背景を考察した.権利委員会はデータに基づいて日本がこれらの分野で条約とは逆行または停滞していると評価し,そのことを明確に指摘した勧告となった.日本政府に逆行・停滞の認識はないと判断したからと思われる.
インクルーシブ教育の根本理念と新たな課題/荒川 智
茨城大学名誉教授
本稿では,障害者権利委員会の総括所見を踏まえ,障害者権利条約,SDG 4 ,2016 年の一般的意見そして最近のユネスコの文書を整理し,インクルーシブ教育の根本理念を再確認すると共に,新たな課題について検討した.すべての学習者の多様性を尊重するというインクルーシブ教育の基本理念を共有するととともに,マルチ・セクションのアプローチ推進や排除のメカニズムのより徹底した分析が必要である
【座談会】総括所見の焦点と権利保障運動の課題
出席者
藤井克徳 (きょうされん専務理事・日本障害者協議会代表)
白沢 仁 (障全協副会長)
越野和之 (全障研全国委員長)
司会 薗部英夫 (全障研副委員長)
報告
国際人権条約における国内人権機関の意義と日本の現状/藤原精吾
弁護士・あいおい法律事務所
報告
精神障害のある人の人権保障,精神医療改革に総括所見(勧告)を生かす /増田一世
公益社団法人やどかりの里理事長・日本障害者協議会常務理事
報告
障害者権利条約第 27 条とシェルタードワークショップの課題/赤松英知
きょうされん常務理事
連載/実践に学ぶ
【報告】特別支援学校高等部の実践
今日は何かな? 気持ち弾む,M さんとの宿題のやり取り/林 陽子 (大阪府立支援学校)
【林実践に学ぶ】
書くことが楽しくてたまらない/川地亜弥子
神戸大学大学院人間発達環境学研究科
連載/実践に学ぶ
【報告】親であり福祉職員である私の実践
障害者とその家族の“じりつ”を考える/清時忠吉
大阪・社会福祉法人いずみ野福祉会 岸和田障害者共同作業所
【清時実践に学ぶ】
「ゆったり」「たっぷり」時間をかけて“じりつ”をめざす /児嶋芳郎
立正大学社会福祉学部
連載/ワイドアングル 第22回
教育における修復的正義の現在/竹原幸太
東京都立大学人文社会学部
▶ご注文は 全障研出版部オンラインショップへ
▶「読む会」情報 9月4日(月)19時~21時 /ZOOM
障害者を排除する日本社会の現実をリアルに、かつ根底からつかみ、尊厳の尊重と平等の実現に向けて力を合わせましょう。
司会・進行 中村尚子(本誌副編集委員長)
【主な発言者】
藤井克徳(きょうされん専務理事)
白沢 仁(障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会副会長)
越野和之(全障研全国委員長)
薗部英夫(全障研副委員長)
■そのほか執筆者からのコメント
■参加者の意見交流
▶申込みはこちらをクリック してください。
▶詳細案内はこちらをクリックしてください
越野和之(奈良教育大学)・児嶋芳郎(立正大学)・「みんなのねがい」編集部編
定価1650円
ISBN978-4-88134-126-1 2023年
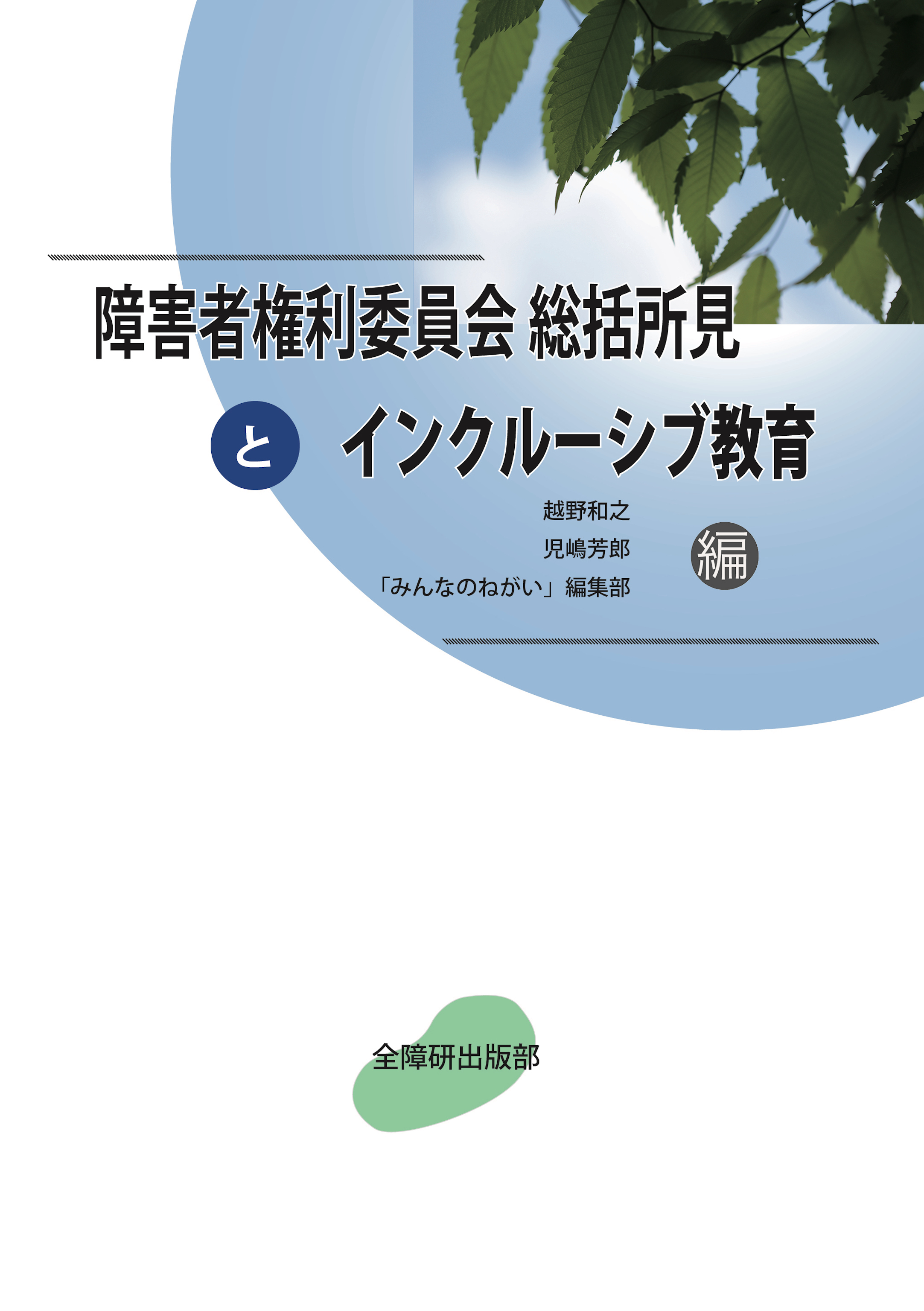
この本を一番読んでほしいのは、現場で日々、奮闘している実践者の皆さんです。「こんな本、読む余裕がないよ」「明日の授業準備もままならないなかで、新しいことを学んでいる時間はないよ」など・・・様々なご意見があるでしょう。
それでも、あえて、伝えたい。忙しいからこそ、目の前のことで精一杯の生活を送っているからこそ、一度、立ち止まり、本書を開いてほしいのです。
目次
はじめに ~実践者の本当の仕事とは何か~
Ⅰ部 いまさら聞けない そもそも編
1 障害者権利条約とは,どんな条約?
2 基礎から教えて Q&A
Q1.条約ってなに? 憲法ではどう決められている?
Q2.条約を締結,批准するということは? 国内法との関係は?
Q3.障害者権利条約っていつ,だれがつくったものなの?
Q4.障害者権利条約は日本国内でどんな意味があるの?
Q5.子どもや教育のことはどこに書かれているの?
Q6.国連「障害者権利委員会」の審査,勧告とは?
Q7.国連「障害者権利委員会」とは,なに? どんな人がいるの?
Q8.一般的意見(GeneralComments)とはなに?
Q9.日本の審査はどのように行われたの?
Q10.日本政府は,障害者権利委員会にどのような報告をしているの?誰が書いているの?
Q11.パラレルレポートってなに?
【資料】.障害者権利条約の構造と内容.
【資料】.障害者権利条約 第7条 第24条
【資料】.障害者権利条約 第34条~40条 (抜粋)
Ⅱ部 国連・障害者権利委員会総括所見 (権利条約24条)を読み解く
1 全障研 委員長談話を読む
【資料】.国連障害者権利委員会「日本の報告に関する総括所見」
教育関係の内容(第51項および第52項)の仮訳(越野訳)
2 特別支援学校の現状と課題
3 インクルーシブ教育への展望
Ⅲ部 学習と議論を深めるための資料
1 すぐに役立つウェブページ
2 全障研の教育改革提言(2010年3月3日)
3 全教障教部の総括所見に対する見解(2022年11月9日)
4 文科省4・27通知(2022年4月27日)
5 大阪障害児教育運動連絡会の文科省4・27通知に対する見解(2022年9月22日)
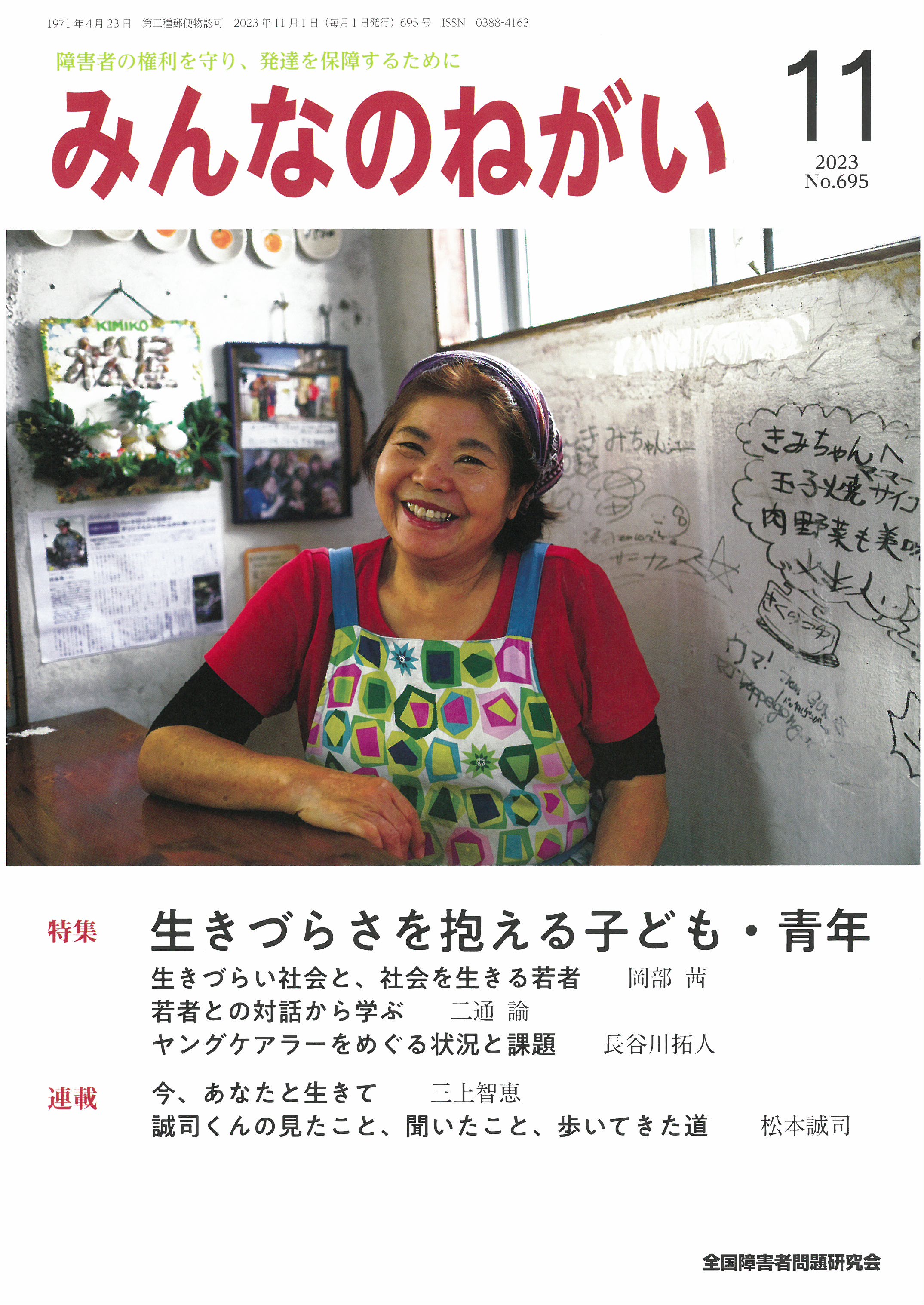
<表紙のことば>
僕は食堂が好きで、全国を旅して撮影をするなかで必ず各地の食堂を探し訪れている。いい食堂の条件は味付けや値段、店の雰囲気などいろいろあるけれど、一番は店主だと思う。沖縄県コザの松屋食堂は、味も雰囲気も抜群の老舗食堂。店主のきみちゃんの人柄と腕で長く地元の人達に愛されてきた。沖縄そばとカツ丼で満腹になって、きみちゃんの笑顔で幸せになった。
残念なことに、撮影してから一年後の夏、きみちゃんは亡くなったと聞いた。地元の人はきっとアンマーが死んだように悲しんだに違いない。この写真を見るとあのときの味と幸せな気持ちが浮かんでくる。写真を残せて、よかった。
土佐和史 とさかずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある。
<目次>
1 人として/石井裕也(映画監督)
2 【インタビュー】今、あなたと生きて/三上智恵(映画監督・ジャーナリスト)
4 この子と歩む/竹中柳子(鹿嶋市)
7 私のタカラモノ/中垣内風雅(奈良)
8 仲間がいっぱい ひろしまの療育/幸田千代子(広島市北部こども療育センター)
11 世界の風 オーストラリア/瀬見さち子
特集 生きづらさを抱える子ども・青年
12 「生きさせろ!」生きづらい社会と、社会を生きる若者/岡部 茜(大谷大学)
14 「自分の存在」を肯定するということ/早川一穂(児童養護施設)
16 ゆっくり、休んでいいんだよ/さらしな ゆう(相談員)
19 発達障害や精神的な困難を抱える若者との対話から学ぶ/二通 諭(札幌大谷大学)
22 ヤングケアラーをめぐる状況と課題/長谷川拓人(成蹊大学大学院)
24 発達のなかの煌(きら)めき/白石正久(龍谷大学名誉教授)・白石恵理子(滋賀大学)
28 社会をみる/杉田真衣(東京都立大学)
30 福祉現場の今を読み解く/田中智子(佛教大学)
32 基礎から学ぶ 障害と医療 脳性まひ/柴田実千代(小児科医)
34 私ときょうだい/福嶋祥暁(奈良)
36 実践の魅力/富井奈菜実(奈良教育大学)
39 支部だより/高橋誠衛(新潟支部)
40 発達保障インタビュー バトンゾ→ン/土岐邦彦(元岐阜支部長)
42 みんなのひろば
44 ニュースナビ 障害のあるひとり親の児童扶養手当併給調整違憲裁判/本誌編集部
46 誠司くんの見たこと、聞いたこと、歩いてきた道/松本誠司(高知)
47 BOOK/編集後記
裏表紙 心のことば 島田伊織
デザイン・イラスト うじたなおき、永野徹子、橋野桃子、細川茉莉
▶ご購読は出版部オンラインへ
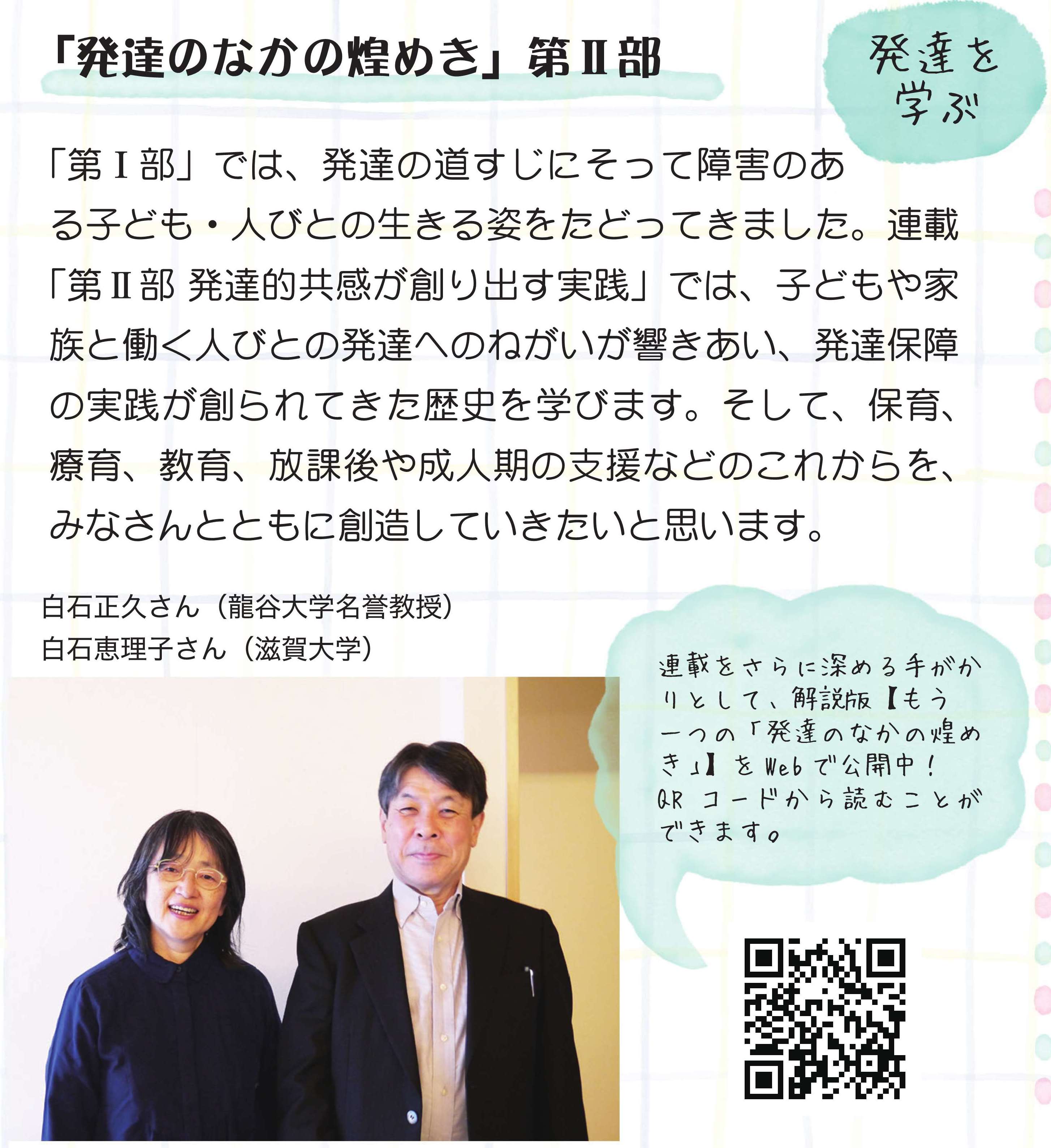
2023年10月 白石正久・白石恵理子
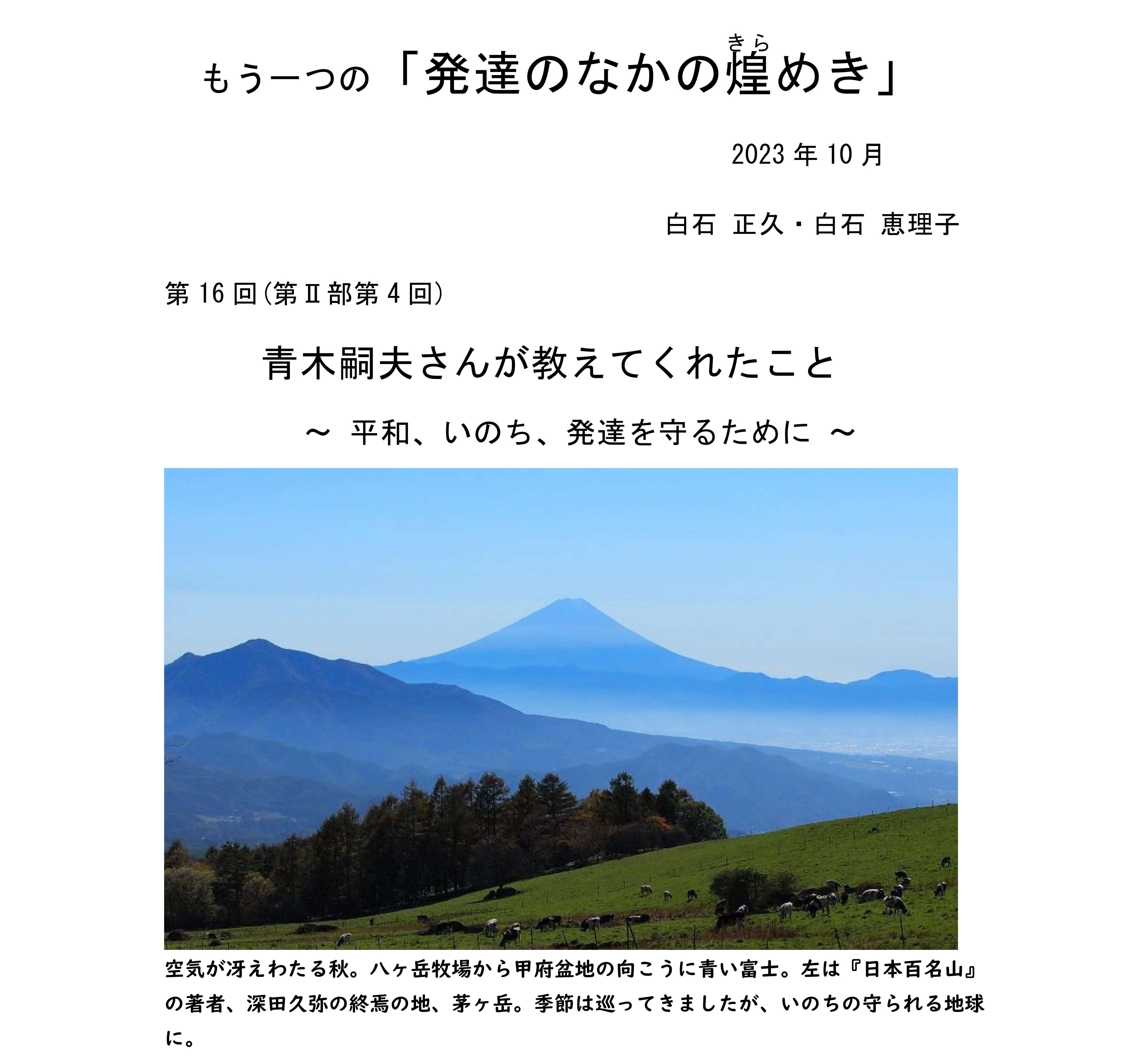
はじめに
私たちは、本年8月5日、6日に開催された全国障害者問題研究会(全障研)第57回全国大会(オンライン)で記念講演を担当しました。その時間を共有してくださったみなさんに、あらためて感謝を申し上げます。
記念講演、連載「発達のなかの煌めき」(以下では「連載」)では、糸賀一雄さん(第Ⅱ部第1回)、青木嗣夫さん(第Ⅱ部第5回)について、それぞれの果たした役割、遺された言葉を、私たちの思いとともにお話ししました。それは、その偉業を伝えしようとしたのではありません。時代が問いかけてきたことに対して、二人がどう向きあおうとしたのか、いかに自他と葛藤しつつ、力をあわせて時代を切り開こうとしたのか。その過程に、私たちが自らを重ねて学ぶべきことがあると考えてのことでした。
「連載」第Ⅱ部第1回、「もう一つの『発達のなかの煌めき』」(以下では「もう一つ」)第13回(第Ⅱ部第1回)で述べたように、近江学園の創設者・糸賀一雄さんは、第二次世界大戦で召集されながら病によって解除され、旧制中学の友人のほとんどを戦地で失ったことを、「生き残った」と語っていました。無数の生命が消えていく事実をまのあたりにし、国民の一人として自らの戦争責任を問いつづけたのでした。糸賀さんにとってその問いへの答えは、言葉や観念で表現されるものではなく、ただ実践においてでした。当時の未発表稿で次のように記しています。
「それは(近江学園建設のこと-白石註)、日本の社会事業一般に対する反省であると共に、教育そのものの反省でもあり、何よりも日本人そのものの反省と再建の道行であると信ずる。(中略)たとえ高尚なものであっても、画餅に等しい様なお説教を聞くよりは、生々しい事実の方が、人の胸を打つことを知っている。事実が何ものにも増して雄弁である。我々は苦しんでいる。この苦しみの事実を打ち明けて、一人でも多くの仲間と共に、更により高い苦しみに突進して行きたいと思う」(『糸賀一雄著作集Ⅰ』日本放送協会出版、176ページ、1982年)。
青木嗣夫さんの『凛として生きる』
青木嗣夫さんは、「連載」第Ⅱ部第5回でお話ししたように、障害のある子どもの教育権が保障されていなかった時代の1970年に本格開校した京都府立与謝の海養護学校(現与謝の海支援学校)の建設運動の中心にあり、後に同校の副校長、校長となりました。「連載」では全文を紹介できなかった与謝の海養護学校の校歌「ぼくらの学校」の歌詞を紹介します(現在は、校歌とはされていない)。
ぼくらの学校
一 おとうさん おかあさん せんせい
ちいきのひとたちが
しょめいあつめて ようきゅうにいった
あしのわるいぼくだって
ねたままのいづみちゃん
はいれる学校つくろうと
ぼくも てがみをかきました
二 おかあちゃん きいてや
あのこがだいじにされんかったら
ぼくかて だいじにされないのやで
おむつをしているみいちゃんも
くるまいすのあぐおくん
ぜんこうしゅうかい かいだんを
いつも ささえてのぼります
私(正久)が大学院の学生であったとき、全障研京都支部事務局長の池添素さんとともに、青木さんの生いたち、与謝の海養護学校の建設運動、そして府政が変わったもとでの教師としての日々をインタビューし、京都支部研究誌『夜明け』第10号「実践家群像5 発達の主体をみつめて-青木嗣夫先生の巻」(1986年)として投稿しました。京都支部のご了解を得て、添付いたします。
全障研大会の記念講演でお話ししたように(註1)、インタビュー当時、すでに京都府政は、「憲法を暮らしに生かそう」を掲げた民主府政から自民党府政に変わり、青木さんは1年ごとに勤務校の異動を強いられるなどの理不尽を被っていました。しかし、「障害児教育のなかで身につけたことが、一般の教育のなかで、どのように通用するのかを確かめる実践的検証の任務がある」と地域の学校に赴かれていたのです。
どこまで書いてよいものか、「発達の主体」などと書く私の筆によって青木さんが教育行政から難じられることにならないかと不安に思いながらお見せした草稿について、「事実は事実として残していくことが大切だと思いますので、このまま掲載してください」とご返事をいただきました。20代であった私は、思わず背すじが伸びたことを、昨日のことのように思い出します。
このインタビューのおりにいただいたのが、「実践家群像」でも紹介した名古屋・舞鶴学徒動員空爆体験記録編集委員会『凛として生きる―学徒動員の鎮魂歌―』でした。そのなかに「号泣」と題された青木さんの文章がありました。京都師範学校(現京都教育大学)から学徒動員され、名古屋に、そしてそこでの空襲後に舞鶴に移った青木少年は、空襲で親友の「起須君」を失いました。その遺体を自らの手で荼毘(だび)にふし、終戦によって帰郷を許されたのちに、遺族の元に遺骨を届けた日の情景が綴られていました。玄関で青木さんの腕から遺骨を奪い取るようにして抱いた起須君のお父さんの号泣の姿が書かれていました。
「私たちの教師としての生活に、一人の人間としての生きざまの中に、消すことの出来ない、いや、けっして消してはならない『宝』として持ちつづけてきたもの、それは『花もつぼみの若桜』として名古屋から舞鶴への学徒動員の中で見てきた戦争であり、人間の生と死であり、生きざまであった。工場で働き、空襲に会い、寄宿舎を消失し、親友の死に出会い、この手でまるで魚でも焼くかの如く長い鉄棒で親友を荼毘にふした悲しくもきびしかった経験。十七歳の少年が経験した事実であった。
同じ村の出身『起須君』を失った私は、毎年お盆が来ると墓前に立ち『君の分も仕事する。僕は二人分の仕事をせんなん』と年に一度ではあるが決意しつづけてきた。近年は、『果して二人分の仕事が出来たろうか』と自省しつつ、名古屋、舞鶴の経験をもち、戦後そのものを生きてきた教師として、『一体何を後輩に伝えるべきか』を考えさせられている」(青木嗣夫『未来をひらく教育と福祉』15~16ページ、文理閣、1997年)。
この言葉の通り、少年の日の戦火と親友の死が、青木さんの人生と生きる姿勢のなかに、いのちと平和を守ることへの妥協のない意志を鼓舞しつづけました。その希い(ねがい)が、いかなる存在に対してもその意味と価値を守り、発達を信頼しつづけた実践と運動の原動力になったのです。
子どもや親が、生きること働くことの意味を教えてくれた
このような先人たちの経験にふれたとしても、自分自身のことと重ねて考えることはむずかしいし、まして戦争経験もない私たちが、同じような信念をもってがんばることにはならないかもしれません。しかし私たちも、あるときに障害のある人びとやその家族と出会い、この人たちの幸福のために働きたいという思いをもって、教育や支援の仕事に就いたのです。
今、私たちの生きる時代は、新自由主義が席捲(せっけん)しています。個人としての成果、効率が求められ、そのための技能・スキルに疎い人間は、自分の不器用さをいやというほど思い知らされます。競争、分断、孤立が心に棲みついてきます。さらには、さまざまな「非正規」の雇用形態が拡大し、低賃金や不規則・長時間労働が多くの人を苦しめています。そのなかで自分の生きる意味や働く意味、存在の価値を感じとっていくことは、たやすいことではありません。生活の現実は、戦争の時代とは異なった「生存の危機」を私たちに強いています。
しかし、そういった桎梏(しっこく)があるからこそ私たちは、この矛盾多き社会と時代が問いかけてくることに対して背を向けず、自分なりの答えを探しながら生きようとしています。そして、障害のある人びと、家族が、私たちが背負う困難にも増して、この社会のなかでの障害という困難を引き受けて生きる姿に、その荷をわかちあうことができないかと思い立ちました。この時代のなかで私たちと障害のある人びとの二つの人生が出会い、その接点で私たちは自らの生きる意味を問いつつ、この仕事を選択したのです。その選択の背景にあった一人ひとりの希いは、私たちの心に深く刻まれ、生きる力そのものになってきたのではありませんか。そのころの自分を忘れずに、そして同僚のこころざしに耳を傾けて、前を向いて歩いていきたいと思います。
青木嗣夫さんの次の言葉は、障害のある人びとやその家族によって生かされているということの意味を、思い出させてくれるものです。
「私が人間として生き、教師として生きてきたその支えと勇気を、子どもたちがくれました。一介の平教師でありながら、(養護学校の建設を要求して-白石註)府庁の秘書課に一人で乗り込んで、知事に会わせてほしいと何時間も粘ったこともありました。それは私個人の問題ではなくて、私にそういう力を与えてくれた地域、親、子どもたちの強い強い要求がそこにあったからです」(前掲書、219ページ)。
良心に立ち返って生きる
私は、大学を出てから発達相談員という仕事に就き、全障研京都支部の事務局員として活動しました。当時、京都支部長であった青木さんは、本を買うことにも窮していた私を心配して、自身が関係していた保育園の講演会などに何度か招いてくださり、その道すがら、いろいろなことを聞かせてくれました。そのなかに、忘れることのできないくだりがありました。
最近、後輩の教員からしばしば受ける相談がある。「管理職への登用を打診されている。これまで教職員組合や地域の運動でがんばってきた身として、どう対応したらよいかと悩んでいる」と。青木さんは、自民党府政になって早晩、民主府政時代の教育理念、体制を「ひっくり返そうとする」力がはたらくことは予期していました。実際に、一人ひとりの発達要求と発達への権利を認めあい、集団のなかでの豊かな人格の発達を実現していこうとする「発達保障」という理念は、実践の場から排除されていきました。
そして青木さんは、私にこう言われました。「肩を叩かれている本人が一番つらいと思う。名を捨てて実(じつ)を取るという言葉もあるが、折りあいをつけるということは、大事なことを守りつつ、ものごとを進めていくうえでは大切なことだ。ただ、自分が障害のある人や社会的に弱い人のために働こう、そのために社会を変革していこうと決意した信念までを捨てないことが大切ではないか」。ハンドルを握りつつそのことを語られる姿は、30年を経過した今でも私の心に残ります。それは、私に対しても、語ろうとして語ってくれた思いだったのでしょう。
青木さんに相談を寄せた先生方は、やがて管理職、要職に登用され、私たちの研究運動に参加されることはなくなりました。今はもう、教師としての仕事からは勇退し、次の人生を歩かれていることと思います。このことに対して、私から申し上げることはありません。しかし、「肩を叩かれている本人が一番つらいと思う」と語った青木さんの言葉は苦しそうでした。「肩を叩かれている」とは、信念をまげて、私たちのがわに来なさいと促されているということです。青木さんは、その苦しさを、ご自身に引きよせて感じていたのだと思います。今、もし、青木さんが「後輩」たちに語ることができるならば、きっと次のようなことを言われるだろうと私は想います。
苦しかったろう。しかしその時代を君は生き抜いた。今、最初のころの志に戻って、弱い立場の人びとを守るために、そして社会と政治を良くしていくために、みんなと力をあわせたらいいじゃないか。君にもやらなければならないことは、きっとたくさんある。
青木さんが好んで口にした言葉に、「ピンチはチャンス」があります。ピンチの裏には、必ず発展のきっかけが潜んでいる。だから大切に受けとめてその背景を読み解き、ピンチだからこそ人とつながって、学校や地域を変革するチャンスに変えていくという姿勢でした。そこには、人間の良心と復元力への信頼がありました。歴史は、曲折はあっても、人間を抑圧し隷従させようとする力を乗り越えて、一人ひとりが大切にされる方向へと進んでいく。そのことへのゆるぎない確信を感じるのです。それは、これ以上の不正義はない軍国主義の本質を、もっとも純粋な感性と正義感のある年齢で感じ取った人の渇望でもありました。
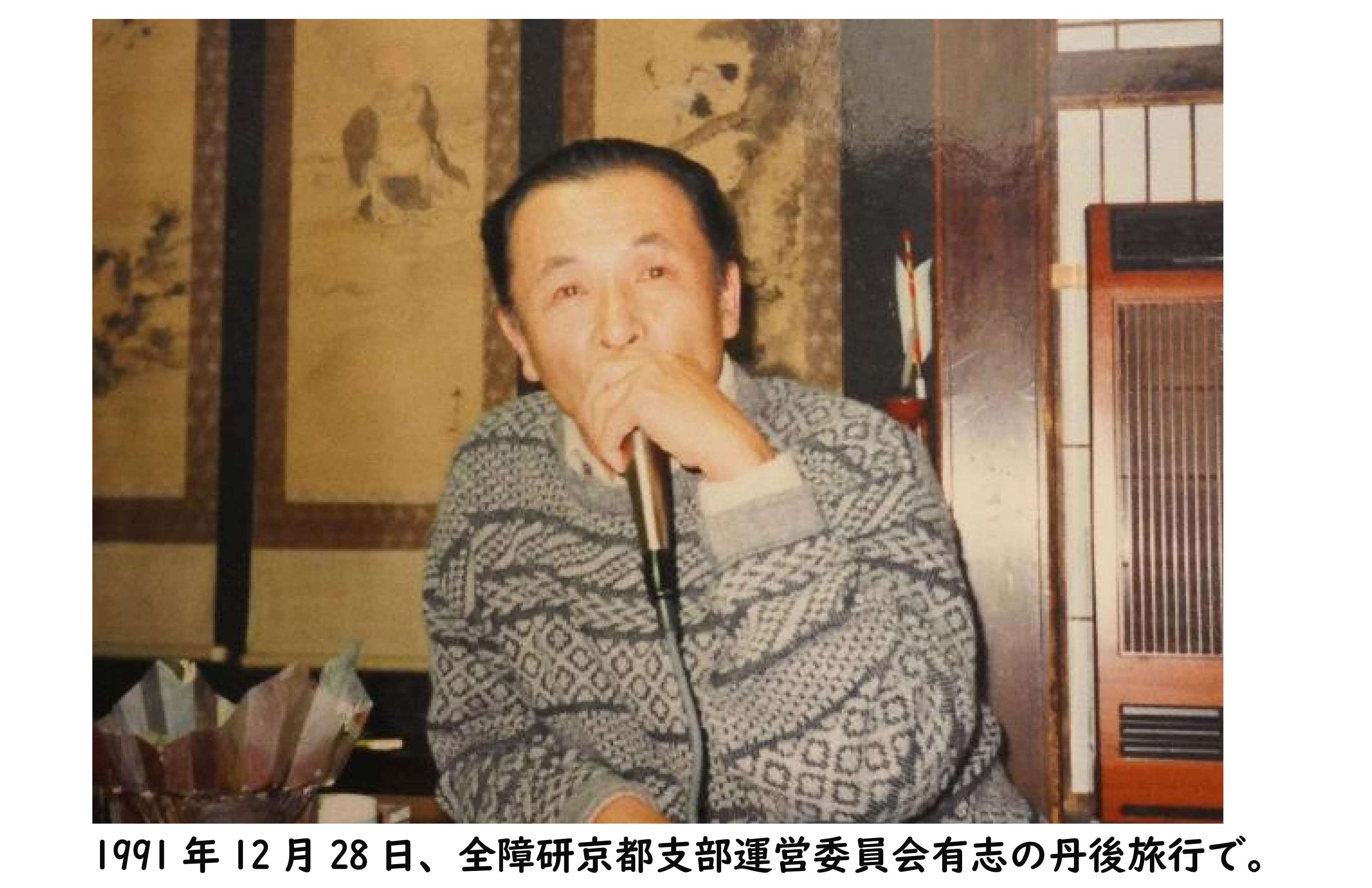
憲法を生かす想像力の発達
糸賀一雄さん、青木嗣夫さん、そして大戦を経験した国民の多くは、その戦争に突き進んだ国のあり方を問い、無力であった自らを反省し、苦しい思いをもって戦後の歩みを始めました。そのなかで形づくられた生きる姿勢や人格は、個人的なものにとどまらず、新しい歴史を切り開こうとする国民のねがいとなって共鳴しあい、日本国憲法を抱く力になりました。その国民のねがいを、憲法の前文がよく語ってくれています。
日本国憲法・前文(抜粋)
「日本国民は、恒久の平和を念願し、人類相互の関係を支配する崇高な理念を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」。
敗戦後に生まれた私たちの世代が、子どものころ、憲法第9条を学んだときの感動も特別なものがありました。私の父は青木さんと同じ歳(1928年生まれ)であり、現群馬県太田市にあった「中島飛行機(現SUBARU)」の戦闘機工場に学徒動員されました。当時、日本本土は米軍による空襲をいたるところで受け、そのアメリカの戦闘機の大きな機影に、米粒のように小さな日本の戦闘機が体当たりし、もろともに砕かれていった光景のことを、一度だけ聞かせてくれました。それから私は、その戦闘機のなかにはどんな人が乗っていたのか、何歳の人だったのか、親はどんな人だったのか、そんな問いをもちつづけました。ですから小学校6年生のときに、日本は憲法で「戦争放棄」を決めているので、もう誰も戦争では死なないと教えられたときの不思議な安堵感は忘れられません。一度だけの父親の話は、私のなかで消えることはありませんでした。ですから、糸賀さんや青木さんの戦争体験とその戦後を記憶として保持しつづけ、しっかりと語り継いでいくことこそ、私たちの世代の役割だと自覚しているのです。
今、世界にはふたたび戦火が燃え立ち、たくさんの生命が奪われつつあります。しかし、ゲームの陣地戦の実況のような報道ばかりがなされ、私たちはそこで奪われていく一つひとつのいのちのことを知ることも想像することもできません。戦火のなかでも、家族の幸せをねがって働き、家族を守りながら暮らそうとする、私たちと変わらない人びとの生活があるはずです。それをたしかに想い描くことができるならば、人も国家も、銃を構えることなどできないはずです。
かつて私は、『みんなのねがい』の連載をまとめた『発達をはぐくむ目と心』(全障研出版部、2006年)の結びで、次のように書きました。
「今、かつての過ちを覆い隠し、アメリカの戦争に加担し戦争を準備しようとする力が強まりつつありますが、再びあの惨禍を経験しなければ、人間の尊厳を再学習できないような愚かな歴史に道を開いてはなりません。時間的に遠ざかろうとも、つねに歴史の教訓に学び、つねに過去よりより良く生きようとする力を人間はもっていることを確信して、学習しつつ歴史を創造する活動を、粘り強く、もっと力強く続けていかなければなりません。
幼き日に父から聞いた砕け散る戦闘機の映像が、私の中でそこにあったいのちへのイメージとして生き続けたように、私たちの学習運動は、常に個別的で具体的ないのちのことを語り継ぐものでなくてはなりません。それは、戦争によって脅かされているいのちとともに、障害をもちながら愛情によって結ばれ育まれているいのちを語ることでもあります。そこには、常にstoryがあるのであり、そのstoryが多くの人の中にあるいのちへの愛情に届いたときに、いのちの営みへの想像力を喚起し、生存と発達を権利として希求する発達保障の理念と運動への共感を呼び起こすことができるのではないでしょうか」。
そこにおいて求められるのは想像力であり、その想像力をはぐくむ土台は、共感の心と言ってよいでしょう。想像力や共感の心は、愛をもって語る生活の営みのなかで、他者やその人の暮らす社会に視座をおいて、考え、想い描くことによって発達していきます。この想像力、共感の発達があればこそ、私たちは、すべての人の基本的人権を真に尊重できる存在になっていくのであり、そのことによって一人ひとりの人間を大切にする社会と国家をつくる条件が準備されていくのです。憲法を本当に生かし守る力は、個と集団における想像力の発達によってはぐくまれていくことでしょう。
おわりに
青木さんは、先に紹介した「実践家群像」の結びで、次のように語りました。
「今、子どもたち(当時、校長をされていたのは野田川町立江陽中学校)に『事実をもとにし、自分の頭で考え自分で自分の意思を決定し、みんなと取り組む力を育てよう』と云っている。(おとなも)きびしい諸状況があるだけにこの事を大切にしながら自分の目の前にある仕事をがむしゃらにやる。そのことによって、展望がひらけ、理解してくれる人もふえるにちがいない。もっとほかにするべきことはないのか、こうしたら、ほかの人はどう思うだろうなどと考えていては、結局、自分の仕事を成し遂げることができない」。
この「諸状況」という言葉には、教育行政の変化によって引き起こされているさまざまな困難のことが包含されています。その困難をあげつらうだけでは何も展望は見えてこない。どうしたらその困難を克服できるか、仲間とともに知恵を絞り、腕を組んで、「がむしゃら」にそれを乗り越えていこうとすることによって道は開ける。青木さんの言葉を、私はそう理解しました。
「がむしゃら」を、今を生きる私たちはどう受けとめたらよいでしょう。血気にはやってふるまうことですが、その一生懸命さが向かっている対象、目的が問われるのだと思います。子どもの要求、親の要求に徹底して学び、それが出されてくる生活の現実を想像、認識し、未来を切り開く要求へと撚(よ)りあわせていく。「連載」第Ⅱ部第5回では、青木さんに学んで、そうお話ししました。同じく「連載」で紹介した「やらんならんときには、やらんならん」(註2)も、教師が自己犠牲的に頑張ることではなく、それが教師の要求でもあり、教師の生きる意味、働く意味を問うていくことにつながるという確信をもって、「がむしゃら」に頑張るという言葉だったのだと思います。そこには、ひたむきに生きる人びととその要求への誠実さがありました。今、問われているのは、「がむしゃらさ」になって現れる「誠実さ」を、私たちも胸に抱けるかだと考えます。働いていくうえでいろいろな困難はあるけれど、それを子ども、保護者、同僚のせいにしたり、諦めたり見限ったりしない粘り強さを信条とすることだとも思うのです。
青木さんの遺した言葉、その生きざまから、「誠実さ」という言葉を、あらためて受けとめたいと思いました。
(註1) 2023年8月5日、全障研第57回全国大会記念講演より。「発達保障の理念への攻撃」
さて、「発達のなかの煌めき」の第Ⅱ部では、「発達の共感」が生まれる実践や生活の場をたどっています。「発達の共感」が成り立つ人間関係は、手をつなぎあう集団となり、要求を共有して社会を変えていく力になります。だからこそ、今のままの政治や経済を維持しようとする人びとにとって、それは好ましいものではありません。
私たちが大学に入学した1978年春、4月、「みなさんの運動に応えて学校をつくりましょう。人間を大切にするとはこういうことだという意味で、日本一の学校をつくりましょう」と与謝の海養護学校の建設を約束し、28年間続いた京都の蜷川民主府政は終わりました。この府政を支えた社会党、共産党の革新統一に楔が打ち込まれたからです。その後、青木嗣夫さんに対して、校長として1年ごとに異動が強要されるなど、理不尽な人事が繰り返されました。しかし、青木さんはこう語りました。「私は最後の最後まで務めようと思いました。そのときに私を支えてくれたのは、筋ジストロフィーの子どもたちや、難病の子どもたちが、やがて自分の体はだんだん萎えていって、終わりになってしまうことを知りながら、なお自分で命を輝かし続けているではないかということです。(中略)あの子どもたちが最後まで灯し火をともし続けるように、私も教師としての灯し火をともし続けなければ、彼らに対しても申しわけない。そんな思いで最後まで務めることにしたのです」(『未来をひらく教育と福祉』文理閣、219ページ、1997年)。
そして1995年、66歳で亡くなったころから、青木さんが「何は失っても、最後まで守らなければいけないもの」と言われていた発達保障の理念への攻撃は強まり、そういったことを研究する研究者は不適切として学校の共同研究から排除され、「発達保障」という言葉を使う自由も制限されました。そして、さまざまな分断が職場にもちこまれました。
そういった経過を身近にみながら、私はむしろ、このあからさまな学問や教育の自由への攻撃にこそ、発達保障の理念の大切さ、消えることのない灯火が映されていると確信を深めてきました。人間の良心は、一度は消えそうになっても、必ず新しい灯火となって輝きます。ふたたび、この理念に心打たれた誠実な青年教師が、子どもの要求を何より大切なものとして耳を傾け、家族が厳しい生活の現実とたたかう姿に心を寄せ、学校や社会を、手をつなぎあって変革していく日がやってくる。そのために、今は、仲間を拡げて、深く発達保障を学習し、学校の内外で子どもや親の要求を聞き、それを叶えるために知恵を出しあうべきときです。何より全障研が、歴史の負託に応えて、発達保障の理念を、胸を張って伝えようとしているかが問われています。
(註2)「やらんならんときには、やらんならん」
添付の「実践家群像5」にあるように、青木さんは1948年4月より、京都府与謝郡加悦町立桑飼小学校で勤務しはじめます。この桑飼小学校に宮津与謝地方ではじめての「特殊学級」(現
特別支援学級)ができ、その担任になります。1954年には宮津市立宮津小学校に転任。翌1955年に、宮津小学校にも「特殊学級」が設置され、その担任となりました。戦後になり、お国や天皇のためではなく、子ども自身のための教育をという運動と実践が燎原の火のごとくに広がっていきますが、そのなかで、「障害を受けている子ども、ちえおくれといわれている子ども、そういう子どもたちを放置しておいて、本当に日本の民主的な教育が確立するのだろうか、できないできないままに放っておいて、できるこどもだけに手厚く教育をしていくようなことで本当に民主教育といえるのだろうか」(『未来をひらく教育と福祉』23~24ページ、文理閣、1997年)という問題意識が強まっていきます。それが、こうした「特殊学級」の開設につながっていったのです。それはまた、「勤務評定闘争」によって、「子どもの発達する権利を守ることと、教職員のしごとの要求・実践・研究・運動や権利要求を統一してとらえること、そして、父母との連帯を強化すること以外に、国民教育の創造は成立し得ないということを身をもって学んだ教師集団の、自己変革をもとにした意識的集団的な取り組みがあったから」(前掲
24-28ページ)でした。
この「特殊学級」での担任を通して、ますます子どもたちの発達の事実に確信を得、学校に行けない(当時は、「知能指数49以下」の子は学校に入れなかった)子を育てる親の涙と切実な訴えを聴くなかで、青木さんたちは養護学校づくりをめざしていきます。そして、1968年からは、京都府立与謝の海養護学校開設準備室に勤務し、1971年4月からは同校副校長、1978年4月から同校校長となりました。
川嶋浩写真・青木嗣夫文『ぼくらはみんな生きている―与謝の海養護学校の実践―』(あゆみ出版、1978)では、養護学校設立からの10年間の歩みが、川嶋浩さんの写真と、青木嗣夫さんの文章で振り返られています。その青木さんの文章のなかに「私たち教職員」という章があります。
そのなかで「やらんならんときは、やらんならん」というのは、教職員集団としての内部規律であったと書かれています。「子どもの変化を喜び、子どもの変化に学び、親の要求に耳を傾け、親の要求に学び、仲間の鋭い指摘を発達の糧として、仲間とともに歩む」教職員、「〝すばらしい子ども集団を育てるためには、より質の高い教職員集団がなければならない〟といい合って歩んできた」教職員、何事も集団で話しあって進めてきた教職員だからこそ、いろいろと状況を分析し、集団の民主的協議で合意決定したら、決定したことは必ずやりきる。それが「やらんならんときは、やらんならん」に込められていると言います。きびしい外的状況があるなかで、「時には外的な原因を内部の矛盾と考え、仲間の間で激しい討論をし、時には、子どもの権利を守ることと教職員の労働条件を対立的にみて、自己矛盾に陥りかけた」こともあったのですが、そのたびに、また議論をしながら乗り越えてきたなかでの確信でもあったのでしょう。
たとえば、寄宿舎で赤痢が発生したときには、本当に厳しいとりくみがありました。学校は休校措置になるのですが、寄宿舎の子どもたちを家に帰すことはできず、休校期間中、どうするのかが大きな問題となりました。寮母(現
寄宿舎指導員)だけで対応することはできないため、全教職員が特別勤務の体制を組んで、一般教職員も寄宿舎に入ったり、健康な子どもは登校させて学校で対応したりしました。地域の病院の隔離病棟に入る子もいたのですが、障害があるということもあり、付き添いが求められました。しかし親の生活にも余裕がないなか、教職員が隔離病棟に入って子どもに付き添うことになったのです。いったん入ると1週間や10日は出てこられないのですが、職員会議の議論で、「私が入りましょう」と希望者が次々と挙手をしたそうです。実際に病棟に入ると、画用紙、クレヨン、絵の具など差し入れてほしいと声が出され、隔離病棟の中でも教育活動が組織されていきました。
赤痢が完全になくなるまでに2週間がかかったのですが、その総括をするなかで、「衛生指導、保健指導」の課題とあわせて、「教育と医療の統一的保障」の課題などが深められます。そして何よりも一つの方向に向かって全体が団結してとりくむことによって、大きく組織的力量を前進させることができたと言います。
学習参考文献
青木嗣夫『未来をひらく教育と福祉』文理閣、1997年。
池添素・白石正久「実践家群像5 発達の主体をみつめて-青木嗣夫先生の巻」『夜明け』第10号、111~119ページ、全障研京都支部、1986年。
川嶋浩写真・青木嗣夫文『ぼくらはみんな生きている―与謝の海養護学校の実践―』あゆみ出版、1978年。
白石正久『発達をはぐくむ目と心-発達保障のための12章』全障研出版部、2006年。
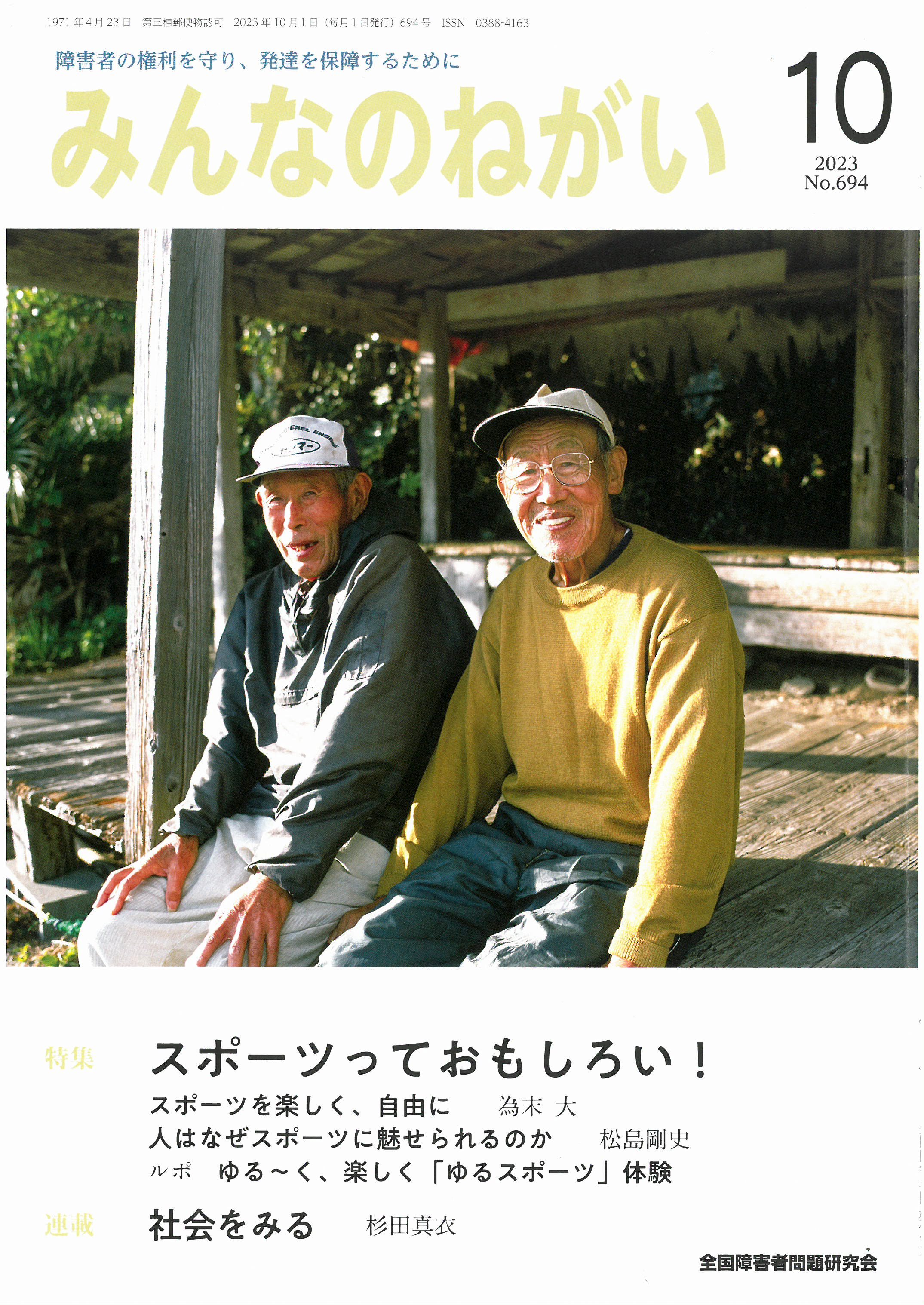
<表紙のことば>
房総半島には幾つもの港町や漁港がある。夕方になると地元の住民や漁師たちが海沿いに出てきて集い、一日の出来事や世間話を持ち寄り海を見ながら夕暮れ時を過ごす。昼間は人影が少ないが賑やかなその時間帯は僕も撮影の書き入れ時になる。
朽ちた木のデッキに座る老人たち。いつもの溜まり場なのだろう。聞くと二人とも100歳近い現役の漁師だと。その顔つきは本当に穏やかで、この土地で長い間生きてきた年輪を夕陽が照らし出しているようだった。
僕にもうひとつの人生があったら漁師がいいなあなんて、憧れの眼差しで彼等を見ていた。
土佐和史 とさかずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある。
<目次>
人として/中村哲郎(堀江車輌電装・未来創造事業部)
【インタビュー】今、あなたと生きて 三上智恵(映画監督・ジャーナリスト)
この子と歩む/上川かずみ(三重)
私のタカラモノ/佐藤優樹(山梨)
仲間がいっぱい ひろしまの療育/吉岡美帆(なぎさ園)
世界の風/瀬見さち子(オーストラリア在住)
特集 スポーツっておもしろい!
ルポ ゆる~く、楽しく 「ゆるスポーツ」体験
スポーツを楽しく、自由に/為末 大(Deportara Partners代表)
私とスポーツ/土佐朝一、福島千支、西 陽平、澤佐景子、木戸俊介、大和田章
スペシャルオリンピックス(SO)世界大会ベルリン2023に参加して/下田有輝(長野)
人はなぜスポーツに魅せられるのか/松島剛史(立命館大学)
発達のなかの煌(きら)めき 白石正久(龍谷大学名誉教授)・白石恵理子(滋賀大学)
社会をみる/杉田真衣(東京都立大学)
福祉現場の今を読み解く/田中智子(佛教大学)
基礎から学ぶ 障害と医療/柴田実千代(小児科医)
私ときょうだい/小倉義昭(滋賀)
実践の魅力/小林達朗(東京)
支部だより/濱田健太(岩手)
発達保障インタビュー バトンゾ→ン/土岐邦彦(全障研岐阜支部)
みんなのひろば
誠司くんの見たこと、聞いたこと、歩いてきた道/松本誠司(高知)
ニュースナビ マイナ保険証問題/本誌編集部
全障研第57回全国大会報告
BOOK/編集後記
裏表紙 心のことば 島田伊織
デザイン・イラスト うじたなおき、永野徹子、橋野桃子、細川茉莉
▶ご購読は出版部オンラインへ
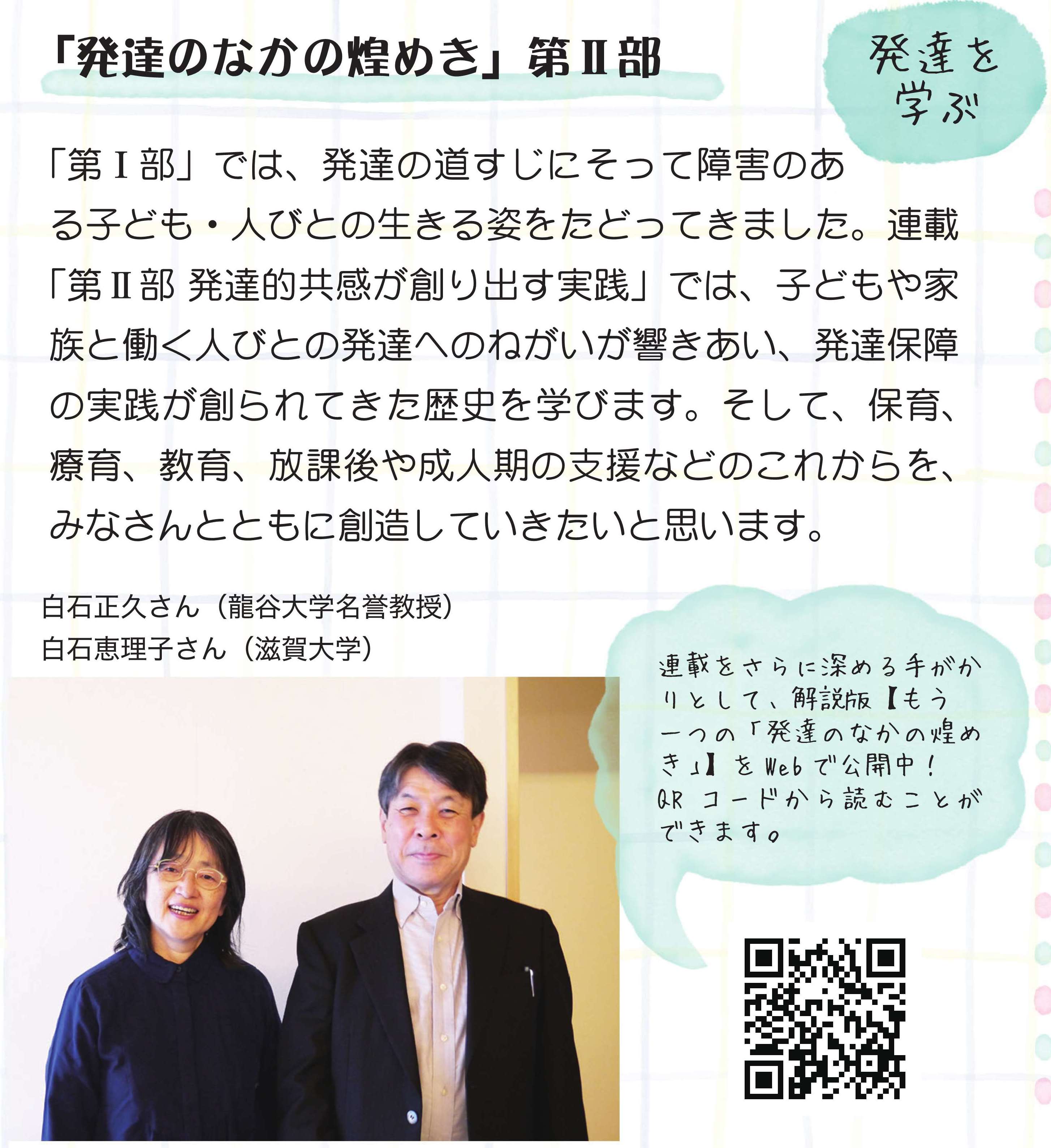
全国障害者問題研究会
定価3960円
ISBN978-4-88134-116-2 C3036 2023年
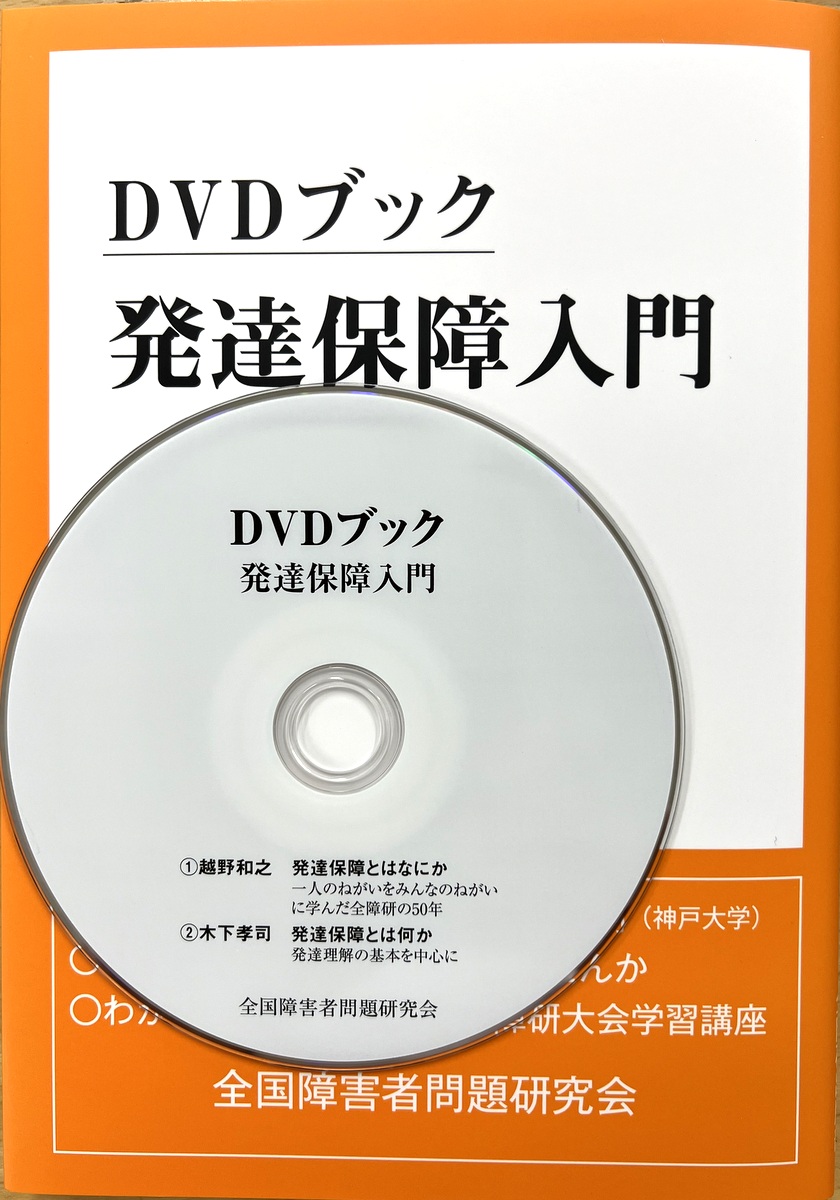
本書は、「発達保障とはなにか」を学びあうために、全障研全国大会学習講座の講演を編集したものです。各全障研支部やサークルで、また各職場や地域などでご活用いただき、発達保障を学び合う輪を広げていただければ幸いです。全国障害者問題研究会
1 越野和之(奈良教育大学・全障研全国委員長)
発達保障とはなにか
~一人のねがいをみんなのねがいに学んだ全障研の50年
第55回全国大会学習講座2021年
1 全障研の50年
2 全障研の結成と発達保障という考え方
▼滋賀県立近江学園での「発達保障」理念の提唱(1961)
▼日教組全国教研(1951年~)特殊教育分科会から障害児教育分科会へ
▼養護学校義務制実施以前の障害児者・家族の状況
▼「車の両輪」 全障研と障全協(障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会)
3 全障研結成以後の半世紀
▼学校教育
▼青年期・成人期
▼国際的には
▼母子保健・児童福祉
▼障害者権利条約と障がい者制度改革推進会議
▼憲法26条に基づく教育権の保障を出発点として
4 発達保障論のいくつかの合意
▼障害のある場合を含んだ「発達のすじみちとしくみ」
▼発達概念の拡張
▼発達保障の方向性
▼発達保障の三つの系
5 今日的な課題との関わりで
▼障害のある人たちとその家族の人間的諸権利の保障の到達点とそれを突き崩そうとするもの
▼「あのころよりも今は条件がある」(浜端武、上杉文代。2008)
6 発達保障論の発展の契機ー「教育実践」というしごと
▼「教えるなかでつかむ」ということ
▼「子ども理解」と「実践」の弁証法
▼「弁証法」=試行と錯誤をはらんだ発展をー誤りを「よき誤り」に
▼「ひとりぼっちをなくす」こと
▼「自主的・民主的な研究運動」の意義
2 木下孝司(神戸大学)
発達保障とは何か
~発達理解の基本を中心に
第56回全国大会学習講座2022年
Ⅰ 「発達」のイメージ、発達観
1 どんな「発達」を大切に(保障)するのか?
2 「ヨコへの発達」について
▼『夜明け前の子どもたち』なべちゃんのとりくみから(実践から学ぶ1)
▼「ヨコへの発達」という視点で変わるもの
3 発達は要求からはじまる自分づくり
▼乳児期から幼児期にかけての変身
▼「いちばん」へのこだわりの背景にある発達要求(実践から学ぶ2)
▼「問題行動」は発達要求のあらわれ
Ⅱ 先人のねがいを実現させてきた原動力 歴史をふりかえって
1 権利としての発達
2 発達の3つの系
▼集団の発達
▼社会の発達
Ⅲ 発達理解の基本
1 発達の質的転換
2 連関をおさえる視点
▼機能連関
▼発達連関
3 発達の原動力
▼発達の謎
▼指導の役割
▼「涼む」文化を学ぶ授業(実践から学ぶ3)
4 さらに理解を深めていくために
▼発達の視点
▼障害の視点
▼生活の視点
◆DVDメディア以外の視聴方法
本書ご購入のみなさんで、機材や旧いバージョン(Windows10以下)などによってDVDメディアで視聴できない場合には、専用のYouTube動画をご視聴いただけます。全障研出版部にお問い合わせください。
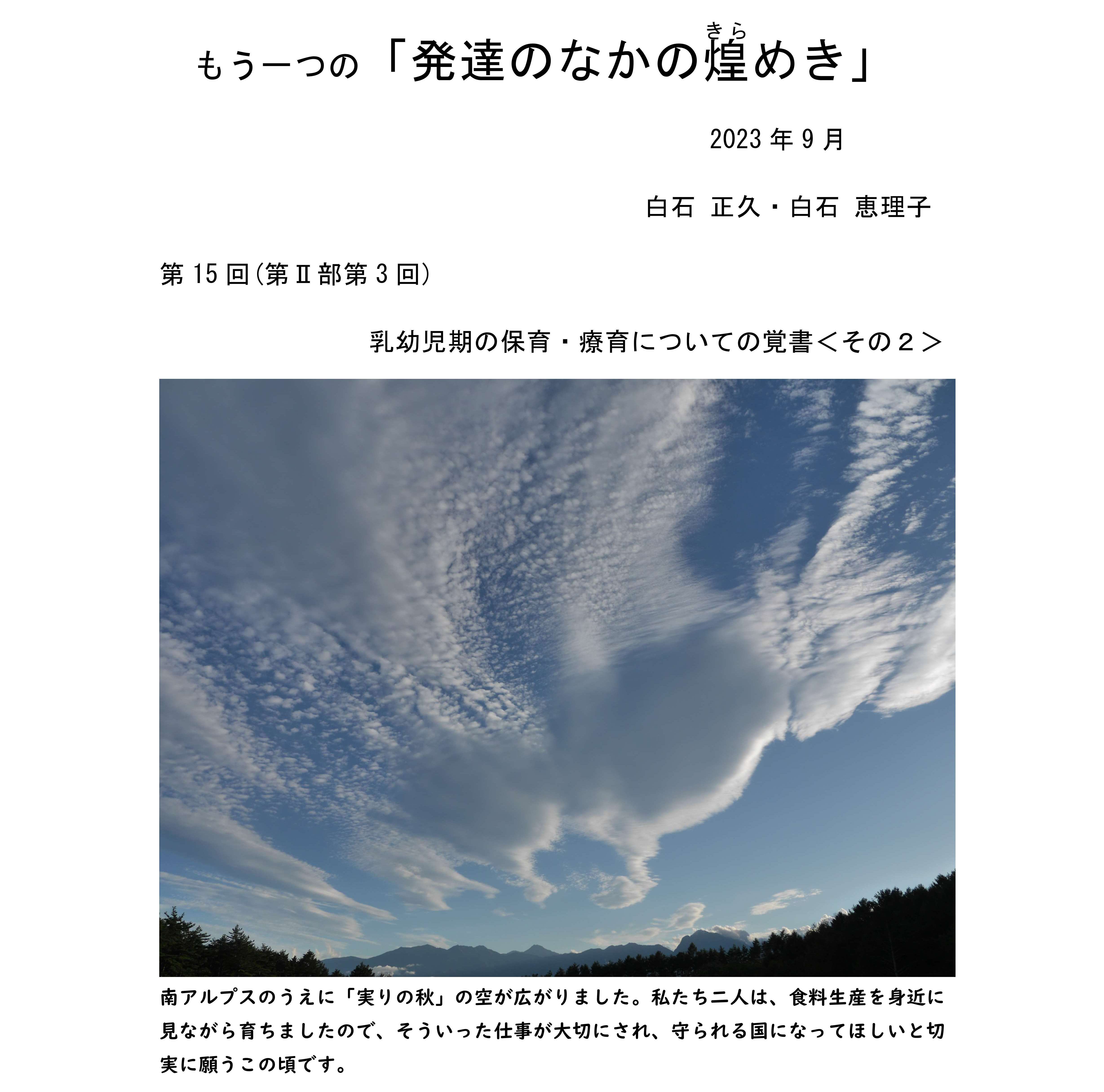
今回は、障害のある子どもたちに対する児童発達支援等での療育や保護者支援にかかわって、「行動理論」を背景とする行動療法・応用行動分析等について考えていきます。
「療育」とは何か
そもそも「療育」という用語は、「肢体不自由児の父」とも呼ばれた高木憲次(1888-1963)によって提唱されました。整形外科医であった高木は、肢体不自由児(この「肢体不自由」という用語も高木の提唱によります。当時は侮蔑と憐れみの意味が強い「片輪」「不具」といった呼ばれ方をされていました)に対し、外科的治療だけではなく、医療、教育、職業の機能を兼ねた施設が必要と考えました。整肢療護園(現
心身障害児総合医療療育センター)にある記念碑には、「療育の理念」として、「児童を一人格として尊重しながら、先づ不自由な個処の克服につとめ、その個性と能力に応じて育成し、以って彼等が将来自主的に社会の一員としての責任を果たすことが出来るように、吾人は全力を傾盡しなければならない」と刻まれています。
1970年代になると、養護学校の設置も少しずつ進み、それまで就学猶予・免除の対象となっていた学齢期の障害児を受け入れていた通園施設等が、就学前児を対象とするようになります。あわせて、未就園児を対象にした早期支援の場も少しずつできはじめます。そのなかで、就学前の障害幼児を対象とした支援に対し、一般の保育と区別して「療育」「早期療育」という用語が使われることが増えていきました。もちろん、子どもの障害によっては医療や機能訓練的取り組みも重要になりますが、多くの知的障害児や、自閉スペクトラム症などの発達障害児に対しては、必ずしも医療や訓練は必要ではないでしょう。また、障害があっても、一人の子どもであることに変わりはありません。医療や訓練を必要とする場合であっても、子どもらしい生活やあそびを保障することが求められます。つまり、医療や訓練の必要性の有無にかかわらず、生活やあそびをベースとした通常の保育を子どもの発達のペースにあわせてゆったりと保障していくことが「療育」の基本であると考えます。ただ、はじめて「療育」という言葉を聞いた人は、通常の保育とは異なったもの、「医療」「治療」の意味合いが強いものという認識をもつことは想像できます。
健診等で何らかの「発達的つまずき」が見つかり、「療育に行きませんか」と勧められた保護者からすると、通常の生活やあそびだったら保育所や幼稚園と変わらないし、あえて「療育」に通わせる意味はどこにあるのかという疑問をもつのは当然です。子どものかかえる遅れやつまずきを「治す」ための特別な手立てをしてほしい、集団ではなく個別に対応してほしいと多くの保護者が願うでしょう。
1歳半健診でことばや指さしが見られず、その後の経過観察を経て2歳から療育に通うようになったAくんのお母さんは、「療育に通い始めたけれど、散歩や水遊びばかりで、いつになったら“ことば”を教えてくれるんだろうと不安になった」「これだったら、わざわざ通う必要がないのではないかと思っていた」と話してくれました。しかし、通い始めて数か月後の親子保育の日、いつものように水遊びをしていたAくんが、水に触れる心地よさと、手にあたってはじける水滴の面白さに目を見開き、そばにいたお母さんの顔を見てニッコリ笑います。そのとき先生の「お母さん、これがことばの芽なんだよ」ということばを聞き、はじめて水遊びの大切さを知ったそうです。そして、「私は子どもの器に詰め込むものばかりを探していたけれど、器の入り口を広げるのも療育なんですね」とも語ってくれました。
こうした発達支援を必要とする子どもたちにとって、一人ひとりにあわせてゆっくりじっくりかかわることは必要ですが、それは「個別支援」を意味するものではありません。保育所等の大きな集団では自分を出しにくく、部屋を飛び出したり、カーテンのなかにくるまってしまいやすいけれども、小集団である療育の場では、お友だちの顔をのぞきこんだり、友だちがするあそびを憧れのまなざしでじっと見ていたりということもよくあります。重い障害のある子どもたちも、おとなと子どもの違いはよくわかっています。友だちに憧れ、友だちに憧れられ、ときにぶつかったり、笑いあったりと、多様な応答関係を積み重ねることで育っていくのは、障害のある子、発達支援を必要とする子も同じです。こうした姿は個別の療育では決してみられません。つまり集団か個別かの二者択一ではなく、その子が自分らしさを発揮できる集団を求めているのだと言えるでしょう。
こうしてその子にあった日課と集団のなかで、安心して自分を出し、人とつながる心地よさを感じ、食事、排泄、睡眠、生活リズムなどの生活の基盤を少しずつ整えていくという幼児期のあたりまえの生活をつくっていくのが「療育」と言えるでしょう。
こうした「療育」の本質にかかわっては、連載(第Ⅱ部第4回7月号)の草笛学園での実践、「もう一つの発達のなかの煌めき」(第14回)、そして、4月号からの連載「仲間がいっぱい ひろしまの療育」を再度お読みください。
ペアレント・トレーニングと行動療法・応用行動分析
次に保護者支援について考えます。連載(第Ⅱ部第2回5月号)では、報酬加算の適用によって、ペアレント・トレーニング(以下、「ペアトレ」)を行なう事業所が増えていることを書きました。そのなかでも、「ペアトレ」とはどういうものか簡単にふれました。ここでは、もう少し、この「ペアトレ」について、その背景にある理論とあわせて考えます。
日本発達障害ネットワーク『ペアレント・トレーニング実践ガイドブック』(厚生労働省の「障害者総合福祉推進事業」(2019年度)として実施された「発達障害支援における家族支援プログラム実施基準策定及び実施ガイドブックの作成」によるもの、以下「ガイドブック」)を見ると、「ペアトレ」の概要を把握することができます。
改正発達障害者支援法(2016)で「家族を含めたきめ細やかな支援」「地域の身近な場所で受けられる支援」の重要性がうたわれ、その「必要な家族支援の一つ」としてペアトレが推奨されるようになりました。また、厚生労働省による発達障害者支援施策のなかに「発達障害者及び家族等支援事業」があるのですが、その事業の中の一つに「家族のスキル向上支援事業」があり、それは、保護者に対するペアトレの実施等に対して都道府県や市町村の自治体を支援するものだと「ガイドブック」は説明しています。そして、ペアトレとは、「環境調整や子どもへの肯定的な働きかけを学び、保護者や養育者の関わり方や心理的なストレスの改善、子どもの適切な行動の促進と不適切な行動の改善を目的」としたプログラムであり、子どもの行動修正までは目指さないものの、「保護者の認知を肯定的に修正すること」に焦点を当てた「簡易的なプログラム」だと説明されます。
「ガイドブック」には、「ペアトレを受講した親は、我が子への理解が進み、自身も子育てのストレスが軽減し、『切れ目のない支援』のキーパーソンとなることができ」、「その親とともに育った子どもも適応的な行動が増えて、自尊心を高めながら成長していけるようになります」と書かれています。つまり「ペアトレ」とは、子ども自身に直接的に働きかけていくものではなく、親を変えることで、結果的に子どもによい影響をもたらそうとするものと言えます。
「ペアトレ」は、1960年代から米国で発展してきたとされていますが、その理論的背景となっているのが「行動理論」と言われるものです。従来の、人間の意識のみに目を向ける心理学を批判し、観察可能な客観的事実としての行動を分析対象とすることで「科学的」な心理学になるとするもので、経験や環境要因に重点をおくという特徴ももっています。これが子どもの療育に応用される場合の目的は、子どもの行動変容であり、その行動変容のために、「親がほめ方や指示などの具体的な養育スキルを獲得すること」が「ペアトレ」の目的ということになります。具体的方法としては、いくつかの方式があるようですが、「ガイドブック」では、プログラムの質の維持のために「基本プラットフォーム」を開発したと説明されています。その詳細をここで述べることはしませんが、いくつかの核となる要素を、対象となる子どもや親の実態に合わせて組みたててプログラムにするもので、方法としてはグループワーク(「全5回以上、概ね隔週で1回のセッションは90~120分程度をめやす」とし、「1グループ4,5人~7,8人」が基本とされ、「参加者は原則として全ての会に出席することが求められ」る)とホームワークが基本になります。その際、回数が少ないと、「『ほめる⇔ほめられる』関係が保てなくなると感じる親も少なく」ないため、「セッションの実施回数だけでなく、実施している期間も重要」だと説明されています。また、終了後2~3か月後には「フォロー回」を設定し、再度ほめることの重要性をグループで確認しあう機会をもつことも強く推奨されています。
このように、子どもへのかかわりの基本は、「ほめる」ことだと何度も強調されます。ただし、ほめる対象は、その子自身ではなく、子どもの「適切な行動」に対してです。逆に「不適切な行動」については、基本的に無視をするという方法がとられます。とにかく、子どもの「適切な行動」をほめ、「不適切な行動」については無視をすることで、子どもの行動の変容をせまっていくということです。そして、この<ほめる⇔ほめられる>関係をできるだけ維持するために、グループワーク、ホームワークを続けるということになります。
そもそも「行動理論」や「行動主義心理学」は、人間の意識や内的な心理過程は、客観的事実として観察できないとして排除するもので、その点では動物心理学との親和性が高いものです。動物の行動を変容させるためには「エサ」が用いられるわけですが、人間の場合、その「エサ」が、「ほめる」という行為に置き換えられているようです。
全障研委員長でもあった心理学者の茂木俊彦さんは、「発達上の障害がある子どもに対する心理学的訓練・治療の技法は、学習心理学を背景とした行動療法的なものと、心理療法的なものに大別することができる」としたうえで、それぞれどのように実施されてきたか、教育のなかでどう位置付けて取り組んでいくのかについての見解を述べています(『障害は個性か』大月書店
2003)。
そのうち、後者の「心理療法」については、受ける人の認知能力が一定水準以上でないと効果をあげにくいとされてきたことから、幼児や知的障害のある場合には適用が難しいと考えられてきました。一方で、「行動療法」は、「オペラント療法」「行動修正法」「応用行動分析」等として、60年代半ば以降にさかんに用いられるようになりました。その基本的手法は、形成しようとする好ましい行動がみられたときにご褒美(おやつ、シール、花丸など)、ほめ言葉といった強化因子を与え、逆に、離席、奇声を発するといった不適切な行動をしたならば、「負の強化因子」として、その場から一定の時間遠ざけさせる(タイムアウト)、無視をするといった対応をとります(茂木は、これらを「処罰学習」の一つだとしています)。これは、子ども自身への直接的働きかけとして行われてきたものですが、親もそうした「治療者」に位置付けるのがペアトレと言ってよいでしょう。
しかし、もし子どもが何らかの「不適切な行動」をしたとしても、そこには何らかの理由や背景があるはずです。ことばではうまく表現できない思いや要求を、そうした行動で必死に訴えていることもあるでしょう。その、ことばにならないことばを聞こうとしなければ、子どもたちは訴えることすらあきらめてしまうかもしれません。
また、前述の茂木は、親が何らかの「宿題」(ホームワーク)を意識して子どもにかかわっていこうとすると、「『宿題』の諸項目というフィルターをとおしてこどもの行動をみたり、対応したりする傾向を強めるのではないか」とし、「これは日常生活を非日常的なものに変えてしま」い、「通常の子育てのように、子どもの生活と活動の全体から出発して、臨機応変に対応するという取り組みを弱めてしまうおそれがある」と指摘します。個別の訓練場面での整理された環境や日課とは異なり、実際の生活場面は変化に満ち、親やきょうだいなど他の家族のさまざまな思いや行動も含み込みながら展開されていくものです。そうした生活のなかで、さまざまな「失敗」も経験しながら、子どもも親も成長していくわけですが、行動療法、応用行動分析では、そうした「失敗」を最初からマイナスのものとしてしかとらえていないように思います。子育てとは、「臨機応変の対応」の連続でもあるのですが、その力を親が獲得していくことはとても大変なことです。でも、日々の子育てのなかで、失敗したけど「ま、いいか」「これくらいなら大丈夫」とおおらかに受けとめられるようになっていくのも生活の大切な意義であり、そうしたおおらかさを奪ってしまわないのか危惧します。
さらに、こうした行動療法、応用行動分析はスモールステップを原理としており、「ガイドブック」でも「小さくてもできている行動を認めてほめることを続けていく」ことが大切だとされています。子どもに獲得させたい行動(たとえば歯磨き)を細かく行程分解し(歯ブラシを水でぬらす、歯磨き粉をつける…)、その一つひとつを「ほめる」ことで獲得させ、結果的に歯磨きという行動の獲得につなげていくのがスモールステップですが、子どもたちの発達をみていくと、「小さい行程」を積み上げたら行動の獲得につながるといったものではないと実感します。「歯磨き粉はうまくつけられないし、とんでもない量をつけたり、落としてしまったり、そこらじゅう水浸しにしてしまったり、ほとんど歯は磨けていない」けれども、「自分で磨いたよ」とばかりに満足そうにしている姿に出会うことも多いですよね。そして、その満足感が「次もやろう」とするエネルギーにもなっていきます。
田中昌人さんは、可逆操作の概念を発達理解に導入するにあたって、「可逆操作」とは、それ以上に分解することのできない、分解してはならない「単位」でもあるとしました。「1歳半の節」であれば、「やりたい」という目的意識や、やったあとの「満足感」「達成感」が子どもの内側にためこまれていくまでが「単位」となります。その子どもの「単位」を、おとなのものさしでブツ切れにさせてしまってはいけないと思います。
子どもも親も“まるごと”受けとめられる場を
もちろん、どの子も「愛されたい」「大事にされたい」と願っています。子どもに対し否定的にかかわり続けることが、子どもの発達に大きな悪影響をもたらすことは言うまでもありません。ただ、子どもを肯定する、受容するということが、単に<ほめる⇔ほめられる>の関係だけでつくられていくものではないと思うのです。
かつて「療育」で出会ったお母さんは、電車が大好きな子どもと毎日のように電車を見に行き、1時間も2時間もつきあっていました。でも、子どもはなかなか帰ろうとはしません。「帰ろう」と言うと泣き叫ぶようになります。「療育」では、他のお友だちがもっているものに興味をもつようになり、それをとりあげようとして結果的にお友だちに手が出てしまうことが増えていきました。それを止められると、やはり泣き叫びます。そうした姿に先生たちもとまどいながらも、どうしたら楽しく遊べるか、保育の工夫をつづけていました。家でも園でも「困った姿」が増えていたのですが、お母さんは、線路脇から帰ろうとしないとき、お友だちに手が出てしまったときに、「赤ちゃんにごはんあげないといけないから帰ろう」「お友だちをたたいたらダメだよ」と言い聞かせながらも、お母さんも泣きながら「つらいね」「しんどいね」と言って、泣き叫ぶ子どもをぎゅっと抱きしめているしかない、という話を先生に話します。それを聞いた先生たちが、「お母さん、つらいね。がんばってるね」と一緒に涙を流したと聞きました。そうした時期は半年ほど続いて、そのあと彼は少しずつ自分の気持ちと折りあいをつけられるようになっていくのですが、そのつらい思いを含めて自分をまるごと受けとめてもらったという感覚は、彼の人格のなかにきちんと備わっていくように思うのです。子どもを「ほめる」ことはもちろん大切なことですが、子どもの行動を「ほめる」だけでは、子どもはまるごと受容されているという感覚にはならないでしょう。ほめられるかどうかばかりを気にして、おとなの顔色をうかがうようになることだってあるのです。子どもたちは、自分の不器用さ、うまくいかなさともたたかいながら、つらさ、悲しさ、悔しさといった感情も含めて“まるごと”受けとめられることを望んでいるのではないでしょうか。そうして自分が“まるごと”受けとめられる安心感があるからこそ、自分で自分をつくりかえるという発達の主体としての力を発揮していくように思います。決して「ほめ言葉」で子どもを操作するようなことがあってはならないと考えます。
そして、このことは親にもあてはまります。障害や発達支援を必要としている子どもたちの場合、乳児期からの「育てにくさ」をもっていることが多く見受けられます。泣いてばかりいるけれども何がしんどいのかわかりにくい、夜ぐっすり寝てくれない、離乳食の段階から過敏で食べてくれない、身体に触れられることを嫌がるといったことが多くあります。一方で、はたらきかけても反応がかえってきにくいということもあるかもしれません。そうしたことが必ずしも障害によるものというわけではないのですが、その「育てにくさ」は親としての自信を失わせます。自分が我が子に否定されているような思いになることもあります。「こんなにがんばっているのに」という思いは、苛立ちに変わり、子どもが悪いわけではないと思いながらも子どもを責め、そして自分自身をも責めてしまいやすいのです。そうした親をまずは「そのまま」「ありのまま」に受けとめる人間関係があることが保護者支援の「はじめの一歩」(連載 第Ⅱ部第2回5月号)ではないでしょうか。
学習参考文献
茂木俊彦『障害は個性か―新しい障害観と「特別支援教育」をめぐって―』大月書店、2003年
定価1980円
ISBN978-4-88134-086-8 C3036 2023年
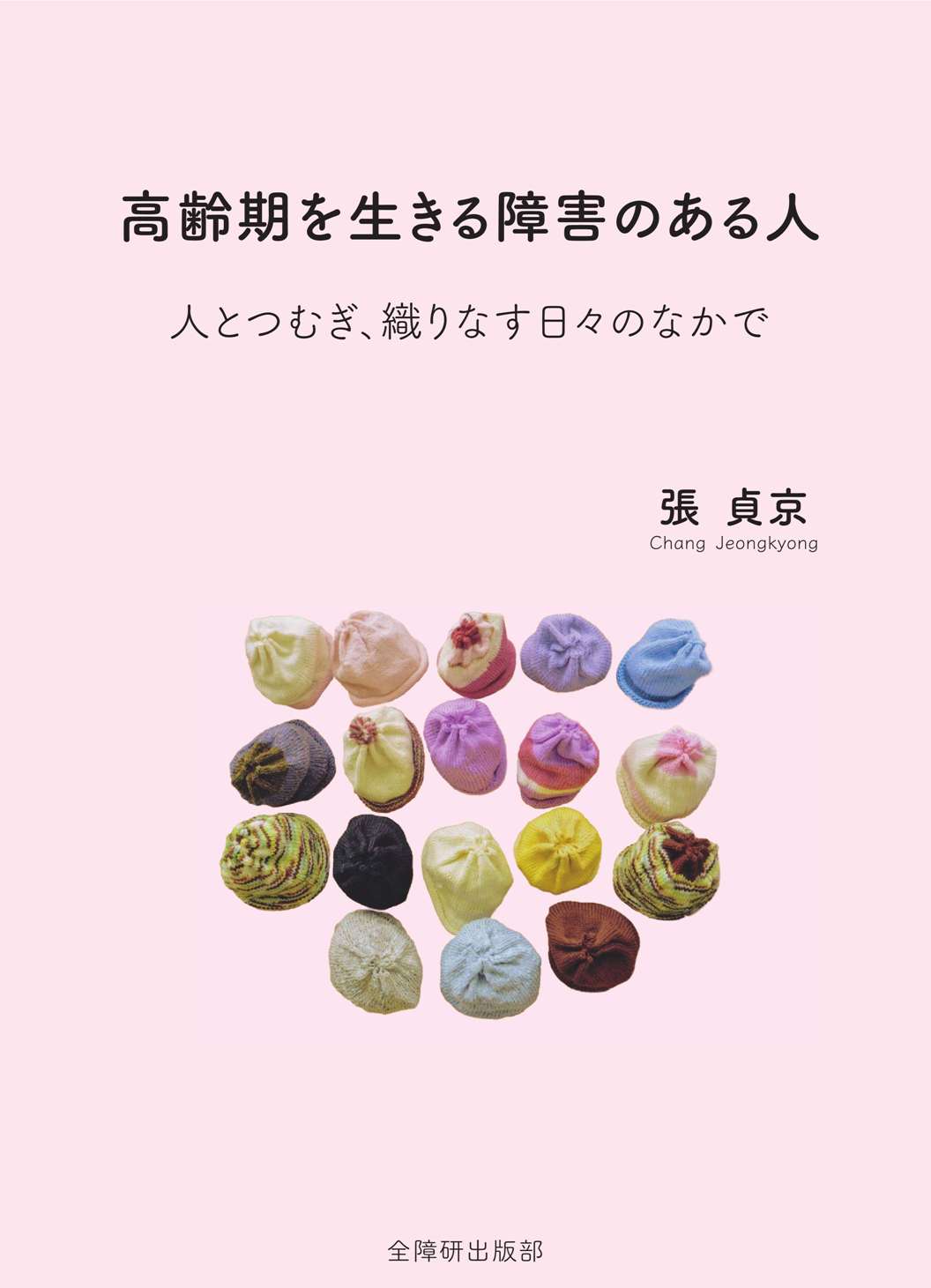
張 貞京(ちゃん ちょんきょん)(京都文教短期大学)著
高齢期を生きる障害のある人 ー人とつむぎ、織りなす日々のなかでー
目次
はじめに
第1章 高齢期の発達に光を当てる
第2章 一人ひとりの人生からみつめる高齢期
1 高齢になった知的障害のある人たち
2 大人の仲間になりました
3 わたしも元気です
4 老いてなお、自分にできることを
第3章 歳を重ねて花開くしごと
1 みんなとしてると楽しい
2 生涯のしごと
3 自分らしい表現で他者とつながる
第4章 老いと死に向き合う
1 一人じゃない、みんな同じ?死と向き合うとき
2 としえさんの「絵日記」 伝えたい想い
3 伝えられない想い
第5章 その人らしく生きる高齢期と看取り
住み慣れたところで、自分らしく暮らし続ける/地域で共に働き、共に暮らす/障害があっても高齢になっても/住み慣れた場所で看取りを/「迷惑を恐れない」
第6章 他者と支え合って生きる
高齢期の悩みに向き合って気づく/他者に想いを伝える/働くことの意味/高齢期の発達
補章 めざしたい実践
発達への気づき/学んで教え、共に学ぶ織物のはじまり/認め合って、力になっていく/学びと気づき/願いが生まれるしごと
おわりに
新刊紹介『高齢期を生きる障害のある人』
白石恵理子(滋賀大学)
2021年度『みんなのねがい』の張貞京さんの連載が一冊の本『高齢期を生きる障害のある人 ー人とつむぎ、織りなす日々のなかで』となりました。
張さんは、30年にわたり、滋賀県湖南市石部にある知的障害のある人の入所施設「もみじ・あざみ」に通い、寮生さんたちの思いに耳を傾け、しごとぶり、くらしぶりを見続けてきました。糸をつむぎ、機を織り、絵を描き、畑を耕しながら、仲間たちとくらしてきた寮生さんたちも、それぞれに老いを迎え、からだを動かすことが難しくなったり、ふるえる手にどうしようもなく不安を感じたり、家族や、ともに月日を重ねてきた仲間たちの死に直面したりと、高齢期ならではの〝課題〟にぶつかることが多くなってきました。
骨折によって2階から1階にうつることになった80歳のなつこさんは、仲良しの友だちや、ずっと手助けしてきた年下の友だちがいる2階のリビングにあがりたいのですが、そのためには職員の手を借りなければなりません。でも、それが待ちきれずに悩む日々です。そんな中でも、年下の友だちが自分を助けてくれることに感謝し、「おとなのなかまになりました」と職員に喜びを綴ります。それは、彼女自身が他の人を助けられるようになったことで「おとなになった」という誇りを感じてきた歴史があるからでしょう。こうして一人ひとりの歴史と今が、織物のように語られていきます。
「発達とは、自分自身の変化、環境の変化と向き合い、かかわり方や付き合い方を新たにしていく過程であり、意味づけ直していく過程」と、張さんは言います。加筆された補章では、石原繁野さんたち職員の歴史にも視点をうつしています。しごととは何か、生きるとはどういうことか、深く考えさせられる一冊です。
▶ご注文は全障研出版部オンラインへ
▶7月9日(日)13時~15時
張貞京さんと白石恵理子さん(滋賀大学)の出版記念トーク
全国各地から60人をこえるオンライン参加で盛会でした。
▶『高齢期を生きる障害のある人』の紹介チラシです
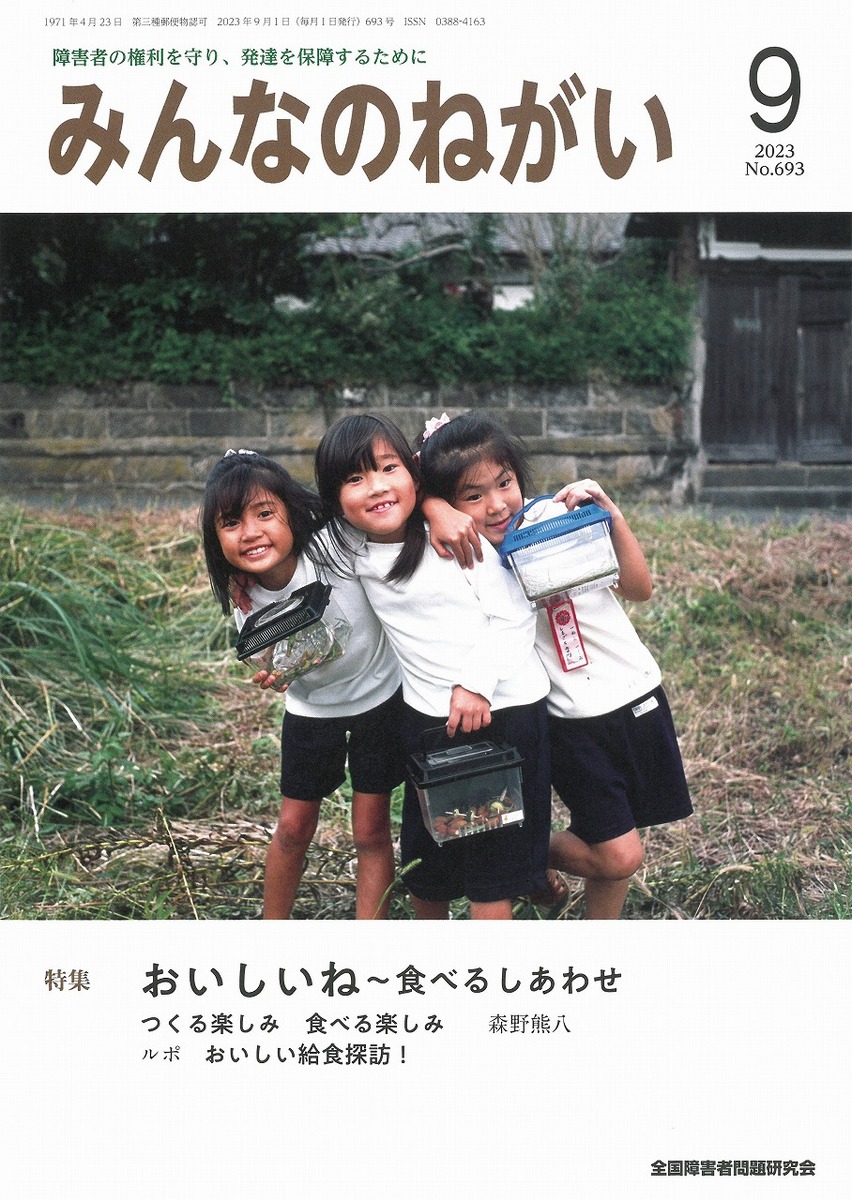
<表紙のことば>
三浦半島の港町で学校帰りに遊ぶ子供たちと出会った。草むらで楽しそうにキャッキャと虫取りする彼女たちは、器用に素手でバッタを捕まえて誇らしげに僕に見せた。「すごいねえ。写真撮ったげるよ」とカメラを構えると三人は仲良く肩を組んだ。
出来上がったプリントを見て、ふと思い出した。そういや僕も同じくらいの頃、近所の仲良し三人組でいつも登下校していたなあと。石ころ蹴りしたり、草むらで駆けっこしたりして。
目を閉じると、7歳の自分が居る。写真が、遠いあの頃の記憶をそっとよみがえらせ、少しだけ僕を
センチメンタルな気持ちにさせた。
土佐和史 とさかずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある。
<目次>
人として/ヨンチャン
【インタビュー】今、あなたと生きて/丸山正樹(小説家)
この子と歩む/髙畠雅恵
私のタカラモノ/大木 博
仲間がいっぱい ひろしまの療育/小川裕子(広島乳幼児サークル)
世界の風/児玉正文(ブルガリア)
特集 おいしいね~食べるしあわせ
ルポ おいしい給食探訪!
つくる楽しみ 食べる楽しみ/森野熊八
食べる力は生きる力の源/岩松まきえ
仲間たちの仕事にねがいを込めて/九内康夫
給食で心がけていること/山中文香
ペースト食は、私にとって愛情表現の一つです/豊田美和子
学校給食の無料化は子どもの権利/石田清人
発達のなかの煌(きら)めき 第Ⅱ部6回/白石正久・白石恵理子
社会をみる/杉田真衣(東京都立大学)
福祉現場の今を読み解く/深谷弘和(天理大学)
基礎から学ぶ 障害と医療/菅野 敦(東京学芸大学名誉教授)
私ときょうだい/山村彩佳
実践の魅力/藤江あや子
支部だより/北川さち
発達保障インタビュー バトンゾ→ン 細野浩一(埼玉支部)
みんなのひろば
ニュースナビ LGBT理解増進法/水谷陽子
誠司くんの見たこと、聞いたこと、歩いてきた道/松本誠司(高知)
BOOK/編集後記
裏表紙 心のことば 島田伊織
デザイン・イラスト うじたなおき、永野徹子、橋野桃子、細川茉莉
▶ご購読は出版部オンラインへ
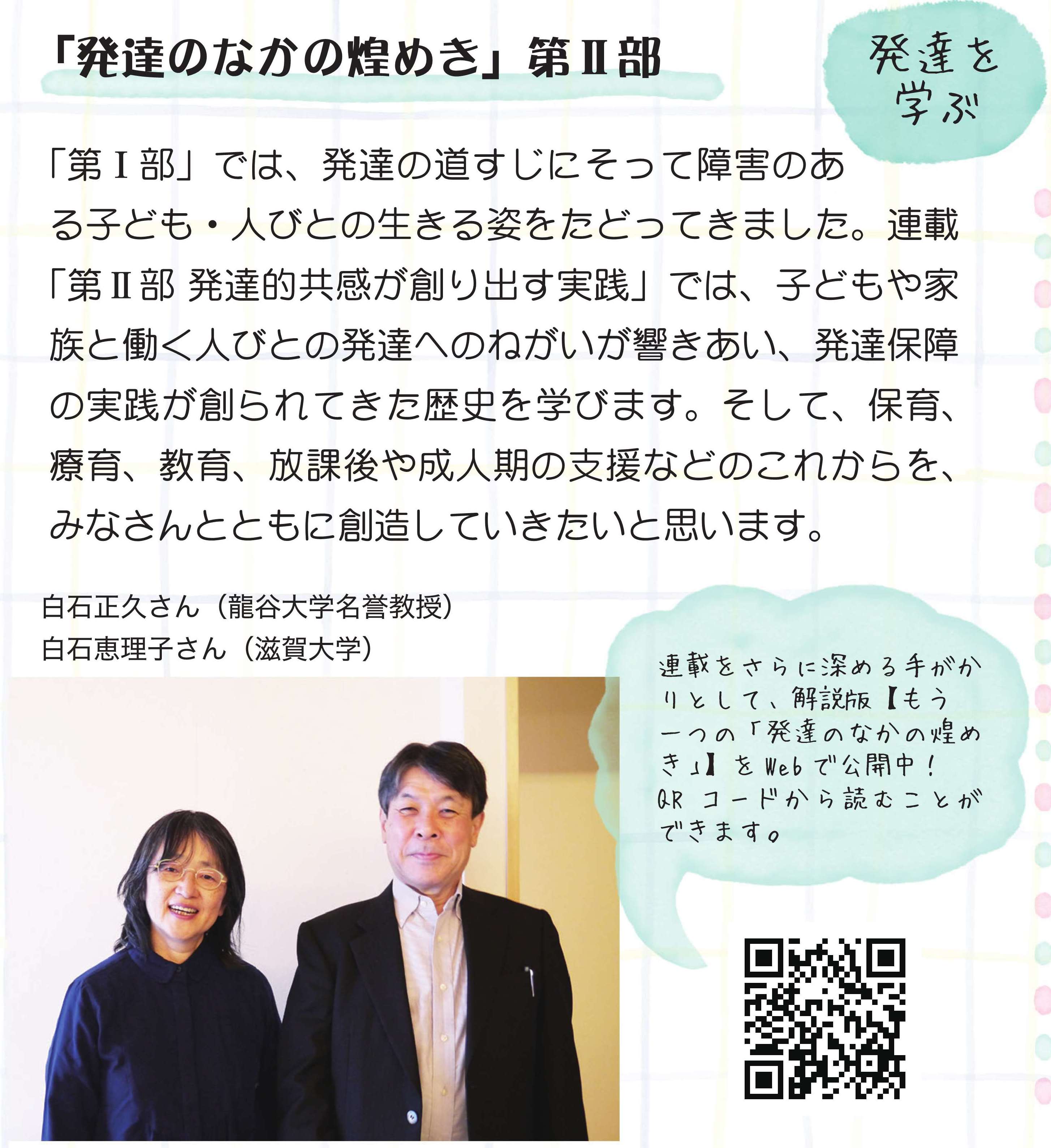
大会アピール
2023年8月5日、6日、私たちは「つながる つなぐ #発達保障 #みんなのねがい」をテーマに掲げ、オンラインコミュニケーションシステムを用いて、第57回目の全国大会を開催しました。
2020年の新型感染症の拡大から4年目、政府はCOVID-19の感染症法上の位置づけを引き下げましたが、感染症の流行そのものが終息したわけではありません。私たちのなかまのうちには、いのちと健康を守る上で細心の注意と配慮を必要とする人たちがあり、そうした人たちの身近で暮らし、働く家族や職員がいます。そのことに十分に意を用いつつ、出会い、集い、語り合う研究会の新しいあり方を創り出すために必要な時間をかけたいと考え、今年度の大会は完全オンライン開催としました。全国各地
から1000人を超える方の参加を得て、充実した研究大会を開催することができました。
大会基調報告は、各ライフステージにおける発達保障の課題を示し、困難の中に潜むねがいを深くとらえること、つながって学び合うこと、私たちの足元から平和と人権を展望することなどを訴えています。白石正久さん、白石恵理子さんによる記念講演では、月刊誌『みんなのねがい』での連載とも響き合いながら、障害のある人たちやその家族と永年にわたって寄り添いながら臨床と研究を進めてきた経験をもとに、障害のある人たちの発達要求をとらえること、障害のある人とその家族のねがいに学ぶことなどの意味が提起され、発達保障という考え方の今日的な意義と課題について深く考えあいました。
19のテーマの下に開かれた分科会には、全国から58本(フォーラム含む)のレポートが寄せられました。いずれも、障害のある人々とその家族のねがいを知り、それにこたえる実践を作り上げていくための貴重な努力を示しています。ライフステージごとのフォーラムでは、障害のある人たちの権利保障をめぐる今日的な課題を語り合い、学び合いました。4人の講師による学習講座もまた、障害のある人たちとその家族のねがいに応えるすじみちと、その今日的な課題を学ぶ機会となりました。記念講演と学習講座は、9月中旬まで配信します。開催日程では大会への参加がかなわなかった方にも、ぜひその内容を伝え、学びを広げたいと思います。
昨年9月の国連・障害者権利委員会による総括所見は、この国に暮らす障害のある人たちの人間的諸権利の実現にむけて、「障害」の認識のしかたや、権利保障の基本的な考え方から始まって、暮らし、教育、労働、政策決定への参加など、実に多面的な課題が残されていること、それらに対する政府のとりくみがはなはだ不十分なものであることを指摘しました。国連によるこの指摘を深く学び、総括所見を、障害のある人たちの権利を保障する方向で生かしていくうえでも、私たちの研究運動の役割は大きいものがあります。私たちは、一人一人が、お互いの力を尽くして、目の前の障害児者・家族のねがいに学び、障害者権利条約と総括所見を活かして、障害のある人の権利保障、発達保障を進めたいと思います。
より多くの方が、この取り組みに参加し、力を寄せていただくよう呼びかけます。
2023年8月6日
全国障害者問題研究会 第57回全国大会(オンライン2023)

全国障害者問題研究会
第57回全国大会(オンライン2023)基調報告
常任全国委員会
はじめに
敗戦後、小学2年生の時に不発弾の爆発で視力と両手を失った藤野高明さん(84歳)は、障害者・患者9条の会でつぎのように語りました。
「私は戦後ずっと障害者として生きて働いてきました。私が一人の人間として人権を保障され、働いてくることができたのは、平和が続いていたからです。この平和を本当に支えていたのは日本国憲法の9条、それから13条や25条です」。戦争と深く関連する事故によって障害を負った藤野さんは、その後の人生で徹頭徹尾、平和を追求し、民主教育や障害者の権利保障運動にとりくんできました。
いま、その平和を根本から脅かす事態が進行しています。ロシアによるウクライナへの戦争や東アジアの緊張情勢を逆手にとって、軍事費を倍増(5年間で43兆円)することを決定し、すでに沖縄や鹿児島などに敵基地攻撃のためのミサイル配備をすすめ、各地の自衛隊司令部を地下に置くなど基地機能強化に着手しています。こうした軍拡の財源として、復興特別所得税の転用まで表明、今後インボイス制度をはじめさまざまなかたちでの増税や国民負担増を目論んでいます。軍備が拡張されるとき、教育や福祉、生活に関わる予算が削られるという、これまでの歴史が証明してきたことが、現在の日本で起きています。
新型コロナウイルス感染症は2023年5月から感染症法上の分類が変更され、自己責任を前提に規制はほぼなくなりました。コロナ感染に対応した特別の施策は徐々に縮小されています。しかし、学校や施設を中心に集団感染が報じられています。コロナ罹患者の33%の人が苦しんでいる後遺症、障害者、高齢者などリスクの高い人への対応など、課題は山積しているにもかかわらず、国の責任ある政策は見えません。
子どもをめぐる政策では、4月からこども基本法が施行され、「こどもまんなか社会」を掲げるこども家庭庁が動きだしました。そして軍拡予算を覆い隠すかのように、「経済財政運営と改革の基本方針」(骨太の方針2023)でも「異次元の少子化対策」が喧伝されています。しかし掲げられた政策は児童手当の所得制限撤廃や増額など現金給付に偏重しており、子どもが自分らしく生きる基盤的条件の整備、すなわち保育所の職員配置の改善は「検討する」に終始しています。表明された現金給付政策も財源は先送りで、国民の負担増が検討されています。
2022年9月に国連・障害者権利委員会は、日本政府の第一回締約国報告を審査した「総括所見(勧告)」を公表しました。その内容は、障害のとらえ方が医学モデルを脱していないことやそこから生じるさまざまな歪み、障害者差別をなくす法整備が不十分であること、さらに大きく立ち後れている精神科医療、優生保護法問題の解決など、いずれも日本の障害者政策の根本を衝くものであり、その改善を強く求めています。根底には、政策決定過程において、「私たち抜きに私たちのことを決めないで」という権利条約の中心的な思想に真摯に向き合ってこなかった日本政府の姿勢への批判があります。いままた政府は、障害者や介護を必要とする高齢者など、社会的に弱い立場に置かれている人たちの意見を聞くことなく、マイナンバーカードと健康保険証の統合を強引に推進しています。これでは国によって社会的弱者をつくり出し、新たな差別を生むことになるのは明らかです。
全障研は、第24条(教育)をめぐって、総括所見の内容を適切に受けとめ今後の課題を提起するために全国委員長「談話」を発表し、旺盛な学習と討論をよびかけました。「障害のある子どもの教育改革提言-インクルーシブな学校づくり・地域づくり」(2010年)が今日的に重要であることもあらためて確認しました。
総括所見を学び深め合い、国の政策改善にどういかしていくか、連帯した障害者運動が求められます。
「この子らを世の光に」とした糸賀一雄さんは、「福祉の思想」を磨き、平和への誓いとともに「発達」の概念を深め、一人ひとりの人間とその社会への信頼と希望を、「発達保障」の理念へと発展させました。経済的価値の優先や、競争と自己責任ではなく、一人ひとりのいのちを輝かせるとりくみがますます求められています。激動する世界と日本の情勢のもとで、障害者の権利を守り発達を保障する私たちの研究運動をさらに広めていきましょう。
Ⅰ 乳幼児期の情勢と課題
(1)徹底して子どもの立場から考える
私たちは、子ども理解を土台にした実践をすすめることをねがい、日々の生活のなかで、その子は何に魅力を感じているのか、何がやりたいことの制約となっているのかと、保護者と一緒に子どもの姿から発達や障害の意味を考えることを大事にしてきました。ところが、保護者が抱える子育ての悩みを、「困った行動の消去」「〇〇の力をつける」といった目標に安易におき替え、発達を「できるか―できないか」といった行動面に矮小化して、部分的な機能を「伸ばす」プログラムを「専門性」と称して勧める児童発達支援の事業が目立ちます。療育は、他の子と比べて足りないところを補ったり、何かの力をつけるためにあるのではありません。安心できる人間関係を土台に「やりたい」という思いを膨らませ、子ども自身が主体的になれるような生活や遊びが大切です。ねがいをていねいにききとり実践を紡ぐこと、子どもらしい生活と遊びの土台となる制度を整えていくことの両方が求められます。
(2)児童発達支援や保育所制度の行方
制度面では、2023年度中に改正児童福祉法の中の障害児通所支援関連条項の具体化と次期報酬改定の議論が行われます。その内容は3月にまとまった「障害児通所支援に関する検討会報告」にもとづくものになることが見込まれ、児童発達支援センターの機能強化のための職員配置や児童発達支援、放課後等デイサービスの支援内容に対応した報酬が注目されています。検討会では塾や習い事に似た支援への明確な改善を求めていません。また「特定の領域に対する重点的な支援(特定プログラム)」という新たな言葉が書き込まれましたが、支援の内容はあいまいです。児童発達支援などが、子ども施策の中でももっとも市場化の進んだ分野であることが、乳幼児期の支援をよくするための議論を阻んでいると思われます。
保育所など一般の施設も、障害のある乳幼児にとって重要な役割を果たしていますが、保育所等への規制緩和と営利企業の参入も著しく、その結果、園庭がない、経験を積んだ職員がいないなど貧しい環境の園も目立ちます。保育所が障害児保育や地域の多様な子育てニーズにこたえることを求められても、対応する職員に見合う公費支出はまったく不十分です。にもかかわらず「こども未来戦略方針」では、親の就労要件を問わず時間単位の給付制での「こども誰でも通園制度(仮称)」の創設が検討されています。子どもの生きる権利、育つ権利を切り売りする保育になりかねないこうした動向にたいして、保育関係者と手をつないで運動をしていく必要があります。
(3)保育と療育が手をつないで
こども家庭庁が出発したことは、母子保健、保育所・幼稚園、療育機関が手をつなぎやすい施策を求めていくチャンスだともいえます。
振り返ると、こうした連携は制度ありきではなく、乳幼児健診とその後の早期対応、親子教室、保育の場の拡充と、子どもの発達をねがう保護者や関係者のねばり強い要求運動によって、自治体ごとに整備されてきました。国の制度で保育所での保育士加配や療育機関との並行通園が可能となったのはその後のことです。今日でも、社会資源や母子保健・療育のシステムは、自治体によって異なりますが、それは子どもを中心にそれぞれの機関が連携して障害のある子どもの発達を保障しようと努力してきたことの到達点でもあります。
近年、健診・保育・療育の公的なネットワークに包括されない多様な児童発達支援事業が療育に参入し、保育所・幼稚園と療育が手をつなぎづらい状況があります。保育所等に通いながら送迎付きで事業所に通う子も多いという報告もあります。そうなると、子どもの生活の場がぶつ切れにされ、「~がしたい」という子どもの気持ちが置き去りにされやすくなります。保育者の側も、児童発達支援のとりくみによって、子どもが変化することを期待する状況に陥ってしまいがちです。
保育所等の実践についても、遊びのなかで思いもしなかったことに笑い合ったり、“もっとやりたい”というねがいを育んだりといった、発達の手応えとは無縁に、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」や社会が求める価値観・目標が早期から押しつけられ、その結果、子どもや保護者が追い詰められています。
国は「インクルーシブ保育の推進」をうたい、保育所に児童発達支援事業等を併設した場合に、後者の職員が保育所の子どもの支援を行うことができるよう制度改正を行いました。「障害児の支援に支障がない場合に限り」とはしているものの、それぞれの場の職員配置を手厚くしてほしいという実践現場のねがいに背くものです。保育と療育は、子どもの発達を保障するという点でしっかりと手をつないでいく必要があります。
今大会では、インクルーシブ保育をテーマに、保育所と児童発達支援などの協働についてフォーラムで話し合います。
(4)子どもの生活をバラバラにしてはいけない
2月に開催された「発達保障のための相談活動を広げる学習講演会」は、改正された児童福祉法の下で、療育機関が手をつないで子どもの発達を保障する地域を意識的につくっていこうと400人がオンラインで討論しました。地域でつながりをつくり地道に学び続けてきた取り組み、0、1、2歳の親子療育を経験することで親子が安心して育っていく大切さ、障害の重い子の主体性を育てるていねいな療育など、私たちが積み上げてきたこと、今後めざしたいことを確認し合いました。乳幼児期に関わる保育・療育の関係者が集まり、到達点と課題を確認していく場が今後も求められます。
Ⅱ 学齢期の情勢と課題
(1)子どもの権利保障の場としての学校・放課後等デイサービス等への注目
3年にわたるコロナ禍の中で、学校や放課後等デイサービス、学童保育等が、子どもの権利を全面的に保障する場として注目されました。給食がない、家族以外の信頼できる他者(先生や友だち)に会えない、家から離れることができないといったことが、いかに子どもや保護者を危機に陥らせるかが認識され、「生きる権利・守られる権利は家庭で」という政策の前提が危ういものであるという理解が広がりました。
来年は子どもの権利条約批准30周年です。子どもの権利という言葉に当たり前にふれることが可能だった世代が、子どもにかかわる仕事につき、保護者になる時代です。小森淳子さんは、今を生きる若者が、息の詰まるような環境で、研ぎ澄まされた人権感覚を持っていること、そのことが彼らを深く傷つけている可能性があることを指摘しています(『みんなのねがい』2022年8月号)。そのしんどさを個人の中に押し込めさせるのではなく、共に手を取り合いながら、運動を進めていきましょう。
(2)学校で発達保障の実践に取り組むために
特別支援学校の設置基準が制定されましたが、この基準が既設校には適用されないため、大規模・狭隘(きょうあい)な特別支援学校が多数存在し、条件改善に向けた運動が喫緊の課題になっています(「障害者問題研究」第51巻1号)。
教員不足は5月で1500人と報道され、学級担任が未定であったり、頻繁に代わったりする学校は少なくありません。教師の待遇を貧しく不安定なものにし、専門性を大事にしてこなかった教育政策のツケが一気に押し寄せています。教員の多忙化を解消するという名目で、行事を縮小する、学級通信を出さないなどが、学校の方針として決められる現実があります。しかし、何が子どもや保護者にとって重要なのかを判断し、決める裁量は、子どもと直接向き合っている教師におかれるべきです。行事の魅力を特集した『みんなのねがい』で、石田誠さんと塩田奈津さんは、行事の中で大人も子どもも集団として育つことを指摘しています(2022年12月号)。
発達保障のために学校は何を大事にすべきか、今日の学校は、他者とともに豊かに全身で学べる場所になっているのか、子どもの姿と現場の状況に基づいて議論できるような体制が求められます。
(3)子どもの学びの場を機械的に決めないで
現在の通常学級で、すべての子どもがゆたかに学べているかと問われれば、ノーと言わざるをえません。不登校の子ども、通常学級から特別支援学級へ転籍する子どもの数は増えています。子どもたちの、「この場所ではしんどいねん」という声が聞こえてくるようです。
特別支援学級在籍の子どもが「大半の時間を通常の学級で学んでいる場合には、原則として週の半分以上を特別支援学級で授業を受けているかを目安として学びの場の変更を検討するべきである」とした、「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について」(文部科学省通知2022年4月27日)は、現場に大混乱をもたらしました。保護者や子どもたちと学校の丁寧な話し合いの上で、「籍は特別支援学級におき、一定数の授業を通常学級で受ける」ということを選んできた子どもたちが、やむなく通常学級へと転籍する事態が生じています。転籍を強いられた子どもたちに豊かな学びと学校生活が確保されているのか、事実に基づいた検証が必要です。
(4)障害者権利委員会の総括所見をふまえて
国連・障害者権利委員会からの総括所見(勧告)は、日本政府報告が使用していた特別支援教育(special needs education)の語ではなく、隔離された特殊教育(segregated
special education)という語を用いて、それが永続的しかねない状況に懸念を表明し、インクルーシブ教育の権利の承認を求めています。私たちは、先に述べたように、現在の日本の学校教育が、しんどい子ども、障害のある子どもを通常学級から排除するような状況にあることを踏まえて、通常教育関係者とともに教育改革の運動を進めていかなくてはなりません。まず、通常の学級が、スタンダードに合わせられない子どもたちへの支援ができにくく、排除の力が強く働く場である状況を、一刻も早く改めなければなりません。そうした努力抜きに、通常学級しか選べない状況にすることは、子どもの守られる権利・育つ権利の侵害にもなりかねません。一方で、特別支援学校の中にも、未だに「18歳で一般就労できる力」ばかりを一面的に重視するなど半世紀以上も前の「差別としての特殊教育」を想起させる差別的な傾向が残されており、こうした状況を変えていくことも必要です。
通常の学校も特別支援学校も、子どもの人格を尊重し、全人的な発達を保障する学びの場になっていくことが徹底されなければなりません。そのためにも、子どもたち一人ひとりの発達的要求を丁寧につかむことができる体制が求められます。
「通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議」報告がなされ、同日通知も発出されました。すでに指摘してきたように、通常の学級も特別支援学校も困難な状況に追い込まれる中で、障害のある子どもたちの発達を保障するものとなりうるのか、教員配置や学校教育などの条件整備、子どもの実態に即して柔軟に運用できる教育課程編成権の確保など多角的な検討が必要です。
(5)ゆたかな生活のための放課後保障
放課後や休日の生活を支える放課後等デイサービスは、感染症拡大防止・対策と、日額報酬制の矛盾の中で、極めて厳しい状況に立たされています。2021年4月の報酬改定での基本報酬の引き下げ、経験ある職員の配置に対する加算の廃止は多くの放課後デイ事業所で収入減に直結しています。子どもの状態をチェックして該当する子どもに加算する個別サポート加算は、子どもを見る目を曇らせます。
放課後デイは、子どもたちとともに遊びや生活を創造し、取り組みをゆたかに展開してきました。次期報酬改定で「特定の領域に対する重点的な支援(特定プログラム)の提供」がどのように組み込まれるのか注目する必要がありますが、放課後の場に特定の課題を課す訓練の役割を担わせることは、こうした自由度の高い取り組みと矛盾します。子どもたちに、ゆたかな放課後生活を保障する実践とその専門性について検討を深め理論化していくことがいっそう求められます。
Ⅲ 成人期の情勢と課題
新型コロナウイルス感染症の流行から3年、私たちの行動・生活様式も様変わりし、成人期の障害福祉現場も大きな影響を被りました。それへの制度的対応が遅れた影響が、様々な場面に出ています。また障害者の人権の確立が永年にわたって放置されてきたことの堆積が、当事者のねばり強い運動により歴史的かつ重大な社会問題として表出しています。
(1)障害のある人の暮らし・人生の家族依存問題の早急な解決を
障害のある人の暮らし・人生は家族が支え続ける、この国の諸制度の大前提をなしてきた考え方ですが、その先にはいわゆる「老障介護」にともなう深刻な問題が生じています。地域で限界を超えた状態で生活を続ける中で、家族全体が疲弊している状況も報告されています。
このような状況下で、国連の総括所見は「障害者の施設入所を終わらせるために迅速な措置をとる」ことを日本政府に求めました。この勧告において言及されているように、誰と暮らすのかを決めることや、特定の場所で暮らすことを強制されないことは基本的人権として非常に重要な問題です。
一方で、現状の障害者の暮らし・人生の家族依存をどのように解決するのかという道筋が見えない中で、(総括所見の勧告によって)暮らしに関わる社会資源が制限されることに危機感を覚える関係者も多くいます。2021年時点のNHKの取材は、入所施設での生活を希望し待機している障害者が、少なくとも27都府県で延べ1万8640人に上ることを明らかにしました。国による調査がないことや待機者数を把握していない自治体も多いことを考えると、実際の待機者はさらに多いとみられます。まずは、全国的に非常に多くいると考えられる入所施設やグループホーム等の待機者の実態を正確かつ詳細に把握するための基準と方法の確立が必要です。
障害のある人と家族双方が当たり前の人生と関係を築けるようにするために、ライフサイクル上の適切な時期に自立できるための仕組みと社会資源の充実が喫緊の課題です。
(2)障害のある人にもディーセントワークの保障を
障害のある人の福祉的就労をめぐっては、依然として新型コロナウイルスの影響が継続している、以前のような仕事内容・工賃水準には回復していないという事業所が多くあります。また一般就労している障害者の雇用回復も依然、途上です。一般社会は、コロナ流行前の生活に戻りつつあり、景気も回復傾向にありますが、それは障害のある人たちまでゆきわたっていません。このことは、「障害者は最も遅く雇用され、最も早く解雇される」という、効率性重視の資本主義社会における行動原理の表れであり、障害のある人が労働環境において弱い立場であることが露呈しました。
この間、障害者の法定雇用率は引き上げられましたが、達成企業の割合はいまだに半分に過ぎません。その上、他社の雇用率達成を受託して働く場を提供する「障害者雇用代行ビジネス」なるものも拡がりを見せています。こうした動向は、障害のある人の「開かれた労働市場への移行」(総括所見)を促進すること、ましてやそこで、働くことのねうちや同僚との協同をわがものとすることとは無縁のものです。
福祉的就労であれ一般就労であれ、障害のある人たちのもてる能力を最大限発揮し、当事者がやりがいを実感でき、また社会に貢献するというディーセントワークを保障が喫緊の課題です。
(3)障害のある人の政策決定への参加を位置づける
障害のある人の投票行為に関連して、合理的配慮提供を求める当事者たちの訴えが実り、選挙権の行使に一定の前進がみられました。しかし、議場のバリアフリー化や障害のある人の被選挙権の行使には依然として大きな課題が残されたままです。
共同通信社が2022年に地方議会全1788の議長宛に実施した調査では、議会の「バリアフリー化」が進んでいるという回答は39%に留まり、段差の解消は24%、一般傍聴席における車いす対応席の設置は49%、視覚障害議員向け設備は7%と、議会の傍聴や議員活動の展開における障壁は山積状態であることが明らかにされました。
障害者権利条約をこの国で具現化するためにも、政策決定過程への当事者参加は不可欠な条件であり、選挙権及び被選挙権、議会の傍聴等あらゆる場面において、合理的配慮を保障することのできる制度と条件の整備を求めていかなければなりません。
(4)障害のある人のケアする権利の確立を
障害のある人のノーマライゼーションを追求するうえで、ライフサイクルにおけるノーマルな経験として子育てや介護等、他者をケアする権利も、当然、他の者と同様に保障されなければなりません。
旧優生保護法下において実施された本人の同意を得ない形での不妊手術という重大な人権侵害事案はけっして過去のものではありません。旧優生保護法下の人権侵害問題について、正義・公平の理念に基づき、「除斥期間」を適用せず、すべての優生手術被害者の被害回復と救済を求めていくことと同時に、現代においてもなお、本人に拒否する権利を保障しないまま不妊手術が実施されている事例があるという実態を早急に改めなければなりません。そのためにも障害のある人にもケアする権利があることについて明確にするとともに、現実に子育てや介護を行うための社会的支援のあり方についても検討する必要があります。例えば、ホームヘルプ制度における子育て支援の枠組みや、グループホームや地域生活の中で子育てをどのように支えるのかということについての制度的裏付けが必要です。
2021年からは障害基礎年金と児童扶養手当の併給調整の枠組みが変更になり、障害基礎年金の子加算部分と児童扶養手当の差額が支給されることとなり、障害のあるひとり親と二人親の間の格差は解消されました。しかしながら本来は、障害のある人がケアするために必要な追加的費用が勘案されるべきであり、障害基礎年金の子加算のあり方の見直しなど、個別の事情に応じた追加的な費用の保障がされなければなりません。
Ⅳ 研究運動の課題
(1)困難の中に潜むねがいを深くとらえる
自己責任と家族依存を前提とした社会保障費の大幅な削減に、物価高騰が追い打ちをかけ、障害者と家族の困難はいっそう深刻化し、ますます声をあげにくくなっています。コロナ禍が障害者の生活と発達にもたらした影響についても、今後長期にわたる検証が求められます。そのためにも、障害者の直面する困難の実態とそこに潜むねがいを深くつかむこと、実践現場で働く人たちの苦悩を語り合い、聴き合うことが大切です。各地域で、社会の困難や矛盾が集中的に顕在化しやすい障害者の権利侵害の実態と構造を明らかにする調査研究に取り組みましょう。自らのねうちを市場経済のものさしで競わなければ生きられない社会ではなく、人びとの連帯と支え合いが広がるなかで、障害者の尊厳を守り、発達保障が前進するような社会を描きましょう。
さまざまな困難の中でも、障害のある人の生活の質を高めようとする実践が各地で、各分野で積み重ねられています。一人ひとりが生活のなかで感じる楽しみや幸せのなかに、発達の土台となる生活の質を豊かにしていく課題を探り、そうした豊かな生活を支える制度が地域で格差なく整えられているかを検証しましょう。
(2)つながって学び合おう
私たちの研究運動は、ライフステージを貫いて一人ひとりの生活を見つめ、地域の実情を学び合い、立場や職種を超えて語り合うことで、発達保障の課題を掘りさげてきました。
この間、オンラインを活用した学習活動も広がっています。全国大会をはじめとして、「教育と保育のための発達診断セミナー」、「発達保障のための相談活動を広げる学習講演会」、「『障害者問題研究』を読む会」や研究推進委員会のオンラインゼミでは、理論や実践を学び合うことを通して、仲間とつながることのねうちが実感できます。
多忙化のなか、自分の思いや考えを表現することがためらわれたり、他の人や同僚と話をする機会がもちにくくなっています。だからこそ、ささやかな疑問や違和感を手放さず、お互いの悩みや迷いを安心して語り合える場をつくっていきましょう。実践の現場では、ここまででも見てきたように、人間らしく働く権利が奪われやすい状況が広がっています。だからこそ、障害者の発達と幸福の実現に寄与したいとねがう人たちに発達保障労働の魅力を伝え、ともに働く仲間として加わってもらうためにも、実践者としての誇りを持って働き、自らの将来の仕事と生活を展望し、専門性を高め合える職員集団づくりを進めていきましょう。
そして、自分の生活や実践をレポートに綴ることにも、励まし合って取り組みましょう。実践記録を読み合い、仲間とともに考えるなかで、それぞれの実践の個性や共有すべき課題が見えてきます。来年の第58回全国大会(奈良)に向けたレポートづくりを進めましょう。
身の周りの実態や問題を学ぶことは、自分の実践や思いを言葉にして伝えたり、他の人の思いや考えをより深く理解することを助けてくれます。人とつながるための学びを支部やサークル活動のなかで深めていきましょう。
(3)足元から平和と人権を展望しよう
不安と緊張が高まる国際情勢を口実に、政権とそれにすり寄る勢力が軍備拡大を推し進め、平和憲法を破壊することを許してはなりません。戦争や災害による命の危機が世界規模で起きている今こそ、国際平和を実現するために戦争の道を選ばず、戦力を持たないことを定めた日本国憲法第9条がもつ普遍的価値を現実の力とする努力が求められています。
私たちの研究運動は、憲法が掲げる恒久平和や基本的人権を障害者の生活と権利において具体化することで、憲法を守る取り組みの一翼を担ってきました。たとえば、65歳を境に障害福祉サービスが利用できなくなる不条理を千葉市に訴えた天海訴訟は高裁で勝訴しました(千葉市は上告)。費用負担なしに自分らしい生活をきずきたいというねがいを実現するために、介護保険優先原則の廃止が求められます。
旧優生保護法による強制不妊手術の国家責任を問う裁判。司法は憲法違反を認める一方で、被害から20年を経過すると賠償を求める権利が消滅するという「除斥期間」を理由に原告の訴えを斥けてきましたが、この間、二つの高裁で勝訴が連続しました。しかし国は控訴、上告しています。強制不妊手術という人権侵害ととともに、権利に期限があるのかという重大な問題が提起されています。6月、国会の調査室は被害の実態調査報告書原案を国会に提出しました。その内容も精査しつつ、この間、関係者の努力によって積み上げられてきた調査研究を土台に、人権侵害の事実を明らかにしていく必要があります。
そして各地で広がる投票バリアフリーの運動。「障害のある人の投票のための合理的配慮」を調査し要望した日本障害者協議会(JD)の要請や国連の総括所見を受けて、国(総務省)は12月に都道府県選挙管理委員会に実態調査を行い、ホームページで公開しました。NHKも「みんなの選挙」の一環として市区町村選管に調査し、積極的に報道しています。
障害者の権利保障を勝ち取ろうとするこうした努力は、日常生活や実践の足元から憲法の理念や価値を確かめること、平和と人権について語り、学ぶことの大切さを教えています。
日本障害者フォーラム(JDF)のパラレルレポートづくりのとりくみなどに象徴される、障害者のねがいを束ねる努力に思いを寄せ、総括所見に照らして、目の前の生活や実践の事実を検証し、発達保障・権利保障の課題を明らかにしていきましょう。
(4)発達保障のうねりをつくり出そう
私たちの研究運動は、生活や実践の事実を多様に持ち寄り、ねがいを束ねていくことで、発達保障・権利保障の原動力を蓄えてきました。そのために、一人ひとりが、立場や職種を越え、地域を結んで、互いが研究運動の担い手として育ち合うことを大切にしてきました。
そうした研究運動の拠りどころが月刊『みんなのねがい』です。誌面からは、生活のぬくもりや実践の息づかいが伝わってきて、最新の問題や発達保障・権利保障の課題を学ぶことができます。地道に続けられる読者会の経験も交流し合いながら、読者から読者へと輪を広げていましょう。
実践と切り結んだ理論の学習には、季刊『障害者問題研究』が欠かせません。「『障害者問題研究』を読む会」では、一人で読み進めることが難しいからこそ、仲間と読み合うことで、多面的な問題の理解や新たな課題の発見につながります。
私たちの研究運動のすそ野を広げていくためにも、地域や職場のなかで「語りたい」「学びたい」という要求でつながる場を作ることが大切です。オンラインの活用も進んでいますが、そこから取り残される人をなくす取り組みも考えていきましょう。全障研出版部の出版物も活用しながら、語り合いや学び合いの文化を受け継ぎ、学びの層を厚くしていくことが、発達保障・権利保障を前に進める土台となります。
私たちは、どんなに小さなねがいであっても大切に語り合い、個人と集団と社会という発達の三つの系を結び合わせて考えることで、権利保障の筋道を描き出し、発達保障の未来を展望してきました。そうした全障研運動の魅力を伝え合い、私たちの研究運動に多くの人を誘い合って、発達保障のうねりをともにつくり出していきましょう。
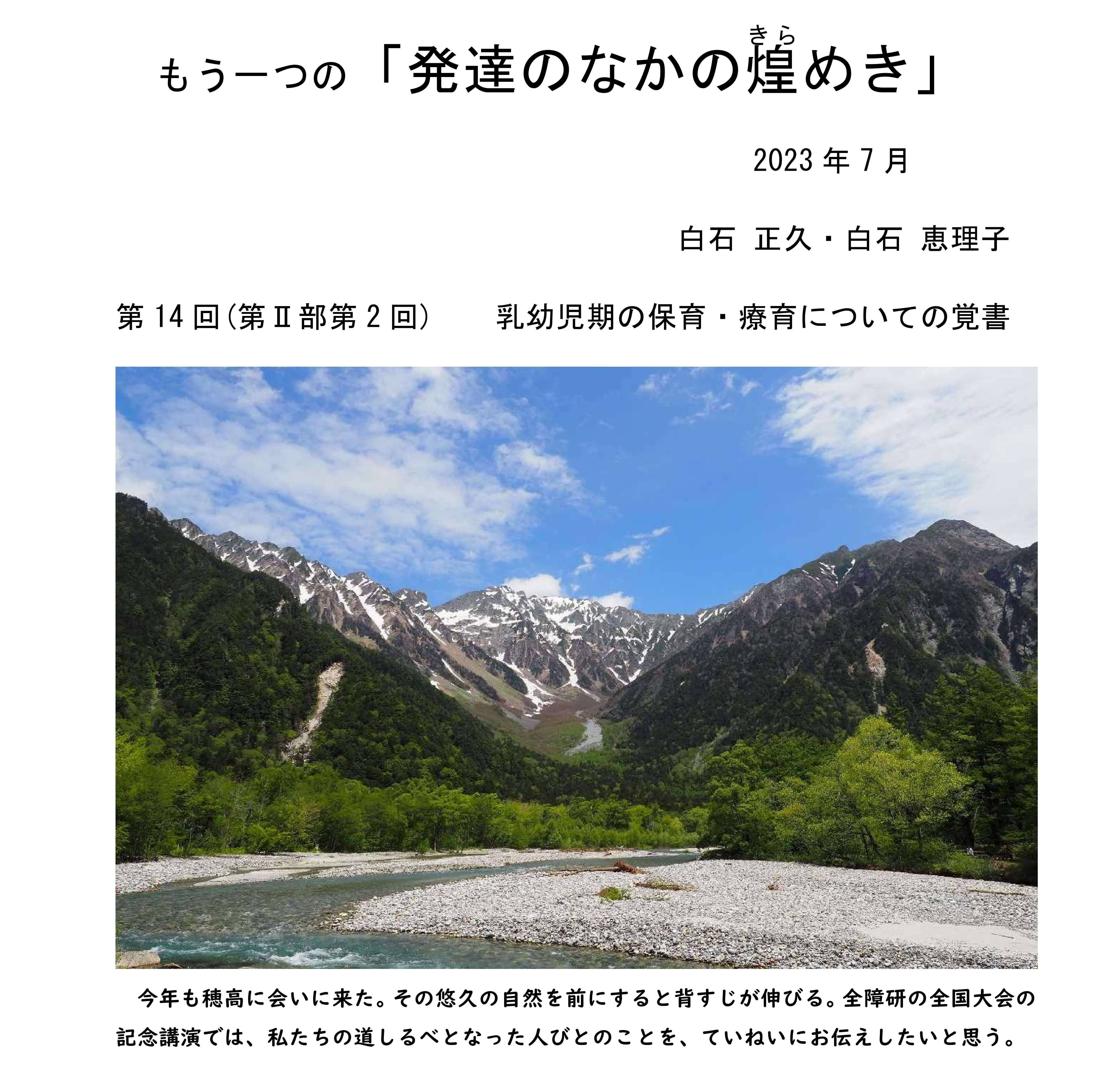
はじめに
まず、6月11日に開催された「教育と保育のための発達診断〈オンライン〉セミナー」にご参加いただきありがとうございました。600名を超える方にご参加いただき、1300回近い見逃し配信視聴回数を数えたとのことです。繰り返し視聴していただいたことに、みなさんの学びへの強い思いを感じました。感想文、アンケートも、たくさんいただきました。大変好評であり、あらためて講師の皆さんに感謝申し上げます。
次回11月12日(日)では、「ライフサイクルと発達の障害」をテーマとして、発達理解を深めていきたいと思います。来夏には、「4歳以降の発達について」のセミナーを計画しています。ご予定ください。
以下に、テキスト編者としての私たちからの、セミナー冒頭でのご挨拶を掲載します。
発達診断セミナーにご参加の皆さま、こんにちは。テキスト編者の白石正久と白石恵理子です。オンラインでお顔を拝見できないのは残念ですが、全国各地の皆さんとつながって学びあえることの幸せをつくづくと感じております。
さて、テキスト(『新版・教育と保育のための発達診断・下巻』)の192頁に、全障研の結成大会時の基調報告(1967)の一節が紹介されています。
「これまでわたくしたちは、はやく、たくさん、たくみに答えを出すことをめざす体制の中で育てられてきたので、発達とは、できないことができるようになる、上へ伸びていくことだという理解のしかたをしてきました。」
こうした発達の見方、発達観は50年たった今も根強くあると考えています。お金を払って、その対価としてのサービスを買うというしくみが強まっているなかで、「一人ひとりの子どものもっている力をのばします」、「一人ひとりに寄り添った個別の発達支援を行います」といった宣伝文句が、私たちがいつも乗車するバスのなかでも聞かれるようになりました。子どもの育ちに何らかの不安を抱えているおかあさん、おとうさんに、こうしたキャッチコピーは深く入り込んでいくでしょう。
そうではなく、本当に一人ひとりに向きあっていきたい、子どものねがいに応えたいと思って実践を重ねているところでも、厳しい保育条件、教育条件のもとで、支援者の側の余裕がなくなればなくなっていくほど、こうした発達観はいつのまにかスルリと入り込んでくるのではないでしょうか。それは、おとなが設定した枠内、条件内でしかモノを見たり考えたりせず、その中でしか自己の力を発揮することができない受け身の発達観とも言えるでしょう。そうではなく、どんなに幼くても、どんなに障害が重くても、その子が発達の主体であり、自分で感じ、自分で確かめ、自分で考えようとしているのだ、その姿に心をよせ、それを共感しあう仲間との関係、保育者や教師の存在が重要であると考えます。
さて、今月2日、厚労省から発表された前年の合計特殊出生率は「1.26」で、7年連続の減少、過去最低となりました。出生数も初の80万人割れでした。政府は焦燥に駆られています。先日公開された子育て支援の基本方針である「こども未来戦略方針」では、「少子化は、我が国が直面する最大の危機」「日本のラストチャンス」という言葉が躍っています。「はじめに」では、「急速な少子化・人口減少に歯止めをかけなければ、我が国の経済・社会システムを維持することは難しく、世界第3位の経済大国という、我が国の立ち位置にも大きな影響を及ぼす。(中略)今後、インド、インドネシア、ブラジルといった国の経済発展が続き、これらの国に追い抜かれ続ければ、我が国は国際社会における存在感を失うおそれがある」と危機感を説明しています。つまり岸田首相のいう「次元の異なる少子化対策」なるものが、なにより経済戦略のためのものであることを露骨に表明しています。
「産めよ殖やせよ」という国策を掲げた1941年1月の近衛文麿内閣の「兵力・労働力確保」のための閣議決定を想起します。「1家庭に子ども5人以上」を実現するために多産世帯にはご褒美を、独身者には課税(「独身税」)をというものでした。しかし、生まれてきた子どもや家族の基本的人権はないがしろにされ、その年の12月に開戦した太平洋戦争のなかで、多くのいのちが奪われていきました。
それから80年余、今また、国家とその経済のために「子どもを増やす」ことを至上命題とした政策が大手を振って登場してきました。そういった政策のベクトルのもとで、保育、教育、児童発達支援、放課後支援において、子どもの人数や取り組みの時間量は問題にされるけれど、生命、生存、発達という一人ひとりの子どもの権利が軽視されている現実を、私たちは目にするようになりました。先にふれたように、「子育て支援」「発達支援」の名によって、利潤追求する企業活動が参入し、「できること」の増大をキャッチコピーとする療育や放課後支援が拡大しました。デジタル技術による実態把握や教材開発で、情報産業の儲けを支えようとする政策も強化されています。子どもが営利追求の手段になるとき、その権利や発達は本当に守られるでしょうか。おとなも、こういった政策によって駆り立てられ急かされて、互いのことを理解しあうことがむずかしい現実のなかにあります。
こんなときだからこそ、このセミナーで発達を学んだ皆さんが、同僚や保護者とともに発達の大切さを語りあって、一人ひとりが大切にされ、互いを尊重しあえる職場や地域を創るための役割を買って出ていただけないでしょうか。全障研は、そういった研究運動を積み重ねてきました。
子どもたちの発達を守るために、ともに手をつなぎあって進んでいきましょう。
「発達のなかの煌めき」第Ⅱ部2回~4回(『みんなのねがい』5月号~7月号、以下では「連載」)は、乳幼児期の発達保障をテーマとしましたが、教師、作業所の指導員の皆さんなどからも、たくさんの感想をいただきました。きっと大きくなった子ども、なかまのなかに、彼らと家族の乳幼児期からの歴史が刻まれていることを想ってくださったのでしょう。その他者の歴史への想像力こそが、子ども、なかまと向きあう私たち自身の発達として求められるのではないかと、この連載ではおりにふれてお話ししてきました。
「連載」第2回では乳幼児健診後の親子教室、第3回では保育所等における障害児保育、そして第4回では通園施設、通園事業、児童発達支援の歩みを振り返りつつ、発達保障の実践に求められる視野と視点をお話ししました。この「もう一つの『発達のなかの煌めき』」(以下では「もう一つ」)第14回では、保育・療育の黎明期を中心に、その時代から学ぶべきことを覚書風に書きたいと思います。第15回(8月中旬を予定)では、応用行動分析、ペアレント・トレーニングなどについて検討する予定です。
障害のある子どもの保育、療育の歴史
これらの乳幼児期の発達保障の制度や実践のスタートは、1970年代を待たねばなりませんでした。法の下に平等であるべき障害のある子ども、人びとの権利保障は、高度経済成長期の経済優先政策のなかで、広範に侵害されていたのです。何より、養護学校設置義務の先送り、学校教育法の「就学猶予・免除」の乱用によって、義務教育すら保障されていませんでした。そのもとで、知的障害(当時は精神薄弱)児通園施設は、中等度の知的障害があり、就学猶予・免除を受けた6歳以上の学齢児のための施設でした。
連載第4回で紹介した広島県福山市の「草笛学園」は1973年の設立ですが、その年に1979年からの養護学校義務制の予告政令が出され、その翌年、知的障害児通園施設の年齢制限も撤廃されました。ですから、「草笛学園」の開設の年には不就学の学齢児も入所していたのです。先生方は、先例のない幼児期の実践への挑戦とともに、学齢児の就学保障にも取り組みました。
この1970年代前半は、東京の美濃部都政、京都の蜷川府政、大阪の黒田府政をはじめとして、社会党、共産党を中心とした革新勢力の統一によって住民の要求実現を大切にする自治体が全国に広がったときでした。住民が主権者として「憲法を暮らしに生かそう」を掲げて、苦しい生活やさまざまな権利侵害をなくそうと立ち上がったのです。障害のある子どもの教育権保障では、京都府の与謝の海養護学校の本格開校(1970年)、東京都の希望者全員就学の実現(1974年)などが、養護学校義務制へ道を拓く画期となりました。呼応するように、大阪府下(大阪市を除く)の多くの自治体で障害乳幼児のための通園施設の開設、滋賀県大津市での「早期発見・早期対応」「希望者全員の保育所等の入所」を掲げた「大津方式」など、乳幼児期の先駆的な施策も取り組まれていきました。さらに、障害のある子どもの保育所入所運動が拡がり、1974年の厚生省(当時)の「障害児保育事業実施要綱」の発出につながりました。これらはすべて国が先導した政策ではなく、住民と働く人びとなどの粘り強い要求によって実現していったことでした。
大阪府寝屋川市の「あかつき園・ひばり園」は1973年に開設されましたが、親の会が自主運営していた障害乳幼児の保育が要求の核となり、無認可の「療育センター」(1971年)を経て、「『一人の願いをみんなの願いに』ということで進めた運動で獲得した私たちの園」(寝屋川市障害児を守る会会長・田中守さん)として実を結んでいったのです。
一人のねがいをみんなのねがいに
この経過で大切なことは、障害のある子どもへの施策が単独で実現していったのではないということです。国民各層と手を携えるようにして取り組まれた運動でした。1960年代後半から1970年代には、「婦人よ家庭に帰れ!」という保守的な家族観によるキャンペーンに抗して、女性の働く権利の確立と子どもの生活・発達の保障をねがって、「ポストの数ほど保育所を!」の運動が各地で取り組まれました。そのなかで、子どもに障害はあっても「働きつづけたい」、保育所に入所させてやりたいという要求は等しく尊重されなければならないと自覚した人びとが、地域の保育運動、女性団体、労働組合、いろいろなねがいをもった市民とともに、障害児の入所運動に立ち上がりました。
連載第3回で紹介した大津市の「つくし保育園」にタカシくんが入園したのは、1967年のことでした。このときはお母さんの孤軍奮闘によって、認可運動に取り組んでいた共同保育所のつくし保育園にたどり着いたのです。就学するまでの1年半の保育によって、タカシくんはたしかな変化を見せたのですが、保育者は既存の保育に「障害児をつけくわえる」ような受けとめになっていたのではないかと反省し、障害児を含めた集団保育づくり、園全体で受けとめるための職員集団づくり、そして園の担う保育運動の大切な柱として公的な「障害児保育」の実現を要求することを課題として残したのです。そして1971年、歩行や言語の獲得を課題とする障害の重い5歳のユミちゃんを受け入れることになりました。当時、『ちいさいなかま』などの保育雑誌に紹介されたユミちゃんへの実践は、今でも学ぶべき大切な視点を残してくれるものでした。大要を紹介します。
ユミちゃんは、お母さんとなら両手を支えてもらって歩いているのに、保育者が手を出すと嫌がって歩こうとはしませんでした。ところがある日、友だちのノブちゃんの誘いに応えて歩みだしたのです。保育者にとってはうれしい瞬間でした。
しかしその後の会議で、こんなことが出されました。「ノブちゃんと歩いたり、はじめて便器でおしっこをしたり、園ではじめてできたと思うことがたくさんあるけれど、お母さんに聞いたら、みんな家でできていることでしょ。いったいユミちゃんは発達しているのやろか」。
カンカンガクガクの議論になりました。「だけどノブちゃんと歩いていたときのユミちゃんの顔には、これまでになかった新しい経験をしたときの感激した輝きがあったよ。家の中だけでしていたことが保育園でもできる。お母さんとだけしかできなかったことが友だちとできる-それはおしっこをする力や歩く力がずいぶんのびて、なかま・社会との結びつきをこれまでよりも強めてきたことになるのではないだろうか。それもたいせつな発達ではないか」。
そして、「マンマと言えた」「五歩歩いた」などとそれだけ切り離して発達としてみてしまっていたけれど、それだけではなく、「どのような条件のもとで、いかなる教育的働きかけによって、だれと、何のために、何に向かって、いかに豊かになしとげたのかを、これまでもっている力の変化にも目を向けつつみていかなければいけない」「なかま・社会との結びつきを強めて、自分の人格を輝やかせながら発達していく姿をたいせつにしていかなければならない」と共有しあうことができるようになっていったのです。つまり、発達は「なかま・社会との結びつき」のなかで、一人でできることがみんなとともに、みんなのなかでできるようになっていくことを通じて、人格の広がり、豊かさをともなって達成していくことを、実践者は学び取っていったのでした。私たちおとなも、一人でできるだけではなく、仲間のなかで、仲間と力をあわせてできるようになることは大切なことですね。
一方、ユミちゃんの手をひいたノブちゃんは、とても怒りっぽかったのですが、「あんなにもユミちゃんの気持ちがわかり、心を結びあわせる力をもっているのだなというように、これまで保母によみとることができなかった子どもたちの力も、みなおすことができるようになった」と言われました。
そして、「ユミちゃんをうけいれるまで討議を重ねるなかで、うけいれるとあんなことも起こるだろう、こんなことも起こるのではないかとたくさんのことを予想していました。そしてこのことは実際おこったけれども、予想しえなかったこともたくさんありました。そのなかで最大のことは、職員集団の子どもたちを見る見方が変化し、前進してきたことです」と結ばれています。
こういった実践によって、障害のある子どもだけではなくすべての子どもが、生活、遊び、集団を基礎とした人格的な育ちあいを遂げていく場として、保育所が発達保障の歴史に立ち現れました。私たちの指導教官であった田中昌人さんは、自身がつくし保育園の園児の保護者であり、園の実践検討に積極的に参加していました。『講座発達保障への道・第1巻』(1974年、全障研出版部)は、当時の『みんなのねがい』連載の単行本化ですが、その本でこの実践を紹介しています(『講座発達保障への道・全3巻』の復刻版は、学習資料として全障研出版部の「オンラインショップ」で提供されています。また、その内容を川地亜弥子さんが、『新版・教育と保育のための発達診断・上巻』「Ⅲ-4章 7歳の発達の質的転換期と発達保障」で解説しています)。ぜひ、お読みください。
通園施設、児童発達支援の開設 ― 保護者、市民とともに
1974年から国の制度としてはじまった「障害児保育事業実施要綱」は、当初、対象が4歳以上で軽度の障害、定員90名以上の保育所で、障害児の人数がその1割程度に及ぶことという厳しいものでした。したがって「希望者全員入所」を原則とした大津市のような自治体は少なく、なかでも障害の重い子どもの保育所等への入所は容易ではありませんでした。一方、通園施設(当時は、知的障害、肢体不自由、難聴の3種別があった)は、1974年の時点では全国で200か所に満たず、1980年でも知的障害児通園施設のない府県が7県、1施設しかない県が9県でした。こういった地域の偏在は、今日までつづいています。
この状況にあっても、通園施設の設置や増設を求める運動が各地で粘り強く取り組まれました。国も障害の重い子どもへの専門的、総合的な対応を行なう施設の必要性は認めざるをえず、1979年から「心身障害児総合通園センター」が設置できることになりました。これは、①相談・検査部門(診療や心理判定・相談)、②療育訓練部門(肢体不自由、知的障害、難聴の通園施設のうち、2つ以上を設置)という2つの機能を備え、都道府県、政令市、中核市のほか、概ね人口20万以上の市を設置主体とするものでした(当初は、3種の通園をすべて設置し、人口30万人以上の市によるとされましたが、後に緩和された)。しかし、国の補助金はあっても自治体負担は相当額に上り、この制度による通園施設の拡大は限られたものでした。
そのなかで広島市では、1974年に市の中心部(東区)に外来診療と3種の通園施設をもつ「児童療育指導センター」(現、広島市こども療育センター)を開設しており、「心身障害児総合通園センター」の全国のモデルとなりました。しかし、政令市の大きな出生数と広い行政域を抱え、通園に長い時間を要するなど、園児、保護者の負担は並大抵ではありませんでした。「広島のどこに生まれても同じサービスを」「地域に根ざした療育センターに」という2つの柱を掲げ増設をめざして、保護者会、職員の労働組合、子どもの権利を守る市民団体などが「実行委員会」を組織し、粘り強い運動が始められました。広く市民に向けて訴えることを大切にして、保護者とともに繁華街での街頭宣伝、署名活動などを繰り返し行ない、その署名は6万筆を超えたのです。
運動が実って、第2の「センター」として1993年に「北部こども療育センター」(安佐北区)が開設されました。ところが、この機に、これらの療育センターの運営を「社会福祉事業団」へ委託するという市の方針が出されました。この方針に反対するために、障害種別を越えて5つの園の保護者会が一つにまとまり、「広島の障害児療育を充実させる会」が結成されました。子どもが療育を通じて豊かに発達することを実感した親は、そのために何が必要なのかを考え、国や自治体に堂々と要求する力をもつようになっていったのです。後に「療育を充実させる会」は必然的に「療育・教育を充実させる会」へと発展していきました。このときの運動は、全国から27万余筆の署名を集め、たびたびマスコミにも取り上げられるなど、大きなうねりになりました。委託そのものはなされましたが、市長が社会福祉事業団の理事長となるなど、広島市の公的責任を明確にした組織関係が構築されました。さらに、第3の「センター」として「西部こども療育センター」(佐伯区、2004年開設)の開設が約束されたのです。これらの詳しい経過については、本年度の『みんなのねがい』の連載、広島乳幼児サークルのみなさんの「仲間がいっぱい ひろしまの療育」を、ぜひお読みください。
広島市の療育を創る運動は、「療育」という言葉を正面に掲げ、「療育とはなにか」を市民に向けて説明し、その大切さを訴えつづけるものでした。障害はあっても療育によって子どもは豊かに発達するのであり、その生命と発達は同じに尊いということを、広く市民のものにしようとするものでした。運動は人を育てます。この運動によって、障害のある子ども、親・家族、そして職員が、主権者として胸を張って生きていくことのできる地域へと歩み出したのだと思います。毎夏の全障研の全国大会に、広島市の療育センターの職員のみなさんは、たくさんの保護者、子どもといっしょに参加されています。その保護者が分科会などで、自らの思いとねがいをはっきりと語られる言葉に、主権者としての姿をみるのでした。
通園事業、児童発達支援事業 ― 地域に根ざした療育
1970年代後半から、全国、どこに生まれても療育を受けることができるように、「心身障害児通園事業」(後に児童デイサービス事業、さらに児童発達支援事業)による療育の場づくりが徐々に拡がっていきました。とくに、1978年からの「18か月児健診」の本格実施が、障害の発見後の療育の場の大切さを認識する契機になりました。
「心身障害児通園事業」とは、1972年の「心身障害児通園事業実施要綱」(厚生省)によるものであり、通園施設などの法定施設を配置するには至らない小規模の市町村に、概ね利用定員は20名とする施設としてスタートしたものです。
簡易な施設とはいえ、この事業の委託を受けるには多くの苦労がありました。今日「全国発達支援通園事業連絡協議会(略称・全通連)」(近藤直子会長)に参加する各地の事業所には、その地域の人びとのねがいを集めて開設にこぎつけた、それぞれの歴史があります。
たとえば鹿児島県では、1984年、教員であった大迫より子さんが、鹿児島市内の自宅を開放し「あすなろ療育相談室」を開設し、小さな通園事業の第一歩が印されていきました。そして無認可の「鹿児島子ども療育センター」に発展させ、1993年に鹿児島市から心身障害児通園事業の委託を受けました。そこにいたる10年、大迫さんはじめ職員・関係者、親、市民による大きな運動が取り組まれました。発達の事実は人に確信を与え、そしてそれをはぐくむための人の輪を広げます。何より保護者に力を与え、「親の会」の組織につながり、その確信を県下にもひろめていきました。この運動は行政を変え、自治体職員を変えて、離島を含む県下各地に、療育の場を創っていく中心の役割を果たすことになりました。旧大口市(現伊佐市)の市長は、義務教育と同じに「療育は(無償で)義務でなければならない」と謳いました。「鹿児島子ども療育センター」は、2017年に「むぎのめ子ども発達支援センターりんく」(児童発達支援センター)へと発展しています。
人口が90万人(現在は80万人を割る)に満たない小県の山梨県には、1980年代になっても限られた療育の場しかありませんでした。とくに、3歳未満児や重症児の通える場がなく、行き場のない親子をなくそうと民家を借りての週1回の療育が開始されました。その2年後に園舎を立てましたが、甲府市から「心身障害児通園事業」の委託を受けるまでにはさらに5年を要しました。しかし、療育の場は根本的に不足しており、県下3番目の知的障害児通園施設の開設をめざして、職員、親が一丸となった運動がつづきました。そして2002年に、知的障害児通園施設「ひまわり」(山梨市)の認可にいたります。なんと息の長い運動だったのでしょう。その間、県下各地で療育を求める「集い」、各地への出前療育などを取り組み、保育所、幼稚園、学校、自治体職員などにも「後援会員」を広げて、県下全域に運動を支えるネットワークがつくられていきました。分け隔てなく人びとと手をつなごうとする運動は、長く施設を支える礎を作ります。
かつて、「『教育は環境ではない、中身だ』という人もいるけれど、障害児のいる場所は、どこにいっても貧しい。でも、一つひとつの遊具や備品には、その施設を支えてきた人びとの歴史がかくされている」と和歌山県の「こじか園」を訪問したときの感想を書きました(『発達の扉・下巻』、89ページ)。それぞれの園の開設を支えたのは、その園を核とした地域のネットワークにつながる人びとです。それは園の応援団であるだけでなく、子どもや家族の地域での生活を支える応援団にもなっていきます。
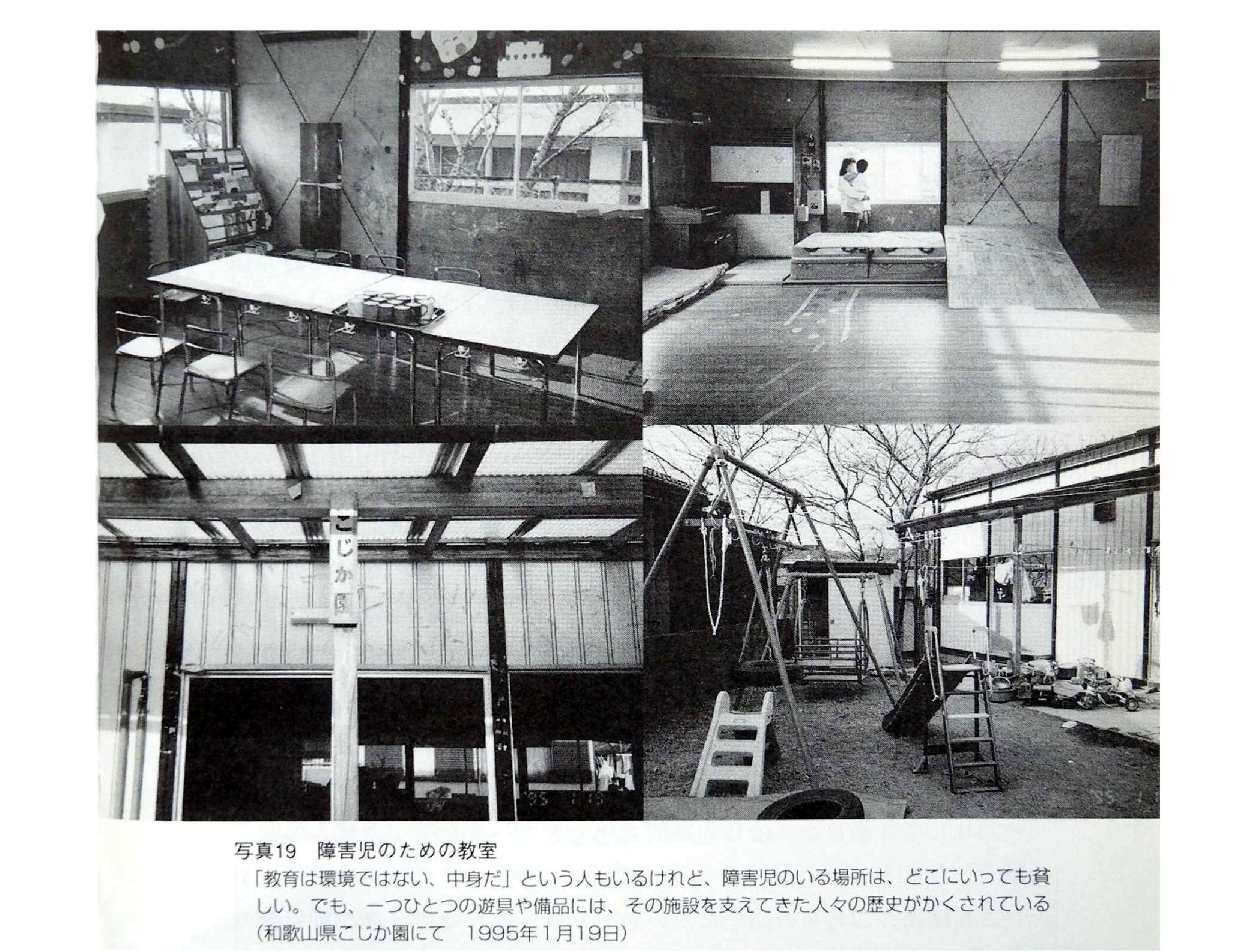
その園がある地域の特徴は、療育実践の中身にも反映します。そこにしかない海、山、川、田畑の営み、飼育、祭り、歌舞、地域の人びととの交流などが、子どもたちの活動や遊び、行事、年間保育計画に位置づいているのでした。それは、「土着の療育」と呼んでもよいものでしょう。障害児の施設はインクルージョンの理念に反するとの言説がありますが、地域の人びとと文化に根ざして、子どもらしい日課、遊び、生活、集団のもとで発達がはぐくまれることは、むしろ障害の有無を越えた発達保障実践の大切なあり方だと思います。
厳しい時代にあって
住民要求に依拠した民主的な自治体の存在をうとましく思った政治の動きは、社会党、共産党を中心とする「革新統一」にくさびを打ち込むことに腐心しました。京都の民主府政が、社会党の独自候補の擁立によって終わったのは1978年でした。1980年、共産党の排除を前提とした社会党と公明党の政権構想合意(社公合意)によって、その動きは加速しました。
その政治状況を背景として、世界的な新自由主義の流れにのった社会福祉制度は、1990年代から2000年代にかけて措置制度を契約制度に転換し、国民に自助・自立を求め、「民間活力」によって公的支出を抑制すべく、「社会福祉基礎構造改革」へと進んでいきました。
新自由主義とは、経済に対する国家の介入を小さくし(「小さな政府」)、市場の競争による価格の自由な動きに任せ、経営の活性化や効率化を図ろうとする経済理論です。これを、社会福祉の分野にも導入しようとしたのが「社会福祉基礎構造改革」でした。
そして「官から民へ」を唱えつづける首長が増え、保育所、幼稚園、障害のある子どもの施設など、それまで公営であったものを民営に転換しようとする動きが広がりました。すでに述べた広島市の「こども療育センター」の運営が、「社会福祉事業団」に転換されたことも、こういった動きの一つでした。公立であることを維持しつつも、経営と運営に民間事業者をあてようとする「指定管理者制度」も導入されるようになりました。その選定には、競争入札的な「公募」が行われることもあります。
保育所、幼稚園、認定こども園、子どもや障害のある人たちの施設は、経営を成り立たせることを目的としたものではなく、それを必要としている子ども、人びとのための権利保障のための施設です。したがって、民営化や指定管理者制度による職員、実践の質、受け入れ態勢、管理者の変化に不安を覚えるのは、なにより子ども、なかまであり、その保護者です。さらには、その園や施設の実践の積み重ねの大切さを知っている卒園者とその家族でしょう。広島市の「こども療育センター」事業団化への反対運動は、この保護者の思いを徹底的に信頼しようとしたからこそ、前だけを向いて歩むことができたのだと思います。
利用契約制度のもたらすもの
こういった新自由主義的な制度改革は、2003年度からの支援費制度で具体化し、さらに法制化したのが、2006年からの障害者自立支援法でした。連載第2回の冒頭で述べたように、①契約による福祉サービスの利用、②給付費の代理受領と利用者の応益負担、③日額の出来高払い報酬制という「三つ組」が、障害のある子どもの通所支援にも導入されました。障害者自立支援法は、「生存のためには応分の負担を」と障害のある人びとに求めるものであり、その思想の悪辣さゆえに、違憲訴訟を含む大きな運動によって廃止されました。そして、障害のある子どもの通所支援も児童福祉法に戻りました。②の利用者の応益負担は軽減され、後の保育・幼児教育の「無償化」によって3歳児以上の負担はなくなりました。しかし、「三つ組」は廃止されてはいないのです。
連載第2回で紹介した「障害乳幼児の療育に応益負担を持ち込ませない会」が、結成以来18年間その名称を改めず「三つ組」の廃止を求めつづけているのは、ここに権利保障とは相いれない国の「下心」が、しぶとく貼りついているからです。
契約制度以前の措置制度にあっては、子どもなどの利用者は措置され、職員は利用者の権利保障のために、行政から措置を委託される立場でした。つまり、どちらも行政による措置を通じて、権利保障のために力をあわせる共同の関係にありました。しかし契約制度は、権利として保障されてきた活動を、「サービス」と名のつく「商品」にしていきました。利用者、保護者は、契約という行為を通じて「商品」を選択し、利用料の多寡はともかくも、買い取る立場になったのです。美味しい料理をつくるために、種まきや水やりから始めて、収穫や調理に至るまで、力をあわせていた関係が、できあがった食べ物をスーパーで選択し、レジでお金を払って買い取るような関係になったということです。品物が商品であるためには、「何」を「どれだけ」という「量」が計られなければなりません。そのために、国は施設への報酬の日額制を取りやめるわけにはいかないのでしょう。
大きな問題は、療育や地域生活支援を子どもにとってより良いものにしていくために、ともに力をあわせるという「過程」が大切にされず、サービスがニーズにあっているかという「結果」だけが評価されることです。さらに、報酬日額制という困難な条件のもとで経営を成り立たせなければならず、施設管理者は「そろばん」に縛られ、働く人びとは「利用者」のニーズに相応しいサービスを提供することに苦心することになります。
つまり契約制度によって、それに関わる人びとは「経済的人間」に変化せざるをえず、自ら進んで、この制度にあった自分に変化していくことになるのです。政治と経済のシステムは、じわりじわりと人びとの意識や人格に浸透し、それを変化させていきます。
児童発達支援、放課後等デイサービスに多くの民間事業者が参入し、そのなかで各種のキャッチコピーを掲げて営利主義の経営をおこなう事業所が増えました。この状況のもとで、療育は契約によって提供されるサービス(商品)であり、その選択は保護者の自由意思によるという認識が一気に広まりました。
それに抗して私たちは、発達のつまずきや障害はあっても、子どもはていねいな保育や療育のもとで発達していくこと、そのためには保護者も職員も、互いのねがいと思いを語りあい、知恵を出しあい、時間をかけて粘り強く療育を創っていく「過程」を大切にしなければならないことを、研究運動の取り組みを通じて弛まず伝えていかなければなりません。
「措置から契約へ」をはじめとして、新自由主義的制度改革の問題点をわかりやすく解説してくれるのが、本年度の『みんなのねがい』連載、深谷弘和さんの「福祉現場の今を読み解く」です。職場や地域のサークルで、集団的に学習したいと思います。
こども家庭庁、「はじめに」でお話しした「こども未来戦略方針」についての検討は、8月末に発行される「障害乳幼児の療育に応益負担を持ち込ませない会」の会報に寄稿する予定です。「みんなのねがいWEB」でご案内いたします。
私たちが営む「野の花こども館」のFacebookができました。
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100093552550918)管理人ががんばって情報発信してくれていますので、ご覧いただければさいわいです。
学習参考文献
近藤直子・白石正久編『障害乳幼児の地域療育』全障研出版部、2003年.
『障害者問題研究』第49巻第1号「乳幼児期の発達保障と児童発達支援の課題」全障研出版部、2021年.
『障害者問題研究』第50巻第2号「乳幼児期の療育と発達保障」全障研出版部、2022年.
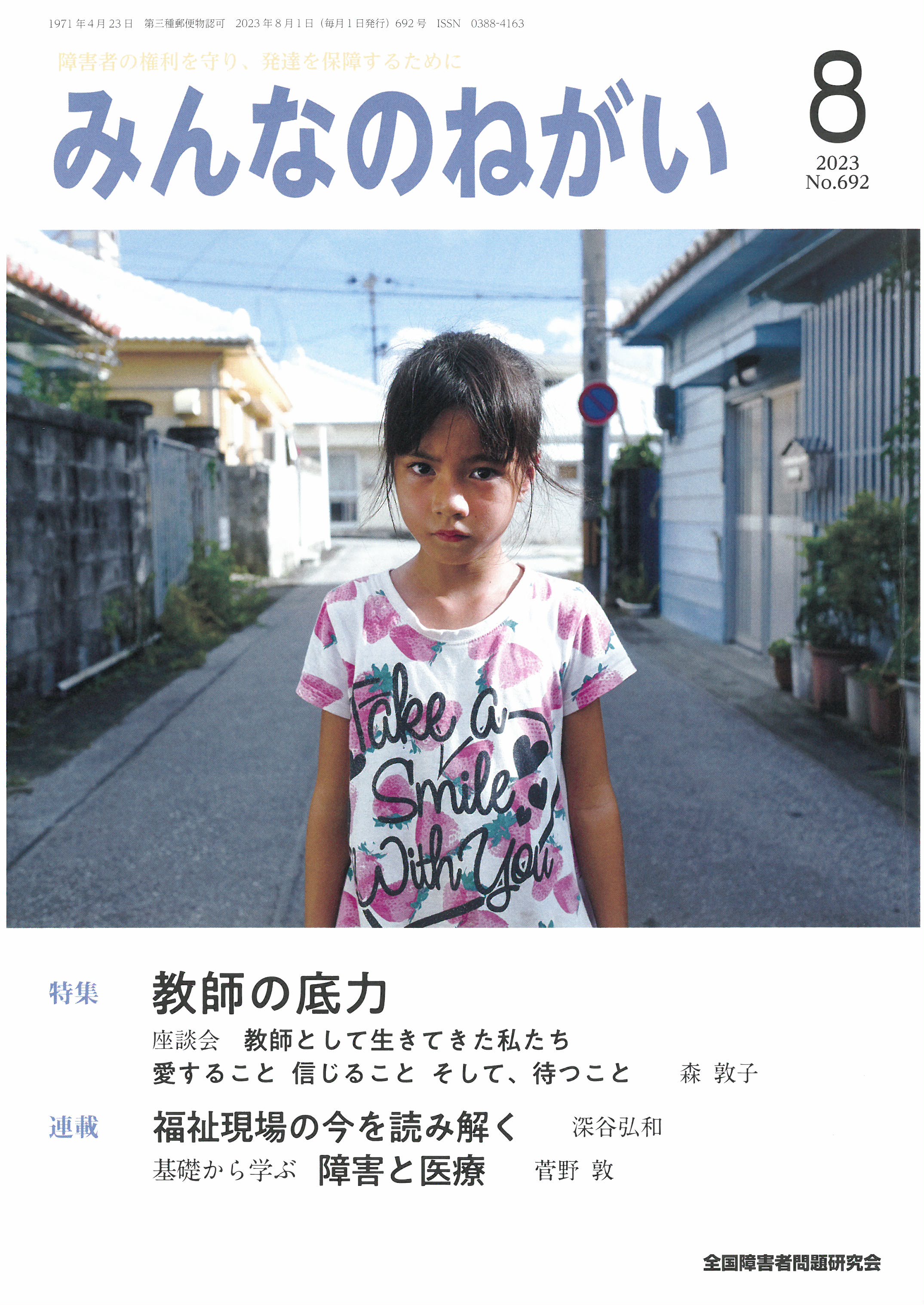
<表紙のことば>
僕が幾度となく撮影に訪れる場所、沖縄。そしてハマった理由のひとつが沖縄の女性の目に惹かれたからである。彼女たちの澄んだ瞳は、強い日差しを吸い込み美しく輝いている。そしてその力強い眼差しは、様々な歴史的背景を生き抜いてきた血筋ゆえだろうか。
夏の昼下がり、コザの路地裏で遊ぶ子供たちの中に居たその少女の瞳に僕は引き込まれてしまった。目は口ほどにものを言う、しかし彼女の目はそれ以上に何かを訴え、想像させる力があった。僕はいつも旅先でファインダー越しに一瞬の恋をする。そしてまたこの土地を訪れたくなるのだ。
土佐和史 とさかずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある。
<目次>
1 人として/吉田重子(ラジオパーソナリティ)
2 【インタビュー】今、あなたと生きて 丸山正樹(小説家)
4 この子と歩む/川﨑美春(甲府市)
7 私のタカラモノ/佐藤 陽(新潟)
8 仲間がいっぱい ひろしまの療育5/石木恵子(広島乳幼児サークル代表)
11 世界の風/児玉正文(ブルガリア)
特集 教師の底力
12 座談会 教師として生きてきた私たち
16 おおらかで温かな学校づくり/坂戸千明(長野)
17 でこぼこな自分を愛して/瀧川惠里子(千葉)
18 子どもたちの笑顔と同僚との語り合いのなかで/藤田明宏(北海道)
19 お母さんたちに育てられて/西堂直子(大阪青山大学)
20 こんな学校をつくりたい 先生たちの〈ねがい〉アンケート
22 愛すること 信じること そして、待つこと/森 敦子(高知)
24 発達のなかの煌(きら)めき 第Ⅱ部5回/白石正久・白石恵理子
28 社会をみる/杉田真衣(東京都立大学)
30 福祉現場の今を読み解く/深谷弘和(天理大学)
32 基礎から学ぶ 障害と医療/菅野 敦(東京学芸大学名誉教授)
34 私ときょうだい/久保田優里(滋賀)
36 実践の魅力/磯部浩美(埼玉)
39 支部だより/中山富喜子(山梨)
40 発達保障インタビュー バトンゾ→ン 細野浩一(埼玉支部)
42 みんなのひろば
44 ニュースナビ 教員不足と近年の教員政策/本誌編集部
46 誠司くんの見たこと、聞いたこと、歩いてきた道/松本誠司(高知)
47 BOOK/編集後記
裏表紙 心のことば 島田伊織
デザイン・イラスト うじたなおき、永野徹子、橋野桃子、細川茉莉
▶ご購読は出版部オンラインへ
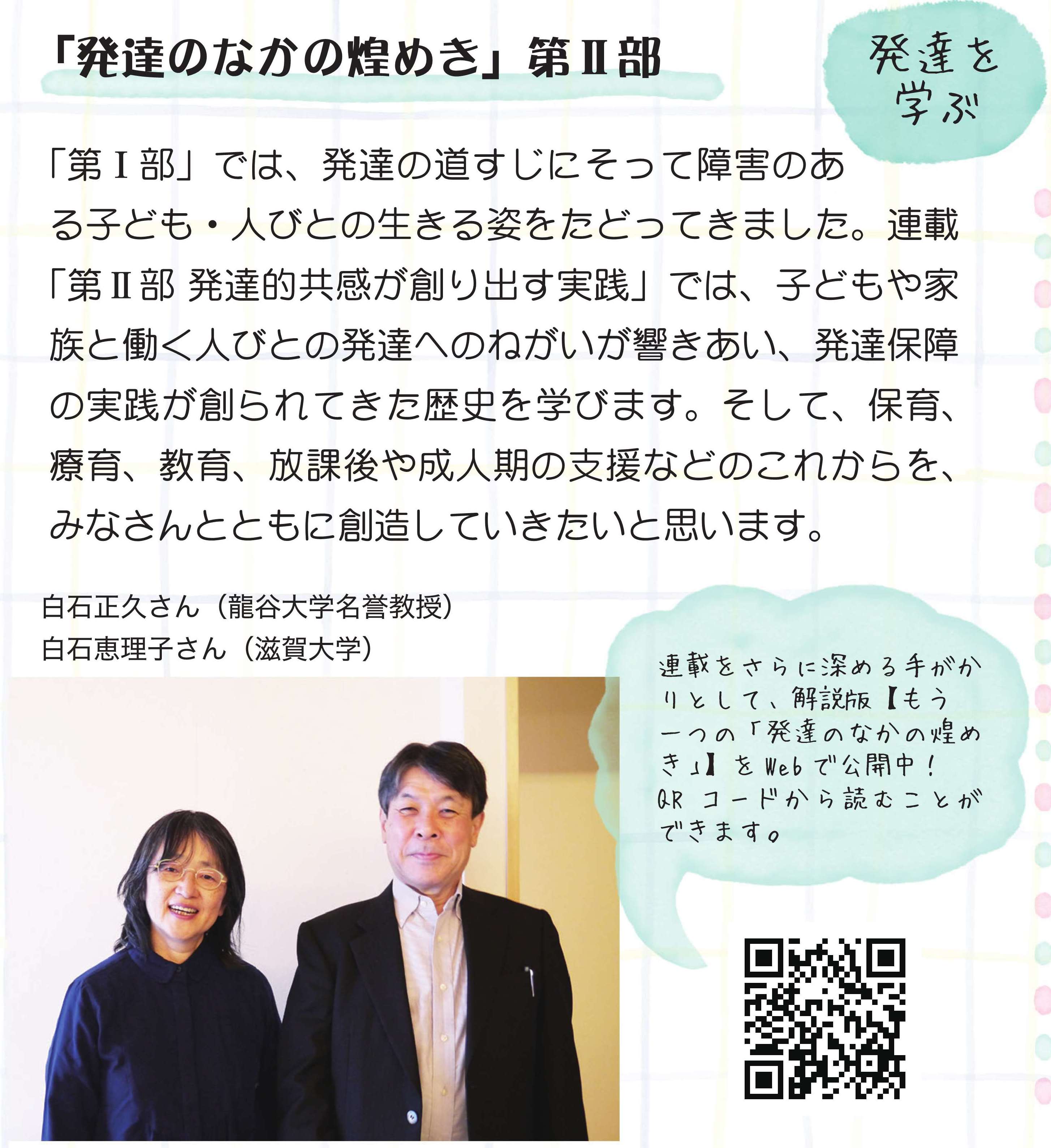
「障害者問題研究」51巻1号
特集=発達保障のための教育環境・学校設備
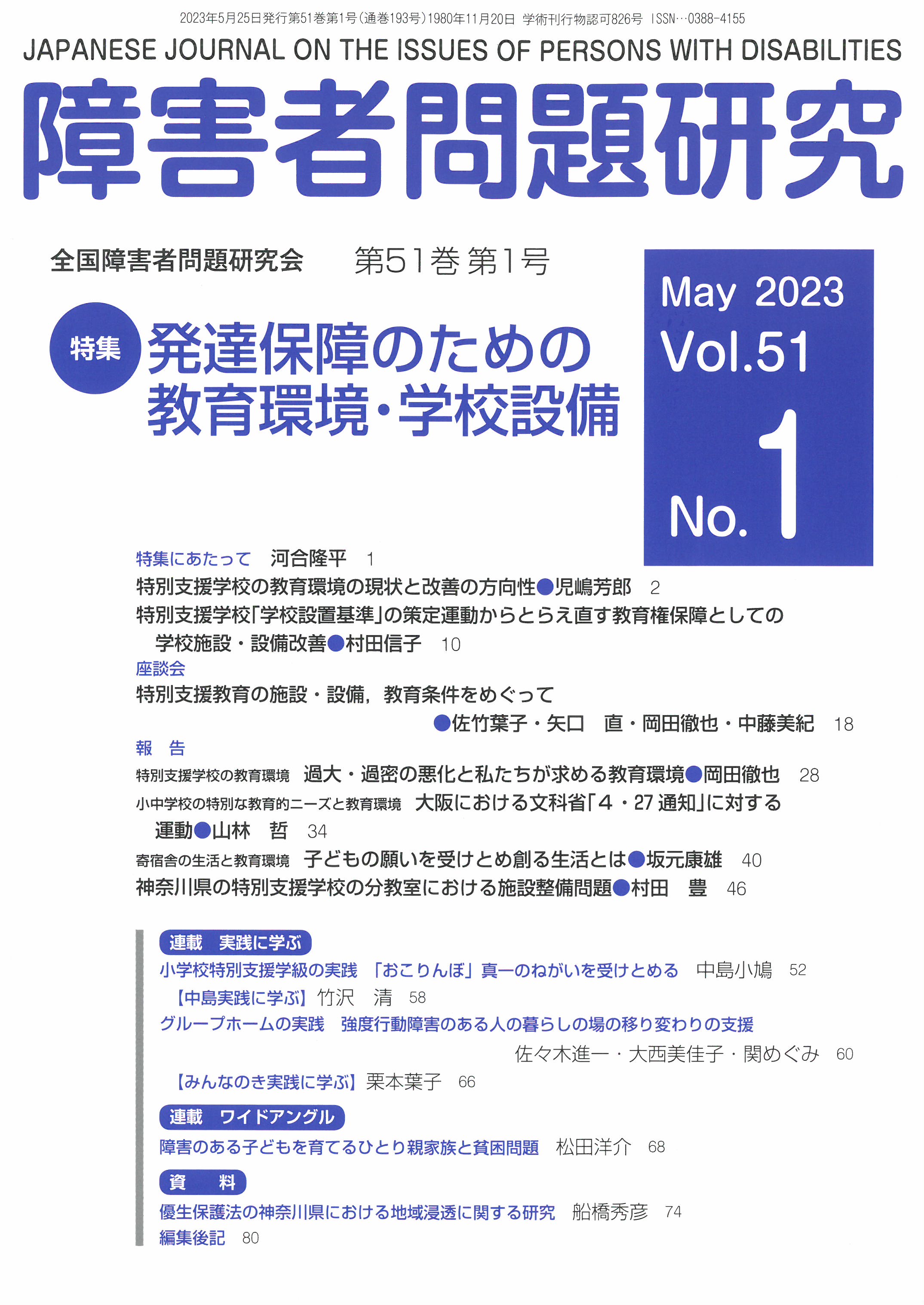
JAPANESE JOURNAL ON THE ISSUES OF PERSONS WITH DISABILTIES
2023年5月25日発行 ISBN-984-4-88134-096-7 C3037 定価2750円(本体2500円+税)
特集 発達保障のための教育環境・学校設備
特別支援学校の教育環境の現状と改善の方向性/児嶋 芳郎 立正大学社会福祉学部
本稿では,まず特別支援学校の教育環境の現状を概観した.そこでは,在籍児童生徒数が激増しているのに対して,学校数がそれに対応できるだけ新設されていないことを示した.また,そのために教室不足など教育環境が悪化し,過密・過大化が進行していることを指摘した.次に,特別支援学校に必要となる特別教室について,特別支援学校施設整備指針を参照して検討した.これらを受けて,過密・過大化の教育実践への負の影響について,物理的側面,人的側面から指摘し,改善の方向として,学級数の標準を設けること,余裕のある教室設置が必要であること,分散化が必要であることを提起した.最後に,子ども・家族・教職員・関係者が,よりよい教育,より豊かな教育実践を展開できる基盤としての教育環境整備について考え合い,それを実現するために教育行政が公的責任を果たさなければならないことを指摘した.
特別支援学校「学校設置基準」の策定運動からとらえ直す教育権保障としての学校施設・設備改善
/村田 信子 全日本教職員組合障害児教育部
全国に広がり常態化している特別支援学校の過大・過密,教室不足を解消すべく,十余年かけて設置基準策定運動に取り組み,「特別支援学校設置基準」が制定された.全教障害児教育部は,その設置基準策定前に「私たちがもとめる設置基準案」づくりを行い,その過程で教職員,保護者,研究者らの教育条件改善への要求を結集させた.「特別支援学校設置基準」は制定されたが,既存校を適用猶予しているために,劣悪な教育環境の改善が見込まれない.保護者,市民,教職員らは,既存校へ適用することや,基準の改善を求める運動にも引き続き取り組んでいる.設置基準をめぐる問題の根底にはそもそも日本の「学校設置基準」の教育法制としての不十分さがあることを指摘した.
【座談会】特別支援教育の施設・設備,教育条件をめぐって
出席者=佐竹 葉子(埼玉)・矢口 直(東京)・岡田 徹也(滋賀)・中藤 美紀(高知)
司会=河合 隆平(東京都立大学,本誌編集委員)
報告 特別支援学校の教育環境 過大・過密の悪化と私たちが求める教育環境
/岡田 徹也 全国障害者問題研究会滋賀支部
報告 小中学校の特別な教育的ニーズと教育環境 大阪における文科省「4・27通知」に対する運動
/山林 哲 大阪市立茨田西小学校特別支援学級担任、大阪教職員組合障害児教育部
報告 寄宿舎の生活と教育環境 子どもの願いを受けとめ創る生活とは
/坂元 康雄 東京都立葛飾盲学校寄宿舎指導員
報告 神奈川県の特別支援学校の分教室における施設整備問題
/村田 豊 神奈川県立障害児学校教職員組合
連載/実践に学ぶ
【報告】小学校教師の実践 「おこりんぼ」真一のねがいを受けとめる
/中島 小鳩 愛知県・公立小学校 特別支援学級担当
【中島実践に学ぶ】
「しなやかな」対応,「確かな」手立て ──中島実践の魅力
/竹沢 清 あいち障害者センター
連載/実践に学ぶ
【報告】グループホームの実践 強度行動障害のある人の暮らしの場の移り変わりの支援
/佐々木 進一・大西 美佳子・関 めぐみ 大阪府・社会福祉法人さつき福祉会
【みんなのき実践に学ぶ】
Aさんが「ここが自分の暮らす家」と思ってくれるまで
/栗本 葉子 社会福祉法人おおつ福祉会 おおぎの里
連載/ワイドアングル 第21回
障害のある子どもを育てるひとり親家族と貧困問題 ――「依存の私事化」と生活保護受給の論理
/松田 洋介 大東文化大学文学部
資料
優生保護法の神奈川県における地域浸透に関する研究
/船橋秀彦 全国障害者問題研究会茨城支部
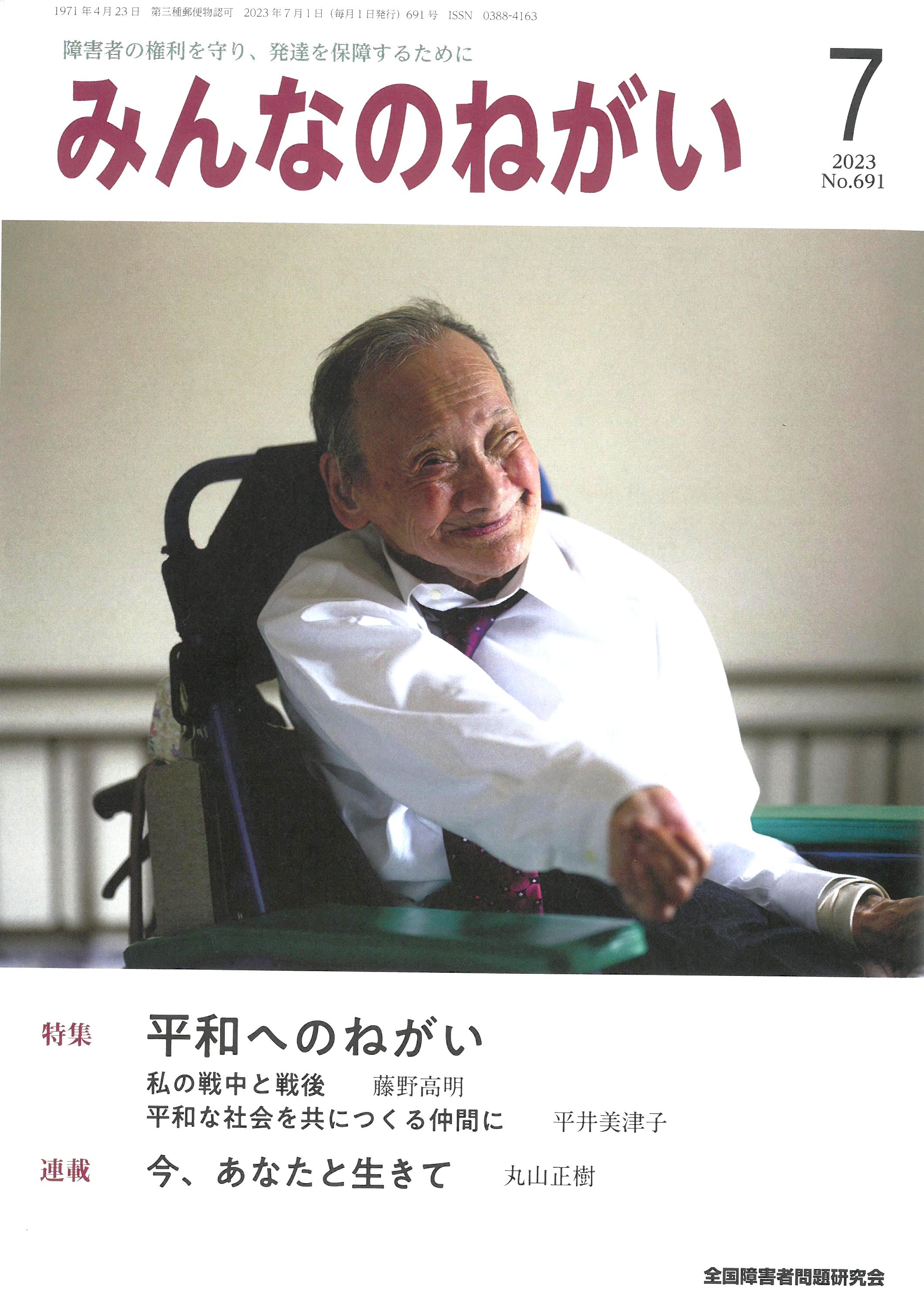
<表紙のことば>
98歳の松田春廣さんは、ネクタイ姿の正装で迎えてくれた。緊張のなか始まった撮影も徐々にほぐれていき、いい写真がたくさん撮れた。だけど、僕は撮影することをやめられなかった。いちど下ろしたカメラを何度も上げてはシャッターを切り続ける。松田さんもそれに応えるように笑顔を返し続けてくれた。とても大事なこの瞬間をできるだけ多く残さなければと思った。脳性麻痺という重い障害を抱えながら生きてきた98年間は、僕には計り知れない。ただ、今ここに間違いなく在るのは、全てを許してくれるような尊い笑顔だった。帰り際に握った松田さんの手は、優しくて、あたたかかった。
土佐和史 とさかずふみ/写真家。1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO PRESSを立ち上げる。写真集に、「SUNLIGHT MEMORIES」(CITYRATpress)「北関東」「路地裏に咲いた花」(いずれもBUFFALO PRESS)がある。
<目次>
1 人として/塚根みづな・宮崎優花(高校生平和大使)
2 【インタビュー】今、あなたと生きて/丸山正樹(小説家)
4 この子と歩む/田原聖子
7 私のタカラモノ/里見顕吾
8 仲間がいっぱい ひろしまの療育 第4回 保護者としてー生活者としてのわたし/真田友恵
11 世界の風/児玉正文
特集 平和へのねがい
12 平和へのねがい/安島弘祐・池田 光・太田修平・坂口賢洋・玉木八重子・服部もも
14 私の戦中と戦後/藤野高明 *藤野さんのスピーチ
17 平和な社会を共につくる仲間に/平井美津子
20 人との出会い、平和への思いをつなぐ/かめやまえいこ
22 『はだしのゲン』が描く平和の尊さ、戦争の愚かさ/井村 誠
24 発達のなかの煌(きら)めき/白石正久・白石恵理子
28 社会をみる/杉田真衣
30 福祉現場の今を読み解く/深谷弘和
32 基礎から学ぶ 障害と医療/菅野 敦
34 私ときょうだい/新井利民
36 実践の魅力/砂川一茂
39 支部だより/ 瀧川惠里子
40 発達保障インタビュー バトンゾ→ン /纐纈建史
42 みんなのひろば
44 ニュースナビ 天海訴訟の勝訴とこれから/三橋恒夫
46 誠司くんの見たこと、聞いたこと、歩いてきた道/松本誠司
47 BOOK 編集後記
裏表紙 心のことば 内田貴大
デザイン・イラスト うじたなおき、永野徹子、橋野桃子、細川茉莉
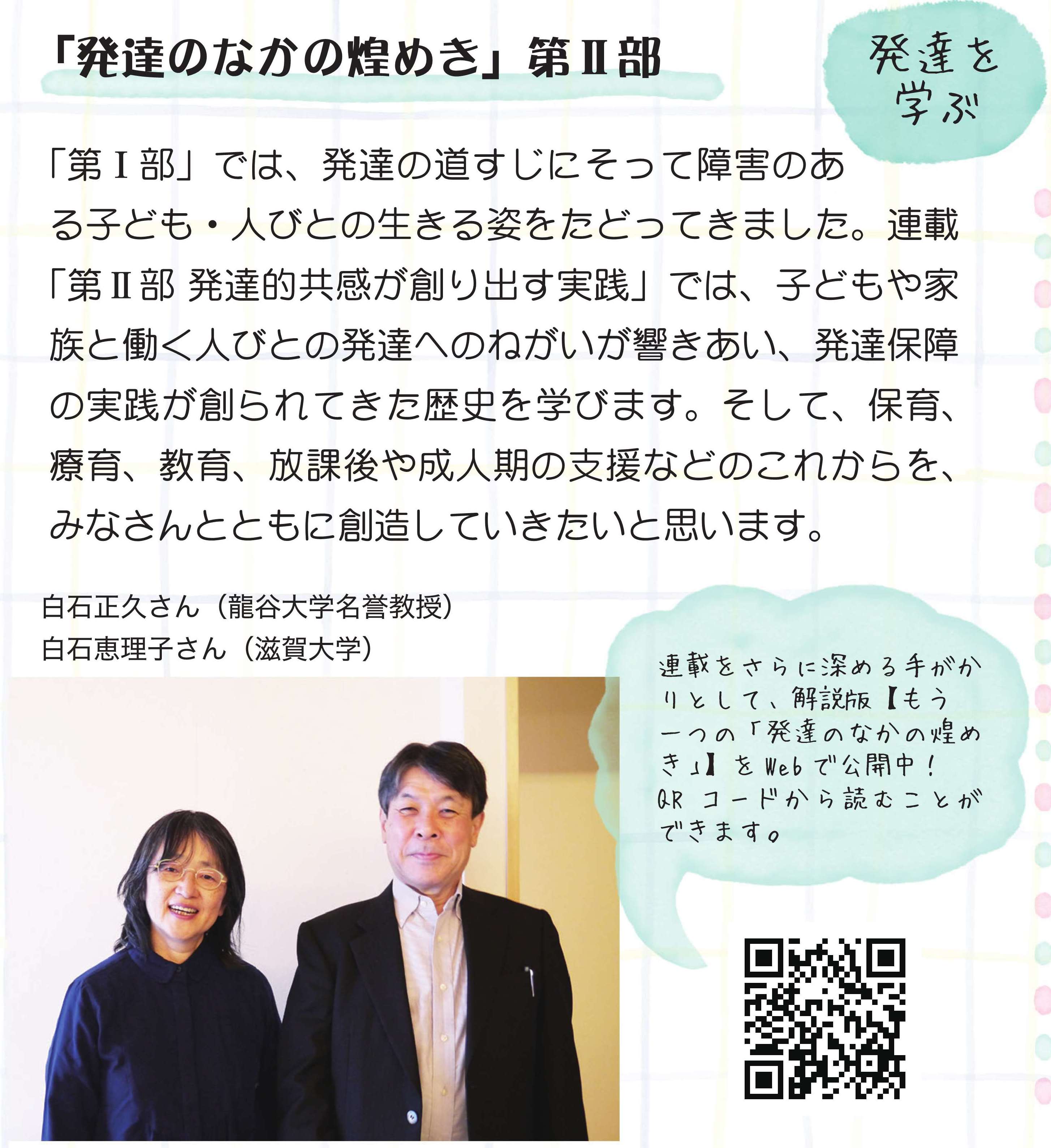
◆全国事務局体制について 2023年6月12日
新型コロナの感染拡大により、全国事務局は、なによりも職員のいのちと健康を守り、感染リスクを減らしながら事務所機能の維持をはかってまいりましが、本日より、感染リスクに注意しながら、通常業務といたします。
◆当面する全国事務局体制について 2022年3月22日
新型コロナの感染は2月のピーク時からは下がりつ つある感じですが、一日数万人の新規感染者が発生し、100人をこえる死者が出る日もあります。「まん延防止等重点措置」は21日で解除されましたが、東京に事務所を置く全国事務局は、
なによりも職員のいのちと健康を守り、感染リスクを減らしながら事務所機能の維持をはかりたいと考えます。当面、つぎのような対応をつづけさせていただきます。
1) 通勤時の感染リスクを減らし、時差通勤もしやすいように 事務所の 開所時間を10時~16時 とします。 2)職員は出所日以外は在宅勤務とします。そのため、出版物などの配送には時間をいただきます。
ご用件は 事務局メール( info@nginet.or.jp ) にお願いいたします。
◆当面する全国事務局体制について 2022年2月14日
新型コロナ・オミクロン株の感染がおさまりません。 なによりも職員のいのちと健康を守り、感染リスクを減らしながら事務所機能の維持をはかるため、
1月25日~2月13日までつぎのように対応してきましたが、さらに3週間(2月14日~3月6日)以下の対応をつづけさせていただきます。 1) 水曜日は閉所
します。 2)通勤時の感染リスクを減らし、時差通勤もしやすいように 事務所の 開所時間を10時~16時 とします。 3)職員は出所日以外は在宅勤務とします。そのため、出版物などの配送には時間をいただきます。
また、 ご用件は 事務局メール( info@nginet.or.jp ) にお願いいたします。
◆当面する全国事務局体制について 2022年1月24日
新型コロナ・オミクロン株の感染が増大しています。なによりも職員のいのちと健康を守り、感染リスクを減らしながら事務所機能の維持をはかるため、
今後3週間(1月25日~2月13日 、以降は今後の状況を見ながら検討します)つぎのように対応させていただきます。 1) 水曜日は閉所 します。
2)通勤時の感染リスクを減らし、時差通勤もしやすいように 事務所の開所時間を10時~16時 とします。 3)職員は出所日以外は在宅勤務とします。そのため、出版物などの配送には時間をいただきます。
また、ご用件は 事務局メール( info@nginet.or.jp ) にお願いいたします。
◆当面する全国事務局態勢について 2021年10月4日
新型コロナウィルス感染に対する「緊急事態宣言」は解除されました。
しかしながら、医療や検査体制含めた政府の対策は依然として不充分です。
こうした状況を踏まえ、全国事務局は、職員の健康と安全を第一に、ついては仕事や意志疎通のしやすさを大切にして、当面つぎのようにとりくませていただきます。
事務所は通常通り開所しますが、職員の勤務は合理的な「在宅勤務」や「時差通勤」も継続します。
物流関係の滞りもあり、書籍発送などにつきましては遅れてしまうことをご了承ください。
なお、今後の情勢により、適時変更させていただきます。
◆当面する全国事務局態勢について 2021年8月26日
新型コロナウィルスの急激な感染拡大と「医療崩壊」は深刻です。 なによりも職員の感染リスクを減らしながら、かつ最小限の事務所機能の維持をはかるため、当面、緊急事態宣言の期間(~9月12日)(その後は今後の状況を見ながら検討)つぎのように対応させていただきます。
1) 水曜日は閉所 します。 2)通勤時の感染リスクを減らし、時差通勤もしやすいように 事務所の 開所時間を 10時~16時 とします。
3)職員は分担して開所につとめますが、出所日以外は在宅勤務とします。 そのため、出版物などの配送には時間をいただきます。 また、ご用件は、 事務局メール(
info@nginet.or.jp ) にお願いいたします。
◆当面する全国事務局体制について 2021年7月14日
7月12日から8月22日まで、東京は新型コロナウイルス感染に対する4度目の「緊急事態宣言」が出されています。全障研は、「コロナ禍の下でのオリパラ強行ではなく、すべての人々のいのちと健康、くらしを守ろう」と声明(http://www.nginet.or.jp/posts/news20.html)しましたが、政府は、「無観客」としながもオリパラ開催に固執しています。
こうした状況を踏まえ、8月7、8日に開催する第55回全国大会(静岡2021)オンラインの準備等がもっとも集中する時期でもありますが、全国事務局は、なによりも職員の健康と安全を第一に考え、ついては仕事や意思疎通のしやすさも大切にして、当面つぎのようにとりくませていただきます。
合理的な「在宅勤務」や「時差出勤」などを継続します。首都圏などでは物流関係の滞りもあり、書籍発送等につきましては遅れてしまうことをご了承ください。
ご連絡窓口は、電子メール=info@nginet.or.jpにお願いいたします。
なお、今後の情勢により、適宜変更させていただきます。
◆当面する全国事務局体制について 2021年6月21日
新型コロナウイルス感染に対する「緊急事態宣言」は解除されましたが、首都圏では「まん延防止等重点措置」が講じられています。東京の場合、高齢者を対象とするワクチン接種が1回目46%、2回目12%をこえたところです。新規感染者数は依然として高い傾向にあり、新しい変異株による感染増も懸念されています。
全障研は、「コロナ禍の下でのオリパラ強行ではなく、すべての人々のいのちと健康、くらしを守ろう」と声明しましたが、政府は、オリパラを観客を入れて強行しようとしています。
こうした状況を踏まえ、全国事務局は、なによりも職員の健康と安全を第一に、ついては仕事や意思疎通のしやすさを大切にして、当面つぎのようにとりくませていただきます。
「原則在宅勤務」体制から、合理的な「在宅勤務」や「時差出勤」なども継続します。首都圏では物流関係の滞りもあり、書籍発送等につきましては遅れてしまうことをご了承ください。
ご連絡は、できるだけ 電子メール=info@nginet.or.jp にてお願いいたします。
なお、今後の情勢により、適宜変更させていただきます。
◆当面する全国事務局体制について 2021年4月26日
新型コロナウイルス感染に対する「緊急事態宣言」が解除されて一月余りですが、東京、大阪、京都、兵庫に三度目の「緊急事態宣言」が発出されました。変異株による感染拡大も懸念されます。こうした情勢を踏まえ、なによりも職員などの安全と生命を守るため、全国事務局は当面、原則在宅勤務体制とします。
そのため窓口は、電子メール=info@nginet.or.jpを基本とさせていただきます。
書籍などの発送等につきましてはたいへん遅れてしまうことをご了承ください。
なお、事務所運営の基本方針は、今後の情勢により適宜変更させていただきます。
◆当面する全国事務局体制について 2021年3月24日
新型コロナウイルス感染に対する「緊急事態宣言」は解除されましたが、首都圏などでは新規感染者数は増加傾向にあり、変異株による感染も対応が求められています。政府の対策は極めて不充分なままです。こうした状況を踏まえ、全国事務局は、職員の健康と安全を第一に、ついては仕事や意思疎通のしやすさを大切にして、当面つぎのようにとりくませていただきます。
「原則在宅勤務」体制から「開所」としますが、引き続き合理的な「在宅勤務」や「時差出勤」も継続します。「フィジカル・ディスタンス」などに留意しす。書籍発送等につきましては遅れてしまうことをご了承ください。なお、今後の情勢により、適宜変更させていただきます。
◆当面する全国事務局体制について 2021年1月6日
新しい年を迎えましたが、「一都三県に緊急事態宣言発出を検討」という政府の対応が報じられています。首都圏の新型コロナ感染拡大の情勢を踏まえ、なによりもスタッフなどの安全と生命を守るため、全国事務局は当面、原則在宅勤務体制とします。
そのため窓口は、電子メール=info@nginet.or.jpを基本とさせていただきます。書籍発送等につきましてはたいへん遅れてしまうことをご了承ください。
なお事務所運営の基本方針は、今後の情勢により適宜変更させていただきます。
◆当面する全国事務局体制について 2020年6月4日
新型コロナウイルス感染に対する「緊急事態宣言」の解除、東京の「アラート発令」などの状況を総合的に検討し、当面つぎのようにとりくませていただきます。
全国事務局は「原則在宅勤務」から「開所」します。状況に応じての「時差出勤」や「フィジカル・ディスタンス」などに留意します。 なお、今後の情勢により、適宜変更させていただきます。
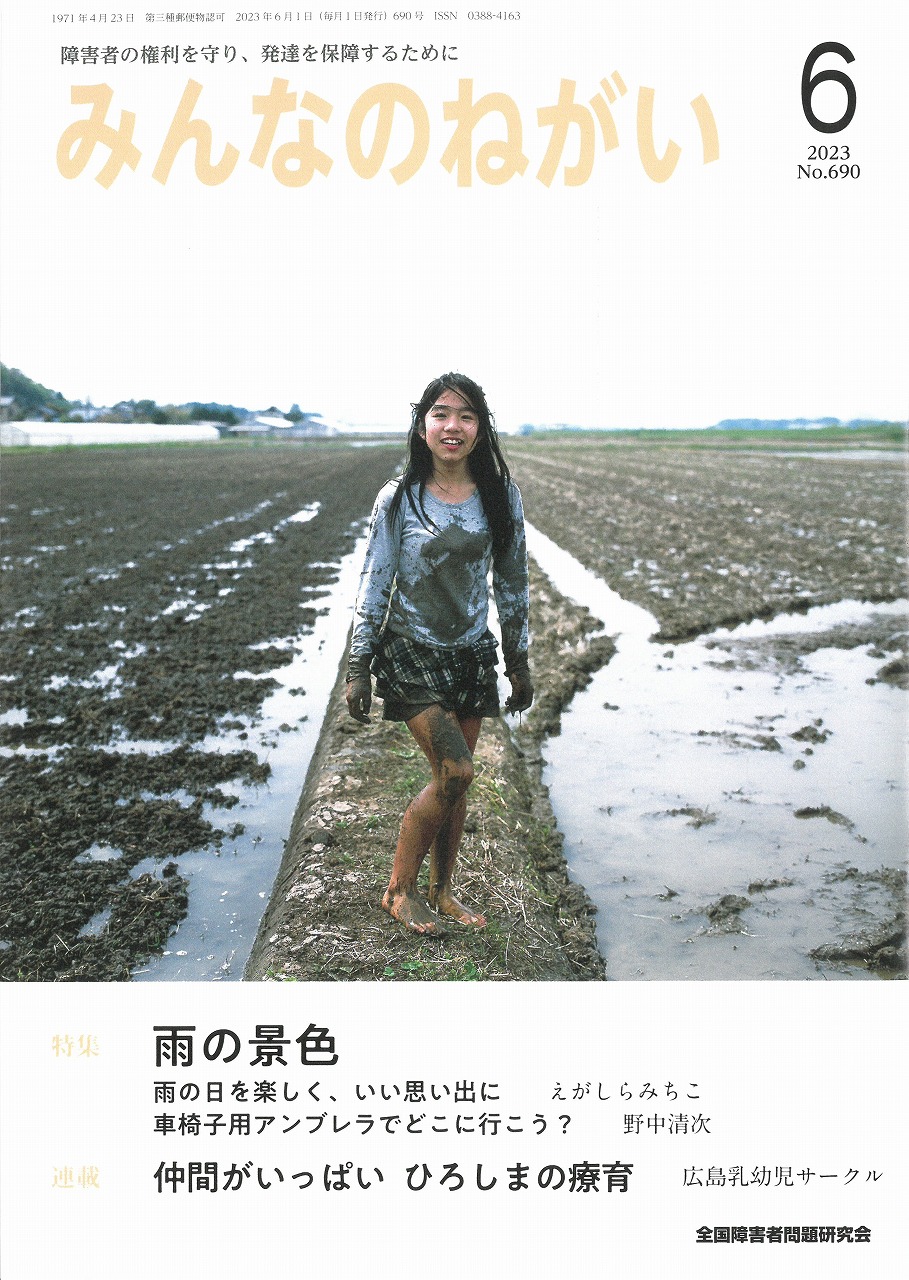
<表紙のことば>
地方を旅していると素晴らしいシーンに出会うことがある。 茨城県のとある村の農道を走っていると、子供たちが田植え前の田んぼに入って遊んでいるのが見えてきた。僕は思わずブレーキを踏んで、しばらく見入ってしまった。あまりに楽しそうに泥んこまみれになってはしゃいでいる姿は、もはや神々しく見えた。これは撮らなきゃ。カメラを手に田んぼに駆け寄っていって声をかけ、僕は夢中でシャッターを切った。
幼い頃遊んだあの土の匂いは遠い昔のかすかな記憶になってしまった。「どんなに文明が発達しても、人は土から離れては生きられないのよ」有名なアニメ映画の台詞が、ふとよぎった。
土佐和史 とさ かずふみ/1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO
<目次>
1 人として 田中偉登
2 【インタビュー】今、あなたと生きて 丸山正樹
4 この子と歩む 藤井佳樹
7 私のタカラモノ 岡本容昌
8 仲間がいっぱい ひろしまの療育 桑田和子
11 世界の風 児玉正文
特集 雨の景色
12 私と雨 竹岡久美子・中村くに子・小倉壮広・長﨑 勤・山本康弘
14 雨の日を楽しく、いい思い出に えがしらみちこ
16 車椅子用アンブレラでどこに行こう? 野中清次
18 雨という「季節・文化」を子どもたちに伝えていくために 若山健太
20 雲、雨、豪雨を実験で学ぶ 澤田淳太郎
22 雨を主体的に遊ぶ子どもたち―川崎市子ども夢パーク
24 発達のなかの煌(きら)めき 白石正久・白石恵理子
28 社会をみる 杉田真衣
30 福祉現場の今を読み解く 深谷弘和
32 基礎から学ぶ 障害と医療 狗巻修司
34 私ときょうだい 齋木よしみ
36 実践の魅力 足立紀夫
39 支部だより 森 安子
40 発達保障インタビュー バトンゾ→ン 纐纈建史
42 みんなのひろば
44 ニュースナビ 通常学級に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒調査 山中冴子
46 誠司くんの見たこと、聞いたこと、歩いてきた道 松本誠司
47 BOOK/編集後記
裏表紙 心のことば 内田貴大
デザイン・イラスト うじたなおき、永野徹子、橋野桃子、細川茉莉
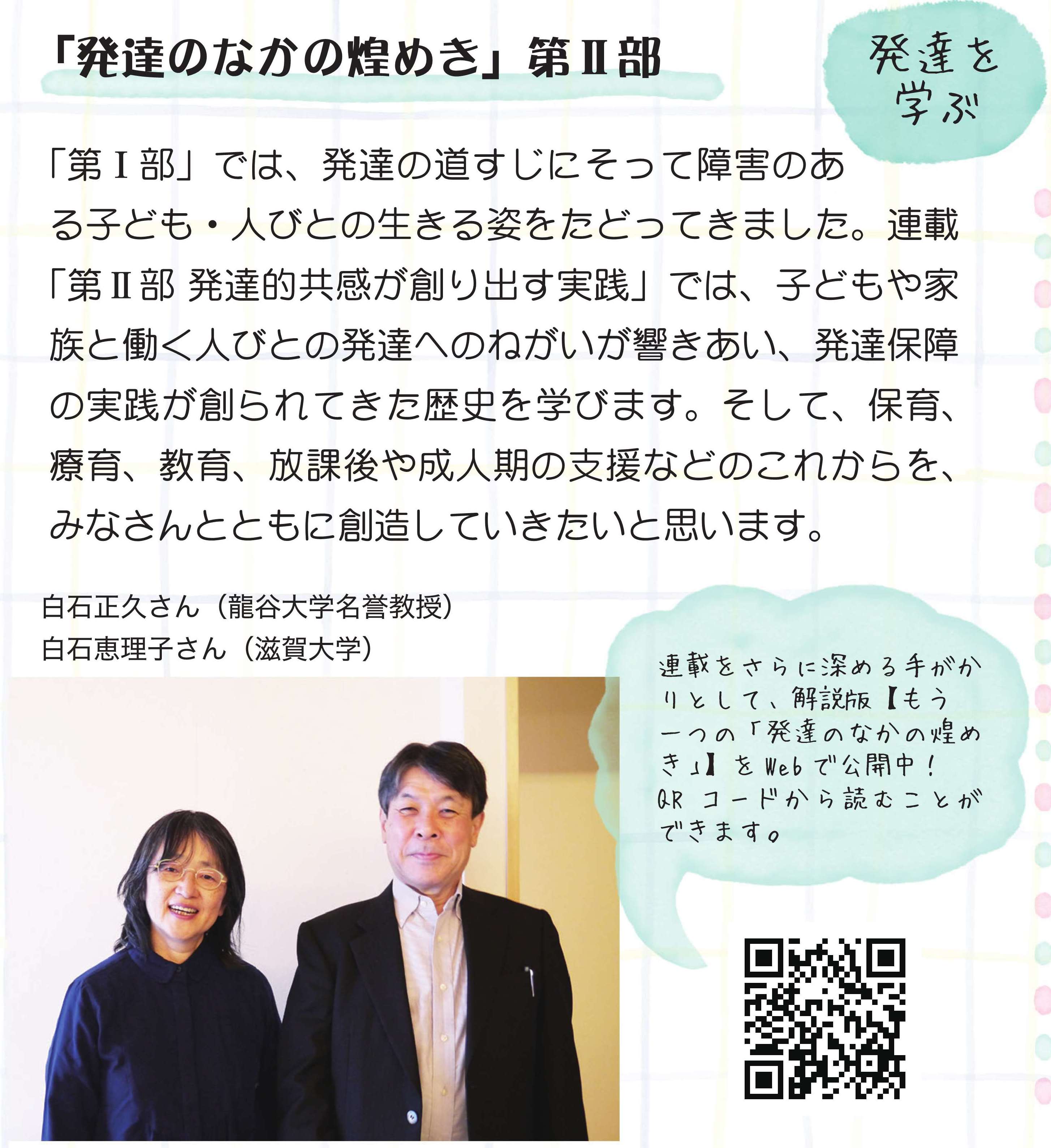
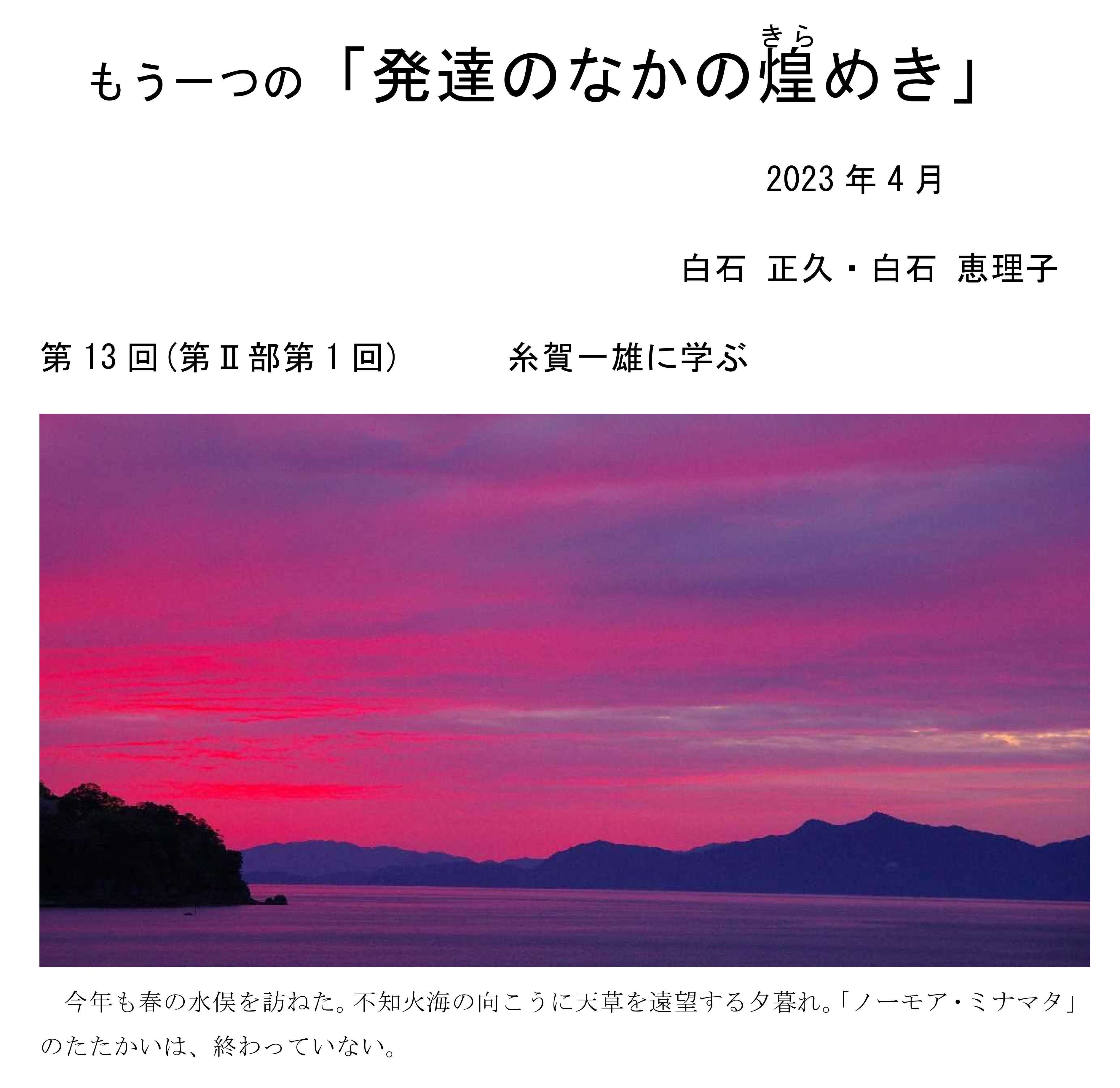
はじめに
連載も第Ⅱ部に入りました。昨年度の第Ⅰ部では、発達の道すじにそって障害のある子ども・人びとの生きる姿をたどってきました。この「もう一つ」も、発達の道すじについて、読者のみなさんと共有したり議論したりができることを、ねらいの一つにおいて書いてきました。今年度4月号からの「第Ⅱ部
発達的共感が創り出す実践」では、より実践にシフトさせながら連載を進めていきますが、この「もう一つ」では、連載をお読みいただくにあたって、連載でとりあげたことの背景や、連載では書ききれなかったことをお伝えしていきます。引きつづき、連載とあわせてお読みくだされば幸いです。
第1回(4月号)では、まずは第Ⅱ部のタイトルにもある“発達的共感”について考えたいと、糸賀一雄を取り上げました。さっそく、品川文雄さん(元全障研全国委員長)から、以下のようなご感想をいただきました。このように『みんなのねがい』が、みなさんの人生と重なり、さまざまなところで、実践の討議や共感となって拡がっていくことを、私たちはうれしく思います。
糸賀たちが「浮浪児」と知的障害の子どもたち両方を近江学園で受けとめたことは、発達論を考える上でも、教育のあり方を考える上でも重要なことであると4月号を読んで、考えました。
両方の子どもたちを受けとめたからこそ、「共通の発達観と、その発達の道すじに障害を位置づけてとらえる障害観が、『共感の世界』の根底に位置づくようになっていた」のでしょう。ここは大変重要な問題提起であると思います。
障害はないが、「戦争孤児」たちは強烈な「人間への不信感」と丁寧に育てられなかったため「いびつな育ち」をしていたと思います。最近読んだ「戦争孤児」を描いた児童文学では、隣に寝ていた仲間の戦争孤児が翌朝には亡くなっていたことがいくつも書かれていました。明日の死と向き合いつつ、今日をとにかく何が何でも生きる、苛烈な日々、人生だったと思います。そんな「浮浪児」たちを受けとめることは、受けとめる側が深い人間観と指導観を持たなくては、なしえないだろうと思います。そのために糸賀をはじめ職員たちは深く学習し互いの古い人間観・発達観をそぎ落とし新たな人間観を作り上げていったのだと思います。
1972年私が教員になってはじめて担当した中学生たちも家庭はありましたが、どの家庭も過酷でした。それまでの私の人生では経験したことのない厳しさ、悲しさ、辛さを生徒たちは抱えていました。どう指導するか悩み悩み、読んで学んだ本、いやすがりつくように読んで学んだ本はクルプスカヤ(旧ソ連の教育学者、『国民教育と民主主義』など)の著作でした。どんなに熱心に教育しても裏切られ反発される日々のなかでクルプスカヤの著作は光明でした。4月号を読んでいると、そんなことまで思い出しました。「人間が生きていく上になくてはならない共感の世界」を我が学級にも作り出さなくてはならない、そんな思いで苦しみながら努力したことを思い出しました。
障害のある児童生徒への教育・保育を行う私たちはどうしても障害の大変さ、発達の遅れを見てしまいがちです。でも、さきほども書いた「共通の発達観と、その発達の道すじに障害を位置づけてとらえる障害観が、『共感の世界』の根底に位置」づけて、教育実践をすすめなくてはならない。それも考えさせられました。
感想を書き始めたら、止まらなくなりそうです。(品川文雄)
さて、今回の「もう一つの『発達のなかの煌めき』」についてです。糸賀の「この子らを世の光に」ということばは、あまりにも有名ですが、そこにはどのような意味が込められていたのでしょうか。今回の「もう一つ」の前半では、第1回の解説として、そのことをお話しします。後半では、「この子らを世の光に」に至る前史について補足します。近江学園をはじめとする諸施設を立ち上げていく草創期において、学園の内外の困難に直面した30歳代の糸賀が、その人間、集団、社会の諸矛盾といかに向きあおうとしたか、いかなる道標を得ていったかを学びたいと思います。
Ⅰ.糸賀一雄と「この子らを世の光に」
糸賀一雄について
糸賀は、1914(大正3)年3月に鳥取市に生まれます。この年に第一次世界大戦が始まり、尋常小学校に入学した1920年には戦後の経済恐慌、さらに1923年には関東大震災とつづくなか、国民の生活は劣悪な状況におかれ、乳児死亡率も非常に高い時期でした。糸賀は1930年に旧制松江高等学校に入学しますが、病気のため休学。この頃、鳥取教会で受洗したとされています。高等学校卒業後、1935年に京都帝国大学文学部哲学科に入学、宗教学を専攻します。翌年には結婚。1937年には日中戦争が始まり、大学を卒業した1938年には国家総動員法が公布され、国民生活全体に戦時色が強まっていきます。大学卒業後、京都市の尋常小学校で代用教員の職に就きますが、間もなく赤紙の招集をうけました。その後、近江学園設立に至る経緯は、4月号に記した通りです。
没後14、5年がたった1982-3年に『糸賀一雄著作集』(日本放送出版協会)が3巻本で出されていますが、その第Ⅲ巻には、1961年6月から、1968年9月に亡くなる直前までの著作が収録されています(ただし1965年の『この子らを世の光に』は第Ⅰ巻、未刊の主著『精神薄弱と現代社会』は第Ⅱ巻に収められています)。第Ⅲ巻の「刊行の辞」で、岡崎英彦(びわこ学園初代園長)は、この時期は「病気のため体力の衰えがかなり急速に進んだ時期」であったが、「それにもかかわらず、先生の思想の形成過程からみれば、むしろ鋭さを内に秘めた、それだけ迫力にみちた、最も力強い時期であった」とし、その背景には「最も重い障害をもって必死に生きる重症心身障害児とかかわり、その中に生き生きとした人間存在の核心というべきものを確認されたからであるとみてよいであろう」と述べています。さらには、重症心身障害児とのかかわりによって、「それまで悩んでおられた人間的矛盾、社会の矛盾を、思想的に克服され」、「身体の衰えとはうらはらに、精神の高揚と平安があったとしてもうなずける」とします。
このことを、もう少しみていきましょう。
近江学園創設は戦後すぐの1946年であり、糸賀、32歳の秋でした。1948年に児童福祉法の施行に伴い、滋賀県立の養護施設兼「精神薄弱」児施設となりました。同時期に、重度「精神薄弱」児のための「さくら組」が編成されています(その後、1950年に「落穂寮」ができ、そこに「さくら組」の子どもたちは移ります)。また、1949年には、学校教育法にもとづき園内に小学校、中学校の分校が設置されますが、教育施設の設置や予算の配分は1962年までなされませんでした。知的障害のない子どもたち(戦争孤児たち)は徐々に進路を見出していきますが、知的障害のある子どもたちの進路は厳しく、新たに入園してくる子どもたちの多くも知的障害のある子どもでした。1952年には新しく「さくら組」が編成されますが、教育委員会からの教育費の支給はなく、財政的困難が増大したとされます。一方で、「さくら組」の寛ちゃんが立木観音(大津市南郷から京都府宇治市に向かう瀬田川沿いにある)近くにある水車小屋で、水車の苔からとびちる無数の水玉に一日中見入っていたというエピソード(学園では、行方不明の寛ちゃんを探して大騒動でした)や、本物の狂言をみて(先生たちは、重度知的障害のある子どもたちに狂言の理解は難しいだろうと思っていたのですが)、「さくら組」の子どもたちが、狂言のツボにくるとキャーキャー声をあげ、手を叩く姿をみて、狂言の面白さがわかっている、理解力や言語力に困難を抱えていても、「感ずる世界」をもっているし、それは、障害のない子どもたちと何も変わらないという見方を深めていきました。「芸術に感動する心は、ひととひととのこまやかな心のやりとりがわかる心であり、愛情と意欲にめざめることのできる心である」(『福祉の思想』、第Ⅲ巻26ページ。以下での引用ページの表示は、すべて『著作集』のものである)と糸賀は述べます。だからこそ、財政的には厳しくても、重度知的障害のある子どもたちが発達していけるような教育が必要だと、実践的な試行錯誤を繰り返していったのです。
「杉の子組」のこと
1953年には、「重度のてんかんと強度のノイローゼの児童2名」の長期療育が医局で開始され、翌1954年に「杉の子組」が発足します。2年くらいたったとき、「われわれがいちばん悲しくまた辛く思うことは、このごろの児童相談に、二重、三重の障害をもった子どもたちがたくさん出てきたこと、その子どもたちを引き受ける設備も能力も乏しい…乏しいなどというよりも、無能であるといったほうがほんとうかもしれない」と、当時の児童7人につき1人という精神薄弱児施設の職員配置の問題を告発しています。さらに、「二重三重障害の子どもたちも、だれひとりの例外なく、感ずる世界、意欲する世界をもっている。ただ生かしておけばよいのではなく、どのような生き方をしたいと思っているかを知り、語り合い、触れ合い、お互いにより高い生き方へと高められてゆくような指導がなされねばならない」と述べています(『近江学園年報』第8号、1958年)。さらに1959(昭和34)年には園児の死亡が相次ぎ、療育施設建設の決意をより強め、それがびわこ学園建設へとつながっていきます。
そこから、逝去に至るまでの約10年間は、岡崎の言う「鋭さを内に秘めた、それだけ迫力にみちた、最も力強い時期」「それまで悩んでおられた人間的矛盾、社会の矛盾を、思想的に克服され」た時期となるのですが、以下に近江学園創設から亡くなるまでの重要事項を年表風に列記します。
1946年11月 近江学園創設
1947年 7月 年長児のための「一麦荘」設置
1948年 4月 児童福祉法施行により「滋賀県立近江学園」となる。
同 重度「精神薄弱」児の「さくら組」編成
1949年 1月 糸賀一雄、堅田教会に転入
同 2月 女子の「あざみ組」編成
1950年 5月 「落穂寮」開設
同 11月 堅田教会の「レーメンス・サンデー」講壇
1951年 4月 機関誌『南郷』に「魂の故郷―四年半の回想」投稿
1952年 4月 「滋賀県立信楽寮」開設
1953年 7月 「あざみ寮」開設
1954年 4月 重度の「杉の子組」開設
1956年 4月 田中昌人、京都大学助手から近江学園研究室職員へ
1957年12月 年少の「もみじ組」編成
1958年 3月 重症心身障害児のための施設の必要を具申
同 5月 大津市市制60周年を機に乳幼児健診に参加
1960年 9月 母子像“世の光”(森大造作)建立・除幕
同 11月 第10回国際社会事業会議(ローマ)出席と視察のためヨーロッパへ
1961年 2月 ヨーロッパより帰国
同 4月 知能指数という見方を廃止、暫定的に精神年齢による見方を採用
同 6月 心臓弁膜症及び心不全と診断される
1962年 5月 びわこ学園の建設着工
1963年 3月 指導体制論議において、可逆操作の概念を導入
1963年 4月 一次元可逆操作獲得前の児童の指導体制に着手
同 4月 びわこ学園開設
1965年 1月 第2びわこ学園の建設着工
同 11月 『この子らを世の光に―近江学園二十年の願い』(柏樹社)発刊
1966年 2月 第2びわこ学園開設
1966年 4月 養護施設を廃止し、精神薄弱児施設のみとなる
1967年 4月 療育記録映画「夜明け前の子どもたち」の撮影開始
同 8月 大津市民健康相談所が開設され、乳幼児の発達相談の実施に協力
1968年 4月 「夜明け前の子どもたち」試写会
同 2月 『福祉の思想』(日本放送出版協会)発刊
同 9月 糸賀一雄、逝去(54歳)
『福祉の思想』より
さて、4月号では、亡くなる直前に著された『福祉の思想』(1968年 日本放送出版協会)の1節を紹介しました。
「重症児が普通児と同じ発達のみちを通るということ、どんなにわずかでもその質的転換期の間でゆたかさをつくるのだということ、治療や指導はそれへの働きかけであり、それの評価が指導者の間に発達的共感をよびおこすのであり、それが源泉となって次の指導技術が生み出されてくるのだ。そしてそういう関係が、問題を特殊なものとするのでなく、社会の中につながりをつよめていく契機になるのだということ。そこからすべての人の発達保障の思想と基盤と方法が生まれてくるのだ」。
この『福祉の思想』の「はじめに」で、糸賀は、「精神薄弱という現象が社会で問題となるのは何によってなのであろうか。こういう根源的な問いに誘われることによって、私たちは社会の構造的な矛盾に目を向けさせられざるを得なかった。そしてその問題性は同時に人間の価値観に私たちをいざなうものでもあった」(17ページ)と述べます。そして「私たちはこの子どもたちとの共同生活のなかで、いつのまにか私たち自身のこの子たちをみる目の変革を経験させられてきたように思う」「わずかこの20年余りのあいだに、自分たちの目もかわってきたのではあるまいかと一種のおどろきをもってふりかえる」(17ページ)と言います。
重症心身障害のある子どもたちの「杉の子組」ができたこと、それが、びわこ学園設立につながったことは上述したとおりですが、1958年に「二重三重障害の子どもたちも、だれひとりの例外なく、感ずる世界、意欲する世界をもっている…お互いにより高い生き方へと高められてゆくような指導がなされねばならない」と書いた頃にはまだ、寛くんのような「精神薄弱」児から教えられたことは、どんなに障害が重くても重複していても共通している、普遍的なものであるに違いないという理念的な捉え方であったのではないでしょうか。
それが、びわこ学園での子どもたちの姿や実践を通して、より深い理解になっていきます。その確信は、「生命あるものは輝いている。それは一片の感傷でもなく文学でもない。現実である」(76ページ)という文に端的に示されていると考えます。1967年から始まった『夜明け前の子どもたち』の撮影フィルムを見ていくなかで、子どもたちの生活があざやかに描き出されます。
「五月の鯉のぼり、あの大きな布製の鯉のぼりが身近に横たわっている。それにさわってみることのよろこび。ポールにセットされた細綱の端に、自分の指を添えて、自分でもひっぱりあげている気持で、青空に高くあがる鯉を見あげているあどけない顔、顔、顔。また、野洲川の河原での石はこび。小石を入れものに入れたり出したり、運んだり、友だちと協同したり、ベッドに結びつけられていた紐をほどいて戸外に逃げ出していくときの解き放たれた姿など。そんなときのこの子らの顔は、ほんとうに輝いていた。表情は、たくさんの言葉なき言葉を発していた。彼らは多くのことをひとに訴えているのであった。
私たちは、この表情と言葉のそばを素通りしていたのである。この子たちは、生ける屍といわれていた。なされるがままになっているものと思われていた。しかし、そうではなかったのである。立派な意志があり、意欲があり、自己主張があった。外界から刺激をうけとるだけでなく、外界にたいし、先生や友だちにたいし、はたらきかけているのであった。外界を変えていこうとする努力があった。外界を媒介として自己主張を実現しようと、たゆみなくはたらいていたのである。」(77ページ)
重症心身障害児と言われる子どもたちが、決して「なされるがまま」「刺激をうけとるだけ」の存在ではなく、「外界を変えていこう」とたゆまぬ努力をしていることへの気づき、それはまさに、子どもたちの側に視座を移してみることへの変革でした。
もちろん、それは映画撮影によって突然に見えてきたものではありません。『この子らを世の光に』が出版されたのは1965年ですが、その頃には、「この子らに世の光を」ではなく「この子らを世の光に」だという確信が明確にありました。近江学園ができて20年、「精神薄弱」児たちと生活をともにし、幾度も失敗し、揺れ戻しも経験しながら職員集団でたどりついた「この子らを世の光に」が重要な意味をもっていました。
『福祉の思想』では、終わりの方で、次の1節が述べられます。
「この子らが不幸なものとして世の片隅、山峡の谷間に日の目もみずに放置されてきたことを訴えるばかりではいけない。この子らはどんなに重い障害をもっていても、だれととりかえることもできない個性的な自己実現をしているものなのである。人間と生まれて、その人なりの人間となっていくのである。その自己実現こそが創造であり、生産である。私たちのねがいは、重症な障害をもったこの子たちも立派な生産者であるということを、認めあえる社会をつくろうということである。『この子らに世の光を』あててやろうというあわれみの政策を求めているのではなく、この子らが自ら輝く素材そのものであるから、いよいよみがきをかけて輝かそうというのである。『この子らを世の光に』である。この子らが、生まれながらにしてもっている人格発達の権利を徹底的に保障せねばならぬということなのである。」(112ページ)
共感には年季がかかる
4月号では、子どもと本当に共感できるかどうか、人間的愛情が教育的愛に高まっていくには“年季がかかる”と述べたことにふれました。それはまさに、糸賀自身が、何度も壁にぶつかり、そのたびに自分の見方の浅さに気づかされ、苦しみ呻いてきたからでしょう。その痛みや恥に目をそむけず、目の前のいる「この子」たちが、生きよう、生きようとしている姿に教えられ、糸賀自身が何度も自分をつくりかえてきたからこそ、「何年かかってもいいではありませんか」という若い人びとへの言葉かけにつながっているように思います。その楽観性と人間的温かさがもつ深みにも、また心が動かされます。
「身分、経済、人種の不平等や差別の克服が人類の課題になってから久しいが、いま私たちは生まれながらの能力のちがいからくる差別観の克服に立ち向かうという、新しい課題の前に立たされていると思う。いまはまだ夜明け前であるが、この子たちをみる私たちの眼がどのように育つかということが、この課題解決の足がかりとなるということを想うのである。
それはつまりは、この子たちの存在そのものが、自分自身との対立にまで私たちを立ち向かわせるということにほかならない。
私たちは、この子たちの前に立って教育を語るまえに、自分自身を告白せねばならなくなる。そしてさらに、この問題は、およそ教育の名において単なる文化財の伝達をもってこと足れりとする立場を越えて、教育がその底に人間の教育について掘り下げられなければならない課題性をもつものであることを明らかにしてくれる。おそらくは教育とか福祉の根底を問うところに私たちをいざなう足がかりがあるといったほうが、より正しいことかもしれないと思うのである。」(113ページ)

Ⅱ.糸賀一雄、平和への誓いと「発達」の概念
「この子らを世の光に」そして「うまれながらにしてもっている人格発達の権利を徹底的に保障せねばならぬということなのである」という「発達保障」の理念に至った最後の10年の前にあって、それを準備したと言える学園の草創期のことをお話ししたいと思います。
時が前後してしまいますが、糸賀にも学園にも、次の時代の礎(いしずえ)を築くための苦悩のときがあったことを、理解していただけるのではないかと思います。
白浜での誓い
近江学園の4周年記念式を終えた1950(昭和25)年末から1951年にかけての日々は、糸賀にとっては大きな試練のときでした。36歳の冬です。
近江学園につづいて「信楽寮」や「あざみ寮」を開設し、それらの事業を前に進めて行くために多忙を極め、持病の心臓の病を抱えながら奔走する日々でした。そうやって学園の外に向かって行かなければならなかったとき、内では職員間のいさかい、セクトのような集団、陰口、自慢話、淫靡な噂などが横行し、「四六時中勤務、耐乏の生活、不断の研究」という「近江学園三条件」のもとでの勤務への不満も噴出するようになっていきました。こころざしを一つにし、困難を受け入れて集ったはずの同僚のなかに、亀裂がいくつも走るようになっていったのです。糸賀は園長としての自らのあり方を問い、大きな自責の思いにとらわれていました。そればかりか、家庭内でも家族へいらだち、人格を否定するような妻への言葉遣いを自制することができず、それが糸賀の心労を重いものにしていきました。
とうとう糸賀は、1951年の2月、学園の仕事の一切を打ち捨て、誰にも告げずに和歌山県の白浜温泉に向かいます(注1)。そして、湯崎という岬のつけ根の漁師の家に身を寄せ、幾日かを過ごしました。その家は、今も料理宿を営まれています。
そうして過ごしたある日の早朝、糸賀は日課にしていた岬の突端の天然の露天風呂に身を委ねます。そのとき、まるでからだを打たれたような「しびれ」を感じました。自分がつかる湯も湯船も、「何万年の昔から、こうしてここにあったのだ」と悟り、「何をクヨクヨ心配していたのだろうか、なんでもないではないか」と、言葉が体中から発するかのように叫んだのです。流れ込む湯も、それを抱きとめる湯船も、悠久の時にあってそこに存在しつづけている…。なにをクヨクヨと考えていたのか。自分は、もっと大きな、ゆるぎないもののなかに身をおき、それを信頼して生きようとしていたのではないか。
そして、宿に帰り、副園長の田村一二に独白というべき手紙を書き、大津市南郷の丘の近江学園に戻ってきたのでした(『この子らを世の光に』、著作集第Ⅰ巻105~108ページ)。この手紙は、おそらく後で述べる「魂の故郷―四年半の回想」に結実していきます。
愛によってむすびあうことから世界の平和へ
この1950年暮れから1951年の春にかけて、糸賀はいくつかの重要な文章を書いています。そのなかで、「信仰とその働きを通じて平和へ」は、自身の手によっては公にされず、『糸賀一雄著作集第Ⅰ巻』(254~257ページ)と『福祉の道行―生命の輝く子どもたち』(73~79ページ、注2)に収められました。1950年11月19日、糸賀が教会員であった大津市の堅田教会の「レーメンス・サンデー」の講壇のために、白浜に旅立つ前の学園の4周年記念式の前後に書かれたものです。糸賀の個人としての「信仰告白」というべき内容をもっています(注3)。レーメンス・サンデーは、「信徒である私たちの献身の日であり、私たちが自分の生活の中に、神とキリストを求め、私たちの公私の生活がキリストによって導かれることに決意する」日と糸賀は説明しています。ときは朝鮮戦争勃発の年であり、東西冷戦激化のなかにありました。
第一次世界大戦では、キリスト教国が互いに銃をかかげて戦勝を誓うという愚かさだった。そして第二次世界大戦を繰り返し、今その「反省のるつぼ」に叩き込まれている。そして東西冷戦がはじまり、はたして新たに生まれた国連はこの争いを防ぐことができるのかと糸賀は問いかけます。その答えは、「結局は、その国を、また世界を構成している私たちと同じ『人間』の問題に帰する」とし、「人間」の問題、換言すれば個人のあり方、人と人のかかわりを問うことは、「私たちをせんりつさせる真実」だとします。そして、「対立と抗争をやめさせるために、果して暴力が効を奏するでしょうか」と問いかけ、「宿命的な悲劇を断ち切るもの、それは十字架の愛でなくて何でありましょうか」と語ります。
「十字架の愛」とは、イエス・キリストが、当時のユダヤ教の厳しい律法(教え)を批判し、抑圧、搾取されて社会の周辺に追いやられていた人びとに手をさしのべ、それゆえに進んで十字架の刑に処せられたことによって、愛の何たるかを身をもって語ろうとしたことを表現しています。糸賀は、十字架の死を事実として認め、意味を知っているのはキリスト者であり、それゆえ、その「自覚者こそ、世界の平和に対する責任者であります」と礼拝堂の聴衆に語りかけました。
4月号(第Ⅱ部第1回)で述べたように、糸賀は2度の召集のいずれにおいても、病によって兵役を解かれました。その「生き残った」こと、そして旧制中学以来の友の多くを戦地で失ったことを、あまり語りはしませんでした。しかし、語らない姿にこそ、一人の国民としての戦争への反省、平和への希いを深く秘めていたのです。すべての生命を守りぬくこと、そして平和への希いは、彼の生涯に意味を与えつづけた、弱まることのない思いでした。
糸賀は、世界平和への「自覚者の責任」という言葉を、キリスト者としての信仰の表現としてだけ語ったのではありません。先の講壇原稿では、戦後の日本人の悲願は、世界の平和の実現に献身することであり、それは「スローガンをかかげることに終わるものではな」いとしています。そして、具体的な日々の実践と生活を通して、人と人が争いを乗り越え、愛情によってむすばれる「良き隣人」に成長していくための努力を、「自覚者の責任」として自他に求めていたのです。
しかし、この信仰告白とは裏腹に、糸賀が直面していたのは、学園という小さな社会における個人の自己中心性や自己顕示欲の醜さであり、その渦中にあって、家族に対しても剣のような言葉を発してしまう自らの弱さでした。個人の創り出す社会が困難に満ちていることを、糸賀は、自らの実践と生活のなかで自覚せざるを得なかったのです。
個人のこころざしの高さだけで草創期を歩んだ学園が、一つの「社会」として確かな力をもつための節目にさしかかっていたのです。糸賀は、その局面で、あらためて「人間というもの」を問わざるを得ませんでした。
発達は一人ひとりの人間とその社会への信頼と希望
そして糸賀は、年が変わってから、南紀白浜への旅に出たのです。
そこでの癒しを得て、南郷の丘に戻ってから、学園の内外の後援者に向けて送られる雑誌『南郷』に、「魂の故郷―四年半の回想」を書きました。1951(昭和26)年4月29日付になっています。以下は、その一部です。
「デモクラシーの原理には『発達』の概念がとり入れられている。時が経てば凡てのものが変化する。その変化が『発達』であるためには、めざす目標へ近づく変化でなければならない。個人も社会も、その行くべき高き価値のめ(・)あて(・・)を指して、時に消長はあっても、常に現実を踏台とし而(しか)も現実に反逆しながら、全体として向上して行くと見る『発達』の概念に私は敬意をおしまない。それは極めて健康なリンゴの様な頬をした若々しさにみちた思想である。此の場合、個人は十八世紀の頃に述べられたような抽象的な孤立した個人ではなく、社会にまもられながら社会の成員としてこれに奉仕しつつ、而(しか)も社会の発達を促がす推進力であることによって自己も亦(また)発達するような、そういう具体的な個人を指していることはいうまでもない。
(中略)学園が此の四年半に、果して成長し発展したかどうか、という問いに変えて、此の四年半に関係した凡ての職員たちが、内面的に果してどのような意識と自覚に立ち、どのような苦しみともがきを経験し、どのようにこれから生きようとしているかを問うことの方が、私は今日最も切実な問であるのではないかと考える。」(『この子らを世の光に』、著作集第Ⅰ巻109ページ)
糸賀の言葉を少しかみくだいてみます。
個人、社会は不変ではなく、内なる力によってつねに変化のなかにある。その変化が「発達」とよべるのは、その内にある大切な価値を実現していくという「めあて」をかかげ、その高みをめざして進むときである。その発達は、直線的で順調な変化ではなく、消長と一進一退のある過程であり、現実にある困難に抗し、そのことを踏み台として困難を乗り越えていくものでもある。そして理想を抱き、一方では足下の現実において自分と他者に問いかけ、葛藤し、困難を乗り越えて、高みをめざして歩いていく道行である。個人は、その構成員として社会のなかで、その自由と人権を守られながら社会の発達を推進していく存在であり、そうであることによって個人もまた、発達していくことができる。
だから、学園の発展を問うことは、とりもなおさず、そのなかで一人ひとりの職員が、どんな意識と自覚をもち、それゆえに現実のなかで苦悩し、いかに乗り越えていこうとしているかを問うことであり、そのことの大切さを見失ってはならないのではないか。
この糸賀の一人ひとりの職員の「発達」へのねがいは、すでに引用した「この20年余りのあいだに、自分たちの目もかわってきたのではあるまいかと一種のおどろきをもってふりかえる」という、亡くなる直前の『福祉の思想』の1節に結実していきます。
文章はさらにつづきます。
「われわれは常に現実の汚濁の中に身を置いている。この汚濁は自己自身であり、此の世の中であり、そして学園も汚濁そのものである。(中略)不完全や汚濁をそのままだきしめて『神は愛なり』と叫ぶ声に私は耳を傾けなければならない。成長しつつ発展しつつ而(しか)も依然として不完全な汚濁そのものである自己を、そのまま許して抱擁する絶対的な実在に真実の謙虚があるだけである。」(111ページ)
われわれは理想をかかげて生きていても、現実のなかでは、それとは裏腹の弱さ、不完全さ、自己中心性などさまざまな矛盾をもって生活しています。自分も、仲間も、そして社会も、その「汚濁」を免れません。しかしそうではあっても、人は意志によって、よりよく生きることをやめようとはしないのです。そして糸賀は、その発達とそれへの人間の意志に「敬意をおしまない」と述べました。
キリスト者の糸賀にとって、その汚濁を抱えつつ、なお高みをめざして歩もうとするのが神の似姿としての人間の本質であり、神は弱くて小さな存在である人間を見捨てず、その汚濁を受けとめて抱擁する絶対的な実在としての「大きなもの」でした。それを信頼して、再び歩みを起こせばよいと自らに言い聞かせたのが、「白浜での誓い」だったのです。それは近江学園の、自分も含む職員の一人ひとりへの「その行くべき高き価値のめ(・)あて(・・)」を抱きあうことへの要求であり、彼らへの信頼と愛情をゆるぎないものにする誓いでもありました。
この糸賀の職員との関係は、清濁をあわせもった職員の発達を見守りつつ、理念を確かめあい、方向づけ、ときには叱責し、支えあげていくという「抱擁」という言葉にふさわしいものでした。何より糸賀は、職員たちの試行錯誤、悩みに心を寄せ、「園長への手紙」という職員からの「声」を歓迎し、出されたものには必ず鉛筆書きでのコメントを書き添えて返信していました。たとえば、「君のその試みは尊いと思う。実(み)を結ぶものと私は確信している」などと。そこに、糸賀の学園に集った職員たちへの限りない愛情を感じるのです。
このように職員たちを受けとめることは、その職員たちの人格を介して、彼らが向きあう子どもたちの発達の事実を受けとめることでもありました。『この子らを世の光に』『福祉の思想』などで書かれている子どもたちの姿を、それを糸賀に語ったであろう職員のことを想いながら読んでみたいと思います。
これらの学園に集った人びとが歩んだ道について、糸賀は『この子らを世の光に』の第1章で感慨深く語っています。
「およそひとつの仕事が歴史のなかでその位置を占めるためには、なんとたくさんの要素がはたらいているものであろうか。そこには、支えや協力だけではない。若い芽をつみとろうとする暴力、悪意、ねたみなど、人間的な、あまりにも人間的な臭気さえ立ちこめるものである。そういう背景や環境のなかで、ひとりの人間が、そして多くの同志たちが、戦い、結合を深め、支えあって仕事がすすめられる。しかし、同志といわれ、内わのものといっても、生身の人間である。考え方や生き方の相異があり、発展がある。喜びもあれば絶望もある。われわれは何時も、はじめにもどり、めざすものは何であったか、自らに問い、人にも問い、確めあって、今日まで辿ってきたのであった。」(22ページ)
「発達保障」の理念への発展
連載第1回で紹介した「辻教官」と「鳥居保母」が「劇」をめぐって思いの丈を語りあったのは、学園が10周年を迎えた1956(昭和31)年のことでした。その年に、京都大学から田中昌人(後に京都大学教育学部、全障研初代全国委員長)が近江学園研究室に入ります。そして学園にさらに多くの人材が集い、子どもの発達の道すじの研究と実践(昨年度の連載第Ⅰ部でお話ししてきたことは、この近江学園での発達研究に淵源があります)のなかから、「発達保障」の理念を掲げたのは1961年のことでした。
障害の有無によらず、そして障害の軽重や違いによらず、その「すべての、文字どおりすべての人の生命が、それ自体のために、その発達を保障されるべきだという根本理念を現実のものとする出発点に立ったことなのである」(『この子らを世の光に』、第Ⅰ巻169ページ)と糸賀は記しています。
つまり、今日私たちは、「発達保障」という言葉を、「子どもの」という前提で理解し語りますが、糸賀と近江学園にあっては、そうではありませんでした。岡崎英彦が言う「それまで悩んでおられた人間的矛盾、社会の矛盾」といかに向きあうかという糸賀の問いが発達の「ゆりかご」となり、そのなかで、「その行くべき高き価値のめあてを指して、時に消長はあっても、常に現実を踏台とし而(しか)も現実に反逆しながら、全体として向上して行くと見る『発達』の概念」が目を覚まし、子どもへの発達研究、実践と運動を「糧」として、「発達の法則性」に裏打ちされた「発達保障」の理念・理論として育っていったのです。
これは、「おとなの発達が先か、子どもの発達が先か」あるいは「おとなが発達しないと子どもも発達しない」という問題ではありません。どんなに障害の重い子どもたちも感ずる世界、意欲する世界をもっている、すべての人間は生まれたときから社会的存在であり、人びとのなかで力いっぱい生命と発達を開花させようとしている。そのことが真にみえるようになるまでには、私たちは自分を問い、自分自身との対立にまで向かわなければならないときがあります。糸賀が言うように、およそ教育とよぶものが、この問いをもちえているかどうかが問題なのです。そして、その自らへの問いの過程があるからこそ、子どもの発達へのねがいも苦労の瞬間も、みえるようになってくるのです。そこに成立するのが、「発達的共感」でありましょう。
「発達的共感」をもちえないならば、その発達認識は、子どもへの単なる「レッテル貼り」の繰り返しになってしまうことでしょう。そして指導・支援を通じて、その発達の知識に子どもを従属させようとします。あるいは、表面的な発達理解にとどまり、指導者としての自分に手ごたえを感じられないまま、他の認識や指導法に「移り気」していくことでしょう。
おわりに
このように、発達保障の理念は、けっして研究室での研究や教室での実践という限られた世界のなかで生まれてきたのではありませんでした。そして糸賀や当時の近江学園の人びとだけではなく、日本のそこここに、障害のある人びとの生きること、発達することの意味と価値を問い、すべての人間の基本的人権、発達への権利を求めつづけてきた「たたかい」の歴史がありました。そのなかでまさに、生身の人間が自分の生きる意味を問い、生きる社会を見つめ、仲間、同僚と力をあわせ、人生をかけて創り上げてきたのが、「発達保障」だったと言えるでしょう。私たちは、ささやかな力ではありますが、その歴史の継承者でありたいとねがいます。
糸賀が逝って55年、今なお、人間と社会の根本的な矛盾は大きく、この社会のなかで「弱くさせられている」人びとの苦しみは小さくなっていません。その困難の原因は、この社会における政治と経済のあり方、つまり人間を大切にしない問題だと私たちは考えます。それを変えていくには、なお長い時間がかかるかもしれません。しかし、人間とその発達、そして仲間を信頼し、短気にならず、粘り強さを信条とした歩みを進めていきたいと思います。
「問題は子どもたちのあらゆる発達の段階をどのようにしたら豊かに充実させることができるかということである。教育技術が問われるのはこの一点においてである。しかし教育技術が生かされる基盤となるもの、むしろ教育技術をうみ出すもの、それは、子どもたちとの共感の世界である。それは子どもの本心が伝わってくる世界である。その世界に住んで私たち自身が育てられていくのである。子どもが育ちおとなも育つ世界である。あらゆる発達の段階において、子どもたちは、このような関係のなかに置かれ、あわてたりひっぱたかれたりしないで、豊かな情操をもった人格に育つ。それはちょうど木の実が熟して木からおちるように、次の発達の段階にはいっていくのである。」(169ページ)
(注1)糸賀は、自ら「私は昔から温泉が好きであった」(『この子らを世の光に』)と記しています。仕事の移動中に青森県八甲田の酸ヶ湯に立ち寄った折り、「いい湯だ。ここで泊まりたいものだ」と残念げに語ったことが伝えられています。それが許される現実ではありませんでした。酒も好きであり、信ぴょう性は確かではありませんが、酒にまつわる「武勇伝」も伝えられています。糸賀の人柄を理解する一助として記します。
(注2)『著作集』に収められたことは当然としつつも、糸賀の思想を多くの方がたに伝えるために、「新書判」として編集された『福祉の道行―生命の輝く子どもたち』(中川書店)に選ばれたことに感慨を覚えます。この『福祉の道行』は、田中昌人、三浦了(故人、元社会福祉法人大木会顧問)の両氏が中心になって、糸賀自身による出版企画の実現として用意されたものでした。しかし、なかなか日の目を見ることはなく、田中の亡くなるまで原稿は保存されていたのです。
(注3)糸賀の遺した言葉と思想は、その人格の骨格を形成していた信仰を措いて理解することはできません。青春の日の、文字通りの苦しい生活のなかで求めた信仰にも、そして近江学園での事業を支えた信仰にも大きな位置を占めたのは、使徒パウロの姿と言葉であったと思われます。京都帝大・宗教学の卒業論文は、「パウロに於ける終末の問題」でした。
パウロは熱心なユダヤ教徒であり、イエス・キリストの弟子を迫害する側にありました。しかし、自らの内で熟しつつあった律法への盲従的な姿勢への反省によって、「目から鱗が落ちる」ようにキリストの教えに「回心」しました。幾多の迫害にも抗して古代キリスト教会の基礎を築いた「たたかいの信徒」であり、「愛と共感」を述べ伝える使徒でした。
現在の苦しみのなかにこそ未来のための力があり、その希望があるからこそ、現在の困難を乗り越えていくことができる、困難や弱さのなかに人間の本質的な力が実現していくことを、身をもって語った人物です。
「主は言われた。私の恵はあなたにたいして十分です。私の力は、弱いところのなかで確かになるからです。だから私(パウロ)は、キリストの力が私に住みついてくださるように、喜んで自分の弱さを誇ろう。だから私は、弱いことを、そして艱難と迫害と苦悩を喜ぼう。なぜなら、私は弱いときにこそ強いのだから。」(パウロからコリントの教会の人びとへの第二の手紙)
そして糸賀は、神との関係で恵みや救いを求めるのではなく、現実の生活において、人と人との関わりのなかで人格的存在が発達していくこと、「弱くさせられている者」の人格の輝きによって、私たちは勇気づけられ人格を解放できることを、未来への大いなる希望として感じ取っていったのでした。
学習参考文献
糸賀一雄(1965)『この子らを世の光に-自伝・近江学園二十年の願い』柏樹社
糸賀一雄(1968)『福祉の思想』NHKブックス
糸賀一雄(1982-83)『糸賀一雄著作集第Ⅰ~Ⅲ巻』日本放送出版協会
糸賀一雄(2009)『糸賀一雄の最後の講義-愛と共感の教育 改訂版』中川書店
糸賀一雄(2013)『福祉の道行-生命の輝く子どもたち』中川書店
髙谷 清(2005)『異質の光-糸賀一雄の魂と思想』大月書店
(『福祉の道行-生命の輝く子どもたち』『糸賀一雄の最後の講義-愛と共感の教育 改訂版』は、大手通販サイトで高額に取引されていますが、出版社の中川書店(福岡)のWEBページから定価で購入することが可能です。)
次回の「もう一つの『発達のなかの煌めき』」の公開は、7月上旬を予定しています。
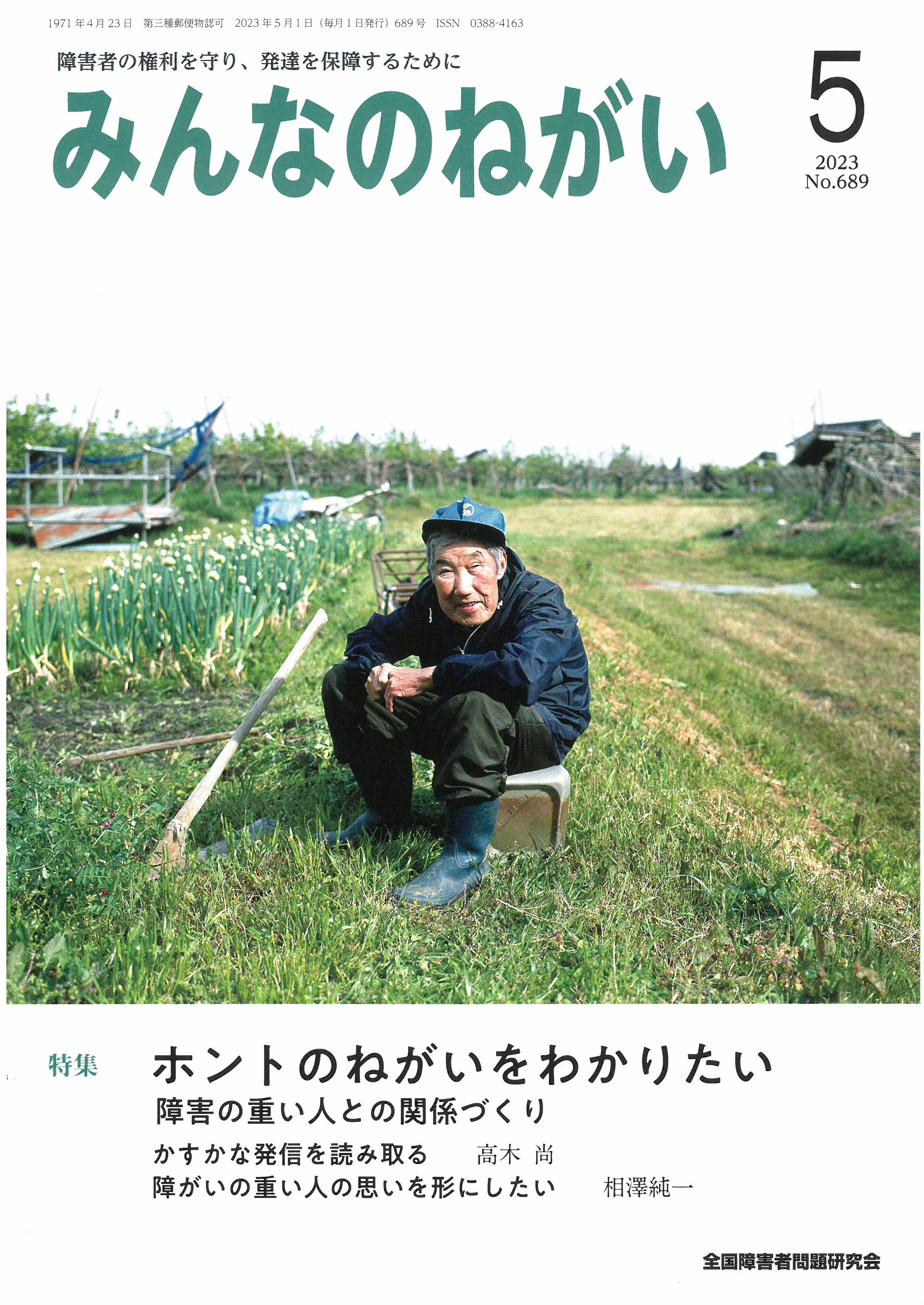
<表紙のことば>
いつかの春。茨城県霞ヶ浦ほとりの畑にて、座って休んでいるおじいちゃんに出会った。自宅の目の前にある畑には、葱坊主が咲き誇り、緑豊かで広々としたその場所はまるで彼だけの楽園のようだった。
「人は顔よりも顔つきだ」そう、日増しに思う。いきなり現れ声を掛けたよそ者の僕に、こんなに穏やかな笑顔をくれる。毎日の生活をどんな風に送り、人生をどんな風に歩んできたのか、全てがその表情に表れているのかもしれない。
僕がおじいちゃんと同じくらいの歳になったとき、こんな優しい顔つきになれるように。そんな日々を送っていこう。
土佐和史 とさ かずふみ/1977年大阪府生まれ。全国各地に出向き、旅ゆく道で出会ったひとや風景を撮り続け作品発表を行っている。2018年に写真集出版レーベルBUFFALO
<目次>
1 人として 原ゆたか
2 【インタビュー】今、あなたと生きて 丸山正樹
4 この子と歩む 寺坂由子
7 私のタカラモノ 今野亮佑
8 仲間がいっぱい ひろしまの療育 大政里美
11 世界の風 児玉正文
特集 ホントのねがいをわかりたい ~障害の重い人との関係づくり
12 障がいの重い人の思いを形にしたい 相澤純一
14 楽しいことをいっぱい! 伊藤久美
17 仲間の思いをつかみ、つないでいく 森田由希
20 かすかな発信を読み取る 高木 尚
24 発達のなかの煌(きら)めき 白石正久・白石恵理子
28 社会をみる 杉田真衣
30 福祉現場の今を読み解く 深谷弘和
32 基礎から学ぶ 障害と医療 狗巻修司
34 私ときょうだい 宮﨑木綿子
36 実践の魅力 加藤法子
39 支部だより 松元 巌
40 発達保障インタビュー バトンゾ→ン 近藤直子
42 みんなのひろば
44 ニュースナビ ゆたか福祉会の消費税更正請求訴訟 宇川賢彦
46 誠司くんの見たこと、聞いたこと、歩いてきた道 松本誠司
47 BOOK/編集後記
裏表紙 心のことば 内田貴大
デザイン・イラスト うじたなおき、永野徹子、橋野桃子、細川茉莉
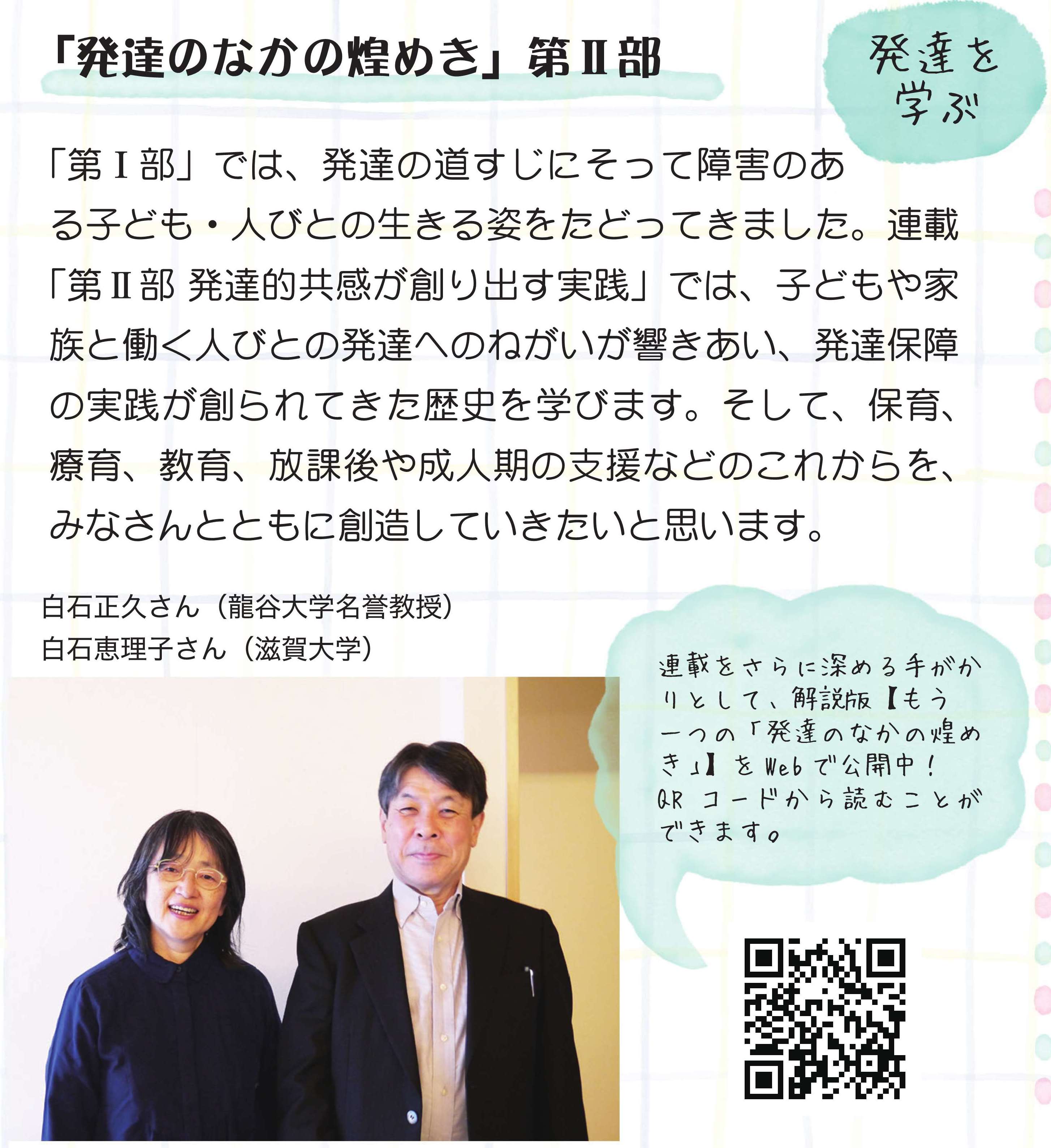
「障害者問題研究」50巻4号
特集=子どもの発達保障と遊び
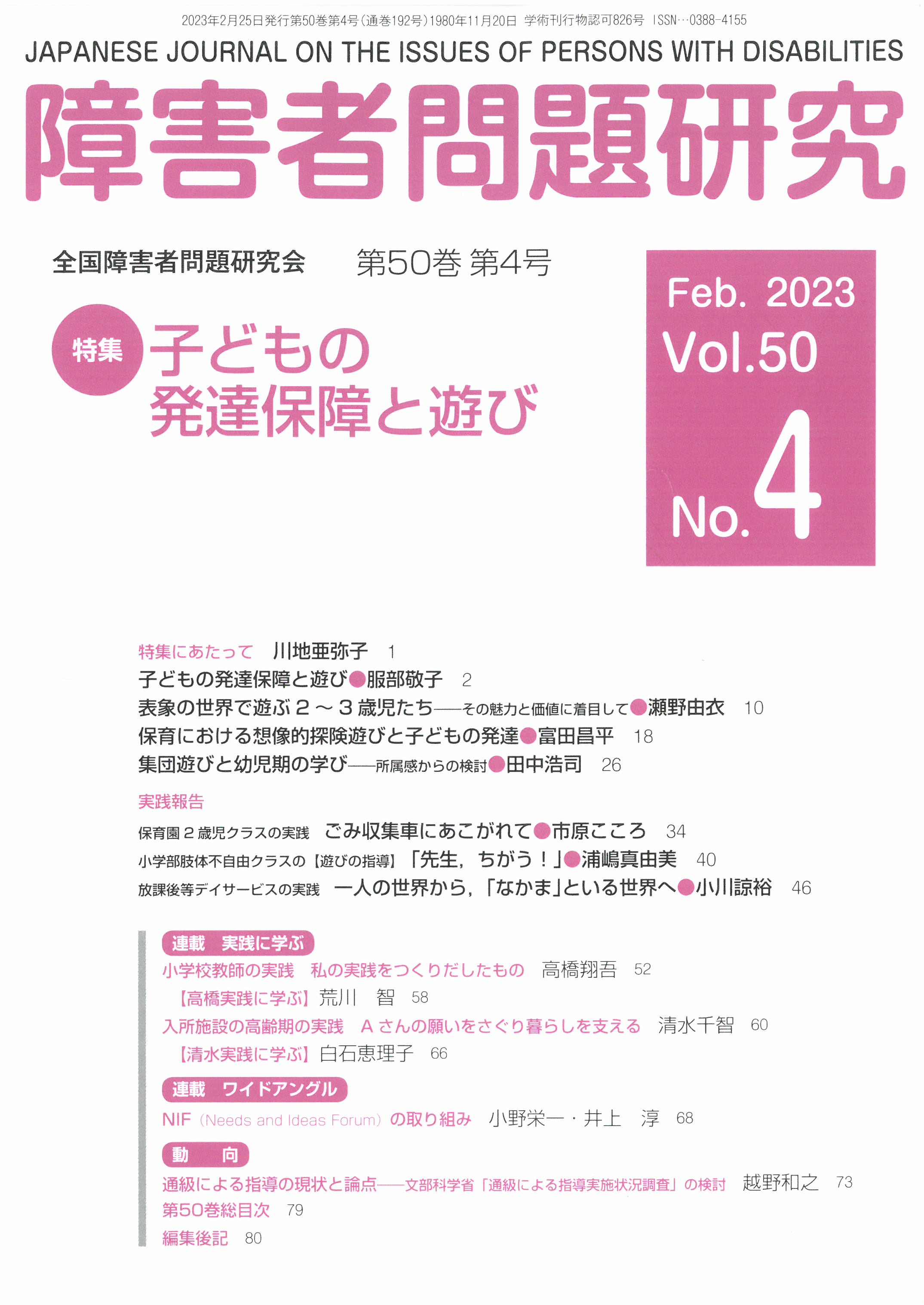
詳細案内 「ちょっと見」やオンラインでのご注文は以下のホームページへ
▶「障害者問題研究」50巻4号 特集=子どもの発達保障と遊び
▶「読む会」情報 2023年4月26日(水)19時~21時、ZOOMで開催します
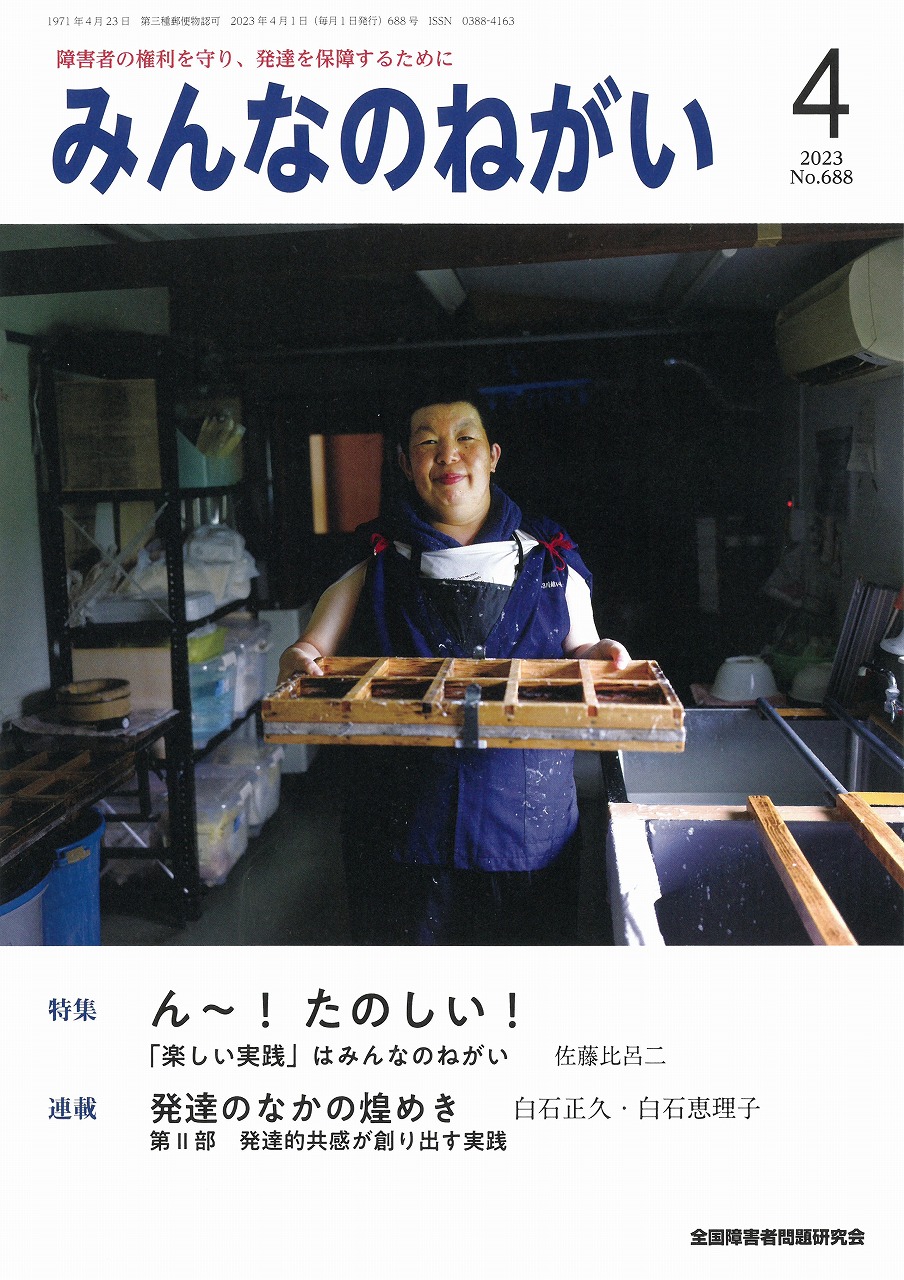
<表紙のことば>
第3川越いもの子作業所では、牛乳パックを原料とした紙漉きが行われている。慣れた手付きとコンビネーションで作業を黙々とこなす彼らの真剣な眼差しは、普段の人懐っこく明るい雰囲気とは違ったまさしく職人そのもの。その仕事のクオリティの高さと、生き生きとした現場の雰囲気に正直驚かされた。
働くこと、創作することが当たり前と思ってないだろうか。自分に問いかけたくなる。
簀桁(すけた)を持って微笑むその顔には、自分の仕事への誇りと働ける喜びが満ち溢れている。
土佐和史 とさ かずふみ/1977年大阪府生まれ。写真集『北関東』『路地裏に咲いた花』(いずれもBUFFALO PRESS)ほか
<目次>
1 人として 土佐和史
2 【インタビュー】今、あなたと生きて 丸山正樹
4 この子と歩む 仲神早予子
7 私のタカラモノ 青木栄一
8 仲間がいっぱい ひろしまの療育 石木恵子
11 世界の風 児玉正文
特集 ん~! たのしい!
13 3年ぶりのそり遊び 飯室智恵子
14 「風で走る犬」 高橋翔吾
15 かけがえのない青春時代 河原京子
16 生活を楽しむ露天風呂 原田文孝
17 「楽しい」から「やりたい」! 木下博美
20 「楽しい実践」はみんなのねがい 佐藤比呂二
24 発達のなかの煌(きら)めき
白石正久・白石恵理子
28 社会をみる 杉田真衣
30 福祉現場の今を読み解く 深谷弘和
32 基礎から学ぶ 障害と医療 狗巻修司
34 私ときょうだい 塚田直也
36 実践の魅力 小島貴子
39 支部だより 金澤園子
40 発達保障インタビュー
バトンゾ→ン 近藤直子
42 みんなのひろば
44 ニュースナビ 「放課後デイに補助金」小平市の運動 村岡真治
46 誠司くんの見たこと、聞いたこと、歩いてきた道 松本誠司
47 BOOK/編集後記
裏表紙 心のことば 内田貴大
デザイン・イラスト うじたなおき、橋野桃子、永野徹子
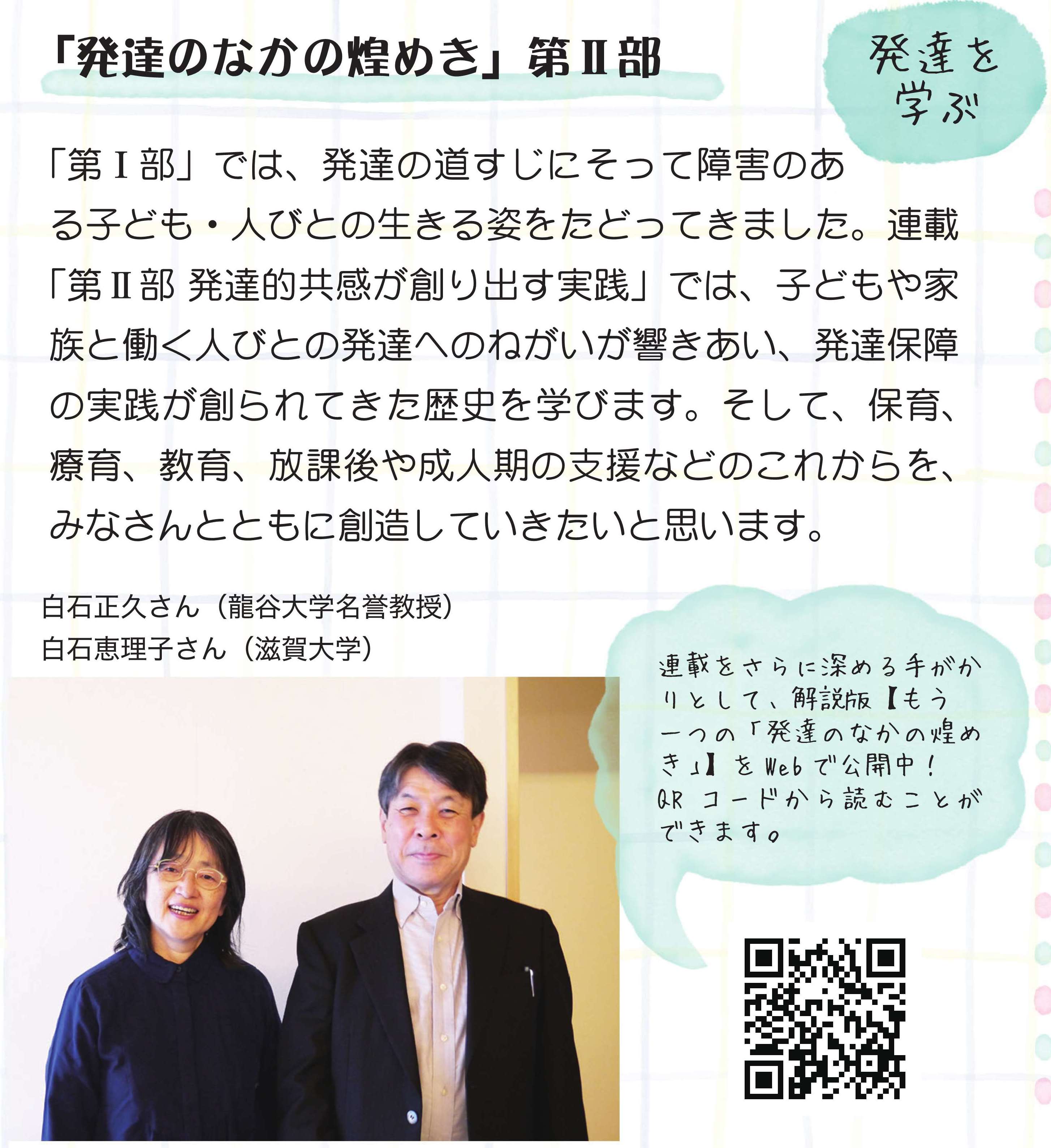
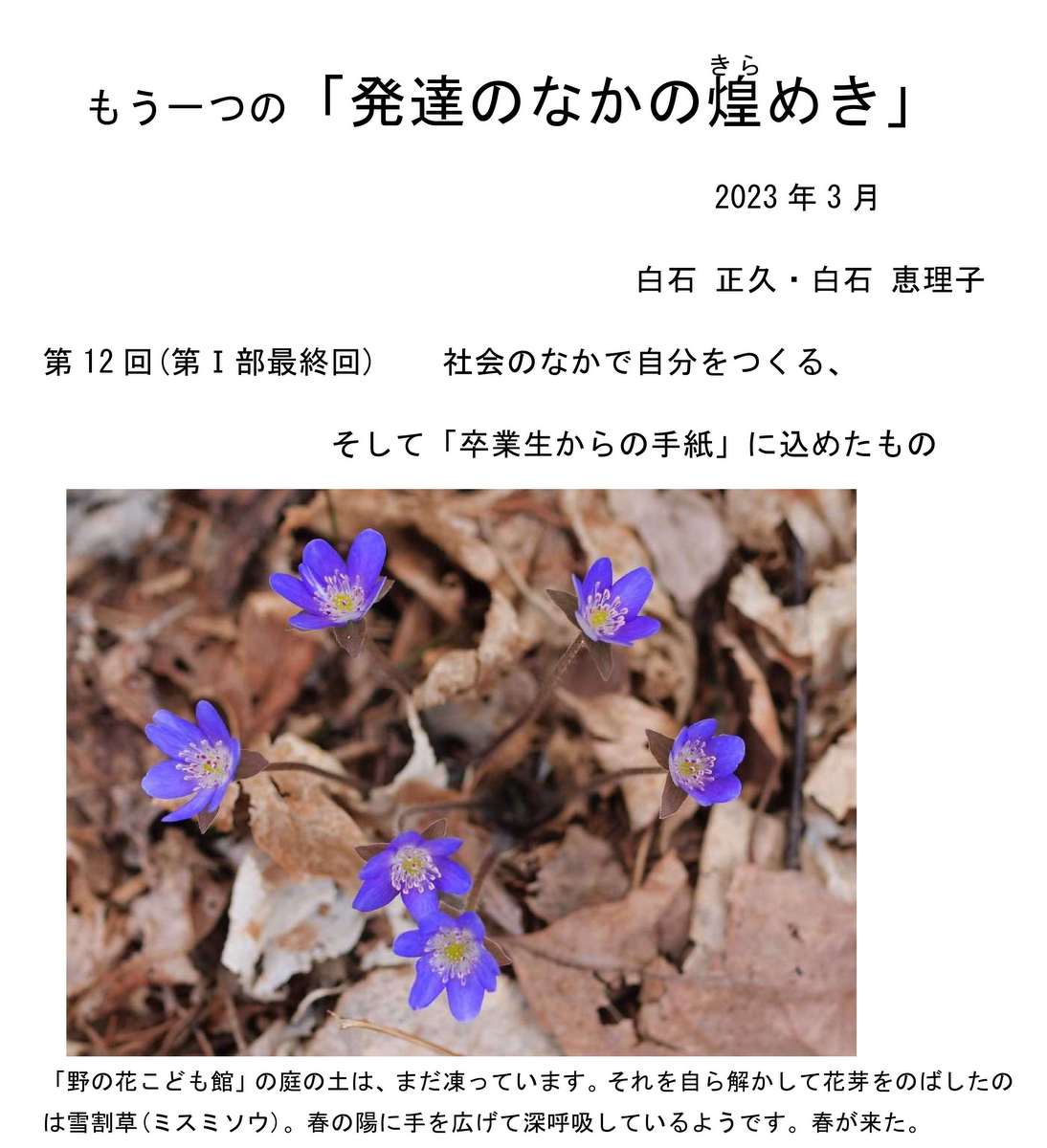
はじめに
第Ⅰ部「障害のある子ども・なかまの発達」の最終回「『社会』のなかで自分をつくる」を解説します。
前回の「もう一つの『発達のなかの煌めき』」(以下では「もう一つ」)では、「9歳の節」の特徴として、まず「概念の階層関係の理解」を説明しました。今回は、以下の3つのテーマについて解説します。
・集団のなかでの自分づくり
・段取り・計画をする力
・「書き言葉」の発達
『新版 教育と保育のための発達診断 上』(以下では『上巻』)の「Ⅲ 第4章 7歳の発達の質的転換期と発達保障」、『新版 教育と保育のための発達診断 下』(以下では『下巻』)の「第7章 7~9歳の発達と発達診断」を参照しつつ、学んでいきたいと思います。
「9歳の発達の節」とはなにか
・集団のなかでの自分づくり
連載第12回に登場したユキさんは、「自分のことを何でも書いてください」課題への高等部1年生のときの応答で、「やさしいたくさんのともだちをつくりたい」と書きました。学校の寄宿舎に入舎し、家庭から離れた新しい生活の場で、仲間関係を広げようとしていたときです。そして3年生になって、「みんなとけんかせずなかよくあそんでいます」と書くことができました。
発達が、「9歳の節」に向かっていくときには、「ギャングエイジ」と呼ばれるように、「気のあう」友だちを欲し、「徒党」を組んで「秘密の世界」(「秘密基地」など)を創ろうとします。ユキさんも、夜遅くまでおとなには言えない話題で盛りあがっておしゃべりをつづけたので、寄宿舎指導員の先生に大目玉をいただくことになりました。おとなの手を借りず、自分たちで生活を創りたいとねがう自治的集団の形成です。
こういった集団があるから、自分自身への理解が多面的で客観的なものになっていくのでしょう。「自分のことを何でも書いてください」への応答では、集団のなかで形成されてきた多面的な自己意識が表現されるようになります。ユキさんも、「わたしは、わるがきです」と書いた後で、そうではあるけれど本当は「やさしいたくさんのともだちをつくりたい」ねがいをもっていると、忘れずに書きました。
遠い昔の秋のことですが、私たちは放課後になると「柿ドロボウ」になりました。学校帰りにおいしそうな柿の木を見つけると、チームワークよろしく段取りを決めて失敬したものです。「コラ?!」と叱られますが、だからといって学校に苦情の電話がかかってくることはなかったでしょう。それどころか、「十五夜」の縁側のお供え物は、子どもたちが徒党を組んで「がめる」(盗るの方言)ことが許されていたのです。「ギャングエイジ」をあたたかく見守る地域社会がありました。「ギャングエイジ」は子どもの潜在的な発達可能性が発揮されていく姿ですが、そのためには、その力が展開していく条件が必要です。自分たちで計画できる時間、空間、多様な遊び、友だち関係。そういった条件が、放課後のなかに満載されているでしょうか。
先生の意図による「学校」ではなく、親の意図による「家庭」でもなく、子どもが主人公になる時間、空間、集団は、まさに「第三の世界」であると田中昌人さんが名づけました。それは単に放課後生活のことを言うのではなく、また「9歳の節」に限らない、子どもが主人公の自治的な世界のことです。学習塾や習いごとなどが放課後時間を侵食して久しいですが、せっかく制度化された放課後等デイサービスの活動が、同じように習いごとになってしまっているならば残念なことです。解放的でのんびりできる時間で心を整え、わくわくする遊び、地域探検、人びとの生活や労働との出会い、生き物との交流など、子どもが仲間とともに自然や文化に触れ、それを主体的に継承していく「第三の世界」であってほしいものです(『みんなのねがい』3月号「放課後活動で大切にしたいこと」で学び、考えましょう)。
ただ、この「9歳の節」の頃の自治的集団は、めあて(目標)、約束や秘密、良い‐悪いなどの価値判断を共有しようとするので、連載第11回で述べたように、それに気持ちがついていかなかったり、なにかのきっかけで排除されてしまう子どもを生みだします。その逸脱や排除を放置するのではなく、またいけないことと決めつけるのではなく、そのことをきっかけとして、一人ひとりのねがいや気持ちの大切さにみんなが気づき、互いに受けとめられる集団でありたいと思います。それは、一人残らず自分の居場所を実感できる集団でしょう。
ユキさんも、喧嘩ばかりしてしまう「わるがき」の自分を「悪」と決めつけるのではなく、それも包み込んだ存在として、他者からも自分からも受けとめられていきました。そのように発達の質的転換期では、一面的ではない、多面的な自己理解や他者からの受容が大切な心の支えとなります。振り返ってみれば「1歳半の節」においても、連載第4回で述べたように、自我の誕生にともなう「イヤ!」や「だだこね」(「拒否」「パニック」などと言われてしまっているかもしれません)の姿はあっても、その意味を理解して受けとめてくれる関係があるならば、子どもも自分のことを調整し立ち直らせていこうとするのでした。
この自治的な集団形成の基盤の一つになるのが、次に述べる目標や条件(全体の枠)を意識して計画する力です。
・段取り・計画をする力
集団形成の基盤である目標や条件を意識して計画する力とは、どのようなもので、どのように発達するのでしょうか。
「もう一つ」第11回で紹介した脇中起余子さんの研究(2009)では、小学校2、3年生と小学校4、5年生の間に、絵カードの分類方法の質的差異が認められ、2、3年生では、「金魚→魚」「鳩→鳥」というように、下位概念から上位概念へ一対一対応で分類していくのに対して、4、5年生ではあらかじめカード全体を見渡して、「動物になるのはこれとこれ」というように、上位概念から出発する分類を行なえるようになるとされました。
このように「9歳の節」では、「あらかじめ全体を見渡して」から方略を練るという力が獲得されていきます。この方略を練る過程をみる課題の一つに「財布探し」があります(「新版K式発達検査」(京都国際社会福祉センター刊。『下巻』178~179ページで解説されています)。「これは広い運動場で、草が一面に生えています。もしこのなかであなたが財布を落としたとして、それを必ず見つけようと思ったら、どういうふうに歩いたらよいでしょう。この入り口から入って、あなたが探すときに通るところを鉛筆で描いてごらんなさい」という問いです。
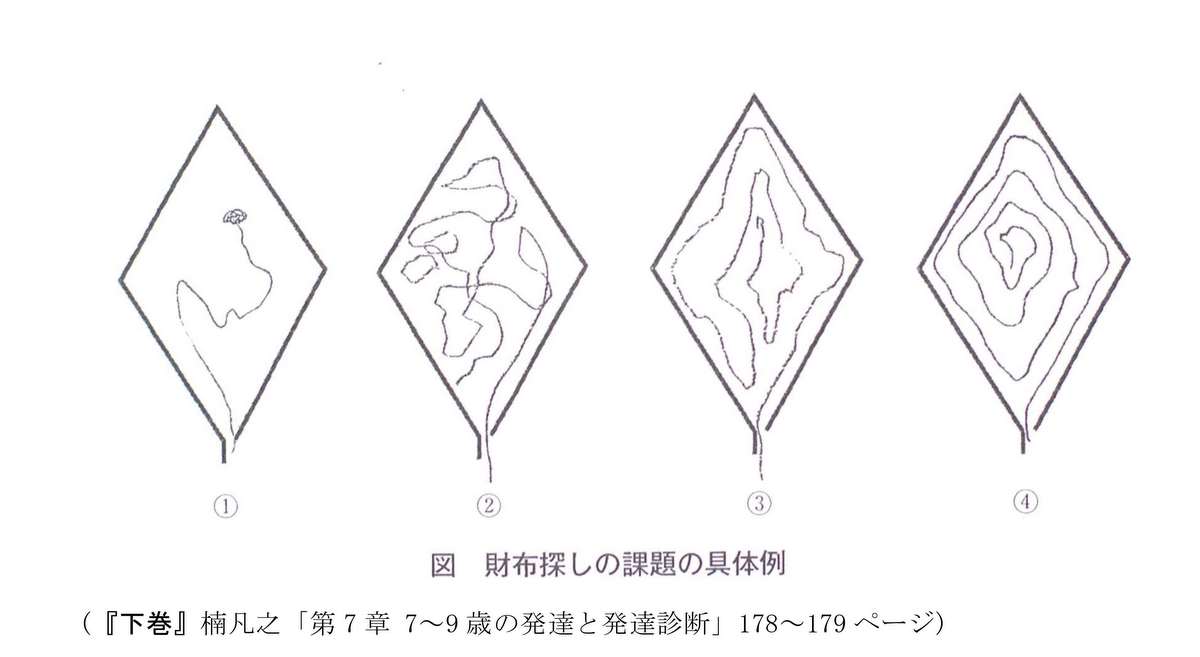
(『下巻』楠凡之「第7章 7~9歳の発達と発達診断」178~179ページ)
7歳頃の低学年では、図の①のように「ここにあった」で見つけたつもりになっています。つまり財布がどこにあるかわからない広くて草の生えた運動場であることをあらかじめ考えて、歩き方を描くことはできません。8歳頃になれば、②のように全部を歩かなくては見つけることはできないことを想定できるのですが、無駄のないように計画的に歩くということまで考えが及びません。それが、「9歳の節」になると③のように「広い運動場」で「草が一面に生えている」ことを想定して、「同じところを歩くことのないよう」にという方略を考えることができるようになります。11歳頃には、④のように「全部を」「合理的に」という複数の視点を結びつけて歩く方略を、立てることができるようになります。
こういった計画の力が、生活や学習のどんなところで発揮され、確かになって行くのか想像してみましょう。とくに、子どもの主体的で自治的な活動が存分に展開していくことの大切さを、私たちは強調したいと思います。生活日課、外出の目的地や交通手段、自分たちの大切な行事の段取りを、子どもたち自身が考えを出しあい、互いの思いの違いも話しあって修正しながら、自分たちで創り上げるようになっていくのです。
ユキさんが、学校の寄宿舎に入舎した当初は、自分ではできないことばかりでした。洗ったタオルを干すときには、ていねいに物干しにかけるだけではなく、洗濯バサミで留めなければ風で飛んでしまうこともたびたびなのです。取り込んだ洗濯物をタンスに片づけなければ、「じゃまや」と仲間に言われてしまいます。ひきだしにじょうずに中仕切をして整理している先輩を見て、見よう見まねで段ボールを切って同じように工夫してみました。おそらく本人も、できないことばかりの自分のことを情けなく思っていたことでしょう。しかし、日々の生活から逃げることはできません。先に入舎していた仲間に憧れ、やがては自分が導く側に立ち、気がつけば自分たちの力で、大切なことはできるようになっていったのです。日々の生活はルーティンですが、だからこそ日々の繰り返しのなかで、導きあい、助けあって、すじ道立てて段取りを考えたり、より良く工夫する力が育っていくのでした。
・「書き言葉」の発達
次に書き言葉について考えてみましょう。
「1歳半の節」からはじまる生後第3の発達の階層は、話し言葉を獲得し、豊かにふとらせていく時期であり、話し言葉が他者と交流する重要な交通の手段でした。「9歳の節」からは、本格的に書き言葉の世界に入っていくことになります。
これまでみてきたように、5歳半ばに誕生する新しい発達の力は、その書き言葉の世界を準備するうえでも重要な意味をもっています。それは単に、文字に興味をもって、文字の読み書きをはじめるというだけではありません。ものごとの空間的・時間的つながりを理解し、新たに創り出していこうとするとき、すじ道を一生懸命にさがし出そうとするとき、「えーっとね、あのね…」がいっぱい出てきます。それを聴き取ろうと心を傾けてくれる人がいるからこそ、子どもたちは話し言葉のなかに文脈を育んでいくことができます。さらに言えば、上述したような「第三の世界」でのわくわくする遊びや探検、人びとの生活や労働との出会いは、子どものなかに伝えたい文脈の土台を耕すことにもなるのでしょう。こうして話し言葉で蓄えられた文脈形成力が、書き言葉の重要な発達的土台となるのです。
そして「9歳の節」を迎えると、財布探し課題でみられるような全体をとらえる力、計画性、方略をつくりだす力は、書き言葉にも大きな変化をもたらします。あったことを順に羅列していくような書き方から、あらかじめ立てたテーマに即して文章を考えたり、文章を推敲しようとしたり…といった姿につながっていくと言えます。
こうした書き言葉の力は、子どもたちにとって、自分をみつめ、自分と向きあうこと、さらには他者や社会をみつめるまなざしにもつながります。書き言葉で綴ることは、この時期の子どもたちにとって、本当に大きなエネルギーを使う大変なことです。自分のなかのひきだしからぴったりする言葉を選んだり、力をこめて文字を書こうとしたり、ときに消しゴムで消して書き直そうとしたり…その一つひとつに時間とエネルギーがかかります。思いや感情はあふれるようにあっても、書いた言葉は本当に短い。だからこそ、そこに書かれている言葉の裏側にいろんな思いがはりついていることを、私たちは見失わないようにしたいものです。
書き言葉は、話し言葉とは異なり、目の前に形として残ります。ユキさんが「わたしは、がっこうのきしゅくしゃでたのしくがんばっています」と書いた言葉は彼女の目の前にあり、「けんかし(せ)ずなかよくあそんでいます」とすっとつながることもあれば、“いやいや、いつもたのしいだけじゃないな”と思い、「先生に、よくおこられたり、ないたりします」になったのかもしれません。でも、そんな自分にも言いたいことがあるという思いが「しつこいときもある」になったのかもしれません。こうして書いていくことで、「なんで私は泣いたんだっけ…おこられるわたしが悪いのかな…いやいや、先生もしつこいわ…でも、おこられる私もちょっとは悪いのかな…そうか、本当は私を信じてほしいんだ」と心は動いていくのでしょう。それは、より深く自分や相手を見つめ直すきっかけにもなるのだと思います。
滋賀県の養護学校教員であった古日山守栄さんが、高等部を卒業し就労した教え子のことを話してくれました。就労先で上司から怒られて、「もう、やめる!」と古日山先生に電話をしてきました。そのときに、「あなたは学校時代に、書くことで自分の本当の気持ちが見えてきたよねえ。また、書いてみたら…」とアドバイスしたそうです。数日後、また電話をしてきた彼女は、「はじめは怒られて、もうやめるって思ったけど、私のためを思って怒ったのかもしれん…もうちょっと働いてみるわ」と言ったそうです。
書くことによって、自分や他者、そして社会をみつめるまなざしに「なんで?なんで?」が加わっていくこと、そして心のひだがたくさん折り込まれていくことを願います(書くことについては、『みんなのねがい』2022年10月号「思いを綴る」も参考にしてください)。
「卒業生からの手紙」に込めたもの
第Ⅰ部の最終回である連載第12回で以下のように書きました。
四月号「卒業生からの手紙」で始まった連載ですが、この手紙にはどんな意味があるのかとたびたび尋ねられました。
まず、「発達をはぐくむ目と心」にとって大切と思うことを、この手紙に忍ばせてみました。連載が終わったときに再び読んでいただけるならば、一年前とはちがう何かに気づいていただけるように。
しかしそれだけではなく、実は私たちも、この手紙によってみなさんにお尋ねしたいことがありました。悩みながら十年という歳月を歩んできた若い教師、自分の存在の意味を求めて「四歳の節」で葛藤するリョウちゃん、三人の子どもを歯を食いしばるように一人で育てている母親、そして学校という職場と同僚の姿に、みなさんは何を感じ、どこに心をとめられたでしょうか。
つまり、この手紙には二つのねがいを込めていました。前半については、私たちによる「種明かし」をせず、読者のみなさんの発見に委ねたいと思います。あらためて第Ⅰ部の12回の連載をお読みいただき、この手紙と連載内容を突きあわせてみてください。
後半についても、みなさん一人ひとりの感想が大切なのであり、私たちの意図はそれを越えるものではありません。しかし1年の時間をかけていろいろな場所でお尋ねしてきたこと、つまりみなさんがどこに心を留められたかを報告しながら、私たちのこの手紙に込めたねがいを述べたいと思います。
・本当の心の叫びは何なんや
大学の学生たちにも、この手紙を読んでもらいました。なんと彼らの多くは、この「心の叫び」に目をとめました。自分が、「子どもや親の心の奥底にある本当の叫び」を理解できる教師や指導員になれるかと、不安になったのだと思います。
私のグチを我を忘れたような顔で最後まで聴いてくれる先輩がいました。聴いてくれるだけではなくて、「子どもや親の心の奥底にある本当の叫びは何なんや」と優しいまなざしですがはっきりした言葉で問いかけられました。それに答えることは苦しいことでした。子どもや家族に視座を移して考えることが、私はまったくできていなかったのです。だからその苦しい問いをいつも向けてくれた先輩に、感謝しています。
サン・テグジュペリ『星の王子さま』や金子みすゞ「星とたんぽぽ」をどこかで読み、「見えないけれど大切なもの」があるということを心にとどめていた彼等ですが、発達や障害をしっかり学べば立派に働いていけるのではない、もっと深くて広い「見えないけれど大切なもの」があることを、この手紙から感じたようです。
学生たちの不安そうな顔を目にしたときには、今はわからないことがたくさんあってよい、将来の実践があなたを育ててくれると言います。そして、次のようなことを話したりもします。
まず、一日一日の実践を大切にして子どもやなかまと向きあう。苦しい日もあろうが、「とりあえず、とりあえず」と自分に言い聞かせながら、その一日を積み重ねること。
苦しいことがつづくときには、自分の話を聞いてくれる(手紙での「組合の先輩」のような)人や仲間を探し、語りあうこと。
このまま、この仕事をつづけて行ってよいのかと迷うこともあろうが、いつか振り返ったときに、自分の後ろに歩いてきた道が見えるようになっている。その道を後ろに感じながら、前を向いて歩いていけばよいこと。
ただ、謙虚さ、たとえば子どもや家族や同僚の生きる姿、働く姿に学び、先達の遺してくれた人間と社会進歩に関する学問(社会科学など)に学びつづけることを忘れないでほしい。発達は、子ども理解や指導・支援の手がかりを見つけるためだけではなく、人間と、その一人である「あなた」を理解し、大切にするために学ぶもの。
・歯を食いしばる日常を、耐えながら受け入れる
子ども、なかでも障害のある子どもを育てることは、「自己責任」であり誰に頼ることもできないと思わされて、歯を食いしばりながら生きる家族の日常が、あなたの瞳に映っているでしょうか。
その(家庭訪問)とき聞いたのですが、お母さんは子どもたちを学校に送り出してから、介護の仕事に出かけています。そしてリョウちゃんを迎えてから子どもたちが寝つくまでに家事を済ますと、夜半過ぎまで近所のコンビニで働いているというのです。「妹、弟も、希望すれば大学まで出してやらなければと思っています。頼れる親戚もいないし」と言われました。
教師の生活も楽ではないのですが、この国で子どもを育てること、そして障害のある子どもを育てることは、その歯を食いしばる日常を、耐えながら受け入れることなのではないかと私には思えてなりません。
この手紙をくれた卒業生は、昼間に介護の仕事をしながら、夜中にコンビニでレジに立つ一人親としてのお母さんの日常を知って、はらわたが突き動かされる気持ちになったのです。そのお母さんに対して自分は、連絡帳の返信がいつも「通り一遍」なことにいらだち、リョウちゃんが学校で不安定なのは、家庭生活に原因があると思い込んでいたのでした。
出会った日のお母さんの言葉を思い出すたびに、私はお母さんに謝らなければならないと思います。私の車は派手ですが、どこにでもある色です。この十年、その色の車を見るたびにお母さんは私のことを思い出していたのでしょうか。
そして、赤い色の車を見るたびに、お母さんを苦しめていた自分のことを思い出しているのではないかと「謝りたい」気持ちになったというのです。「もう一つ」第1回で書きましたが、お母さんは赤い車を見るたびに、「あの一途な新任の先生が、学校という社会のなかで働きつづけられているか」と気遣ってくれていたのではありませんか。
この3つの文章に目を留めたのは、福祉の現場に出ようとしている学生、施設で働いている方などです。そして少数ながら、特別支援学校・学級の教師の方もおられました。きっと、この手紙の卒業生のように、子どもと親の生活の苦しさやそれに立ち向かう意志をみようとしていなかった自分を知って、ぬぐうことのできない心の痛みをもった方でしょう。
非正規雇用が常態化し、とくに母親だけの一人親家庭が、経済的な困難を背負わされている現実があります。深刻な貧困、まじめに働いてもそれにふさわしい賃金が支払われない搾取の「しくみ」を変えていかなければなりません。
卒業生から教えられるのですが、若い彼らには他者の生活への想像の力、そこにある現実を追体験できる共感の心があります。私たちは連載第Ⅰ部において、発達は視座を他者に置いて、他者の感情、思考、意志を認識し、それをまるで我がことのように感じられる想像と共感が育つことでもあると述べてきました。その力と心は、すべての人間に備わっている発達の潜在的可能性ですが、きっかけを与えられないと開花してきません。きっと障害のある人びとのために働こうとしている彼らは、幾重にも発達のきっかけを得てきたのだと思います。その力と心をもちつづけて、障害のある子ども、なかま、家族の生活と向きあい、心の痛みも味わいながら、社会の「しくみ」を変えていこうとする人びとと、手をつなぎあってほしいと思います。
そして、とても大切なことですが、その家庭がさまざまな生活の困難に陥っていることを知ったときには、けっして見過ごさず、助けなければなりません。学校、施設として自治体の福祉の窓口、相談支援事業所などと協力して、生活保護や地域生活支援をはじめとする諸権利の行使のために、具体的な対応に踏み出していただきたいと思います。
・同僚を愛すること
以下は、卒業式の日に手渡している手紙のなかの一節です。「愛する」とはむずかしい言葉であり、ここでは「大切にする」と言い換えてみましょう。
「同僚を愛すること。これから出会う人々を好き嫌いで選り好みせず、見限らず、粘り強く向きあってほしいと思います。あなたも同僚も、よりよく生きたいと願い、それゆえに自分の不器用さと向きあい、矛盾を抱きつつがんばって生きているのですから。」
実は、ここに私たちのお尋ねした読者のみなさんの過半数、とくに特別支援学校の先生方の目が留まったようです。「だれといっしょに担任を組むのか、いつも憂鬱な気持ちになる自分にとっては、辛い言葉です」「以前は同僚とこんな気持ちで向きあっていたのに、今、そうなれないのはなぜなんだろう」「いったいどうしたら、こんな気持ちになれるのですか」「こんな立派な人間にはなれない」等々。
私たちは、同僚に不満をもってはならない、いつも同僚には「我慢強く」向きあうべきと思っているのではありません。「粘り強く」は「我慢強く」とはちがうと思います。とくに若い人たちは、「やりがい、働きがいが大切」と強調される風潮のもとで、「しんどい」と言ってはならないと思い込み、「がんばって働いているのに、どんどん苦しくなる」という心理に追い詰められようとしているのです。そして、「苦しい仕事を選んだのは自分」「うまくいかないのは自分の能力のなさ」と、知らず知らずに取り込んだ「自己責任」の原則で自分を評価していきます。
そのことを認識したうえで、教育や施設実践に歩み出ていく卒業生に対して、この「手紙」を毎年書いているのです。この社会にあって、障害があり、幸福の追求、基本的人権の享有が虐げられている、いわば「弱くさせられている」人びとのために働こうと思った彼らは、その子どもやなかま、家族を、「好き嫌いで選り好みせず」、等しく大切にしたいと期して社会に出ていきます。その彼らですから、いっしょに働くことになった同僚のことを、同じ思いをもった人間として信頼し、大切にしたいとねがっているはずです。
考え方、感じ方、根本的な価値観のちがい、さらには相性もあるわけですから、ときには厳しい話にもなることがあります。もしそのときに、同僚への信頼を失い、見限って、何を言っても無駄なのだからと思ってしまったら、互いに背を向けて自分の世界、自分の実践のなかに逃げ込み、自分の担当の子どもだけを大切にするような領界を作ってしまうでしょう。そういった壁を作ってしまった関係を、「閉じた対(つい)」と名づけてみました。「対」とは「あなた‐わたし」の関係のことです。主には「子ども‐おとな」の関係が問われるのですが、「おとな‐おとな」であっても「閉じた対」になってしまったら、互いの思いを受けとめ心のキャッチボールをしようとする可逆操作は、生きてはたらく力になってくれません(白石正久『やわらかい自我のつぼみ』全障研出版部)。
もし今、そんな気持ちになってしまっているならば、あなたや同僚の心のもち方のせいではなく、そう感じさせられ、そう働かされている原因があることも見抜いてほしい。たとえば、この10年でさまざまな人事評価の制度、職位の細分化とヒエラルキーが政策的に導入されました。本来は同僚という同じ場に立つ関係のなかに、上下や競争の関係が押し込まれてきたのです。さらに、人手が足らない、空間が確保できないというもとで、その一日を事故なく乗り越えるだけで必死になっているというのが現実だと思います。そういった環境にあって、図らずも、上に立って職場集団をまとめなければならない役割を担うことになった人は、苦しいことも多いでしょう。
誰かが誰かのうえに立って上意下達で指示し評価する、さらには職場の情報共有を画一化・マニュアル化することによって、職場の秩序と経済的合理性(効率化)を維持しようとするシステムは、語りあい、わかりあうという時間の大切さを過小評価します。そして、人と人の心を切り離し、共感という感情を抑え込み、いつも他者のまなざしを気にしながら働かなければならない状況へと職場を変えていきます。そのもとで、夕方になるとよくわからない疲労感にさいなまれ、学習や実践交流をしようなどというエネルギーは残っていないという人もいるのではありませんか。この現実に負けたくないと私たちは思います。(そういった職場の状況を分析する視点を、深谷弘和(2021)「新自由主義における福祉労働者の『個別化』と集団性の意義」(『障害者問題研究』第49巻2号、90-97ページ)から学びました。みなさんにも、お読みいただきたいと思います。)
何でもそうですが、導入期はその新しいシステムが効を奏したかに見えるものです。しかしそれが、人間の共感、共同という心のはたらきを大切にしないシステムならば、必ず人間本来のあり方との「ずれ」が大きくなります。こういったシステムを自分のなかに取り込み、自らを順応的に変えて生きることも一つの道ですが、ますます「ずれ」を意識して、違和感や反感を感じる人もいるでしょう。
もし職場のなかで、このシステムに適応できない、あるいは反対する人の、精神や人格への攻撃がなされるならば、それを見過ごすことはできません。自らの身と心を守り、仲間を守るために、力をあわせなければなりません。
そういった現実に身を置きながら、手を挙げて「受け入れられない」「やめてください」と声を出せない自分を、不甲斐なく思うこともあるでしょう。それは、良心の側に立とうとしているからこそ感じる情けなさだと思います。その良心によって、「こうありたい」という自分へのねがいをもっているのですから、自らと対話しつづけ、「どう生きて行ったらよいか」という道案内人を、きっと自分のなかに育てることができるはずです。
この良心に従って、それを実現していくためには、手をつなぎあわなければなりません。良心の側に立とうとする同僚関係は、ただ互いにみつめあい、相手の目や自分への評価を気にしながら働くのではありません。子どもの最善の利益を守っていくという互いのねがい(理念、目的)に確かな信頼を寄せ、その実現のためにともに同じ方向を向いて、力をあわせようとする関係だと思います。「卒業生からの手紙」の次の言葉には、そんな気づきが表現されていると思います。
子どものことで力をあわせられている実感は、自分のことをくよくよ考えないで、前を向いて歩くきっかけになりました。
・きょうもよく来たね
最後に一つ、大学の教員である私たちと学生たちのことを書きましょう。
そのお母さんそっくりの妹さんは今春、大学を卒業して障害のある人の生活介護の施設で働くとのことです。
たった一文で語られたことですが、リョウちゃんの妹が障害者施設で働くことになるまでには、本人にも家族にも、苦労の道のりがあったはずです。「きょうだい」である彼らは、物心ついたころから、さまざまな悲しさ、さびしさ、葛藤を重ねてきました。さらに、「人間を大切にする」とは言えない社会の現実を感じ取ってきたはずです。能力主義の溢れる「学校」や「施設」という「社会」に嫌悪感や疎外感を味わい、そういった場所での仕事に背を向けたくなることもあったでしょう。しかし、いくつかのステキな出会いのなかで、やっぱりここに自分の生きる意味があるかもしれないと思い立って、教師や指導員への道を歩み始めます。
あるいは一人親家庭などで、親の労働の厳しさや家計の困難をともに背負いながら、授業料も、生活費もアルバイトで捻出している学生は少なくありません。授業料だけで、国公立は数十万円、私立文系は百万円を超える年額を払わなければなりません。
授業や実習の進行に、追いつけないこともあるでしょう。朝も働いていることが多く、始業に間にあうように登校するのは、きっと至難の業です。教員は、「レポートが期日通りに提出されない」「今日も遅刻した」といらだち、彼らの生活の現実を見過ごしていることもあります。その生活の苦しさは、教員の目にもだんだんみえてくるので、そのとき学生に「謝りたい」気持ちになります。
学生たちが、学ぶよりも長い時間を働かざるを得ず、さらに人生の半ばを過ぎても、低賃金のなかから国の経営する「奨学金ローン」(利子付)を返済しつづけなければならない現実を国民に知ってもらって、ともに政治の不作為を追及してほしいとねがいます。国際人権規約A(社会権)規約第13条の定めるように、高等教育を他の先進資本主義国なみに、もっと早く確実に「漸進的無償化」へと進めるべきです。
私たち教員は静かに見守るしかありませんが、たぶんともに学ぶ学生たちは、互いに無関心を装いつつ、心のなかでは「がんばれ!がんばれ!」と言っているのです。障害のある人びとだけではなく、社会のなかで「弱くさせられている」身近な存在を大切にする人間になってほしいと、私たちは学生にねがってきました。「仲間を大切にする」とはどういうことか、「人間を大切にする」社会を実現するために自分には何ができるか、一人ではできないことをどうしたらよいかをいつも考えて、実行してほしいと思っていました。
「卒業生への手紙」の以下の節は、私たち自身の、大学の教員としてのねがいでもあります。「クラス」を「ゼミ」「研究室」と言い換えてみるのです。
「今日もがんばって、よう(よく)来たね」と今からでも心を抱きしめてあげたいのです。それは、リョウちゃんだけではなくて、重い荷物を背負いつつも、今日も学校にやって来てくれるどの子に対しても。そして子どもたちが、そうやってお互いを抱きしめあえるようなクラスをつくりたいのです。
・おとなも仲間に支えられ、発達の矛盾を乗り越える
さて、何のためにこの手紙への感想をお尋ねしてきたのかといえば、それは読者のみなさんが今、向きあっている「人生の節目」、発達の矛盾を知りたかったからです。みなさんが、「こうありたい」とねがっていることと現実のあいだにあって、その苦しい思いゆえに読み過ごすことのできないことが、「手紙」のなかにあったでしょう。
教師として働くみなさんが、「同僚を愛すること」に目を留められたことは、現下の学校のなかにある苦労の一端を示している事実だと考えました。その苦労を否定的にみる必要はありません。多くの方が本当は同僚と心を通わせながら働いていきたいとねがっているからです。その苦しい思いに負けず、流されることなく、自らの発達の矛盾として自覚し、それを乗り越えていくために一歩踏み出したいと思います。
連載第12回では、次のように書きました。
私たちはこの手紙を読んで、「教師になる」のではない「なって行く」のだと教えられました。その「行く」という道行(みちゆき)こそ、一人の人間の、そしてその人間のつながりである集団の発達なのだと思います。つまり発達は、子どもやなかまのことでありつつ、私たちのことでもあります。
子どもやなかまは、本当はみんなのなかで楽しく生活したいのに、教室から出ていったり、身を隠してしまうことがあります。それでも戻ってきてくれる彼らを、私たちはあたたかく迎え入れようとします。おとなも同じように、疎外感を味わったり、一人になりたいときがあったりしながら、やがて、仲間のなかに自分の居場所を探し、苦労を分かちあうきっかけを求めはじめます。
おとなも、語りあい、学びあい、ねがいを共有することによって、発達の矛盾を乗り越えていけるのです。もし、苦しい思いの仲間が近くにいるならば、「ここに、あなたの椅子は用意しているよ」「なんでも話していいんだよ」と迎え入れられるような職場を創りたいと思います。いつも、子どもやなかまのことが語られ、そのことを通じて、子ども、なかま、そして私たちが発達していくような、あたたかい仲間の輪を拡げていきましょう。
おわりに
連載第Ⅰ部に対する「もう一つの『発達のなかの煌めき』」は、今回が最終回です。1年間おつきあいいただき、ありがとうございました。また、「みんなのねがいWEB」への掲載をつづけてくれた『みんなのねがい』編集部と全障研全国事務局の仲間に感謝いたします。
4月からは第Ⅱ部「発達的共感が創り出す実践 ― 歴史に学び、今をみつめ、未来を創る」へと連載は進みます。第Ⅱ部の「もう一つの『発達のなかの煌めき』」は、第Ⅰ部のような定期ではなく、テーマごとにまとめて、不定期に掲載していきたいと計画していきます。とくに、私たちが学び、私たちを育ててくれた実践や学問を、できるだけたくさん紹介していきたいと思っています。
これまで以上に職場、地域で『みんなのねがい』の読者を拡げていただいて、発達保障のねがいを実現していくためのつながりの輪を大きくしていきましょう。
今回の学習参考文献
・深谷弘和(2021)「新自由主義における福祉労働者の『個別化』と集団性の意義」(『障害者問題研究』第49巻2号、90-97ページ)
・白石正久(2011)『やわらかい自我のつぼみ』全障研出版部
・白石正久・白石恵理子編(2022)『新版 教育と保育のための発達診断 上』全障研出版部
・白石正久・白石恵理子編(2020)『新版 教育と保育のための発達診断 下』全障研出版部
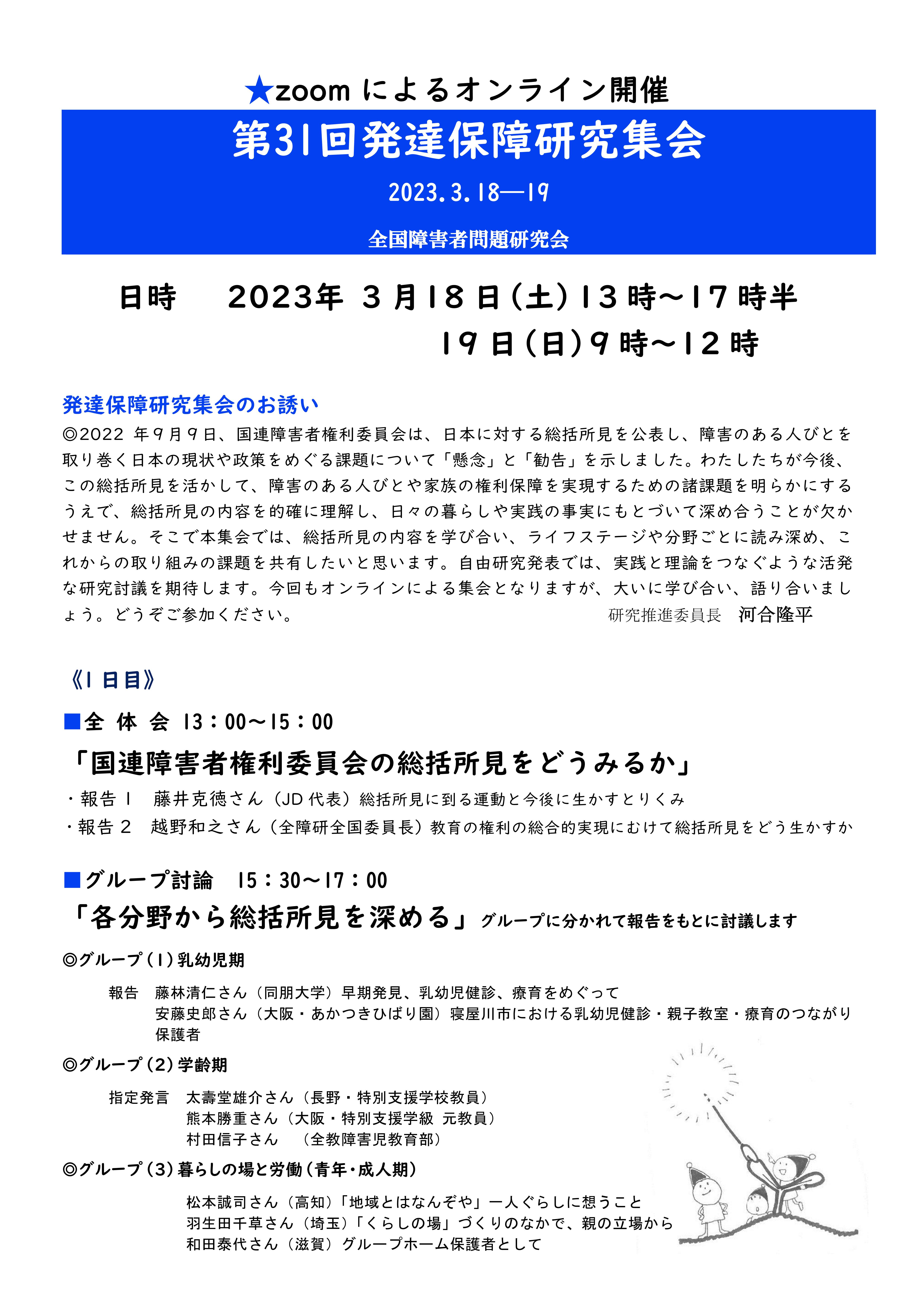
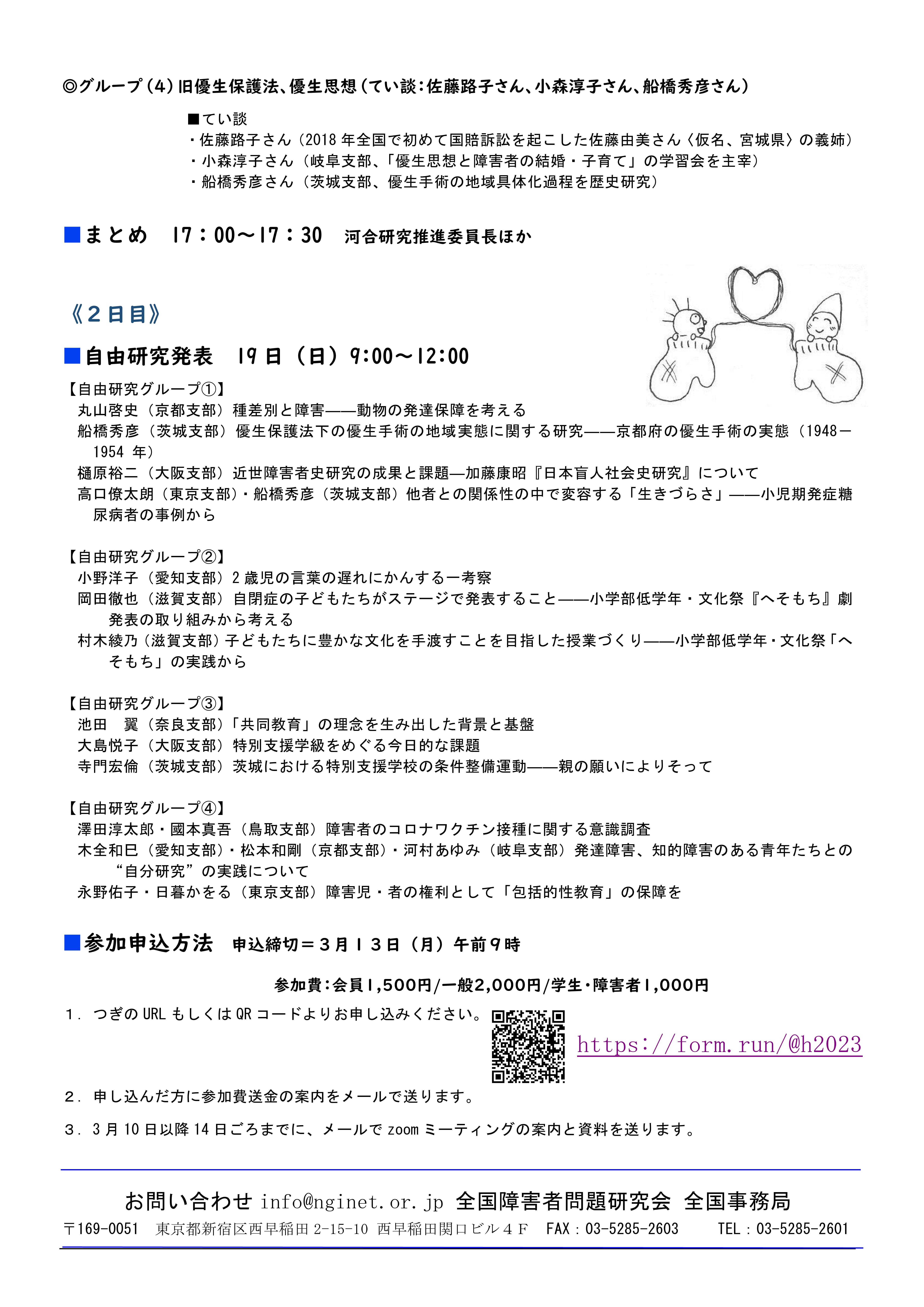
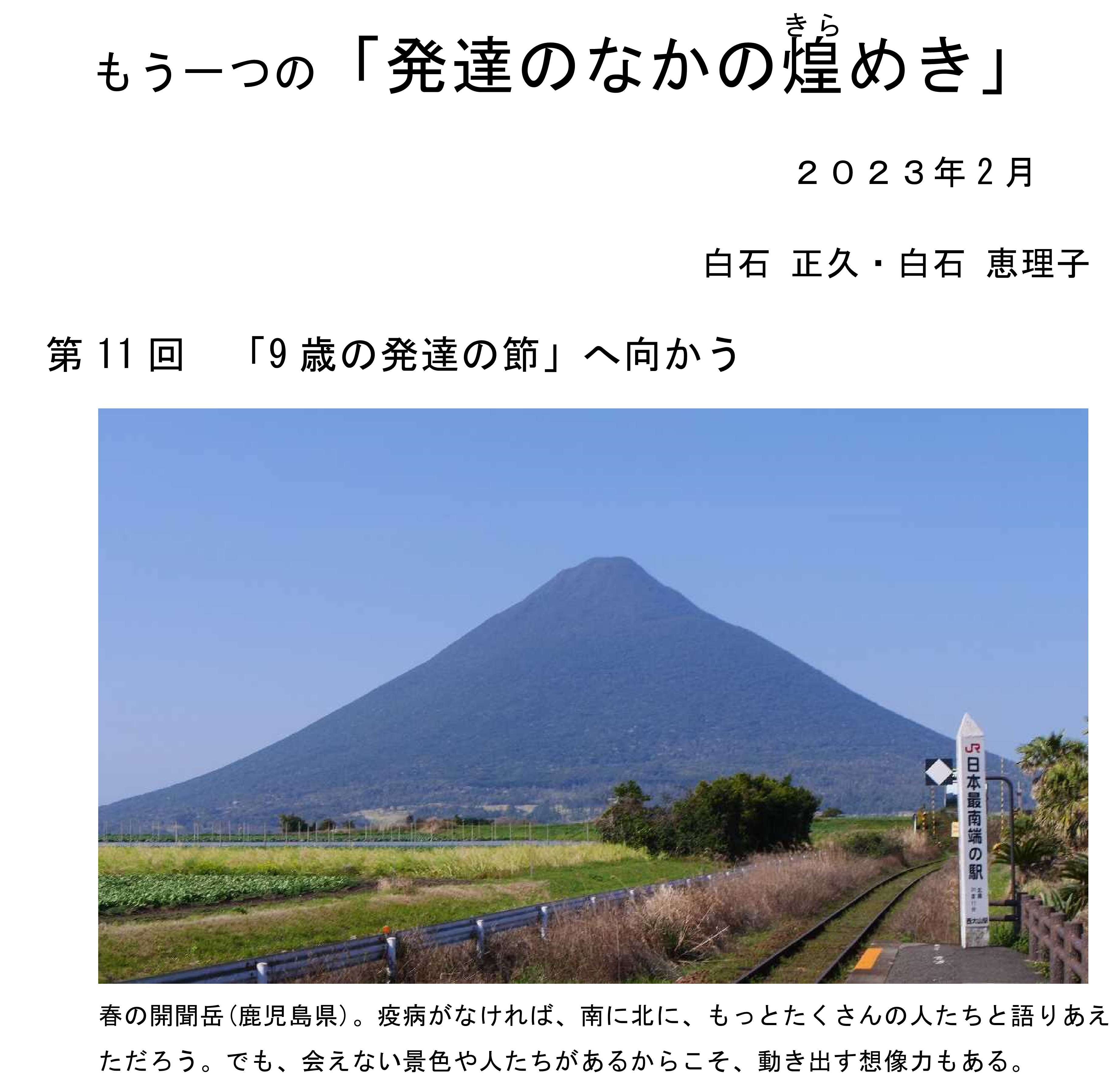
はじめに
連載第10回と第11回では、「3次元形成期」(障害のない場合の5歳後半~6歳)で誕生する「生後第3の新しい発達の力」、および「9歳の節」にあたる「1次変換可逆操作期」について説明しました。一方、「7歳の節」にあたる「3次元可逆操作期」については、発達の重要な転換点である「3次元形成期」に力点をおいたために、説明を行ないませんでした。「3次元可逆操作」を含む「3次元の世界」を詳しく学ぶには、『新版 教育と保育のための発達診断 上』(以下では『上巻』)の「Ⅲ 第4章 7歳の発達の質的転換期と発達保障」、『新版 教育と保育のための発達診断 下』(以下では『下巻』)の「第7章 7~9歳の発達と発達診断」をお読みいただきたいと思います。
今回の「もう一つ」では、「3次元形成」からの発展としての「3次元可逆操作」の特徴、それが「9歳の節」へ向けて展開するようすについて、以下のテーマで解説します。
・他者視点の獲得
・現象(みかけ)の奥にある本質をとらえる力
・「ちがうけど同じ」の基礎にある「保存」の思考
・概念の階層関係の理解
「3次元可逆操作」への発展 ― 3枚の写真から
① 他者視点の獲得
連載第10回の「人物の3方向からの描画」課題、第11回の「相手の左右の手の弁別」課題、そして「もう一つ」第9回の「道順描画」課題に取り組む子どもの写真をご覧ください。「生後第3の新しい発達の力」を誕生させようとする子どもの心のなかの取り組み(内的作業)が、いかにエネルギーを必要としているか、だからこそそれが「発達のなかの煌めき」の如く、新しい力に満ちていることを実感していただけるでしょう。
連載第10回(1月号)では、「人物の3方向からの描画」課題(『下巻』157~159ページ)を用いて、「生後第3の新しい発達の力」を次のように説明しました。
自分の「前向き」「横向き」「後ろ向き」の絵を描いてもらうのですが、三次元形成の力がうまれてくると、「横向き」では目を一つにしたり、髪を片方だけにしたり、「後ろ向き」では顔のなかに目鼻を描きこまなかったり、黒塗りにしたりと、それぞれに工夫しながら「前向き」とは異なる絵を描くようになります。
なぜ、このような絵が描けるようになるのでしょうか。もちろん「前」「横」「後ろ」といった空間の理解や表現が進むということもあるのですが、「自分を横(後ろ)から見たらどう見えるのかな」と、自分のなかで視点を変えることができてくるからでしょう。この力は、相手から見たらどう見えるのかといった他者視点の獲得とも深く結びついています。この他者視点の獲得は、「ちがうけど同じ」という転倒を伴う共感の過程をくぐることによって、現象(みかけ)の奥にある本質をとらえる力につながっていきます(ゴチックは大切にしたい概念を示しています)。
実は、ここでいう「他者視点の獲得」や自分と他者は「『ちがうけど同じ』という転倒を伴う共感」は、子どもにとって簡単なことではありません。「ちがう」ことはわかっているのだけれど、どうちがうかがイメージできないので、子どもは、写真のように頭を抱えたり、宙を仰いだり、手指で仕草をしながら、発達の課題に取り組もうとします。その姿は、まさに「新しい発達の力」の生みの苦しみのなかにあるようです。
子どもが後ろや横をイメージすることができないで苦しんでいるときに、検査者である私たちは、「見えないからむずかしいよね。いっしょに考えてみようか。私の後ろはどうなってる?」などと自分の姿を見せたりします。すると子どもは、何かに気づいたように「(後ろは)なんにもあらへん。毛だけやな」「(横は)目(耳)が一つしか見えへん」などと言いながら鉛筆を動かし始めます。他者の「後ろ」や「横」は自分のとは「ちがうけど同じ」という理解にはまだ至っていませんが、「前」とはちがう「後ろ」や「横」の手がかりをつかんで、自分なりに表現しようとするのです。
この課題だけではなく、「他者視点の獲得」の入り口では、他者はどう見るのか、どう感じるのか、どう考えるのかの「手がかり」を、いかに組織するかが問われています。しかしもっと大切なことは、「生みの苦しみ」を味わいながら、子どもが自らつかみ取っていくのが「新しい発達の力」だということです。ここで、「生みの苦しみ」に出会わずに、あるいは「生みの苦しみ」に共感されずに、答えだけを知っていくようなことになるなら、次の発達の質的転換をつくりだすような内的エネルギーは薄っぺらいものになりはしないでしょうか。
「人物の3方向からの描画」の、これ以後の変化について補足しておきます。「3次元可逆操作期」になると、「ちがうけれど同じ」が確かにわかって、手がかりを必要とせずに、「横は目も耳も、手も足も、全部一つしか見えへん」と言いながら、描けるようになっていきます。しかも、手の指は5本であること、自分には好みの髪形や衣服があることなど、自分の知っている「自分」を表現しようとします。それが、「9歳の節」である「1次変換可逆操作期」に向かっていくと、身体の全体と部分の大きさのバランスや、「前」「後ろ」「横」の身体部位の相互の位置関係を意識して、見た通りの客観的な「自分」を描こうとするようになっていくのです。異なった方向からの描画ですが、多面から同一の人間を描いているのであり、表現には「統一性」がないといけないことを認識するようになっていくのです。
以上は「人物の3方向からの描画」課題の説明ですが、読者の皆さんは、ここから想像力をたくましくしていただいて、子どもやなかまが、さまざまな生活場面で、「自分のなかで視点を変える」ことや「相手から見たらどう見えるのか、相手はどう感じるのか」がわからないで、頭を抱えている姿はないかと考えてみてください。学習した発達の事実が、子どもやなかまの日常の姿のなかで、どのように現れているかに視野を広げることによって、発達はしだいに生きた認識になっていくものです。
たとえば、「他者視点の獲得」の芽生えの段階では、自分の思いや考えが優ってしまうことも多々あります。連載第11回のケイタさんも、リレーのチームリーダーになってから、ただ「勝ちたい」思いが先行して、バトンタッチを失敗した友だちを「あほ、ぼけ」と罵倒してしまうのでした。そのことで、クラスの仲間との心理的距離は、さらに広がってしまいます。でもケイタさんは、別のチームの友だちが、「失敗しても、ドンマイとリーダーに言ってもらってうれしかった」と発言しているのを聞いて、気づきつつあった「このままの自分ではいけない」ことと向きあい始めます。そして、「友だちに喜んでもらえる自分になりたい」とねがうようになりました。ケイタさんは、「自分」のあり方の「手がかり」となるモデルを、仲間のなかで探していたのです。
小学校教育への「円滑な接続」のためにという「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」(保育所保育指針、幼稚園教育要領等)では、たとえば「協同性」は、「友達と関わる中で、互いの思いや考えなどを共有し、共通の目的の実現に向けて、考えたり、工夫したり、協力したりし、充実感をもってやり遂げるようになる」と説明されています。文字通りの「育ってほしい姿」として否定するものではありませんが、この「姿」が育ち始めるときにはまだ自分の「思い」が強く、友だちの思いや考えなどに「想い」が及ばず、悔しさや情けなさを味わうものです。そのたくさんの「まだ育っていない姿」があるからこそ、頭を抱え、宙を仰ぎながら、子どもは自分の視点を他者に転じることの大切さに気づき、「協同性」の基礎になる力を発達させていくのです。いっけん「負の姿」を、大切な発達のきっかけととらえる発達観を、私たちは大切にしてきました。『保育所保育指針解説』などが、そういったことに留意していないこととは対照的と言ってもよいでしょう。
② 現象(みかけ)の奥にある本質をとらえる力
連載第11回(2月号)では、「相手の左右の手の弁別」課題(『下巻』154~155ページ)を用いて次のように説明しました。
自分の左右がわかってきた子に対し、互いの両手を突きあわせるようにして、向かいあう相手(検査者)の左右を尋ねます。「先生の右手はどっち?」に対し、最初は、自分の右手と同方向(左手)を答えるでしょう。それが、「生後第三の新しい発達の力」が生まれてくる五歳半ばになると、自分の右手とは反対側が相手の右手であることを直感的に理解し始めます。しかし、「どうしてそう思ったの?」と聞かれると答えは動揺しがちです。それが、第三段階である七歳頃(三次元可逆操作期)になると、「向きが反対やし」等と理由もきちんと説明して揺るがない答えをするようになります。
「3次元形成期」では、自分と他者は「ちがう」ということに気づき、その気づきが「直感的」とも言える相手の左右の理解につながっていきます。このときも、連載第11回の写真のように自分の両手を机上に出して、向きあう相手の両手と何度も見比べながら、「向きあう相手は左右が反対」という事実を、自分でつかみ取ろうとするのです。そして、どの人もその人のなかにある基軸によって左右は決まっていくのだという、いわば共通性を取り出せるのが「7歳の節」つまり「3次元可逆操作期」です。
「可逆操作」とは「往き‐戻り」のある逆操作が発達のさまざまな能力やその連関(つながりあい)において可能になることです。たとえば「左右の弁別」では、「中心」である基軸を据えて、「左ではない右」「右ではない左」を区別しつつ、「中心」「右」「左」の3つを確定していきます。さらに自分と他者の関係にあっても、他者に視点を移して相手の左右を弁別し、さらに相手から見て自分の左右を弁別できるという自由な逆操作を獲得していきます。その操作が確かであることは、「向きが反対やし」と理由が言えることなどに表れます。
可逆操作は、外界に働きかけ、それを取り込んで運動や認識を高めていくだけではなく、自分と他者、自分と「社会」との関係でも発揮できるようになっていきます。可逆操作によって、長い時間をかけて視座を他者に対して移していき、相手の思考、感情、その背景にある生活を認識し、対話や共感ができるようになります。そして、自分のことを反省的に理解し、修正できるようになっていくのです。そういった他者との交流や共同のなかで、自己中心性や自意識過剰な心理を、自身との葛藤を一つひとつ踏み越えながら脱却していくことができます。
先に述べたように、このことが「左右の弁別」にとどまらず、「他者視点の獲得」として、日常のどんなところで発揮されているかを想像していくことが大切です。たとえば、連載第11回と「もう一つ」第10回では、「導き、導かれる関係」によって、「自分のうれしいことは、友だちもうれしいだろう」と共通の感情世界への深まりをもった人間理解がなされていくことを述べました。
その基礎を築く発達段階(「2次元可逆操作期」)にあったのが、連載第1回、第2回に登場したリョウちゃんです。リョウちゃんは、医療的ケアを必要とする重症児のクラスに毎日出かけるようになりました。障害の重い子どもの手に優しく触れたことが、その交流の始まりでした。重い障害をもっている子どもたちがリョウちゃんのことを毎朝待ってくれている、そう考えるのは思い込みかも知れません。しかし、日々の交流がつづいている事実のなかに、通いあう感情世界があることを否定することはできないでしょう。リョウちゃんは、この朝の交流によって心が癒されて、その日のためのエネルギーを得ているようでした。「他者視点の獲得」や人としての共通性を認識し感じ取ることは、長い発達の道すじのなかでの交流、共感、共同のうえに花開いていくのです。
③ 「ちがうけど同じ」の基礎にある「保存」の思考
「ちがうけど同じ」という認識の基礎にある「保存」の思考について補足します。
「3次元形成期」では、子どもは直感的に「ちがい」や「同じ」を理解するのですが、「3次元可逆操作期」になると、ものごとのなかにある本質や法則を見出すことができるようになり、それを言葉で説明するようになります。
発達心理学者ピアジェの「数の保存」に関する実験があります。6個の青い「おはじき」と同数の赤い「おはじき」を、両端をそろえて平行にならべて子どもに見せます。その後、青いおはじきの間隔を広げて列を長くして見せてから、「どちらがたくさんありますか」と尋ねます。
5歳頃の子どもは、列の長さやおはじきの間隔の詰まり具合という「みかけ」に影響されて、「青」あるいは「赤」と答えます。理由を尋ねると、「長いから」「広くなったから」「たくさんある」などと言います。7歳頃になると、「どちらも同じ」と答えるようになります。その理由は「足しても引いてもいないから」(同一性)、「元に戻したら同じになる」(可逆性)、「長くなったけど、すき間があるから」(相補性)などと自分の観察によって、自分なりに説明できるようになります。「みかけ」は変わっても数は変わらないことを論理的に理解できるので、これを「保存」の思考と言います。「足す‐引く」「広げる‐狭める」というような具体的で可逆的な操作を通じて、数や量がどうなっていくかの思考が獲得されていきます。
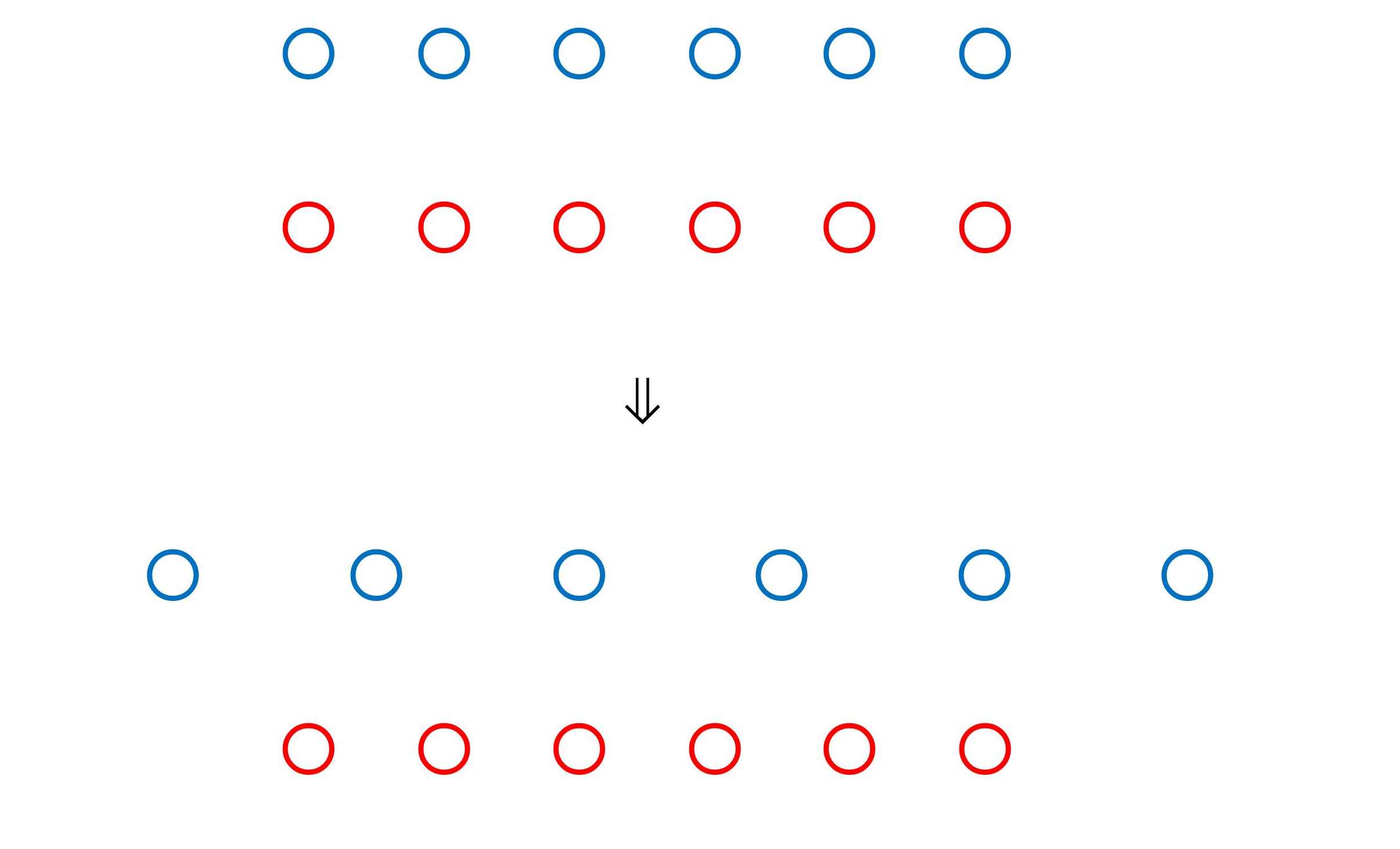
このような「保存」の思考は、7歳で突然のようにできるのではありません。まだ保存の思考が獲得されていなくても、「なんか変だぞ」とこの問いのカラクリに気づき始めるときがあります。長くなった青いおはじきの列を、子ども自身で元の間隔に戻してみると同じ長さになりました。元のように間隔を広げてみると、列は長くなりました。そういった試みや具体的な操作を通して、そこにある「同一性」「可逆性」「相補性」などの法則性に「気づく」ことが大切なのです。時間をかけ、なんどもやってみて、自分自身の「気づき」によって歩みだすことができるようになっていきます。しかも、説明の仕方が「自分なり」のものであるように、一人ひとり違う感じ方と考え方があります。その違いを集団のなかで語りあい、わかりあい、「手がかり」としていくことが大切です。
こういった思考の発達は、生活のなかでいろいろな素材に出会い、はたらきかけることによって、感じたり、考えたり、工夫したり、仲間とそれを共有しあってきた経験が基礎になっています。心理学の実験素材として等質性のある「おはじき」は有効ですが、この「保存」の思考が可能になっていくには、むしろ変化、変動のある素材にはたらきかけて、さまざまな驚きや発見を経験していくことに意味がありそうです。
つゆ草の色水は、たくさん花を集めた方が濃くなること、花を投じる水の量によって色の濃さが変わることを、子どもは経験によって知っていきます。農村で育った私には、北風にうつむきながら祖母と麦踏みをした記憶が残ります。「カニのよこ歩き」で、同じ畝の長さを踏んでも、踏み方のていねいさによって密度が異なることに気づくのは、ずいぶん大きくなってからでした。そこには、「保存」の思考の基礎になる経験があります。
ただ、こういった経験のなかで発達するのは、「保存」の思考だけではないことを、私たちは大切にしたいと考えています。たとえば、つゆ草の色水のような自然の創り出す色彩の変化の繊細さと透明感、密度高く踏まれた麦のもつ復元の力強さを、自分自身の感覚と感性によって理解していったことも、何かを残してくれたように思うのです。他者、仲間とともに、自然や、人間の創り出す文化に出会い、はたらきかけることの大切さについては、連載第Ⅱ部「発達的共感が創り出す実践」で述べたいと思います。
「9歳の節」―「1次変換可逆操作」へ
先の連載第11回(2月号)からの引用には、次がつづきます。
このように、みかけ(現象)の違いに迷わされずに、その奥にある共通性を取り出せるようになることが、上位概念の獲得に代表されるような「九歳の節」につながっていくのです。バス、船、バイク等々を個別具体的に理解していた段階から、「九歳の節」を迎えると、「人を乗せて運ぶもの」として「のりもの」という本質を抽出できるようになります。これが、抽象的・論理的な理解の基盤になります。
「9歳の節」は、障害がない場合には、文字通り小学校の中学年に対応する大きな発達の質的転換期です。田中昌人さんの「可逆操作の高次化における階層‐段階理論」では、「1次変換可逆操作」の獲得期であり、「変換可逆操作の階層」への飛躍のときです。読者の皆さんは、こういった「変換」などの概念の難解性にすでに辟易されているかもしれません。これまでも述べてきたように、「その言葉に大切な意味が込められていることから気持ちを背けず、まず概念のむずかしさは横において、具体的な子どもの姿から理解する」という姿勢でおつきあいください。
さて、「9歳の節」は、「9、10歳の節」「10歳の節」、あるいは「節」ではなくて「壁」と言われることもあります。その名称を用いる論者によって、「節」や「壁」の特徴の取り出し方は、少しずつ異なります。そのことについては、『障害者問題研究』第48巻2号(2020)「『9歳の節』と発達保障」をお読みいただければ幸いです。
「9歳の壁」は1960年代に、聴覚障害教育のなかで仮説され実践によって深められてきたこと、障害のない子どもたちにおいても、学力と人格の形成上の課題が顕在化しやすい時期として注目されるようになったことは、ここでも共有しておきたいと思います。
概念の階層関係の理解
『下巻』の174~175ページで楠凡之さんが「目に見えない関係を理解して『変換』していく力の獲得」を解説されています。そのなかで、「9歳の節」の特徴として、「概念の階層関係を理解し、上位概念と下位概念のどちらからどちらへも置き換える(変換する‐白石註)ことができる力が生まれてくる」時期として説明しています。
知能検査「WISC‐Ⅳ」のなかにある「類似」課題では、「ピアノとギターはどんなところが似ていますか」「クレヨンと鉛筆はどんなところが似ていますか」などと問います。「楽器」「書くもの、筆記用具」などと答えるのが、上位概念の形成される「9歳の節」の時期です。その逆の問い、「楽器の名前を言ってください」に、たくさんの楽器を挙げることも可能になります。そこには、上位概念から下位概念という「逆」も成立しているのです。
楠さんも紹介されている脇中起余子さんの研究(2009)では、小学校2、3年生と小学校4、5年生の間に、絵カードの分類方法の質的差異が認められるとのことです。つまり、小学校2、3年生では、「金魚→魚」「鳩→鳥」というように、それぞれのカードについて下位概念から上位概念へ一対一対応で分類していくのに対して、小学校4、5年生ではあらかじめカード全体を見渡して、「動物になるのはこれとこれ」というように、上位概念から出発する分類を行なえるようになります。
ここには、「9歳の節」つまり「1次変換可逆操作期」の形成期において、下位概念から上位概念への思考を豊かに拡げている子どもの姿と、その過程を跳躍台にして、全体を見渡してそこにある共通性を取り出して分類する方略が成立してくる過程を見出すことができるでしょう。この「思考の方略」については、次回の「もう一つ」第12回で解説する予定です。
連載第11回では、(抽象的・論理的な理解の基盤になるのは)「外からの教え込みによってではなく、子ども自身が主体的に外界に働きかけていくこと、多様な人とのかかわりのなかでつかみとっていくこと、それが互いを大切にしあう人格発達につながること」を述べました。そのことの大切さを、実践によって確かめあいたいと私たちは思っています。
次回の「もう一つ」では、ひきつづき「9歳の節」について解説する予定です。そして「第Ⅰ部」の締めくくりとして、連載第1回の「卒業生からの手紙」について、振り返ってみたいと思っています。
今回の学習参考文献
・『障害者問題研究』第48巻2号(2020)「『9歳の節』と発達保障」全障研出版部
・脇中起余子(2009)『聴覚障害教育 これまでとこれから コミュニケーション論争・9歳の壁・障害認識を中心に』北大路書房
・白石正久・白石恵理子編(2022)『新版 教育と保育のための発達診断 上』全障研出版部
・白石正久・白石恵理子編(2020)『新版 教育と保育のための発達診断 下』全障研出版部
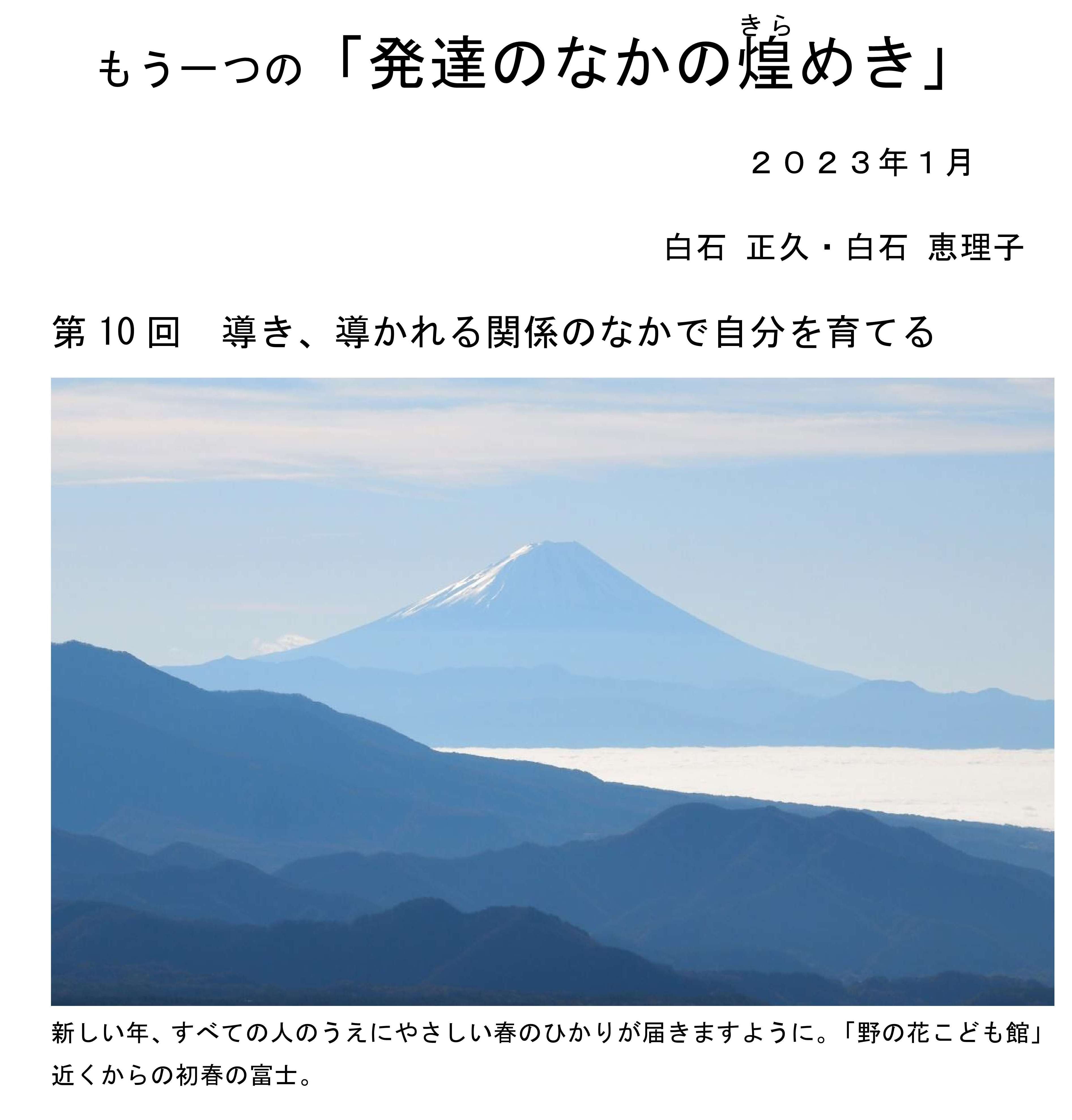
はじめに
新年あけましておめでとうございます。
昨年度は、『みんなのねがい』の連載「発達のなかの煌めき」(以下では「連載」)、そしてこの「もう一つの『発達のなかの煌めき』」(以下では「もう一つ」)で本当にお世話になりました。皆さんからいただいた励ましや気づきの声に、たくさんの新たな視点をいただくことができました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
前回の復習から
連載第9回(12月号)では、幼児期の発達の階層である「次元可逆操作の階層」の第3段階である「3次元可逆操作」の形成期となる「3次元形成期」をとりあげました。その発達的な解説を、前回の「もう一つ」で詳しく述べました。この「3次元形成期」は、「9歳の節」からはじまる学童期半ば以降の「階層」(「変換可逆操作の階層」)への飛躍のための力である「生後第3の新しい発達の力」が誕生するときであることを説明しました。
これまでにみてきたように、4か月で生まれた「生後第1の新しい発達の力」(『新版 教育と保育のための発達診断 下』「第1章 乳児期前半の発達と発達診断」)は乳児期後半を切り拓く力となり、10か月で生まれた「生後第2の発達の力」(『新版 教育と保育のための発達診断 下』「第2章 乳児期後半の発達と発達診断」)は幼児期を切り拓く力になったのと同様に、5,6歳で誕生する「生後第3の新しい発達の力」(『新版 教育と保育のための発達診断 下』「第6章 5~6歳の発達と発達診断」)は学童期半ば以降を切り拓く力にもなるのです。
その具体的な姿として、前回の「もう一つ」では、①過去や未来への時間軸ができはじめ、そこに自分を位置づける、②「ちがう」と「おなじ」を一つの事物・事象のなかに見出す、③「書きことば」の土台は、すじ道立てて考え文脈を形成すること、④仲間・社会とつながって、「書きことば」は人格の発達へとむすびついていく、⑤「二分的評価」を乗り越えた自己形成のねがい、の5点をとりあげました。
前回の復習が長くなりましたが、連載第10回でとりあげた「導き、導かれる関係のなかで自分を育てる」は6点目の特徴と言えるでしょう。
『夜明け前の子どもたち』のこと
連載では、びわこ学園(重症心身障害児施設・当時)の療育記録映画『夜明け前の子どもたち』(1968年公開)に登場する子どもたちを通して、上記の姿を紹介しました。これまで何十回となく、この映画を観てきましたが、いくつかのシーンと並んで今回とりあげた「友だち同士の食事の場面」も、最初からとても強烈に印象深かったシーンです。重度の肢体不自由をもっている子どもたちが、自分のリズムを刻むことも困難にみえるのに、相手のリズムにあわせて待ち、結果的に自分のリズムを意識し、自分をコントロールする力を高めていることに強い驚きを禁じ得ず、同時に大いに納得させられました。
もちろん、誤嚥等の危険もありますから、指導者の目が行き届くところでとても慎重に進められた取り組みであったし、より脆弱性の強い子どもたちにおいては、こうした取り組みは難しいものでしょう。ただ、誰もがそうであるように、自分のことを理解したり、自分自身を意識するのは、自分一人ではできないものです。そもそも発達という営みそのものが、自分で自分を変えていくプロセスなのですが、その自分をみつめる力は他の人から切り離された関係のなかでは育っていかないものだと考えます。あのシーンは、人は誰もが、他者と関わりあうなかで自分というかけがえのない存在を浮き上がらせていくものであることを教えてくれているようです。
食事場面の次のシーンは、10か月頃の「生後第2の新しい発達の力」を誕生させつつある子どもたちのリズム遊びの場面なのですが、自分が手にしている鈴のついたひもが、隣の友だちの動きによって揺れ、その揺れと鈴の音に誘われて、自分の手の動きが引き出されていきます。そうしてそれぞれの子どもたちが持ちあわせているリズムが重なりあっていく面白さのなかに、他者の動きを意識し、同時に自分の動きを意識しているようです。それは、話しことばの土台につながっていくのだと、当時の指導者たちは考えていたようです。今日でも、この発達段階にある子どもたちの教育実践においては、音楽やリズムがとても重要な位置づけをされているわけですが、当時のびわこ学園の指導者たちは、日々の子どもたちとの試行錯誤の実践のなかで、その値打ちを見出していったのだと考えます。
映画では、先に食事のシーン、そのあとにリズム遊びのシーンとなるのですが、子どもたちのリズム遊びの面白さに着想を得て、友だち同士で食事をするという大胆な実践を試みたのではないかとも考えさせられます。
なべちゃんと生間くんの関係に学ぶ
連載では、野洲川の河原での石運びシーンも取り上げました。この場面は、それまで多動であるがゆえに安全を守ることができないと、「必要悪」として白いひもにくくられていたなべちゃんが、そのひもから解き放たれて、自分の意志と力で目的的行動をつくろうとしていることに注目が集められてきました。また、常に手にひもをもっている自閉症の上田君に焦点をあて、彼にとってのひものもつ意味とは何かを探ることを通して、とても「人間的な」面に気づいていった職員たちの気づきが印象的な場面です。しかし今回、生間くんなどの「3次元の世界」を開きつつある子どもたちに着目して映画を見返すと、とても面白いことに気づかされました。
上記の「友だち同士の食事」や「リズム遊び」は、発達的に共通の時期にいる子どもたちのグループで取り組まれた活動だったのですが、この石運びの場面では、もっと多様に、発達段階や障害の違いを超えた子どもたちの関わりあいがつくられています。いつも狭い居室やプレイルームで過ごすことが多い(映画内では「閉じ込められていることが多い」と表現されています)子どもたちが、河原という広い空間に出てきた(そのためには「手もかかる」ために、厳しい職員体制のなかで、その取り組みをすることは容易ではありませんでした)子どもたちと職員たち。「この河原の広さがあれば何かができるのではないか」と語られるナレーションの楽天的な響きに、観る側も期待が高まります。
生間くんは、耳が聞こえないのですが、プールをつくるという石運びの目的も理解し、はじめて出会う他の施設の子どもとも一緒に石運びをするようになります。耳が聞こえず、就学も拒否されて、行き場のない思いをぶつけるように、壁に字のようなものを書きなぐっているシーンは、彼の切なさの奥に静かな怒りがあるのではないかと感じさせる場面です。思いはあるのに、コミュニケーションの行き先、受け手が不在で、壁に向かうしかない…その生間くんが、なべちゃんと組んで石運び作業に取り組みます。なべちゃんもまた耳が聞こえず、また発達的にもことばの獲得に至っていないことから、そのコミュニケーションは難しいと思われるのですが、生間くんは、なべちゃんに目の高さと呼吸をあわせるような動きを幾度かみせます。そして、なべちゃんも、職員が相手のときとは異なるやわらかな動きをみせます。
導き、導かれる
3次元の世界を開きつつある子どもたちにとって、他者に教える経験はとても重要です。4歳児も、「教える」気持ちはあるのですが、まだまだ相手の視点に立つことが難しいため、一方的に自分がやるだけで終わってしまうことが多いのです(それでも、学びたい子にとっては、見様見真似ながらも一生懸命なので、結果的に「教える」行為が成り立つこともあるのですが…)。他者にわかるように教えようとすることは、必然的に他者の視点に立つことにつながっていきます。ある幼稚園での自由遊びでのこと。3歳児の子どもたちが、色水遊びをしているおにいちゃん・おねえちゃんたちのテーブルに近寄っていきます。自分もやりたそうにしている3歳児を見ながらも、4歳児は自分たちが色水をつくることで精いっぱいです。つまらないと思ったのか、3歳児たちは、そのテーブルからいつの間にか離れ、5歳児が遊んでいるテーブルに寄っていきます。5歳児は、4歳児とは異なり、3歳児たちに「何色したいん?」とちゃんと聞いてくれます。
確かに5歳児には、年少児に教える力がぐんと備わってきていることを感じるエピソードです。このように教え教えられる経験が積み重なっていくことで、子どもたちは自分とは異なる視点を学び、それは徐々に「鉄棒は苦手だけど、絵を描くのは上手だよ」と多面的に仲間や自分のことを見ることにもつながっていくのでしょう。
ただ、「教える」という行為は、ややもすると、自分の見方を一方的に押し付けてしまうときもあります。それが、相手を苛立たせてしまうこともあるでしょう。逆に、「教える」という行為は、かなり意図的、主体的な行為ですが、生間くんのなべちゃんへの接し方は、そこまで意図的ではなく、なべちゃんに合わせていくことで、結果的になべちゃんの姿をひきだしているように思えます。「教え、教えられる」というよりも「導き、導かれる」の方がしっくりくると考えて、この言葉を使わせてもらいました。
今回の学習参考文献
・白石正久・白石恵理子編(2022)『新版 教育と保育のための発達診断 上』全障研出版部
・白石正久・白石恵理子編(2020)『新版 教育と保育のための発達診断 下』全障研出版部
みんなの声が総務省を動かす!
投票のバリアフリーで総務省が大規模調査を実施しています
以下は、12月17日の朝のNHK「お早う日本」で流れたニュースです。
障害のある人の投票環境 初めての大規模調査 総務省
2022年12月17日
体や心に障害のある人にとって選挙の際、投票所に行って一票を投じることは必ずしも簡単なことではありません。こうした現状を改善しようと総務省は、全国各地の選挙管理委員会を対象に投票しやすい環境をどう整えているかなどを尋ねる初めての大規模調査を始めました。
障害のある人の投票環境をめぐっては、障害者団体などでつくるNPO法人、日本障害者協議会がことし5月、投票環境の改善を求める要請書を総務大臣あてに提出しました。
要請書では投票所への移動の支援や、投票所のバリアフリー化の徹底、投票先を選ぶための十分な情報提供などを求めています。
こうした動きを受けて、総務省は来年春の統一地方選挙に向けて、全国各地の選挙管理委員会を対象に、投票しやすい環境をどう整えているかなどを尋ねる初めての大規模調査を始めました。
調査では、投票所に派遣する職員に研修を行っているかやマニュアルを作成しているか、投票所で行っている具体的な工夫などについて質問しています。
総務省では、集まった回答をもとに効果を上げている先進的な事例をホームページに公開するなどして、投票しやすい環境づくりにつなげたいとしています。
NHKではことし夏の参議院選挙に先立って「みんなの選挙」という特設サイトを立ち上げ、投票所で障害のある人が受けられる具体的な支援策や各地の取り組みなどを発信しているほか、当事者などからの意見を募集しています。
障害者団体「障害のある人の参政権守られるよう期待」
総務省の大規模調査について日本障害者協議会は、「自治体によって投票所での対応に格差があり、支援が必要だといった声が数多く寄せられている。障害のある人の参政権がきちんと守られるよう、現状の改善につながる調査になることを期待しています」とコメントしています。
▶NHK「みんなの選挙」(役立つ情報満載の意欲的なプロジェクトのサイトです)
▶JD 要請書「障害者の投票行為における合理的配慮を欠く問題事例の改善を」(PDF)
資料「投票における合理的配慮を欠く問題事例の改善を求める201の事例・要望集」
▶PDF版
▶テキスト版
▶「みんなのねがい」ニュースナビ=バリアフリー投票を求める運動(PDF)
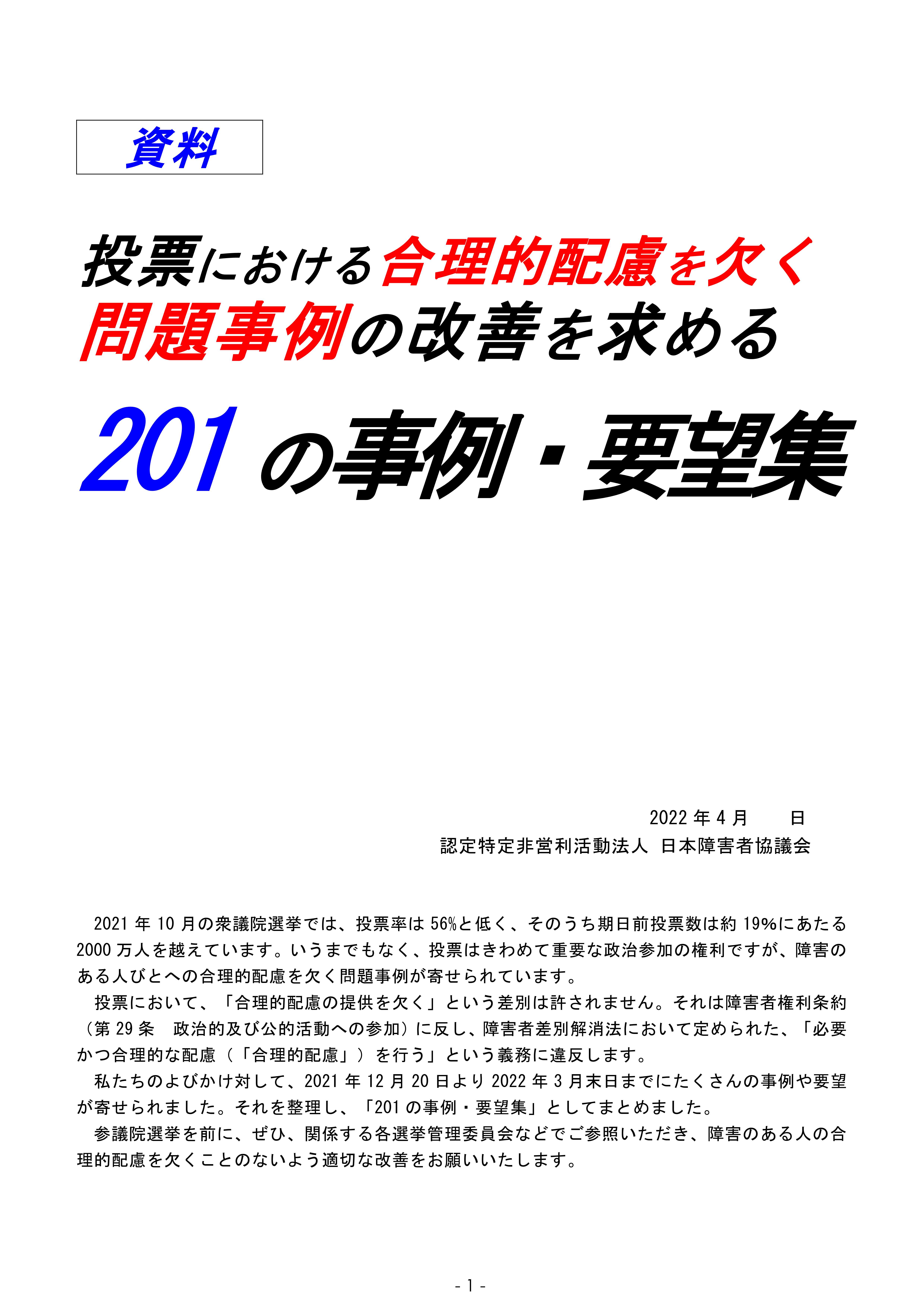
◆参考資料 障害者権利条約 日本政府への総括所見(勧告)
仮訳政治的および公的な活動への参加(第29条)
61.委員会は、懸念をもって次のことに留意している。
(a)障害者の多様性に応じた、投票手続き、施設、資料へのアクセシビリテイが制限されており、また選挙関連情報が不十分であること。
(b)特に障害のある女性にとって、政治生活や行政に参加し、議員となり、公的な機能を果たす上での障壁。
62.委員会は、締約国に次のことを勧告する。
(a)公職選挙法を改正し、選挙放送やキャンペーンなどの選挙関連情報の配慮とともに、投票手続き、施設、資料が、すべての障害者にとって適切でアクセスしやすく、理解しやすく使いやすいものにすること。
(b)障害者、特に障害のある女性の政治生活および行政への参加が促進され、支援機器や新しい技術の使用を促進し、パーソナル・アシスタンス(個別の支援)を提供することによって、あらゆるレベルの政府で効果的に役職に就き、あらゆる公的機能を果たすことができるようにすること。
以下は、こうした動きのはじまりとなったJD(日本障害者協議会)からのよびかけです
JDでは、障害のある人の投票に関して、先の衆院選でもみられた合理的配慮を欠く事例は、国民に等しく保障された参政権を侵し、障害者権利条約第29条(政治的及び公的活動への参加)実現の妨げにつながる重大な問題であるととらえ、問題の改善を国や自治体などに求めていきたいと考えています。国選・地方選での投票における合理的配慮を欠く事例(体験)やご要望を募っています。専用のフォームよりお寄せください。
投票における合理的配慮を欠く問題事例の改善を求めるとりくみにご協力ください
日本障害者協議会(JD)代表 藤井克徳
2021年10月の衆議院選挙では、投票率は56%と低く、そのうち期日前投票数は約19%にあたる2000万人を越えています。いうまでもなく、投票はきわめて重要な政治参加の権利ですが、障害のある人びとへの合理的配慮を欠く事例が寄せられています。すべての投票において、合理的配慮の提供を欠くという差別は許されません。これは障害者権利条約(第29条 政治的及び公的活動への参加)に反し、その実現を妨げるものです。
私たちは、投票における合理的配慮を欠く問題事例を寄せ合い、それを整理し、問題を改善するよう国や自治体などに要請したいと考えます。ぜひ、多くのみなさんにこのとりくみのご賛同をいただき、投票における合理的配慮を欠く問題事例や改善要望をお寄せください。
◆つぎの専用フォームをご利用いただき、
問題と思われる事例やご要望を、2022年2月末日までにお寄せください。
https://forms.gle/t6GbpT4m8QWMugXv6
◆または、以下の内容をメールにて事務局にお寄せください。
①メールアドレス、②お名前、③所属団体名または「個人」、④障害の有・無、
⑤1)情報に関連する問題事例、ご意見/2)投票所の環境などに関連する問題事例、ご意見/3)投票方法、投票用紙などに関連する問題事例、ご意見/4)その他の問題
担当事務局=薗部英夫(JD副代表)、白沢仁(JD理事)、内田邦子(JD理事)、山本忠(立命館大学法学部教授)
連絡先=日本障害者協議会(JD) メール:office@jdnet.gr.jp TEL:03-5287-2346
◆現在寄せられている問題事例や改善要望など
1)情報のバリアフリー
○「期日前」がはじまっているのに「選挙公報」が届かない。「裁判官国民審査」の「公報」はじめ、「期日前投票所」には電子データでの提供含め「選挙公報」を掲示して欲しい。
○選挙公報・選挙通知を点字版・音声版・拡大版、デジタル版、ルビふり版で提供して欲しい。入院・入所中の障害者にも確実に届けて欲しい。
○知的障害のある人へのわかりやすい「選挙公報」が欲しい。
2)投票所の環境などに関するバリアフリー
○低床の投票記載台で「イスに座って記入したい」と希望しても「車いす専用です」と断られた。投票用紙に安心して記入できる場所を確保して欲しい。
○カラーユニバーサルデザインに基づく投票箱の色分けや誘導矢印表示が欲しい。
3)投票方法、投票用紙などに関するバリアフリー
○原則自書のみとする公職選挙法第46条が、自書の困難な障害者の投票権の行使を妨げている。
○「裁判官国民審査」用紙のマス目はめちゃくちゃ狭く、不随運動がある人には記入困難。
○視覚障害者は、審査で×をつける場合は、一人一人の裁判官の名前を、自らが点字で打ち、バツ(×)を打つ。投票方法を改善して欲しい。
○代理投票について、補助者を投票所事務員に限定する公職選挙法が、通訳介助者を介して自らの意思を伝える必要がある盲ろう者や、自らの意思を家族・支援者に対してであれば伝えられる障害者の投票権の行使を妨げている。自らが選んだ同伴者による代理投票を実現して欲しい。
4)その他の問題
○フィンランドではすべての病院で投票をやらなければならないという法がある。より身近な場所でもできるように施設・病院等に移動投票所を開設して欲しい。
○「筋ジス病棟で暮らしてます。期日前投票を代理投票で投票しました。代理記載人の管理課員に、指さししてもらって投票しました。立会人には投票内容が知られないようにするためカーテンの外で立ち会ってもらいました。他所ではどうしているか知りたいです」(大分・筋ジス患者)。
○障害者手帳取得が非常に困難で、障害者総合支援法の対象にもなっていない難病の人には、投票所まで歩いて行くことができなくても車いすは支給されず、期日前投票することもできない人がたくさんいる。改善して欲しい(筋痛性脳脊髄炎の会)
◆参考資料 障害者権利条約第29条 政治的及び公的活動への参加
締約国は、障害者に対して政治的権利を保障し、及び他の者との平等を基礎としてこ
の権利を享受する機会を保障するものとし、次のことを約束する。
(a)特に次のことを行うことにより、障害者が、直接に、又は自由に選んだ代表者を通
じて、他の者との平等を基礎として、政治的及び公的活動に効果的かつ完全に参加する
ことができること(障害者が投票し、及び選挙される権利及び機会を含む。)を確保す
ること。
(i)投票の手続、設備及び資料が適当な及び利用しやすいものであり、並びにその理解
及び使用が容易であることを確保すること。
◆参考資料 障害者権利条約 日本政府への総括所見(勧告) 仮訳
政治的および公的な活動への参加(第29条)
61.委員会は、懸念をもって次のことに留意している。
(a)障害者の多様性に応じた、投票手続き、施設、資料へのアクセシビリテイが制限されており、また選挙関連情報が不十分であること。
(b)特に障害のある女性にとって、政治生活や行政に参加し、議員となり、公的な機能を果たす上での障壁。
62.委員会は、締約国に次のことを勧告する。
(a)公職選挙法を改正し、選挙放送やキャンペーンなどの選挙関連情報の配慮とともに、投票手続き、施設、資料が、すべての障害者にとって適切でアクセスしやすく、理解しやすく使いやすいものにすること。
(b)障害者、特に障害のある女性の政治生活および行政への参加が促進され、支援機器や新しい技術の使用を促進し、パーソナル・アシスタンス(個別の支援)を提供することによって、あらゆるレベルの政府で効果的に役職に就き、あらゆる公的機能を果たすことができるようにすること。
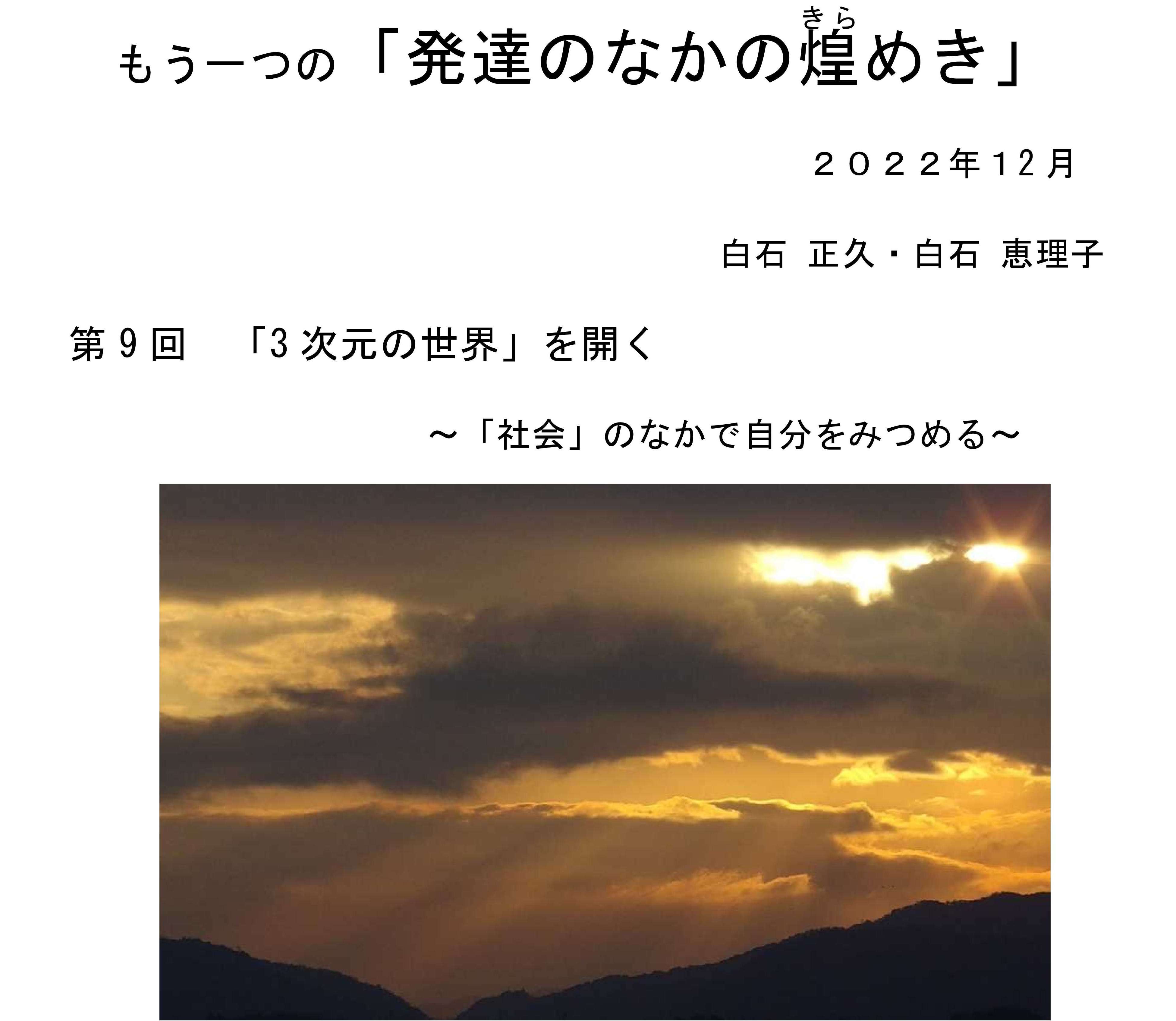
日本海から雲が流れこむ近江盆地。糸賀一雄は、冬の琵琶湖に故郷の夕景を思い出すと言った。雲間から射す光に、やがて来る陽春を想ったのだろう。そのころ糸賀は、職場のなかにも光のあることを見出していた。
はじめに
『みんなのねがい』の連載「発達のなかの煌めき」(以下では「連載」)は、第9回に入りました。テーマは、「『3次元の世界』を切り開く―仲間とともに『だんだん大きくなる』」です。
「もう一つの『発達のなかの煌めき』」(以下では「もう一つ」)では、田中昌人さんらの「可逆操作の高次化における階層‐段階理論」に依りながら、それぞれの発達の「階層」とそのなかにある3つの「段階」について解説してきました。
幼児期の発達の階層である「次元可逆操作の階層」の第3段階が「3次元の世界」です。そこでは「3次元可逆操作」を獲得していくのですが、「連載」第9回はその形成期となる「3次元形成期」について、以下のように解説しました。(『新版教育と保育のための発達診断 下』「Ⅱ‐第6章 5~6歳の発達と発達診断」も参照してください)
「3次元の世界」とは、「7歳の節」である「3次元可逆操作期」と、その準備期である「3次元形成期」(5歳後半~6歳)のことです。それまで「大きい‐小さい」などの対比、比較で世界を捉えていた子どもが、「だんだん大きくなる」に象徴されるように、「大きい」「小さい」だけではなく、「うんと大きい」「ちょっと小さい」さらには「中くらい」といった間(あいだ)をさまざまに捉えて、ものごとを細やかに、すじ道だてて理解するようになっていきます。だから、「きのう・きょう・あした」「遠いところ・中くらいに遠いところ・うんと近いところ」などと時間や空間を区別と連続(つながり)において捉え、ものごとを「好きなところもあるけれども、嫌いなところもある」というように多面性や客観性をもって理解をするようになるのです。この認識は、自分自身へも仲間へも向けられ、お互いが「だんだん大きくなる」ことが嬉しくなるのでした。
「2次元の世界」から「3次元の世界」への発達の変化は、外界にある関係をとらえる変数が「2つ」から「3つ」へと一つ増えるだけではありません。「3次元形成期」は、9歳での学童期の「階層」(「変換可逆操作の階層」)への飛躍のための力である「生後第3の新しい発達の力」が誕生するときです。
発達の道すじを振り返ると、乳児期後半の「連結可逆操作の階層」に飛躍するための「生後第1の新しい発達の力」は4か月頃、幼児期の「次元可逆操作の階層」に飛躍するための「生後第2の新しい発達の力」は10か月頃に誕生します。この第1と第2の「新しい発達の力」について、『新版 教育と保育のための発達診断 上』の「Ⅲ‐第1章 乳児期の発達診断と発達保障」の68~69ページで解説しています。そこでは、第1と第2の「新しい発達の力」の誕生に共通することを、以下のようにまとめました。
① 「新しい発達の力」の誕生のときは、次の発達の階層で主導的な役割を担うコミュニケーション手段(4か月頃は「人しり初めしほほえみ」など、10か月頃は「はじめてのことばや指さし」など)が芽生えるとともに、その手段を必要としそれが意味をもつ人間関係が形成される。
② その関係はおとなだけではなく、仲間(友だち)を意味ある存在として意識し、憧れや葛藤を経験しつつ、互いの結びつきを確かにしていく。
③ 新しい発達要求とそれを実現しようとするための矛盾が生まれ、子どもはその抵抗に立ち向かうために、自らの機能・能力を制御・調整しながら、活動の主人公に生まれ変わろうとする(4か月頃は対象への手指のリーチングなど、10か月頃は抵抗を乗り越えての目標への移動など)。
さて、「生後第3の新しい発達の力」の誕生する「3次元形成期」は、どんな特徴をもっているのでしょうか。
「3次元の世界」(3次元可逆操作の獲得)とは
「3次元の世界」の開き方について、「連載」ではシゲちゃんの発達によって解説しました(白石正久『発達とは矛盾をのりこえること』「集団のなかで子どもは育つ」162-170ページを題材としています)。「連載」は、読者の皆さんの集団での議論を通じて子どもやなかまの理解が深まることをねがい、あまり説明的にならないようにしています。とくに第9回では、「これは具体的にどういうことなのだろう」と、読者の皆さんが疑問に思われることが多かったと思います。その行間を解説していくことが、今回の「もう一つ」の役割です。
・過去や未来への時間軸ができはじめ、そこに自分を位置づける
「ラーメン大好き」なシゲちゃんが憧れをもち、未来へ開かれた時間のなかに社会との接点をみつけて、「ラーメン屋さん」になる自分をイメージしているのがよくわかりました(27ページ、2段目)。
「4歳の節」(「2次元可逆操作期」)を越えていく頃、「ずっと前に、…したな」「きのう、…だったな」などと過去の経験に依拠して語り、「あしたは、…したい」「お休みの日は、…行きたい」などと未来への見通しのなかでねがいを語るようになります。まだ「3次元形成期」のように「きのう・きょう・あした」「きょねん・ことし・らいねん」「きょう・あした・あさって」などと、確かな3つの単位を内包した時間軸の形成には至りませんが、自分の経験の範囲内で過去と未来と現在の間を行き来しながら、自分のことを考えられるようになるのです。
とくに、未来に開かれた認識は、「期待」という感情と結びついたときに、ねがいや目標を実現するためにどうしたらよいのか、一人ではできないことを仲間にどう語り、どう力をあわせていくかを考えたり、語りあう力になります。だから「走り縄跳び」がじょうずになりたくて、夕闇迫るなかで練習したりします。発表会や運動会などの行事では、やりたいことを出しあい、自分たちでテーマや段取りを考えようとするのです。
シゲちゃんは、「3次元の世界」が開くとき、未来に開かれた時間のなかに自分を置き、自分なりの「社会」のなかで「ラーメン屋さん」という大好きなことを結びつけて、夢を抱き始めていたのでしょう。夢と希望、つまり未来ヘの志向性を育んでいくことも、教育や保育の大切な課題となります。
・「ちがう」と「おなじ」を一つの事物・事象のなかに見出す
相撲は本気で勝ちたいのですが、ときどきKくんを勝たせているような姿もありました。そんなとき「Kくん、強くなったなぁ」と優しい目で見つめているのでした。Kくんのねがいがわかり、それをいっしょに叶えたかったのです
(27ページ、2~3段目)。
シゲちゃんのように「2次元可逆操作期」にある子どもの場合、外界や自分を対比的にとらえる認識によって「勝ち‐負け」がわかり、勝敗のある遊びを楽しむようになります。勝てばうれしいのですが、負けたことを受け入れられず、大泣きすることもあるでしょう。
シゲちゃんも、もちろん相撲は勝ちたかったのです。でも自分よりもからだの小さいKくんと相撲をしていると、Kくんも勝ちたいと思っているし、勝ったときには本当にうれしそうな顔になることを知りました。対比や比較という認識の特徴をもっている「2次元可逆操作期」は、「ちがい」を認識していくことが優位になるのですが、交流を通じて仲間にも自分と「おなじ」に、勝ちたい、勝つとうれしいという感情があることを知っていきます。そういった共感によって、「いっしょに頑張って機能訓練したから、だんだんこけへん(転ばない)ようになったな」とお互いのことを誇らしく感じられるようにもなっていきます。
物事に、「ちがい」と「おなじ」があることを理解することは、「りんご」と「みかん」は「ちがう」けれど「くだもの」として「おなじ」だというように、上位の概念を形成し言語の認識を豊かにしていく土台になります。そういった認識が個人のなかで可能になるだけではなく、自分と他者、自分と仲間の関係においても、ねがいや感情に「おなじ」があることを知っていくことによって、互いを大切にできる人格として発達することができます。「サトちゃんは、赤ちゃんが産まれるんでお母ちゃんが入院しはった。さびしいやろな。晩ご飯いっしょに食べてもいい?わたしもお母ちゃんが入院したときにさびしかった」などと思いやりをもって友だちのことを想像します。また、口げんかしている仲間を見つけると仲裁に入って互いの思いを聞き取り、心が「おなじ」になって仲直りできるように、折りあう手がかりを探すようにもなります。「連載」第10回(1月号)では、「ちがい」をくぐって「おなじ」に気づくことについて、解説する予定です。
さて、シゲちゃんにとって、Kくんは「小さい」ゆえに大切にしたい思いをもてる友だちでした。そういった「大切にしたい」思いをもてる友だちを求めるのも、「3次元の世界」を開きつつある心です。
・「書きことば」の土台は、すじ道立てて考え文脈を形成すること
その頃、シゲちゃんにはむずかしかった「小さな丸からだんだん大きくなるように丸をたくさん並べて描いてください」という「円系列課題」(『新版 教育と保育のための発達診断 下』、115ページ)で、途中で丸が小さくなってしまうことはあるのですが、気づいて書き直すようになっていきました。「だんだん大きく」などという活動の規準枠(テーマ)を忘れずに、活動をつなげていくことができるようになったのでしょう。「三次元の世界」を開きはじめたのです(28ページ、3段目)。
「だんだん大きく」を理解しながら、丸を描きつなげていくことができるのが「円系列課題」です。活動の規準枠(テーマ)とは、それを認識しながら活動をつなげたり、調整していくことです。集団活動の約束事、ルール、理解すべき状況も、この規準枠にあたるものです。
「書きことば」は、「伝えたいこと」をテーマとして意識して、文字とことばを選びながらそれをつないで構成されるコミュニケーション手段です。「読み書き」能力が、それだけで「書きことば」になるのではなく、実は「話しことば」で「お話」をつくることの豊かさ、確かさが基盤にあると言えるでしょう。
「お話」には、「伝えたいこと」が認識されて、その伝えたいことをテーマとして言葉を探し、つないでいくという過程があります。5歳児が、「あのね、えーとね」「ほんでな、あんな」を多用して「お話」をしてくれるときには、そのトツトツとした展開に、おとなはしびれをきらして、急かしたり遮ってしまうこともあるでしょう。「あのね、えーとね」は、言葉を探す子どもの一歩一歩の頑張りの表現です。私たちも子ども時代のことを思い出してみると、伝えたいことを自分の言葉で表現でき、聴いてもらえたことが、どんなにうれしかったことか。
また、その「お話」をする喜びが、ときに現実を越えた作り話になってしまうこともあります。「あんな、散歩でな、大きなトラックがビュンビュン来たねん。風がビューと吹いて、子どもはみんな魔女みたいにな、飛ばされたねん」。「うそ」を言っているのではなく、お話ししたい思いが余り、言葉をつなげられることもうれしくて、調子のよい「お話」を作ってしまうのでしょう。きっと文脈を形成していくための準備運動をしているのです。
また、シゲちゃんの「マラソンしたこと」の作文のように、テーマから離れて「ミシン縫い」になったり、気づいて元のテーマに戻ったり、でも本当に伝えたいことは「ミシン縫い」だったので、それで話を一気に結ぶという脱線の繰り返しは、よくあることです。「伝えたいこと」があるからこそ、その思いの丈が文脈を作る牽引車になっていくのです。
10か月頃、「話しことば」の獲得期である「1歳半の節」を乗り越えていくための「生後第2の新しい発達の力」が誕生すると、「何ごとも不思議と思う心」によって、見つけたものを指さしで教えてくれます。そのとき、おとなや仲間はそれを同じ目の高さで共感・共有する存在でした。同じように、「書きことば」の獲得期である「9歳の節」を乗り越えていくための「生後第3の新しい発達の力」が誕生すると、子どもの「社会」のなかでの伝えたい生活の事実を我がことのように受けとめてくれる存在が、3次元のつながりと広がりをもった文脈の形成を支えることになるのです。そこでは、子どもたちが力いっぱい主客を転倒させて、コミュニケーションの主人公になっていきます。
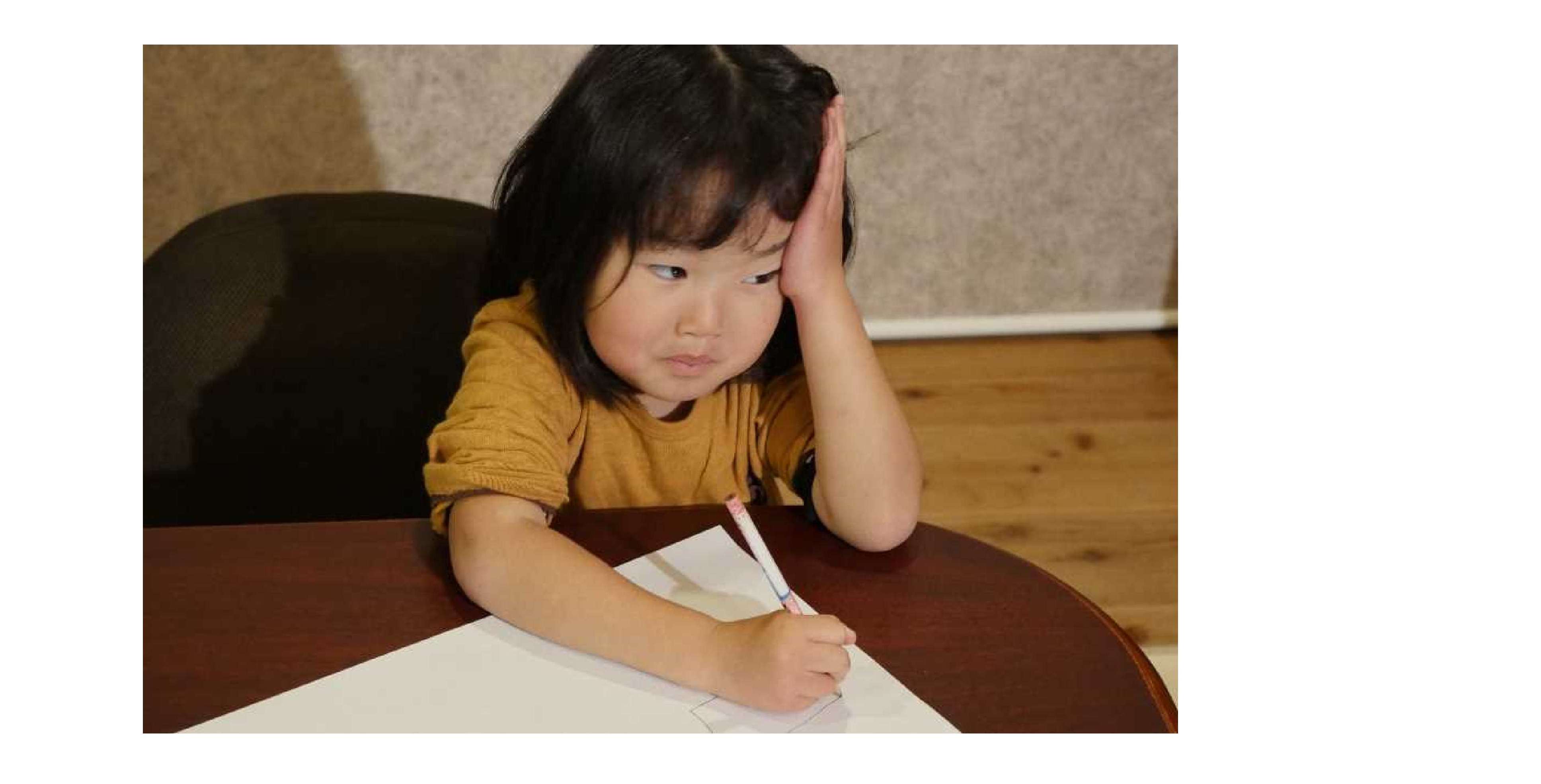
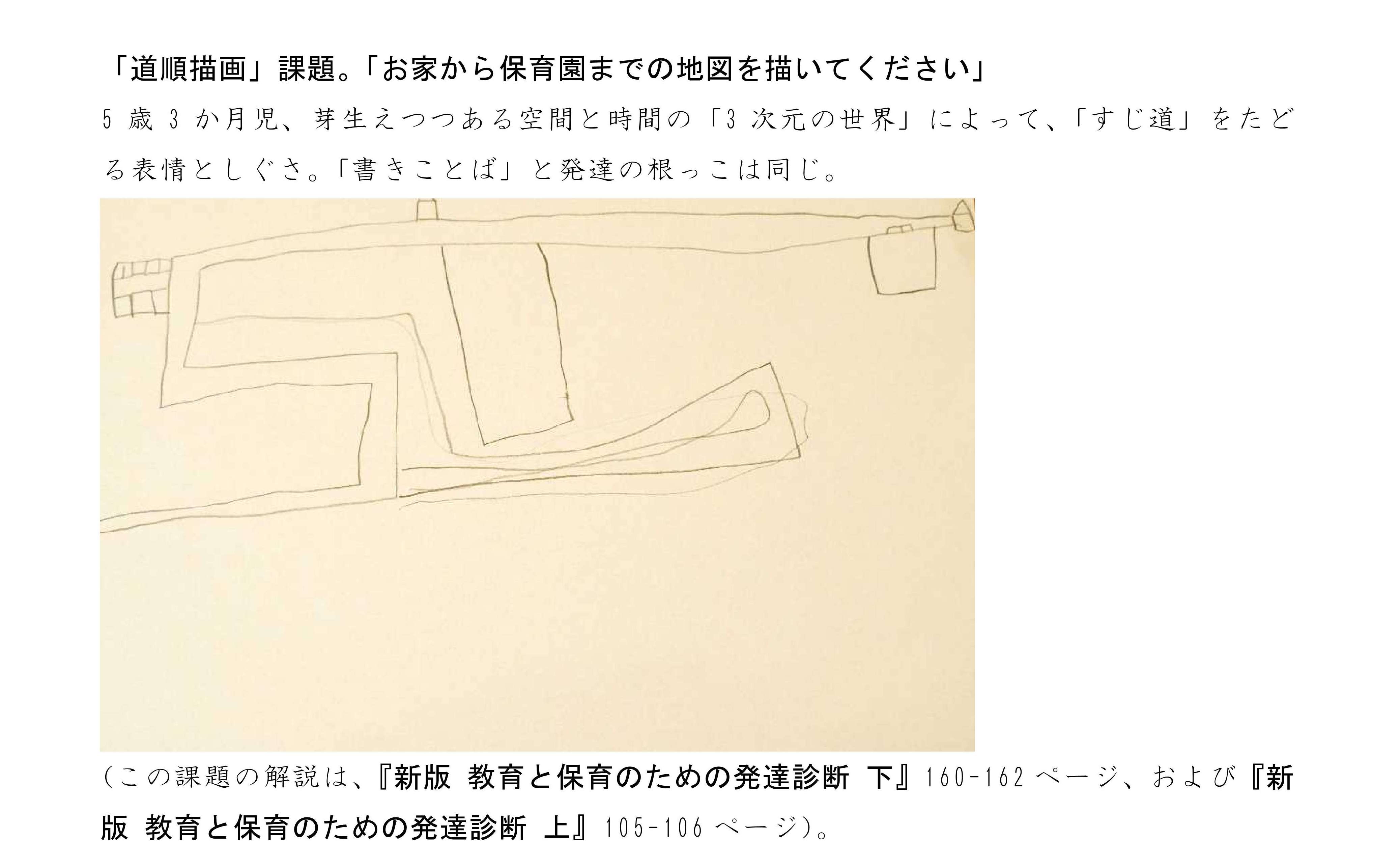
・仲間・社会とつながって、「書きことば」は人格の発達へとむすびついていく
「ぼく、へたやから」の日々があったから、「うれしくてうれしくて」は真実の言葉になりました。「こん度もがんばります」には新しい発達のエンジンが備わったことが暗示されていました(28ペーシ、1段目)。
「ぼく、へたやから」という言葉には、シゲちゃんの自分の現実と向きあう苦しい心が表現されていますが、ただ立ちどまっているのではなく、なんとかその現実を乗り越えていきたいという思いが隠れているようでした。子どもには、いつも「よくなろう、よくなろう」という言葉にならない思いがあります。自暴自棄に聞こえる言葉も、他者へのいら立ちの言葉も、その背後の本当のねがいを受けとめてもらったときに、発達の矛盾を乗り越えて「うれしくてうれしくて」にいたることができるのです。シゲちゃんは、その矛盾を乗り越えたことが自分への信頼につながり、ちょっとむずかしいことにも挑戦しようとする「新しい発達のエンジン」を始動させることができました。そしてそのことを、「こん度もがんばります」と表現しました。シゲちゃんにとって、この「新しいエンジン」は、「生後第3の新しい発達の力」の誕生だったのでしょう。
「うれしくてうれしくて」は、シゲちゃんの「ミシン縫い」を励まし、その雑巾を喜んで受け取ってくれた仲間へのメッセージでもあります。「書きことば」で表現された「伝えたいこと」には、それを伝えたくなる他者がいます。とくに、「話しことば」で伝えられない目前にいない他者や、複数の他者に対して、その思いを伝える役割を担ってくれるのです。そこには、読み手の側に視座を移して、相手の心情を想像する力が求められます。
こういった「書きことば」の獲得を、個人のなかの「閉じた」文脈の耕し方ではなく、他者と心でつながった「開いた」文脈の耕し方として指導していくことの大切さを、『新版
教育と保育のための発達診断 上』「Ⅲ‐第4章 7歳の発達の質的転換期と発達保障」で川地亜弥子さんが論じています。そこでは、障害児保育の開拓者であった大津市の「つくし保育園」の70年代前半の保育実践が、田中昌人さんの『復刻
講座発達保障への道 第1巻』での論評とともに紹介されています。育ちあった友だちの入院生活への激励を込めて、そして卒園旅行でお世話になった民宿の「おばさん」への感謝を込めて、みんなで力をあわせて文字を拾い、文脈を作ろうとする「共同の事業」としての「書きことば」の獲得が描かれています。「読み書き」がうまくできるかどうかではなく、仲間・社会と結合して、手をつなぎあって発達していこうとするヨコへの広がりを内にもった言葉が「書きことば」なのです。
この田中昌人さんの『復刻 講座発達保障への道 第1巻』は、「3次元の世界」の開き方を学ぶための格好のテキストとなるでしょう。
・「二分的評価」を乗り越えた自己形成のねがい
二分的評価にとらわれていたシゲちゃんの自分へのイメージが、できないこと、へたなことはあるけれど、友だちと思いやねがいを共有して頑張り、その頑張りをみんなに受けとめてもらえる、新しい次元の自分へと変化していったのです(29ページ、1段目)。
シゲちゃんが、養護学校(当時)中学部の体験入学で目にしたのは、自分と向きあい「ぼく、へたやから」と言わざるをえない自分とはちがい、思いを共有して、そのために活動している集団の姿だったのです。仲間とともに新しい価値を「生産」している、つまり「おしごと」している姿だったのでしょう。
「二分的評価」やいわゆる劣等感は、簡単に消えてなくなるわけではありません。「3次元の世界」では、苦手意識や自分の不器用さへの思いはもちつつも、自分と向きあうだけではない、それを越えて、仲間との小さな「社会」のなかに自分を位置づけていこうとするのです。そしてその「社会」のなかで、自分の受容感や存在の意味の実感をもてるようになっていくことが、「3次元の世界」の「新しい次元」の自己認識なのです。それは「できる‐できない」「じょうず‐へた」という自分への「二分的評価」を乗り越えながら、「社会」にあって「こうありたい」という自己形成(自分づくり)へと視野を広げていくことです。
「4歳の節」にある子どもは、対比や比較によって、特別支援学校や学級に通う自分のことを否定的に感じがちです。さらに「3次元の世界」が開くと、視座を自分から「社会」の側に移して、客観的に自分のことを認識するようになっていきます。他者から「特別支援学校は、頑張っている子どもたちの学校です」と言ってもらっても、この認識は簡単には塗りかえられません。子どもたちが求めているのは、この学校、学級が、どんな素敵なところなのかを、自分の実践を通じて文字通り実感していくことです。その実感は、シゲちゃんの「うれしくてうれしくて」に込められているように、仲間と互いを認めあい「だんだん大きく」なってきた自分たちへの誇りによるのだと思います。
子どもやなかまは、属する集団のありようによって輝きます。そのキラキラ輝く集団では、教師も、保育者も、作業所の指導員も、ともに輝いていることでしょう。その実感がもてないときには、職場の仲間と語りあい学びあって、おとなの側のしんどさの理由を考えましょう。自分たちの輝きを取り戻していこうとする知恵と意志が集まれば、苦しいことも乗り越えていけると思います。
第3回「発達のなかの煌めき」執筆者交流会(Zoomでのオンライン)
12月10日(土)13~15時に迫りました。そっと耳を傾けていただくだけの参加も大歓迎です。「連載」第9回(12月号)29ページでご案内しています。
参加申込み https://forms.gle/RHm9HwuWJa3PcB6Q7
今回の学習参考文献
・田中昌人(原著1974、復刻2006)『復刻 講座発達保障への道 全3巻』全障研出版部
私たちは学生時代に何度も、新書版であった『講座発達保障への道 全3巻』をサークルや研究室の仲間とともに学びあいました。田中昌人さんが1970年創刊の『みんなのねがい』に連載していた「発達保障への道を力強くすすもう」を単行本化したものです。
「書きことば」獲得期にある5歳児(第1巻、32-70ページ)
「笑顔」の獲得期にある3,4か月児(第2巻、176-194ページ)
「話しことば」獲得期にある1歳児(第3巻、142-200ページ)
以上の発達要求についての解説は、単なる発達論ではなく、発達の原動力を子どものなかに探求しない非科学、実践における個人主義を批判し、民主的な集団のなかでこそ子どももおとなも育つことが語られています。この部分は、平易な記述になっています。
全障研の「みんなのねがいWEB」の「オンラインショップ」で、学習のための特別な頒価で購入することができます。
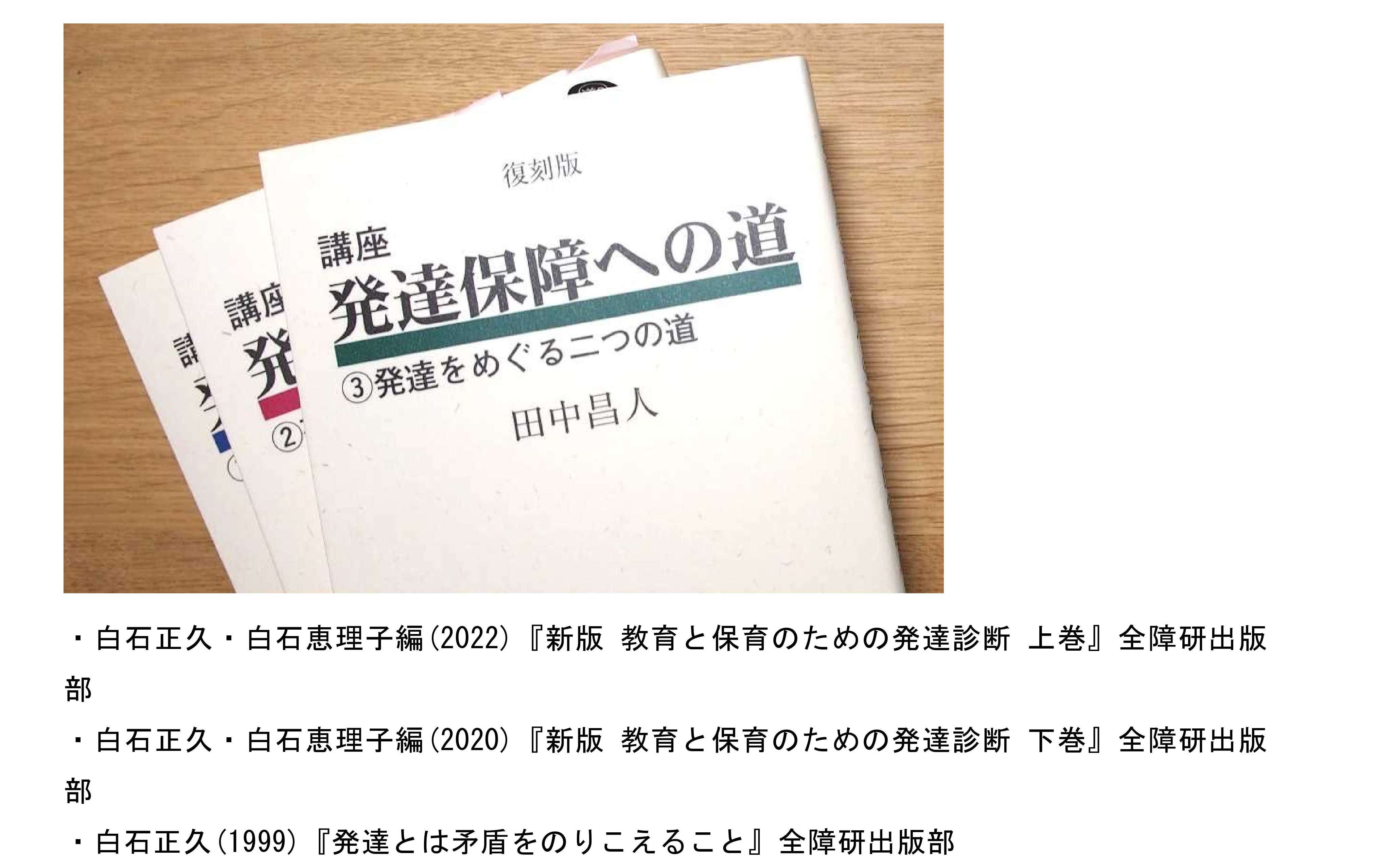
「障害者問題研究」50巻3号
特集=障害者の防災・災害福祉の到達点
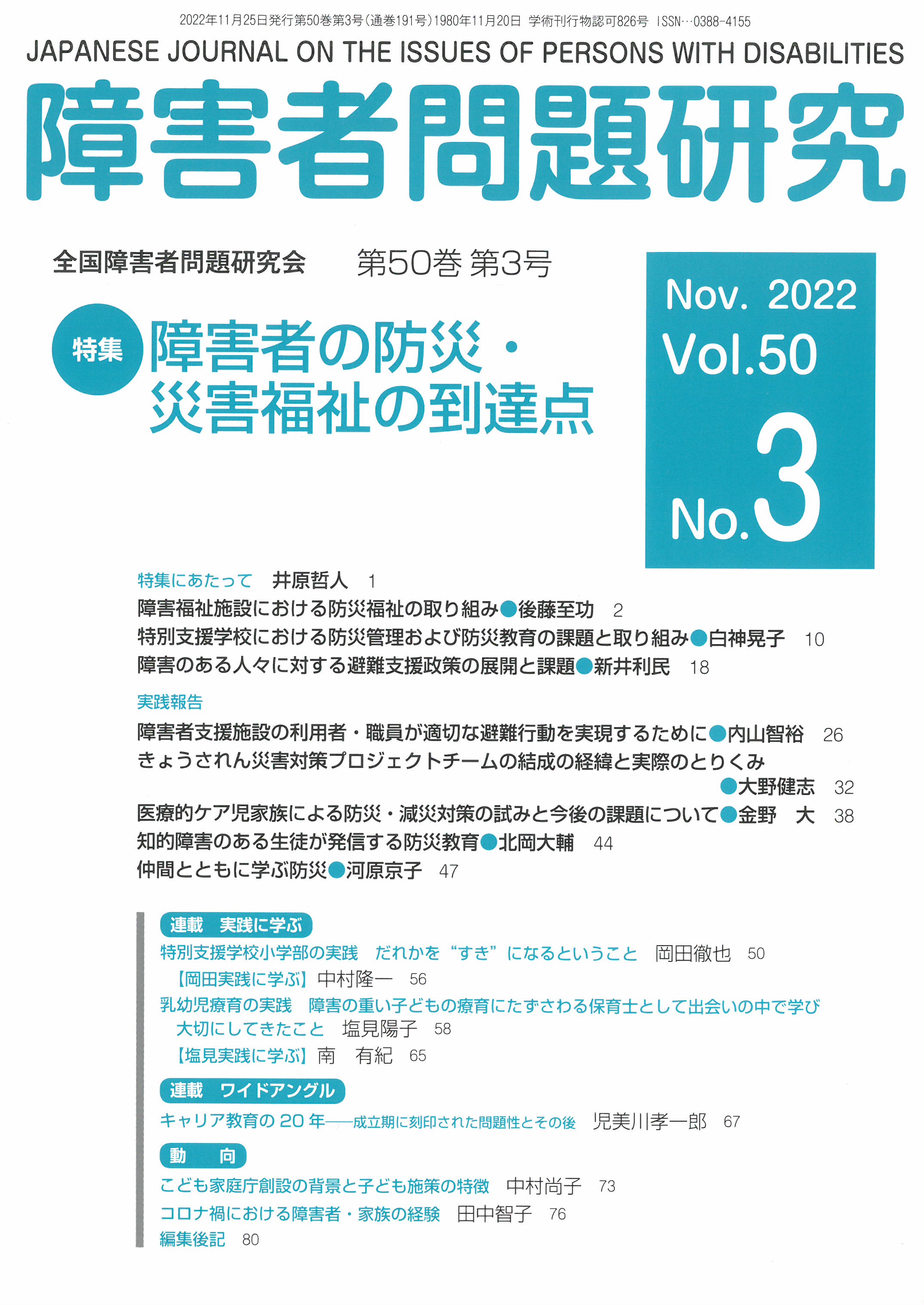
必ず起こる東南海地震。地球温暖化によって多発する水害。そのとき、私たちはどうしたらよいのでしょう。政策としては地域福祉に災害福祉が位置づけられ、防災・減災のための計画づくりや地域連携を求めています。改定災害対策基本法や災害時要援護者の避難支援ガイドラインに目配りし、自治体や地域コミュニティで障害児者が取り残されない取り組みが必要です。障害のある人が隅に追いやられることなく、「助けてやる」と無理やり引き回されるのでもなく、社会の成員として尊重され、いのちを守り暮らしの継続が図られる営みに「発達と権利」が貫かれる、そんな災害福祉をつくりあげるために、まずは、この到達から学びたいと思います。不十分な条件下で障害のある人の命を一身に負わざるを得ない家族や現場の経験(コロナ禍のもと現に進行中の経験に通います)や願いを、しっかり形にしなければなりません。
詳細案内 「ちょっと見」やオンラインでのご注文は以下のホームページへ
▶「障害者問題研究」50巻3号 特集=障害者の防災・災害福祉の到達点
▶「読む会」情報
12月16日(金)19時~21時
詳しくはPDFを参照ください
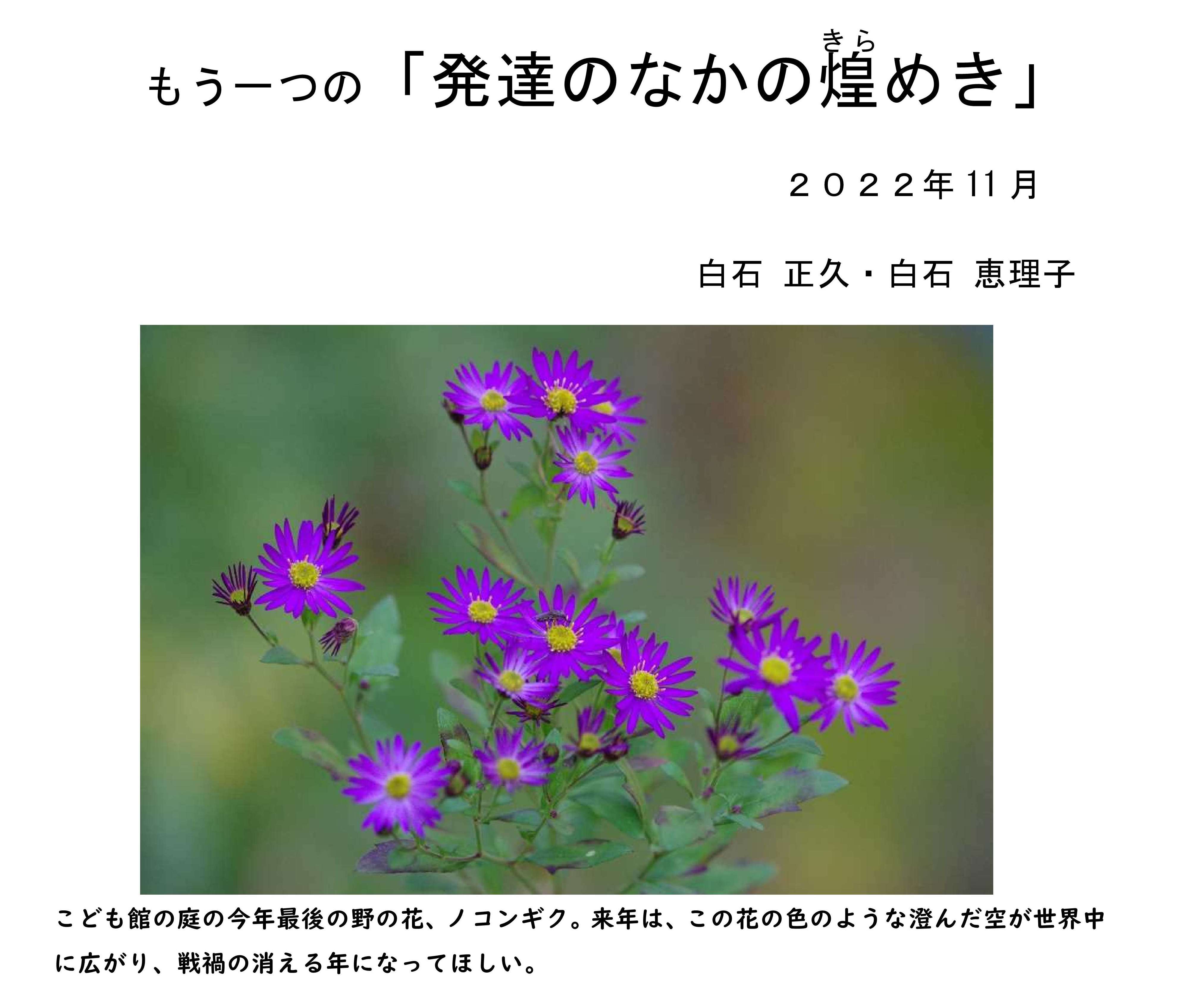
第8回 誇りある自分を育んでいく発達の土台
~「2次元可逆操作」の豊かな世界~
はじめに
10月23日の「教育と保育のための発達診断セミナー」にご参加されたみなさん、ありがとうございました。冒頭での私たちのご挨拶を、ここに掲載いたします。
******
発達診断セミナーにご参加くださり、ありがとうございます。
2009年に刊行された『教育と保育のための発達診断』をテキストに多くの方たちと学習・研修をすすめ、そこでの気づきをもとに全面改訂に着手し、2年前には「下巻 発達診断の視点と方法」を、そしてこの夏、「上巻 発達診断の基礎理論」を発刊いたしました。
本日、ご参加くださったみなさんの多くは、保育や教育の現場で子どもたち・なかまたちに日々よりそいながら実践し、そのなかで子どもの発達をとらえたい、発達診断の実際を学び、自分でもやってみたい、あるいはその知見を日々の実践に生かしたいと望んでいらっしゃることと思います。そうしたご要望に対し、下巻では、各時期の発達診断課題とその見方について説明し、保育・教育の課題は何かについて述べました。それに対し、上巻でとりあげた国際動向や歴史は、少し敷居の高いものかもしれないと思っています。しかし、子どもやなかまの発達を理解し、実践を創造していくうえで、人間が幸福に生きる権利がどのように深められ発展してきたのか、理論も実践の蓄積もない時代に、先人たちは目の前の「この子」たちにどう手探りで向きあい、仲間といっしょに実践を創り上げてきたのか、その歴史を知ることは、私たちにとって貴重な羅針盤です。その経過のなかでは、支援者としての見方からいったん離れて、何度も何度も「この子」たちが何を感じ、何に心を動かし、何に悩み、何を願っているのかに視座を移して考えてきたのだと思います。それはときに自分自身とも向きあわざるを得ないことでもあったと思います。しかし、子どもたちとの発達的共感関係のなかで力をもらい、支援者としての自分をも発達させてきたのではないでしょうか。
先日、『みんなのねがい』の読者の方からお便りをいただきました。
「『みんなのねがい』を購読させていただいております。少しずつ言葉のなかに込められた『ねがい』に心がふれて、景色や日常に変化を感じております」。
景色や日常が変わってきたという言葉を本当にうれしく思います。子どもたちとの日常のこと、そしてそこにある風景を、景色にたとえられているのだと思います。発達の大切なことは、遠くにあったり、何かに隠れてしまったり、あるいは小さくてよく見えないことがあります。だから、行動の背後にある心、生活の困難、感情や人間関係の機微など、奥行やディテールを、見落としてしまうことはあるものです。
私たちもそうでした。連載で取り上げている事例や実践は、私たちが20年、30年前に出会い、どこかで紹介してきたものです。しかし、その時点では、みえていないことがたくさんありました。私たちも、自身
の発達とともにだんだんとみえるようになってきた、つまり景色が変わってきたのです。連載では、そのことを正直に書こうと思っています。
ぜひ、今日のセミナーでの学びとあわせ、テキストや『みんなのねがい』連載「発達のなかの煌めき」を職場や地域の仲間と読みあってください。語りあい、わかちあい、知恵を出しあい、試行錯誤しあっていく、そして自分自身に問い続けていく…そのたゆまぬ道行きのなかでこそ、明日への展望が見いだされていくのだと確信しております。
******
さて、連載11月号、前回の「もう一つの『発達のなかの煌めき』」では、「4歳の節」すなわち幼児期の階層の第2段階である「2次元可逆操作期」についてみてきました。今回は、この「4歳の節」について、もう少し深めていきましょう。まずは生活年齢と発達の関係について、次に連載第1回でのリョウちゃんのことを、ふたたび取り上げたいと思います。
かずえさんの歴史に学ぶ ― かけがえのない日々の値打ち
子どもたち・なかまたちの発達を理解するときに、発達年齢や発達段階だけでなく、生活年齢やライフステージという観点を忘れないことの重要性は言うまでもありません。ただ、それらは、両者を合算したり、何らかの方程式に入れたら答えが出てきたりするようなものではありません。私たちは、発達年齢や発達段階をおさえることは、その人のかけがえのない歴史、生きてきた日々のもつ値打ちをきちんと照らし出すうえでも大切なことだと考えています。もちろん、社会や教育のありようや課題を明らかにするうえでも必要だと言えるでしょう。
「4歳の節」を迎えると、日々の実際のくらしや人間関係のなかで、「自分で決めたい」「自分が手伝ってあげたい」と今まで以上に自分が行為や認識の主体であることを意識し、そのうえで「自分でできてうれしかった」「自分は悔しかった」等々、自分の感情をも対象化していき、誇りある自分を育んでいく発達的土台ができていきます。それはまた、他者のなかにある「自分」に気づくことにもつながります。したがって「4歳の節」の時期にある人のライフステージを考えるときにも、この視点は重要です。
長年、滋賀県のあざみ寮で暮らしてきたかずえさんのことを田中昌人さんが語っています(「自制心の普遍化による自治能力の発生」 人間発達研究所編『青年・成人期障害者の発達保障3 集団と人格発達』1989)。かずえさんは10歳であざみ寮に入寮しましたが、ちょうど「大きい‐小さい」がわかりかける「2次元形成期」の入り口にあったようです。何事にも意欲的であった一方で、注意されるとカッと怒ってしまいやすかったかずえさん。その後、なかまたちと一緒に様々な造形活動や学習にとりくみ、「2次元の世界」を豊かにしていきます。
そして、2次元可逆操作の獲得という発達の質的転換期が、思春期というライフステージの質的転換期に重なって訪れます。さらに、20代に2次元可逆操作を充実させていくのですが、「吃音がきつくなったり、ヒステリーが出てきたり、心臓障害が顕著になってきたり」したとのことです。彼女の初潮は20歳を過ぎていたのですが、友だちには生理があるのに自分にはなかなかこないことで大騒ぎを繰り返す日々でした(このときのことは、石原繁野さんが詳しく書いています)。自分の身体の変化に敏感になる思春期から青年期において、かずえさんは「自分」をみつめていったのでしょう。なかまがいるからこそ、なかまと比べてしまうことによる不安が彼女を苦しめます。しかし、その不安を一人ぼっちのもの、一人ぼっちで乗り越えなければならないものにするのではなく、みんなで見守ります。そして待ちに待った生理が訪れたことを皆で喜び合い、かずえさんは満足そうに、少し恥ずかしそうに「ありがとう」と答えます。田中昌人さんは、そこには、生活のなかの一つひとつのことがらを共同の喜び、共同の財産にできるような豊かな教育的人間関係を築いていった実践があったと述べます。
30代には心臓の手術を受けるのですが、そのときの担当医はかずえさん本人に、彼女にわかりやすい伝え方で手術のことを話します。「病気だから手術」なのではなく、「元気になりたい」「みんなと一緒に暮らしたい」、だから手術を受けるのだという、かずえさん自身のねがいとすじみちにつくりかえる社会的関係がありました。手術後のかずえさんは、人との関係においても、アーティストとしても、一層の輝きをみせるようになりました。
かずえさんは66歳で亡くなるのですが、その晩年の様子を、張貞京さんが昨年度の『みんなのねがい』の連載(2022年1月号)で書いています。
「亡くなる2年ほど前からのかずえさんは、老いや死に強い不安を見せるようになります。…徐々に体力的な衰えが目立つようになり、手のふるえが増えていき、自分の手を見つめながら、…『なんでかな』『ふるえるの』『食べられないの』と話します」
さらに怖い夢を見るようになったかずえさんは、石原さんに相談し、そのことを張さんに語ります。「石原先生言ってた。(先生も)怖い夢が多いって言ってた」。そして、石原さんから、怖い夢を見ないようにお願いの手紙を書いてみたらと勧められたかずえさんは「かみさま こわいゆめを みないように おねがいします」と書いた手紙を枕元に置いて寝るようにしたと、安心した表情で話したそうです。
「死への不安と向き合うために自分でできることを探し求めたかずえさんの想いと、かずえさんができることを共に考えた石原さんの提案からは、老いや死の不安への慰めだけではなく、本人のできることを共に考えることが大切であると感じています」
そして、新しい仲間がむすび織体験をした日、「直前まで手のふるえや不安を語っていたかずえさんが、穏やかにやさしく言葉をかけながら結び方を教え、それまで激しくふるえていた手は、しっかりとむすび織の機と次に使う材料を持っていたの」だそうです。(さらに、張貞京「4歳の発達の質的転換期と発達保障」『新版・教育と保育のための発達診断 上』87-103ページを、ぜひお読みください)
卵を割るときのリョウちゃんの真剣なまなざし
連載第1回で取り上げた「卒業生からの手紙」に登場したリョウちゃんは、「4歳の節」で頑張っている特別支援学校中学部の生徒でした。もう一度お読みいただければ、リョウちゃんを通して「4歳の節」の理解が深まるでしょう。
その手紙をくれたリョウちゃんの担任だった卒業生に、「もう一つの『発達のなかの煌めき』」第1回で、以下の質問をしました。
私たちからの質問です。お手紙には、リョウちゃんが両手で慎重に卵を割るときの、手先を見つめる真剣なまなざしに、「4歳の節」を乗り越えているという実感をもつことができたと書かれていました。この「実感」とは、どんなことだったのでしょうか。卵に注意を集中しながら両手で割る、あるいは左右の手のそれぞれに注意を向け協応させながら卵を割るという、「…しながら…する」2次元可逆操作の獲得のことは、理解してくださっているようですが、このくだりを読んで、それだけではない「4歳の節」の大切なことがあると私たちは直感しました。それは、生活のプロセスのなかに、その能力を自らの必要によって取り込んでいこうする発達要求が発揮されるときがあったということです。きっと家庭生活において、リョウちゃんが「真剣なまなざし」になって、卵を割ろうとした瞬間があったはずです。その場面は何であったのか、そのときの発達要求とは何かを、私たちは知りたくなりました。今度お会いしたときに教えてください。宿題のようですいません。
返事は、すぐにありました。
新任の教師として中学部2年生のリョウちゃんたちの担任になって間もない春の日、一息入れようと「お楽しみ会」をしました。そのときにホットケーキを作りました。リョウちゃんは、自分から卵を割ると言いました。ところが、ボールのふちにあてて割ろうとした卵は、力を入れ過ぎたからかグチャとなり、黄身はボールの外に落ちてしまいました。リョウちゃんは、「おちた! おちた!」と、なかばパニックになっていました。そのとき先輩の同僚は、「ごめんな、先生がボールを持ってやればよかった。だいじょうぶ、だいじょうぶ、も(もう)一回やろか」とリョウちゃんの肩に手を置いて言いました。「だいじょうぶ、だいじょうぶ」は、懐かしい響きの言葉でした。
ところが、リョウちゃんは力を入れ過ぎるのか、ボールのふちで卵はグチャと割れてしまいました。「もうちょっとや、こうすんねん(こうするんだよ)」、先輩は力を抜いてボールのふちにあてるとちょうどよい割目が入ることを実演し、リョウちゃんの注意を引きながら両手でゆっくりと卵を割りました。リョウちゃんは、力を抜くことをコツとして吸収したのでしょうか。割目の入った卵を、両手でそっと開き、見事に卵はボールの真ん中に落ちました。「両手で慎重に卵を割るときの、手先を見つめる真剣なまなざし」とは、そのときのことです。「三度めの正直は、運でも必然でもなく、意志と知恵の力」という白石先生の言葉が浮かびました。
連絡帳にはリョウちゃんのその頑張りを書きました。それからずいぶんと後、お母さんはおよそ次のように書いてこられました。「お楽しみ会」の翌日の朝食で、リョウちゃんは目玉焼きを自分で作ると言い出したのです。「リョウは、嬉しそうに作りました。学校で教えていただいたように割目を入れ、ていねいにフライパンの上に卵を落としていました。いつもうまくいくわけではありませんが。妹の作るボイルのシャウエッセンと弟が焼く食パンが、我が家の朝食の定番です」
お母さんは、介護の仕事で働いていた老健施設を変わられ、新しい施設では始業が30分早くなりました。小学生2人を送り出し、リョウちゃんを通学バス停に送るのは、大変なことです。リョウちゃんの「申し出」をきっかけに、子どもたちに朝食の用意を頼むことにしたのです。大変になった親の仕事を、リョウちゃんなりに感じて、頑張っていたのでしょう。
「…しながら…する」という2次元可逆操作期は、手指の操作のことだけではなく、他者や自分のまわりの状況を理解し、そこから自分に目を向けて自分のことを考え、自分を調整できるようになっていくのですね。たぶん、こういったことを、先生方の質問では問われていたのだと思います。少し模範解答過ぎますか。(「卒業生からの手紙」は事実を手がかりとして構成されたフィクションであり、登場人物は実在しません)
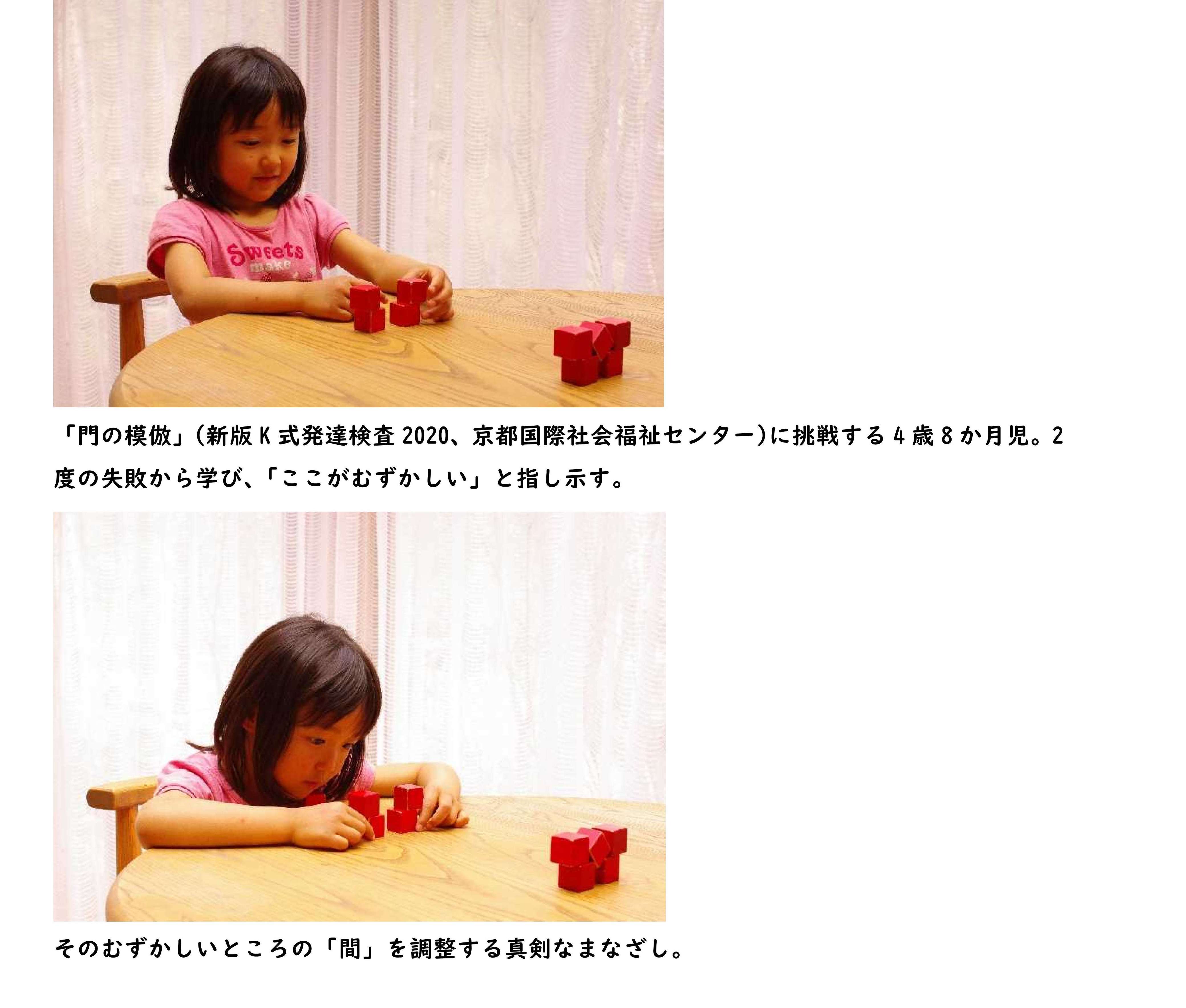
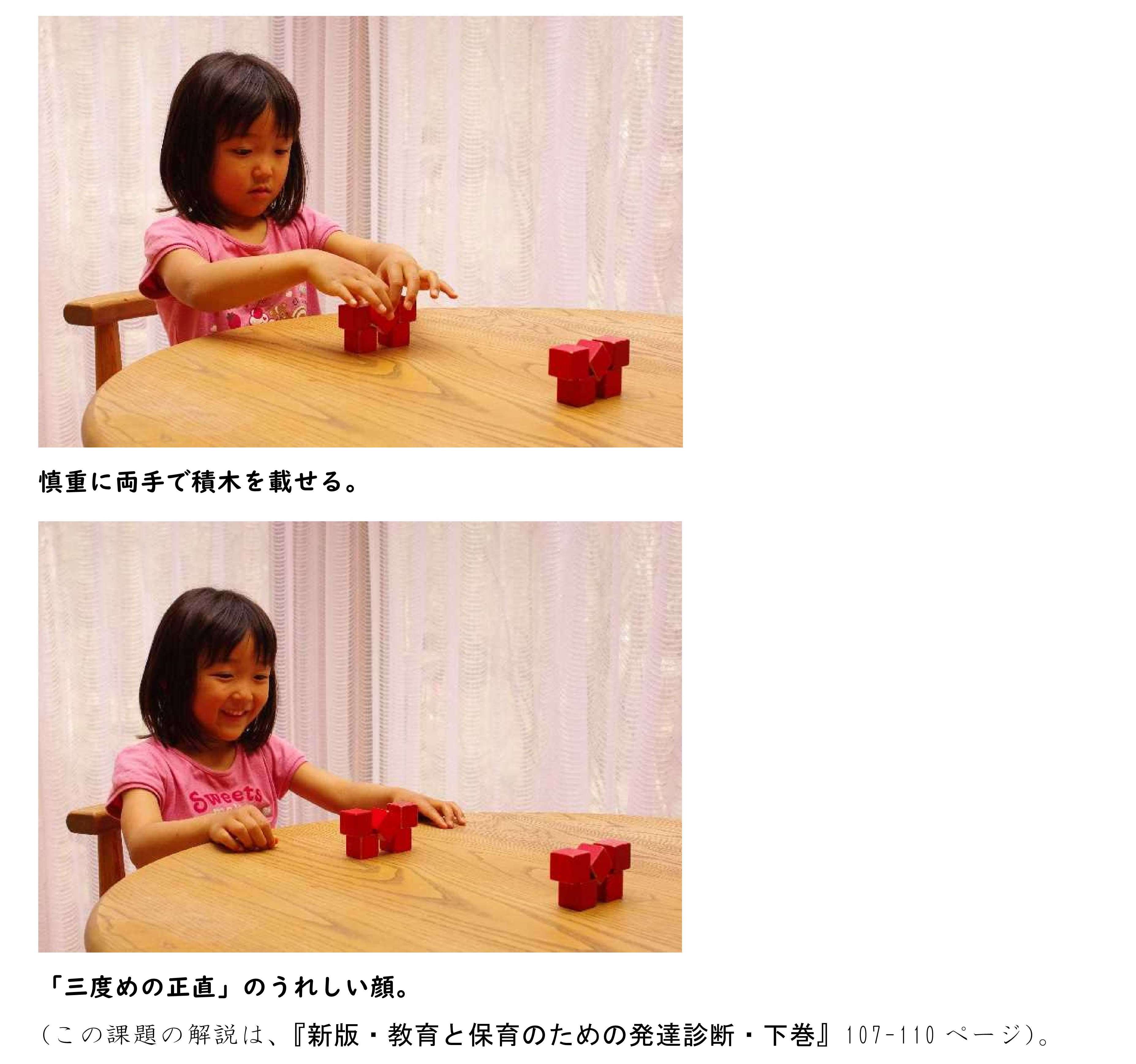
「社会」のなかでの存在の意味を探している
ご返事ありがとうございました。それぞれの発達段階での可逆操作によって、子どもは機能や能力を発達させていくだけではなく、自分の外の世界と自分を可逆してとらえ、自分を対象化する(みつめつつ、はたらきかける)ようになっていきます。そして、自分を変革していくのです。朝、お母さんが自分たちを急かせているのは、仕事が大変になったからだとわかっていたリョウちゃんは、ホットケーキ作りのときに、いつも朝食を作っているお母さんの姿を想ったのでしょう。お母さんやきょうだいのための「しごと」として、目玉焼きを作りたい。だから失敗に負けないで、先生に教えてもらい、卵を割れるようになりたいと願ったのです。それは、社会生活に適応していくための生活技能の習得だったのではなく、家族が暮らしやすくなるように、自ら買って出て、身につけようとしたことです。お母さんと3人きょうだいの家族は、もちろん朝からさまざまな衝突を繰り返し、心乱れる現実のなかにあったでしょうが、リョウちゃんはその役割を果たし続けました。
そうやって家庭で頑張っている子ども一人ひとりの生活を、新任の彼女は想像することができなかったことを、連載第1回の手紙では正直に書いてくれました。リョウちゃんは、立派に役割を果たしてから登校する自分のことを、わかってほしいし受けとめてほしかったのです。しかし、その思いとは裏腹に、同じような思いをもって登校してくる友だちや先生との心の齟齬をきっかけとして、毎日のように「ささいなこと」で大騒ぎになりました。
彼女の転機になったのは、家庭訪問で目の当たりにした「つましい」生活であり、寝る間もなく夜中にコンビニのアルバイトに出かけているお母さんのことでした。若い教師の心に響いたのは、それだけの苦労を引き受けても子どもを大切に育てようと歯を食いしばっている母親の姿であり、きょうだいの存在でした。教師として子どもを頑張って指導し、親にも頑張ってもらおうと気負っていた彼女は、自分はたいそうなことができるわけではない、だから肩の力を抜いて、子どもや親の目の高さに立てる教師になろうと思い立ちました。組合に加わり、学校のこと、子どもや家族の生活のこと、そして社会の問題を考えながら、一人の「小さい者」として、仲間と手をつなぎあっていこうと思ったのです。
リョウちゃんの家庭がそうであったように、日本の現実は一人親家庭や障害や病のある子どものいる家庭をはじめとして、社会的に弱い立場の人びとに対して過酷です。その政治、行政、経済を、一刻も早く改めていかなければなりません。しかし、そういった苦しい生活のなかにあっても、家族が互いの存在を尊びながら、現実に負けない生活を送ろうとしている意志もまた、忘れてはなりません。そのなかから、新しい時代のための確かな人間発達が実現していくように私たちは思います。
子どもは、それぞれの発達の段階で、自分の存在の実感、存在の意味を求めています。どう生きるか、どう生きたいかという問いを子どもなりにもっているのです。一人ひとりは、その発達段階や年齢に相応しい「小さい社会」のなかで暮らし、その「社会」のなかに存在の意味を見つけようとしていることでしょう。その願いはなかなか叶えられず、それゆえの葛藤があります。しかしその苦しみこそが、人間を人間たらしめる心なのだと思います。教師も、いやすべてのおとなも、労働や生活を通して、生きる意味や価値を求めつづけているのではありませんか。みな苦しい思いとともに。
惜別のことば
私たちの友人であり、広島市の療育の職員として働かれていた塩見陽子さんが、懸命な闘病の末に旅立たれました。今年度の『みんなのねがい』では、「だいじょうぶ
大丈夫」を連載されている途上でした。9月4日の連載オンライン「交流会」に仲間とともに参加され、私たち2人を励ましてくれていたのです。
闘病を共にされたご家族、働く仲間の皆さんの悲しみを想うと、ここに記すべきことばは見つかりません。惜別のことばを送ります。
30年近く前、私たちは、あなたや広島の療育の仲間と出会いました。何度もともに学び、そして全障研の活動で力をあわせてきました。
あなたの困難に負けない気概、困難を乗り越えていく思想性(たいそうな言葉だとあなたは笑われるでしょうが)に勇気づけられてきました。そして、ともに頑張る仲間を陽の光のように輝かし、そして仲間によってあなたも輝いていました。
あなたの光は消えてしまいました。しかし今、あなたのことを想うとき、私たちはとてもあたたかい気持ちになります。光は失われても、あなたのあたたかさはそのまま残りました。
あなたの遺してくれたことの数々をここに記すことはしません。あなたの仲間が、時間をかけて私たちに教えてくれることでしょう。
子どもたちの幸福と発達、平和な世界を願っていたあなたのあたたかさを胸にいだいて、私たちも頑張ります。
国連障害者権利委員会総括所見・教育関連の勧告事項について(談話)
2022年10月17日
全国障害者問題研究会全国委員長 越野和之
国連障害者権利委員会が2022年9月9日に公表した「日本の報告に関する総括所見」(以下「総括所見」)については、国内でも既に多くの見解などが示されているが、そのうちの教育に関する内容については、総括所見の趣旨と内容を適切に受けとめ、この国に暮らす障害児者・家族の権利保障に生かしていく上で、より多くの英知を集めた検討が求められている。この談話は、私たちがこうした課題に総合的に応えていくための契機となることを願って公表するものである。
総括所見のうち、教育(障害者権利条約第24条)について言及しているのは、第51項(懸念事項)および第52項(要請)の2項である。これは、総括所見の「Ⅲ.主な懸念事項と勧告」のうち、「B.具体的な権利(第5-30条)」のうちに位置づくもので、このパートは条約の条文ごとに、「懸念事項」(奇数番号)を指摘した上で「勧告」(偶数番号)を示すという体裁をとっている。
教育に関する「懸念事項」と「勧告」はいずれも(a)~(f)の6項目からなり、「懸念事項」と「勧告」の各項目の内容は対応関係にある(別添仮訳参照)。各項目に短いタイトルを付すとすれば、以下のようになる。
(a) 隔離された特殊教育の永続化への懸念とインクルーシブ教育への権利の確認
(b) 通常の学校へのアクセスと文部科学省4.27通知
(c) 合理的配慮
(d) 通常の教育の教師の研修および意識変容
(e) 通常学校におけるコミュニケーション方法
(f) 高等教育
このうちの(a)における隔離された特殊教育(segregated special education)をめぐる記述が、日本では「分離された特別な教育をやめるよう要請」(朝日新聞2022年9月13日)などと報じられた部分であるが、この点(以下(a)項)については後に述べることにして、まず残余の部分を概観してみよう。
(b)では、「懸念事項」として、通常の学校における障害児の受け入れ拒否と、その背景にある、障害のある子どもを通常の学校の教育に受け容れる準備ができていないという認識および事実があげられ、それと並んで特別支援学級に在籍する児童生徒は、学校で過ごす時間の半分以上を通常学級で過ごすべきでないとする文部科学省通知(2022年4月27日)の問題性が指摘されている。対応する勧告内容は、障害のあるすべての子どもの通常の学校への受け容れの確保、そのための「拒否禁止(non-rejection)」条項の導入、および先の文部科学省通知の撤回である。
(c)では、障害のある児童生徒への合理的配慮の提供が十分でないことへの懸念が示され、障害のあるすべての子どもに対し、一人ひとりの教育的要求に合致し、インクルーシブ教育を確保するための合理的配慮を保障することが求められている。
(d)は通常教育の教職員をめぐる指摘である。ここでは、通常教育の教師のスキルの不足と否定的態度が懸念事項とされ、通常学校の教職員の研修の確保、中でも障害の人権モデルに関する意識の向上が要請されている。
(e)は通常の学校におけるコミュニケーションのモードおよび方法に関する内容である。ろう児への手話教育の欠如、盲ろう児へのインクルーシブ教育の欠如などに対する懸念が示され、通常の教育環境において、さまざまな障害に即した補助的・代替的コミュニケーション(AAC)のモード・方法の使用が保障されるべきことが要請されている。
(f)は高等教育をめぐる問題である。大学入試および入学後の学修・研究プロセスの両面において、障害学生に対する社会的障壁を除去するための国レベルの政策が欠如していることが指摘され、そうした状況に対処するための包括的な政策の策定が求められている。
以上の要約からもわかる通り、(b)~(f)の5項目については、通常の学校、通常の学級を含み、さらに義務教育(ないし初等中等教育)段階のみならず、高等教育等(さらにいえば就学前の教育や社会教育、生涯学習、職業訓練等)も含んで、障害のある子ども、青年、成人の教育を受ける権利の保障、そのための諸条件の整備を求めてきた私たちの要求と一致するところであり、また、そうした各領域における教育条件を貧しいものに留め置き、障害のある人たちの学習し、発達する権利を侵害してきたこの国の教育行政に対する痛烈な批判として、心より歓迎すべき内容である。とりわけ、(b)の後段で、2022年4月の文部科学省通知の撤回を求めていることは、通級指導のための教育条件がきわめて貧弱であり、かつ通常学級内での特別な支援の提供を可能にする条件整備も欠如している下で、それらを代替する役割を果たしてきた特別支援学級の多様な運用を否定し、必要な教育条件の整備を行わないまま、通常学級へのダンピング(投げ込み放置)を強要しようとするこの間の文部科学行政のありようへの明確な批判として、重要な内容であると言える。
他方で、このような積極的な内容にも関わらず、総括所見は教育に関する (a)項の内容において、障害児教育関係者に大きな衝撃を与えている。しかし、この(a)項については、その内容そのものの理解に正確を期する必要があるとともに、それが、今回の勧告において、教育に関する内容の冒頭に位置づけられた背景についても、適切な吟味の下に理解することが必要だと私は考える。
先にも述べたとおり、日本の報道では、原文のsegregated special educationが、「分離された特別な教育」と訳されたことなどにより、特別支援学校や特別支援学級における教育全般について、その「存続」(perpetuation)
そのものが懸念の対象とされ、それを「やめる」(cease)ための国家行動計画の策定等が求められたとする理解が基調であるが、それは果たして妥当だろうか。
日本政府が提出した障害者権利委員会への報告では、「特別支援教育」はspecial needs educationと訳され、特別支援学校や特別支援学級についてもそれぞれ、special
needs education schoolやspecial needs education classesなどの語が充てられている。しかし、これらの用語は、総括所見では1カ所(懸念事項の(a)後段)を除き採用されていない。このことは、一方では生硬な和製英語が避けられたということでもあろうが、もう一方では、日本の特別支援教育は、権利委員会の目から見ると、引き続きspecial
education(特殊教育)の性格を脱しているようには見えない、という認識をも示しているように思われる。
特別支援教育のキャッチコピー「障害の種別と程度に基づいて特別な場で行う特殊教育から、障害のある子ども一人ひとりのニーズを把握し、適切な指導と必要な支援を行う特別支援教育へ」にも関わらず、日本では相変わらず、障害に応じた特別な指導・支援は、特別な場(特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室)以外には用意されず、しかもこれらの特別な場は、通常の教育からsegregate(隔離)されたものであることも少なくない。特別支援教育の成果を主張する政府報告にもかかわらず、こうした状況は改められないどころか、「特別な場」で学ぶ子どもの数は増え続けており、それは通常学校・通常学級が、障害のある子どもへの排除圧力を強め続けていることと深く結びついている。日本政府は、2007年からの特別支援教育の開始、2013年からの就学先決定手続きの変更などを持って、「インクルーシブ教育システム」の確立・推進を言うが、それは、特別な場で学ぶ子どもの数の著増状況が明白に示すように、実効性を持ち得ていない。
権利委員会が、「特殊教育の永続化(perpetuation)」という表現を用いて懸念を示したのは、この国の特別支援教育のこうした状況に対してなのであり、それを転換するためにこそ、総括所見は、条約の締約主体であり、その実行に責任を持つ日本政府に対して、インクルーシブ教育への権利を認めることを求め、具体的な目標、時間枠および十分な予算措置を伴った国レベルの行動計画の策定を求めた、ということなのではないだろうか。
一方、これに対する日本政府の反応は不誠実といわざるを得ないものである。永岡文部科学大臣は、記者会見での総括所見に関する質問に対して、「特別支援教育を中止することは考えていない」、「〔2022年4月の〕通知は…むしろインクルーシブを推進するもの」、「勧告で撤回が求められたのは大変遺憾」などと述べるに止まった(2022年9月13日永岡文科大臣記者会見録)。そこには、総括所見の指摘やその趣旨を真摯に受けとめて、特別支援教育の制度や施策を再検討する構えは感じられず、ましてや、通常学校・学級の教育、たとえば教員配置や学級規模をはじめとする教育条件、あるいは、「過度に競争的な制度を含むストレスフルな学校環境」(国連・子どもの権利委員会,2019)と批判される教育課程行政を含む教育環境等を改める姿勢は皆無であった。
私たちは、このような政府答弁などをして、特別支援教育の存続などととらえ、胸をなで下ろすことは決してできない。私たちが、障害のある子どもたち、青年たち、仲間たちやその家族とともに求めてきたことは、特別支援教育=特殊教育の現状のままの存続などではなく、私たちの暮らすこの国の社会が、本当の意味で、権利条約第24条第1項の示す「教育についての障害者の権利を認め」る社会となることであり、その実現を確実なものとするために、日本政府および地方自治体等をして、「インクルーシブなあらゆる段階の教育制度および生涯学習」を確保することに真摯な努力を傾けるものとしていくことである。総括所見における教育に関する内容は、この国の現実に即して、こうした課題の実現をはかる取り組みの重要な拠り所となるものであり、この国における障害のある人たちの教育をめぐる状況をリアルに捉え、解決すべき諸問題を考えあっていくための指針として、重要な意義を持つものであると私は理解する。
なお、総括所見を以上のようなものととらえ、その実現を図る努力の過程において、「隔離された特殊教育の廃止(cease)」という総括所見の文言が、人間の発達のすべての時期において、通常の教育環境とは相対的に区別された一切の特別な教育の場、特別な教育課程等の存在を否定するものであるのか、それは果たして、条約第24条第1項の示すインクルーシブ教育の三つの目的の実現に資するものであるのかどうかということについての、建設的で実りある対話が求められよう。この国には、障害のある子ども、青年の人間としてのゆたかな発達の実現を期してとりくまれてきた、特別支援学校、特別支援学級等における教育実践の豊富な蓄積があり、その発展を期す真摯な努力がある。それは歴史的にみれば、通常の教育環境とは相対的に区別された教育の場および教育課程等の存在を前提として成立し、発展してきたものである。障害を理由に、特別な教育での場を強要されることは、換言すれば通常の教育環境からの排除に他ならず、そうした事態は根絶されなければならない。しかし、そのための努力と並んで、現存する特別な教育の場と通常の教育環境との間の物理的な隔絶をなくしていくこと、あわせて、教育目標や教育課程、教育年限や卒業後の進路保障等々、特別な場における教育に残存する差別的なとりあつかいを一つ一つ確実になくしていくことと結びながら、これらの場によって生み出されてきた、障害のある子ども・青年のゆたかな発達を確保し、その源泉となる教育実践をさらに発展させ、それを基礎づける教育条件を整えていくこともまた、「隔離された特殊教育の廃止」を展望するもう一つの道ではないか。国連障害者の権利委員会総括所見の勧告に対しては、このような論点もまた提起される必要があるものと私は考える。総括所見を期に、この国における障害のある人たちの「教育についての権利」の総合的な実現にむけて、事実に基づいた旺盛な議論がなされることを願う。
教育関係の内容の仮訳は以下のPDFファイルをご参照ください
▶委員長談話と仮訳含めたPDFファイルのデータです
2022年10月
白石 正久・白石 恵理子
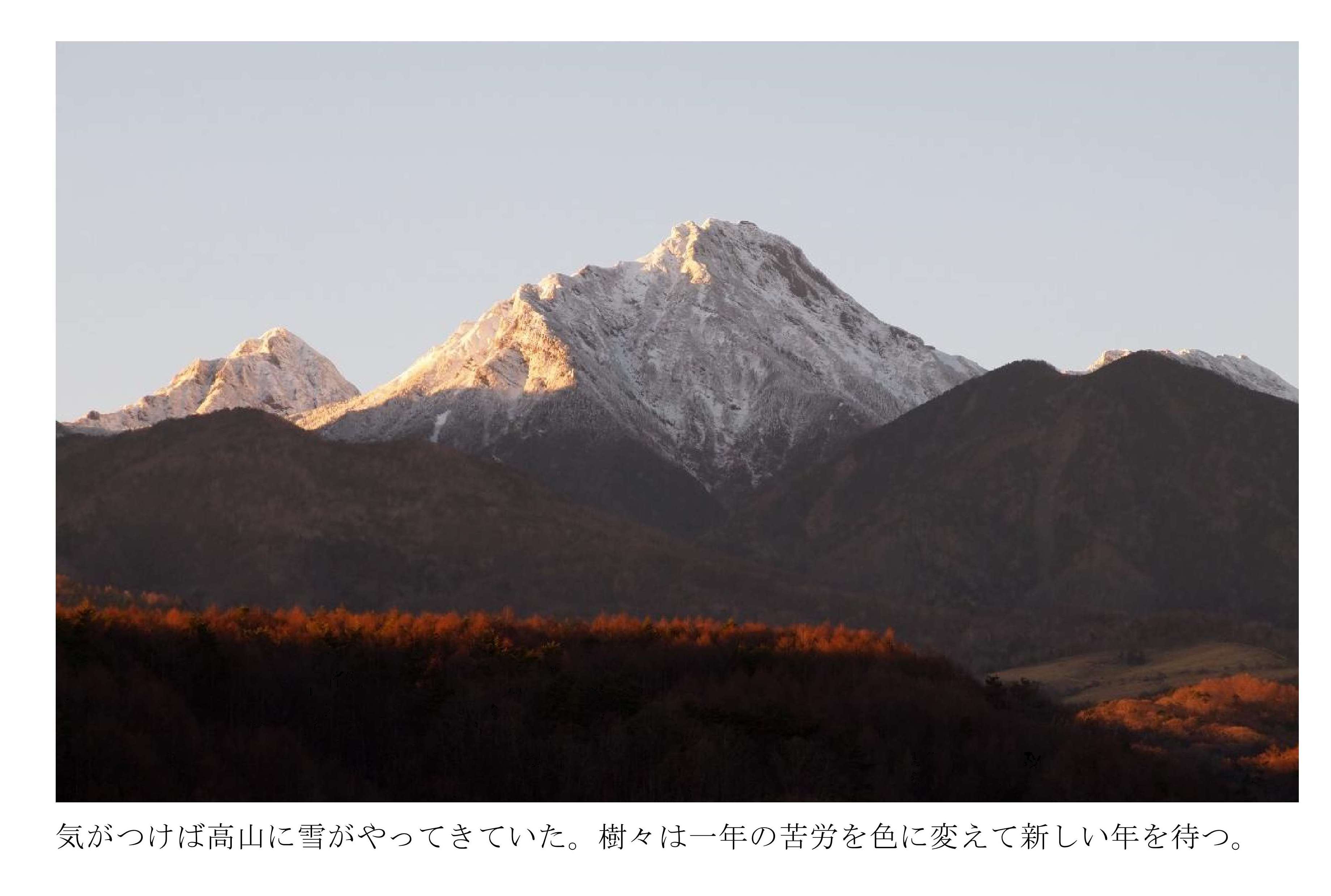
第7回 つないで、まとめあげ、そしてまた考える
~「2次元可逆操作」の世界へ~
連載がはじまり、あっという間の半年が過ぎました。猛暑もようやくやわらいできました。じっくりと学びの秋にしたいですね。先日、2回目の連載「交流会」を開催したところ、全国から多くの方がご参加くださいました。皆さんと、子どもたち・なかまたちの「本当の要求ってなんだろう?」「子どもをつなぐ文化ってなんだろう?」と語り合いながら、たくさんのエネルギーや視点をいただきました。
いくつかの感想文をご紹介します(部分的に修正しています)。
・授業案(略案)を作るのに、若い教員の皆さんは、「学習指導要領」とにらめっこして目標を決めています。そこに目の前のこどもの願いが載ってるの?と思いながら・・・どう話していくのか、悩む日々。職員室の机上にはボロボロになった「学習指導要領」が並んでいます。目の前の行動の変容に、一喜一憂している姿があります。読書会のような、ゆったりした雰囲気で学校から離れて語り合う場が必要だと思います。若い方の言葉にハッとさせられる、良い刺激もたくさんあるから、ゆっくり話したいです。
・正解を白石先生に求めるということは、この交流会の主旨ではないなと気づきました。親としてこの交流会に参加して、あの支援とか実践とかはこういう意味や意図があるのかなあ?と自分なりに考え、職員さんに問いかけてみようと思うようになりました。
・大切だと感じていることはたくさんあっても、それを自分なりの言葉にすることが苦手でなかなか話をする勇気は持てませんでしたが、みなさんの話を聞き、自分が思っていることと重なることを実感することができました。今後もこういった機会があれば参加したいと思っています。
第3回の交流会は、12月10日(土)13時から15時を予定しています。
新刊『新版・教育と保育のための発達診断・上 ― 発達診断の基礎理論』(以下では『下巻』)をテキストとする「発達診断セミナー」が10月23日に迫りました。オンラインではありますが、みなさんにお会いできることを楽しみにしています。
*セミナーの申し込みは、以下の全障研HPからどうぞ(締切10月15日まで)
https://www.nginet.or.jp/schedule1.html
乳児期の第2段階-「二次元可逆操作期」
前回の「もう一つ」でも述べたように、「1歳半の節」に始まる発達の階層である「次元可逆操作の階層」の第2段階が「4歳の節」である「2次元可逆操作期」になります。
「1次元可逆操作期」では、頭のなかに「対」を形成し、それを並列させて、「…ではない…だ」と可逆操作し、頭のなかで選択したり、活動を切り替えたり、関係をとらえる思考ができていきます。「2次元可逆操作期」では、「対」を並列させるだけではなく、可能になった「大きい-小さい」「よい-わるい」などの対比、比較という「もう一つ」の操作が加わり、ものごとの意味や価値を理解したうえで、選択や思考ができるようになります。さらに、たとえば一方の手でハサミを持ち、他方の手で紙を持って、意図した通りに曲線を切るというように、左右の手の活動を分化させたうえで、「…しながら…する」と協応させることができるようになります。つまり、「2次元可逆操作」とは2種類の可逆操作が結合することなのです。
子どもたちは、遊びや生活のなかで、様々なものに自分で働きかけ、その結果を感じ取りながら好奇心をはぐくんでいきます。また、周りの人とかかわりあうなかで、笑ったり怒ったりしながら心を太らせていきます。…その日々の積み重ねのなかで、それまでは別々にとらえていたことを、「…だから、こうなる」「…したら、こうなる」とつなげて理解しようとします。そうして、幼いながらも自分なりの“論理”をつくりだしていくのです。しかし、その“論理”からはずれることも当然増えていきます。「あれあれ、どうなってんだ?」「なんで、こうなるんだ?」と戸惑うことも増えていくでしょう。それがまた、子どもの思考を育てていきます。ときには、相手に喜んでもらえると思っておもちゃを差し出したのに、なぜか相手が怒りだしてしまうこともあるかもしれません。お母さんにほめられると思ったのに、逆に叱られてしまうことも…。そのたびに、悔しい思い、切ない思いもしながら、またきっと一所懸命に考えていくのでしょう。子どものつくる“論理”は、決して客観的に正しいとは限りません。それに対し、正論をおしつけるだけでは、思考や表現の喜びを育てることにはならないのだと思います。
学生時代に聞いた「問いと答えの間が短くなっていないか」という投げかけは、学校教育のあり方への警鐘だけではなく、もっと幼い時期の子どもたちとのかかわりを考えるうえでも大切な問題提起だと考えます。発達診断のなかでも、子どもたちが「正しい答え」を言ってくれたときに、正直ほめたくなる自分がいました。しかし、おとなにとっての「正解」が、目の前の子どもにとっての「正解」とは限りません。とくに2次元形成期に入ってきた子どもたちは、おとなの評価にも敏感になるため、おとなの正論をおしつけられることで、自分を否定された感覚だけが残ることがあります。2次元可逆操作期になれば、よけいに「できない自分」「間違った自分」という意識につながってしまうこともあります。大切なことは、子どもたちが生活や人間関係のなかでいろんな事態にぶつかったときに、「あれれ?」「なんで?」と少しでも自分で考えようとする力を育んでいくことなのでしょう。そう考えると、今一度、この時期の子どもたちの“論理”そのものに心をよせ、「なるほど。そう考えたんだね」「面白いなあ」と寄り添ってくれるおとなの存在の重要性を強調したいと思います。
「2次元可逆操作期」については、『上巻』Ⅲ 3章「4歳の発達の質的転換期と発達保障」、『下巻』Ⅲ 5章「4歳の質的転換期の発達と発達診断」をご参照ください。
<両手の交互開閉にとりくむ4歳0か月児>
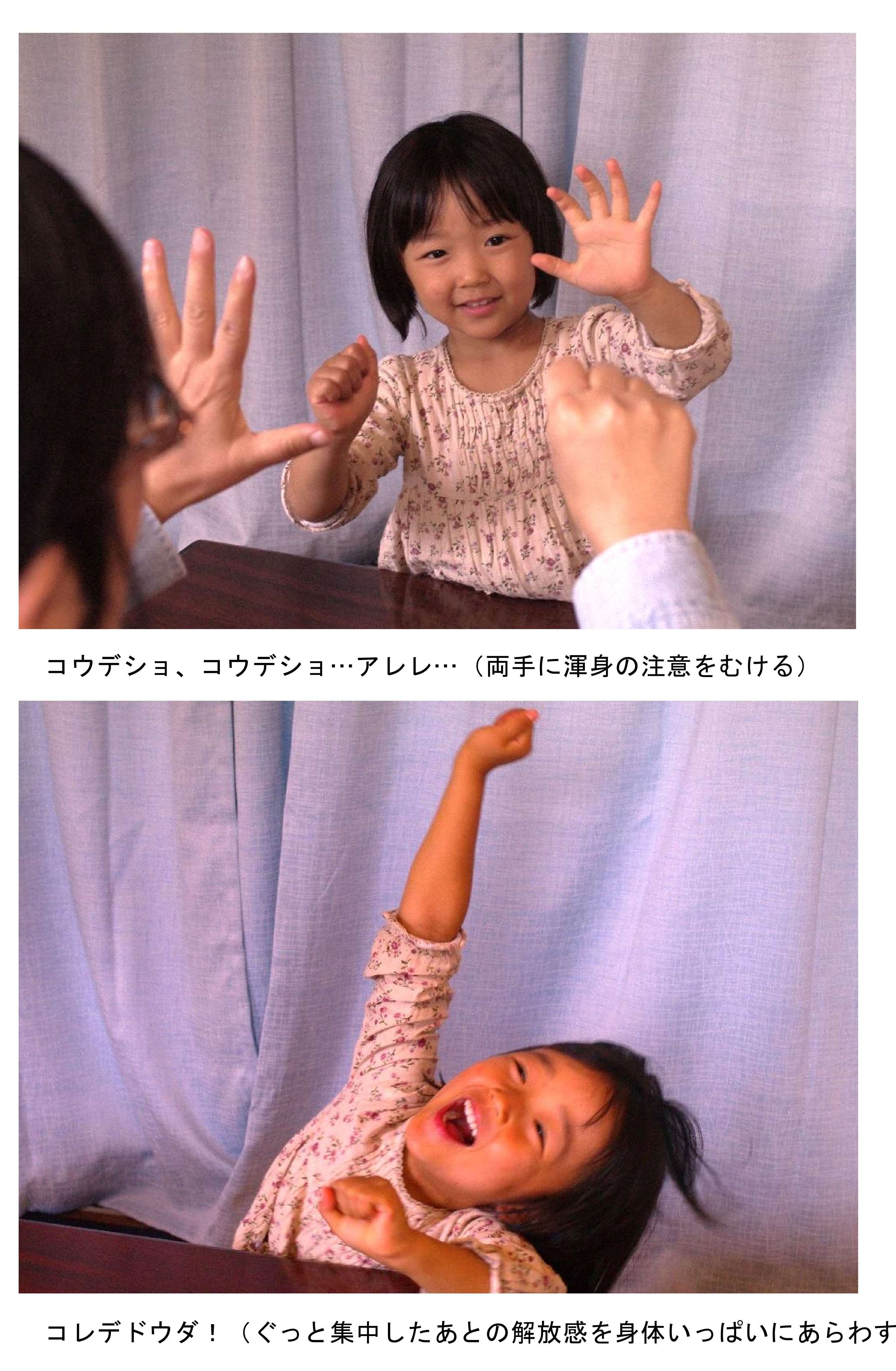

知的障害のある成人期の方たちのこと
連載第7回(10月号)では、成人期の知的障害のある人たちのことを取り上げました。成人期において、働くことにどんな値打ちを見出しているのか、すなわち労働に対する価値観が、それぞれの発達の時期によって異なるのではないか、発達的に2,3歳頃、すなわち「2次元形成期」にある人に、「お仕事がんばらないとお給料もらえないよ」という当然の激励が、実は本人を追い詰めてしまうこともあるのだということを書きました。
「2次元形成期」までの人にとっては、目の前の具体的な変化を通して、目の前の具体的な人との間で仕事の値打ちがつくられていくのだと思います。「今日、これだけがんばったね」と実感ができること、一緒に働くなかまや職員との間で「ありがとう」「がんばったね」と共感しあえることが重要なのだと考えます。「2次元可逆操作期」になると、すぐに労働の成果が見えなくても、「自分のつくったもので誰かが喜んでくれている」「誰かの役に立っている」という、「誰か」という抽象的な人を頭に描くことができるようになるのでしょう。これは、社会という目に見えない関係のなかで自分の存在に手ごたえをもつ第一歩とみることもできるでしょう。
しかしそれは「4歳の節」を超えれば自動的にそのような捉え方ができるというものではありません。実際に自分があてにされているという実感の積み重ね、お給料を使うことで自分の生活が豊かになるという実感の積み重ねが重要であることを強調したいと思います。
また「2次元形成期」までの人にとっては、社会との関係の理解が難しいからといって、作業所のなかだけの人間関係だけでよいのかというと、決してそうではありません。いつもの職員の声かけよりも、地域の方の「ご苦労さん!」という声かけを嬉しそうに顔をあげて聞いたり、施設内のコーヒー当番よりもいろんな方が訪れる喫茶店の店番にはりきって行きたがる方もたくさんいます。発達診断などで“たまーに”作業所に顔を出す私の前で、急に仕事をしはじめる方もいます。もちろん、いつものなかま、いつもの職員との安心した関係があるからこそなのですが、誰もが、「新しい外」との関係で「新しい自分」を感じる要求をもっているのではないかと思います。とくに「行動障害」が強い方たちの場合、一対一対応で職員がつくことも多くなりがちですが、逆にそのような「閉じた関係」がなかまも職員も追い詰めてしまうことはよくあります。職員が必死でそのなかまのことを理解しよう、「わかってあげたい」と思うからこそ、余計に、その雰囲気をなかま自身も感じ取り、互いの一挙一動に敏感に呼応しあってしまうのだと思います。
全障研滋賀支部では、この間、2か月に1回くらいのペースで、成人期のオンラインサークルを行なっています。ある生活介護事業所は、「強度行動障害」と言われる方が多いのですが、「一対一関係」が必要と考えられるなかまであっても、できるだけ「一対二」「二対一」「二対二」になるようにしている。そのなかで、職員も見方が深まるし、なかまも本当の要求を出しやすくなる、ということでした。また、別の事業所では、自分の要求を語りにくいなかまの「個別支援計画」をたてる際に、複数の職員が「案」をつくり、それを職員集団で議論して、よりなかまの思いに寄り添えるものにしようとしているとのことでした。「案」をつくる際には、そのなかまの日頃の言動や生育歴から、「こんな“ねがい”もあるかも…」と考え、そこから「甲子園球場に行こう!」がなかまと職員の共通の目標になった経過も出されました。
「本当の要求」をとらえていくためにも、職員の実践目線が閉じないように、常に開かれたものになるようにしていきたいものです。
今回の学習参考文献
・白石正久・白石恵理子編(2022)『新版・教育と保育のための発達診断・上巻』全障研出版部
・白石正久・白石恵理子編(2020)『新版・教育と保育のための発達診断・下巻』全障研出版部
・白石恵理子(2018)『障害のある人の発達保障 成人期のなかまたちが教えてくれること』全障研出版部
「障害者問題研究」50巻2号
特集=乳幼児期の療育と発達保障
▶「読む会」情報
日時=10月14日(金)19時~21時/zoomによる開催
話題提供=近藤直子さん(あいち障害者センター)
障害の早期発見・早期対応,子育て支援における発達保障
・参加費は無料です。
・お手元に当該号をご用意ください。
・読む会参加申し込みフォーム(右)からも注文できます。
・お申し込みは以下のフォームから↓
https://forms.gle/gNLThxLkvd8S6iY79
●読む会へのおさそい●
乳幼児健診から、その後の対応としての親子教室、親子で通う療育、そして通園療育や、保育所・幼稚園での支援……療育の制度化を求めるとりくみと制度改変の、そのせめぎあいの中で療育がどのように変化してきたか、そして、そのことがどんな意味をもっているのか、療育という言葉で発達保障をめざす運動は何を創ってきたでしょうか。
パッケージされた商品のような「療育」セットでなく、断片の寄せ集めのモザイクのようなぶつ切りにされた生活ではなく、信頼できる大人や友だちとともに過ごす遊びや生活の時間の、ゆったりとした流れこそが子どもには必要だと思うけれど、ひろがる営利主義・訓練主義に抗して、発達を保障する療育をどのようにつくっていけるのか、と保育・療育の現場での悩みはつきません。
この特集をもとに語り合いませんか。
療育とは何かを考えたい人、児童発達支援・保育・教育の関係者にひろく参加をよびかけます。ぜひ職場や地域の仲間を誘ってご参加ください。
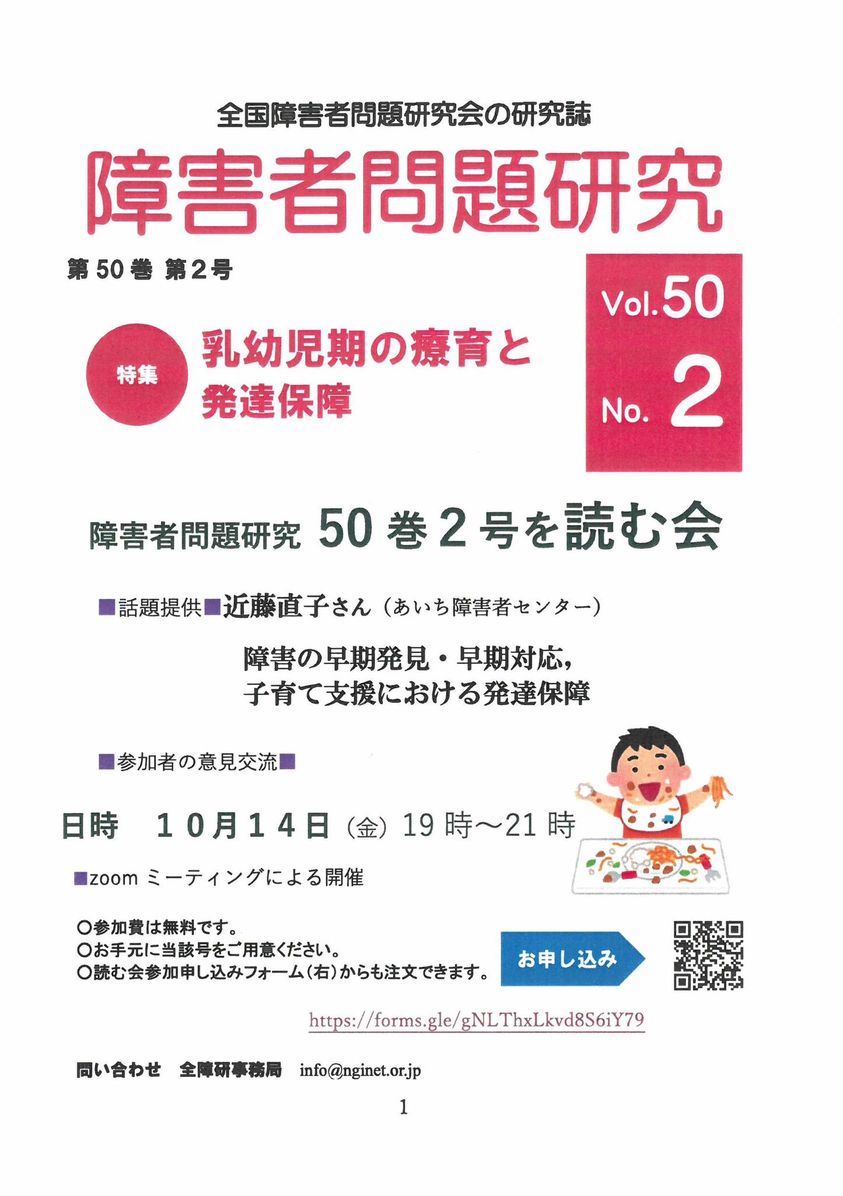
詳細案内 「ちょっと見」やオンラインでのご注文は以下のホームページへ
▶「障害者問題研究」50巻2号 特集=乳幼児期の療育と発達保障
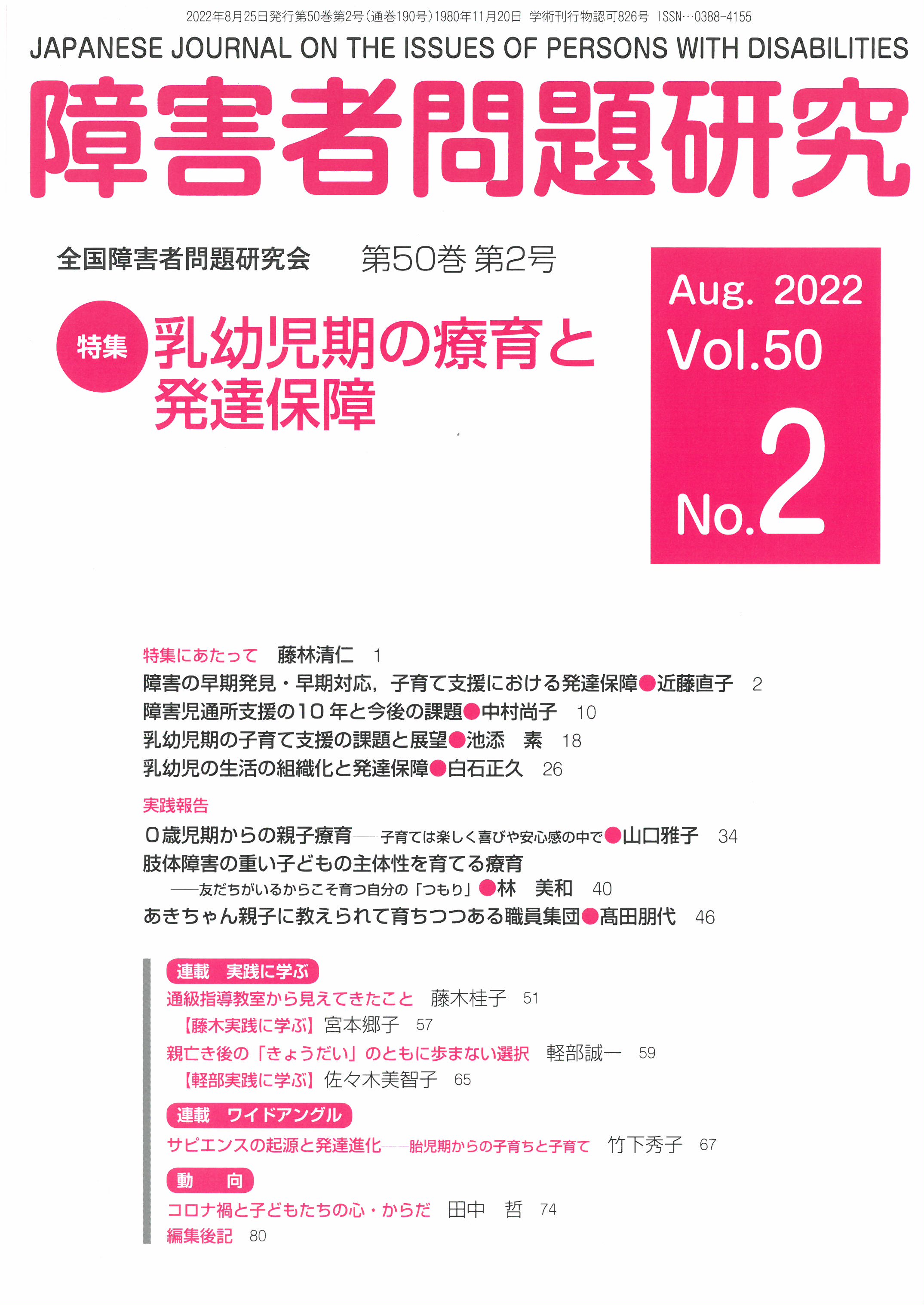
定価2750円 ISBN978-4-88134-036-3 2022年8月31日

もくじ
はじめに
執筆者一覧
Ⅰ 子ども・障害のある人たちの権利と発達保障
子ども・障害のある人たちの権利と発達保障/玉村公二彦(京都女子大学)
はじめに
1 「子どもの世紀」における精神発達の発見と歪曲―― 知能・能力の測定による選別から発達診断へ
(1)ビネーの知能検査の開発
(2)測定運動とテスト法の緻密化――能力の「量」への還元
(3)測定運動への批判と発達診断・アセスメントの萌芽
2 発達の権利と発達保障の提起――「この子らを世の光に」する取り組みの中で
(1)人権認識の発展と国際人権規約――国連における自由権・社会権を中心とした人権条約の成立
(2)「発達の権利」と「発達保障」の胎動――障害の重い子どもたちへの取り組みから
(3)「学習権宣言」と「発達への権利宣言」
3 子ども・障害のある人の権利の総合保障
(1)「子どもの権利条約」と意見表明権
(2)「障害者権利条約」
4 インクルーシブな社会の実現と参加主体の形成(インクルーシブ教育の権利)
5 子ども・障害のある人の権利保障のための発達診断を
Ⅱ 発達理論と教育・保育の実践
発達理論と教育・保育の実践/松島明日香(滋賀大学)
1 発達の基本的理解
(1)子どもの手応えを想像する
(2)自己変革の「ねがい」に導かれる
2 子ども理解のための発達理論
(1)発達理論を学ぶ意味
(2)「可逆操作の高次化における階層―段階理論」とは
(3)発達の質的転換期
(4)「新しい発達の力」の誕生
(5)人格形成の発達的基礎
(6)発達における連関
3 発達理論は保育・教育実践にどのように寄与するのか
(1)ヨコへの発達姿勢を変換させる
(2)新しい発達の力と保育・教育実践
(3)「問題行動」を発達要求ととらえて実践のなかで実現をはかる
4 結びにかえて
Ⅲ 発達の質的転換期とはなにか――その発見と実践研究
1章 乳児期の発達段階と発達保障/白石正久
1 障害の重い子どもたちが教えてくれたこと
(1)映画『夜明け前の子どもたち』から
(2)シモちゃんの笑顔
(3)三井くんの「心の窓」
2 乳児期の発達の階層―段階
(1)乳児期前半の3つの発達段階
(2)乳児期後半の3つの発達段階
(3)発達の段階間の移行で芽生える力
3 発達の源泉としての心輝く自然と文化
2章 1歳半の質的転換期と発達保障/白石恵里子
1 「1歳半の節」がどのように認識されてきたか
2 はめ板課題と1次元可逆操作
3 「発達の節」は「発達の危機」
4 障害の早期発見・早期対応において
5 1960年代後半の近江学園での実践から
3章 4歳の発達の質的転換期と発達保障/張 貞京(京都文教短期大学)
1 ある4歳児クラスの話
2 発達研究にみる4歳の質的転換期
(1)近江学園を中心とする発達研究のはじまり
(2)「精神作業過程測定装置」にみる質的転換期
(3)2次元可逆操作を獲得していく難しさ
(4)2次元可逆操作期と生活年齢の効果
3 実践研究にみる4歳の質的転換期
(1)質的転換期をふまえた実践指導の検討
(2)近江学園の指導体制の変遷
(3)指導実践の歴史からみえた4歳の質的転換期と生活の広がり
(4)友だちを見ながら,自分と比べて考える―4歳の質的転換期にいる成人の姿から
4 さまざまな指導実践における諸問題
(1)4歳児の悩みと願い
(2)青年期以降の実践について
4章 7歳の発達の質的転換期と発達保障/川地亜弥子(神戸大学)
1 発達の質的転換期と保育・教育の節目
2 なかまとともに筋道をつくる――生後第3の新しい発達の力の誕生から3次元可逆操作期へ
(1)道順描画やその説明にみられる変化
(2)自分を中に繰り込んで,みんなで達成する
3 自分の視点と他者の視点を調整しようとする――3次元可逆操作期の特徴
4 書き言葉の中に見えてくる子どもの発達と内面世界の深まり
(1)友だちとの世界―やんちゃな遊びと「ひみつ」の共有
(2)信頼できる他者を支えに,自分なりの筋道をつくる
(3)思考や感情「の理解の深まり
5 発達に課題をもつ子への実践からみえてくること
Ⅳ 障害と発達診断
1章 自閉スペクトラム症と発達診断/別府 哲(岐阜大学)
1 自閉スペクトラム症と発達診断
(1)鑑別診断である診断基準(DSM-5)と発達診断
(2)機能連関,発達連関―機能間のズレ
2 1歳半の節と自閉スペクトラム症
(1)定型発達時における1歳半の節
(2)自閉スペクトラム症における1歳半の節
(3)こだわりと破壊行動を頻発した成人の自閉スペクトラム症者
(4)アタッチメント――発達連関の視点より
3 自閉スペクトラム症の発達診断の課題
(1)ユニークな機能連関,発達連関の解明
(2)目の前の子どもの好きな世界を知る
2章 重症児と発達診断/白石正久
はじめに――重症児とは
1 重症児と発達診断
2 乳児期前半の発達段階にある重症児の発達診断
(1)感覚と運動を協応させて外界を志向する発達の連関過程
(2)「生後第1の新しい発達の力」の誕生と発達の連関過程
3 重度の機能障害の背後に言語認識をもつ重症児
(1)「みかけの重度」問題
(2)「みかけの重度」問題に対する発達診断と教育指導
4 重症児の発達診断の方法を構築していくために
おわりに
Ⅴ ライフサイクルと発達診断の役割
1章 早期発見・早期対応と発達診断
/小原佳代・西原睦子・高田智行(大津市幼保支援課)・高橋真保子(コスモス)
1 乳幼児健診と子育て支援・療育――滋賀県大津市を中心に
(1)乳幼児健診と発達相談
(2)子育て支援と発達相談
(3)保育園・幼稚園における発達相談
2 児童発達支援における発達診断を療育実践
(1)児童発達支援センターのかなめとしての通園療育
(2)発達相談の一つ目の役割――子どもがどんな発達への願いをもっているかを職員集団が考え合う
(3)発達相談の二つ目の役割――子どもが見せる姿を保護者と担当者が共有し、子どもの育ちを確かめ合う
2章 学校教育と発達診断/櫻井宏明(元特別支援学校)
1 実践の中での子ども理解と発達診断
(1)子ども理解は子どもとのふれあい・かかわりから (2)子ども理解の方法
2 アセスメントと発達診断
(1)個別の支援計画・指導計画とアセスメント
(2)アセスメントに心理検査等を利用する際の注意点
3 学習意欲を取り戻したダイスケさん
(1)ダイスケさんの内面を探る
(2)ダイスケさんの内面を考え、学習内容を見直す
(3)学習面での変化
4 障害が重度の子どもの発達診断の難しさ
5 障害が重度の子どもの行動をとらえ直す
(1)定位的活動の獲得の検討
(2)動作模倣の検討「あらって,あらって」
(3)教材や活動についての発達的意義の理解を深める
6 子どもの発達課題の理解と授業づくり
(1)発達課題に合った教材を選択する
(2)一歩先の発達的課題も含める
(3)障害や生活に配慮する
(4)教師との関係や集団を大切にする
7 実践における発達診断・アセスメントの留意すべき傾向
(1)表面的な子ども理解にとどまる傾向
(2)指導と結果を短絡的に結びつける傾向
(3)PDCAサイクルの問題
(4)実践のマニュアル化の傾向
3章 成人期実践と発達診断/白石恵理子
1 成人期の発達をとらえる意味
2 発達保障とは
3 可逆操作は行動の基本単位である
4 発達は右肩上がりにきれいに進むものではない
5 具体的事例から考える
(1)1次元可逆操作期言語にある「強度行動障害」のAさん
(2)自傷行為の激しかったBさん
(3)期待と納得の中でのCさんの姿
(4)陶芸に生きがいを見いだすDさん
6 生活の歴史を尊重する
7 ねがいや要求の内実は生活の質によって規定される
8 「問題行動」の発達的理解
9 集団の中で自分の価値を築く
10 職員集団として、語り合う
あとがき
▶ご注文は全障研出版部オンラインへ
定価1980円 ISBN978-4-88134-047-9 2022年8月31日
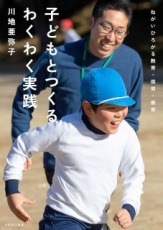
川地亜弥子(神戸大学・全障研副委員長)著
子どもとつくる わくわく実践
ねがいひろがる教育・保育・療育
まえがき 3
第1章 すてきな教材・文化と出会う 13
1 一人ひとりが輝く授業、みんなで学ぶ授業をつくる 14
2 やってみる、なってみる 25
3 一人ひとりの思いを深く想像して33
コラム1 教材づくりのおもしろさ 23
コラム2 障害児教育における教材とは 40
第2章 ねがいをひもとく、ねがいを育てる 43
1 「むっちゃ楽しい」クラスの中で 44
2 学校のねうち 52
3 ゆたかな人間関係と偏食指導 60
4 楽しい節目をつくりだす 68
コラム3 「私は~」作文調査から見えること 76
第3章 青年・成人期を謳歌する 81
1 青年期を謳歌する 82
2 恋うる心を授業にする 90
コラム4 旧優生保護法被害者の一刻も早い救済を 98
第4章 実践と発達診断のいい関係 99
1 要求を育てる 100
2 子どもの輝く姿をとらえる子育て・療育・発達相談 108
第5章 実践記録のねうち 117
むすびにかえて 127
あとがき 133
▶ご注文は全障研出版部オンラインへ
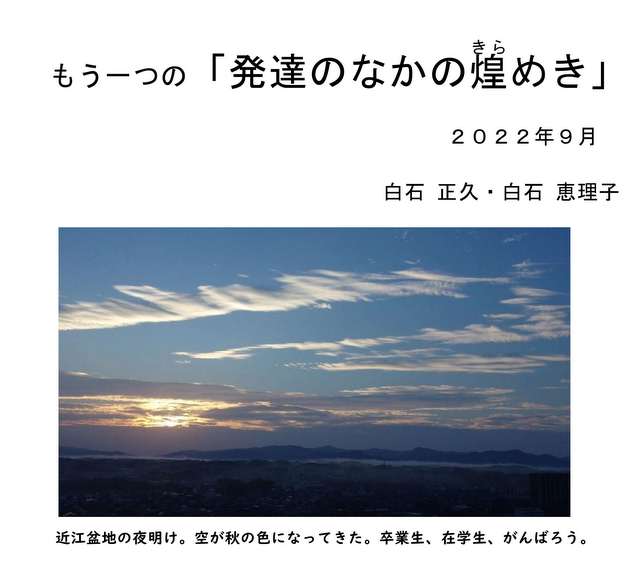
第6回 「二次元の世界」を開く
いつも「もう一つの『発達のなかの煌めき』」(以下では「もう一つ」)をお読みいただき、ありがとうございます。プリントして持ち寄り、『みんなのねがい』連載とともに読みあわせをしていただいているとのお便りを拝見しました。どちらを先に読んだ方がよいかとのお尋ねもありました。
そこで、「もう一つ」を書くことになった動機を改めてお話ししたいと思います。私たちの『みんなのねがい』連載企画には、「発達を学びたい」「実践とつなぐ視点を得たい」との要望をいただいています。少し困ったのは、限られた文字数で、それにお応えする内容が書けるかということです。説明的な文章になりすぎて発達の理論を一方的にお伝えするような内容にしたくない。むしろ子どもやなかまの姿と発達の理論の接点を探しながら、発達へのまなざしが開かれていくようなものにしたい。しかも職場や地域の集団で読みあい、議論していただくことによって、その理解が拡がっていくような、いわば「行間」のある文章にしたいと思いました。それは、なかなか難しいことですが。
連載をそのように書こうとしたときに、「発達を系統的に学びたい」という要求にどこまで応えられるかという心配があります。一方で、すでにテキスト『新版・教育と保育のための発達診断・下巻―発達診断の視点と方法』(以下では『下巻』)『教育と保育のための発達診断』(旧版)をたくさんの方がお読みいただき、「発達診断セミナー」を受講してくださっている事実もあります。そこで、連載とテキストの学習をつなぐ「解説版」を出そうということになりました。それがこの「もう一つ」です。
したがって、まず連載をお読みいただき、想像力をめぐらしながら語りあっていただければと思っています。「もう一つ」は、その議論のなかで、これまでの発達の学習を整理して、理解を深めていくきっかけになるように書き進めていくつもりです。
さて、長らくお待たせした『新版・教育と保育のための発達診断・上巻―発達診断の基礎理論』(以下では『上巻』)を刊行することができました。執筆者一同、がんばって書き上げた新刊です。ぜひ、お手元において学習の友としてください。
幼児期の「次元可逆操作の階層」の3つの段階
「もう一つ」の第1回と第2回で、田中昌人さんらの「可逆操作の高次化における階層‐段階理論」に依りながら、乳児期から学童期にいたる発達の質的転換期と発達段階について説明しました。『上巻』の4ページ、『下巻』の6ページの図を参照していただきながら、少し復習をします。
通常、生まれてから9,10歳に至るまでに、3つの種類の「可逆操作」を取り出すことができ、それを「回転可逆操作」「連結可逆操作」「次元可逆操作」と言います。生後半年間は「回転可逆操作」を特徴とする時期で「回転可逆操作の階層」(「乳児期前半」にあたります)、生後半年を越えて1歳前半までが「連結可逆操作の階層」(「乳児期後半」)、さらに「1歳半の節」からが「次元可逆操作の階層」となり、この第3の階層は7,8歳頃まで続きます。「階層」とは複数の段階を含み込んだ、より大きな段階のことです。階層のなかには複数の段階を含むと書きましたが、上記理論では、それぞれの発達の階層に3つずつの発達段階があるとします。第1段階、第2段階、第3段階と進んでいき、次は第4段階かと思いきや、そうではなく、新しい質をもった次の階層の可逆操作の獲得に進んでいくのです。つまり、まるで螺旋(らせん)階段をのぼっていくような過程です。この螺旋構造については、『上巻』「Ⅲ
第1章 乳児期の発達段階と発達保障」で説明しています。
「回転可逆操作」から「連結可逆操作」、「連結可逆操作」から「次元可逆操作」などと可逆操作の質が大きく変わる「飛躍的移行の時期」、すなわち「大きな発達の節」として取り出せるのが「6、7か月の節」「1歳半の節」「9歳の節」です。
先に述べたように、「1歳半の節」に始まる階層が「次元可逆操作の階層」です。第1段階が「1歳半の節」である「1次元可逆操作期」、第2段階が「4歳の節」である「2次元可逆操作期」、第3段階が「7歳の節」である「3次元可逆操作期」です。
乳児期の「6、7か月の節」(「示性数1可逆操作期」)では、2つの対象、つまり「対」を操作して見比べや持ち替えという活動を行ない、違いがわかり、選択したり、つなげたりという「可逆操作」を獲得していくのでした。「1次元可逆操作期」では、同じように新しい「対」の操作ができるようになるのですが、今度は頭のなかに「対」を形成し、それを並列させて、「…ではない…だ」と可逆操作し、頭のなかで選択したり、活動を切り替えたり、関係をとらえる思考ができるようになります。「2次元可逆操作期」では、「対」を並列させるだけではなく、「大きい-小さい」「よい-わるい」などの対比、比較という「もう一つ」の操作が可能になり、ものごとの意味や価値を理解したうえで、選択や思考ができるようになります。さらに、たとえば一方の手でハサミを持ち、他方の手で紙を持って、意図した通りに曲線を切るというように、左右の手の活動を分化させたうえで、「…しながら…する」と協応させることができるようになります。つまり、「2次元」とは二つの操作が結合することなのです。「3次元」の入り口(「3次元形成期」)になると、「大‐小」など二項の対比のなかに「中」をとらえはじめます。だから、ものごとを「だんだん大きくなる」というような「つながり」と変化において「すじ道立て」て理解したり、文脈を作りながら話すことができるようになります。このつながりと変化をとらえる力によって、時間軸などの3つめの単位も加えた操作の結合になるのが「3次元可逆操作期」です。たとえば、「きのう‐きょう‐あした」の関係を理解し、「きのうのつぎがきょう」「あしたのまえがきょう」などとわかるようになるでしょう。こういった「3次元の世界」については、『みんなのねがい』連載の第9回と第10回でお話しする予定です。
すでに述べてきたように発達は、欲求を自分の発達への要求に高めつつ、他者を含む外界にはたらきかけ、外界をよく知りつつ新しく創造し、自分に取り込んでいく過程です。そのとき、自分自身をも対象としてはたらきかけ、新しい自分を創造していくことになります。その外界と自分にはたらきかける活動に共通する特徴として取り出されたのが「可逆操作」です。そこには、「行き‐戻り」すなわち「可逆」という性質の操作があり、各階層において一つから二つ、二つから三つというように、新しい操作が加わって複雑化していくのです。
それぞれの段階には、まだその可逆操作が未確定な、文字通り作られつつある「形成期」があり、「1次元可逆操作期」には「1次元形成期」(1歳前半)が先立って存在しています。この「形成期」は、未確定ゆえの不安定さを子どもの心理に惹き起こし、それをいかに乗り越えていくかが大切なことになります。「2次元形成期」は、「大きくなった自分」を認めたい、認めてもらいたいゆえに葛藤が大きくなり、人格形成にとって大切な時期です。「3次元形成期」は、「だんだん大きくなってきた」自分の変化への手ごたえを感じつつ、「9、10歳の節」を乗り越えていくための「生後第3の新しい発達の力」を誕生させていく発達の画期です。これらの発達の階層‐段階についての理解をより深めるために、『上巻』「Ⅱ
発達理論と教育・保育の実践」をお読みいただければと思います。
「二次元の世界」を開く
「もう一つ」の第5回で、「器への積木の入れ分け課題」について説明し、次のように予告しました。
「1歳半の節」を越えて2歳になる頃には、ていねいな入れ分けを行なわなくなり、一方にたくさんの積木を入れて、他方に残りの少しの積木を入れるようになります。そういった「重みづけ」を創り出すようになるのが「二次元の世界」の入り口の姿です。
2つの器(お皿)と8個の積木を用意し、「こっちのお皿とこっちのお皿に半分ずつ分けてね」「おんなじずつ、ワケワケしてね」と子どもに声をかけます。「1歳半の節」の前、1歳前半の子どもたちは、器に入れるという定位的活動を続けて行なっていくのですが、片方の器だけに「…ダ、…ダ」という入れ方をしていきます。「1歳半の節」になると、片方の器に入れていき、「こっちデハナク、こっちダ」とばかりに、もう一つの器にも入れ、結果的に両方のお皿に入れ分けることがよく見られます。また、一つの器に全部を入れた後に、もう一つの器に入れ替え、また元の器に戻すといったお皿ごと入れ替えるような行動をみせる場合もあります。ただし、決して「半分ずつ」「おんなじ」といった関係理解ができているわけではありません。2つの器という対をとらえ、「こっちにも、こっちにも」と両方に気持ちを配っていこうとするプロセスが面白い時期です。お砂場でも、2つのコップに交互に砂を入れていったり、コップからコップへと何回も入れ替えを繰り返すことを楽しむ時期ですよね。これを「もう一つ」第5回では、「…ではない…だ」という「1次元可逆操作のリハーサル」と説明しました。同じことを食事の際にもしようとするので、おかあさん・おとうさんの苛立ちが強まることもあるでしょう。
では、2歳になる頃には、なぜそうしたていねいな入れ分けをしなくなるのでしょうか。実際のやり方は様々ですが、片方の器に1個だけ入れて、残りはもう片方に入れたり、片方の器に全部を入れたあとに、もう一つの器に1個だけ入れ替えるといった分け方をすることがあります。また、ちょっとだけ入れた器を相手(検査者)にさしだしたり、逆にたくさん入れた器を隣にいるお母さんに渡すような行動をすることもあります。そこには、子どもが、単に対をとらえているだけではなく、「こっちにいっぱい」「いっぱい入っているのを大好きなお母さんに」といった何らかの重みづけをしようとしている姿があるのだと考えます。赤い積木と白い積木など2色の積木を使うと、よりそうした選択性が強まります。

そして、「大きい―小さい」「半分」といった比較がしっかりしてくる2歳後半になると、しっかり見比べて半分ずつになるように分けるようになります。さらに、「こっちがあなたのお皿、こっちがお母さんのお皿」などと意味づけると、その意味づけがわかったうえで、自分の思いを込めて分けようとするようになります。
この配分課題は、正解がはっきりしているようなものではなく自由度の高い課題であるために、発達検査として標準化することは難しいですが、だからこそ面白いと思っています。そもそも「分配する」という行為は、人間の進化の歴史においても重要な意味をもつ行為であり、そうした人間や社会の歴史も感じさせてくれるというのは大袈裟でしょうか。
「みかけの重度」問題について
『みんなのねがい』9月号では、重度の脳性マヒ、難治性てんかんなどのある重症児のなかに、その機能障害の重さからは推し量れない言語や概念による理解が可能な子どもがいることをお話ししました。
「アヤちゃん」は、発達検査を通じて「大きい-小さい」などの対比的概念の理解が可能であることがわかりました。そして、お姉さんの学校の「給食」という包含性のある言葉に興味をもち、そのメニューの一つである「海苔」に心がひかれたのです。対比的概念を理解してはいますが、自信をもってそれを選択し、決めきることができない心の動揺もあり、3歳頃の「2次元形成期」にあるとみられました。
こういった機能障害の重い子どもたちに対しては、通常の発達検査を用いての発達診断を行なうことはできません。たとえば、「新版K式発達検査」(京都国際社会福祉センター刊)は、「姿勢・運動」「認知・適応」「言語・社会」という3領域で検査の項目が構成されていますが、運動や言語の機能障害がある場合には、わかっていたとしても、いずれの領域の項目も応答することはほとんどできません。
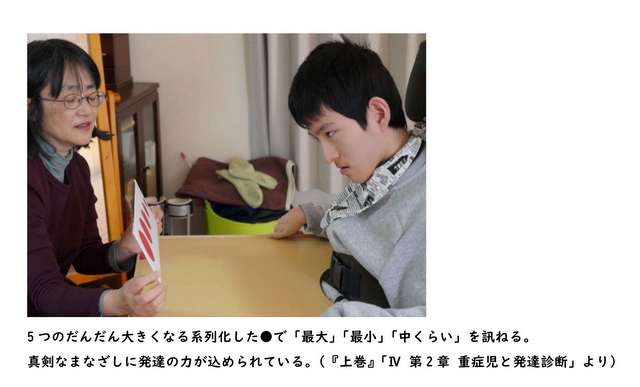
そこでアヤちゃんに「大小比較」課題を問うときには、視線での応答を求めることになったのです。さらなる発達診断のために、5つのだんだん大きくなる系列化した●を示し、「一番大きい」「一番小さい」「中くらい」などを問うこともあります。「だんだん大きくなる」という系列や「中くらい」がわかるということは、先に述べたように二項の「対比」「比較」から進んで、「大中小」などの三項の理解ができるということです。
アヤちゃんは随意的な眼球の運動と視覚認知をもっていたことによって、視線の応答による発達検査が可能でしたが、重症児の場合、視覚障害をあわせてもっていることがあります。そのときには、たとえば「口はどれですか」「耳はどれですか」などと身体部位を訊ねてみます(新版K式発達検査では「身体各部」)。口を開いてくれたり、頸を回して耳を検査者側に向けてくれるようなしぐさをしてくれることがあります。こういった身体部位をわかって応答できるのは「1次元可逆操作期」です(「もう一つ」第4回の写真解説)。そのうえで「もう一つの耳はどれですか」と訊ねると、頸を動かして反対の耳を向けてくれることもあります。一方と他方(反対)という「対」の関係を認識するのは、ちょうど2歳頃です。
視覚障害があると、「大きい-小さい」などの対比的概念の弁別について、図版を示して訊ねる課題は行なえません。そのときは、「口を開けてごらん」を問うてから、「もっと大きく開けられるかな」と訊ねてみます。対比的概念を獲得している場合には、明瞭に大きく開けてくれるでしょう。また「新版K式発達検査」には「泣いている顔はどれですか」「笑っている顔はどれですか」を図版の顔の絵から弁別する「表情理解Ⅰ」(2歳前半の課題)、6つの表情の絵から「怒っている顔」「喜んでいる顔」「ビックリしている顔」「悲しんでいる顔」を弁別する「表情理解Ⅱ」(3歳前の課題)がありますが、これも視覚の制約のもとでは行なえません。そんなとき「うれしい顔をしてごらん」「怒った顔をしてごらん」「泣いている顔をしてごらん」と問うてみます。視覚障害ゆえに他者の表情変化を認知しにくい子どもたちなのですが、自分の表情で表現してくれることがあります。「喜ぶ」「怒る」「泣く」といった日常的に生起する自分の感情を理解して、イメージすることができるようになっているのだと思われます。「親指はどれですか」「小指はどれですか」に、その指を動かしたり、手首をゆっくりと回して答えようとすることもあります。こういったはたらきかけをするときには、ゆっくり、じっくり、子どもを信頼して待つ気持ちで向きあいます。詳しくは『上巻』「Ⅳ
第2章 重症児と発達診断」、白石正久『障害の重い子どもの発達診断』(クリエイツかもがわ、2016年)を参照してください。
さらに大切なことは、発達検査への応答だけではなく、子どもの「まるごと」の姿を受けとめることです。たとえば親御さんと私たちの会話を聴こうとしていることに気づくこともあるでしょう。「きょうだい」が学校に通えなくなっていること、お父さんのお給料が減ってお母さんが働き始めたこと、学校の先生がなかなか親子の思いをわかってくれないことなどが話題になると、つらそうに涙を流すのでした。その傾聴、つまりおとなの話に一生懸命に耳を傾けている姿に、言語の理解が確かにあるだけではなく、ともに生きるものとしての感情とその機微への共感をもっていることを強く印象づけられるのです。
機能障害の重い自閉スペクトラム症と「みかけの重度」問題
この「みかけの重度」問題は、重症児に限られることではありません。たとえば、自閉スペクトラム症(以下では自閉症)があり、発語がほとんどなく、行動の困難がある子どもたち、あえていうならば発達の障害が重いように見え、重度感のある子どもたちのなかに、概念や文脈の理解が可能な子どもがいるのでした。
彼らは、モノを噛む、隙間に次々と入れる、水道の蛇口の水を叩いて飛ばすなどの行動をしていることがあります。学校から帰宅すると台所や洗面所で水遊びを飽かず続けたりするので、家族にとっては大きな負担になっていることでしょう。手首の運動によって筆記具などの道具を操作したり、目標を定めてそこにあわせるという定位的活動を続けることが苦手なようです。「はめ板回転」では、回転後に円板を入れようとしなかったり、「お手つき」をして、しばらくしてから入れ直すことがほとんどです。
つまり、いっけん、「…ではない…だ」と切りかえながら調整する1次元可逆操作の獲得に向かいにくい、発達の障害の重い子どもたちでした。そういった操作が求められると、手にしたモノを口に入れて噛む、口に入れて引きちぎるなどを始めることがあり、それを制止されると、跳びはねたり、着衣を破ったり、自分の手首を噛むようなことがあります。こういった口を基点とした行動は、不安や緊張とたたかい、かつ自分の思いを表現できず、理解してもらえないことへの訴えのようにみえます。そうせざるを得ない背景状況にある文脈を理解することが、まず求められているのです。
私は、こういった事例を整理しながら、可逆操作が求められる苦手な活動や、結果の「出来-不出来」「成-否」が問われる活動に取り組まなければならないときに、それを求めてくる他者の意図への不安感や拒否感が強くなっているように思いました。とくに、自分のことを試すように接近してくる他者や、そういった他者のいる場所への不安や拒否が、ありありと感じられるのです。それは、運動障害とも言える自分の機能の制約をよく理解していること、それなのに、そこにあえてはたらきかけようとする他者の意図に強い感受性と洞察をもっていることの結果にみえました。さらに重症児の場合と同様に、周囲の会話へ耳を傾けたり、チラッと目を向けようとする姿がありました。つまり、重度感のある姿とは対照的に、確かな自己認識と他者心理への認識を窺わせるのです。
発達検査では、「だんだん大きくなる」系列化した5つの●が描かれた図版を提示して、「最大」「最小」「中くらい」を尋ねると、からだや手を振るような行動をしばらく繰り返してから、手を伸ばして応えてくれたりするのでした。それは、人さし指をまっすぐ伸ばす「指さし」ではなく、手先でそっと触れようとする示し方です。これらのことは『障害の重い子どもの発達診断』「機能障害が重い自閉症の子どもの発達とその診断」(211~223ページ)で解説しました。
全障研の委員長であった茂木俊彦さんの『障害児教育を考える』(岩波新書、2007年)を読まれた方は多いでしょう。「筆談で表現する自閉症児」(169~174ページ)で、大阪の教員であった三浦千賀子さんの『自閉症の中学生とともに-松原六中・青空学級担任日誌』(未来社、2006年)のなかの知世ちゃんへの実践が紹介されています。
三浦さんは知世ちゃんを絵本の世界に導きたいと願いましたが、のってきてはくれませんでした。しかしある日、『すてきなひらがな』(五味太郎、講談社)の「て」の絵のページで「手のひらを太陽に」を歌うと、本をチラッと見ようとしたことに気づきます。知世ちゃんは歌が好きなのでした。「赤とんぼ」の歌の情景描写にうっとり聴き入っている姿にも出会います。「負われてみたのはいつの日か」を聴きながら窓際に走り寄り、指で輪をつくって、そこから空を見上げていたのです。
「赤とんぼ」の歌の頃、「知世ちゃんとの距離は一歩近づいたように思えました」「内言語は、たくさんあると思えました」とあります。きっと三浦さんが知世ちゃんの本当の心に気づいた時期だったのだと私は思います。それらをきっかけとして、「ひらがな」に興味がもてるように、ていねいな教材の工夫と指導を始められます。この指導は、試行錯誤のある粘り強い道のりでしたが、ここで紹介する余裕はありません。
そしてある日、知世ちゃんの手に三浦さんの手をそっとのせて語りかけると、知世ちゃんは手にした鉛筆を動かして文字を書き始めたのです。そのやりとりのなかで、映画「対馬丸」を観て、「学童疎開」などの意味まで理解していることがわかっていきました。そして、「あんなせんそうは もう二どとおこらないでほしいとおもいます。ちかこせんせいはどうおもっていますか」と書いたのです。
三浦さんは、入学直後の窓ガラスに突進して舐めようとする姿などに翻弄されつつも、常にステキな絵本や歌・リズムの世界に誘い入れたいという思いをもって、いっけん無関心な知世ちゃんの前で、まるで一人芝居を演じるように、読み聞かせたり、歌ったのです。そのなかで、「チラッと見てくれた」「うっとり聴き入っている」などの姿をとても大切なものとして受けとめ、知世ちゃんの本当の心に接近していきました。その実践者としての感受性に、子ども理解の要諦があるように思われます。
これらの事例は、「僕たちは、見かけではわからないかも知れませんが、自分の体を自分のものだと自覚したことがありません。いつもこの体を持て余し、気持ちの折り合いの中で、なげき苦しんでいるのです」(東田直樹『自閉症の僕が跳びはねる理由』角川文庫、56ページ)という当事者の言葉が、ぴったりと説明してくれているようでした。こういった当事者の「筆談」などによる手記に、真実性を疑う見解が述べられることがありますが、そう簡単に否定できるものではないと考えます。もともと自閉症はその「スペクトラム」という概念通りに拡がりと多様性をもった症候群であり、一人の事例が自閉症のすべての特徴を包含したり代表するわけではありません。さらに大切なことは、一人ひとりの心のありようは、他者によって容易に解釈され、決められるものでなく、ただ一つの真実として本人のなかに存在しているということです。先入観をもたず、行動に目を奪われることなく、いつも子どもに問いかけ、思いを聞き取りながら、子どもの真実に近づいていきたいと願います。
胎児性水俣病の人びとのこと
「みかけの重度」問題を提案して30年近くが経ちました。事例検討を積み重ねる私たちの研究方法について、実証性が乏しいとの意見もあり、それを受けとめていくことは容易ならざることだと思っています。その実証性の求めに応じて「実験」という方法を用いたとして、子どもたちはその課題に応えてくれるでしょうか。仮に実験によって子どもの能力のある部分を取り出すことができたとして、それは大切な認識ではありますが、その外にある子どもの心の事実に目を向けないならば、狭い子ども理解で終わってしまうように思います。
私たちの研究は、私たちのためのものではなく、この子どもたちの心の表現を拾い、子ども自身にそれが事実であるかを尋ね返して、一つひとつの事実を子どもとともに確定していく共同の所産です。そこには長く続く子どもとの心の対話があり、それを実際に展開する教育や療育の実践が必要です。それゆえに、実践とのつながりのなかで、私たちにはみえていないたくさんのことにも視野が広げていけるのでした。
実は、「みかけの重度」問題の提案を後押ししてくれたのは、胎児性水俣病の人たちであり、彼らと向きあう人びとの姿でした。なかでも、患者の立場に立って水俣病の原因を追究し続けた故・原田正純さん(熊本大学医学部)の言葉でした。
原田さんは、胎児性水俣病のなかでも最も障害が重かったという中村千鶴さん(23歳で亡くなる)が、自分(原田)の写真を欲しがっていると施設でいっしょに暮らす清子さんから聞いて、千鶴さんに尋ねました。
「同じ胎児性患者の加賀田清子さんが、『ちーちゃんが先生の写真をくれって(くださいと)言っている』と意外なことを言いました。清子さんの言葉は辛うじて分かるので、びっくりして『うそだろう。わたしをからかうなよ』と言いましたが、清子さんが真顔なので、千鶴さんのベットへ戻り『写真が欲しいのほんとう?』と覗き込むようにして訊ねました。千鶴さんははにかむように笑いながら、うなずくように全身で表現するではありませんか。医師としての経験がまだ未熟だったとはいえ、この子たちにそのような感情の動きと表現力があるとは考えていませんでした。無知な自分を恥ずかしく思いましたし、そのような教育を受けなかった(当時の)医学教育とは何であったかと思いました。それにしても、わたしには『あーあー』としか聞き取れない千鶴さんの言葉が、同じ障害をもつ清子さんにどうしてわかるのでしょうか」(原田正純『宝子たち-胎児性水俣病に学んだ50年』弦書房、2009年、111~112ページ)。このことについては、『上巻』「Ⅳ
第2章 重症児と発達診断」でもふれました。また、このエピソードは、原田正純『水俣病は終わっていない』(岩波新書、1985年)でも述べられています。
事実に対して誠実であるだけではなく、水俣病に侵された人びとを単に研究の対象とはせず、一人ひとりを慈しみ、救済のための研究に人生を捧げた研究者の姿勢には、あまりにも多くのことを学びました。胎児性水俣病の人びとは私たちとまったく同年齢であり、その痛みのあるからだをもって同じ長さの人生を生き、老年期を迎えています。そのことを想うときに、この人たちの発達保障に無自覚ゆえに何もしてこなかった自らの無力さを感じます。
千鶴さんが生まれたのは水俣の茂道(もどう)です。その海とミカンの丘は、今は本当に美しく、訪ねることしかできない私たちを、やさしい光のなかに迎えてくれます。

今回の学習参考文献
・白石正久・白石恵理子編(2022)『新版・教育と保育のための発達診断・上巻』
・白石正久・白石恵理子編(2020)『新版・教育と保育のための発達診断・下巻』
・白石正久(2016)『障害の重い子どもの発達診断』クリエイツかもがわ
障害者権利条約を考える
日本への「事前質問事項」が2019年秋に国連で採択され、日本審査となる「建設的対話」は2020年夏が予定されましたが、コロナ禍の状況から延期されました。政府は「事前質問事項」への回答案を作成し、JDFや日弁連などと懇談しながらまとめようとしています。
そして、いよいよ2022年8月22日、23日にジュネーブの国連で日本審査が行われます。
◆国連TV(中継・録画)8月22日・23日 国連障害者権利条約 日本審査など
◆JDF(日本障害フォーラム)総括所見用のパラレルレポート等
◆初回の日本政府に報告に関する質問事項への回答案 2021.6.28
◆JDF(日本障害フォーラム)日本の総括所見用パラレルレポート(パラレポⅡ)2021.3
などを掲載しています。
▶詳細は「障害者権利条約を考える」ページへ
大会アピール
3年間にも及ぶ新型コロナウイルス感染症の影響。今も激しく続けられるウクライナでの戦争。そして、各地で引き起こされる自然災害。障害のある人びとのいのちと権利保障をめぐる歴史的な危機が続くなか、全国障害者問題研究会は、2022年8月6日、7日の2日間、第56回全国大会(兵庫2022)を開催しました。
障害のある人びとの権利保障のうねりを生み出してきた開催地・兵庫のとりくみは、全国の実践や運動を大いに励ましてきました。30年前、「花ひらけ15の春」を掲げて、養護学校の高等部全入を求めた「ひゅうまん・ぼいす」の運動は、本人と親の熱いねがいを要に全県のとりくみへと広がり、高い壁をうち破って障害のある青年たちに後期中等教育への扉をひらきました。こうして無数の人びとの悲しみとねがいを刻んできた発達保障のバトンを受けとろうとする人の輪は、今、確かに広がっています。
記念講演と特別報告を通して、人びとの暮らしを破壊し無数のいのちをうばい去る戦争、そして、障害や病気のある人のいのちの始まりとつながりを断ち切ろうとする優生思想は、国家や社会に役立つかどうかで人間をふるいにかけるという点で深くつながっていることを学びました。そして、平和と人権をねがう世界中の人びとと手を結んで、力強くあゆんでいきたいとの思いを新たにしました。子どもたちやなかまたち、そして家族のささやかなねがいを「かるた」に込めて分かち合おうとした文化交流企画では、障害のある人びとが自らのライフステージにふさわしく生活の質を高めていくことが、すべての人のいのちと権利が守られる社会の実現に向かう、ゆっくりではあっても確かなすじ道であることをユーモアたっぷりに示しました。
兵庫の発達保障のあゆみからつむぎ出された「久しぶりに話そうや、私たちのねがい」という大会テーマは、わたしたちの内に湧き起こるねがいであるとともに、暴力の連鎖を断ちきり、社会の分断を乗りこえるために欠かすことのできない対話と連帯を呼びかけるものです。分科会の討論では、惻々と胸をうつねがいが綴られたレポートをもとに、それぞれの実態を持ち寄り、実践を語り合うことで、ねがいが明らかとなり、そのねがいを束ねてみんなで共同することが、具体的な制度の改善につながることを学びました。
戦争と障害のある人びとの幸福は絶対に両立しません。わたしたちは「戦争をする国づくり」をすすめる憲法改悪を許さず、すべての人の発達が花ひらく平和な社会を、未来に生きる人たちに手渡していきたいとねがっています。「私たち抜きに私たちのことを決めるな」という理念の下で具体化された障害者権利条約は、一人ひとりのねがいを聴き合い、語り合うことが、人権保障の礎になるという発達保障の研究運動が大切にしてきた思想を国際的な理念に押し上げました。このことに確信を持ちたいと思います。
身近な地域や職場で、ともにねがいや悩みを語り合い、日々の暮らしや実践をゆたかにするために譲れないものは何か、新たにつくり出すべきものは何かを明らかにしていきましょう。そこに多くの人を誘いあって参加し、語り合いと学び合いの輪を大きく広げていきましょう。日本国憲法が社会の隅々をあかるく照らし、障害者権利条約が確かに生きる輝かしい未来にむけて、発達保障の道をともに切りひらいていきましょう。
2022年8月7日
全国障害者問題研究会 第56回全国大会(兵庫2022)
▶PDF版はこちらに
2022年8月
白石 正久・白石 恵理子

第5回 1歳半の発達の節(その2)
連載第5回(8月号)の「『本当の要求』とはなにか ― 自閉症児と『一歳半の節』」では、横軸に私たちの発達相談という仕事を通して考えた、地域で暮らす、生きるということの発達にとっての意味を、縦軸に「1歳半の節」における発達の障害をとりあげました。
変化する素材と道具
8月号では、「1歳半の節」において「Aの次にはB」「Cの上にはD」などと言う時間的空間的な「むすびつき」が先行し、それゆえに思いや期待にそわない現実とぶつかりながら、「…ではない…だ」と思考して「切りかえる」可逆操作を獲得していくことができると述べました。この「1次元可逆操作」の獲得が、運動、活動、対人関係、話し言葉、自我などの発達の土台として大切な役割を果たすことを、「もう一つ」第4号とともに、『新版・教育と保育のための発達診断・上巻』(以下では『上巻』)の「Ⅲ
2章 1歳半の質的転換期と発達保障」「Ⅳ 自閉スペクトラム症と発達診断」、『新版・教育と保育のための発達診断・下巻』(以下では『下巻』)の「Ⅱ
3章 1歳半の質的転換期の発達と発達診断」で深めていただければと思います。
そして、自閉スペクトラム症(以下では自閉症)は、この可逆操作の獲得に発達の障害が現れることも述べました。この傾向は自閉症に限られず他の障害、あるいは障害はなくても「発達の偏り」として起こりやすいものです。
「もう一つ」第4号のなかに「はめ板回転課題」の解説があります。
1歳すぎの子どもたちは、さっきと同じように目の前の孔に入れようとするのですが、それでは円板は入りません。「入っていない」ことに気づいて、怪訝な表情になったり、四角孔の上でカタカタさせたり、検査者をじっと見たり…なかには、立ちあがってしまう子もいれば、入っていなくても「気にしていない」子もいます。そのうち、「ここじゃないのかな…」とばかりに、別の孔にチャレンジしようとしたり、円板をひっくり返してみたり、なかには基板の下から入れようとしたりと、様々な試行錯誤をはじめます。これらは、いずれも検査上は「不通過」、「できない」と評価される姿なのですが、そこには1次元可逆操作を我がものとしようと努力する大切なプロセスが潜んでいるのです。
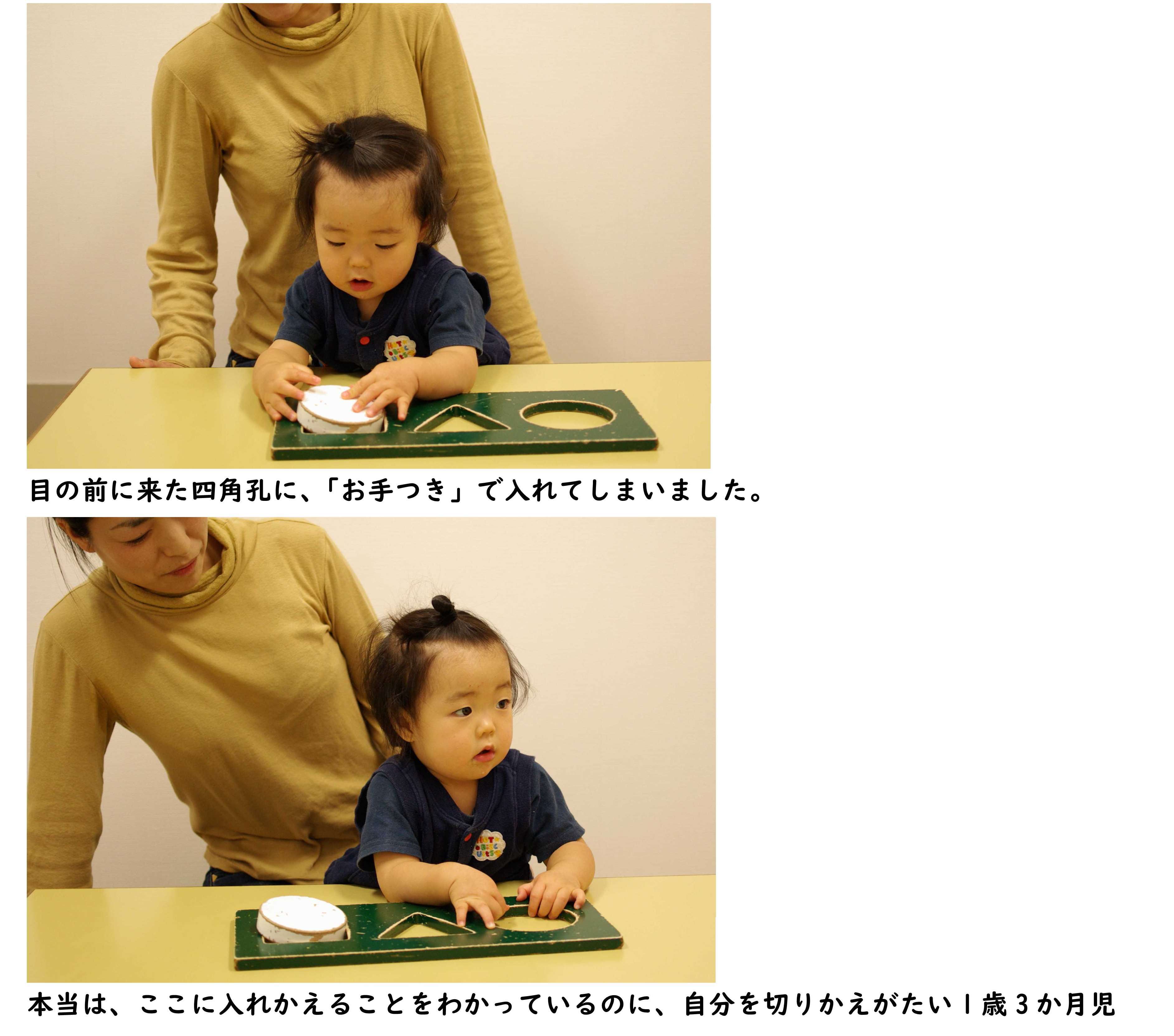
子ども本人は円孔に入れようとする自分なりの「つもり」の達成のために一生懸命なのですが、この「さまざまな試行錯誤」を近くで見守る人はイライラするものです。だから、「そこじゃないでしょ」と言葉をかけたり、手を出してしまったりするかもしれません。きっとそういったことは、子どもを混乱させる役割しか果たしません。「…ではない…だ」と状況のなかで自分を切りかえたり、調整していくためのかけがえのない「自分づくり」をしているのであり、その自由で主体的な活動を心から応援し、見守りたいと思います。1歳前半の子どもは、その「入れ切る」ことを目的とはしておらず、むしろ「…ではない…だ」のリハーサルを重ねているようにもみえます。そのリハーサルの豊かさをみるためには、「はめ板」ではなくて、もっと自由度があって、さまざまに操作できる素材や道具の方がよいはずです。
保育所の砂場で遊ぶ0,1歳児の姿を見てください。片手にコップをもち、砂をすくってはひっくり返し、両手にコップをもって一方のコップですくった砂を他方のコップに移しかえ、スコップですくった砂を器に入れてはひっくりかえし…。「1歳半の節」の前後において、子どもは変化する素材と道具の創り出す活動に魅入らされていきます。
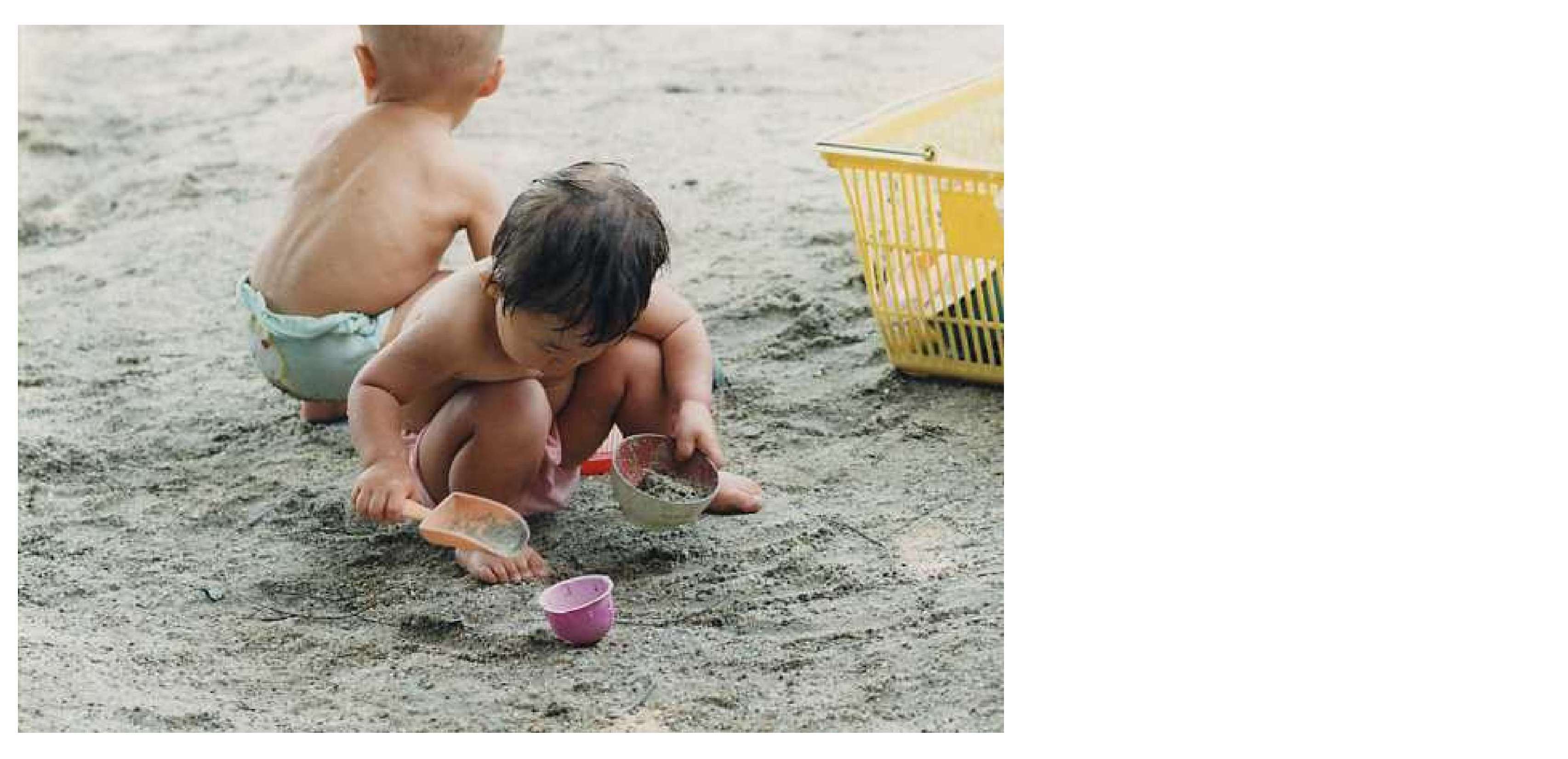
そういった自由度を発揮できる発達検査にしようと、田中昌人さん、田中杉恵さんは、「器への積木の入れ分け課題」を考案しました。8月号の30ページの写真です(『子どもの発達と診断2』大月書店、また『下巻』85ページ)。1歳前半では、まだ「…ではない…だ」が内面化していないために、一方の器に8個すべての積木を入れてしまいます。しかし、他方の器がカラであることに気づいて、その器に全部の積木を移しかえます。そしてまた、カラになったもとの器に移しかえることを繰り返します。この移しかえで、まさに「…ではない…だ」のリハーサルをしている感じです。
1歳後半になると頭のなかで考えて、一つあるいは少しの積木を左右の器に「コチラではないアチラだ」と配分していくのです。子どもは、自由に操作できる素材と道具であるゆえに、単に自由であるだけではなく、移しかえたり重ねたりと、発展性のある活動を展開するでしょう。しかも、1歳後半になれば、相手の意図を受けとめて配分を試みたことを意識しており、自分なりの入れ分け方をした器を、相手に「どうぞ」という感じで差し出してくれるようになります。自分のなかで「…ではない…だ」を操作するだけではなく、相手の意図を引き受けて、自分の意図として応え返すという自他のあいだでの可逆操作もみることができるでしょう。「もう一つ」の次号で扱いますが、「1歳半の節」を越えて2歳になる頃には、ていねいな入れ分けを行なわなくなり、一方にたくさんの積木を入れて、他方に残りの少しの積木を入れるようになります。そういった「重みづけ」を創り出すようになるのが「二次元の世界」の入り口の姿です。
変化する素材への抵抗を乗り越える
変化する素材の代表例として、砂場の「砂」をとりあげました。皆さんのなかには、自閉症のある子どもの嫌いなものの一つだと思われた方もいるでしょう。手につき、新奇性のある素材は、彼らの教材として好ましくないと言われることもあります。
私たちは、そのことを固定的にみてはならないと考えてきました。『上巻』の「Ⅲ 2章 1歳半の質的転換期と発達保障」で述べましたが、砂遊びの輪に入ろうとしなくても、「外れていない外れ方」「なかまにはいっていく手がかりを遠くに示した外れ方」「やりたい思いを高めつつも、ドキドキしながら背中でようすを窺っている外れ方」をしているようにみえることはないでしょうか。
このような「行動は見えないけれど、心がみえる」という評価は、昨今の特別支援教育では、客観的な証拠がないとして「書き直し」を求められると聞きました。しかし心の動きは、誰であっても外に表れ出るとは限りません。その見えない心理を大切にして、わかりあい、互いを尊重していこうとみんな努めていると思います。障害のある子どもの心の動きは、「見える」ものだけで評価するのでしょうか(目で見えるときには「見える」、心の目でみえるときには「みえる」と、私たちは表記します)。
証拠は、時間の経過のなかで子どもが示してくれます。ある日、気がつけば砂場の近くに寄ってきている子どもの姿があったりします。手のひらに載せた砂を「だいじょうぶ、だいじょうぶ」と応援しながらそっと差し出すと、指先で触って、走って行ってしまうかもしれません。でも気がつけば、また近寄ってきています。そうやって、気持ちを支えてもらい、ときには先生に勇気を引き出してもらって、一つひとつの矛盾、葛藤を、この子らも乗り越えていくのです。そのときの指先には、しだいに勇気が満ちていくようです。
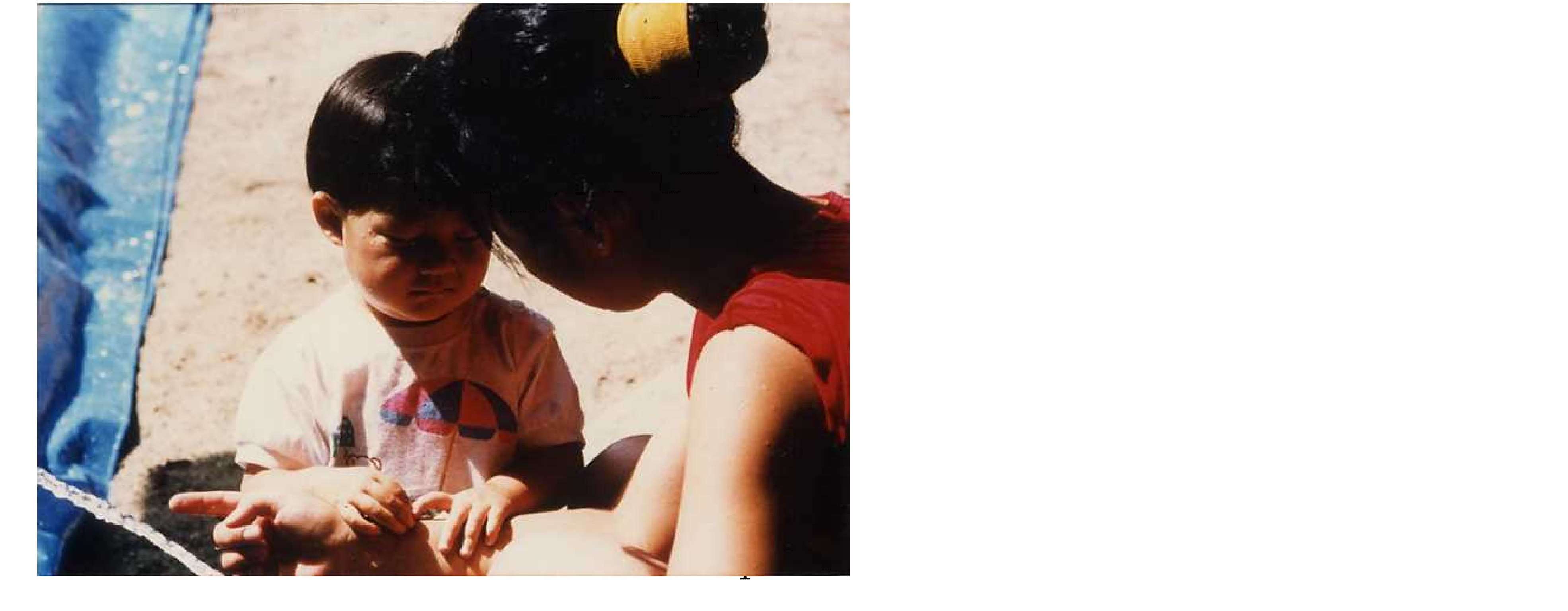
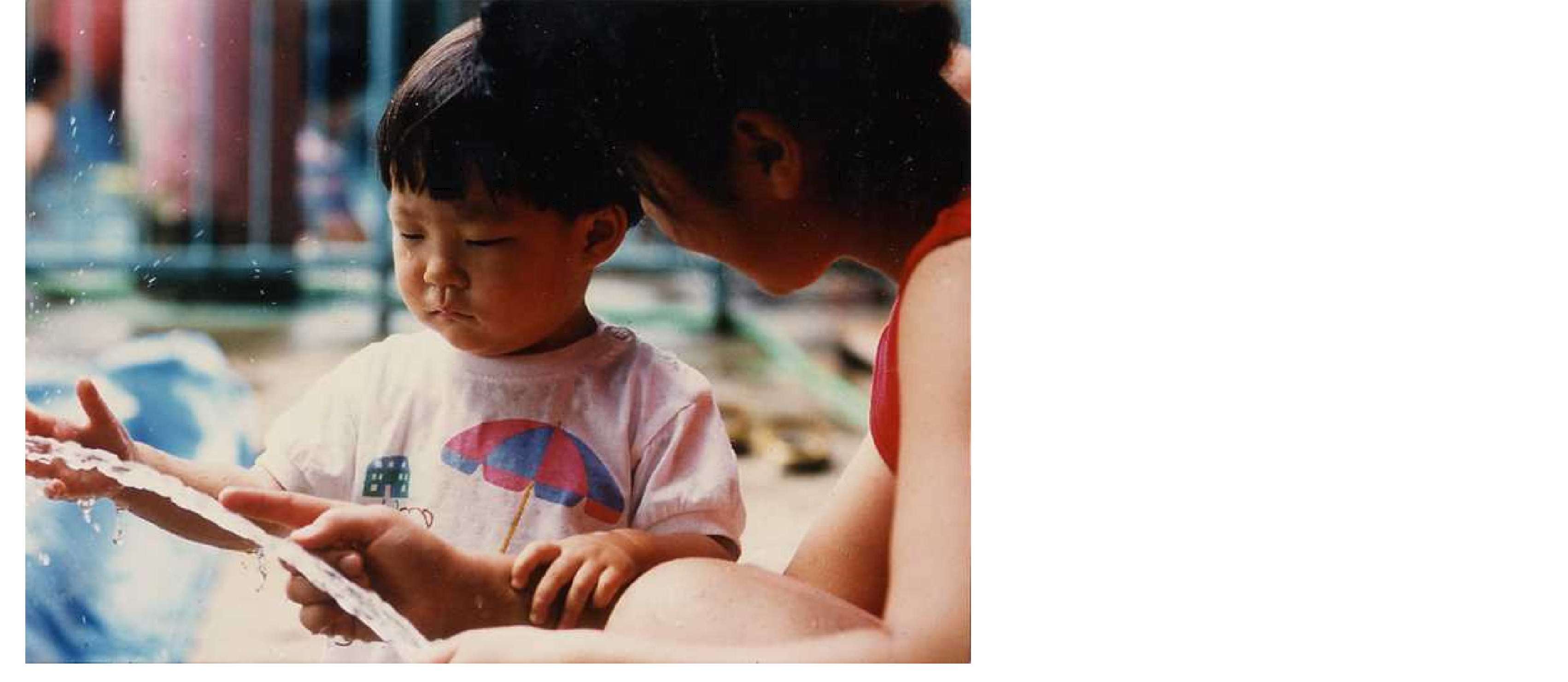
変化する素材への興味は、砂ばかりではなく、いろいろなものに拡がっていきます。手で触れたときの変化の喜びを、いっしょに抵抗を乗り越えた人とまなざしを交わしあって共有するようになっていきます。子どもは、素材にはたらきかけていくなかで、「…ではない…だ」と変化を創り出し、またその変化から「…ではない…だ」という可逆操作を、自らのなかに豊かに取り込んでいきます。変化する素材で、「…ではない…だ」という1次元可逆操作のリハーサルをしているようなものなのです。
「1歳半の節」で、器やスコップ、スプーンや櫛などの道具の意味を発見していくと、変化する素材へのはたらきかけはいっそう豊かになり、生活で憧れたことを手がかりに、プリンを作ったり、ごはんをよそったり、「みたて・つもり」遊びもできるようになるでしょう。
こういった素材や道具への興味は、年齢や経験の拡がりとともに変化していくものです。そのときの社会的関係のなかで意味をもつものに、心惹かれるようになります。8月号のコウジくんのように、牛乳瓶を洗う、野菜を袋詰めにするという広い生活経験に依拠したものに変化していくのです。
だから乳幼児期には乳幼児期でしか味わえない素材や道具とのふれあいがあります。10か月頃の「生後第2の新しい発達の力」が誕生するときには、砂や水などの変化する素材に指先でそっとふれて抵抗を乗り越えていきます。その指先が散歩で出会ったアリや小鳥、花などに伸びて、指さしとしての機能をもつようになります。そして、他者とともにその変化や発見を喜び、「第二者と第三者を共有する」関係を形成していくのです(白石正久「乳幼児の生活の組織化と発達保障」『障害者問題研究』第50巻2号、最新刊)。そして、音や色の変化を楽しむ感覚玩具よりも、生活のなかで見かける道具に興味をもつようになります。
児童発達支援は、利用契約制度になってから、「○○療法」を名乗る看板を掲げて利用者を集める動きのなかにあります。細切れの時間単位のなかで、「はめ板」をそのまま教材化したような「パズル」に取り組んでいるところもあると聞きました。そういった事業者は、乳幼児期の通園施設、通園事業、児童デイサービスが積み上げてきた発達保障の実践を知りません。狭い空間や短い時間での活動ではなく、土や砂、水、畑の作物などの変化する素材に、先生や友だちとともにからだをいっぱい使ってはたらきかけ、散歩で出会う生命あるもの、人びとの暮らしの姿に瞳を輝やかすような実践を、ぜひ知ってもらいたいと思います。そしてそういった実践が、心置きなく取り組める制度に改めていきたいものです。
幸福感においてつながる
8月号で、「1歳半の節」では、次のような発達がみられると書きました。
「対」の人間関係、つまり「わたしとあなた」において、自分の意図と他者の意図、自分のモノと他者のモノという自他を区別し、対立・葛藤しつつ調整ができはじめる(30ページ)。
自閉症のある人たちは、「他者」の意図を意識すること、それができるようになっても、他者の意図と自分の意図を調整することがむずかしく、混乱や拒否、あるいは従属や指示待ちという関係になりがちです。しかし、このことも決して固定的ではないことを、私たちは発達相談や実践の過程から認識してきました。
8月号で、コウジくんの姿を通して以下のように書きました。
最初に訪問したときに商店主がその仕事をしており、彼に手伝わせてくれたようです。そのていねいさにびっくりされたのでしょう。彼にとっては、そう受けとめてもらえたことがうれしかったのです(29ページ)。
コウジくんも洗瓶のエピソードにおいて、自分の挑戦をまるで我がことのように喜び、幸福感において他者とつながれる人がいるのだと実感したのでしょう。閉じてしまった活動や人間関係が未来に向かって開かれていく実感であり、そのことによって生活に「はりあい」を感じるようになっていったのだと思います(31ページ)。
この「幸福感においてつながる」とはどういうことでしょう。それは、発達の過程のなかに、そして日々の暮らしのなかに、その大切さを認識することができます。
・「第二者と第三者を共有する」
「生後第2の新しい発達の力」が誕生する10か月頃、子どもは自ら発見した生命のあるものを指さしで教えてくれ、入れたり、渡したり、放ったりの定位的活動ができ始めます。しかしまだ、そのことが他者の喜びや怒りにつながるとはわかっていません。「きれいなお花ねぇ」「じょうずやなぁ」「ありがとう」「そんなことしたら、アカンよ」などという言葉を添えられた他者の反応から、その意味をだんだん理解できるようになるのです。
すでに述べたように、このように「第二者」という大切な人と何ごとかを共有できるようになっていくことを、「第二者と第三者を共有する」と言います(田中昌人・田中杉恵)。心理学では、「三項関係」と言われますが、それでは子どもの主体性が表現されていません。10か月頃は、その「第二者」がこれまでの限られた関係から、他のおとな、そして友だちへと普遍化し、拡がり始める段階でもあります。そうやって新しい他者とつながったとき、子どもは本当にうれしそうです。その幸福感があるからこそ、もっと他者とつながって生きたいという、次の時間や空間への期待や要求が確かになっていくのでしょう。
・日々の暮らしのなかで
この「第二者と第三者を共有する」ことによって生まれる幸福感は、日々の暮らしのなかでかけがえのない姿として育まれていきます。
かつて『発達をはぐくむ目と心』(24~32ページ)で、深見憲『ひろしくんの本Ⅰ~Ⅶ』(中川書店、1999~2017年)を紹介しました。
「あの時の物凄い博の形相を思い出すだけで胸が痛み一生忘れることは出来ません。この時を契機に家族はどんな些細な興味の世界でも博の世界の中にどっぷりつかって楽しんで守っていこうと誓いました」(『ひろしくんの本Ⅳ』2004年、26ページ)。
博さんは、現在55歳になった自閉症のあるかたです。お母さんの憲さんが、その成長・発達と生活の過程を、『ひろしくんの本』として刊行されてきました。4歳のときにプレイセラピーの先生から「生活の内容を改善していくため」に、「こだわり」の対象となっているクラシック・レコード、おとぎ話のレコードや本を隠してしまって、戸外で思い切り遊んであげなさいという指導を受けました。その通りに庭の物置に隠してしまった日、「奇声と泣きわめきのすさまじいパニック」になり、食事も受けつけず、瞳もうつろになった姿を目の前にして、「これから好きなレコードをいっぱい聞こうな。毎日、博の好きなことをいっぱいしよう」と言いながら、お父さんはレコードと本を物置から持ち帰ったそうです。「自分たちの一方的な身勝手な押し付けをしてきたことを反省」させられ、いつまでもわが子の「瞳の輝き」が失せない生活をはぐくんでいきたいと決意したと綴られています。そのことが、後の家族の生き方の礎になったとも言われます(『ひろしくんの本
Ⅶ』、2017年)。
「興味の世界こそ自閉症児の至福の時であり遊びの世界である。付きあってあげるという感覚の方々には幼稚な世界と片づけられるが、年を追うごとに奥が深く夢の広がる世界はとても楽しいのである」(「成人期」『そだちの科学』第1号、日本評論社、2003年)。
「付きあってあげるという感覚の方々」は、胸に痛い言葉です。自閉症のある人たちが、心地よさ、楽しさ、なにごとかを成し遂げた喜びなど、さまざまな幸福感を求めていること、しかしそれ以上に状況や他者と自分がむすびつきがたく、悲しみ、苦しみをもって生きる時間が長いことを私たちは感じています。私たちもそうだと思うのですが、自他つまり「わたしとあなた」の関係でいろいろな齟齬や葛藤はあっても、それを乗り越えて共感できる関係が欲しいし、我がことのように受けとめあえる人とつながりながら、日々を生きたいのです。
自閉症のある人たちが示す行動、「特性」と呼ばれるもの、その背景にある発達の連関の「ずれ」は、本人の生きづらさの要因でもあります。それらは現実に存在しており、それを理解しようとすることは大切なことです。しかし同時に、それが「彼らは私たちと違う」という認識に留まってしまうことはないでしょうか。私たちは、ものごとを「違い」において理解する癖をもっていることを否定できません。困難をもちつつ、それを乗り越えて生きようとする人の精神、心理を、人間としての普遍性・共通性において理解しようとしなければ、「してあげる」「してあげなければならない」「はたらきかける」などと、心の離れたところから、あるいは高みから関わるようなことになってしまうと思うのです。そのことが、指導や支援の前提としての子どもを理解すること、子どもと関係をむすんでいくことを困難にしていることはないでしょうか。
成人になった博さんは、「第九を歌う会」に参加し、ケーキやクッキーを作って販売する「プティフールヒロシ」を開き、子どもたちへのおとぎ話の紙芝居の上演へと、地域の人びととの関係を拡げていきました。すべてが幼児期の「興味の世界」に根ざしています。今は、社会福祉法人の運営する食堂で、長く憧れであった食器や調理具の洗浄の仕事をして働かれているそうです。家族は、小さいときから「よくできました」ではなく「ありがとう」と受けとめあう関係を大切にして、ともに歩まれてきました。
地域の人びととのつながりは、自分の活動、仕事、そして存在そのものの意味を実感できる関係です。何ごとかを創造する喜びが、それを手にしてくれた人の喜びにつながったとき、明日もまたがんばろうと、未来に開かれた希望をもって生きることができるのだと思います(8月号、31ページ)。
地域、生活、労働と発達をつなぐ
療育や教育は、子どもの発達要求を踏まえ、「めあて」をもってはたらきかけ、子どもたちの姿から、さらに指導をつないで発展させていくという「時間の単位」をもった営みです。
一方、子どもやなかま、その家族は、家庭や地域のなかで「暮らし」という営みをつづけながら、さまざまな経験や人間関係を重ね、拡げていきます。この暮らしの営みは、必ずしも「めあて」をもたず、人生という悠久の時間のなかにあるともいえるでしょう。
振り返れば、8月号のコウジくんもすでに40年余の人生を歩いてきました。障害を告げられてから、幼児期に通った保育所の支えのなかで、地域の空間や人間関係に親子で歩み出し、地域に見守られながら暮らしてきました。そしてやがて、地域の人たちとのつながりを彼自身が求め、牛乳屋さんや八百屋さんでの「しごと」をすることになったのです。自分の活動を、「ありがとう」と受けとめてもらいながら、そうやって活動することの幸福感を知り、「はりあい」を感じて、学校を出てからの生活の礎をつくりはじめました。
人生を振り返ったときに、発達にとっての画期となったことがみえてくるものです。そのときに自分の活動の意味を感じ、これが自分の暮らしであり仕事なのだという意識をもてるようになっているはずです。それまでの淡々とした生活や労働の日々が、実を結ぶ瞬間です。
そういった長い時間とともにあって、「時間の単位」をもつ療育、教育などは、どんな役割を果たすことができるのでしょう。乳幼児の療育である児童発達支援さえ、その目的を「動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援」(児童福祉法)と定めています。障害のある子どもたちへの指導・支援は、社会生活を営むための技能の習得や適応のためにのみあるのでしょうか。適応とは、自分の生きる環境・社会や、すでに定められたものに適うようにするという意味です。つまり、子どもが受身となってすでにある社会生活の規準を身につけていくことが目的となるわけです。そこに、自分らしい暮らしや人生を創っていくきっかけを見出すことができるでしょうか。
結論を急がずに、私たちも暮らしと人生に視座をおいて、それに対して療育や教育に何ができるのかを考えていきたいと思います。7月号の羽田千恵子さんの実践から「子どもをつなぐ文化のねうち」を考えたのは、その答えを探す試みの一つでした。少し説明を加えておきたいと思います。
文化のねうちって?
かつて出会った脳性マヒによる肢体不自由と知的障害をあわせもつA子さんは、視線はあいにくいのですが、リズミカルな喃語によって気持ちを表出している子でした。発達検査場面では、積木にもはめ板にも手を出さず、私が働きかければ働きかけるほど、天井の蛍光灯に視線が吸い寄せられていきます。
そんなA子さんが、療育のなかで花瓶にお花を生けるときに、すっと手をのばし、茎の向きも少し調整しようとするのです。その姿を見て私は、「検査場面での自分の声かけの仕方が悪いのかな」「私との信頼関係ができていないからかな」と考えたり、「選択的にしか力を発揮できない弱さがある」と理屈づけようとしたりしていました。療育のなかでは、大好きな先生もいるし、お友だちもいて、個別の検査場面とは異なるのは当然です。でも、そのときの私には、彼女にとって思わず手を出したくなる「文化のねうち」には十分に気づけていなかったのです。
その後の発達相談で(その日は“中秋の名月”の翌日でした)、お母さんが「昨日は、家で月見団子をつくって、A子といっしょに花瓶にススキをさしたんですよ。わかってないと思いますけどね」と話されました。「わかってほしい」「できるようになってほしい」というより、そういう生活の一コマを我が子といつくしんでいることがすっと伝わってくるエピソードでした。今思えば、彼女にとって「花を生ける」という行為は、単なる操作ではなく、周りの人とつながっていく価値ある行為であり、幸福感を共有することすら予期していたのかもしれません。
羽田千恵子さんの言う「単に集団を保障するだけでは、一人ひとりのかけがえのない価値を引き出すことはできない、友だちとつながるには、共有できる世界、媒介する文化が必要」という思い、そして、そのために、子どももおとなもそれぞれにもっている「文化的もちあじ」を融合させていく妙味…これからの連載でもまた考えていきたいと思います。
今回の学習参考文献
・深見憲(1999~2017)『ひろしくんの本Ⅰ~Ⅶ』中川書店(博さんの50年余の記録には汲めども尽きぬ示唆があります)。中川書店は、糸賀一雄『糸賀一雄の最後の講義』『福祉の道行』も出版されています。
・白石正久・白石恵理子編(2020)『新版・教育と保育のための発達診断・下巻』
・白石正久・白石恵理子編(8月末発行予定)『新版・教育と保育のための発達診断・上巻』
開会全体会の実施方法について(お願い)
全国障害者問題研究会
全国委員長 越野和之
2022年8月1日
全障研第56回全国大会(兵庫2022)に参加申し込みをいただいたみなさん、長期にわたるコロナ禍の下、さまざまなご苦労を押して、全障研大会への参加を申し込んでいただき、本当にありがとうございました。大会開催地・兵庫の現地準備委員会ならびに全国事務局では、大会の成功に向けて準備活動の追い込みに入り、みなさまとともに大会を成功させるために全力を傾けています。そうした折ですが、第七波と言われる新型コロナウイルス感染症変異株の拡大期が到来し、連日過去最高の感染者数とともに、医療機関の逼迫などが報じられています。私たちの全国大会の実施方法についても、こうした状況を踏まえて具体的な対応が求められる状況であると判断し、7月31日の大会準備委員会において、その検討を行いました。
7月22日をもって締め切った参加申し込み状況を見ると、8月6日の開会全体会の神戸会場には、地元兵庫県をはじめ近畿各府県の方を中心に、200名近くの参加の申し込みをいただいています。「久しぶりに話そうや、私たちのねがい」の大会テーマの下、本当に久しぶりにお互いの顔を見合わせ、また初めて大会に参加する方々とも直接に出会って、日々の生活や実践の苦労と喜び、そこに寄せるねがいを語り合いたいという私たちの思いに応えていただいたものと、大変嬉しく思っています。しかし、大変残念なことですが、現時点の感染症拡大状況を踏まえると、これだけの規模の参加者を各地から現地にお迎えして、開場から閉会までの4時間の時間を屋内の会場でご参加いただく場合には、感染防止のためのさまざまな措置を含め、できる限りの態勢を持ってしてもなお、会場での感染の拡大などの危険を完全に防ぐことはできないのではないかとの判断に至りました。
ご存知のように、私たちの全国大会に参加される方々は、その多くが、日々障害のある子どもたちやなかまたち、またそのご家族ときわめて密接に触れあうことを職業とし、あるいは家族としての日々の生活とされている方々です。大会参加を終えて帰宅した自宅で、あるいは大会を終えた月曜日からの勤務として、そうした生活に再び戻られる方も多くあります。これは、参加者のみならず、大会を準備し、当日の運営に携わる現地準備委員やスタッフの方々も同様です。
そうした人たちの健康と生活を、万が一にも感染等によって脅かさないこと、全障研という自主的な研究運動に心を寄せていただいたすべての方々の生活と労働を守ることは、私たちの研究運動において第一義的に重要なことがらです。そのためには「完全無観客」での全体会開催も選択肢として検討しましたが、大会開催地として、初参加の方を含め、多くの方々にこの大会への参加を訴え、全障研活動を広めていただいた兵庫支部の「久しぶりに話そうや」という思いを少しでも実現し、今後の全障研活動の発展への基礎を築く上で、「兵庫の人たちだけでも集まりたい」との声も重視したいと考えました。以上を踏まえ、今大会の開会全体会の実施方法について、以下のことを提案し、ご理解とご協力をお願いします。
1. 神戸ポートオアシスでの対面型開会全体会は、原則として兵庫県内に在住もしくは在勤の方に限定して実施させていただきたいと思います。申し込みの際には「対面参加」としてご予約いただいている場合でも、兵庫県以外の地域の方は、すでにお届けしたオンライン参加のためのURL等を用いて、ご自宅などでのオンライン参加もしくは近隣のパブリックビューイング開場での参加に切り替えて下さい。ただし、自宅等でのオンライン参加がどうしても困難な場合などは、送付される「健康状態申告書」を提出し、必要な感染防止対策をご理解いただき、ご来場ください。なお、開会全体会については内容を録画し後日「見逃し配信」も準備します。
2. 兵庫県内に在住・在勤の方は、必ず神戸ポートオアシスで対面参加しなければならないということではありません。対面参加を予約された方でも、ご自宅等でのオンライン参加に切り替えられる場合はその判断を尊重します。
全国大会当日の一週間前にこのようなお願いをお届けせざるを得ないことは返す返すも残念です。「久しぶりに話そうや、私たちのねがい」を掲げた大会でもあり、また各地の方々からの熱い思いも伺ってきただけに、残念な思いはひとしおです。しかし、上にも書いた通り、私たちには、いま、直接に出会うこと以上に大切にすべきことがあると考えました。
「非対面」という形式でのご参加にはご不便やもどかしさも多々あると思いますが、現下の感染拡大状況と、私たちの研究運動の置かれた状況、果たすべき役割などを踏まえ、ご不便やもどかしさを、みなさんのご理解とご協力で乗り越えていただきたいと思います。どうかこの提案の趣旨を深くくみ取っていただき、知恵と力をお貸しいただきますよう、心よりお願い申し上げます。
▶Word版はこちら
2022年7月
白石 正久・白石 恵理子
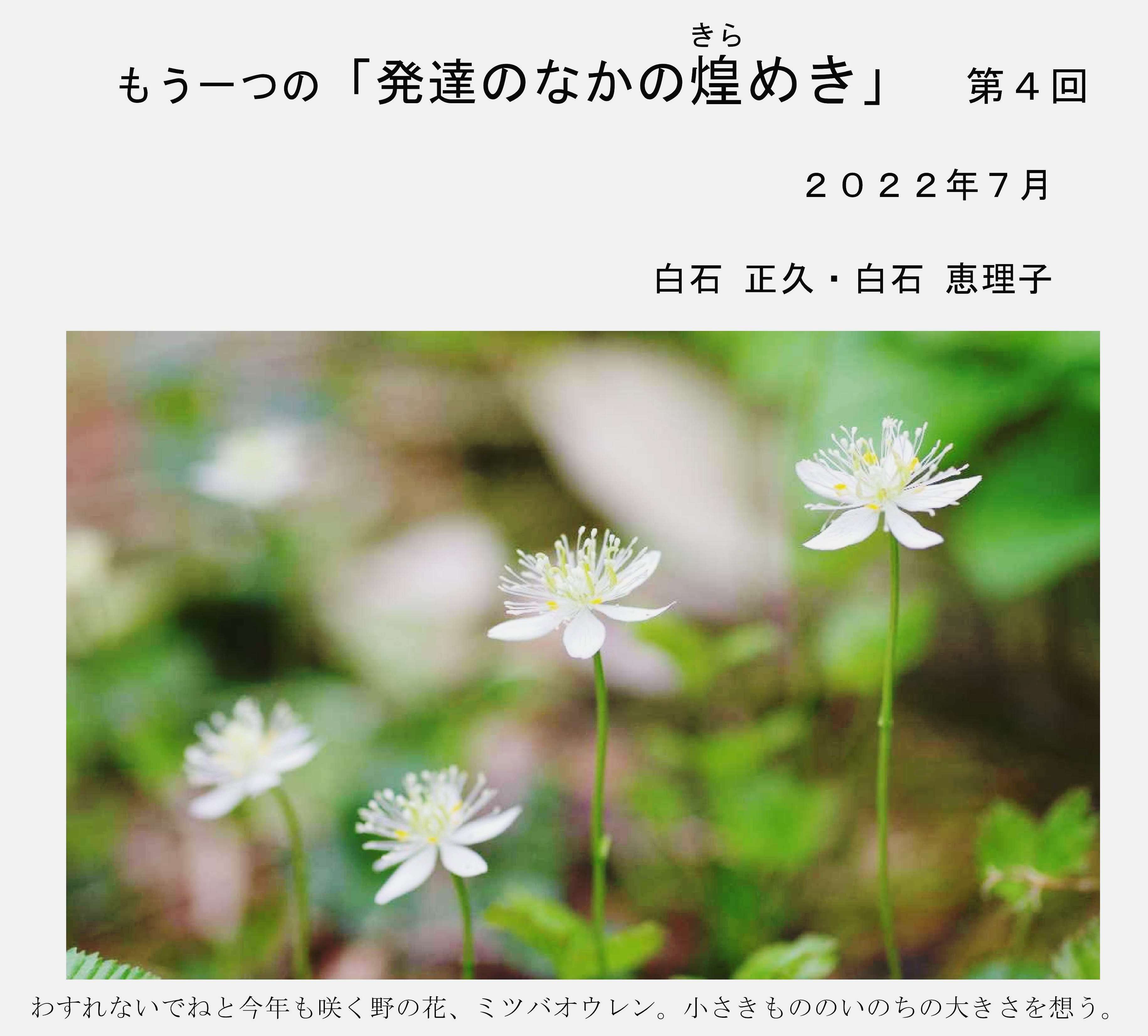
第4回 1歳半の発達の節(その1)
「もう一つの『発達のなかの煌めき』」(以下では「もう一つ」)をお読みくださり、ありがとうございます。
先日、オンラインでの読者会に参加しました。平日の19時からだったのですが、多くの方が参加くださり、あっという間の2時間でした。就学前から成人期まで、さまざまなライフステージにかかわる皆さんがつながって、担当している子どもやなかまのこと、職場や地域のこと、そして自分自身のこと…糸賀一雄さんが、発達保障とは子どもだけではない、指導者自身も親も地域も行政も、みんなが発達の主体でなければならないと言われていたことをしみじみと思い返していました。
さて、連載第4回(7月号)の「言葉の世界を拓く―障害のある子どもといっしょに創る文化を通して」では、横軸に故羽田千恵子さんの実践を通しての教師や指導者の授業づくりへの想い、縦軸に1歳半の発達の節をとりあげました。
1歳半の発達の節
これまで、通常の乳児期前半にあたる「回転可逆操作の階層」、乳児期後半にあたる「連結可逆操作の階層」についてみてきました。乳児期、まさに赤ちゃんと呼ばれる時期だったわけですが、生後1年をすぎると、ヨッコラショと立ちあがり、直立二足歩行の世界に入っていきます。さらに1歳半ば頃になると、道具を使用し、話し言葉を獲得するようになります。赤ちゃんを卒業し、幼児期に入っていくわけです。この大きな変わり目を「1歳半の発達の節」と呼んでいます。「可逆操作の高次化における階層-段階理論」では、生後第3の階層にあたる「次元可逆操作の階層」に入っていくことになります。連載第4回(7月号)、第5回(8月号)では、この「1歳半の発達の節」をとりあげます。
「1歳半の発達の節」をこえると、子どもたちはそれまでとはずいぶんと異なる姿をみせてくれます。直立二足歩行の確立、道具の使用、ことばの獲得、などが目に見える変化としてあげられるでしょう。もう少し立ち入ってみていくと、①全身運動や手指の操作などのさまざまな活動や生活において、目的(つもり)をもち、活動の達成感を自らのものとし(活動の内面化)、達成感ゆえに「もっとしよう」と活動を再生産し、「つもり」通りにならなくても立ち直っていこうとする主体の誕生、②他者と自分を区別し、他者の目的(つもり)をとらえ、ぶつかったり、自分の行動を調整したり、他者と目的を共有する力の誕生、③「…ではない…だ」をくぐった認識・表象の獲得、④指さしやことばに代表される表現手段を媒介にしたコミュニケーションの成立、などが大切な特徴としてあげられます。
以下、もう少し詳しくみていきます。
目的(つもり)をつくって行動する
乳児期段階の子どもたちは、たとえば、ハイハイするときに、面白そうなおもちゃや大好きなお母さんを見つけて這っていきますね。そこには、おもちゃやお母さんという目標はあるのですが、「ぼくが這っておもちゃのところにいくんだ」とか「わたしが這ってお母さんのところにいく」というように自分の行動の目的を意識しているわけではありません。1歳半の節をこえると、自分が行動の主体であるという意識がはっきりし、「ぼくが歩いていく」「わたしが積木を積む」といった自分の行動の目的をつかむようになるのです。
積木を積む遊びをしていても、1歳前半の子であれば、横にいるおとなが積んだことでも喜ぶことがありますが、1歳半になると、人が積んだ積木は嬉しくありません。「自分が積む」という目的意識、すなわち自分の「つもり」がはっきりしてくるからであり、その「つもり」が実現したときに、はじめて達成感を得ていくわけです。達成感を得ると、今度は「もっと積みたい」になり、さらに積んでいこうとします。しかし、当然ながら「つもり」通りにならない、すなわち失敗するということにも、今まで以上に向きあわざるを得なくなります。しかし、生活や遊びのなかで「自分でできた」「自分で(パンツを)はけた」というような達成感を積み重ねていくと、失敗してうまくいかなくても、「もう1回やってみよう」と繰り返していくようにもなります。
相手のつもりにも気づく
このように自分の目的(つもり)ができていくと、相手の目的(つもり)にも気づいていきます。二つの器を示して「こっちにも、こっちにも分けてね(はんぶんこしてね)」と声をかけたとき、まだまだ「はんぶんこ」の意味はわからなかったり、比べる認識には至っていないのですが、両方の器に入れ分けてくれるようになっていきます。二つの器に入れ分けることができてくる時期、子どもの心のなかにも、自分のつもりを入れる器と、相手のつもりを入れる器ができてくるのです。
すなわち、「もっと遊びたい」という自分のつもりがはっきりすると同時に、「もう片付けよう」という相手のつもりにも気づいていくわけです。「もう片付けよう」と言われていることがわかるからこそ、「でも、ぼくはもっと遊びたいんだ」という自分のつもりがより明確になり、「いやー」と怒ってひっくり返って「だだこね」をするようにもなるでしょう。「だだこね」「かみつき」については、『新版・教育と保育のための発達診断・下巻』(以下では『下巻』)94~96ページで詳しく触れられています。でも、いつもぶつかるだけではありません。「もっと遊びたいんだね」という気持ちを受けとめてもらえると、多少時間はかかっても、今度は「先生の言うことも聞いてあげるよ」とばかりに、次の活動に切りかえてくれることもあります。さらには、自分と相手を区別するからこそ、「一緒にやったね」「一緒にできたね」と目的を共有したことが、今まで以上に嬉しくなることもあるのです。
「…ではない…だ」
まもなく発行予定の『新版・教育と保育のための発達診断・上巻』(以下では『上巻』)では、近江学園の子どもたちのテレビドキュメンタリー番組『一次元の子どもたち』(東京12チャンネル制作、1965年4月放映)の中の、はめ板課題に取り組む子どものようすを紹介しています。
「きよしくんは右のきき手にもった丸い板を、すぐ前の丸い穴にはめることはできる。穴の位置が反対に変ると、もうついていけない。きよしくんは、自分の体と心にぴったりとくっついていた行動をいろいろとくりかえすことはできるのだが、まだ外のようすが変ったとき、その意味がくみとれない。すべての正常な子どもも、1歳半までにこの段階を通る。そのことを明らかにしたのは、正常児ではなく、実はこのきよしくんたちである…」。
1946年に戦災孤児と知的障害児の総合施設として創設された近江学園では、1950年代以降、発達年齢4歳ごろまでの知的障害が比較的重い子どもたちが多くなっていきました。しかし当時はまだ、「重度」とひとくくりにされており、学校教育からも排除される状況があったのです。近江学園では、そうした子どもたちの発達を明らかにしていくことこそが、この子どもたちに必要な教育のありかたを明らかにすることはもちろん、「教育の成り立つ基盤に何が必要なのか」を知らしめることになるという思いをもって実践や研究が進められていきました。
『一次元の子どもたち』では、子どもたちの食事や洗面といった日常生活の場面、あそびや労働の場面が生き生きと紹介されています。そのなかに子どもたちの発達検査の場面があるのですが、はめ板課題に取り組むきよしくんは、目の前の円孔に円板をはめ込むことはできるのですが、基板が180度回転したとき、その変化についていけず、目の前に現れた四角孔に円板をはめようとしてしまいます。はめ板課題については、『下巻』82~83ページを参照してください。
はめ板課題について、京都児童院式のテスト(今の新版K式発達検査です)では、「できる」か、「できない」かで評価されることがほとんどだったのですが、田中昌人さんたちは「できない中にも位置反応があるし、お手つき反応がある」と「できなさ」の中身をみていきます。さらに、「発達に障害があるばあいにはこの位置反応やお手つき反応が長く続き、神経症症状などもそなわっている。これができるということはそれら諸問題が大きく解決することになる」という事実に気づき、それが質的転換期だと認識していきました。そして、「180度入れ代わったことに対する可逆操作ができるという」ことから、1次元可逆操作と命名しました。
これまでみてきたように、乳児期後半の第3段階(「示性数3可逆操作期」)である11か月頃になると、「入れる」「渡す」「のせる」といった定位的活動がしっかりしてきます。したがって、はめ板課題でも目の前の丸い孔に円板をはめることが可能になります。はめ板回転課題は、そうして「入った」ことを子どもと一緒に確認したあとに、基板を180度回転させて、今度は子どもの目の前に四角い孔がくるように基板をおき、再び「ナイナイしてね」と声をかけます。1歳すぎの子どもたちは、さっきと同じように目の前の孔に入れようとするのですが、それでは円板は入りません。「入っていない」ことに気づいて、怪訝な表情になったり、四角孔の上でカタカタさせたり、検査者をじっと見たり…なかには、立ちあがってしまう子もいれば、入っていなくても「気にしていない」子もいます。そのうち、「ここじゃないのかな…」とばかりに、別の孔にチャレンジしようとしたり、円板をひっくり返してみたり、なかには基板の下から入れようとしたりと、様々な試行錯誤をはじめます。これらは、いずれも、検査上は「不通過」、すなわち「できない」と評価される姿なのですが、そこには1次元可逆操作を我がものとしようと努力する大切なプロセスが潜んでいるのです。「入れられる」かどうかよりも、このかけがえのない努力に心をよせていきたいものです。
「…ではない…だ」の力は、指さしやことばの力とはどのように結びついているのでしょうか。犬をみて「ワンワン」と言う、すなわちことばで表出するようになるには、犬=ワンワン等と、事物と名称が結びつくだけではありません。相手(第二者)に、このこと(第三の世界)を伝えたい、共有したいという関係が成立してくることが必要です。そこに至るまでには、「この人に伝えたい」という思いがふくらんでくること、そして、「このことを伝えたい」という伝えたい中身ができてくることが必要になります。加えて、「〇〇ちゃんのお目目はどこですか?」と問われて目を指さす、「ワンワンはどれかな?」と問われて犬を指さす…といった「可逆の指さし」が成立してくることも、とても重要な意味をもっています(『下巻』87~88ページ参照)。
こうした「指さし」を「可逆の指さし」とよぶのはどうしてでしょうか。一つには、自分から一方的に指さすのではなく、相手から聞かれたことに指さしでこたえ返すという可逆性が成立していることがあげられます。もうひとつは、「お目目どれ?」と聞かれて、「お口じゃなくてお目めなんだ」「お鼻じゃなくてお目めなんだ」という認識も関わっています。「ワンワンはどれ?」に対しても「ブーブーじゃなくてワンワンだ」という、その子なりの認識の過程があるのです。この「…ではない…だ」というつながりと、「…は…だ」というつながりの両方ができてくることによって、子どもの認識は大きく変わっていきます。
以前、休日の早朝に散歩をしている親子を見かけました。道端に置かれたゴミ袋をつついているカラスをみて、お父さんに肩車をしてもらっている男の子が嬉しそうに指をさして「ワンワン!」と言うのです。お父さんは、「ワンワンじゃないよ、カアカアだよ」と答えていたのですが、きっと男の子にとって、道を歩いている(?)動物は「ワンワン」だったのでしょう。彼なりに、まわりのものをカテゴライズし、それを共感的に受けとめられたり、修正されたりして、徐々にことばを獲得していくのだなと面白く思ったものです。
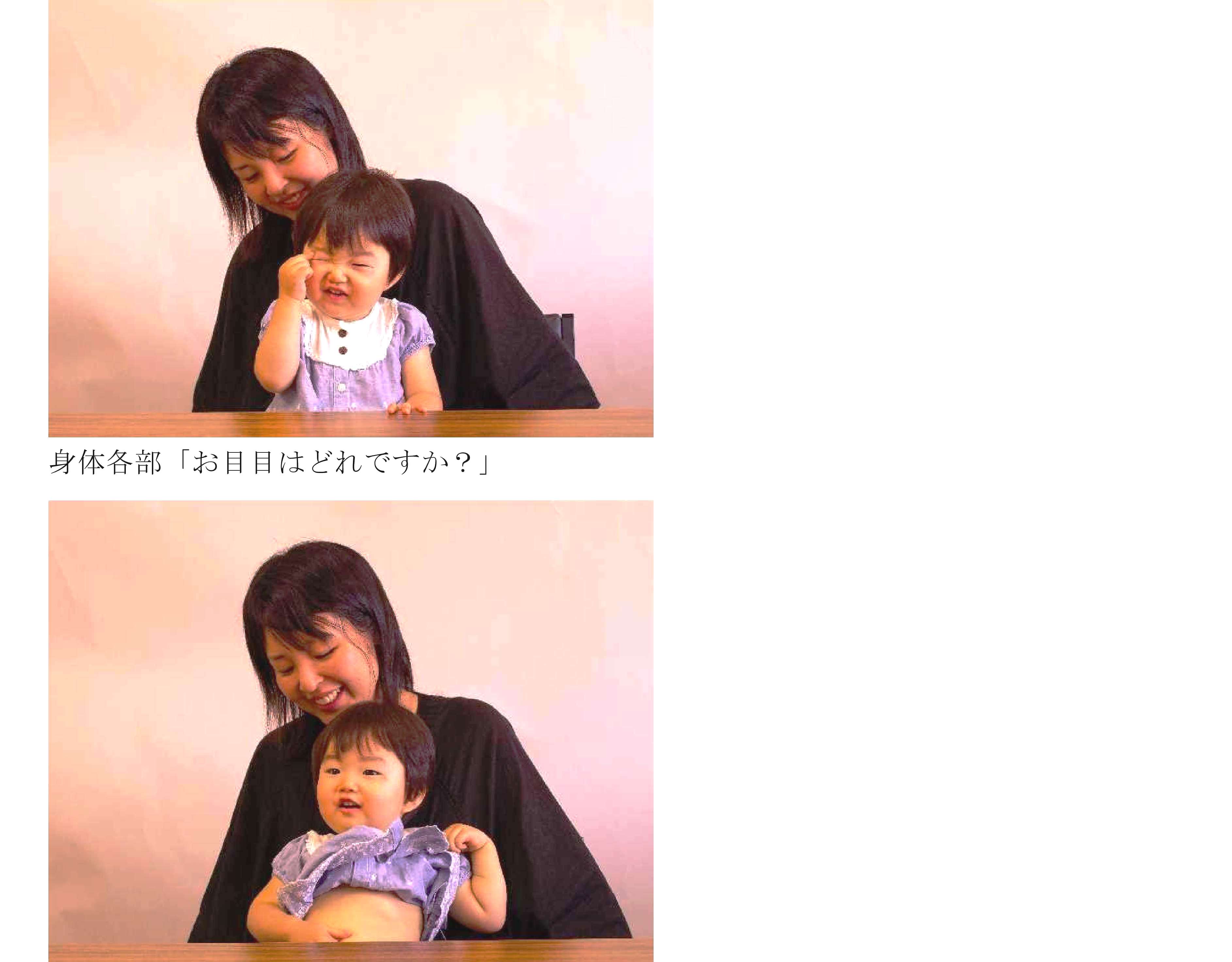
「おなかはどれですか?」(新版K式発達検査には「おなか」の問いはありません。)
道具を使う主人公になる
1歳半の節においては、目的と手段の分化と統合が可能になる、というのも大きな特徴です。これは道具の理解や使用とも結びついています。たとえば、スプーンは「食べる」という目的のための手段であり、鉛筆は「かく」という目的のための手段です。乳児の場合、目的と手段の分化には至らないため、スプーンも道具ではなくモノということになります。おにいちゃんやおねえちゃんがスプーンを使う姿を見て、自分もスプーンを持ちたがるけれど、実際に食べる際には手づかみで、という姿もよく見られます。
しかし、道具としてスプーンを使おうとしても、最初からうまく使えるわけではありません。うまく使えないからと言って、道具を使いたいという願いがうまれる前に戻れるわけではありません。そこに大きな矛盾と葛藤がうまれることは7月号に書いた通りです。
7月号では、おはなし遊びを中心に羽田千恵子さんの実践を紹介しましたが、『文化に出会い、友だちに出会う―障害の重い子どもたちと創る授業・教育・学校』(クリエイツかもがわ、2019)には、「ふれる・えがく・つくる」の実践も載せられています。肢体不自由をあわせもつ子どもの担任をした教師は誰もが、「口腔内や手のひらが過敏で、物に触れることを拒否したり、触ったとしても、教師の“やらせ”に終わり、子どもの表情はピクッとも変わらない、こわばる、あるいは寝てしまう」(羽田、89ページ)子どもの姿に、悩むのではないでしょうか。
7月号に登場する“ありちゃん”もそうでした。しかし、ある日、お家でお姉ちゃんが寝そべって絵を描いているそばで、ありちゃんも寝そべりながら、いつのまにか、同じようにクレヨンを手にもって絵を描き始めたということをお母さんから聞いた羽田さんは「これだ!」と思ったそうです。おとなの「描こう!」という意図を強く感じて拒否をしてしまうありちゃんに対し、教師が並ぶ形でさりげなく見本をみせたり、友だちの姿をみせたりしながら、あとはひたすら待ったそうです。あわせて、感触あそびでは物足りない、すなわち「1歳半の発達の節」を獲得してきつつある子どもたちに対しては、自分の「つもり」がつくりやすいようにと、「鯉のぼりをつくる」「運動会で自分たちが着るTシャツにアイロンプリントをする」「自分で使うお皿をつくる」などの取り組みにしていきます。陶芸の際には、ほんものの芸術家(県、美術館や博物館、学校の連携事業を活用)にも来てもらいました。こうした授業のなかで、肢体不自由の子どもたちも自分の手を使うことに少しずつ喜びを感じていきます。
おわりに
最後に、羽田千恵子さんの思い出を少しお話しします。私たち二人の職場の大学でも非常勤講師として長年、重症児の教育について講じていただきました。感銘を受けたのは、学生の感性のユニークさ、隠れた慈しみの深さなど、ともすると私たちが見落としてしまっていた「もちあじ」を、限られた交流のなかでも見つけてくださっていたことです。子どもと向きあう教師のまなざし、その基底にある人格には、だれに対しても、どこにあっても、一筋の芯が通っているのだと教えられました。
羽田さんの『文化に出会い、友だちに出会う―障害の重い子どもたちと創る授業・教育・学校』は、『みんなのねがい』の連載原稿を中心としつつも、新たな検討を加えられて生前から出版を準備されていました。遺された原稿を前に「編集委員会」の仲間と目をとめたのは、何度も書き直した形跡のある「はじめに―重症心身障害児教育に携わった32年を振り返って」の結びの言葉が、「今後も、重症心身障害児といわれる子どもたちが予想を越えた姿をみせる授業づくりのおもしろさや、人間として大切にされる教育課程づくりについて、より理解を広げるための活動を続けていきたいと考えます」であったことです。その記録媒体の最終更新は、亡くなる2週間前になされていました。
この「今後も」に込められた思いが私たちに遺された羽田さんの精神なのだと思います。羽田さんは、教師の集団としての発達の事実を創り上げることを、自らの課題として厳しく課していました。つねに教育実践を共同の財産と位置づけ、私有物にはされませんでした。だから7月号に写真で掲載した教材は、引き継ぐものとしてていねいに解説文を添えられて私たちに託されました。そして仲間と作り上げてきた教育実践の生命力を確信し、若い教師や仲間への信頼を「今後も」に込めて、「はじめに」と人生を締めくくられました。
『文化に出会い、友だちに出会う』を開くと、羽田さんが遺してくれたものの豊かさに心があたたかくなります。私たちはそれを紹介しながら、教師も集団のなかで輝き、仲間とともに育っていくものであることを、日々、「未来の教師」たちに語りかけています。

「三上山のムカデ退治」
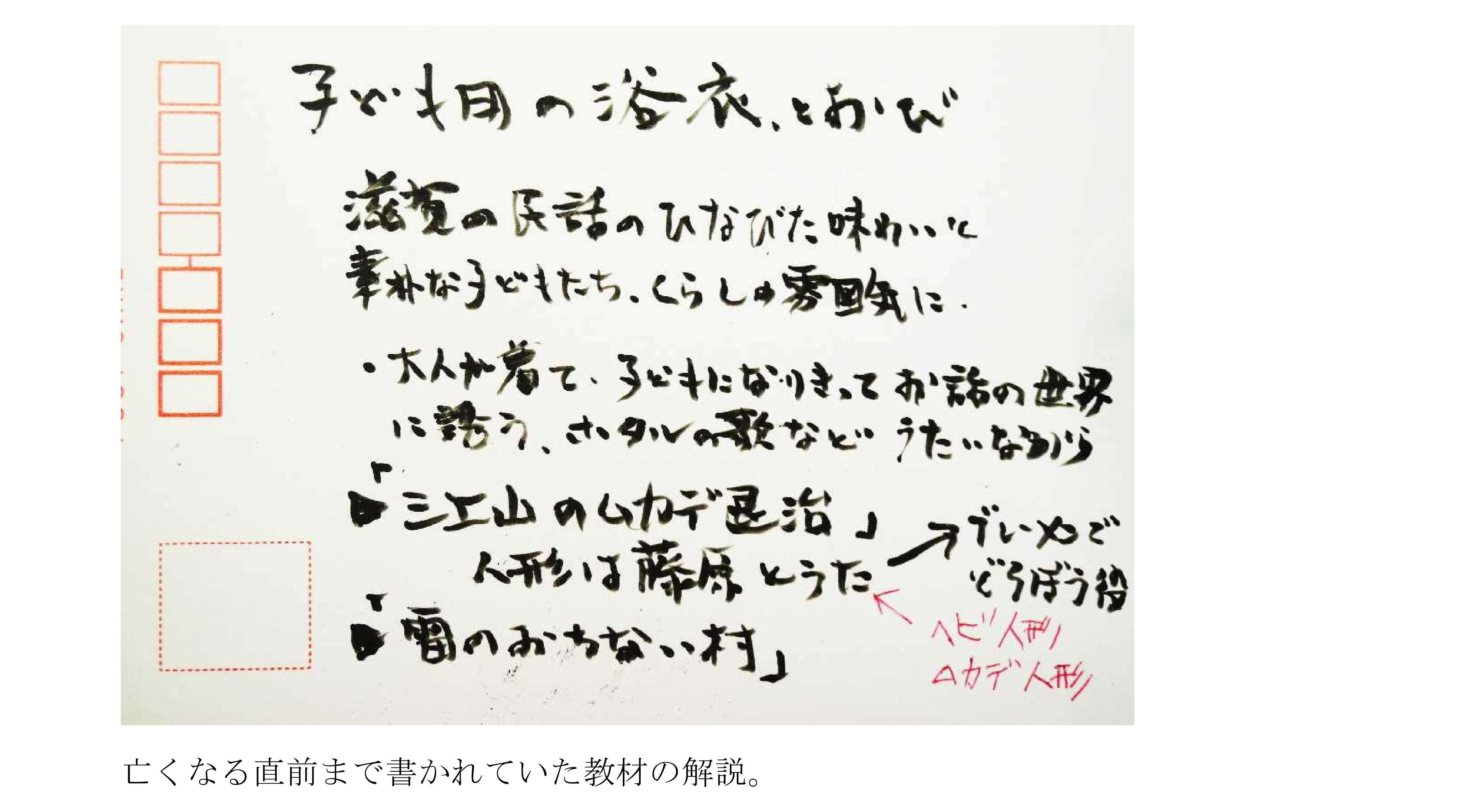
今回の学習参考文献
・羽田千恵子著、編集委員会・白石恵理子・白石正久編(2019)『文化に出会い、友だちに出会う―障害の重い子どもたちと創る授業・教育・学校』クリエイツかもがわ
・白石正久・白石恵理子編(2020)『新版・教育と保育のための発達診断・下巻』全障研出版部
・白石正久・白石恵理子編(まもなく発行予定)『新版・教育と保育のための発達診断・上巻』全障研出版部
全国障害者問題研究会
第56回全国大会(兵庫2022)基調報告案
常任全国委員会 2022年7月1日
はじめに
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大から2年以上が経ちました。コロナ禍といわれる社会状況は、私たちの生活や行動、人とのかかわりを大きく変化させ、暮らしや子育て、教育、労働を制約してきました。その影響は、障害のある人とその家族の暮らしにいっそうの困難をもたらし、保育・教育・福祉現場に疲弊と苦悩を招いています。
『みんなのねがい』2022年2月号の特集「新型コロナ禍から2年 ~これまでとこれから」で、京都の池添素さんは、働きながらシングルで障害のある2人の子どもを育てるお母さんからの相談を紹介しています。お母さんは、感染拡大が収束してからも在宅勤務が続いているため、「子どもと過ごす時間が格段に増え、イライラしてよくないことばかり」「誰かと会って話したい!」と話してくれたそうです。「誰かとしゃべりたくて、聞いてほしくて」というのは、障害のある子どもを育てる保護者の多くがもっている切実なねがいです。日々の悩みごとや子どもの困りごとなどを誰かに聞いてもらうことで、子育てに向き合う力を得ている保護者もたくさんいます。人とのつながりやかかわりが大きく制約されるなかで、保護者が「困っている」「助けてほしい」という声を上げづらくなっていないか、また支援する側もそうした保護者のSOSを聴きとりにくい状況が放置されていないか、確かめ合うことが必要です。
この2年余りの教訓が活かされないまま、感染拡大のたびに事業所や家族にケアの責任が押しつけられてきました。感染を抑え込むために行動を制限することは、障害のある本人と家族に大きな負担をもたらす場合があります。医療体制が逼迫するなか、障害福祉行政の現場で住民の命と健康を守るために奔走してきた二見清一さんは、障害のある人の「日々のくらしを大切にする視点」をもった感染症対策が必要であるといいます(『みんなのねがい』2022年2月号)。
2002年2月、新型コロナウイルスオミクロン株による感染が広がり、障害の有無にかかわらず、すべての人の命が守られ、安心して暮らすことのできる社会の仕組みを作り出すことに知恵と力を結集することが求められたこの時期に、ロシアがウクライナに軍事侵攻し、多くの市民が犠牲となりました。反戦平和と停戦を求める声が世界をかけめぐるなか、全障研の常任全国委員会は、2022年3月10日に声明「ウクライナにおける武力行使と戦争に反対し、障害のある人と家族のいのちと安全を守ろう」を発表しました。
しかし、日本政府は、この国際危機に乗じて「非核三原則」を捨て軍事費をGDP比2%に増強する方向を打ち出しています。さらにこれに同調する勢力とともに、「核共有」を主張し、憲法9条改正を強引に進めようとしています。唯一の戦争被爆国であり、憲法9条をもつ日本には、戦争の停止と平和の実現に向けた国際的な共同を進める役割が求められています。武力で平和は実現しません。戦争は障害のある人びとのいのちと暮らしを脅かします。政府が求める防衛費倍増は「自助」・「共助」を推し進めて社会保障費を削減する動きと一体であり、この動きを許せば、障害のある人びとの生活はいっそう不安定になります。
いまだ感染の収束が見通せず、物価も高騰し、日々の生活を成り立たせることに多くの困難が押し寄せるなか、障害のある人と家族が安心して暮らすことができるよう懸命の努力が各地で重ねられてきました。そして、多くの人が、毎日伝えられるウクライナの人びとの厳しい状況に心を痛めながら、自分たちに何ができるのかと逡巡しています。すぐには解決の糸口が見えないこれらの問題に向き合い続けるためにも、私たちは、目の前にある事実から出発し、日々の暮らしや実践のなかで感じたこと、考えたこと、思っていることを手放さず、一人ひとりのねがいや悩みを自由に話し合うことを大切にしたいと思います。
私たちにとって、目の前にある実態やねがいをみつめ、実践や運動のなかに問題解決のすじ道を見出していくための道標が、日本国憲法と障害者権利条約です。旧優生保護法にもとづく強制不妊手術をめぐる国賠訴訟では、大阪高裁(2022年2月)と東京高裁(同3月)はともに、旧優生保護法の違憲性を認め、20年の除斥期間の適用は著しく正義・公正の理念に反するとして、国の賠償を命じる画期的な判決を下しました。また、65歳になると障害者総合支援法による支援を打ちきり、介護保険適用へと強制的に移行させることは、障害のある人を年齢で差別し、憲法25条が保障する生存権を奪うものだとして、制度の改善を求める「天海訴訟」が東京高裁で闘われています。これらの裁判闘争は、日本国憲法に依拠しながら、障害のある人の尊厳と権利を取り戻そうとする闘いです。そうしたねばり強い闘いにも学びながら、障害のある人びとの暮らしを障害者権利条約にふさわしいものにしていくための多面的なとりくみが求められます。
障害者権利条約をめぐっては、新型コロナウイルス感染拡大の影響により延期となっていた日本の審査が2022年8月に開催される予定です。今回示される「総括所見」を日本の障害者政策の未来を拓き、障害のある人びとの権利保障を前進させるための手がかりとしていく上でも、みんなで語り合い、学び合うことでねがいを掘り起こし、そのねがいの実現に向けたすじ道を明らかにする研究運動が求められます。
今大会のテーマは「久しぶりに話そうや、私たちのねがい」です。私たちの身近なところにある問題やねがいは、権利保障のための歴史的な努力と国際的な動きと深くつながっています。日本国憲法と障害者権利条約を手に、多くの人たちが集い、実態を出し合い、ねがいを大いに語り合い、私たちの足元に芽吹いている発達保障、権利保障の取り組みを大きく育てていきましょう。
Ⅰ 乳幼児期の情勢と課題
(1)子どもに合った生活を
全障研の結成間もない1970年代、高度経済成長が終焉を迎える中で、住まいや遊び場の貧困が指摘され、科学技術の導入とひきかえに自然と人間の関係が壊され、子どもの生活が解体され、発達の土地を耕す時間も仲間もなくなっていないかと問題が提起されました。50年経った現在、さらなる資本主義の利潤追求のために、情報通信機器の拡大化、遊び場や交流の場の減少、そして気候変動により、子どもたちの発達の土壌はさらに貧しいものになっていないでしょうか。「暑すぎてプールに入れない、さんぽに行けない」「ゆたかな四季を感じられない」といった状況は年々深刻化しています。さらに、障害のある子をもつ保護者は、「すみません」と謝らざるを得ないわが子のふるまいに公園や公共の遊び場に行くのもためらい、地域の子どもたちと遊ぶ機会を失っています。親子で孤立させられているのです。
長引くコロナ禍のもとでの生活はこうした状況にさらに追い打ちをかけました。触れ合って遊べず、おとなもマスクをとって一緒にごはんを食べたり笑い合う経験をつくりづらくなっています。実践現場では、「なんとか、子どもたちにゆたかな経験をしてほしい」と工夫を凝らしていますが、時間、空間、集団の解体はその度合いを強めています。
人と人とが触れ合う関係、自然やいのちのきらめきとの出会い、子ども自身が「これはなんだろう」「やってみたい」と心を動かしながらゆるやかに続く生活や遊び、そしてそのようなかけがえのない時間を一緒に過ごす仲間。子どもの生活や発達にとってなにが大事なのか、実態と実践を出し合い、語りあいながら考えていきましょう。
(2)障害・子育てを自己責任にしない社会に
乳幼児期の子どもたちの発達保障の場や実践を考える際、昨年秋に行われた「障害児通所支援のあり方に関する報告会」の報告、2002年6月に国会で決まったこども家庭庁の設置、こども基本法の制定、児童福祉法改正などに見られる政策の動向に注目する必要があります。
2023年4月、こども家庭庁の設置がスタートします。障害児支援が厚労省からこども家庭庁に移管されます。障害があっても「子どものことは子どもの部局で」という私たちの声が届いたかに見えます。一方で、こども家庭庁推進を掲げた閣議決定「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」では、必要な財源について「社会全体での費用負担の在り方を含め、幅広く検討」すると提案しており、育児保険の導入を検討しているとも考えられます。また、「基本方針」には、「保護者が子育ての第一義的責任を果た」すという表現もみられます。ここには、子育てへの公的責任を回避しようとする厚生労働省の従来からの姿勢が現れています。障害があることによって生じる特別な支援に自己負担を強いることはおかしいと訴えてきたことに立ち返って、こうした動向を厳しく批判していく必要があります。子育ての負担や障害があることを自己責任に帰さない、地域や社会でともに安心して子育てをしていける仕組みづくりが求められます。
こども基本法も制定されました。基本法自体は子どもの権利条約以来、長く求められてきたものですが、このたびの基本法は、条約に明示された諸権利を誠実に遵守するものにはなっておらず、国内外の子どもを守る取り組みの上に積み上げられてきた発達への権利が軽視されていると言わざるを得ません。常任全国委員会は、5月、真に子どもの発達と権利を保障する法を求めて声明「日本国憲法と子どもの権利条約を遵守し、子どもの発達の権利を真に保障する基本法を」を出しました。
(3)子どもの発達を保障する普遍的な仕組みを
障害種別ごとの施設が再編されて10年、地域差はありつつも児童発達支援事業所は急増しています。そういった現状を踏まえて、2021年10月に取りまとめられた「障害児通所支援の在り方に関する検討会報告書」では、多様な主体の参入によって課題となる療育の質の確保について言及しています。しかし、日額制、契約制度、応益負担という現行制度の根本的な問題については触れられていません。療育の事業は運営の心配をせずに実施される必要があり、またわが子の障害に向き合う保護者の気持ちの揺れが大きい時期であることを考えると、利用契約や費用の応益負担は適していません。
報告書は、女性の就業率全体が高くなっている状況も踏まえ、「保護者(とりわけ母親)も就労を継続できる社会を目指す観点からは、発達支援の提供を通じて保護者の就労を支えることも、障害児通所支援の役割」と述べています。このこと自体は重要な視点です。しかし、保護者の就労を支えるためには児童発達支援の場にはどんな機能が必要か、一方で保育所を選択した場合にも、どのようにして行き届いた支援を保障するのかなどの検討はなされておらず、さらには子育て中の親の労働条件の改善等について検討する方向にも向かっていません。児童発達支援も保育所も、家族の生活と労働の権利を守りつつ、何より子どもの発達を保障するものでなければなりません。
「あしたもまたやりたいな」と、安心できる共感関係のなかで、自分のタイミングでじっくりたっぷりと遊びこんでいく時間、「ほんとはやりたい」というねがいやもどかしさに寄り添ってもらいながら、おとなや友だちと一緒に生活や自分をつくっていくこと。これらは保育でも療育でも共通して大切なことであり、それを実現するために、療育ではよりていねいな関わり、条件が必要なのです。働く親の「預け先」として子どもの生活を営利の対象にしたり、子どもを部分的に捉えて「力をつける」「足りないものを補う」ようなこま切れの「支援」、生活・発達から疎外した「サービス」にしてはいけません。療育をスポット的サービスとして一般の子育て施策から切り離すのではなく、子どもの生活と発達を保障する保育・教育といった普遍的な体系に組み込んでいくことが求められます。
乳幼児期において保護者を支援することの重要性はいうまでもありませんが、近年「ペアレントトレーニング」が推奨される傾向にあることに注意が必要です。2021年報酬改定において「ペアトレ」が事業所内相談支援の一つとして例示されたことから、マニュアル化された講習などが広がっています。子どもや保護者を一方的に変えようとする発想ではなく、時間をかけながらも子どもの姿を一緒に見守り、時には「思ったようにならないよね」と悩みや悔しさも分かち合いながらともに変わっていける保護者支援を大切にしたいと思います。
また、児童発達支援センターについては、乳幼児期における中核的な支援機関として、「高度な専門性」の確保、地域の児童発達支援事業所や保育所などに対する支援、発達支援の入り口の相談機能が示されました。乳幼児期の支援の歩みを振り返ると、住民の要求を紡いで自治体が公的責任をもって地域療育を築こうとしてきたことがわかります。母子保健はすべての子どもの出生から把握し、発達と健康を保障しようとするシステムを地域の中につくってきました。障害の早期発見・早期療育をめざしたネットワークはそうした子どもの発達を保障しようという実践と結びついています。それは、すべての子どもと親の子育てと発達を応援するものであり、もれのない健診、親が子育ての主人公になっていくような親子教室などの整備は大切な課題です。それぞれの地域のなかで、これまでの蓄積と到達点を踏まえた療育システムの構築をめざし児童発達支援センターの役割、児童発達支援事業との連携のあり方を考えていかなければいけません。『障害者問題研究』第50巻2号では保護者支援をふくむ乳幼児期の療育の課題を特集しています。
Ⅱ 学齢期の情勢と課題
(1)続く「コロナ禍」での学校教育の困難と課題
新型コロナ感染症オミクロン株の感染拡大による第6波は、これまでにない感染者数を記録する大流行となり、若年層、学齢期の児童・生徒にも感染が拡大しました。学校現場ではこの間、学級閉鎖、出席停止などが相次ぐ一方、子どもの学び、生活を保障しようと、感染症対策、さまざまな配慮を講じながら、教育活動が続けられてきました。
この時期、GIGAスクール構想の突出した推進もあいまって、タブレット端末の個人配布や学校におけるICT環境の整備が急速に進められ、オンラインによる授業も当たり前のように行われるようになりました。登校自粛や出席停止の中、オンライン授業を「出席」扱いとすることも行われました。それが必要な局面もありましたが、オンライン授業をつなぐことがあたかも教育保障であるかのように正当化される風潮は見過ごせません。子どもたちの学びは、オンラインで行っているからよいというものではありません。画面に注目することが難しかったり、直接的なふれ合いや教材を通してようやく外界を感じることのできる障害の重い子どもたちもいます。感染症に弱い医療的ケアが必要な子どもたち、病院や施設にいる子どもたちの教育保障は、オンラインか対面かの二者択一ではなく、両方があってこそだと言われます(『障害者問題研究』第50巻1号特集「入院中の子どもの教育」)。オンラインでは学びにくい障害のある子どもたちが置き去りにされていないか、子どもたちの学ぶ権利がきちんと保障されているか、改めて問う必要があります。
そのような中で教員の働き方は、ICTの活用方法を身につけるための研修やICT活用の準備などに多くの時間を要し、ますます多忙化しています。また、ICTを活用する能力が教師の専門性として評価されたり、授業でICTを活用することばかりが求められたりし、教材を製作したり子どもたちについて話し合うといった教員に本来必要な時間が奪われています。ICT機器の使用が「子どもたちにとってどうなのか」といった検討なしに、「コロナ禍だから仕方がない」という風潮に流されてしまうのではなく、何のために活用するのか、どのように活用していくのかを問い直し、考えることが必要です。
感染症の変異と感染対策の見直しの中、これまで中止とされてきた学校行事が、再開の方向へと動いています。しかし、3年も続く「コロナ禍」の影響は、けして小さくありません。たとえば卒業式、入学式、始業式などの学校行事は、縮小、簡素化され、それがスタンダードになりかねません。コロナ禍以前の学校へと動き出した今、教員の働き方改革を名目に必要以上に簡素化が進んでいないかを問い、学校の主人公である子どもたちにとっての意義や学び、そして各行事をはじめ、学校教育に込められていた教員の思いや願いを改めて確認し合うことも必要です。
感染症対策の中での教育活動はまだまだ続くと思われます。それらが及ぼす子どもへの影響をきちんと捉えつつ、その中で、子どもたちの願いや学びを保障する教育活動をめざし、保護者や同僚としっかりと手をつなぎ、思いを確かめ合って教育実践をすすめていくことが求められます。
(2)子どもに合った学びの創造
「コロナ禍」が続く中、学校現場では、ICT環境の整備が急速に進められ、GIGAスクール構想も相まって、「一人一台端末」という状況が作り出されました。「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議」の報告は、新時代の特別支援教育が目指す方向性として、ICT環境の充実と教師の活用スキルの向上を強調し、「令和の日本型学校」を謳う中教審答申では「協同的な学び」と並べて「個別最適な学び」が示されています。ICTを活用した教育の「個別化」は、対面授業とICTの組み合わせが想定されたもので、従来の校教育の仕組みや形態を少しずつ変えていこうとする意図が読み取れます。
タブレット端末ありきのこの流れは、これまでの対面での授業の価値、集団での学びの価値を軽視していると言わざるをえません。改めて、学習指導だけにとどまらない学校の役割や、そこで行われている実践の価値、子どもたちの発達や学びの事実を確認し合うことが求められます。
経済産業省のかかげる「Society5.0」は、人材育成に応じた教育を進めようとする文科省の姿勢にも重なり、個別に能力を伸ばすという「個別最適な学び」につながっています。そもそも学校は「人材育成」の場ではありません。能力重視、人材育成という教育観を問い、私たちが大切にしてきた、子どもの発達を保障する豊かな学びと、それを実現する教育実践を創造していくことが求められます。
教育のICT化は、教育現場にさまざまな産業、企業参入をもたらそうともしています。教師の働き方改革、専門性の向上などを名目にした学習アプリなどでの導入は、一人ひとりの子どもに向き合い、創意工夫をして行われてきたこれまでの実践の価値や教師の専門性をゆがめてしまいかねません。教員免許更新制が廃止される一方で、教員の特別支援教育に関する専門性向上を名目に、通常学校の教員が特別支援学校等での勤務を経験することを義務化するといった動きがあることも見過ごせません。教員の専門性は、決してICTの活用スキルなどに解消できるものではありませんし、特別支援学校での勤務経験があればいいということでもありません。子どものねがい、保護者のねがいに寄り添い、集団的に子どもを深く理解することや、目の前の子どもにあった学びを創造していくことこそ、譲り渡すことのできない専門性の核心なのではないでしょうか。
(3)教育条件整備をめぐる現状と課題
2021年9月、これまで特別支援学校にだけなかった「特別支援学校設置基準」が、ようやく制定されました。これは、十数年にわたる保護者、教職員、市民のねばり強い運動の成果です。設置基準は、学校を設置する上での「最低の基準」であり、今後、特別支援学校で学ぶ子どもたちの教育条件の改善を図っていく上での土台を築くことができたという大きな意義があります。けれど、制定された基準は、決して十分なものとは言えません。在籍児童・生徒数の上限が規定されなかったため、過大校の問題は容認されます。また、特別教室の種類や数はまったく明記されませんでした。さらに、既存の学校については適用が猶予されたため、「カーテン教室」に代表されるような教室不足、過大・過密といった待ったなしの教育環境の問題が直ちに改善されることにもなりません。文科省による「公立学校施設実態調査報告」では、7000以上の教室不足が生じています。新たな学校建設の計画が示されていない、教室が新設された特別支援学校でさえ、すでに教室不足が生じているなど、教室不足は常態化し、未だ放置されたままです。設置基準は制定されましたが、引き続き、基準の見直し、改善や教室不足の解消をめざす運動が求められます。
教育条件が劣悪なのは、特別支援学校に限ったことではありません。特別支援学級、通級による指導、通常学級においても同様です。特に教員不足の問題は深刻です。昨年4月の文科省の調べでは、2500人以上の教員不足が生じています。そのしわ寄せを受けるのは子どもたちです。
通級指導教室では、在籍に年限が示される地域があったり、担当する児童生徒の数が増やされ、子ども一人あたりの指導時間が減ってしまったりといったことが生じています。そのような中、文部科学省は、特別支援学級に在籍する児童生徒については、「原則として週の授業時数の半分以上を目安として特別支援学級において(略)授業を行う」ことなどを、特別支援学級などの「適切な運用」として全国に求める通知を発出しました。どこの地域、どこの学校でも通級指導が自校で必要なだけ受けられるための条件整備を欠いたまま、こうした機械的な「目安」を教育現場に押し付けるなら、その子に必要な特別な支援を基礎づける制度的基盤を欠いたまま通常学級に放り出される子どもたちは確実に増加します。
どの子にも行き届いた教育条件のもとで豊かな教育保障をというねがいは、教育環境の整備に留まらず、教師一人ひとりが、子どもにじっくりと向き合い、子どもとともに豊かな教育実践を繰り広げることのできる自由をも求めます。このことこそが教師の名にふさわしい専門性を培っていく条件だからです。こうした観点からも、行き届いた教育条件を整え、必要な教員配置を求める運動続け、広げていきましょう。
(4)ゆたかな生活のための放課後保障
放課後や休日の生活を支える放課後等デイザービスは、この間も感染症対策を講じ、さまざまな工夫をしながら子どもと家族への支援を続けています。感染症拡大の中で、「通所自粛」ややむを得ない休所もあり、日額報酬制=出来高払い制度のもとで大幅減収となった事業所が多発しました。にもかかわらず、これに対する策は講じられていません。
2021年4月からの報酬改定によってもたらされた問題にも目を向ける必要があります。この報酬改定によって、事業存続と実践のあり方の両方にわたるさまざまな問題が持ち込まれました。改定で基本報酬が引き下げられ、資格のある職員の配置に対する加算が廃止されたことによる減収は大きく、事業所運営を困難にしています。一方、新設された個別サポート加算、専門的支援加算の二つの加算は実践にも影響します。個別サポート加算は、子どもの障害の状態を判定して加算をつけるかどうかを決めるというこれまでにない仕組みです。子ども一人に対する働きかけ、支援ごとに値段がつけられるようなこの仕組みは、子どものねがいに寄り添い、ゆたかな生活や発達を保障しようとする放課後実践をゆがめかねません。専門的支援加算は、事業所に理学療法士等の配置をした場合の加算ですが、放課後活動における「専門性の高い支援」とは何かという問題と関わります。次期2024年報酬改定では「特定プログラム特化型」(仮)という放課後活動の類型化も予定されており、子どもたちに、ゆたかな放課後生活を保障する実践とその専門性について検討を深め理論化していくことがいっそう求められることになります。
学校、家庭、放課後の場は、学齢期にある子どもたちにとってどれも欠かせない時間と空間です。子どもたちの生活、健康やいのちを守るために、それぞれの関わる人びとの連携は不可欠です。コロナ禍により、学校との連携が以前にも増して難しくなったとの声が聞かれます。学校教育と放課後等デイサービスなどの事業とが相互に連携、協力する関係づくりを意識的にすすめ、地域の関係者をむすぶ全障研らしい活動を広げていきましょう。
Ⅲ 成人期の情勢と課題
新型コロナウイルス感染症の流行が続く中、成人期施設では仲間が安心・安全に生活するために細心の注意を払いながら実践を展開しています。一方、障害のある人たちの暮らしが、長期にわたって多面的な困難に直面する中で、青年期から高齢期にいたるいくつものライフステージにわたって、生活を保障する制度的な基盤の脆弱さが鮮明になっています。
(1)働く場の課題
障害者総合支援法による日額報酬制は、コロナ禍において障害者の働く場の運営や障害者の生活に対しても大きな影響を与えています。
きょうされんは3回の「新型コロナウイルスの影響に関する生産活動・工賃実態調査」を行っています。第3回の調査では、6割の事業所でコロナ禍以前より生産活動の収入が減収となったことが報告されています。一方で、減収を補うはずの「生活活動活性化支援事業」補助金は、対象事業が就労継続支援に限られているという問題点をもつ上に、上述の調査では、就労継続支援事業所であっても、申請した事業所の6割強が「要件に該当しなかった」ために給付されなかったと回答しています。こうしたことを背景として、半数以上の事業所で障害者の賃金・工賃が減額しています。しかし、行政による対応は不十分であり、それぞれの事業所で新たな収入源を確保する独自の努力が重ねられているのが現状です。
働く場の課題は、そこで働く職員の生活にも影響を与えています。
政府は内閣官房に「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障の総合的な検討を行う」ため、「全世代型社会保障構築会議」を設置、2021年11月から同会議を開催し、この会議の下に公的価格評価検討委員会を設けています。そこでは、障害者福祉に携わる職員の処遇改善として2022年10月以降について臨時の報酬改定を行い、収入を3%程度(月額平均9千円相当)引き上げるための措置を講じることを検討しています。しかし、この程度の引き上げでは他職種の平均月収から10万円ほど低いとされている状況を根本的に改善することはできません。福祉労働者のこのような劣悪な労働条件などを背景として、成人期施設では慢性的な職員不足が生じ、また働き続けることが困難になっています。
こうした中でも障害者支援の場で働く多くの職員は真摯に実践に向き合っていますが、社会福祉の場にも経済競争を持ち込み、政府の公的責任を縮小しようとする新自由主義的な施策の影響が渦巻く中、実践がうまくいかないのは自分自身の力量の不足に原因があると考えさせられ悩んでいます。その背後には、職員を個別化することで孤立させる自己責任論の根深い影響があります。しかし、一人一人の職員が孤立するのではなく集団として実践に向き合い、やがて制度的な矛盾にも目を向けることができるような職場づくりの取り組みも報告されています(発達保障研究集会での茨城・あすなろ園の報告)。こうした実践にも学びながら、自己責任論に基づく孤立化の罠を乗り越える職場づくりをすすめたいものです。
(2)「暮らし」の課題
3年ごとの障害者総合支援法見直しの作業が行われ、2022年6月に報告としてまとまっています。報告は、居住支援として「地域生活への移行」においてグループホームを強調、医療的ケアや強度行動障害のある人が利用できるグループホームの整備も求めています。またさらに「一人暮らし」をめざす計画をたてたり利用期限を設定するなど、十分な条件を示さないままさまざまな機能・役割をグループホームに課そうとしています。
NHKの取材では入所施設での生活を希望し、待機している障害者が昨年の時点で、少なくとも27都府県で延べ1万8640人に上ることが報じられました。しかし、この数字は氷山の一角にすぎません。このNHK報道では、20の道府県は待機者の人数すら把握しておらず、国も調査を行っていないことから、実態はさらに多いとみられることも指摘されています。高齢の親が障害のある人の介護をする「老障介護」が問題となっていますが、その背景には民法の扶養義務などに代表される、障害者の生活支援における家族依存があります。
障害者権利条約第19条「自立した生活及び地域社会への包容」には「(a) 障害者が、他の者との平等を基礎として、居住地を選択し、及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有する」と謳われていますが、現実には、「地域生活」の名の下に、障害者・家族が、支援の貧しい特定の生活様式を強要される事態が起こっています。地域生活への移行を言うのであれば、行政は障害者・家族の高齢化・重度化などの実態を正確に把握するとともに、必要な法整備と重点的な予算措置を行わなければなりません。
様々な矛盾や弱点をはらみながらも、医療や福祉などの発展によって、障害者が高齢期をすごすことができるようになってきました。しかし、高齢期を迎えてもゆたかな生活を送ることができる制度などの整備は、65歳を境に介護保険制度への移行を強要される「65歳問題」に象徴されるように、十分ではありません。特に、高齢化・重度化に対応できる医療制度の整備と、医療と連携した福祉制度の構築などは急務です。私たちの研究運動においても、医療関係者との連携をさらに強く、太くしていくことが課題となっています。
(3)政治的及び公的活動への参加及び生涯学習の課題
国の政策のあり方を障害者の権利を保障する方向へ変更させていくためには、障害者自身の声を政治に反映させていくことが欠かせません。そのためには、政治的及び公的活動への十全な参加が必要です。障害者権利条約第29条には「政治的及び公的活動への参加」が規定されていますが、日本の状況は不十分です。
玉野裁判(1980年、言語障害のある玉野ふいさんが知り合いに候補者の文書を手渡したことで逮捕されたことに対して、公職選挙法の問題性を訴えた裁判)以降、公職選挙法の改正が適切に行われておらず、障害者の参政権は十分に保障されているとはいえません。JD(日本障害者協議会)や障害をもつ人の参政権保障連絡会では、障害者の参政権の状況について調査し、障害者の適切な参政権保障のあり方を検討しています。投票においては環境整備が推進され、障害者権利条約や障害者差別解消法で定められた「合理的配慮を欠く」問題事例は正されなければなりません。また、障害者が政治参加の権利を含む人権の主体者となるための学習の機会の確保は生涯学習の課題でもあります。
障害者権利条約第24条では、生涯学習の機会の確保が謳われていますが、日本においては障害者の高等教育を含む18歳以降の教育の保障は、障害の種別や程度による格差を含みつつ、全体としてきわめて限定的な水準にとどまっています。福祉制度を利用した福祉事業型「専攻科」が全国的に広がり、新たな学びの可能性が模索されていますが、そこでの実践のあり方とともに、教育年限の延長を含め、学びの場をどう創造していくのかを検討していくことも課題です。
ーーーーー
2022年6月
白石 正久・白石 恵理子

第3回 乳児期後半の発達の階層‐段階
「もう一つの『発達のなかの煌めき』」(以下では「もう一つ」)をお読みくださり、ありがとうございます。
連載第2回(5月号)を読んでくださったベテラン保育士さんから、「重症児を担当することになった同僚の若い先生にさっそくすすめました」と伺いました。ゆっくりゆっくり時間をかけて発達していく子どもたちに接していると、ときに自分の仕事の意味を見出せなくなる焦りを感じてしまうことがありますが、「人がかかわることの値打ちが、こんなふうにあるんだよ」ということを伝えたいと思ったとのことです。連載が、人と人をつなぐきっかけになっているのかなと、とても嬉しくお聞きしました。
さて、連載第3回(6月号)の「子育てを応援する地域づくり―『新しい発達の力』が親、地域、社会を変える」では、横軸に乳幼児健診や子育て支援、縦軸に乳児期後半期の発達をとりあげました。
まずは、乳児期後半の発達についてみていきましょう。
乳児期後半の発達の階層
第1回の「もう一つ」で解説したように、乳児期前半すなわち「回転可逆操作の階層」につづく乳児期後半の「連結可逆操作の階層」は、6、7か月ころから1歳前半までの大きな発達段階(大きな発達段階を階層とよびます)であり、そのなかに「示性数1可逆操作期」(7か月ころ)、「示性数2可逆操作期」(9か月ころ)、「示性数3可逆操作期」(11か月ころ)という3つの段階が含まれています。『新版・教育と保育のための発達診断・下巻』(以下では『下巻』)の6ページの図2「発達段階の説明図」を参照してください。
乳児期後半になると、子どもたちは外界の人やモノに積極的に働きかけながら世界を拡げていきます。乳児期前半では、基本的な姿勢は臥位(あおむけやうつぶせなどの寝ている姿勢)であり、まだ移動の自由を獲得していません。しかし、乳児期後半になると、寝返りでゴロゴロ動いたり、這い始めたりしながら、行きたいところに行く自由を獲得していきます。また、モノをつかんだり放したり振ったりつまんだり…と、手の自由も拡がっていきます。つまり、乳児期後半とは、外界との交流が格段に広がる時期なのです。「連結可逆操作」とは、その際の外界との結び目(結節点)とおさえておきましょう。その結び目(結節点)が順に増えていくのです。
個人的には、外界との結び目(結節点)を連結可逆操作とよぶのはわかるし、「連結可逆操作の階層」という呼び方はすんなり理解できるのですが、そのなかの各発達段階の名称はどうして「示性数」になるんだろう???と悩みました。きっと多くの方がそうだろうとお察しします。一瞬、「連結1可逆操作期」「連結2可逆操作期」「連結3可逆操作期」としてくれた方がまだとっつきやすいのに…と思ったのですが、ただこれだと、電車の車両がたてにつながっていくイメージになってしまいますね。田中昌人さんも、それではまずいと思って、別の用語を探したんじゃないかと想像します。ちなみに、「示性数」とは、位相幾何学(位相数学)の用語らしいです。
でも、こうした用語が並ぶと、やっぱり心が引いてしまいます。前回も書いたように、それぞれの発達段階のことを理解していくうえで、ヒントになることがその名前には隠れているらしい(・・・)というくらいでいいと思います。具体的な子どもの姿から考えていきましょう。
ということで、前回の乳児期前半の階層から、今回の乳児期後半の階層にどう飛躍的移行をなしとげるのかについて、まずは考えます。
乳児期後半への飛躍的移行
5月号「あなたといっしょに、もっと生きたい」のハルちゃんの記述を振り返ってみましょう。
ハルちゃんは、たんに先生のはたらきかけが心地よいからではなく、それぞれの先生たちのことを知り分け、その人をその人としてわかって微笑むようになったのでしょう。そして、その人がいるから、『もう一つ』の『心の窓』をも開いていきます。この対の『心の窓』こそ、いろいろな事物や人間関係を取り込んでいくための外界との結節点になります。それはまさに、乳児期後半の発達の階層への飛躍のための『生後第1の新しい発達の力』が誕生した姿です。
前回の「もう一つ」にも書いたように、「新しい発達の力」は、各階層の第2段階から第3段階への移行期において誕生する力で、「生後第1の新しい発達の力」は通常4か月ころに誕生します。この力は、次の大きな発達の階層への飛躍的移行を準備するものです。
ハルちゃんは、障害によって姿勢保持にも追視にも困難を抱えていたのですが、日々かかわってくれる先生たちの声を聞き分け、さらに聞き分けるのみならず、「大好きな先生だ」「いつもの先生だ」と知り分けていったのでしょう。その先生への「心の窓」は、今度は、先生がさしだすものや用意してくれる世界に気持ちを向ける対の「心の窓」を開くことにもつながっていきます。
発達検査の課題としては、追視やリーチング(モノに手をのばす行為)をみる時期ですが、それは決して、目の前のガラガラや積木といった刺激への反応をみるだけではありません。4か月ころになると、ガラガラや積木を追視するだけではなく、検査者の顔もよく見るようになります。「あなたは、このおもちゃで遊ぼうとしているのね」と問いかけてくれているようです。そのまなざしに「そうよ。これで遊ぼうね。面白いよ」などと対話をするつもりで、おもちゃをさしだすのと、唐突に子どもの眼前におもちゃをつきだすのでは意味が異なるし、実際、子どもがみせる姿も違うように思います。
さて、通常、4か月での対追視は、あるときは右方の積木を目で追って、でも次の試行では左の積木を目で追って…というものですが、これが徐々に、右を見て、左を見て、また右を見返って…というような可逆対追視になっていきます。4か月ではまだ、「反対側にもいいことがありそうだ」というようなものですが、そこから2か月くらいかけて、自分で両方を確かめる力に変えていくのです。また、積木を見て、相手を見て、積木を見て…を繰り返したあとに積木に手を伸ばすというのも、可逆対追視のあらわれかたと言えます。こうして、確かめたり比べたり選んだりという主体性をより発揮して外の世界に向きあっていきます。その営みをくぐることによって、モノにつられて手を伸ばそうとするのではなく、「これをつかむんだ」という、より自分の意志をともなったリーチングに質を変えていくのです。こうしたリーチングが明確になると、モノを見比べる可逆対追視は表面的にはみられなくなります。
また「見る」だけではなく、右にゴロンと寝返って元に戻り、今度は左に寝返って元に戻るといった寝返り運動を繰り返す姿、右手にもったものを左手に持ち替えて、また右手に持ち替えて…を繰り返す姿にもつながっていきます。寝返りの次はハイハイ、片手に持ったら今度は両手に持てるようになって…と、おとなはともすると先へ先へと急ぎがちで、こうした繰り返しの姿はもどかしくも思えるのですが、子どもたちは、たくさんの対を自分で生産しながら、世界を自分の力で確かめているのです。新しい発達の階層へ移行するという大事業を、時間をかけて行っている姿として、ゆっくりと見守ってあげたいものです。
「連結可逆操作の階層ー段階」の特徴
次に、連結可逆操作の階層-段階の特徴を、もう少しみていきましょう。
生後7か月ころの「示性数1可逆操作期」では、上述したように、モノに対し片手を寄せて取り込み、それを右から左、左から右に持ち替えて遊ぶ姿が多くみられます。もったモノを口に持っていって確かめる
ことも多い時期です。しかし、二つ目のモノに対しては、まだあまり関心を示さなかったり、あるいは二つ目に手を伸ばそうとして、最初のモノを落としてしまったりします。すなわち、外界との結び目が基本的に「一つ」なのです。
9か月ころの「示性数2可逆操作期」になると、両手にそれぞれモノを持って遊ぶことが増えます。スリッパなどを両手に持って、パンパンとたたくのも大好きな遊びです。外界との結び目が「二つ」になった姿です。目の前にたくさんの積木などがあると、片手に積木を持ったまま、もう一方の手の積木を放して、別の積木を取るように次々と持ち替えて遊ぶようなこともします。
11か月ころの「示性数3可逆操作期」になると、両手にそれぞれ持ったうえで、目の前の相手に差し出したり、見せたり、あるいは器のなかに入れたりと、外界との結び目が「三つ」になります。
姿勢・運動面ではどうでしょうか。
生後7か月ころの「示性数1可逆操作期」では、うつぶせになり、おなかをつけて、時計の針のように右や左に旋回する姿がみられます。これも、外界との結び目が「一つ」と言えるでしょう。9か月ころの「示性数2可逆操作期」になると、よつばいのように、右側と左側を交互に前に進めていくような、結び目「二つ」の姿になります。さらに、11か月ころの「示性数3可逆操作期」になると、伝い歩きなど、平面の世界から立ち上がって「高さ」という軸をもつようになります。これは、結び目「三つ」の姿と言えないでしょうか。
つまり「連結可逆操作の階層」では、子どもが外界に向かってはたらきかけていくときの「結び目」(結節点)が一つずつ増えていく、3つの発達段階が取り出されます(この乳児期後半の3つの発達段階は『下巻』の53~60ページで解説されています)。
発達段階から発達段階への移行
次に、発達段階から発達段階への移行の時期についてみていきます。前回の「もう一つ」でも触れたように、発達段階から次の発達段階への質的変化にはエネルギーや人間的な支えを必要としており、それは「発達の障害」がはっきりとしてくるときでもあります(詳しくは『下巻』192~217ページ「Ⅲ 『発達の障害』と発達診断」)。
それでは、移行のときである「示性数2形成期」と「示性数3形成期」について解説します。
・第1段階から第2段階への移行(示性数2形成期)と「人をもとめてやまない心」
「示性数1可逆操作期」から「示性数2可逆操作期」へ向かう「示性数2形成期」(8か月ころ)では、二つ目の結び目を志向するようになります。一つのおもちゃだけではなく、もう一つのおもちゃも気になって、手を伸ばそうとします。しかし、実際には二つの結び目をつくるには至りません。また、目の前にあるおもちゃだけではなく、少し離れたところにあるおもちゃも気になります。そこに向けて移動しようとしても、坐位から伏位へと上手に姿勢を変えられなかったり、何とか伏位になって前に進もうとしても身体は逆に後ろにさがってしまったりと、ますます目標から遠ざかってしまうことも起きてきます。こうした矛盾の高まりは、子どもの心を波立たせ、泣くことが増えたり、夜泣きにつながったりすることもあります。
二つ目を志向するのに実際には手に入れられない矛盾だけではなく、この「2」の形成期は、感受性や情動などにも変化があらわれる時期です(乳児期前半では「快-不快」でしたね)。おもちゃに手をのばしかけて、「あれ、何だろう」と、いつものおもちゃと違うことに気づいて手をひっこめたり、これまで以上によく見比べてから「こっちがいいわ」とばかりに選択的に手をのばしたりと、外界の変化やちがいにより敏感になる時期です。認知的には、ちょっと先の未来を予期できるようになり、また、目に見えない裏側の世界にも気づきはじめます。このような、違いに敏感になる感受性の高まりや予期の力は、「不安な心」をももたらすようになるのです。
しかし、6月号でも述べたように、くすぐり遊びでは、最後の「コチョコチョ」の前に大笑いをするようになったり、イナイイナイバア遊びでは、ハンカチの向こうに大好きなおとうさんがいるとワクワクして「バア」と出てきた時に、「やっぱりいたあ」と嬉しくなったりしながら、遊びを通して、不安を期待につくりかえていきます。そうして期待につくりかえてくれるおとなのことが、ますます好きになっていくのです。「もっとして」とばかりに、相手を期待のまなざしでみることも増えるでしょう。
もちろん、大好きな人になるからこそ、愛着も強まり、その人がいないと不安で仕方なくなるように、「期待」と「不安」はつながった関係であることもおさえておきましょう。
自閉スペクトラム症の子どもたちの場合、変化への感受性がより強いことも多く、それが「不安」の高さとしてあらわれることも多いようです。「不安」の高さゆえに、外界の変化を受け入れにくく不機嫌さが続いたり、逆に、外の世界をシャットアウトするかのように自分の世界に閉じこもっているように見えることがあります。運動発達に遅れがみられる肢体不自由の子どもたちでも同じです。ずりばいをしかけていても、まるで、目に見えないバリアがあるかのように、そのバリアの外には絶対に出ようとしなかったり、特定のおもちゃにしか手を伸ばさなかったりします。でも本当は、人や周りの世界が気になっているのでしょう。急がずゆっくりと、子どもの「不安」を受けとめつつ、期待の心がつくられるような遊びを積み重ねていきましょう。
・第2段階から第3段階への移行(示性数3形成期)と「生後第2の新しい発達の力」の誕生
「示性数2可逆操作期」から「示性数3可逆操作期」に向かう「示性数3形成期」(10か月ころ)になると、次の幼児期、すなわち直立二足歩行への準備をするかのように、立位という高さのある世界への志向性が高まります。高いところにあるモノに手を伸ばそうとし、階段などの段差も大好きになっていきます。まだ上手にハイハイできない子も、10か月ころになると、何も置いていない平面よりも、高さや段差がある方が意欲的に動こうとします。高さという抵抗を「発達的抵抗」にする力が芽生えるのです。ただ、こうした要求は、事故にもつながりやすくなるため、浴槽や、テーブルクロスなどには十分な注意が必要です。
また、「示性数3形成期」になると、三つ目の結び目を志向するようになります。両手に積木をもってカチカチと打ち合わせるだけでなく、両手に持ったまま、机上にある3つ目の積木にも手を近づけていきます。器があれば、手に持ったものを器に近づけていきます。
同時に、「三つ目の結び目」は相手との間でもつくられていきます。遊びはじめる前に相手をじっとみつめたり、両手を使って遊びながら、視線も相手によく向けてきたりします。それまでは、ほめられると嬉しくて、その遊びをさらに繰り返していたのが、ほめてもらうことを期待して、相手に自分の遊びを見せようとしているかのようです。また、誘いかけられてもすぐには手を出さずに、じっと相手をみつめ続けるまなざしには、相手が自分に何
を求めているのかを探っているのだと感じます。4か月児が、あやされてもすぐに笑わなくなり、相手がわかってから微笑みかけるように、10か月児もまた、相手の意図を探り、その意図がわかってから遊び始めるのでしょう。この探りを入れているときに、おとな側のペースでコトを進めようすると、うまくいきません。「やらされる」と感じて、とたんに逃げ出したくなる気持ちは、私たちと同じですよね。
また、8か月ころに培った「人をもとめてやまない心」は、この10か月ころの、相手の意図と対等にむきあっていくところで大きな支えとなります。「ボール、ポンしてね」「ここ、ナイナイしようか」「先生にちょうだい」等と言われ、その求められていることが何となくわかっても、それに応じるためには、かなりの勇気が必要です。発達検査の場面では、相手の意図を感じるからこそ、後ろにいるおかあさんを何度も何度も見返ります。大好きなおとなとの間で育んできた安心感が、新しい世界への挑戦につながっていくのでしょう。
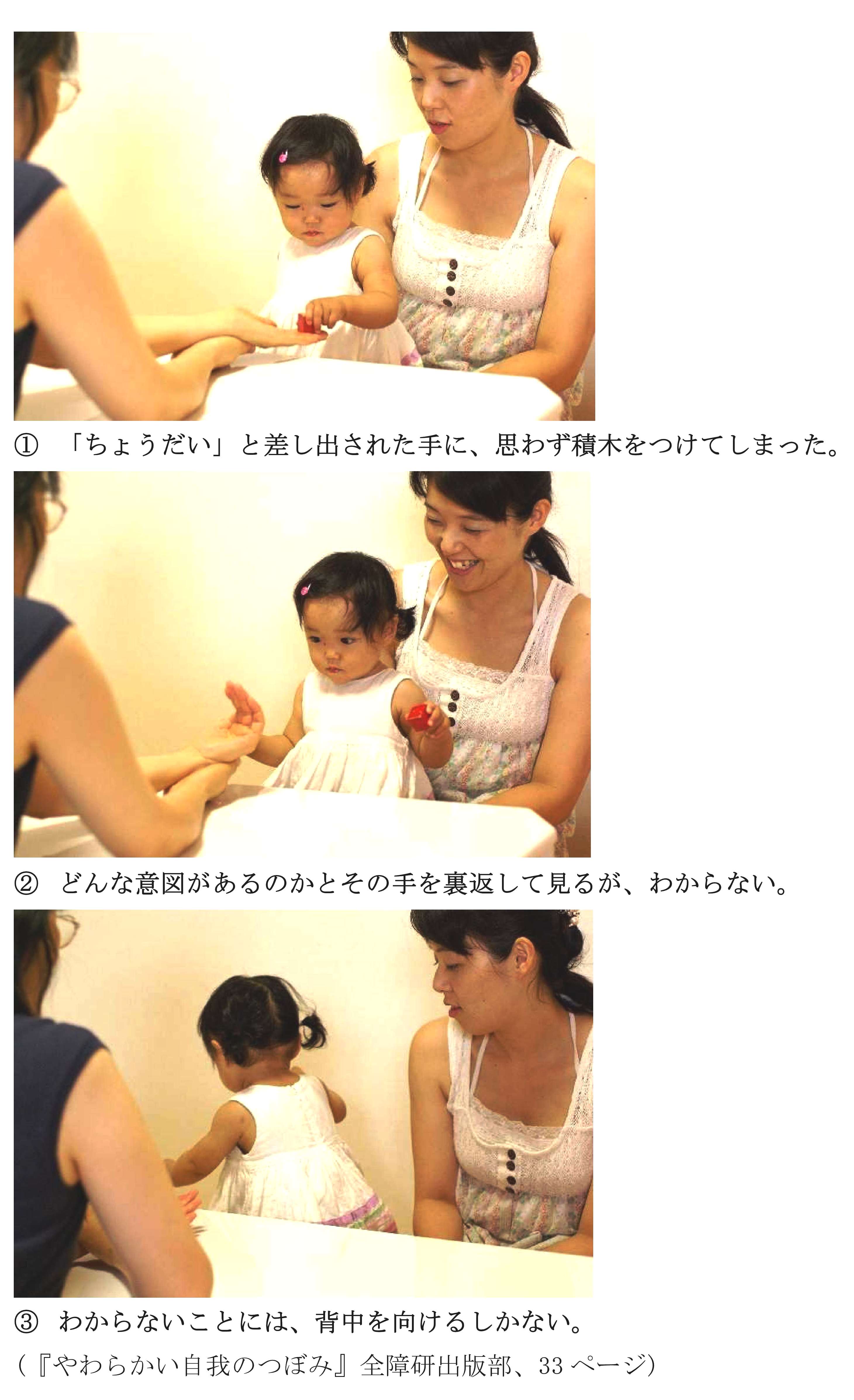
この「生後第2の新しい発達の力」が誕生する時期には、戸外に出ること、おとなの生活に一緒に入っていくこと、おとなだけではない子ども同士の関係があることなどが、より重要になってきます。外に出れば自分から見つけていける世界が拡がります。おとなの生活にはワクワクする魅力がいっぱいです。子ども用に買ったおもちゃでは遊ばないのに、台所のおなべやしゃもじには生き生きと目を輝かすことがありますよね。また、おとなと子どもの違いはよくわかっています。きょうだいや友だちなどの存在もまた、「新しい発達の力」を芽ばえさせた子どもたちが、発達の主体になるうえで不可欠なのだと考えます。
この10か月ころの発達と発達診断については『下巻』の61~70ページをご参照ください。
子育てを「自己責任」にしないで
6月号でふれたように、1970年代前半に、全国に先駆けて乳幼児健診のシステムや早期対応のシステムをつくりあげた滋賀県大津市では、試行錯誤の末、乳児健診の時期を4か月、10か月に設定しました。なぜ、4か月、10か月だったかは、これまでの連載や「もう一つ」からおわかりいただけたかと思います。次の階層への飛躍的移行のための「新しい発達の力」の誕生に焦点をあてることで、障害の早期発見と同時に、先を見通した育児への応援をしようと考えられたのだと思います。
4か月児健診の場では、おかあさんから「最近、以前のように声が出ないのですが大丈夫でしょうか?」という主訴が出されることがありました。以前できていたことができなくなるというのは、保護者にとって不安なことですよね。そうした主訴に対し、「大丈夫ですよ。これから赤ちゃんの後半にむかっていくための準備がはじまったんですね」とお答えしていました。つまり、それまで何気なく見ていた相手や外界に対し、よりしっかりと主体的に見つめるようになったために、一時的に声が潜(ひそ)むのだと思います。実際に、「声が潜む」時期を過ぎると、今度は自分から相手に呼びかけるような、自ら人間関係をつくりだしていく声に変わっていきます。
また、10か月児健診では、離乳食を食べなくなるという主訴が増えることを6月号に書きました。これも、次の幼児期にむかう変化の兆しなのです。こうした、一見、マイナスに見える変化は、子どもたちがまさに発達の主体として自分をつくりかえようとしているからこそなのでしょう。そうした変化をおかあさん、おとうさんと一緒に共有し、子どものもっている発達の力を愛(いつく)しむきっかけになってほしいと切に願います。
もちろん、障害や虐待の発見も健診の重要な役割です。医療機関等ですでに障害や疾患が診断されている場合には、そのことをふまえた育児の相談や、療育、福祉等について伝えていく責任が行政にはあります。
しかしながら、こうした健診を民間委託しようとする動きが強まっています。健診の民間委託は、行政の公的責任を後退させ、育児や障害を「自助」「自己責任」の対象にするものです。もちろん、保護者のなかには、自分で調べ、情報を得て、様々な機関をコーディネートして使おうとする方もいらっしゃいます。しかし、多くの保護者はそうではありません。日々起きる子どもの変化に、とまどい、たじろぎながら、子育てをしているのです。一人ひとりの子どもは親の一部ではなく、一人の人格をもった存在なのですから当然のことです。そうしたとまどいやたじろぎに共感し、親が親になっていく道すじを応援するのは行政と社会の役割です。
かつて一緒に仕事をしていた保健師さんが、家庭を訪問するときは、できるだけ電車やバスを使うと話されていました。電車やバスのなかで聞こえてくる会話から、その地域に住む人たちの健康や子育てに関する不安やねがいを知ることができるから、という理由でした。もちろん、時代も変わって、今はSNS等が主役になっているのかもしれません。しかし、この保健師さんの姿勢は、住民からの訴えを待ってそれに応えるだけでは、本当に住民一人ひとりが暮らしやすく子育てしやすい地域づくりにはならない、自分から地域に分け入り、声にならない声を拾いながら仕事や施策に結びつけていくのだということなのだと思います。そうした努力の積み重ねでつくられてきた自治体の仕事を、安易に民間に委託するということがあってはならないと考えます。
子どもの発達の権利を守る国に
折しも、「こども家庭庁」設置、「こども基本法」制定が国会で審議されています。子どもの権利を守り育てることは、国のありかたとして当然のことであり、先進国中で最下層というあまりにも不十分なこれまでの施策と予算を、一気に塗り替えるだけの方針転換が必要です。
しかし私たちは、その法案を読んでかえって大きな心配をもちました。子ども施策が、虐待や少年犯罪などの事象への対策に偏重し、根本の問題でもある子ども施策の貧困を改めようとする姿勢がありません。そして、将来の労働力の確保のために、子どもの「自立」を図ろうとする意図が透けて見えてしまいます。社会防衛、社会効用のために子ども施策を考えないでほしいと率直に願います。
また、「こども基本法」案には多くの賛意も寄せられていますが、国連・子どもの権利条約第6条の定める子どもの基本的権利、「生命」「生存」「発達」を明記せず、「発達」は「成長」にすり替えられようとしています。全障研は、「発達の権利を保障する」ことを目的とする研究運動の団体ですが、その立場から出された声明には、力強い願いが表明されています。学び、子どもの未来のためにみんなで力をあわせていきたいと思います。
声明「日本国憲法と子どもの権利条約を遵守し、子どもの発達の権利を真に保障する基本法を」(2022年5月26日)
また、「こども家庭庁」の設置にともなう児童福祉法の改定法案のなかで、児童発達支援センターの「福祉型」と「医療型」の一本化などが提案されています。これは、現在の児童発達支援センターのありかたに大きな変更を迫るものであり、内容を検討して意見表明が必要だと思います。全障研「みんなのねがいWEB」のなかのリンク「子どもの支援」をクリックしていただくと、「障害乳幼児の療育に応益負担を持ち込ませない会」のサイトに到達できます。それらを学びつつ、私たちの願いを形あるものにしていきましょう。
今回の学習参考文献
・白石正久・白石恵理子編(2020)『新版・教育と保育のための発達診断・下巻』全障研出版部
・稲沢潤子(1981)『涙より美しいもの―大津方式にみる障害児の発達』大月書店(本書は古書サイトからの入手になります)
声明
日本国憲法と子どもの権利条約を遵守し、子どもの発達の権利を真に保障する基本法を
2022年5月26日
全国障害者問題研究会常任全国委員会
私たちは、障害者の権利を守り、発達を保障するために、自主的・民主的研究運動を発展させることを目的としている研究運動団体です。
現在、「こども基本法」案が国会で審議されています。基本法の制定は、子どもの権利条約批准(1994年)以来、国内法の中軸として待ち望まれていましたが、今国会で審議中の法案のままでは子どもの発達と権利を保障することができないと考え、意見を表明します。
「こども基本法」案は第1条(目的)で、「児童の権利に関する条約の精神にのっとり」といいます。しかし、法の重要な位置にある目的規定には、単に「条約の精神にのっと」ることではなく、「条約を遵守する」ことが明確に示されるべきです。このことは、締結した国際条約を「誠実に遵守する」ことを定めた日本国憲法第98条に照らしても当然です。子どものための基本法の前提として、子どもの権利条約が示す諸権利を実現する立場を明らかにすることを求めます。
政府は、「こども基本法」案や児童福祉法等の子どもに関する現行の法律において、「発達」をしばしば「成長」(growth)、「自立」(independence)にすり替え、あるいは並列して用いています。「こども基本法」案第一条(目的)の「ひとしく健やかに成長すること」、同第二条(定義)の「健やかな成長に対する支援」、同第三条(基本理念)の「成長及び発達並びにその自立」などです。
一方、子どもの権利条約第6条は、条約の一般原則として、生命、生存、発達の権利を定めています。この条項を構成する発達(development)は国際的議論において、一人ひとりの潜在的可能性を実現するという概念として発展してきました。そのための条件を保障されることが子どもの重要な権利なのです。また、「発達」の概念には、差別や戦争、搾取などの権利侵害から民主主義的な過程を経て、権利として勝ち取ってきた歴史が内包されています。このようなものとしての「発達」を軽んじ、成熟という意味の「成長」、独立・自活という意味の「自立」を打ち出すことは、子どもの政策を社会の存続や経済成長を志向する人材づくりに従属させることになります。現在の「こども基本法」案は、「発達」を軽んじるという点において、人類が獲得して豊かに発展させてきた発達の権利に逆行しています。
「こども基本法」案第三条(基本理念)の五は、子ども施策において、養育における父母等の第一義的責任を認識するよう求め、「家庭での養育が困難」な場合に「家庭との同様の養育環境を確保する」と定めています。子どもの権利条約第18条は、どんな場合も保護者がその責任を果たせるように施策を講じることを締約国に求め、国の責任を明確にしているものであって、養育困難に限定するものではありません。だれでも第一義的責任が果たせるよう、すべての子育てに支援がゆきわたる施策を講じることが国の責任であると明記した条文に書き改めるべきです。
発達を権利としてとらえ、そのための条件を積極的に講じることに対する消極的な姿勢は、子どもの福祉及び教育のための予算がOECD加盟の先進国中最低レベルであることにも表れています。
全国障害者問題研究会は、すべての人の発達の権利が保障される社会をめざしています。日本国憲法と子どもの権利条約を誠実に遵守し、一人ひとりの悩みや発達へのねがいを大切なものとしてとらえ、権利を保障する核となる子どものための基本法を望みます。
▶wordデータです
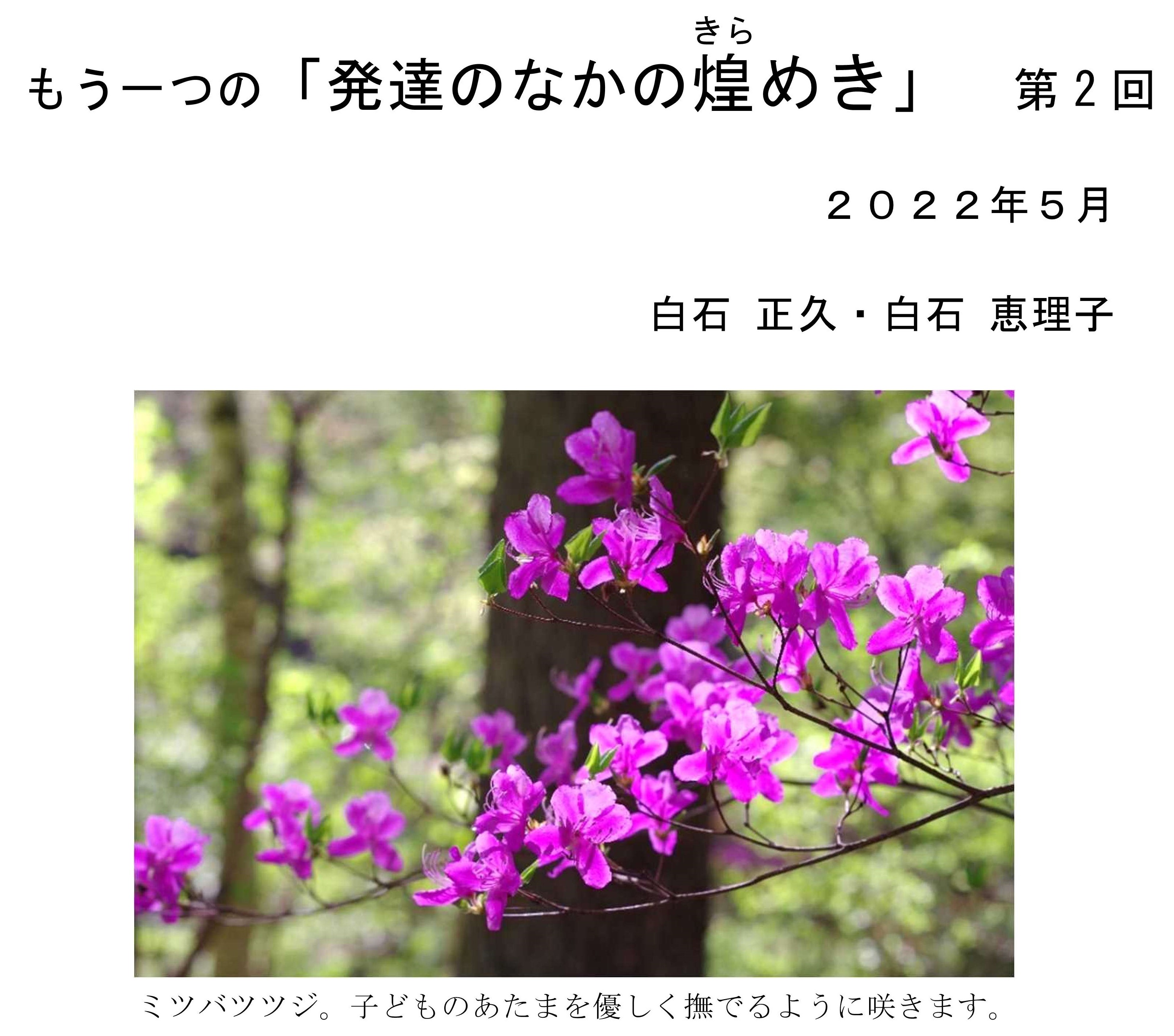
第2回 乳児期前半の発達の階層‐段階
「もう一つの『発達のなかの煌めき』」(以下では「もう一つ」)の第1回をお読みいただいた方から、『みんなのねがい』連載といっしょに「読みあわせ」の学習会を開催したら、議論が具体的になり、学習の深まりを実感する時間になったとの感想をいただきました。
この「もう一つ」への私たちの願いは、そういった学習会や読者会が職場や地域で拡がって、『みんなのねがい』がみなさんの共有の財産になっていくことです。わが家の書庫には、学生時代から読みつづけてきた『みんなのねがい』が大切に並べられています。そこには、その時々の全障研サークルの仲間との語りあいがいっしょに記憶されているのです。
定期購読の読者の輪を拡げつつ、ぜひ学習会、読者会を始めてみてください。もちろん、全障研サークルでもOKです。「みんなのねがいWEB」の「発達診断セミナー」を開いていただくと、その最下欄に「サークル活動の手引き」があります。そこには、全国のサークルや読者会のようす、さらに品川文雄さん(元全障研委員長)による「実践記録を記録し、実践報告を書き、学び合おう」が掲載されています。
発達の階層と3つの段階
今回から、発達の道すじにそって解説を進めていきます。連載第2回(5月号)の「あなたといっしょに、もっと生きたい」のハルちゃんの発達は、乳児期前半の発達の階層‐段階にありました。
前回の「もう一つ」で書いたように、階層とは大きな発達段階のことであり、乳児期前半の階層は出生から生後6、7か月ころにあたります。そのなかに、1か月ころ、3か月ころ、5か月ころという3つの段階が含まれます。田中昌人さんは、この階層を「回転可逆操作の階層」、そして3つの段階を、「回転軸1可逆操作期」「回転軸2可逆操作期」「回転軸3可逆操作期」としました。こういったむずかしい言葉を目にして、心が引いてしまうかもしれません。しかし、この発達段階の名前の意味がわからなければ発達がわからないということではありません。それぞれの発達段階のことを理解していくうえで、ヒントになることがその名前には隠れているらしい(・・・)という気持ちで相対(あいたい)してください。「可逆操作」については、前回の「もう一つ」で簡単に解説しています。これも、最初に定義を行なうよりも、具体的な子どもの発達の姿のなかから意味をつかんでいただけるようにと考えています。
前回の「もう一つ」で解説したように、「回転可逆操作の階層」につづく乳児期後半の「連結可逆操作の階層」は、6、7か月ころから1歳前半までの大きな発達段階であり、そのなかに「示性数1可逆操作期」「示性数2可逆操作期」「示性数3可逆操作期」という3つの段階が含まれています。この発達段階については、次回解説する予定です。そして1歳半から7、8歳ころまでの幼児期・学童期前半の大きな発達段階は「次元可逆操作の階層」であり、そのなかに「1次元可逆操作期」「2次元可逆操作期」「3次元可逆操作期」という3つの段階が含まれています。「1」という数字のつく段階は、可逆操作の質が大きく変わる「飛躍的移行の時期」、すなわち「大きな発達の節」であることを前回述べました(前回の「可逆操作の高次化における階層?段階理論」の項では、「飛躍的以降の時期」となっていました。以降→移行と訂正いたします)。すぐには理解しにくいことでしょう。『新版・教育と保育のための発達診断・下巻』(以下では『下巻』)の6ページの図2「発達段階の説明図」を、何度もたどってみてください。
田中昌人さんの「可逆操作の高次化における階層‐段階理論」は、3つの発達段階が、どの階層においても見出されるところに、ひとつの特徴があります。つまり発達はそれぞれの階層において3つの段階をのぼりきり、次の階層に入っていくのです。次の階層でも3つの発達段階が待っているということです。それは、まるで螺旋(らせん)階段をのぼっていくようです。なぜ「3つ」なのかと思われるかも知れませんが、その問いはしばらく保留していただいて、各階層の「1」「2」「3」という数字の意味を理解することから入りましょう。
「回転可逆操作の階層-段階」の特徴
生後1か月ころの「回転軸1可逆操作期」では、まだ四肢が躯幹(くかん。からだから四肢を除いた部分)と一本の軸のように一体化しています。四肢を屈曲させた姿勢をとっていることが多く、顔の向いた側の上下肢を伸ばし、後頭部側の上下肢を曲げるATNR(非対称性緊張性頸反射)、びっくり反射とも言われるモロー(Moro)反射、手のひらに触れたものを握り込む手掌(しゅしょう)把握反射などの原始反射が現れます。そのために仰臥位(ぎょうがい。仰向けのこと)では、非対称姿勢をとっていることが多いでしょう。思い通りにはならない姿勢なので、この姿勢でいるときには笑顔にはなりません。手指は、親指を内に折り込んでおり、他の指と向きあってモノを握ることはありません。光や音などの刺激は「点」のように認知しており、線を引くように追視したり、音源を探そうとする動きはみられません。
3か月ころの「回転軸2可逆操作期」になると、四肢が躯幹という軸から自由になり、もう1つの軸として動くようになって、緩やかに曲げたり伸ばしたりをくりかえします。親指は手のひらから離れて、ガラガラを持たせると自分で握り、やがて自分の手と手を触れあわすこともできるようになります(hand-hand
coordination)。躯幹から四肢の運動が分離するようになって、原始反射はしだいに減っていきます。その結果、仰臥位は、対称姿勢をとっていることが多くなるでしょう。左右、頭足方向に追視して戻り(往復追視)、外界(がいかい)を連続した「線」のように認知しており、音源を探すように頸(くび)と眼球を動かすこともできるようになります。
5か月ころの「回転軸3可逆操作期」になると、四肢がさらに自由に動き、そこから指の動きが分離して、第3の軸として外界に向かって開閉するようになります。ですから、追視のようすを確認するために胸の前に赤い輪などを提示すると、手を伸ばし手指を触れてつかもうとします。見る(追視)だけではつまらなくなり、見たものを把握することが子どもの欲求になっていきます。音源を探索して、それを見つめながら手を伸ばそうとする目と手の協応ができるようになります。
つまり「回転可逆操作の階層」では、子どもが外界に向かってはたらきかけていくときの運動の「軸」が一つずつ増えていく、3つの発達段階が取り出されます。子どもには失礼ながら、躯幹を一本の丸太としてみるならば、その中央をタテに貫く基本の軸(これを正中線とよびます)を中心として、運動は軸を増やし、対称的に回転するように自由度を増していくということです(この乳児期前半の3つの発達段階は『下巻』の36~38ページ、往復追視の課題は、同43~44ページで解説されています)。
発達段階から発達段階への移行
この「回転可逆操作の階層」の3つの発達段階は、はっきりと区別される特徴をもっていることがおわかりいただけるでしょう。言うまでもなく、段階から段階に移っていくときに、大きな発達の変化があるということです。それは前回の「もう一つ」で説明した階段を一つあがる質的な変化があるということです。その質的変化にはエネルギーや人間的な支えを必要としているので、「発達の障害」がはっきりとしてくるときでもあります(詳しくは『下巻』192~217ページ「Ⅲ 『発達の障害』と発達診断」)。
それでは移行のときである「回転軸2形成期」と「回転軸3形成期」について解説します。
・第1段階から第2段階への移行(回転軸2形成期)と「途切れてもつながる」
「回転軸1可逆操作期」から「回転軸2可逆操作期」へ向かう「回転軸2形成期」(2か月ころ)では、快と不快の情動が分化して、心地よい色彩や音に引きつけられるようになります。ミルクなどの美味しいものを与えてくれ、あやしてくれる人の表情や声がわかって、その人の顔を探すようになります。その人の抱き方もわかって、それ以外の抱き方に対して、不機嫌になることもあるでしょう。そして、その人の顔に近づこうとするように手足を動かすようになります。だからATNRがあって非対称姿勢になっていても、一生懸命に頸を動かし、手足が躯幹から分離した動きをするようになっていきます。
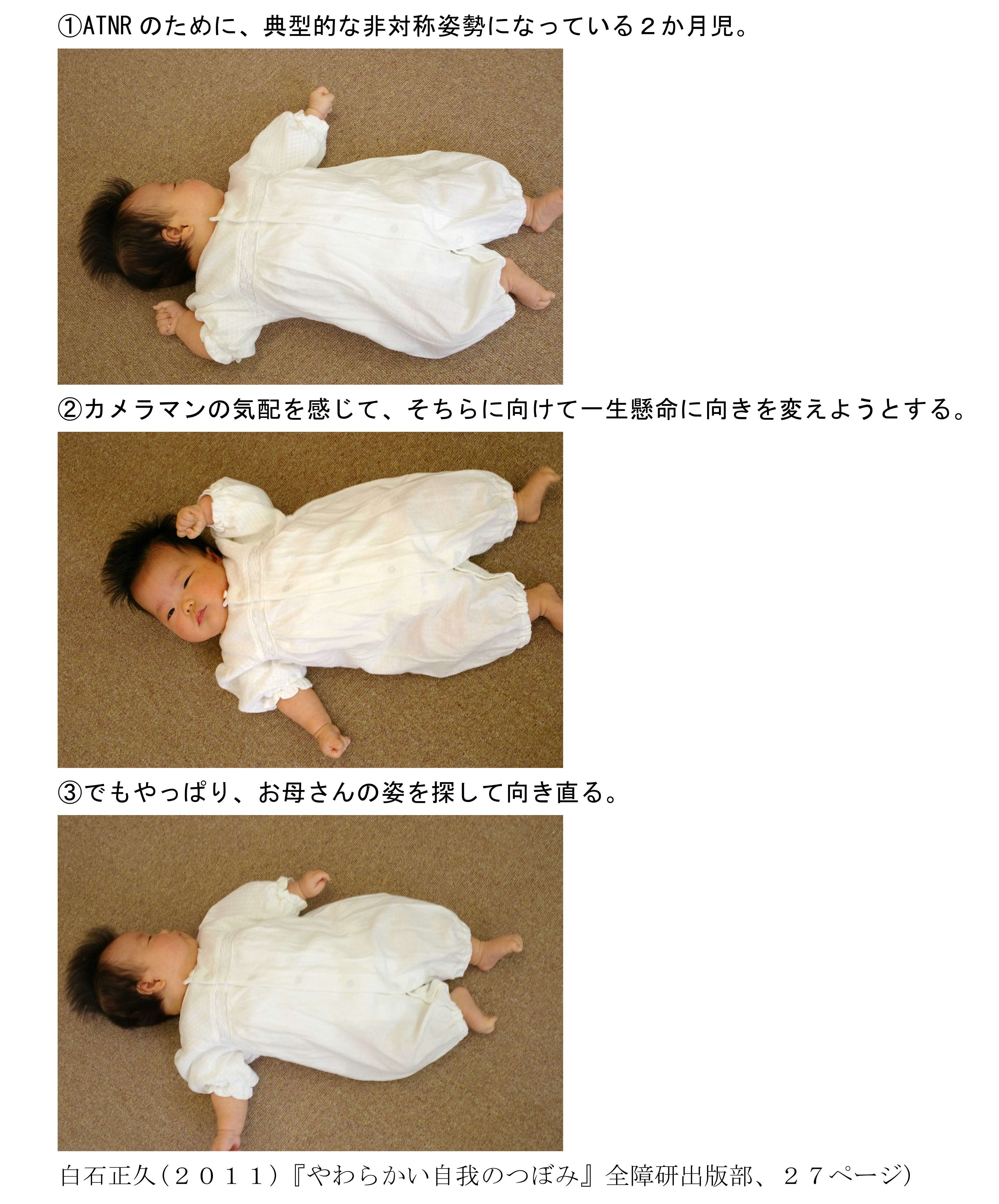
追視は、左右いずれかが上手で、まだ往復(可逆)追視が確実にできるわけではありません。しかし、視線が途切れても、もう一度それを見つけることができるようになります。そして、日ごろはたらきかけてくれる人の顔を追跡するようにもなります。見失っても、もう一度見つけようとすることでしょう。そのような「途切れても戻る」という復元性があるから、外界への意欲的な探索がたしかになっていくのです。やがて「行って戻る」という自由度のある往復追視へと発展していきます。
この過程では、心地よい世界を創ってくれる特定の他者への「人を求めてやまない心」が、感覚や運動の発達を牽引(けんいん)しているようにみえます。すでにこの段階で、「人」は特別な意味をもちはじめているのです。
・不快や機嫌の悪さからの復元
「回転軸2形成期」では、おとなが一方的に名前を呼んだり、歌いかけるだけで、心のキャッチボールをしてくれないときには、機嫌が悪くなって泣き出してしまうことがあります。小さいけれども、ちゃんと心の動きを受けとめてくれる関わりをしてほしいのです。
このように「2」のつく発達段階の準備のはじまる「形成期」では、乳児期前半の「快と不快」、乳児期後半の外界への「興味と不安」というように、まるで硬貨の表裏の関係で結びついている相反する情動・感情が生まれます(情動と感情は明確には区別されず、情動は喜怒哀楽などとして分化していく社会的感情の原初のレベル、短時間で生じる強い感情のことを言います。乳児期前半の発達の階層における快と不快は、ここでは情動としました)。肯定的な情動・感情が妨げられたり、状況が変化することによって、快から不快が、興味から不安がというように、情動・感情が変転していくのです。
このときの情動や感情の不安定さの背景には、聴きたい、見たいという外界への欲求を高めながら、そのための感覚や運動が思い通りには使えないという矛盾があります。このときに、子どもの機嫌の悪さや不安の強まりを我がことのように受けとめ、その感情をなんとか元に戻そうとしてくれたり、思い通りにならない運動に手をさしのべてくれる人がいることによって、子どもは不快や不安から、情動・感情を復元させていくことができるのです。
・第2段階から第3段階への移行(回転軸3形成期)と「生後第1の新しい発達の力」の誕生
「回転軸2可逆操作期」から「回転軸3可逆操作期」に向かう「回転軸3形成期」(4か月ころ)では、外界をとらえる視覚や聴覚、躯幹、四肢、手指の運動の自由の拡大によって、少し遠くにあるものも欲しがるようになります。伏臥位(ふくがい。うつ伏せのこと)では、肘で支えて頸を挙げる肘支位(ちゅうしい)ができるようになり、左右方向にあるものを取ろうとして寝返りにも挑戦します。自分では座れませんが、膝の上で支えてやれば頸はすわっており、支座位で、左右、上下の追視をし、音源も探すようになります。
正面に2つのおもちゃを出すと、一方だけではなく他方にも視線を向けて、一つだけではないモノに手を出そうとします。これが『みんなのねがい』5月号(28ページ下段)で解説した「可逆対(つい)追視」の芽生えである「対追視」です。そのことによって一方だけではない、さまざまな方向やモノに注意を向け、そのなかから選択的な関わりをするようになるのです(「対追視」は『下巻』42ペーシと46ページで写真とともに解説されています)。
このころ、相手の顔をまじまじと見つめ、それが誰であるかわかったように、子どもから微笑みかけるようになります。つまり、一つではないものを視野に入れることができるようになって、人と人を区別し、その人をその人と分かったうえで、自分から微笑みかけようとしているようです。つまり、あやされたことがうれしくて微笑むのではなく、子どものなかに「わかった!」というような認識と情動が生まれて、自分から他者に向かってはたらきかけようとしているのです。これが5月号(28ページ下段~29ページ上段)で取り上げた「ひとしり初(そ)めしほほえみ」です。乳児期後半の「連結可逆操作の階層」において、発達を主導する役割をはたすコミュニケーション手段と人間関係が芽生えているのです(「ひとしり初めしほほえみ」は『下巻』41ページで解説されています)。
こういった主体的なコミュニケーションや自らモノをつかもうとする活動などが、仰臥位だけではなく、支座位や伏臥位という楽ではない抵抗のある姿勢でもなされるようになります。さらに、他児が離乳食を食べさせてもらっている姿や、それを援助しているおとなを見比べて、自分にも食べさせてほしいというしぐさをするようになります。人と人の「対」の関係をとらえて、それを欲求の対象とするようになっていくのです。
ハルちゃんの発達から学ぶ
・追視の応答にみる復元性
さて、5月号のハルちゃんは、どのように発達の道すじを歩いていたのでしょうか。重症児の場合には脳性マヒ、中枢性の視覚障害、さらには難治性てんかんや抗てんかん薬の副作用による覚醒のふたしかさなどがあり、運動、感覚、コミュニケーションなどの応答が安定しないことがほとんどです。そのときに、たとえば往復追視ができないからと言って、「回転軸2可逆操作」を獲得していないとは言えないでしょう。
ハルちゃんも、視覚障害があって「見えにくい」と言われていました。しかし、丹波養護学校亀岡分校の先生方の教材への強い思いによって創られた『三びきのやぎのがらがらどん』の授業のなかで、ハルちゃんは緊張や非対称姿勢に打ち克って、「やぎ」の動きを追視したのです。それは「やぎ」への追視でしたが、歌い、語りかけ、そしてからだを包みこむように受けとめてくれていた先生方への「人を求めてやまない心」が、見たい、聴きたいという思いになって結実したのだと思います。事実、朝の「呼名」では、「まるで細い糸で結ばれたように」先生の顔を追いつづけました。「途切れても戻る」という追視の復元性が、たしかになっていったのです。もちろん、視覚障害ゆえに、よどみなく追視しつづけられたわけではありませんでした。しかし、この復元性は、往復追視ができること以上に発達の本質的な力としてとらえられるのです。しかも、そのときに「もう一人」の先生のはたらきかけを待っていたように、ニッコリ微笑んでくれました。そこには、「対追視」と同じように外界を知り分け、それぞれを自分のなかに取り込んでいこうとする「心の窓」が開き始めていました。
・発達の一歩前からのはたらきかけ
ハルちゃんの発達をたどると、教育のなかに大切なはたらきかけがあったことに気づきます。『三びきのやぎのがらがらどん』の授業では、「次の展開を予期し意欲を高めていけるような工夫」(27ページ下段)が随所になされていました。次の展開を予期することは、「回転軸2可逆操作」を獲得しようとしている子どもにとっては、まだむずかしいことです。しかし、「今」と「次」の関係が心に残るように、楽しい音楽、「おや、なんだろう」と思える登場物、心弾むような先生の声というハルちゃんの大好きなことを手がかりにして、発達の一歩前からはたらきかけていったのです。一人だけではない「もう一人」の先生が、それぞれの語り方を大切にしてハルちゃんにはたらきかけていたことも、発達の一歩前からのはたらきかけであったと思われます。
「一歩前からのはたらきかけ」とは、次の発達段階の特徴をもった少しむずかしいことだけれど、やってみようと思える活動を発達的な抵抗として組織することで、子どもが発達の矛盾を乗り越えようとするように導くということです。その答えは、すぐに出るものではありません。しかし、長い見通しのなかで、一日一日の授業を楽しみながら積み重ねていくという日常を大切にすることによって、ハルちゃんは一人ではない、もう一人の先生の「呼名」も予期できるようになっていきました。
予期は認識の力ですが、次をワクワク期待するという情意の力とつながっていきます。期待の芽生えは、「生後第1の新しい発達の力」(4か月ころ)として大切な役割を果たすことになります。
発達を過程として理解する
乳児期前半の「回転軸可逆操作の階層」にある子どもを担当されている方は、多くはないでしょう。また、最重度の子どもを指導する自信がないので、担当になることは回避したいという思いも、現場にはあると聞きました。しかし、このテーマを5月号において選択したのには、私たちなりの願いがあります。
5月号で書いたように、「ともに生きる」あるいは「いのちを守る」営みへの想像力の大切さを、みなさんと共有したいという思いがありました。しかし、それだけではありません。
発達の学習は、担当している子どものことを理解するために大切だと思われていることでしょう。だから、その子どもが「今」歩んでいる発達の道すじに焦点を当てて、その発達段階の特徴から学ぶことはよくあることですし、そうすることで子ども理解のヒントが得られることはたしかです。しかし、目の前にいる子どものなかには、その発達段階にいたるまでに歩んできた発達の道すじが、見えないけれども存在しているのです。そして、これからまだ長い発達の道すじを、一生懸命に歩いていくのです。
たとえば今回解説した「回転軸2形成期」(2か月)ころの「切れても戻る」復元性や快・不快の情動を調節することは、やがて「生後第1の新しい発達の力」の誕生において、コミュニケーションの主人公になり、外界に自らはたらきかける力に発展していきます。それは、伏臥位や支座位でもその力を発揮しようとする、抵抗に立ち向かう姿につながっていくことでしょう。そして、その子らしい人格の特徴として、一人の人間のなかに積み重なっていきます。そういった過程を遡(さかのぼ)り、その子の歩いてきた発達の道すじのすべてを知ろうとすること、そしてその道すじに関わってきた保育や教育、生活のありようを知ることは、きっと子どもの理解に深みを与えてくれます。それは、子どもの発達を目に見える技能、能力において理解するだけではなく、情動や感情、意欲や意志、自我のありようなど、一人ひとりの人格を形づくる大切なことに目を向けることにもなるでしょう。
そして、発達の道すじのすべてを知ることは、目の前の子どもの理解を深めるだけではありません。人間は、発達において挫(くじ)けそうになっても、人とつながりながら自らを復元させ、やがて抵抗に立ち向かい、螺旋階段をのぼろうとするのです。そういった発達の道すじを貫く発達の法則を生き生きと認識することは、「人間というもの」、つまり人間の普遍性を理解していくことにつながると私たちは考えています。発達を通して「人間というもの」を知ることは、他者を慈しみ、そして自分を慈しみながら、共に生きていくための大切な「心の目」を与えてくれるはずです。
今回の学習参考文献
・白石正久・白石恵理子編(2020)『新版・教育と保育のための発達診断・下巻』全障研出版部
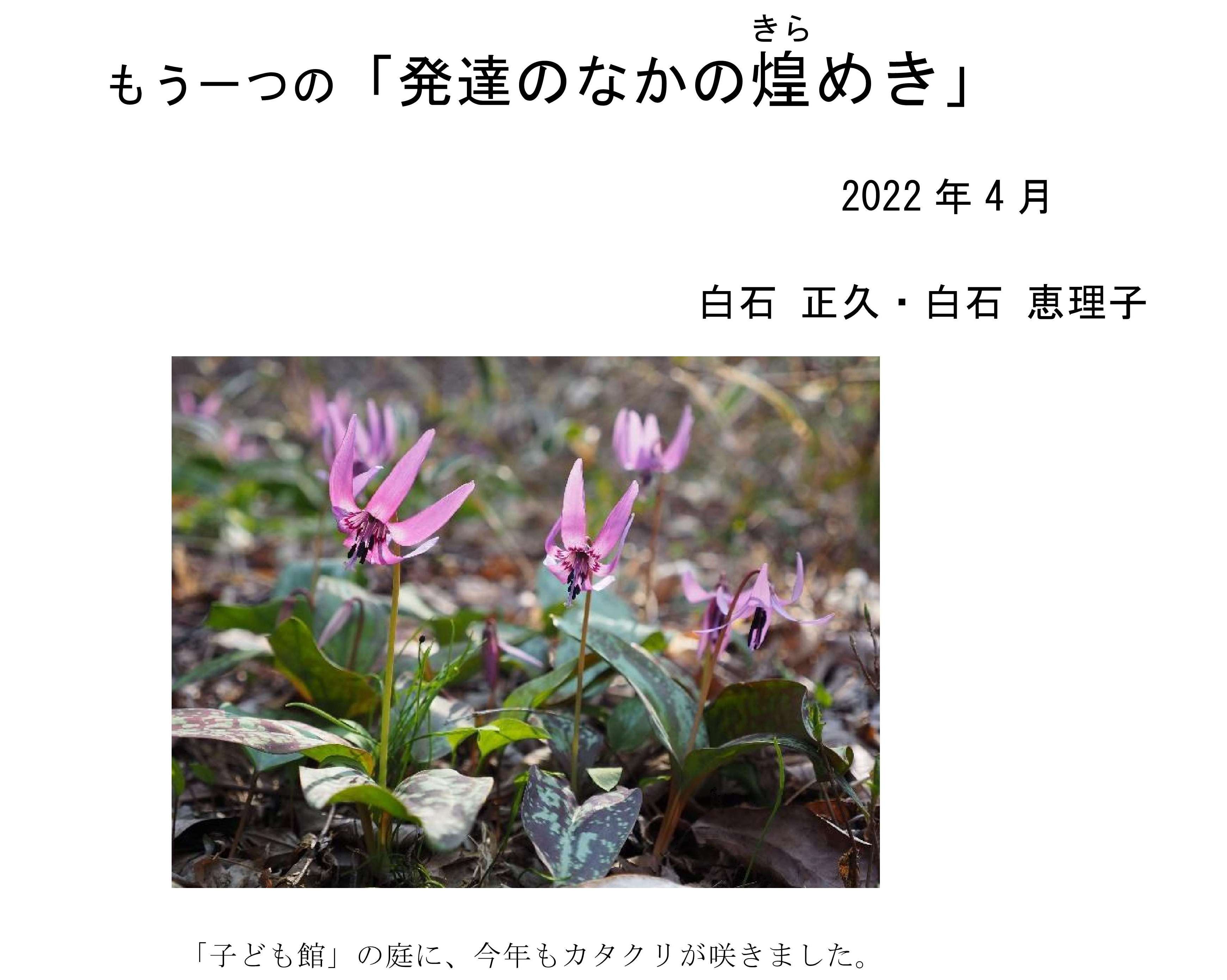
第1回 「障害のある子ども・なかまの発達」を学ぶために
4月号の「生きる・つながる・発達する」はいかがだったでしょうか。私たちのもとで学んだ卒業生たちのしごとの日常を紡ぎあわせて、一つの手紙にしてみました。
さて、この「もう一つの『発達のなかの煌めき』」は、『みんなのねがい』の連載、「発達のなかの煌めき」をお読みいただいている皆さんに、学習や討議を進めていくための手がかりを提供したいと企画したものです。連載の目的の一つである系統的な発達の学習が進められるように、私たちが編集したテキスト『新版・教育と保育のための発達診断・上巻―発達診断の基礎理論』(以下『上巻』)、『新版・教育と保育のための発達診断・下巻―発達診断の視点と方法』(以下『下巻』)を活用し、解説していきます (『上巻』は、今夏の刊行をめざして準備しています)。
発達の学習に王道はない
私たちが発達理論を学び始めた学生時代、授業で学んでも、テキストを読んでも、大切なことは頭に入らず、理解が進まないことへのイラだちばかりを味わっていたものです。「学問に王道はない」のたとえ通り、テキストを100回は読み込まなければならないのだと自覚しました。そのころのボロボロになったテキストを学生たちに見せて、学習は苦労の多いものであり、本がきれいなままでいるはずはないと説いています。しかし、もっと大切なことは、理論と実践の間を何度も往復し、実際に向きあっている子どもやなかまのことを思い浮かべたり、指導・支援のありかたを問いながら学習していくことです。そうすれば、実践のなかでの子どもやなかまの姿から教えられ、学んだことが自分の奥底に染み渡るように、生きてはたらく力になるときがやってきます。楽ではない学習の過程だからこそ、一人ではなくみんなで、知恵や意見を出しあいながら学んでいくことが大切なのでしょう。
発達とは何か
それでは連載第1回「生きる・つながる・発達する」の解説編に入ります。
発達は、人がよりよく生きるために一生懸命に事物や事象(自然や文化)にはたらきかけ、創造、変革しつつ、自分をも変革していく過程です。さらに、他者と向きあい葛藤しながらも、手をつなぎあうことの大切さを知り、そのつながりや集団を通じて、みんなが幸福になれる社会を創ることにも関わっていく過程であることを、今回の「生きる・つながる・発達する」では素描してみました。一人ひとりの発達は「閉じた」道すじではなく、社会とその歴史、集団、生活や労働、教育や支援のありかたとつながった「開いた」道すじであり、そのつながりのなかで、人格の輝きをもつようになるのです。
そして発達は、子どもやなかまのことだけではなく、私たちのことでもあります。
このことを念頭におきつつ、ここでは、これからの連載第Ⅰ部「障害のある子ども・なかまの発達」のために、「発達とは何か」ということを中心に整理したいと思います。
まず、私たちが参加する全国障害者問題研究会(以下では全障研)の結成大会(1967年)の基調報告を紹介します。『下巻』の192ページから引用します。
「これまでわたくしたちは、はやく、たくさん、たくみに答えを出すことをめざす体制の中で育てられてきたので、発達とは、できないことができるようになる、上へのびていくことだという理解のしかたをしてきました。(中略)機能別あるいは領域別に比較し、ちがいとおとっている点をかぞえあげることを発達研究とよび、細かい尺度をつくって、できないことができるようになることをおいもとめたりします。つまり発達とは個人が連続的、調和的に上へのび、社会に適応していく過程だと理解していたわけです。
しかし教育実践の中で発達とは、そのような受身的、連続的な適応の過程ではなく、主体的に外界にとりくみ、外界を変革していく過程としてとらえなければならないのだということをしり、討議をすすめることができてきました。それによって、IQなどをすてることもできるのではないかといわれたりしています。しかも、発達はたとえば、獲得した操作のしかたが高次化するという、一つの方向へのびるだけではなく、獲得した操作のしかたを、志向的に、豊かな自由度をもって高めていく、いわばヨコへの発達を必然的に内包しているのだということも討議することができだしました」。
当時、発達は「できないことができるようになる」「できることが増える」という成長の事実とその量的な拡大として理解されていました。知的障害がある場合には、IQ(知能指数)やDQ(発達指数)を用いて、機能・能力のアンバランスを描き出し、障害に固有な傾向や、人格の特徴をも説明しようとされていました。障害のある人びとを人間としての普遍性や共通性において理解しようとする視点は、当時の発達研究には乏しかったのです。
また、このような視点は、「できないことをできるようにする」「遅れている機能・領域を引き上げる」「障害の宿命的特徴として教育を放棄する」ような教育の方法と結びついていました。そこでは子ども本当の思いである、感情、意欲、意志などは見過ごされ、ただ受動体としてとらえる見方が支配的になっていました。
教育制度においては、全障研が結成された当時、「精神薄弱児」と呼ばれた知的障害のある子どもは、1953年文部省通達「教育上特別な取扱を要する児童生徒の判別基準について」で「精神発育が恒久的に遅滞」したものであるとされ、1957年通達「精神薄弱の学齢児童生徒に関する就学について」などによって義務教育から実際に排除されていました。
一方、その社会の一隅において、「精神薄弱児」入所施設・滋賀県立近江学園では、文部省の「判別基準」に対して、「育ちのなかにねうちを発見して、そのみちすじをたしかなものにしていく」という姿勢に立って、「発達しないとみられている人たちの発達を研究し、発達の道を拓こう」という意志をもった研究が取り組まれ始めていました。後に全障研の初代全国委員長となった田中昌人さんが、近江学園研究部に就職したのは1956年のことです。
さらに1963年に開設された重症心身障害児施設・びわこ学園などにおいて、「障害のある子どもの再発見」と言うべき事実が見出されていきました。「寝たきり」と言われた重症児が、粘り強い実践のなかで生涯においてはじめての笑顔を花開かせた姿、介護の保育士のオムツを換える手を助けようと、あらん限りの力で腰を浮かそうとする姿、「動き回る」といわれた多動な子どもが、すくってはこぼし、押しては戻す動きのなかで、「…ではない…だ」という1歳半頃の力を自分のものにしようとしている姿、そしてマヒのある不自由さに打ち克って、友だちの動きにあわせながら食事を食べさせようとする姿がありました(「びわこ学園」の療育記録映画『夜明け前の子どもたち』1968年。また『上巻』第Ⅲ部・第1章「乳児期の発達段階と発達保障」)。これらの実践は、どんなに障害の重い子どもも自ら外界や他者にはたらきかけ、そうすることで外界、他者との関係、自分自身を創造し、それを取り込みながら自分を変革していこうとする発達の主体であることを見出してきました。
その頃、こういった施設実践と呼応するように全国各地で広がっていた障害児の不就学をなくす運動と実践のなかで確かめられた多くの発達の事実が、近江学園などでの研究と一つに練り上げられ、先の全障研結成大会「基調報告」に書かれた発達観・教育観となっていきました。これらの経過は、『上巻』の第Ⅰ部「子ども・障害のある人たちの権利と発達保障」で解説されています。ぜひ、お読みください。
「発達段階」と「発達の節」
この「もう一つ『発達のなかの煌めき』」の連載では、「障害のある子ども・なかまの発達」について、発達の道すじにそって解説していきます。今回はまず、「発達段階」と「発達の節」について説明します。『下巻』6ページの図2「発達段階の説明図」を参照してください。
発達とは、坂道をのぼっていくようなものではなく、どちらかというと階段をのぼっていくような変化です。階段の横面(踏面)にあたる部分が「発達段階」、縦面(けあげ)にあたる部分が「発達の節」ととらえていいでしょう。言い換えると、発達には量的変化を中心とする時期と、質的変化を中心とする時期が交互に訪れるということです。ある発達段階において、量的蓄積が少しずつ進んでいき、それが一定の限度を超えると新しい質の獲得に至ります。これは、人間の発達だけではなく、自然や社会の様々な事物や事象においてみられる変化であり、あらゆる事物や事象はこうした変化、すなわち運動を続けます。氷、水、さらには水蒸気への変化をイメージしてもらってもよいと思います。
発達をこのように量的変化と質的変化の両面からとらえる見方は古くからあったのですが、障害のある子どもたちに対しては、なかなかそのようにとらえられてきませんでした。すでに述べたように、子どもの発達をとらえる指標として、基本的にIQ(知能指数)やDQ(発達指数)が用いられることが多いのですが、これは知能検査もしくは発達検査から得られた結果(精神年齢、発達年齢)を実際の年齢(暦年齢)で割って100倍した数値です。たとえば、5歳の子のIQが60であるということは、精神年齢が3歳ということになります。その子が10歳になったときに再度、知能検査を受けて結果(精神年齢)が4歳であったとします。「3歳」から「4歳」に変化していますから、きっと話しことばでのやりとりが広がってきたのだろうな、色や数などの抽象的なことにも興味をもって、わかりかけてきたのかな…と大きな変化を実感できるはずですが、IQでみると、60から40に低下することになり、療育手帳では「軽度」判定から「中度」判定に変わることになります。発達的に変化していると思うのに、検査を受けたらより数値が低くなっていたということで親御さんがショックを受けたというような話はよく聞かれるのではないでしょうか。IQやDQ、さらに言えば精神年齢、発達年齢でとらえることの問題点については、『下巻』第Ⅰ部「発達保障のための子ども理解の方法」(14-32ページ)で説明されています。
「可逆操作の高次化における階層-段階理論」
戦後、「教育勅語」は否定され、教育は国家や天皇のためのものではなく、一人ひとりの子どものためのものとして大きく価値転換がなされました。学校教育法に障害のある子どものための学校や学級も位置づけられました。しかし先に述べたように、障害が重い子どもについては、IQが低い=障害が「重度」であるという理由で、教育の対象とはみなされず、学校に行きたくても行けない「不就学」の時代が続いたのです。そうした子どもたちを受け入れていた近江学園で、1950年代後半から田中昌人さんを中心に、IQによってではなく、子どもの「内側から把握する」ことをめざして発達研究が取り組まれました。その後、その発達過程を「可逆操作の高次化における階層-段階理論」として提起していきました。
ここでも、『下巻』6ページの図2「発達段階の説明図」を参照してください。この理論では、発達の基本単位として可逆操作に注目しました。可逆操作については、あらためて詳しくとりあげますが、ここではとりあえず、発達の主体は子ども自身であり、子どもが外界や自分自身にはたらきかけながら自分自身を変革していくプロセスが発達であるという発達観にたち、そのはたらきかけのしかた、外界や自分自身の認識のしかたを示すものとして可逆操作なるものをとらえたとおさえておきます。そして、通常、生まれてから9,10歳にいたるまでに、3つの種類の可逆操作をとりだすことができるとし、それを「回転可逆操作」「連結可逆操作」「次元可逆操作」と名づけました。その後、9,10歳以降についても仮説的に提起されていきますが、この連載では、9,10歳ころまでをとりあげます。「回転」「連結」「次元」の意味するところは、これからの連載でふれていきます。
通常、生後半年間は「回転可逆操作」を特徴とする時期で「回転可逆操作の階層」(通常の「乳児期前半」にあたります)、生後半年をこえて1歳前半までが「連結可逆操作の階層」(「乳児期後半」にあたります)、さらに「1歳半の節」からが「次元可逆操作の階層」となり、この生後第3の階層は7,8歳ころまで続きます。この「階層」という用語も難しいですが、複数の段階を含み込んだ、より大きな段階ととらえればよいと思います。階層のなかには複数の段階を含むと書きましたが、上記理論では、それぞれの発達の階層に3つずつの発達段階があるとします。第1段階、第2段階、第3段階と進んでいき、次は第4段階かと思いきや、第4段階ではなく、新しい質をもった次の階層の可逆操作の獲得に進んでいくとしたのです。発達は「4」にはならず、「3」を積みあげていく螺旋階段の構造であることについては、『上巻』第Ⅲ部・第1章「乳児期の発達段階と発達保障」で説明しています。
「回転可逆操作」から「連結可逆操作」、「連結可逆操作」から「次元可逆操作」などと可逆操作の質が大きく変わる「飛躍的以降の時期」、すなわち「大きな発達の節」として取り出せるのが「6、7か月の節」「1歳半の節」「9歳の節」ということになります。
先ほど階段をのぼるような変化と書きましたが、この「大きな発達の節」さらには、それぞれの階層内の「発達の節」は、決して簡単なものではありません。質的な変化が行われるということは、言い換えると、それまでの「古い自分」を崩して「新しい自分」をつくりあげるという至難のプロセスでもあるのです。4月号に登場したリョウちゃんは「4歳の節」にあると書かれていましたが、この「節」においても、それまで「お兄ちゃん」「お姉ちゃん」と言われることに嬉しさを感じてきた子が、おとなから押しつけられる「お兄ちゃん」「お姉ちゃん」に抵抗して、自分なりに「大きくなる」ことの中身をとらえようとして反抗を強めたり、それまで以上に周囲や自分がみえてきて、思い通りにならない現実に自分を否定的にとらえイラだちを強めることがあります。こうした姿を単に「問題行動」とみるだけではなく、子どもの内側にどのような葛藤があるのか、どのようなねがいがうまれているのかを考えること、そして、その葛藤を自分で乗り越えていけるようなエネルギーを蓄えられるようにすることが教育に課せられていると言えるでしょう。そのために、『みんなのねがい』4月号32ページの写真のような子どもの後ろ姿から、その内面を理解できるまなざしを、私たちはもちたいとねがいます。なお、「4歳の節」については、連載第7回と第8回で、あらためて取り上げることにしています。
卒業生への返信
最後にこのページを借りて、4月号に手紙を寄せてくれた卒業生に、一言の返信をしておきたいと思います。
お便り、うれしく拝見しました。私たちは元気にやっています。今年は、卒業生の皆さんとお会いできる日があることを楽しみにしています。その前に少しだけご返事を書きます。
リョウちゃんのお母さんから、「真紅の車を見ると先生のことをいつも思い出した」と聞いて、お母さんのなかにずっと留まり苦しめていたあなたのかつての未熟さを、「謝らなければならない」と思ったのですね。学生時代、いつも他者への気遣いをしていたあなたのことを思い出しています。でも、あなたの言葉から察するリョウちゃんのお母さんは、違う思いで赤い車を眺めていたのではないかと私たちは思います。
中学部2年生のリョウちゃんの担任になったあなたは、お母さんから見れば「一回り」以上も歳の違う新任の先生だったのです。そのときには、「この先生、大丈夫だろうか」と心配になったかもしれません。お母さんも感じていたであろう学校という職場の大変さのなかで、この若い先生が教師として育っていってくれることを、祈るような気持ちで見つめていたのではありませんか。だから、同じ色の車に出会うと、あなたのことをいつも想ってくれていたのだと私たちは感じました。10年ぶりに、教師としてがんばり続けているあなたに出会えて、お母さんは安堵したのです。私たちも「発達相談員」としての駆け出しのころ、同じようにお母さんお父さんたちに見守られ、ときに叱咤激励されながら、一歩一歩を重ねてきたことを、昨日のことのように思います。
もう一つ、これは私たちからの質問です。お手紙には、リョウちゃんが両手で慎重に卵を割るときの、手先を見つめる真剣なまなざしに、「4歳の節」を乗り越えているという実感をもつことができたと書かれていました。この「実感」とは、どんなことだったのでしょうか。卵に注意を集中しながら両手で割る、あるいは左右の手のそれぞれに注意を向け協応させながら卵を割るという、「…しながら…する」2次元可逆操作の獲得のことは、理解してくださっているようですが、このくだりを読んで、それだけではない「4歳の節」の大切なことがあると私たちは直感しました。それは、生活のプロセスのなかに、その能力を自らの必要によって取り込んでいこうする発達要求が発揮されるときがあったということです。きっと家庭生活において、リョウちゃんが「真剣なまなざし」になって、卵を割ろうとした瞬間があったはずです。その場面は何であったのか、そのときの発達要求とは何かを、私たちは知りたくなりました。今度お会いしたときに教えてください。宿題のようですいません。
この冬は寒かったですね。重い空気に包まれたこの世界にも、春の花は咲いてくれました。
声明
ウクライナにおける武力行使と戦争に反対し、障害のある人と家族のいのちと安全を守ろう
2022年3月10日
全国障害者問題研究会常任全国委員会
このたびのロシア政府によるウクライナへの軍事侵攻は、国連憲章に反する侵略行為であり、武力により他国の主権を侵害すること、戦争によって人々の生活を破壊し、子どもを含めた多くのいのちを犠牲にすることは、いかなる理由によっても正当化できません。さらにロシア軍は原発施設を占拠し、プーチン大統領は、核兵器の先制使用も示唆しています。核兵器の使用は、人類の生存を脅かし、地球環境を破滅に向かわせる、決して歩んではならない最悪の道です。わたしたちは、全世界の人びとのいのちとくらしを危機に追いやる核戦争へとつながりかねない軍事侵攻の即時中止を強く求めます。
一方、日本政府は、ウクライナへの自衛隊の「防衛装備品」の供与を決定しましたが、これは紛争当事国への「武器輸出」に相当し、容認できません。さらに、この機に乗じて日米が共同で管理・運用する「核共有」や憲法9条改正の議論を押し進めようとする動きすら出ています。唯一の戦争被爆国であり、戦争放棄を掲げる憲法9条をもつ日本が、ウクライナにおける武力行使や戦争の拡大に加担することは決して許されません。
戦禍を逃れて周辺国に避難するウクライナの人びとへの人道的支援がはじまっています。ウクライナ国内では、食料品の不足をはじめ、深刻なライフラインの危機に陥っており、障害のある人びとと家族が生き延びるうえでいっそうの困難が予想されます。ウクライナの障害のある人びとと家族が、障害者権利条約第11条(危険のある状況及び人道上の緊急事態)に則して保護されるとともに、食料と住居、移動と情報手段の確保、医療とリハビリテーションの提供などが、国際機関や諸国の連帯によってすみやかになされるよう求めます。
第二次世界大戦後の国際社会は、戦争の歴史を深く反省し、平和と民主主義の実現にむけて共同の歩みをすすめてきました。そのなかで、戦争を含む、あらゆるかたちの暴力が障害を発生させる最大の要因であること、戦争の悲劇を繰り返すことなく、平和な社会が実現されてこそ、障害のある人びとの人権が保障されることを歴史の教訓として、すべての人の権利保障の道を一歩一歩切り拓きながら、障害者権利条約を手にしました。
全国障害者問題研究会は、戦争がもたらす惨禍への反省のうえに「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和の内に生存する権利を有すること」を謳った日本国憲法の理念を、障害のある人びとの権利において実現することをめざして研究運動をすすめてきました。わたしたちは、生命・生存・発達の権利を保障しようとする発達保障の理念に立ち、ウクライナにおける武力行使と戦争に強く反対します。
▶PDFデータです
「障害者問題研究」49巻4号
特集=障害のある人の思春期における発達と教育実践
詳細案内 「ちょっと見」やオンラインでのご注文は以下のホームページへ
▶「障害者問題研究」49巻4号 特集=障害のある人の思春期における発達と教育実践
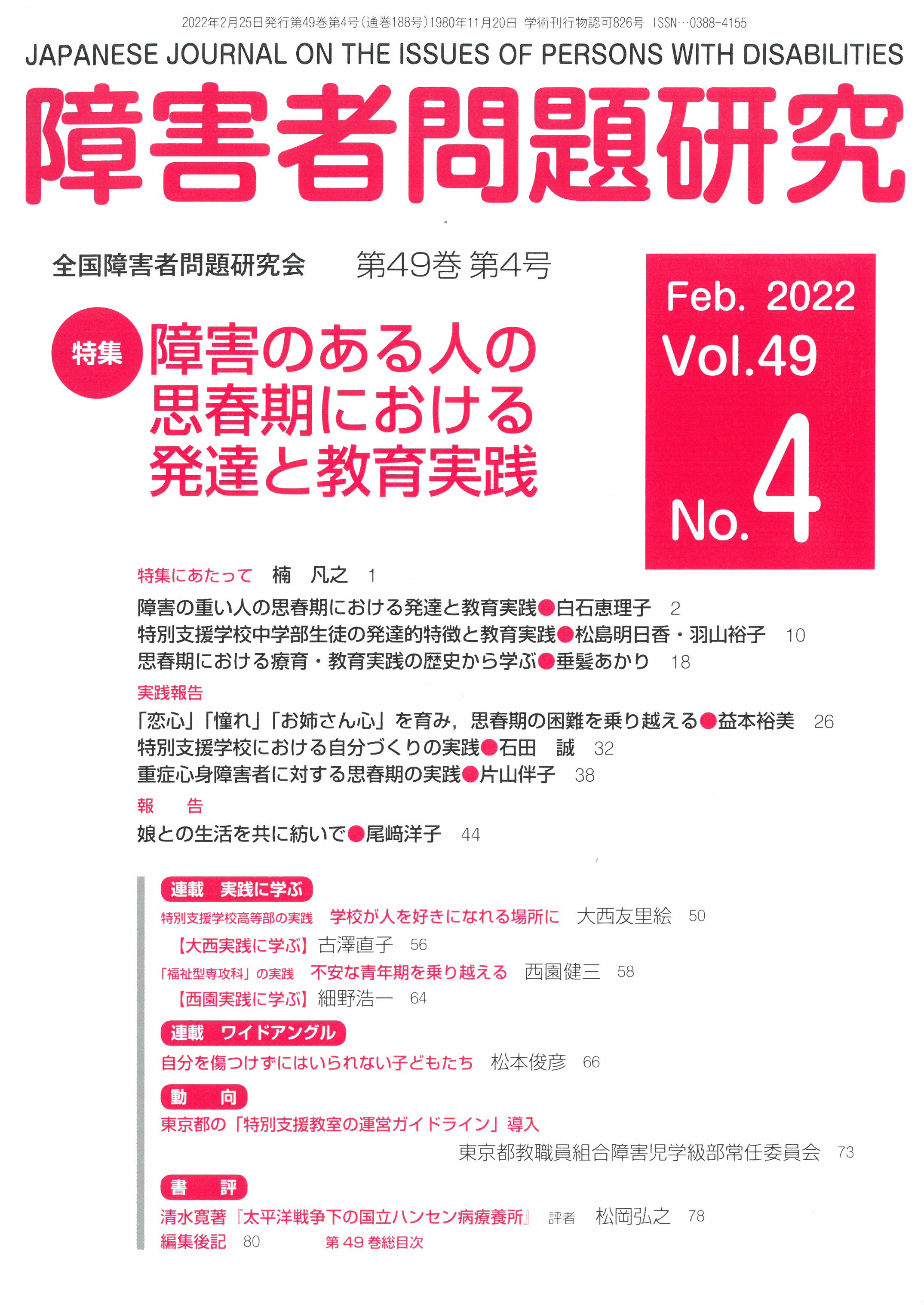
「障害者問題研究」49巻3号
特集=教育実践における教材 読む会のお知らせです
◆障害者問題研究49巻3号を読む会
日時=2022年1月21日(金)19時~21時
■話題提供■
■1 猪澤由起子さん(奈良教育大学附属小学校)
絵本を楽しみ,なかまと学ぶ「ことば」の授業づくり
■2 越野和之さん(奈良教育大学)
障害のある子どもの学校教育と教材・教具
■参加者の意見交流
★Zoomによる開催
申込は https://forms.gle/yHFVKXSnr8r8gkQ89
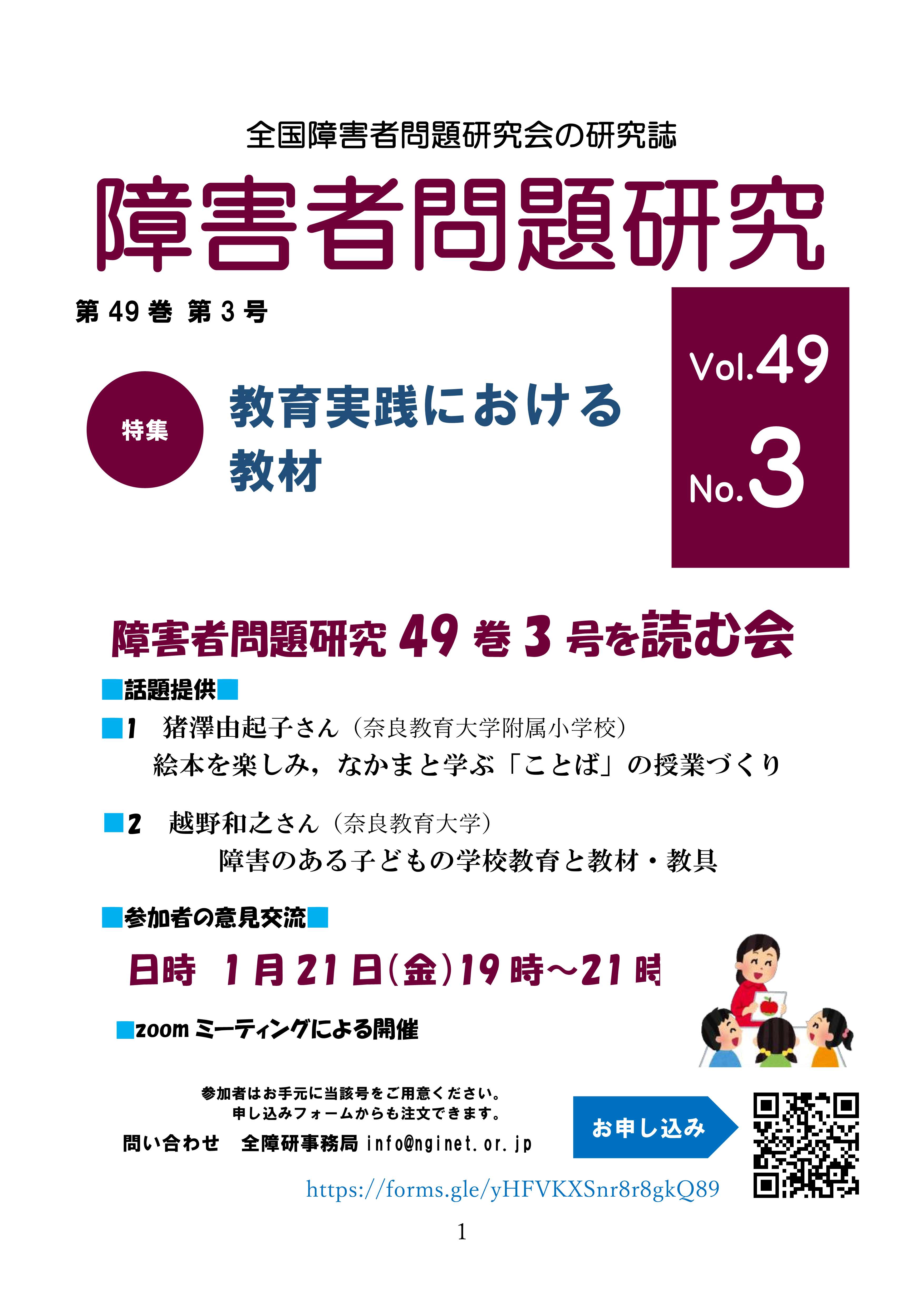
詳細案内・「ちょっと見」やオンラインでのご注文は以下のホームページへ
▶「障害者問題研究」49巻3号 特集=教育実践における教材
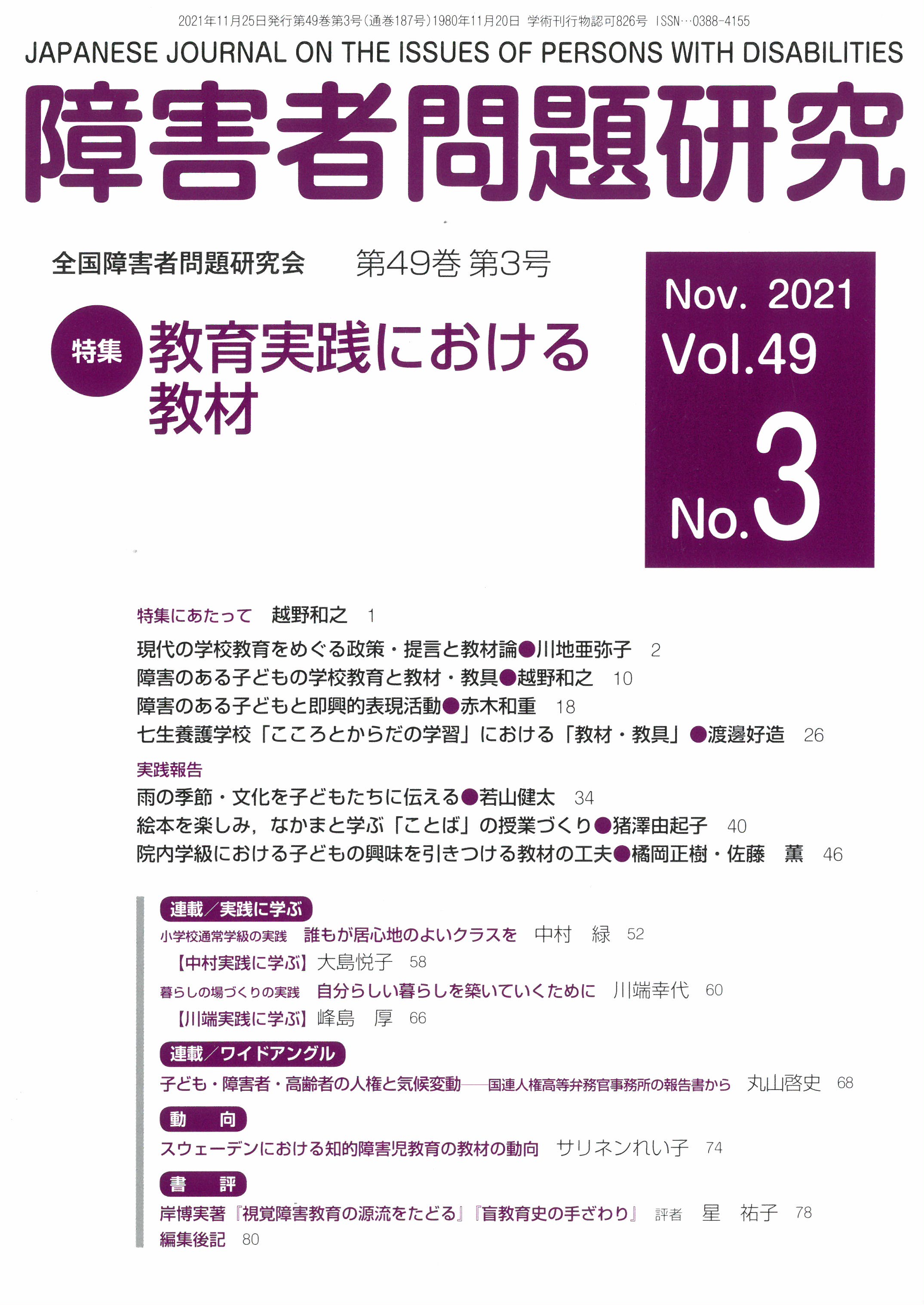
本づくりを支え、学びの”わ”を広げるプロジェクトです
待望の刊行です!

越野和之(奈良教育大学・全障研委員長)・河合隆平(東京都立大学・全障研副委員長)編
『子どものねがいと教師のしごと
―障害のある子どもと創る教育実践の記録』
第1章=障害の重い子どものねがいを聴き取る(鈴木輝子、南有紀、阿部直俊)
第2章=からだと心をひらき文化を手渡す(野津保、鶴町喜代子、松本将孝、大前学)
第3章=仲間とともに学びあう子どもたち(小島貴子、箕浦啓太、与倉麻美)
第4章=子どもと向き合う教師たち(塚田直也、村上徹、鈴木こずえ)
▶詳細案内のページへ
出版記念オンライン学習会
日時:2021年12月4日 (土)講師=竹沢清さん 全国から50人の参加で盛況でした
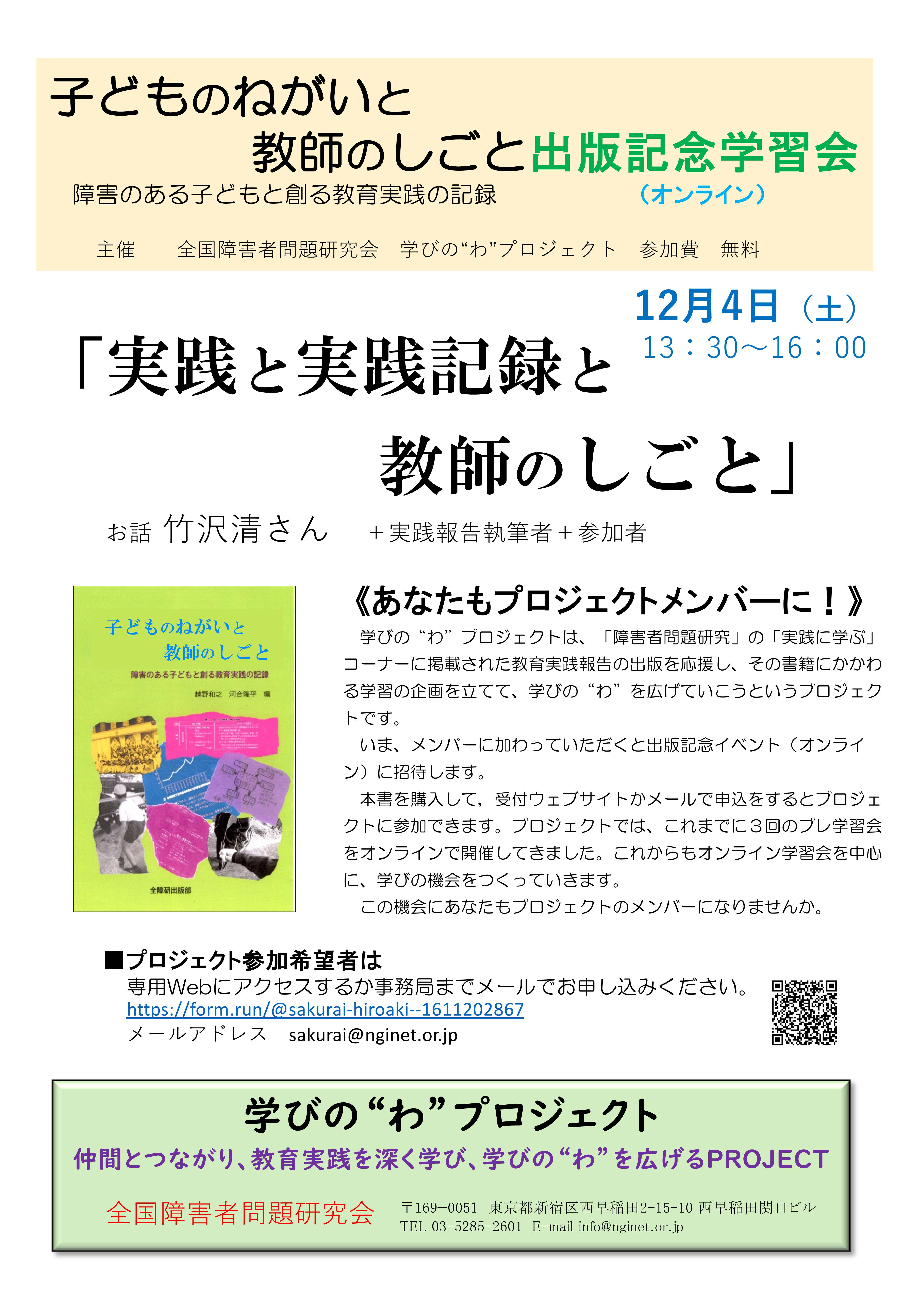
全障研「学びの“わ”プロジェクト」
コロナ禍で教育実践を深く学びにくくなった方、自分の近くに語り合える仲間が見つからずサークル活動に一歩が踏み出せなかった方、この機会に一緒に学びの“わ”を広げませんか。
このプロジェクトのコンセプトは、
◯学びの機会をつくる ◯学びの仲間をつくる ◯学びのうねりをつくる
です。
具体的には、別紙資料にあるように「本づくりを支える」こととその本にかかわった「学びあいの“わ”を広げる」活動を行います。
◯書籍を刊行します=障害者問題研究の「実践に学ぶ」コーナーに掲載された教育実践報告の出版の資金援助を行います。
◯オンライン学習会を開催します=出版前から、そして出版後も障害者問題研究の「実践に学ぶ」コーナーに掲載された教育実践報告をもとに、オンラインでの学習会を行います。限られた誌面では語り尽くすことのできなかった実践者の思いや実践の背景なども学び尽くし、普遍的な教育実践として大切にしたい視点を学びあいたいと思っています。
◯仲間と学習の“わ”を広げます=仲間とつながって、自分たちで学習の企画を立て、学びの“わ”を広げましょう。
ぜひ、みなさんプロジェクトメンバーになってください。
プロジェクト参加希望者は専用の申込フォームからお願いします。
https://form.run/@sakurai-hiroaki--1611202867
佐藤比呂二(特別支援学校)『出会いはタカラモノ 子どもから教えられたことばかり』
大好評増刷へ
「はじめに」より
思うようにいかない子どもとのかかわり。考えても考えてもわからない子どもの気持ち。そんな先の見えない子どもとの日々を繰り返しながらも、(あっ、そんなふうに思っていたのか)(えっ、そんなねがいがあったのか)と気づかされる瞬間がありました。
こだわりの強い自閉症児が自分のこだわりを食い止めようと必死に葛藤したり、不登校になった子が自分の居場所を見つけて変わっていく姿を目の当たりにしたとき、彼らの本当のねがいは何かを教えられた思いがしました。
「つまずいても、そこから自分を変革していく教師の姿は、本来、学校とは、教師とはという問いに、答えを与えてくれる本。ぜひ、幼児期のお母さん、お父さんだからこそ、読んでいただきたい」(白石正久さん)
「『みんなのねがい』の連載で大変好評で、私も楽しみに読んでいたものの単行本化です。子どもに学ぶということの大切さを教えてくれます」(大迫より子さん)
▶詳しい目次へ(「ちょっと見」できます)
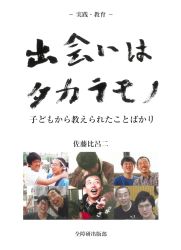
田中智子(佛教大学)『障害者家族の老いる権利』大好評2刷 納品されました
大好評につき2刷が本日納品されました
<書評より>
『障害者家族の老いる権利』は、著者が障害のある人・その家族との楽しい経験も共有してこられ、心から寄り添ってこられたからこそ、そして今を受けとめ、課題を引き寄せて考えられるからこそ、その調査の視点、分析に説得力があり、私たち家族を励ましてくれる稀有な著書であると思います。
障害のある子どもの黒子として生きてきた多くの母たちが、自分のことを語り始めてきた今「家族から社会へのケアの移行を考える」の章の、それぞれの立場からの視点は、立場を越えて考えあい、共有しあう、そんな機会を持つ上で大切な提起をいただきました。
▶詳しい目次へ(「ちょっと見」できます)
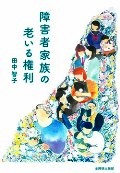
▶2021年7月12日 出版記念トークイベント100人こえる参加ありがとうございました
大会アピール
私たちの国の政権は、新型コロナウイルスの度重なる感染拡大により、かけがえのない命が危機にさらされ、人間らしい生活が脅かされる現実に目を背けながら、オリンピックの開催に踏みきりました。国民の命と健康を守る責任を投げ打ち、経済的な富を求めてやまない政治がそこにあります。命の切り捨てを許さず、政治への不信によって損なわれた社会への信頼を回復することなくして、障害のある人びとの発達保障は実現しません。
全国障害者問題研究会は、2021年8月7日、8日の2日間、第55回全国大会(静岡2021)をオンラインで開催しました。開催地である静岡・浜松のなかまたちによるオープニングや文化行事は、「ひとりひとりのたいせつないのちにスポットライトを~RightsandLights~」という大会テーマと響き合って、いのちを輝かせ、平和に生きるための文化のねうちと力を伝えました。
すべての人の命が脅かされることなく、豊かな発達が保障される社会を実現するためには、人間の命を破壊し、多くの障害者を生み出してきた戦争の歴史と向き合い続けなければならないことを、記念講演から学びました。
分科会では、障害のある人びとの命を守り、ねがいを大切にしようと倦まず弛まず営まれてきた生活や実践の事実を語り合い、日々直面する悩みや困難をていねいに聴き合いながら、一人ひとりの足元から発達保障への道すじを明らかにしようとしました。そのなかで、はじめて全障研大会に参加された多くのなかまのことばにも脈打つ発達保障へのねがいを分かち合いました。
新型コロナウイルスの感染爆発による危機は世界規模で広がっています。わたしたちの研究運動は、国際社会における権利保障の努力と歩みをともにし、障害のある人びとのねがいに学んで、すべての人の発達と権利を保障する社会をめざしたいと考えます。
2日間で学び蓄えた力、確かめたつながりを糧に、それぞれの地域や職場で「ひとりぼっち」をつくらせず、みんなのねがいを語り合い、明日への希望を分かち合いましょう。「この子らを世の光に」。障害のある人びとの人格発達の権利を徹底的に保障するとりくみのうちに、だれもが生きるに値する平和な社会の発達を展望しましょう。互いに結び合った手を離さず、発達保障の道をともに歩んでいきましょう。
2021年8月8日
全国障害者問題研究会 第55回全国大会(静岡2021)
全国障害者問題研究会
第55回全国大会(静岡2021)基調報告
常任全国委員会 2021年8月7日
はじめに
昨年来の「コロナ禍」と呼ばれる状況のなかにあっても、たくさんの人が、それぞれに困難を抱えながらも、障害児者の発達保障・権利保障のために、知恵を集め、力を注いできました。
一方で、日本の政府は、新型コロナウイルス感染症に対して、必要な対策を怠るだけでなく、「GoToキャンペーン」を展開するなどして感染のリスクを高めました。社会生活に欠かせない「エッセンシャルワーク」の重要性が鮮明になるなかでも、保健医療・福祉・教育等を軽視し続け、病院・病床の削減すら狙っています。東京オリンピック・パラリンピック開催に固執する姿に象徴されるように、人間の健康・命よりも経済の活性化を優先する姿勢、私たちの生活よりも大企業の利益を優先する姿勢を露わにしています。
全障研は、5月、「コロナ禍の下でのオリパラ強行ではなく、すべての人々のいのちと健康、くらしを守ろう」と声明を発表し、「いのちと健康を守ることを自己責任とする政策がむき出しになれば、障害のある人、なかんずく重い障害があり複合的な権利保障を必要とする人のいのちと健康は守られません」と訴えました。いま、コロナ禍の中で生じている、さまざまな困難は、菅首相の言う「自助・共助・公助、そして絆」では解決できません。
日本の社会は、多くの歪みを抱えています。福島第一原子力発電所の事故から10年以上が経過しましたが、未だに原発から脱却できていません。政府は「脱炭素」を口実に原発を推進しようとしており、運転開始から40年を超えた原発の稼働まで認めています。また、貧困が依然として深刻な問題であるにもかかわらず、国の軍事費の増大は続いており、2016年度以降は5兆円を上回る額に及んでいます。日本学術会議会員の任命拒否や、「コロナ禍」のもとでの「憲法改正」の策動のように、政府が物事を強硬に押し通す動きも目立ちます。
世界的にみても、私たちの社会は、新型コロナウイルス感染症に加えて、いくつもの脅威に直面しています。ロシアや米国などの国々が保有する大量の核兵器は、世界に破滅をもたらしかねません。何百基もの原子力発電設備の存在も、無数の命を危険にさらしています。また、気候危機が深刻化しており、日本においても、近年は毎年のように台風・豪雨による災害が多発し、気候変動の影響が顕在化しています。土壌の劣化、地下水の枯渇、森林の破壊、生物の大量絶滅など、人間の社会を崩壊させ、地球の生き物を追いつめていく世界規模の危機が、目の前にあります。
課題は山積していますが、そうしたなかでも、障害児者の発達保障・権利保障のために取り組む多くの仲間がいます。自らの実践に真摯に向き合うと同時に、その実践のためにも、学び、交流しています。私たち全障研も、「コロナ禍」のもとでも、オンラインなど、新たな方法の活用も模索しながら、発達と発達保障を学び、実態や実践を語り合うことを大切にして、研究運動を進めてきました。
また、人々の権利保障をめざす運動は、いくつもの重要な成果を生み出してきました。2021年2月には、国による生活保護費の引き下げを違法とする判決が大阪地方裁判所で出されています。2021年3月には、札幌地方裁判所が、同性婚を認めないのは憲法違反であるとしました。そして、学校教育に関しては、公立小学校の学級人数の上限を35人に引き下げる法律改正が2021年3月になされ、少人数学級化が前進しました。特別支援学校の設置基準の策定に向けた動きも進んでおり、過大・過密の解消など、教育条件の改善が望まれます。医療的ケア児支援法(医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律)の成立、民間事業者における合理的配慮を努力義務に止めていた障害者差別解消法の改正(施行日未定)も障害分野における現状改善への一歩であり、実効性のある施策の具体化につなげたいと思います。
国際的には、核兵器禁止条約が2021年1月に発効しました。障害児者の発達保障・権利保障は、戦争と両立するものではなく、核兵器の存在と相容れません。日本政府は条約の批准に背を向けていますが、平和を願う声を集め、核兵器の廃絶に向けての歩みをさらに進めなければなりません。
一人ひとりの発達保障・権利保障のためには、一人ひとりのための具体的な実践とともに、地球規模の問題を含めた社会的課題への取り組みが必要です。しっかりと社会に目を向けつつ、日々の実践を大切にしていきましょう。
Ⅰ 乳幼児期の情勢と課題
乳幼児期の療育の今後を左右する二つの動向に注目する必要があります。一つは2021年度からの障害福祉サービス報酬における子どもにかかわる改定であり、もう一つは児童福祉法改正に向けた障害児通所支援の見直しの議論です。
1)療育の土台を掘り崩す報酬改定
2021年度報酬改定において、児童発達支援の加算が変更されました。これまで基準以上の職員配置に認められていた加算が部分的に削られ、代わって個別の子どもの通所に対応した個別サポート加算と、特定の資格をもつ職員を配置した場合の専門的支援加算が新設されました。前者は子どもの状態によって報酬に高低が生じる(公費の給付額が変わる)という点で、後者は特定の専門性を報酬に反映させたという点で、今後の療育のあり方にかかわる重大な問題をはらんでいます。
個別サポート加算には、障害の状態などの聞き取り調査の結果による加算Ⅰと、虐待などの可能性のある要保護・要支援の子どもが利用したときの加算Ⅱがあります。加算Ⅰを判定するための「乳幼児等サポート調査」は「5領域11項目」からなります。障害についての診断が確定せず苦悩する保護者に「行動障害及び精神障害」に関する具体的特徴の有無を問うことは、育児の希望とわが子の成長・発達への信頼を奪うことになります。「食事」や「排せつ」などの身辺自立に関する介助の状態も、障害ゆえのできなさなのか、発達途上の課題なのかを見極めて答えることは困難です。発達科学の知見を踏まえず、乳幼児の実態からかけ離れた調査は、保護者の困惑をひきおこすものであり、「できる」「できない」を問うことは子どもの尊厳を踏みにじるものです。
一方、加算Ⅱは、虐待などの可能性や養育上の課題のある要保護・要支援児童で関係機関との連携を行っている場合の加算です。利用契約を前提とした現行制度では、加算Ⅱの適用を支援計画に明記して保護者に同意を求めることになりますが、これは保護者との信頼関係を損ない、子どもの療育を受ける権利を奪いかねません。実際に要保護・要支援児童の支援をていねいに行っている事業所はありますが、個別の加算の手続きは現実的ではないとの意見があがっています。
発達のつまずきや障害のある子どもの乳幼児期において、保護者がその事実を受けとめながら子育ての喜びを感じて生きていくためには、療育などの支援と出会う場面からのていねいで心のこもった支援が必要です。二つの加算の調査や手続きはそのことに逆行し、子どもと保護者の尊厳、基本的人権を侵害するものです。
また専門的支援加算については、「専門的支援を必要とする児童のための専門職」として、理学療法士や心理指導担当職員の配置がこれまで以上に強調されています。保育士・児童指導員も併記されているものの経験年数「5年以上」という限定つきです。理学療法士等を配置し、個別指導をする事業所が「専門性が高い」と見なされ、加算を得ると、療育を個別の支援や訓練に狭め、発達保障のための療育実践を制約することにならないかが懸念されます。子どもの発達や生活を丸ごととらえ、乳幼児期にふさわしい遊びを保障することで、育ちの土台を築く。こうした実践を重ね検証しながら、療育の専門性の議論を深めてくことが求められています。子どもへの働きかけ一つひとつに値段をつけるような加算方式や日額報酬制をやめて、安定して児童発達支援の実践がすすめられる制度的基盤をつくっていくために、ひきつづき職員と保護者がともに学び、運動していく必要があります。
2)特別なケアと子どもらしい発達の保障
このように、今回の報酬改定は、報酬の上げ下げにとどまらず、障害児支援の質の変更を迫る内容を含んでいます。振り返ると、2006年の障害者自立支援法施行から障害のある子どもの福祉にも利用契約、応益負担、日額報酬のしくみが導入され、その骨格を維持したまま、2012年からは児童福祉法のもとで子どもの福祉が「障害児通所支援」として再編されました。
本来、発達的な変化の著しい乳幼児期は、障害がある場合も含めて、すべての子どもに「よく遊んで、たっぷり食べて、ぐっすり眠る」という当たり前の生活を保障することが何よりも大切です。発達や障害のつまずきがある場合には、保護者へのていねいな支援も求められます。療育を商品とみて、利用料の対価として相談・支援が行われるしくみでは、職員と保護者がともに子どもの成長・発達を喜び合い、じっくりと時間をかけて話し合いながら、ねがいや悩みを分かち合うことが困難になります。こうした観点から、障害児通所支援の各事業の役割を見直す必要があります。
しかし、6月から厚生労働省内で始まった「障害児通所支援の在り方に関する検討会」は、利用契約や応益負担など障害を自己責任に帰す制度の根本にふれないまま、利用者増の抑制や支給決定のあり方、保育所などの一般施策の利用促進などについて「検討」しようとしています。
また、子どもの状態を聞き取る「5領域11項目」調査が個別に加算をつけるために用いられるようになったことは、成人の「障害支援区分」により類似したしくみになったことを意味します。利用契約、応益負担、日額報酬のしくみは、発達しつつある子どもの支援に大きな矛盾と困難をもたらしてきましたが、これを改善しようという方向とは逆行します。
子どもの生活や人間関係を切り刻むようなしくみを改め、障害があっても「子どもは子ども」として尊重されるためには、制度の根本が見直される必要があります。子どもが育つためには、当たり前の生活と安心できる人とのかかわりが必要です。遊びにくさがあったり、生活リズムを整えることが苦手な子どもたちにとって療育の場は、安心して自分を出し、友だちと一緒に遊びを楽しみながら、自信をたくわえていくことのできるかけがえのない場所です。子どもが思わず手を伸ばしたくなるような、心がぐっと動く遊び、子どもを自然と巻き込んでいくようなクラスの雰囲気、その一つひとつに、子どもの育ちをねがう療育者たちの意図が込められています。「コロナ禍」にあっても、感染を防ぐためにさまざまな制約がありながらも、子どもらしい当たり前の生活を保障しようと努力や工夫が重ねられています。ところが、こうした発達のつまずきや障害のある子どもと保護者が、毎日安心して楽しく通える療育の土台や入り口が大きく揺るがされているのです。
子どもの権利条約(1994年批准)や障害者権利条約(2014年批准)に照らして、障害があっても、障害のない子どもと同等に、毎日の生活の拠点があり、そこで障害への特別なケアを受けながら、子どもとして発達することを保障する施策が求められます。児童発達支援をはじめとする障害児通所支援の改善とともに、保育所、幼稚園、認定こども園などの一般の子ども支援制度から排除しない制度がつくられなければなりません。
3)地域療育づくりの歴史に学び、総合的な発達保障を
障害乳幼児に療育を保障するための運動と実践は、住民自治と結びつきながら、乳幼児健診や母子保健と一体となった自治体の療育システムをつくりあげてきました。そうした地域療育づくりの歴史にも学びながら、障害乳幼児の発達保障としての療育の理念を確かめたいと思います。親子教室をはじめ、障害の診断の確定にかかわりなく、子どもの必要に応じて療育が受けられるよう、保健師、療育・保育の関係者が連携して、地域のすべての子どもの発達保障に責任をもつ、ゼロ歳からの系統的な発達支援・子育て支援のシステムが求められています。『障害者問題研究』第49巻1号の特集「乳幼児期の発達保障と児童発達支援の課題」も活用しながら、乳幼児期の総合的な発達保障にむけた地域療育のあり方を話し合っていきましょう。
Ⅱ 学齢期の情勢と課題
1)「コロナ禍」のもとでの学校教育の困難と新たな展望
この春、「コロナ禍」のもとでの2回目の新年度を迎えました。昨年初夏の学校再開以後、各地の学校では、感染拡大防止に細心の注意を払いながら、子どもたちの当たり前の生活を取り戻し、発達へのねがいに応える教育実践を創り出すために、実にさまざまな工夫が行われています。
その一方、ソーシャルディスタンスの一方的な強調とGIGAスクール構想の強行のもと、実践の工夫が、オンライン授業でどんなコンテンツを提供すれば子どもたちの興味をひけるのかといったことに一面化する危惧もあります。「オンラインでは、子どもたちの心の動きがほとんどわからなかった」、「そばにいるから感じること、触れているからわかること、働きかけるから気づくことがある」。再開後の学校から伝わるこうした声は、子どもたちのことを深く知りたい、子どもたちとつながりたいというねがい、だからこそ、子どもたちの内面に思いを寄せ、子どもとのかかわりから学ぶことを大切にしてきたいという、実践者としての切実なねがいの表明でしょう。
こうしたねがいは、困難が大きい今だからこそ学び合いたい、仲間とつながりたいという要求を生み出します。コロナ禍のもと、これまでの学習活動を継続することが困難な中でも、オンラインなどの新たな形態を取り入れながら、さまざまな学習活動が力強く進められようとしています。
2)中教審答申と「新しい時代の特別支援教育」有識者会議報告
2021年1月、中央教育審議会は「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」と題する答申を公表し、それと前後して、「新しい時代の特別支援教育の在り方」に関する有識者会議もその最終報告を公表しました。
中教審答申は、従来の「日本型学校教育」を高く評価する一方で、子どもの多様化や教師の長時間労働、情報化への対応などの課題を指摘し、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の双方を「一体的に充実」するとしていますが、その背後には、よりストレートに「学びの個別最適化」を主張する経済産業省「未来の教室」創出事業や、それと呼応する「Society5.0に向けた人材育成」(文部科学省2018年)などの動きがあります。これらは、学校における「一人一台端末」の実現などを強行するGIGAスクール構想などとも相まって、子どもたちの学習の個別化を促進するとともに、学習成果に対する「自己責任論」を押し進める危険性の強いものです。学校マネジメントや持続的で魅力ある学校教育の実現といったスローガンも、政治による学校及び教師への管理統制の強化につながりかねません。
「新しい時代の特別支援教育」を掲げる有識者会議報告も、ICT環境の充実と教師の活用スキル向上を強調しますが、実現が急がれる「自校通級」のための環境整備や、学校数の少ない盲学校・聾学校からの専門的指導などを「ICT・遠隔技術の活用」に委ねるなど、本来必要な予算措置や教員配置に背を向け、安上がりに済ませるための方便という性格が色濃いものとなっています。
急ピッチで進められるGIGAスクール構想にかかわっては、学校施設の補修などの切実な課題には予算措置がないのに、ICT環境の整備だけが行われるといった矛盾も報告されています。
有識者会議報告では、特別支援教育を担う教師の専門性の向上も謳われていますが、特別支援学校における特別支援学校免許の所持に関する特例は放置され、ICTを活用したより効率的な研修の実施を求めるなど、現場の教師の実感とはかけ離れたものとなっています。
3)教育条件整備の課題
一方で前進もあります。「新しい時代の特別支援教育」有識者会議と中教審は、政府のこれまでの方針を転換し、特別支援学校の設置基準の策定を表明しました。
「教育環境が非常に劣悪なのに、それを正す指標としての設置基準が特別支援学校にだけないのはおかしい」「よりよい環境で学ばせたい、学びたい」という保護者・教職員・子どもたちの思いを背景とした、十数年におよぶ運動の成果です。形式的な策定に止めることなく、教育条件を実質的に押し上げるものとしていかなければなりません。全日本教職員組合などでは、実効性のある設置基準とするために、多くの教職員・保護者の声を集めた設置基準案を提起しています。教育条件が劣悪なのは、特別支援学級も通級による指導も、通常学級もしかりです。設置基準策定を実現させた運動の底流にあるのは、どの子にもゆきとどいた教育条件の下でゆたかな教育保障を、という要求です。その実現のためには、現在の教育条件の劣悪さと、そのもとでの教育実践の制約をリアルに明らかにし、より広範な人びととの連携をつくり出していくことが必要です。
一方で、特別支援学校では小学部の段階から、将来の一般就労を目標とし、実践をその目標に従わせようとする傾向が広まっています。日々の学校生活を、常に「できる―できない」で評価されるなかで、自信と自尊の感情を持ちづらくさせられたまま卒業していく子どもたちの姿も報告されています。現在の教育現場では、「働き方改革」の名のもとでタイムカードでの勤務時間管理が導入されたり、授業や教育課程は学習指導要領と整合しているかどうかだけが問題にされたり、実践が、数値で測定できる短期間の変化だけで評価されるなど、教師の仕事に対する管理・統制が幾重にも強められています。教育条件の整備は、学校増設などの教育環境の改善に留まるものでなく、一人ひとりの教師がしっかりと教育実践に向き合い、子どもとともにゆたかな教育内容を創り出していくことができる条件につながらなければなりません。子どもたちの教育権を実質的に保障していくためには何が必要なのか、視野を大きく持った総合的な検討と改善に向けた運動が必要です。
4)ゆたかな生活のための放課後保障
拙速な休校要請によって障害のある子どもと家族の生活にはさまざまな困難が生じました。学校での教育活動が大きく制約される中でも教師によるさまざまな努力が各地で行われましたが、休校の間、子どもと家族の生活を支えたのは放課後等デイサービスであったことも事実です。公園や公共施設などの閉鎖で場が狭められ、職員も感染の危険にさらされながら、活動を続けました。こうした困難はたびたび報道され、「コロナ禍」のなかで、放課後等デイサービスは障害のある子どもにとってなくてはならない社会資源として知られるようになったといえます。
しかし、4月からの報酬改定では、「収益を上げている」という数字を根拠に、放課後等デイサービスの報酬は引き下げられ、今後の活動継続を見通すことが困難だとの報告も相次いでいます。
放課後等デイサービスに代表される学校外の障害児支援の場は、学校とならんで、障害のある子どもたちの生活と発達保障に欠かせない大切な場です。3ヵ月以上にわたる非科学的な「臨時一斉休校」の経験は、これら放課後保障のとりくみの大切さと、そのおかれている制度的基盤の脆弱さに加えて、学校教育と放課後等デイサービスなどとの相互理解と緊密な連携の必要性も明らかにしました。障害のある子どもたちとその家族のゆたかな生活を実現するために、行政による分断を乗り越え、学齢期の発達保障にかかわる幅広い人々の連帯をつくり出していくことが求められます。
Ⅲ 成人期の情勢と課題
1)他の者との平等を基礎とした生活・人生の確立を
成人期において暮らしの質を追求するためにも、ライフサイクルを通じてのノーマルな経験の保障は不可欠です。乳幼児期の保育・療育の保障に始まり、学齢期の生活、さらに、青年期には同年代の多くの市民が高等教育機関に進学するのと同様に、学びの場を保障すること、その後の成人期においても生涯学習を保障するとともに、親離れ、結婚、親になることなどを含めて、多様な人生の選択肢を、障害者にも平等に開くことが重要です。
また、障害者が家族に依存しないで生きることを考えることと同時に、障害者の介護に専念せざるを得ないために家族が貧困リスクを高めることになるのではなく、家族も自立する視点をもつことが必要です。障害者がいることが要因となって、きょうだいや夫婦、祖父母といった家族の関係が緊張を強いられるのではなく、相互に尊重しあって生活するために何が必要か、それぞれの就労や休息など家族の要求に基づく運動、社会的支援のあり方について検討することが求められています。
入所施設で暮らしている人の外出支援や、グループホームや入所施設の中で家族が過ごすスペースの制度化など、障害者と家族の交流を保障する手立ても必要です。「全国障害児者暮らしの場を考える会」の基本要求には、家族依存からの脱却ために「親が元気なうちから社会的支援への実質的な転換」ということが掲げられています。障害があっても、本人も家族もゆたかな人生を追求することを諦めない社会づくりが求められています
2)成人期施設の安定した運営を支える制度を
新型コロナウイルス感染拡大状況下では、成人期障害者施設においても休所や利用者による通所自粛があり、居宅支援では移動支援や訪問介護の利用のキャンセルなどが相次ぎました。不測の事態であっても事業所への報酬は日割りで実績払いのため減収になり、事業の継続自体が困難になっている施設も多くあります。
加えて、2021年度の報酬改定においては、就労移行実績や月額工賃の高低によって報酬に差をつけ、生活介護事業では利用者に行動障害や身体障害がない場合には報酬を減額するなど、成果主義と障害支援区分偏重がさらに露わになりました。グループホームにおける夜間体制の弱体化を招くような報酬では暮らしを守ることはできません。その他にも事業基盤の不安定化につながるような施策がつづいています。成人期障害者を対象とした施設は、多くの利用者にとって、有期限ではなく長期にわたり、仕事や暮らしなど人生を支える拠点ともいえる場所であり、安定的な運営が欠かせません。人生に見通しをもって、仕事や暮らしの場のあり方を考えることができるような安定した運営を支える制度が求められます。
3)所得保障政策の整備を
市場化された経済生活を営む現代において、障害のある人の自立を考えたとき、所得保障政策の整備は他の者との平等を基礎とするための前提条件です。この点では、2021年2月22日、国が物価下落に合わせて、2013年から2015年にかけて生活保護費を約10%引き下げたことは違法とした大阪地裁判決や、2021年3月から、障害基礎年金を受給しているひとり親が「児童扶養手当」を受給することができるようになったことは、私たちをおおいに励ましました。
一方で、新型コロナウイルス感染拡大状況下において、8割以上の事業所で生産活動が減収になり工賃は大幅に下がった(きょうされん調べ、2020年7月)ことで、障害のある人たちの生活や余暇を支える経済的基盤が不安定で脆弱なものであることが改めて問題となりました。障害のある人の労働による給料や工賃保障のための社会的手立ての充実とともに、最低生活水準を大きく下回る障害基礎年金の問題などを改めて問い直す必要があります。
その障害基礎年金さえも、障害の医学モデルに依拠した受給要件で対象者を制限するといった制度の不備によって無年金状態となっている人たちや、その救済策である特別障害者給付金制度からも対象外とされている人も多くいます。加えて、2019年10月から、消費税増税にかかる緩和措置として、低年金者に年金生活者支援給付金が支給されるようになりましたが、無年金障害者は対象外というように、何重もの排除が働いています。そもそもの問題として、生活の主要な支えである年金を社会保険という「共助」の仕組みにしていることが、大きな問題です。
自己責任や自己努力を求めるのではなく、生活の支えは国家の責任でということへと転換を図る必要があります。
4)暮らしの場の整備を
障害者家族における、老障介護、「ロングショート」(短期入所を長期間つなぐ)、親なき後をめぐっては、深刻な実態が生じています。地域で入所施設やグループホームなどの暮らしの場を求めて待機状態になっている人が多数いる現状を踏まえた喫緊の課題として、量的整備の必要があります。
また、障害のある人たちの多くの尊い命が無残に奪われた津久井やまゆり園事件から5年が経ち、事件を振り返りこれからを展望するような関係者からの発信が行われつつあります。量的整備だけではなく、暮らしの質にも着目し、どこで暮らすかだけでなく、どのように暮らすかを考えることのできるような社会資源の整備が必要です。
5)ケアの家族依存・専門職のボランタリーからの脱却を
新型コロナウイルス感染拡大状況下においては、成人期障害者の利用する社会資源の休所や通所自粛などが相次ぎ、ケアにおける家族役割の大きさが再認識されることなりました。グループホームや入所施設でもできるだけ帰省を求めるなどの対応がとられたところもあり、極限の状態で、高齢の親が子どものケアを全面的に引き受けざるを得ず、親子ともに行き詰まりを感じているケースも多く見られました。
新型コロナウイルスは障害者施設をも例外なく襲い、障害があるとケアの体制が取れないので陽性であっても入院することができない、体調不良や発熱などの症状があってもPCR検査さえも受けられない事例が続出しました。
そのような中で、家族や専門職は、まさに命がけでケアを行いました。障害児者を支える専門職は、エッセンシャルワーカーとして、緊急事態下であっても休むことのできない、社会生活において欠かせない職業として認識されはじめたものの、労働条件や環境を支える制度は、何ら改善が見られません。
新型コロナウイルスによる危機は、これまで家族に押し付けられてきたケアの矛盾をあぶりだしつつあります。また、寄り添う専門職のボランタリーな活動に依存しすぎていることも問題です。障害のある人の命を守るということは、それを支える人たちの命も守るということです。ケアの家族依存や、専門職のボランティア性に依存している状況を構造的に見直す必要があります。
Ⅳ 研究運動の課題
1)脆弱な制度に分断させられることなく要求でつながろう
「家での生活を強いられ、子どもも親も疲れきっています」。自分の責任、家族の責任で命を守れという究極の自己責任論に対して、障害や年齢を問わず、日本中から発せられた叫びです。家族が面倒をみることを当然だとする考えが根強く残るなか、障害のある人とその家族は、障害者自立支援法以来、小刻みにされた支援をつなぎ合わせて生活を組み立てることを強いられています。その矛盾は、ステイホームの強調でいっそう鮮明になりました。こうした矛盾は、ときとして障害者・家族、学校、福祉事業所などの間に溝をつくります。
だからこそ、目の前の障害者・家族を中心に、分野をこえてつながり、語りあい、一緒に考えることが大事なのではないでしょうか。この1年余、各地で模索し、足を踏み出して展開された実践は、いずれも私たちに新たな課題を提起しています。感染に十分気をつけながら何ができるかを考え工夫した実践、感染に直面して実感した保健所や医療機関との連携など、『みんなのねがい』、『障害者問題研究』にはたくさんの報告が掲載されており、ここから学ぶことができます。
必要な支援は「サービス」ではなく、権利保障の根幹です。制度にないことも要求に基づいて実践し、新たなつながりをつくり、自治体に働きかけるなど、制度を変え新たにつくることを展望した研究と実践、運動に取り組んでいきましょう。
2)発達研究と発達保障の実践を車の両輪として進めよう
「発達の理論と目の前の子どもたちの姿がなかなか結びつかず、どうしても『~の力をつける』を考えている自分がいます」。6月の「教育と保育のための発達診断セミナー」に寄せられた声です。実践の場は異なっても、多くの人々が障害のある子どもや大人のねがいを受けとめる実践者でありたいとの思いをもって、人間が発達することの価値を学ぼうとしています。
私たちは、何かが一人でできるようになることだけをとらえて「発達」と呼ぶような、貧困な発達観には立ちません。子どもの発達要求を無視して、同じ場所で、同じ道具や同じようなかかわりがあればそれでよいという立場にも立ちません。これまでに積み重ねてきた、人間発達の研究と、家庭や地域と手を取り合って進めてきた発達保障実践を車の両輪としてとらえ、よりゆたかに進めることが重要です。障害者が主体として生きる、その主体性を中心に据えながら、時には全身で、時には本当に小さいサインとしてあらわされる発達要求をしっかりと理解し、その要求に応える実践を創り出すこと、そこで生み出された事実をもとに研究を進めることを大切にしましょう。
希望する子どもへの後期中等教育保障が実現してきた現在、生涯にわたる発達を展望しつつ、多様な形で広がってきた18歳以降の教育の場の実践をはじめ、青年期の発達と発達保障実践を検討しあうことが大事な課題となっています。
実践とそれにもとづく研究の発展のためには、実践の成り立つ基盤にも目を向けることが必要です。発達保障実践をすすめる療育や放課後活動、自立訓練事業などの場の土台が日額報酬という「明日の保証がない」脆弱なしくみで成り立っていること直視しなければなりません。ゆたかな実践と結んだ制度の改善に力を合わせることにも取り組みましょう。
3)同年齢の市民と同等の権利を実現するために手をつなごう
障害ゆえに移動や生活上の支援を利用して自分らしい生活を送ってきたから高齢になっても支援を継続してほしいということは当然の願いです。しかし、5月18日、千葉地裁は、「65歳から介護保険を優先して利用せよというのは理不尽だ」とする天海正克さんの訴えを退けました。判決は、「公費負担の制度より社会保険を優先する」のが基本だといい、障害者の生きる権利ではなく国の不十分な社会保障政策に追従した姿勢を露わにしています。天海訴訟によって「65歳問題」は日本の社会保障制度の根幹にかかわる問題だということが明らかになりました。こうした本質を幅広い人々に知らせ、輪を広げていくことが大切です。
同じように、保育・学校教育でも、障害の有無をこえて課題を共有し、同年齢の市民と同等の権利保障を実現するすじ道を明らかにしていきましょう。
4)あなたも全障研へ 今こそ、発達保障の研究運動をすすめよう
今こそ、「私たち抜きに私たちのことは決めないで」を合言葉に、声をあげ続けましょう。
暮らしの場、学ぶ場、働く場における発達保障労働は、障害者の発達の権利をゆたかに実現するために重要です。それらの一つ一つが魅力的な労働の場でもあります。よりゆたかに発達を保障していくために、全国大会やサークルに集い、研究運動を進めていきましょう。『障害者問題研究』や『みんなのねがい』の読者会を通じて、会員が広がっています。実践を語り合うグループをつくって、仲間を広げていきましょう。全障研ホームページには、学びを深めるための「ラーニングガイド」、学びを止めないための「オンライン活用」のページも充実しています。
地球規模の課題を視野に入れ、障害のある人の命、暮らし、発達の権利を守る研究運動を、社会全体で進めていきましょう。安心できる生活を破壊し、ねがいを分断し、他者と共に文化を謳歌することを認めず、発達権を後回しにするような動向に反対の声をあげ、発達研究に基づく権利保障の運動を展開していきましょう。個人のねがい、集団・組織のねがい、社会のねがいのそれぞれを深め、つなぎ、障害者権利条約の時代にふさわしい権利保障を訴え、平和・非暴力・民主主義を社会制度と国際社会に貫いていきましょう。
2021年8月2日
各支部支部長、事務局長、全国委員のみなさま
全障研会員のみなさま
全国障害者問題研究会
全国委員長 越野和之
新型感染症をめぐる現下の状況を踏まえた全国大会(静岡・オンライン)参加の取り組みについて
全障研第55回全国大会(静岡・オンライン)の開催が間近に迫りました。静岡はじめ、各地の支部では、一人でも多くのなかまとともに、大会に参加できるよう、パブリックビューイングの設定と参加の呼びかけなど、様々な準備を進めていただいていることと存じます。
一方で、多数の懸念や反対を押し切って東京オリンピックが強行される下、新型感染症の「第五波」と も呼ばれる感染拡大が急速に進行し、東京都に続き、埼玉、千葉、神奈川、大阪でも四度目の緊急事態宣言が発出される事態が引き起こされています。感染は近畿や東海を始め、全国に拡大する状況を呈しており、私たちは、こうした状況を十分に考慮して、間近に迫った大会に臨むことが必要だと考えます。
今年の第55回大会は、当初、集まって話し合う従来型の開催を予定し、開催地静岡を中心に、様々な準備活動が取り組まれてきましたが、私たちは、感染の拡大によって、本来奪われなくてもよいいのちが万が一にも奪われたりすることのないように、オンラインを基本とする大会開催を決意しました。大会の成功は、障害のある人たちの権利を守り、発達を保障することを願う一人でも多くの人が集うこと、大会に参加した一人一人が、全体会や分科会での討議、学習講座などでの学びを通してお互いの努力を知り合い、自身の課題をつかんでそれぞれの地域に持ち帰り、地域での取り組みを広げることにあります。大会に参加するすべての方のいのちと健康が脅かされないことは、そのもっとも基礎的な前提です。このことは、各地で準備されているパブリックビューイングなどの取り組みにおいても徹底されなければならないと考えます。
感染拡大には地域差があり、具体的な対応は、それぞれの地域における慎重な検討に基づいて行われるべきですが、現下の状況を踏まえ、どのような対応を行う場合にも、以下のことなどに十分に留意して大会成功に向けた取り組みを進めていただくよう、心よりお願い申し上げる次第です。
1.各地で準備されているパブリックビューイングなど、集まって・対面で開催される取り組みについては、当該地域の感染拡大状況に十分に留意し、必要な場合には、個別もしくは小規模の視聴に切り替える等の可能性も検討してください。
2.感染状況等を踏まえ、パブリックビューイングを開催する場合には、以下の諸点を厳守してください。
A)会場の定めているルールを守ること
B)隣、前後の座席を空けるなど、十分な間隔をとって着席すること
C)出入口、窓を開放しての常時の換気を可能な限り行うこと
D)マスクの着用、手指消毒、設備の清拭など、感染予防に必要な対策を徹底すること
E)必ず参加者名簿を作成し、電話連絡先を把握すること(万一の感染発生の際に参加者への迅速な連絡ができるように)
F)参加される方々に当日朝の検温を依頼し、発熱、長くつづく咳などの体調の不良がある場合には、 参加をご遠慮いただくこと
「障害者問題研究」49巻2号
特集=障害福祉現場で働く職員の育ちと集団化 刊行しました
詳細案内・「ちょっと見」やオンラインでのご注文は以下のホームページへ
▶「障害者問題研究」49巻2号 特集=障害福祉現場で働く職員の育ちと集団化
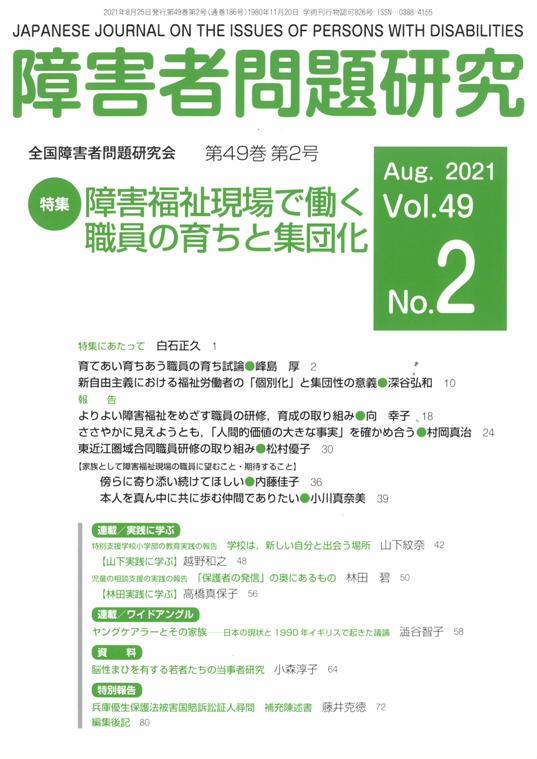
「障害者問題研究」49巻1号
特集=乳幼児期の発達保障と児童発達支援の課題
特集にあたって/中村尚子
児童発達支援の機能と役割
井原 哲人 白梅学園大学子ども学部
自治体における障害児福祉計画の現状と課題
――埼玉県下40市の第1期障害児福祉計画の分析
新井 利民 立正大学社会福祉学部
発達支援と地方自治 ――鹿児島県伊佐市を例に
若林 隆泰 奈良教育大学非常勤講師
連帯して療育の質を高めあう地域づくり
――広島県東部幼児通園療育機関協議会の取り組み
長谷川貴一 社会福祉法人こぶしの村福祉会 児童発達支援センター 草笛学園
中塚まちい 社会福祉法人こぶしの村福社会 児童発達支援センター ひかり園
報告
「安心」「楽しい」「大好き」を大切にした療育 ――“ほんとはやりたい”思いとつながる
安藤 史郎 大阪府・社会福祉法人療育・自立センター 寝屋川市立あかつき・ひばり園
報告
保育園と家庭の間につくるスモールステップ ――並行通園の役割を考える
飯室 智恵子 山梨県・社会福祉法人いずみ会 児童発達支援センターひまわり
政策動向
障害児通所支援2021年度報酬改定の問題点
中村 尚子 特定非営利活動法人 発達保障研究センター
連載/実践に学ぶ
【報告】障害の重い子どもの特別支援学校の実践
今こそドキドキわくわく心おどる学校を
滋賀県立特別支援学校 教員 木?澤 愛?子
【木澤実践に学ぶ】
みんなで“あぁ楽しかった”と思える授業づくり
鳥取大学地域学部 寺川志奈子
連載/実践に学ぶ
【報告】放課後等デイサービスの実践
集団の中で「一緒にしたい」思いを育んだ子どもたち
放課後等デイサービススタッフ 中嶋麻衣
社会福祉法人おおすぎ 城山れんげの里,立命館大学大学院社会学研究科博士後期課程
【中嶋実践に学ぶ】
放課後になかまと育ち合うことの大切さに気づくこと
静岡県立大学短期大学部 佐々木将芳
連載/ワイドアングル
認知症の人と家族の会のあゆみと介護・福祉の未来
花俣 ふみ代 公益社団法人 認知症の人と家族の会副代表理事
動向
コロナ禍における障害児教育の現状把握オンライン研究会の取組みから
國本 真吾 鳥取短期大学幼児教育保育学科
書評
田中智子著『知的障害者家族の貧困──家族に依存するケア』
評者 藤原 里佐 北星学園大学短期大学部
詳細案内・「ちょっと見」やオンラインでのご注文は以下のホームページへ
▶「障害者問題研究」49巻1号 特集=乳幼児期の発達保障と児童発達支援の課題
声明
コロナ禍の下でのオリパラ強行ではなく、
すべての人々のいのちと健康、くらしを守ろう
2021年5月9日
全国障害者問題研究会常任全国委員会
私たちは、昨年5月、声明「新型コロナウイルスをめぐる情勢の下で障害児者の権利を守るために」を発表し、コロナ禍における障害児者の困難や権利侵害の実態をつかみながら、障害児者とその家族、そして障害児者に関わる人たちの権利を守り、発達を保障するための施策を求めました。
それから1年が経ちましたが、現在の感染拡大の状況下では、感染力が強く重症化の可能性が高いとされる変異ウイルスが急拡大し、各地の新規感染者数は過去最多を更新するとともに、死亡者も増え続けています。病床がひっ迫した医療機関では新たな患者の受け入れも困難となり、「救えるはずのいのち」が救えない危機的な事態が生じています。
しかし、政府は、医療崩壊をくいとめる抜本的な施策を講じることなく、国民に「自粛」と「自衛」を求めるばかりです。医療従事者や高齢者へのワクチンの優先接種も混乱しています。にもかからず、オリンピック・パラリンピックの開催には大量の医師の募集や看護師の派遣要請が報じられています。
いのちと健康を守ることを自己責任とする政策がむき出しになれば、障害のある人、なかんずく重い障害があり複合的な権利保障を必要とする人のいのちと健康は守られません。いのちの選別はあってはなりません。
障害のある人のなかには、慢性疾患があり、感染すれば重症化しやすく、日常的な医療・介護を必要とする人たちが多くいます。いま、求められていることは、希望すればPCR検査ができること、希望者がワクチン接種を受けられること、適切な医療が受診できること、障害を理由に入院が拒まれないことです。本人や家族が感染した場合も、安定した生活基盤が確保できるような医療や福祉の体制が必要です。事業所や施設等で奮闘を続ける人たちのいのちと健康を守り、障害児者の発達と生活を支えるために最善を尽くすことのできる手厚いしくみが求められます。
東京オリンピック・パラリンピック開催に固執することなく、すべての人々のいのちと健康、くらしを最優先することを強く求めます。
▶PDFデータです

◆白石正久・白石恵理子編
『新版 教育と保育のための発達診断 下 発達診断の視点と方法』のラーニングガイドです。
▶ラーニングガイド(PDF) (20210414)
*プリントの際には、A4用紙一枚に2ページ入る指定をすると便利です
<編者から>
このラーニングガイドは,本書の理解を容易にするためのものではありません.本書のなかでくりかえし登場しながら,必ずしもその解説がなされていない事項,つまり①基本的な用語・概念,②子どもの具体的な姿の背後にある発達のしくみについて補足的に説明するものです.その用語・概念や発達のしくみへの認識を通じて発達の理解が一歩深まることを願って,本書の読者のみなさんにお届けします.
白石正久・白石恵理子
▶『教育と保育のための発達診断 下 発達診断の視点と方法』目次へ
「障害者問題研究」48巻4号
特集=地域社会へのインクルージョンと暮らしの場
特集にあたって/中村尚子 本誌副編集委員長
座談会 暮らしの場に値する障害者施設をめざして
出席者 社会福祉法人みぬま福祉会 足立早苗・植村 勉・園部泰由・野崎壮一
司会 中村尚子(本誌編集委員)
デンマークとスウェーデンにみる障害のある人たちの住まいと暮らし
薗部 英夫
全国障害者問題研究会副委員長・日本障害者協議会副代表
グループホーム制度30年と今後の課題
伊藤 成康
きょうされん大阪支部グループホーム部会
【手記】
サポートを受けながら私らしく暮らしたい
社会福祉法人皆の郷グループホーム利用 相田あづさ
きょうされん埼玉支部利用者部会WA会
【手記】
私にとってのインクルーシブな暮らしを考える
県営住宅居住 上野 耕一
報告
北の大地の仲間たち2020~グループホーム編~
北村 典幸
旭川大学/社会福祉法人あかしあ労働福祉センター(北海道・旭川市)
報告
多様な家族の形態を支える
川瀬加代子・菅原裕子
麦の芽福祉会(鹿児島県)
運動
親のねがいと「全国障害児者の暮らしを考える会」の結成、運動の経過
播本 裕子
全国障害児者の暮らしの場を考える会
連載/実践に学ぶ
生徒と楽しむ理科実験
吉村 邦造
群馬・特別支援学校中学部
【吉村実践に学ぶ】 自然の不思議さに迫り,文化や科学の面白さに迫る
品川文雄 特定非営利活動法人発達保障研究センター
コロナ禍における学生の健康と生活と学習の危機に、障がい学生支援室はどう向き合えばよいのか
龍谷大学 障がい学生支援室
支援コーディネーター 瀧本美子
【瀧本実践に学ぶ】 学生の苦しみ,悩みに心を寄せる
社会福祉法人いたみ杉の子発達支援連携室
芦屋大学特任准教授
神戸大学・学ぶ楽しみ発見プログラムコーディネーター
河南 勝
連載/ワイドアングル
学校図書館における特別なニーズへの対応をめぐる現状と展望
野口 武悟
専修大学文学部
原著論文
二分脊椎症児の母親のソーシャル・キャピタル醸成プロセス
古城 恵子
帝京短期大学生活科学科
障害者問題研究2020年度(第48巻)総目次
詳細やオンラインのご注文は以下のホームページへ
▶「障害者問題研究」48巻4号 特集=地域社会へのインクルージョンと暮らしの場
2021年度の教科用一般図書(特別支援学校・学級用)として、『くらしの手帳 ~おとなとしてゆたかに生きるために』(みんなのねがい編集部編 2014年刊行)が選定され、文科省と契約を結びました。
すでに、中学の障害児学級や特別支援学校の高等部などから注文が入り、供給に入りました。定時制高校からの問い合わせも入っているところです。
「くらしの手帳」は、「障害のある青年たちの学びの場で教科書として使ってもらえるようにしたい」という願いをもっていました。柱は「くらす」「はたらく」「あそぶ」「性」「お金」の5つ。イラストやマンガで楽しくやさしく、総合的に学べる1冊です。
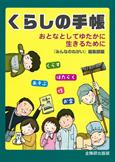
全国障害者問題研究会
第54回全国大会 基調報告 2020年8月9日
常任全国委員会
<はじめに>
人と人が語りあい、向かいあって暮らすというあたりまえの日常に制限を受けた数か月でした。この間、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の拡大という事態の中で私たちが経験した日常とは異なる生活は、子ども、大人の年齢を問わず、障害のある人びとと家族に、はかりしれない不安と困難をもたらしました。不安や困難の背景には、この感染症に対する処方箋がないということに加えて、すべての人の生きる権利を保障するはずの社会福祉・社会保障の制度の脆さが日に日に明らかになってきたということがあります。そうであるなら、どんな困難があったのか事実を出しあい、記録し、話し合うことは、予想される次の感染への対応にとどまらず、障害のある人びとのいのちとくらし、発達を保障する土台を改善する提起につながると考えます。
ここで3月から、私たちの周りで起こったことをふり返ってみましょう。
またたくまに世界中に広がった新型コロナウィルスによる感染症に対して、WHOは3月11日、世界的大流行(パンデミック)を宣言、各国政府はそれぞれに人びとの社会的活動や経済活動を制限する対策を実行しました。ウィルスについて科学的解明が続けられていますが、いまだ決定的な治療薬、ワクチンは開発されていまいせん。感染の広がりは世界的規模で格差を浮き彫りにしました。医療体制の不備のもと「経済優先」に舵をきる国も増え、6月末には、世界の感染者数は1000万人を、死亡者は50万人を超えています。
日本では、2月27日の夕刻、安倍首相による突然の一斉休校要請に始まり、4月7日には、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法によって「緊急事態宣言」が出され、以後、全国的には5月25日まで、生活全面にわたる規制が強いられました。
この事態の中で、全障研は、まず3月2日に「緊急声明」を出し、障害のある子どもと家族のもつ特別の困難に照らして、一律の休校を求めることの問題点を指摘し、要請の撤回を求めました。そして障害のある子どもと家族の健康と生活を守る方途を、国民的な英知の結集と議論によって検討していくことをよびかけました。
さらに「緊急事態宣言」から1ヵ月を経て、「補償なき自粛要請」への批判が高まるなか、5月9日には「声明=新型コロナウィルスをめぐる情勢の下で障害児者の権利を守るために」を発表しました。この声明では、社会福祉の仕組みの決定的な弱さが障害児者・家族に困難をもたらしていることを指摘し、乳幼児の施設や事業所、学校と放課後支援、児童および成人の施設などそれぞれにおいて、障害児者とその家族、障害児者に関わる人たちの「人間的な諸権利を守り、発達を保障することが必要だ」と訴えました。
2つの「声明」に呼応して、全国からたくさんの報告が寄せられました。
密になる集団生活をさけるために学校は休校とされる一方で、児童発達支援や放課後等デイサービスの事業所は開所を求められ、しかも感染防止のための方策はすべて事業所任せだったこと。卒業生を送り出し新入生を迎える大事な時期であったにもかかわらず、感染対策のみが優先され、子どもの気持ちに寄り添った活動を準備することすらままならなかったこと。在宅生活による生活リズムの乱れ、活動や集団が保障されないなかでの行動の不安定化などが家族から訴えられても、十分議論できない日々を送らざるを得なかったこと。いずれも、マスコミ報道には取り上げられることのない障害児・者と家族がかかえる困難から生じた問題ばかりでした。
「緊急事態宣言」後の4月以降は、児童発達支援、放課後デイ、作業所などの障害福祉事業所は、利用控えが顕著になり、事業継続の危機に直面しました。厚生労働省から電話などでの支援も報酬の対象となるという事務連絡が出されましたが、これにたいする疑問を感じながら、障害のある人への支援とは何か、それを支える制度はどうあるべきかという課題にいっそう向き合い、多くの事業所が事業を継続してきました。こうしたなかで、支援の対価としての日額報酬制という制度への批判が高まっています。
以上のように、まさに「コロナ禍」によって、国民生活を守る制度の脆さから矛盾が噴出したなかにあっても、政府は社会保障全般にわたる公費抑制をもくろみ、自助・互助・共助を基本とする「全世代型社会保障改革」にもとづいて、年金法、社会福祉法などの「改正」を強行してきました。
3月、津久井やまゆり園事件の裁判が終結しました。裁判では、「障害者は生きる価値がない」という被告の主張を正面から問うことがありませんでした。しかし、いま未解明の感染症とそこから生じた不安の拡大という状況のもとで、「すべての命は平等」であるという価値はますます重要になっていると思います。このことを基盤にした社会をめざす運動をすすめていかなければなりません。
私たちは、どんな情勢の下でも、人間のいのちと尊厳を軽んじる考え方や社会のしくみを断固として否定します。憲法と障害者権利条約の理念を地域のすみずみに広げながら、だれもが安心して生きられる平和でインクルーシブな社会の実現にむけて、みんなのねがいと力を重ね合わせて、発達保障をめざすとりくみをさらに進めていきましょう。
Ⅰ.乳幼児期の情勢と課題
(1)登園できなくてもつながる療育
感染が拡大するにつれて、保育園や幼稚園、児童発達支援の施設に通い、楽しい時間を過ごすという子どもたちの日常が消えていきました。3月、学校と同様に休園になる幼稚園がめだち、4月の「緊急事態宣言」以降は、保育園にも登園自粛の要請があり、子どもにとっての日中の生活と集団の基盤が揺らいでいきました。児童発達支援の施設(センターや事業所)は感染予防に努力しつつ可能な限り開所することが求められましたが、保護者の判断で登園を自粛する、事業所として登園制限や臨時休所を選択するという場合もありました。
友だちと遊ぶのが苦手、好きな遊びが見つけられないといった課題があるから、保育園や療育の場に通っていた子どもたちです。登園できなくなったとき、子どもに対してどんな支援ができるのか、各地で模索がつづきました。一方では、コロナ禍をも好機にしようと、オンラインの個別支援と称して動画や教材を有償で家庭に提供する事業者もあらわれました。
コロナ禍のもとにあっても重ねてきた実践の中には、今後の感染対策に引き継ぐべきことだけでなく、保護者・家庭への支援の基本として大事にしたいことがたくさん含まれています。少しでも楽しく過ごせるよう、子どもの心身の状態を把握し、工夫を凝らして試みた在宅生活における子どもへの支援について、経験を交流していくことも必要だと思われます。
(2)保護者への支援
父親が在宅勤務になった家庭では、家族一緒の時間が格段に増えました。しかし、障害のある子どもたちにとって、ふだんと異なる日課や家庭での暮らしはストレスとなる場合もあります。保護者からは、つい強くしかってしまう、適切でない対応になる可能性もあるという切実な声が聞かれました。在宅支援は、保護者にたいしても大切な支援であり、実践的な検討をしていかなければない課題です。
一方、厚労省や自治体が出す事務連絡では、保護者や子どもがコロナウィルスに感染することは、ほとんど想定されていませんでした。感染への不安は、障害の重い子どもや医療的ケアを必要とする子どもがいる家庭ではさらに深刻です。子どもを対象にしたショートステイの場の整備などが緊急に求められています。
障害のある子どもを育てる保護者の就労困難は以前から大きな問題ですが、今回のコロナ問題は家計にも大きな影響を与えました。
(3)事業所を守る
育ちを守り育てる療育の場では、まさに療育者と子どもが身体と心を通わせ働きかける場であり、「3密」状態を避けることは不可能といっても過言ではありません。療育の場が安心安全とはいえない状況が生まれました。
感染に配慮しつつ開所し続けても通園児が5割を切った、とうとう1名になったといった事業所もあります。楽しい集団療育ができないだけでなく、通所する子どもの人数の減少は、事業所の減収に直結するので園の運営そのものが不安定さの度合いを高めました。子どもが通園した日にしか公費が支払われないこの制度は職員の雇用をも不安定にしています。
厚生労働省の事務連絡にもとづいて電話などで支援をする場合には、支援計画等の書類を作成し、事前に1割の費用負担があることを保護者に了解してもらうことを徹底するよう求められ、自治体によっては、支援の内容や書類に細かい指示もありました。支援をしたら報酬を出す、利用料は応益負担という障害福祉制度ゆえの問題に、多くの事業所が戸惑いを感じたのが現実でした。
(4)乳幼児期の総合的な発達保障を
今年2020年は、2021~2023年度を期間とする第2期障害児福祉計画にむけた施策の見直し期にあたります。厚生労働省は、2020年度までに「重層的な地域支援体制の構築」を目指し、児童発達支援センターを市町村に少なくとも1カ所以上設置するという目標を掲げていますが、実現に向けた特別な方針がないまま市町村にまかされています。子どもと保護者のねがいを障害児福祉計画に反映させるよう地域の自立支援協議会児童部会などで議論し、計画策定に参加していくことも重要です。
乳幼児期の支援は、母子保健施策である乳幼児健診と結んだ総合的なシステムが求められますが、ゆとりのない職員体制のもとで保健センターにおける障害の発見から対応、療育への橋渡しの機能低下が危惧されています。全障研大会では、すべての子どもの健康と発達を保障するという視点から子育て支援の枠組みを発展させ、早期療育へつなぎ、親子を支える仕組みを充実させている自治体の取り組みが毎年報告されています。そうした実践に学びあうことを大切にしたいと思います。
Ⅱ.学齢期の情勢と課題
(1)突然の休校要請の下での子どもたちの暮らし
2月27日の夕刻、全国の学校の職員室では大きな不安と動揺、混乱がもたらされました。首相による全国一斉休校要請の突然の発表、そこからの数日間、学校は対応に追われました。卒業や進級という一つの大きな節目を控え、次のステージに向けて期待や意欲を高めていこうとする子どもたちの気持ち、その学年、学級、学校生活の残りの日々で、子どもたちに何を手渡していくのかという教職員の思いは、まったく突然に、そして一瞬にしてやり場を失うことになりました。首相とその周辺による強行的な決定は、多くの自治体や学校から、教育的な判断を主体的に行う機会を奪い、子どもたちはその間、教育を受ける権利を保障されなくなったのです。
3月に入ると、休業補償等の手立てに関する十分な検討もないまま強行された休校によって、多くの障害のある子どもたちとその家庭は、日中をどうやって過ごすのかという問題に直面します。休校要請に際して、厚生労働省は放課後等デイサービスに対し、「可能な限り時間を延長して子どもたちを受け入れること」という事務連絡を出しました。感染拡大予防という一斉休校要請の趣旨と大きく矛盾する課題を、福祉の現場に丸投げしたのです。放課後等デイサービスの事業所では、午前中からの体制づくりに突然直面させられ、職員の不足や職員家族の負担、マスクや消毒液の不足、公共施設が使えないなどの多くの困難と向き合いながらも、子どもと家庭の困難さに応えようと、必死の努力を続けました。4月の「緊急事態宣言」以降も、公的責任に基づく根本的な手立ては示されることなく、各地域や現場レベルでの工夫を強いられている状況が続きました。
「緊急事態宣言」解除後にいくつかの自治体等で取り組まれた調査などでは、子どもたちの家庭での生活の困難の実態や、放課後等デイサービス事業所が直面した困難の実態とともに、学校と家庭、また学校と障害児支援事業所との矛盾が、「学校に見捨てられたような気がした」「学校は何もしてくれなかった」など、悲鳴のような表現で指摘されています。5月に公表した全障研の声明は、この間の施策が、「教育と福祉の関係性に大きな歪みをもたらした」と指摘しました。この歪み正し、障害のある子どもと家族、関係者の人間的な諸権利を守り、発達を保障するための具体的なとりくみが緊急に求められています。
(2)学校に「行く」ことの意味を問い返す
昨年、障害を理由に、長きに渡って教育を受ける権利を奪われてきた人たちの、「学校に行きたい」「学びたい」というねがいを結実させた養護学校義務制実施から40年を迎えました。全障研しんぶんでは「義務制実施40年を考える」と題し、2019年6月から7回にわたって、義務制実施までの道のり、そして義務制実施以降のさらなる教育権保障の道のりを辿りました。すべての障害のある人たちの義務教育実現を大きな基盤としながら、さらに障害の重い人たちの教育内容の深化、後期中等教育の保障、卒業後の進路保障と作業所づくり、さらなる学校設置運動の広がりなど、教育の豊さの広がりはもとより、障害のある人たちのライフステージ全般にわたる豊かさを求め、実践と運動を地道に積み上げてきた歴史に学ぶことができました。
どの子も学校に行けるようになってから40年を経た今年、日本の多くの地域で、子どもたちは3ヶ月もの長きにわたって、学校に「行く」ことを奪われました。そうした事態の中でも、全国の少なくない教師たちは、子どもと家庭の状況をつかみ、子どもたちが少しでも笑顔で過ごせるようにしよう、わずかながらでも発達を保障しようと、家庭訪問や電話、手紙などを用いて連絡をとり、学校生活の中で、子どもたちが好きになった歌のCDを届けたり、絵本の読み書かせや身体を楽しく動かすための動画データを配信するなど、さまざまな努力を続けました。
障害のある子どもたちにとって、学校は「学ぶこと」をただ受け取るだけの場所ではありません。子どもたちは、「学校」という場所に毎日通うことで自ら生活リズムを作り、自分に合った環境で心身をリラックスさせ、適切な運動の機会をつくり、友だちや先生との人間的なかかわりをつくっていくのです。そうした毎日の生活の中で、子どもたちは学校でしか学べないものに出会い、自分自身がよりよくなりたいという「ねがい」を育みます。学校でしかできないこととは何か、子どもたちにとって、学校の価値はどこにあるのかということを改めて問い返しながら、再開後の学校と、そこで営まれる子どもたちと毎日の生活の質を吟味する必要があります。
(3)「再開」後の学校の「学び」をめぐる問題と教育政策
しかし、登校が再開されつつある今、学校は、子どもたちの「ねがい」に応えうる場所になっているでしょうか。学校行事の中止や縮減の一方で、7時間授業や土曜登校、夏休み登校など、授業時数の確保や「遅れを取り戻す」ことばかりが一面的に強調されてはいないでしょうか。
安倍政権が推し進めてきた教育改革、さらには今年から小学校、特別支援学校小学部で本格実施となる学習指導要領では、「何ができるようになったか」「学んだことをどう使えるようになったのか」という視点ばかりが重視されます。そこでは子どもや親、そして教師の「ねがい」から実践を構想するのではなく、短期での目標達成や行動の変容のみをターゲットにした実践を助長させるような「評価」と、一面的な社会からの要請の影響を色濃くうけた「教育目標」が教育現場に押しつけられ、そのことに教育実践が縛られようとしています。
2019年度から開始された文部科学省「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議」は、6月末に「これまでの議論の整理(案)」を示しました。この文書には、障害のある子どもの保護者や教職員が長年要求してきた特別支援学校設置基準の策定に初めて言及するなど、ゆたかな権利保障をめざす声の高まりを反映したと見られる箇所もありますが、特別支援学級と通常学級の「交流及び共同学習の拡充」と称して、「ホームルーム等の学級活動や給食等については原則共に行う」等の一面的な方向性を示したり、「自校通級を進める」との名目の下に「ICTを活用した遠隔による専門的指導」を例示するなど、子どもたちのゆたかな学びと生活へのねがい、子どもと寄り添い、子どもの事実から実践を構想しようとする教師のねがいに背く危険性もはらんでいるとみられます。特別支援教育をめぐる今後の政策動向に直結する動きとして十分な注意を払う必要があります。
(4)自ら考え、行動できる教職員集団づくりを
長期にわたる休校とその後の学校再開の動きの中、学校と福祉がこれまで以上に連携を深めながら、子どもたちの生活を少しでもよくしよう、家庭やそれぞれの現場の負担を軽減しあおうという動きも見られます。子どもの家庭や生活の状況をつかもうと、従来以上に密に連絡を取り合うようになった学校や福祉事業所の事例もあります。休校期間中、体制の不足する福祉事業所に応援に入った学校や、学校施設を家庭や福祉事業所に開放した自治体、学校もありました。こうしたとりくみは、行政上の障壁や教職員集団の合意形成の困難などに制約されて、いまだ多数とはなっていませんが、困難な状況の中でこそ、障害のある子どもたちの権利を守るために何ができるか、現場レベルで話し合い、考え合うことの重要性と、そうした努力を重ねることで、少しずつでも困難を切り拓いて前に進めることを私たちに教えています。
教職員集団が「集まる」ことが強く制約された経験を経て、「集まる」「語り合う」ことの価値を、再発見している人たちは少なくありません。今年度の『みんなのねがい』の連載「出会いはタカラモノ 子どもから教えられたことばかり」の冒頭で、著者の佐藤比呂二さんは「私の教師人生は、子どもから学んだことの積み重ね」だと記しています。子どもたちの教えてくれるタカラモノを一つ一つ大事に掬い取ることができるように、そしてその「価値」を決して手放すことのないように、みんなで語り合いながら、子どもの「ねがい」に応える授業づくり、教育課程づくりを進めましょう。「働き方改革」と「コロナ対応」などの名の下、再編される行事や教育活動についても、「子どもにとっての値打ち」をしっかりと語り、現下の状況に即して創造できる教職員集団づくりを進めましょう。
Ⅲ.成人期の情勢と課題
(1)「全世代型社会保障」の動向
成人期の障害者の権利保障を考えるうえでは、社会保障全体の動向に目を向けておく必要があります。
政府が2019年9月に設置した全世代型社会保障検討会議は、12月に中間報告をまとめ、「年金」「労働」「医療」「予防・介護」の各分野について、改革の方向性を示しました。その内容は、第201回国会において一部具体化され、70歳までの雇用継続と結んだ年金支給年齢の引き上げなど、関係法の「改正」がなされました。さらに、2020年6月には、第2次中間報告がまとめられ、「フリーランス」の拡大のための労働関係法の改正などが準備されています。
こうした動向の基調になっているのは、経済成長を最優先する姿勢です。昨年12月の中間報告は、「障害や難病のある方々」にも言及していますが、それは「一億総活躍社会」を語る文脈においてです。政府がめざしているのは、「強い経済の実現」なのです。日本に住む人の権利保障の観点から社会保障改革が考えられているわけではありません。
そのため、全世代型社会保障改革は、「制度の持続可能性」の名のもとに、社会保障の抑制を図るものになっています。医療についても、窓口費用負担割合の引き上げなどが提案されています。
そして、重視されているのは、高齢期に至るまでの就労です。人間らしく働く権利の保障は重要ですが、経済成長や社会保障抑制のために就労を強いられることは問題です。
私たちは、権利保障の観点から、あるべき社会保障を考えていかなければなりません。
(2)報酬改定をめぐる動向
障害のある人の生活と権利に直結することとしては、「障害福祉サービス等報酬改定」の問題があります。3年ごとの報酬改定が、2021年度に予定されており、感染対策で中断していた検討チームの会合が再開されました。
2018年度の報酬改定の際には、国が食事提供体制加算を撤廃しようとしましたが、障害者団体等の運動によってそれを阻止しました。昼食・食事は、障害者の労働や生活を支える大切なものです。次回の報酬改定で食事提供体制加算を廃止することは許されません。
また、事業所による送迎支援も重要なものであり、送迎加算は廃止されるべきものではありません。それにも関わらず、厚生労働省のもとで送迎に関する実態調査が行われるなど、送迎加算の見直しが進められてきています。
現実には、公費支出の水準が低い現状のもと、事業所の運営は困難を抱え、職員の働く環境も厳しいものになっています。また、2018年度の報酬改定においては、就労継続支援事業B型の報酬単価を平均工賃と連動させるという成果主義的な方式が導入され、そのなかで多くの事業所が減収に追い込まれました。報酬改定は、これらの問題を解決する方向でなされるべきものです。
新型コロナウィルス感染症に関係して、障害者や家族、事業所が抱える困難が増しているなか、報酬改定がさらなる打撃をもたらすようなことがあってはなりません。
(3)安心できる生活の保障
必要なのは、社会保障の拡充であり、障害者が安心して暮らせる社会の構築です。
今年度の『みんなのねがい』の連載「高齢期を迎えた障害者と家族―老いる権利の確立をめざして」(田中智子)でも述べられているように、障害者のケアの責任は、費用面も含めて、親・家族に押しつけられています。障害者の生活を支える社会資源の整備も、家族によるケアを前提としている面があります。障害者および家族の権利保障にとっては、家族依存を当然のこととするような現状からの脱却が重要です。
そのためには、障害者の暮らしの場の充実が欠かせません。障害者権利条約の第19条は、「障害者が、他の者との平等を基礎として、居住地を選択し、及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有すること並びに特定の生活施設で生活する義務を負わないこと」を確保するように締約国に求めています。障害者が意に反して「特定の生活施設」で暮らさなければならないことが問題であるのと同時に、障害者が親・家族との生活を強いられることも問題です。
遠くないうちに、国連・障害者権利委員会から、日本への勧告(総括所見)が出されることになります。その内容を吟味したうえで活用しながら、障害者の暮らしの場の保障を進めていくことが、今後の課題になります。
(4)文化的な生活の創造
障害者の労働や生活の場を豊かなものにすることと合わせて、障害者の文化的活動が十分に保障されるようにすることが重要です。
東京オリンピック・パラリンピックの開催が2020年に予定されていたなかで、障害者のスポーツに対する社会的関心はいくらか高まったのかもしれません。しかし、幅広い障害者がスポーツを楽しめる環境が整備されてきたとは言えません。家族による援助に依存するような状況は、スポーツについてもみられます。
文部科学省のもとでは、「障害者の生涯学習の推進」が言われ、「文化芸術活動」や「スポーツ活動」を支援するとした「障害者活躍推進プラン」が2019年に発表されています。その背景には、生涯学習等に対する障害者の要求や、その要求に応えてきた諸実践もあるでしょう。養護学校義務制の実施や養護学校高等部の拡充などに結びついてきた、これまでの教育権保障の取り組みが、「生涯学習」を政策的課題に押し上げてきたとも言えます。しかし、高い能力をもって「活躍」することばかりに価値を置く発想がないか、特別な才能のある障害者を政策的に利用するようなことにつながらないか、といったことには注意が必要です。
障害者権利条約の第30条では、「文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加」についての権利が明記されています。すべての障害者がこの権利を享受できるようにしなければなりません。
そのためには、障害者の余暇活動のための制度の構築も求められます。学校に通う子どもについては、2012年に放課後等デイサービスの制度が創設されました。類似の仕組みを必要とする人は、成人期にある障害者のなかにも少なくありません。
障害児者の生活のありようを構成する不可欠の要素の一つにセクシュアリティをめぐる問題があります。すべてのライフステージに関わる大切な課題ですが、この領域における権利侵害の実態や権利保障・発達保障の課題は、これまで必ずしも十分に論議されてきたわけではありません。全障研出版部の新刊『ゼロから学ぶ障害のある子ども・若者のセクシュアリティ』(伊藤修毅著)なども用いて、セクシュアリティをめぐる権利保障の課題についても議論と実践を深めましょう。
(5)権利保障の道を描くこと
現状に甘んじることなく、障害者の権利保障のために必要なことを考え、取り組んでいきましょう。
新型コロナウィルス感染症をめぐる事態は、さまざまな分野で従来の仕組みの歪みを浮かび上がらせました。保健所が統廃合によって減らされてきたことも、その一つです。余裕のない医療体制では危機的状況に対応できないことも明白になりました。障害者支援の領域においては、「日割計算」の弊害が改めて顕在化したといえるでしょう。ゆとりのある安定的な職員体制の大切さも再確認されることになりました。また、行政の責任・役割が小さなものになっていることの問題性も顕著に表れました。
障害者自立支援法の成立から約15年が経過し、社会福祉基礎構造改革の流れのなかでつくられてきた仕組みが当然のもののようにみなされる傾向があるかもしれません。しかし、私たちは、現在の仕組みを固定的なものとして考えることはできません。障害者自立支援法違憲訴訟の基本合意(2010年)や障がい者制度改革推進会議総合福祉部会の骨格提言(2011年)などをふまえ、障害者と関係者の実態や要求を立脚点にして、あるべき権利保障の道を描いていきましょう。
Ⅳ.研究運動の課題
(1)平和的生存権を基盤に、三つの系でねがいを束ねる
新型コロナウィルスを契機として引き起こされた情勢は、社会にもともと存在していた矛盾や格差、差別と偏見を浮かび上がらせました。近い将来人類の存続さえ脅かすような気候変動・気候危機も急速に進行しています。ウィルスがもたらす危機だけに目を奪われることなく、発達保障・権利保障の課題を正面からとらえる必要があります。
新型コロナウィルスの世界的な感染爆発により、無数の人びとの生活が破壊され、いのちが奪われていくなか、アメリカ合衆国では、重度の知的障害、脳性まひ等のある人への治療を抑制したり、人工呼吸器を装着させないという選択肢を含んだガイドラインを作成した州もあります。障害を理由とするいのちの選別は、障害のある人びとのいのちを脅かし、いのちの切り捨てをさらに進めることにもつながりかねず、いかなる場合にも断じて容認できません。
2020年3月31日、津久井やまゆり園事件をめぐる裁判で死刑判決が出され、その後この判決は確定しました。しかし、「障害者は不幸をつくり出すことしかできない」、「生きるに値しないいのちがある」という被告の価値観がこれ以上追及されず、事件の本質も解明されないまま、事件に終止符が打たれることがあってはなりません。今回の事件を忘れることなく、人間のいのちに軽重をつける価値観に抗い、いのちの選別をおし進めようとする動きに向き合い続けなければなりません。
新型コロナウィルス対策をめぐり、異論を唱えることを許さない空気が社会に蔓延し、「自粛」要請による生活の統制が一気に進みました。3月半ばから4月の初めにかけて、新型インフルエンザ特別措置法改正から「緊急事態宣言」発令へと事態はきわめて急速に進行しましたが、自民党は今回の緊急事態宣言に便乗して憲法を改正し、「緊急事態条項」を創設する意向を示したことに注意が必要です。政府の判断で検察幹部の定年延長を可能にする検察庁法改正案も、国民の声に押されて頓挫したとは言え、民主主義の根幹に関わる三権分立を脅かそうとするものでした。未知の感染症の蔓延という危機に乗じて、私たちの自由を奪い、政府の意に沿わない声を封じ込め、平時には実現しにくい政策をなし崩しに強行しようとする動きが顕著であったことは決して見過ごしてはなりません。
私たちは、障害者のいのちと権利を守り、すべての人の発達保障を実現するために、日本国憲法が定める平和的生存権を拠りどころとして、「個人-集団-社会」という発達の三つの系を統一し、民主的に発展させることをめざしてきました。「コロナ禍」の下で顕在化し、あるいは新たに引き起こされた情勢は、集団の系の展開を強く制約するとともに、社会制度の系において人類が築いてきた進歩に対しても大きな反動を招きかねないものであり、そうした情勢の下で個人の豊かな生存と発達の権利が脅かされるという構造を持っているものと見られます。発達の三つの系を断ち切らせず、それぞれの系において一人ひとりのねがいを持ちより、みんなのねがいとして分かち合うとりくみを大切にしていきましょう。
(2)本人や家族のねがいや不安を聴きとり、権利侵害の事実をつかむ
この間、「自粛」要請による生活や行動の制限にくわえて、新自由主義改革によって弱体化させられてきた社会保障制度の矛盾が、障害のある人や家族を追い詰めています。そうしたなかで、本人や家族が困っていることや不安に思っていることを十分に聴きとり、受けとめることができないまま、不自由な生活を強いてしまっている現実があります。
私たちの研究運動に求められるのは、そうした障害のある人びとや家族の抱える不安と、その背後にある人間的な生活と発達へのねがいをていねいに聴きとること、そのことを通して、障害のある人びとに対する権利侵害の事実を具体的につかむことです。コロナ情勢下での障害のある人や家族の実態をしっかりと記録しながら、多様かつ複合的に立ち現れている権利侵害の事実を総体として明らかにすることで、動かしがたくみえる現実に立ち向かう実践と研究の課題が明らかになります。
いっぽう、困難な状況をていねいにつかみ、本人の要求をじっくりと探るとりくみが、関係者や関係機関を結びつけ、新たなつながりのもとで、それぞれのライフステージで安心できる生活を保障しようとするとりくみも生まれています。困難な状況下で生まれつつある新たなつながりや実践の芽をつかみ、そうした実践のなかで生み出された事実を共有することが、権利保障の道すじを見出すことにつながります。
(3)実践者のそだちと発達保障労働の専門性
福祉や教育の現場では、感染の危険性を抱えながら困難な状況にねばり強く立ち向かい、障害のある人や家族の抱える不安に心を寄せて、一人ひとりのねがいに応えようと奮闘する実践者がたくさんいます。本人の不安を少しでも取り除き、ことばと心を通わせあうことで、障害のある人たちと家族のねがいをつかみ、それに応えようとする人たちが、お互いのの不安や悩みを聴き合うこと、障害のある子どもや仲間が示すわずかな変化のうちに実践の展望を見出そうとする努力を励まし合うことが大切です。
いま、障害のある人びとの発達や幸福の実現に寄与する実践に力を尽くしたいとねがって現場で働く人たちが、これまでの歴史のなかで深められてきた発達保障の思想をわがものとしながら、主体的な実践者として育ち合う道すじはどこに見出されるでしょうか。実践がうまく立ち行かない原因を、自分や同僚など、個人の力量の不足に求める自己責任の発想は、実践と、それを制約する制度などに対する疑問や悩みを抑え込ませる方向に作用します。こうした考え方が幅をきかせる現場では、実践者は自らの実践に手応えを感じにくく、展望を見出しづらくなります。障害のある人びとが困難や葛藤を抱えながらも人間らしく生きようとする姿のなかに、本人たちのねがい、そして自分自身のねがいの実現を阻んでいる社会や政治の矛盾を読みとり、そうした困難や矛盾の根源に共同して立ち向かう力こそ、発達保障労働に求められる専門性であるといえます。
とはいえ、個人の疑問や悩みを自覚することが、ただちに社会や政治への視野を開くわけではありません。身近なところから、小さな悩みや疑問、自分が実践を通して出会ったささやかな事実を安心して語り合い、聴き合い、みんなで共有し合うなかで、「個人-集団-社会」という発達の三つの系のつながりに気づき、自分や仲間の悩みやねがいと、社会や政治とのつながりへの視野が少しずつ開かれていくのではないでしょうか。
(4)障害者権利条約の水準にふさわしい制度改革を実現する
日本国憲法にもとづき、すべての人の権利を保障することなしには、障害のある人びとの発達保障を実現するとりくみの前進はありえません。この間、2018年の生活保護基準引き下げが違憲であるとして取り組まれてきた「いのちのとりで裁判」の名古屋地裁判決が6月25日に、また強制不妊手術による人権侵害を訴えた優生保護法違憲訴訟の東京地裁判決が6月30日に出されましたが、2つの判決とも、司法が人権救済の最後の砦としても役割を果たしえない現状にあると言わざるをえない内容でした。国内の人権保障の基盤を強固にしていくことがたいへん重要です。
そうした国内の人権保障へのとりくみと結びつき、障害のある人びとのねがい、生活や発達の事実と結びついてこそ、障害者権利条約は、「他の者との平等」を実現させる大きな力を発揮します。国連の障害者権利委員会による政府報告書の審査日程も流動的ですが、今後示される国連の総括所見などを最大限に活かしながら、国内の障害者団体が叡智を結集して完成させたパラレルレポートが示した障害者制度改革の諸課題を、権利条約にふさわしい水準で実現させていくとりくみが大切になります。
(5)仲間をつなぎ、ねがいをつなぐ
私たちの研究運動は、「ひとりぼっちをつくらない」ことを大切にしてきました。対面で言葉を交わすことができない状況に直面する中でも、SNSやインターネット等を活用して、職場の実態や各地の情報を交流する動きが生まれました。支部やサークルでは「語りたい」「学びたい」というねがいをていねいに受けとめながら、ねがいや悩みを分かち合う仲間を求めている人と出会い、仲間とつながり合う方法を模索しましょう。
私たちは、今年9月に予定されていた北海道・旭川での全国大会を中止するという苦渋の決断をしました。いまは、それぞれの職場や地域のとりくみを持ちより、全国の仲間と直接交流し、深め合うことは叶いません。しかし、私たちには全国の課題と地域での研究運動をつなぐための素材がたくさんあります。月刊誌『みんなのねがい』は、毎月各地の実践や運動、研究の成果などを届けることで職場や地域の課題を掘りおこし、自分たちの実践の意義や課題を語り合う場をつくってきました。発達保障の研究運動の成果を科学的に整理し、実践と理論を往還させる道すじを明らかにするための理論誌が『障害者問題研究』です。「発達を学びたい」「実践を吟味したい」という要求に応えて、学習の導き手となるような出版物もたくさんあります。それぞれの地域や職場で、これらの素材を積極的に活用して、新たに出会う人たちのねがいや悩みを分かち合い、発達保障の魅力に触れてもらいながら、研究運動をともに担う仲間になってもらえるよう働きかけていきましょう。
(2020年11月23日 最終版を常任全国委員会は確定しました)
「障害者問題研究」48巻3号 特集=障害基礎年金の制度的課題と生活問題 刊行しました
特集にあたって/濵畑芳和 立正大学
障害基礎年金の現状と課題――障害のある人の権利条約を踏まえた見直しをめざして
鈴木 靜 愛媛大学法文学部
障害基礎年金の認定格差とあるべき姿
市川 亨 共同通信記者
障害基礎年金と児童扶養手当の併給へのたたかいの今日的課題
仲尾 育哉 椙山女学園大学現代マネジメント学部准教授・弁護士
障害年金の認定問題――成人先天性心疾患患者の運動から
下堂前 亨 一般社団法人全国心臓病の子どもを守る会 事務局長
報告
救済措置が取られない無年金障害者の立場から見える年金問題
原 静子 無年金障害者の会代表幹事
報告
精神障害者支援の現場から障害年金の問題を報告する
松本みを 大阪府八尾市 医療法人清心会 相談支援事業所ちのくらぶ、精神保健福祉士・相談支援専門員
報告
無年金障害者における生活問題――生活実態調査を通じて
無年金障害者の会(大阪市・障害者(児)を守る大阪連絡協議会内)・田中智子(佛教大学社会福祉学部)
◆連載/実践に学ぶ
①「学びは「教わる」から「つきとめる」へ
――子どもと対話し,子どもと共につくる授業をめざして
長友志航 滋賀県 特別支援学校教員
【長友実践に学ぶ】子どもと共につくる授業の楽しさ
宮本郷子 龍谷大学社会学部
②贅沢な仕事――障害の重い人の仕事を考える
原田文孝 兵庫県・重度障害者通所事業所さち 生活介護事業サービス管理責任者
【原田実践に学ぶ】生活を意味づけ,新しい人生をつくる
細渕富夫 川口短期大学
◆連載/ワイドアングル
ドキュメンタリー映画『ゆうやけ子どもクラブ!』を語る
井手洋子 映画監督
◆動向
全世代型社会保障とは何か――障害福祉に何をもたらすのか
平野方紹 立教大学コミュニティ福祉学部
詳細やオンラインのご注文は以下のホームページへ
→「障害者問題研究」48巻3号 特集=障害基礎年金の制度的課題と生活問題

はじめに 白石恵理子
Ⅰ 発達保障のための子ども理解の方法
発達保障のための子ども理解の方法/木下孝司(神戸大学)
Ⅱ 発達の段階と発達診断
1章 乳児期前半の発達と発達診断/河原紀子(共立女子大学)
2章 乳児期後半の発達と発達診断/松田千都(京都文教短期大学)
3章 1歳半の質的転換期の発達と発達診断/西川由紀子(京都華頂大学)
4章 2~3歳の発達と発達診断/寺川志奈子(鳥取大学)
5章 4歳の質的転換期の発達と発達診断/藤野友紀(札幌学院大学)
6章 5~6歳の発達と発達診断/服部敬子(京都府立大学)
7章 7~9歳の発達と発達診断/楠凡之(北九州市立大学)
Ⅲ 「発達の障害」と発達診断
「発達の障害」と発達診断/白石正久
おわりに 白石正久
日本学術会議新会員候補の任命拒否に関する声明
2020年10月11日
全国障害者問題研究会常任全国委員会
10月1日、菅内閣総理大臣は、日本学術会議が推薦した第25期新会員候補のうち6名の任命を拒否しました。しかも、任命拒否の具体的な理由は明らかにされていません。1983年の国会では、内閣総理大臣の任命について、学術会議の推薦にもとづく形式的な任命であることを確認しており、拒否する性質のものではないことは明らかです。したがって、今回の菅内閣総理大臣による任命拒否は、日本学術会議法に違反して日本学術会議の独立性を侵害し、「学問の自由は、これを保障する」と定めた日本国憲法を蹂躙する行為であり、断じて許すことはできません。政権が多種多様な学術研究の評価に立ち入ることで、学界や社会の分断を誘発し、時の政権の見解・意向にそぐわない知見や意見を排除する空気が醸成されていくことを深く憂慮します。
日本学術会議は、戦前・戦中に国策協力した学術界自らへの歴史的な反省に立ち、政府からの独立性を原則に、日本の平和的復興ならびに人類社会の福祉への貢献を使命として1949年に設立されました。科学研究の立ち遅れや民主主義の未成熟が、障害のある人びとの人間的なねがいを奪い、人権侵害をいっそう厳しいものとすることは、障害者問題の歴史が教えるところです。障害者問題の根本的解決をはかり、障害のある人びとの権利保障と発達保障を期すためには、思想や言論の自由、学問の自由、差別なき人権の尊重を前提とした科学的な認識と批判が欠かせません。不当な権力を行使して学問の自由と自律性を侵害し、自由な言論や対話の機会を閉ざすことは、個人の自由や権利を制限し、ひいては発達保障のための研究運動を制約するものとして見過ごすことはできません。
全国障害者問題研究会常任全国委員会は、菅内閣総理大臣の行為に抗議の意を示すとともに、任命を拒否した6名の候補者について、任命拒否に至った具体的な経緯を説明し、推薦にもとづきすみやかに任命することを求めます。そして、真理・真実にもとづき、科学的な認識にひらかれた自主的・民主的な研究運動をたゆまず進めていきます。
この15分間のビデオは、オンライン学習会を企画する側の、必要な知識、手順を解説したものです。これを参考に、従いながら、設定できる優れものとの声も(^_-)
▶15分でわかる支部・サークル・読者会などオンライン活用のヒント
▶特設ページ オンライン活用へ
2020年5月9日
声明
新型コロナウイルスをめぐる情勢の下で障害児者の権利を守るために
全国障害者問題研究会常任全国委員会
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)をめぐる問題が広がるなかで、社会保障の仕組みの決定的な弱さをはじめ、日本社会の抱える矛盾が露呈しました。そのなかで、障害児者や家族の生活にとりわけ大きな困難が生じています。
そうした状況のもと、私たちは、少なくとも以下のようなことを確認し、障害児者とその家族、また障害児者に関わるさまざまな人たちの人間的な諸権利を守り、発達を保障することが必要だと考えます。
◎今年3月には、国会でほとんど審議されることなく、新型インフルエンザ等対策特別措置法が改定されました。そして、4月には、改定法に基づき、緊急事態宣言が発令されました。さらに、安倍首相は、緊急事態条項の創設を主張しつつ、憲法九条の改変を含めた改憲を進める意思を表明しました。感染の拡大に便乗して権利制限の仕組みを強化すること、改憲を図ることは、絶対に許されません。
◎アメリカ合衆国のいくつかの州などでは、感染が拡大した地域において、障害者の治療を後回しにする事例や、障害者や高齢者に人工呼吸器を装着させない事例が起きていると報じられています。すべての命は平等です。障害を理由に命が軽んじられてはならないことが、再確認されなければなりません。
◎慢性疾患への日常的な治療、体位変換、呼吸、摂食などの重い機能障害への医療・介護と家族への支援、施設入所しつつ通学している子どもの生活保障など、複合的な権利保障を必要としている実態の把握と施策の必要を看過してはなりません。
◎乳幼児期の発達保障の場である児童発達支援に、事業所の閉所や感染予防のために、多くの子どもが通えなくなりました。家庭内に限られた生活は、子どもの精神や生活リズムを不安定にし、その行動や健康の問題が家族を疲弊させています。子どもの活動の場の確保や家族の相談支援のための具体的な方策が求められます。
◎学校の臨時休業が続くなか、「グローバルスタンダード」や「留学」なども理由に、「9月入学」の導入が主張されています。危機に乗じて拙速に学校制度の根幹を変えることは許されません。障害児者の豊かな生活と発達をめざす立場からは、グローバル経済やエリート人材育成ばかりに目を向ける傾向も見過ごすことができません。今必要なことは、すべての子どもたちのこころとからだの状況をていねいにつかみ、そのねがいに応える学校再開の在り方を、多くの知恵を集めて考えあうことです。
◎学校を臨時休業にしながら、障害のある子どもの居場所を放課後等デイサービスや学童保育に求めるこの間の施策は、感染防止という面においても不合理であり、教育と福祉の関係性にも大きな歪みをもたらしました。子どもたちの、子どもらしい生活と権利を守るために、関係者がいっしょになって考え、それぞれの役割を果たしていくことが求められます。
◎感染の防止は必要なことですが、学校や施設を休校・休所にすれば問題がなくなるわけはありません。家で過ごすことが難しい子どももいます。毎日の通所に張り合いを感じてきた人もいます。障害のある子どもたちの学習や生活、障害者の仕事や生活を守るために、何ができるのかを考えていかなければなりません。
◎障害児者支援の領域においては、「日額報酬制度」の問題性が改めて顕在化しています。財政面を心配することなく、事業所・職員が最善を尽くせるよう、開所の場合にも休所の場合にも事業所の運営が守られるような緊急施策が必要です。また、事業所の安定した運営が可能になるよう、制度を抜本的に見直すことも、今後において求められます。
◎今、各地の障害児者支援事業所、生活施設、医療機関等では、障害児者の発達や生活を支えるために、感染の不安を抱えながらも、多くの人たちが懸命の努力を続けています。そうした努力に応える施策や、現場の努力だけに問題解決を委ねない施策が、早急に実施されなければなりません。